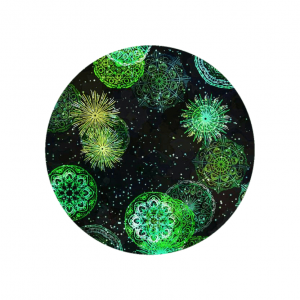掌編小説集
メモ代わりの短いお話を集めました。
後々、増えます。多分。
世間とのズレ
二十歳を迎えた日から、バケモノになってしまった。爪も髪も伸びず、肌はいつまでも若いまま。 怪我をしても軽いものなら、十秒もせず完全に治ってしまう。
自分が酷く恐ろしかった。
ある日、自殺を決行した。刃物で自分の首を切り裂いた。痛かった。血が吹き出した。そして、酷く気分が悪くなって意識が途切れた。
その寸前、これで自分は死ぬだろう、バケモノはいなくなると心のそこから安心した。
しかし、死ぬことはできなかった。
血だまりのなかで目が覚めた。天井や壁至るところに血が飛び散っていた。
自分は死ぬことさえできないのかと絶望した。
首に触れると、血でべたつきはするが傷のないまっさらな肌だった。
「これはこれは……我が嫁は恐ろしいことをする」
男の声がした。部屋の入り口の方からだった。見た瞬間、人間ではないと思った。霞のかかった月のようにおぼろげで美しかった。
「迎えが遅れて済まなかった。しかし、輿入れを志願したのはお前からだろう。そんなに俺が恋しかったか?」
そういわれて思い出した。高校生の頃、毎日のように通っていた深い森に囲まれる人気のない神社で願ったことを。
『神様、お嫁にして下さい』
たしか、そう願ったのだった。
親の言うお家の安泰のためとかで、勝手に一回りも年の離れた好きでもない男と将来、結婚させられる位なら居心地よく、暖かいここの主と結婚したい。ふと、そう思ったのだ。
まさか、叶うとは思っていなかった。しかも、こんな体になるなんて。
「嫁を迎えるのは初めてだ。しかし、目一杯愛し、必ず幸せにしよう」
私は彼に抱き抱えられた。何かわからない花のような良い匂いがした。
「よろしくお願い、いたします」
男性に耐性のない自分には、か細い声で顔を火照らせながらそういうしかなかった。
ぼんやりと自分はこれから神隠しに合うのだなと思った。
「愛いな」
名前すら知らない。けれど、好きだ。だから、結婚してから彼を知っていくのも、悪くない。
辛辣な口調
「僕は歯に衣着せぬ物言いをする奴が嫌いなんだ。良いことについてはいいんだ、でも悪いことをそのまま辛辣に言っちゃうのはどうかと思うんだよ」
そんなことを昔、ある男に話したことがあった。
すると彼はガハハッと元気に笑って言った。
「そりゃ、あんたがそうなりたいって思ってるからだ。なりたい、でもなれない。だから嫌う。けれどな、あんたの性格を嫌う奴もいる。あんたは思いやりのあるいい男だ。人の心に敏感だしな……つまり、そういうことだよ」
「つまり、どういうこと?」と僕は彼に尋ねた。
彼の言わんとしていることがわからなかったのだ。どうやら僕は案外おつむが弱いらしい。
「なんだ、わかんねぇのか?」
彼がちょっとバカにしたように言うので少し頭にきたけれど、僕は素直に頷いて先を促した。
「つまりだな、見方を変えりゃいい性格だってことだよ。互いに補い合うようになってんだよ、世の中。例えば気の強い奴ばっかり居てみろ、戦争ばっか起きて滅ぶぞ。どっちが良いだの悪いだの考えるだけ時間の無駄だぜ」
彼の言葉を聞いて僕は長い間心に渦巻いていた黒い霧が晴れた心地がした。
そうか、僕はこのままで良いのか。
僕はお礼を言わずにはいられなかった。
「ありがとう、教えてくれて。さすが僕の親友だね」
そういえば彼は、頬を赤らめながら
「あんまり褒めるなよ」と嬉しそうに言った。
そんな出来事を10年たった今でも、僕は彼を見るたびに思い出すのだ。
土の下
花束を持って歩き慣れた坂道を歩む。
路肩の草むらに目を向けるとタンポポが咲いていた。紅葉の季節だと言うのに生き生きと黄色が鮮やかだった。しばらく歩くと、舗装された道は砂利道となって、そして野原となった。そこにはいつものように見慣れたお墓が立っていた。その五メートル奥は崖で、したには青い海原が広がっている。
この墓の下に眠っている彼はとても海が好きだった。だから、この場所に彼の……いや、私の義理の父母は墓をたてたいと言ったのだろう。彼とは二年と少しの短い夫婦生活だった。
「やぁ、元気?」
そう彼に話し掛けて見たものの、死人に元気かと尋ねるのはおかしいなと、独りでクスクス笑ってしまった。
海から吹く冷たい風に私はブルッと身を震わせた。
「この間まであんなに暑かったのに、今日は寒いね。上着を来てくればよかったよ」
言葉にすれば寒さは増すようだった。
「土の中ってどんな感じ? 冷たい? それとも案外温かいの?」
持っていた花束を墓石に立て掛け、しゃがんだそのままの体勢で地面に触れた。地面は太陽に温められて温(ぬく)かった。視線を上げると目の前は墓石でまるで座っている彼と視線を合わせたようだった。
「あのね、私、独りぼっちでも頑張って生きるから。あなたを好きなままで、生きて、生きて、いきて……可愛くて素敵なおばあちゃんになって死ぬから、そっちで浮気しちゃダメだからね」
植物のタンポポだってこの寒い中、鮮やかに花を咲かせているのだ。人間の私がいつまでも寒さに泣いて、立ち止まってちゃ、いけない。
「じゃあね、またくるよ」
立ち上がり、彼の墓に背を向けた。
『愛しているよ、永遠に』
その時、彼の声が聞こえた。思わず振り向いたけれど、彼はいなかった。
愛情と優しさに満ちた、懐かしい声だった。
きっと、空耳だろう。それでも溢れる恋しさと涙に自分の胸をかき抱かずにはいられなかった。
「――頑張るからね」
そう、彼と自分にもう一度誓った。
弾むように歌う声
嬉しい事があると、彼女は歌う。家が隣同士で、彼女が歌い出すと僕はすぐに気付く。
「今日、何かいいことありました?」
初秋のある日、窓を開け放ち、弾むように歌う彼女に僕は自室の窓を開けてそう尋ねた。
「うん。あったの! じゃじゃーん!!」
そんな効果音と共に彼女が僕に見せたのは左腕。なるほど、きれいな翡翠のブレスレットがはまっている。
「翡翠ですか?」
わかっていながら、僕は彼女にそう問いかけた。
「よくわかったね! これ白っぽいやつなのに!!」
「さっき、『ひっすい~♪ ひっすい~♪』って変な調子付けて歌ってたじゃないですか」
「あれー? そうだった?」
彼女は可愛らしくコテッと首をかしげた。
「そうですよ」
僕がそう答えるとまた彼女は「ひっすい~♪ ひっすい~♪」と変な調子を付けて歌い出した。
ああ、付き合ってられない、そう思って僕が窓を閉めようとした時、彼女に名前を呼ばれた。
「これ、ポストに入れたの君でしょ? 誕生日覚えててくれたんだね」
「何で僕だと思うんですか?」
僕はそう尋ねた。
「だって、私、君にしか今日が誕生日だなんておしえてないもの」
彼女は勝ち誇ったようにニンマリと笑っていった。
電話越しに聞いた声
もうかかるはずのない電話番号に電話をかけた。
どうせあの無機質な女性の声が彼のいない事実を突きつけてくるのだろうと、そう思っていた。
「もしもし、お前か。元気にしているか?」
それなのに、どうしているはずのない彼が出るのだろう。
「……元気だよ、もちろん。君のいた頃には負けるかもしれないけれど……うん、ご飯もちゃんと食べてる」
久しぶりの彼の声に涙が出てしまいそうだ。まいったな、もうとっくに涙は枯れてしまったと思っていたのに。
「そうか、長生きしてくれよ。そうだな……あと50年は」
「えー、頑張るよ。そうしたら誉めてくれる?」
「ああ」
突然ザザッとノイズが走り始めた。
途切れ途切れの彼の声を聞き取ろうとキッとスマホを握りしめた。
「愛してる」
電話が切れる直前、そんな彼の言葉が聞こえた。
「うん、私も愛してる」
私の思いは彼に届いただろうか。
気がつくとベッドの中だった。やっぱりあれは夢だったらしい。
夢でも久しぶりに彼の声が聞けて嬉しかった。
カレンダーを見ると、今日は彼の月命日だった。
隠し事はしないで
「隠し事はしないでね。約束だよ?」
「うん、約束。指切りげんまん嘘ついたら針―――」
3年前、町を一望できる丘の上の公園で約束を持ちかけたのは彼女だった。
そんな彼女は骨になった。最後まで僕に病気のことを隠して、勝手に死んでいった。
元々指切りは吉原の遊女達が客との約束のために本当に指を切っていたことが由来らしい。博識だった彼女のことだからもちろん知っていただろう。
「それでは、納骨をお願いします」
葬儀屋の男に言われて彼女の骨を箸で取って骨壺に入れていく彼女の両親は目の下に凄い隈を作って、言うのもなんだけど今にも倒れてしまいそうだ。どうして、彼女は約束を破ったのだろう。死んでしまった彼女には針を千本飲ませたくても飲ませられやしない。
あれ? 残ってる。
ふと、視線を落とすと台車の上に灰に埋もれるようにして骨片が残っているのをみつけた。周りを見渡すと、図ったように誰もいない。ソロリと手を伸ばして触れ、人差し指と親指でつまみ上げた。
指仏と呼ばれる指先の骨だった。彼女の望みだろうか。
「約束、破った罰にもらっておいてあげるよ」
でも、絶対に許してなんかあげないから。
漸く、僕の頬を生暖かい涙が伝った。
かわいいわがまま
彼女は甘え方を知らない。いや、もしかしたら自分はわがままを言ってはいけないなんて思っているのかもしれない。
「いつでも相談に乗るから。私をを頼ってね」
いつも彼女はそう言って、頼られたなら自分のことのように悩む。根が優しいんだろう。
「友達が頑張り過ぎているんだ。俺はどうしたらいいだろうか?」
「休むようにいえばいいんじゃないかしら」
「あいつがわがままを言ってるとこをみたことないんだ。たぶん悩みも一人で抱え込んでるんじゃないか?」
「そう、それは心配ね。直接聞けば答えてくれるんじゃない? 友達の頼みならわがままだってするし、悩みだって話すわよ」
「そういうものか?」
俺は首を傾げて尋ねた。
「そういうものよ。……その友達は幸せ者ね」
そう言って彼女はほほえんだ。
「休め。わがままだって存分に言え。悩みごとだって聞くぞ?」
「なに、私のこと? だったら『友達』じゃなくて『恋人』でしょ?」
「そう言ったらバレるだろう」
そういえばそれもそうかと彼女は笑った。
「そうね……今日は一緒に寝よう。明日はショッピングにいこう。もちろん一緒にだよ?」
彼女は俺のパジャマの裾を掴見ながらそういった。
「なんだそりゃ。ずいぶんかわいいわがままだな」
「仕方ないでしょ。慣れてないんだもの。……まあ、わがままもたまには悪くないわね」
そうだろう、と俺は頷いて笑った。
歓喜
3年にわたる魔王軍との決戦に終止符が打たれた。
世界は歓喜に包まれた。世界――――人間界は。
「これは一体どういうことなのだ!?」
勇者は見てしまった、知ってしまった。魔族は美しい心を持っていた。魔族は人間界を攻めてなどいなかった。攻めたのは人間の方だった。
「嫌だ! お願い! 手を離して!!」
魔族の子供が人間の軍人に母親から引き離された。
「お母さん!」
「アナスタシア!!」
振り上げられた剣キラリと輝き、血潮が飛び散った。子供の首がゴロリと道に転がった。それを見た母親は糸が切れた操り人形のように崩れ落ちた。
「あ! 勇者様見てくれてました? 俺、なかなか首跳ねるの上手にだったでしょう?」
軍人の男はこちらに駆け寄って来ると、笑顔を浮かべながらそういった。
これは一体なんなんだ。人間の方が『悪』ではないか。
――――勇者よ! 我々魔族が何をしたというのだ! 己が目で確と見定めよ!
手打ちにする前の魔王の叫びが頭の中でこだました。
ああ、人間とはなんと卑しいのだろう。そう思うと、黒いもやが視界を掠め始めた。どうやら、体を覆っているらしい。
――――人を辞めたいか? 勇者。
ああ、辞めたい。
誰かの声ににそう答えたとたん、体にとてつもない魔力が溢れた。魔力が馴染んだ時には俺は人では無くなっていた。その姿は魔王にそっくりだった。
まずは軍人の男を殺した。さて、次は何をしようか。
疑似家族
――――愛してるわ
――――小学校はどう? お友だちはできたかしら?
――――明日は父さんと遊園地にいこう
――――お誕生日おめでとう
そこでハッと目が覚めた。ベットの横に立つ男にゴーグルを渡す。
男は『家族コンサルタント』とかいう仕事をしているらしい。ゴーグルで数多の親の元に生まれた未来を見せ、生まれる先を決める手助けをする仕事らしい。
「どうですか? その夫婦の元に生まれればある程度の幸せは保証されるかと思いますが……」
男は優しい笑みを浮かべそう言った。
「ええそうね。富豪の子供はあまり興味ないし、ここにする」
「承りました」
恵まれた家庭というのはやはり限りがあって、全員が全員幸せな家庭に生まれ変われるわけではないらしい。私がこうして、選べているのは抽選で一等に選ばれたから。
「選ばれなかった人はどうなるの?」
ふと、疑問がわいた。
「それは抽選で選ばれなかった人という意味で?」
お辞儀から顔を上げた男はそう問い返した。私は「そうよ」と答えた。
「それは……病気でどちらかを亡くした片親の家庭だったり、また虐待されたり、そんな家庭に生まれることになるかと」
「虐待……前の私は貧乏くじを引いたのね」
「ああ、勘違いなさらないでくださいね」
男は慌てたように言った。私は「勘違い?」と首をかしげた。
「我々の仕事は家族以外にもたされる幸せ、不幸せについては考慮していないんですよ」
「つまり?」
「つまり、どのような家庭に生まれても幸せになれないわけではないんです。覚えておいてくださいね」
そう言ってから男は「覚えておくのは難しいですね」とわらった。
邪険にされても
――――人々はお前を嫌うだろう。私がそういう呪いをかけたのだから。たった一人を除いてね。ああ、死なないようにしないとね。
幼い日の魔女のねっとりとした声が頭のなかでこだました。
僕には友人がいない。親がいない。親しい人は誰もいない。そんなんじゃ生きていけないだろうなんて言われるかもしれないけれど不死の呪いがかけられているんだから死ねる訳がない。
『たった一人』僕はその人を探していた。探して探して、見つけたと思ったら裏切られて、僕の心はずいぶんと擦りきれてしまった。
朝から雨が降っていた。そんななか歩いていても誰一人見向きもしない。いっそのこと死ねたら楽なのに。
「大丈夫? 風邪引くよ?」
そう言って、傘を差し出してきたのは同じ年ほどの女の子だった。
前にもあった。体質のようなものだろう。ほんのちょっとだけ僕から発せられる魔女の呪いにかかるのが遅いのだ。
「……あっちいけよ」
もう嫌なんだ。見つけたと思ったら裏切られて、どれだけ苦しめば気がすむんだ。
「絶対にいやよ!他人には優しくなさいって、かあさまがいってたもの」
「僕が嫌いじゃないの?」
おかしい、いくら遅くてもそろそろ効き始めるはずだ。
「何で嫌わないといけないの? それにほら、あなた瞳がとっても綺麗じゃない! 黄色……お日様の色ね。明るくてキラキラしてるわ」
「……ありがとう」
たった一人、受け入れてくれる人がいるだけでこんなにも世界は違って見えるらしい。
初めて、他人の瞳を綺麗だと思った。彼女の瞳は澄んだ空の色をしていた。
切断面
「これやるよ」
職場の図書館から出ると同僚にそう声をかけられて、何かを手渡された。
「俺の贔屓にしてる飴屋のなんだ。シンプルだがうまい」
そしてしゃあなと言うと、彼は足早に駅に向かって歩いて言った。その背に、ありがとうと声をかけると振り向きもせず彼は片手を上げた。
手のひらに収まるほどの丁寧にラッピングされた小さな箱。
うふふ、と帰り道思わず気持ち悪い笑いが漏れた。甘いものに頬が緩むのは甘党に生きる者の宿命だけれど、これは少し浮き足立ってはいないだろうか。足を止めて考えると潔く原因が思い当たった。初めてなのだ。異性から何か貰うのは。
家に帰りつくと、耐えきれずに玄関でラッピングを解いた。
小さな折り畳まれたカードを片手に箱の蓋を持ち上げる。中に入っていたのはハートの形をした金太郎飴だった。ひとつ指でつまんで口に放り込むと優しい甘さが広がった。
これはなんだろうと、さっきのカードを開くと彼の字が見えた。
『返事は明日きく。決めておいてくれ』
ぶっきらぼうに、けれど丁寧な字でそう書いてあった。
箱一杯のハート。つまりはそういうことらしい。
あまりの嬉しさと驚きに私はへなへなと座り込んだ。
めぐりあい
あれから千年、何度も生まれ変わりを繰り返しようやく今生で彼女を見つけることができた。
「君は誰? どこかで会ったことあったかしら」
それなのに彼女は僕のことを覚えていないらしい。
「本当に、覚えてないの?」
そんな言葉さえ吐くこともできずに唇を噛みしめて僕はうつむいた。血の味がしたけれどどうでも良かった。
「なんで? なんでなのよ――――!」
突然彼女はそう叫んだ。ポタポタと頬を伝わせて涙を落としていた。
「何で来たのよ! 千年も待って! よりにもよって――――!!」
「うん、ごめんね。許して」
そう言って、僕は点滴チューブを抜いてしまわないように彼女の細い手を握った。
「全部知ってるよ。それでも、どうしても会いたかった……」
「馬鹿!! もう私には時間がないのに!!」
うん、ごめんと僕は彼女をだきしめた。
「私を目一杯楽しませて。今度は笑って死にたいの。あと、もう一度約束してよ」
もちろん、とうなずくと僕は千年前と同じ誓いを口にした。今度は、千年もかけてたまるかと思いながら。
素振り
あるクラスの女の子が自殺した。教室の隅の机、その女の子が座っていた場所には花が生けてある。
ショックで学校を休む奴がいるくらいだから、人間関係はうまくいっていた方なのだろう。
「あいつ、何で死んだんだろうな?」
ある男子がそうポツリともらした。
「……知らねぇよ。そんな感じなかったもんな」
近くにいた奴がそう返した。
なんだ、わからなかったのか。『素振り』は充分あったろ?
心のなかで、馬鹿な会話をするそいつらに言ってやった。
思い返せばやたらめったら明るい歌を口ずさんでいたし、授業中はボーッとしていた。今思えばあれがサインだったのだろう。
女の子は遺書を残してはいるがマイナスなことは何一つ書いていない。死んだ理由は彼らには推測しかできないはずだ。そう思うと僕は心底愉快だった。
やっぱり、成仏しないで正解だった。しばらくはこうして現世をぶらぶらしていよう。
冷たい
彼女とふたりで夜の住宅街を歩いていた。空にはまんまるな月が上っていてライトなんて持っていなくても充分に明るかった。
「今日は楽しかったよありがとう」
先を弾むように歩いていた彼女がこちらを振り返って言った。その顔には笑顔が浮かんでいて僕は良かったと思った。
「実はね、あの映画君に気に入って貰えるかドキドキしていたんだ」
後ろ向きに歩く彼女に転けて怪我しないかな、なんて思ったけれどすぐにそんな心配はいらないなと思い直した。
「えー何で!? 面白かったよ。正しく私の好みにドンピシャ!『トクトク言うてるか? ん? トクトク……』」
彼女はそういうと一人でウフフとわらった。
僕らはいつしかとある住宅街から外れてとある場所に来ていた。
「だからね、今日はありがとう」
彼女はそこで歩みを止めた。
「うん」
そう頷いて彼女の手を握ると氷のような冷たさが伝わってきた。
「ダメだよ? 貴方はまだダメ。今度のためにオススメの映画探しておいてよ」
悲しそうに彼女は微笑みながら彼女はそういった。
「わかった」
そう言って僕が彼女の手を話すと彼女はスッと消えた。
目の前には川が流れている。
3年前の今日、小学生を助けようとして小学生は助かって彼女ひとり溺れて死んだ。そんな場所。
今年もついて逝くことはかなわなかった。彼女はいつになったら許してくれるだろうか。
隔たり
海から吹きはじめた風がますますヤナギの鼻を掠める潮の香りを強くした。今日の海は昨日の海より綺麗だ、ヤナギはそう呟いた。
「そうなの?」
海と陸を隔てる柵に寄りかかる彼女がヤナギに尋ねた。
「昨日は雨だったから。雨の日の海は灰色であまり綺麗ではないよ」
ヤナギは海に目を向けたまま答えた。「まあ、僕はいつの海も好きだけどね」
「そう、良かったじゃない。それならここにいくらいても飽きないでしょう?」
彼女は優しげな笑みを浮かべた。それにヤナギは困ったように微笑み返した。いくら好きでも、飽きるものは飽きるのに。
「君は飽きないの? 晴れの日は毎日ここに来ているけど」
「飽きないわよ。私は元々山生まれで、水遊びといっても川ばっかり。本物の海を見たのは大人になってからなの」
海の無い暮らし。ヤナギには予想もつかなかった。ヤナギのそばにはいつも海があるからだ。
「ここに残れば? 僕と」
ヤナギは彼女を見つめていった。彼女は見つめ返しておかしそうに笑った。
「やあね。告白? あなたの告白を飲んだら私、ここから海に飛び込まないといけないわね」
彼女は冗談めかしていった。
「冗談だよ。友達でいいんだ。僕らは。これからもずっと」
ヤナギはそう答えると、視線を落とし鉄柵を掴む己の透けた手をじっとみつめた。
痛覚
痛覚が無くなった。
そう、トウダが自覚したのは休日のお昼時だった。うっかり、包丁を落としてそれが足の甲に刺さったのだ。白が見えたかと思えば、ぷくりと溢れ出る、赤。すくそばの床に転がる包丁。いくら、勉学を苦手とするトウダにもこの状況で『痛くない』事は異常だとすぐに気が付いた。
しかし、トウダは病院には行かなかった。幼い頃から『医師』という職業人は苦手で、どうも重い腰が上がらなかったのだ。
トウダは傷の血を拭き取るとガーゼを被せ包帯を巻いた。そして、ぬくぬくとした電気炬燵に潜り込んだ。
心地よいぬくもりにトウダが舟を漕ぎはじめてしばらくすると、インターホンの音が聞こえた。トウダが覗き込んだドアスコープの向こうには付き合って、半年ほどのトウダの彼女の姿があった。ニッコリと微笑んでいる。
「どうしたの?」
そうドアを開けた瞬間、トウダの体に衝撃が走った。よろめいて後ろに尻餅をつく。続いて骨盤辺りに彼女の重みを感じると、目の前を銀色が掠めた。一回、二回、三回、四回、五回、六回、……十一回まで数えたところで彼女は赤で、ぬらりとてらつく銀色を振り上げたまま、ふぅ……と息をついた。
彼女の訪問、きらめく銀色、妙な温かさを感じる身体、満足そうな赤に彩られた彼女の顔、まるでこのために痛覚が無くなったようだった。
トウダは徐々に重みを増す瞼を閉じると、神様も余程暇なんだろうなと、ほんの微かに口角を上げた。
掌編小説集