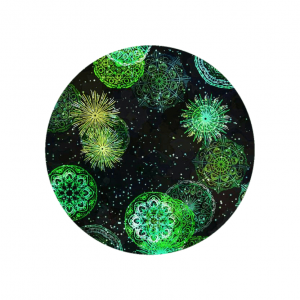Une rencontre
散歩に行こうと思ったのは降りだした雨がきっかけだった。
先日友人と喧嘩した。自己中心的で身勝手な振るまいについ声をあらげてしまった。冷静になり我に返った時には友人が走り去る後ろ姿が遠くに見えるだけだった。こちらに非はない。しかし、理由があったのかもしれない。謝ろうにも謝れず、ついに今日まで来てしまった。
だから、気分転換に散歩をすることにした。傘にポツポツと響く雨音に耳を傾け、濡れたアスファルトや土の匂いのする空気の中で呼吸するうちに心の中の重くどろどろとした感情は少しずつ雨に流されて行った。
雨は昔から好きだった。怒られたり、何か嫌なことがあったときに雨が降ると心が軽くなった。まるで泣いた後のように。それを友人に話してみると怪訝そうな顔をされた。どうやら皆がそうではないらしい。
この町は昔、城下町で栄えていたと聞いている。いま歩いている大通りを真っ直ぐ行けば、城跡の公園が見えてくる。春には桜で、夏には何千という灯籠で彩られ、冬にはその公園の中の城の城主の奉られる神社への初詣でにぎわう場所だ。最近は城下町というのをコンセプトに町おこしがおこなわれていて建物が和風に改装されたものとそうでないもので混在している。
カフェの手前で脇道に入ると一気に昭和の香りが漂う。あくまでも、個人のイメージではあるが。
目当てはその通りにある店の今川焼きだ。老夫婦が作るそれは餡がぎっしりと入っていて薄い生地は焼きたてだとパリッとしてさらに美味しい。値段も一個百円とお手頃だ。白餡と黒餡を二個ずつ買い受け取った。
「一個おまけしといたわよ。常連さんにはサービスしとかなきゃね」
おばあちゃんがニコニコと笑って言った。相変わらず笑顔の可愛いひとだ。
「ありがとうございました。また来ますね」
笑顔を浮かべて答えた。さらに、奥で険しい顔で型に生地を流し込むおじいちゃんにもお礼をいうと店を後にした。
「ユネ……ユニレコントレ……?」
しばらく歩くと読み方のわからない看板掲げた和装建築の店を見つけた。最近できたらしい。少なくとも前来たときにはこの建物は空き家だったはずだ。白い文字で『Une rencontre』と書かれた小さめのそれは入り口の右側にかけられていた。そのとなりにはさらに一回り小さい木の板に同じく白い文字で『Open』と書かれたものが掛けられていた。一体何の店なのか気になり、ガラス窓から中を覗いた。
店内の土間には棚が並べられ、商品と思われる文房具がところ狭しと陳列されているのが見えた。右奥の一段高くなった畳の間では戸が開け放たれ、黒縁メガネの店員と思わしき青年が正座でぼーっと、虚空を眺めていた。
入りづらいな、また今度にしようか、そう思い始めたそのとき、急にばっと青年がこちらを見た。
「ひゃう……!」
驚いて出た変な声に恥ずかしさを覚えながらも青年と見つめあったまま動くことができなかった。先に動いたのは青年だった。顔に笑みを浮かべ、どうぞ、と口の動きだけで言った。加えて、手で入り口の方を示した。
「お、お邪魔します」
入り口の引き戸を遠慮がちに開け、通り抜ける。
初対面の人を相手にするのは苦手だ。たとえ、店員であっても。
「いらっしゃいませ」
優しい声音だった。緊張した体から無駄な力が抜けるのがわかった。ふう、と息を吐き、一番近くの棚から見ていくことにした。
ボディが木でできたペンやシックなデザインのシャープペンシル、シンプルでお洒落なノートなど、どれも普通の店ではあまり見かけないような文房具だった。
ボディが木のペンを手に取り、試し書きの紙に『望月桜良』と名前を書いた。驚くほど書きやすい。重さもちょうど良いし、握り心地も申し分ない。心が踊っているのがわかった。
「好きなんですか? 文房具」
そう声をかけられて振り返ると、あの青年がいた。
「はい、大好きです。使うのも見るのも昔からわくわくします。いいですね、このペン。書きやすくて、木の温もりがあります」
初対面の人相手にすらすらと紡がれる言葉に内心、驚いた。やればできるじゃないか、と心の中で自画自賛する。おそらくそれは、青年の優しい声音と穏やかな店の雰囲気のおかげだろうが。
青年は嬉しそうにうんうんと頷いた。
「わかりますよ、桜良さん。僕はそれが高じて文房具屋になったくらいで。そのペンも一目惚れだったんです」
青年がこちらを見る。
「学生の頃は文房具オタクと良く友人にからかわれました」
そして、青年は苦笑しながら言った。
友人、というワードに喧嘩していたことを思い出した。浮遊していた心がずっしりと沈み込んだ。
「ご友人……がどうかしたんですか?」
青年は不思議そうに首を傾げていた。どうやら無意識に口から出ていたらしい。
「いえ……」
困って眉に皺が寄った。
「何か悩みごとなら良かったら僕に話してみませんか?」
「でも、迷惑じゃ……?」
青年がいいえ、と首を振った。
「……それにこの雨では他のお客さまも来ないでしょうし、時間ならたっぷりとありますよ。どうですか? お茶でも飲みながら」
青年は畳の間を示した。
「じゃあ、お言葉に甘えます」
その言葉に青年は嬉しそうに破顔した。
畳の間に案内されて、青年がちゃぶ台の前に出してくれた座布団の上に座った。
「どうぞ、アイスティーです」
台所から戻って来た青年は目の前にそれをおいて言った。ちらりとこちらを見て何かに気づいたような声をあげた。
「そういえば、自己紹介を忘れてました……僕は海汐雫と言います」
忘れていたことがよほど恥ずかしいのか耳が赤くなっている。
「はい、よろしくお願いしますね。雫さん」
海汐雫、良い名前だと思った。青色を連想する名前だ。
「ああ……はい。それで、悩みごとでしたね。ご友人がどうかしたんですか?」
彼は気を取り直すように居住まいを正して尋ねた。
「えっと……私、喧嘩してしまったんです」
こちらも、彼につられるようにして居住まいを正して答えた。
「喧嘩ですか、どんなことで?」
喧嘩の内容や言った言葉を洗いざらい話した。雫さん……彼は所々で相づちを打ちながら、熱心に話を聞いてくれた。
「桜良さんは優しいひとですね」
全て話終わったとき、彼は言った。
「話を聞いたところ、あなたが声をあらげてしまうのも当然だと思います。それでもあなたは、そのご友人を心配して、謝ろうと思っている……僕には真似できませんよ」
彼が微笑みながら言った。優しいのはあなただ、と言いたくなった。
「でも、謝る勇気が出ないんです。いざ面と向かうと、言葉が喉につっかえてしまって……」
あー、と彼が同意するような声をあげる。
「僕にもありますよ、そんな経験。そんな時はですね、手紙にしたためれば良いんですよ」
「手紙に、ですか?」
「はい。文字には人の心がこもるものなんですよ。それが誰かに宛てたものなら尚更」
なるほど、と思った。
「そうなんですね。じゃあ、手紙書いてみます」
うんうん、と彼は笑顔で頷いた。
「桜良さんの悩みが解決しそうで良かった」
彼の方が喜んでいるように見えるのは何故だろうか?
「解決の目星がついたところで、一緒に今川焼食べませんか?」
それでも、充分にこちらも気分が高揚していたらしく、気づけば今川焼の入った袋を掲げながらそんなことを口走っていた。
「あ、えっと……解決しそうなのは雫さんのおかげですし、美味しいので……!! えっと……」
ああ、何を言っているんだろう。穴があったら入りたい。否、自分で穴を掘ってでも入りたい。
「良いんですか?」
彼は微笑みながら言った。
「はい! ああ……でも、甘いものは平気ですか?」
男の人は甘いものが苦手なイメージがある。
「むしろ、大好物ですよ。桜良さん」
その言葉を聞いて良かった、という言葉と共に安堵のため息を漏らした。
今川焼の入った紙袋をちゃぶ台の上に出して、取りやすいように破って広げる。美味しそうな匂いが鼻腔をくすぐっている。
「小判の焼き印が入っている方が白餡で、何にも入っていない方が黒餡です。どうぞ」
彼は白餡の方を手に取った。いただきます、と呟くと、がぶりとかぶりついた。それを合図にこちらは黒餡の方に手を伸ばし、食べ始めた。
美味しい。焼きたてではないけど温かいし、相変わらずちょうど良い甘さだ。
「んー!! 美味しいですよ、桜良さん!!」
彼がいきなりそんな感嘆の声をあげた。吃驚して体が跳ねた。
「あっ、すみません。でも、こんな美味しい今川焼は初めてで……」
「いえ、喜んで頂けたみたいで良かったです。こんなに餡もたっぷりで、生地も薄い今川焼は珍しいと思うんです」
あの店以外のものは生地が厚かったり、餡が少なかったり甘すぎたりして、落胆することが多かった。初めてこれを食べたときはあまりの美味しさに雷に撃たれたような衝撃を覚えたものだ。
「そうですね。ここまで餡を惜しげもなくたっぷりと入れられていると、逆に経営は成り立つのか心配になります」
彼があまりにも真剣な顔でいうものだから、なんだかおかしく思えて声をたてて笑ってしまった。
「何で笑うんですか? 桜良さん……」
彼はすねたらしく、唇を尖らせて言った。
「……いえ、ごめんなさい。なんだかおかしくって。でも、結構長く続いているし、経営難で潰れちゃうなんてことはないと思いますよ」
ああ、でも老夫婦で営んでいるし、年齢の関係でお店を畳んでしまうことはあるかもしれない。それは寂しい。果たして跡継ぎはいるのだろうか。
「それなら、よかった」
彼は安心したように息をつき、微笑んだ。そして、彼の意識は今川焼の方へ戻った。すっかり拗ねていたことは忘れてしまったみたいだった。
その後今川焼に二人で舌鼓を打ち、雑談に花を咲かせた。
「じゃあ、私そろそろお暇します。その前に、さっきのボディが木でできたペンとレターセットの勘定をお願いしますね。持って来るので……」
彼が承諾したのを聞くと、そそくさと土間に脱いでいた靴を履き、それらを持ってレジへ向かった。
「二千百円になります」
財布の中身に触れたときはた、と気がついた。
「レターセットの方は?」
それの値段が含まれていない。
「僕からのプレゼントですよ、桜良さん」
黒淵メガネの奥で目を細めて彼が言った。
「ご友人に手紙を書くようアドバイスしたのは僕ですし、美味しい今川焼も頂いてしまったので。心ばかりの応援とお礼ですよ」
「でも……」
「いいから、いいから」
断ろうとにもそこまで言われては断りずらい。
「あ、ありがとうございます」
結局、店の名前の入った紙袋に入ったそれらを受け取った。そこで、店の名前の読み方がわからなかったことを思い出した。
「そういえば、このお店の名前なんていうんですか?」
「ああ……、フランス語でユヌ・ラコンタルと読みます」
ユヌ・ラコンタル、と覚えるようにその単語を反芻した。
「日本語に直訳すると、一つの出会いという意味ですね」
一つの出会い、と今度は心の中で反芻する。
「良い名前ですね。このお店にぴったりだと思いま
す」
その言葉に彼は嬉しそうに笑って、ありがとうございますと言った。
「それじゃあ、また来ますね。今日はありがとうございました」
「いえ、僕も久しぶりに楽しい時間が過ごせました。またのお越しをお待ちしています」
笑顔の彼にペコリと軽く会釈をするとその店を後にした。
その夜、今日梅雨入りしたことをニュースで知った。
「桜良さん。今度の祭り、一緒に行きませんか?」
彼がそんなことを言ったのは、初めて『Une rencontre』を訪れて数週間が経ったある日の帰りがけだった。あれから何度も訪れては、文房具を買うというより畳の間で彼との雑談に花を咲かせていた。
二回目の訪問で仲直りできたことを報告したとき彼は一緒に喜んでくれた。
彼の言葉を聞いて道理で今日、挙動不審だったのかとひとり納得した。
「今度の祭りというと、あの城跡の公園である灯籠の?」
確か学校帰りにそれのポスターをみた気がする。はて、その祭りはいつあるんだっただろうか?
「はい。今週末の土曜日にあるんですけど桜良さんの予定は……もしかして、すでにご友人と約束してたり?」
彼は不安そうな表情をして、首をかしげた。
「いえ、あの子は友達が多いので祭りは他の子と行くみたいです。……行きたいんですけど私ひとりじゃ行く気にならなくて」
ひとりぼっちで屋台巡りはさすがに寂しい。
「じゃあ!」
彼が嬉しそうな声をあげた。心なしか瞳も輝いて見える。
「はい。ぜひ一緒に行きましょう、お祭り」
「ああ、よかった。断られたらどうしようかと……」
異性とお祭りに行くなんて初めてだ。浴衣を着てみようか。ああ、これじゃまるで……
「……デートみたい」
ポツリと心の声が漏れた。
「ふぁっ!? デ、デート!?」
自分で誘っておきながら、そういった捉え方はしていなかったらしい。そのワードを聞いてから彼は顔を真っ赤にしてあたふたし始めた。なんだか面白くてこちらはふふふっ、と笑った。そんな彼を見ているとこちらまで恥ずかしくなってきた。
「そんなにあたふたしなくても……」
彼に言った。とりあえず、落ち着いてもらわないとこちらの顔の火照りも取れそうになかった。
「そう、ですよね!」
そんな言葉を返した彼は胸に手を当て、深い呼吸を数度繰り返した。
「……落ち着きました?」
「はい。……すみません、取り乱しちゃって」
暑そうに、彼は手で顔を扇いだ。
「……どこで当日待ち合わせしましょうか?」
気を取り直した彼は言った。
「この店の前はどうですか? 此処からふたりで歩いて行きましょうよ」
首を傾げながら提案する。
「良いですね。じゃあ、夜七時半に此処で」
そんな約束をしてその日は別れた。
そして祭り当日。
浴衣を着てカラコロ、カラコロと下駄を鳴らしながら待ち合わせの場所へと向かった。
彼はどんな格好をしているだろうかと内心わくわくしていた。
「雫さん!」
名前を呼ぶと黒いかすれ縞の浴衣を着た彼と目があった。とても浴衣が似合っていた。
「……こんばんは、桜良さん」
彼が微笑んで言った。
「浴衣着て来たんですね。良く似合ってますよ」
「あ、ありがとうございます」
褒められて、嬉しくてそれでも恥ずかしくてペコリと頭を下げて言った。
「……雫さんは格好いいですね」
ちらりと見上げてそう言うと、彼はそっぽを向いてしまった。どうしたんだろう? 本当なんだから恥ずかしがることはないのに。ああ、ひとのことは言えないか。
「……それは、ありがとうございます。さて、行きましょうか」
ふたりで並んで歩いた。カラコロと鳴るふたり分の下駄の音は屋台が出る辺りまでくると人混みの騒音に溶け込んでしまった。
「桜良さん、リンゴ飴がありますよ! 食べます? でも、最初はかき氷にしましょうか? クレープも美味しそうですよね」
わくわくと効果音が聞こえそうなほど楽しそうに彼は言った。候補に出てきたのは全て甘いもので、甘いもの好きな彼らしいと思った。不意にもかわいいと思ってしまった。彼は成人した男性なのに。
「そうですね……」
冷たいものが食べたいと思った。
「まずはかき氷にしましょう!」
「いいですね!」
ふたりでその屋台に近づけば人の良さそうなおじさんが店番をしていた。
「何味にします?」
並べられたシロップを見ればかなりの種類があった。悩んだけれどスタンダードにイチゴ味に練乳をかけてもらうことにした。
「イチゴ味の練乳かけください」
「僕も同じのを」
彼も同じものを頼んだ。
手提げ鞄からいそいそと財布を取り出す。
「あっ、桜良さんだめですよ」
さらに小銭を出そうとしたその時、そんな言葉共に手をやんわりと押さえられてしまった。
「僕が奢れなくなっちゃうじゃないですか」
彼は微笑んで言った。
それはいけないと思った。ただでさえ屋台の品物は一つ一つが高いのだから。
「あの、やっぱり自分で……」
「いいから、いいから。ここは男の僕の顔を立ててください。ね?」
彼は言った。そんなふうに言われてはいつかのように断ることはできなかった。
「そっちで食べましょうか?」
彼が言った。
彼の手からかき氷を受け取るとふたりで道の脇に寄った。できたてのかき氷を歩きながら食べるのは難しいからだ。
慎重にすくって口に入れれば冷たい甘みが広がった。
「本当に良いんですか? 奢って貰っちゃって」
そう問いかけると、氷の山をサクサクと崩していた彼がこちらを向いた。
「良いんですよ。もとよりそのつもりだったんですから」
浮かない顔をしているのに気づいたのか彼は困ったように微笑んだ。そして、提案した。
「じゃあ、こう考えませんか? 僕は桜良さんとの時間を買い取っている、というふうに」
「時間を?」
ええ、と彼はうなずいた。
「だから、奢るお返しにこれからも僕の店に来て僕と雑談してください」
商談ですよ、と彼が笑う。
「僕はあなたと過ごすあの時間が大好きなんです。……どうですか?」
そんなのではなんにもならないと思った。あの時間が大好きなのはこちらも同じだから。
「良いですよ、商談成立ですね」
でも、彼とのこれからが約束できるのならいいかと思った。
彼は嬉しそうに笑った。
「さて、それでは次はどれ行きましょうか?」
気付けば手に持っていたかき氷はもったまま歩き回れるほどに溶けてしまっていた。
それからもふたりでクレープ、ポテト、リンゴ飴と屋台を順にまわった。クレープとポテトを一緒に食べてみると意外に美味しかった。
「そろそろ、灯籠を見に行きます?」
リンゴ飴片手に彼は言った。
「行きましょう、今年もきっと綺麗ですよ」
何千という竹灯籠が並べられるこの祭りはまあまあ有名で毎年地元のテレビで報道される。今年もテレビカメラが来ているんじゃないだろうか。
「僕、実はこの祭りは初めてなんです。だからそれもあって、あの日からずっと楽しみにしていました」
ふたりで並んで歩いていると彼は言った。
「この町に来るまで毎年、テレビで見るだけでずっと来れず仕舞いだったんですよ」
「じゃあ、こころゆくまで存分に楽しみましょう」
そう言って笑いかけた。彼もそうですね、と笑った。
それから数分もしない内に目的の場所にたどり着いた。
「これは……想像以上の数ですね」
ずらりと並んだ竹灯籠を前に彼は言った。
「多いでしょう?」
ええ、と彼は答えた。
斜めに切った竹筒の切り口の中に入った蝋燭の灯りが風にゆらゆらと揺らめいて、幻想的な雰囲気を作り出していた。
「まだ上にもあるんですか?」
彼は脇を竹灯籠に縁取られた上に続く坂道を見上げながら言った。
「ありますよ。上は多分、小学生が作った灯籠じゃないかと思います」
小学校時代の記憶を引っ張り出しながら答えた。
「竹ひごで作った立方体の枠に和紙をはって作るんです。絵とか文字を自分で好きに入れられるので、たくさん並べられた灯籠の中から自分のを探すのもこの祭りの日の楽しみでした」
探しまわっていつの間にか両親からはぐれて迷子になったことも今では良い思い出だ。
「へぇ、いいですね。それは是非とも、桜良さんが作ったものを見てみたかったです」
彼が言った。
「私のは何の捻りもなかったですよ。毎年、祭りから連想して金魚描いてましたから。そのお陰で今でも金魚の絵には自信があるんですけどね」
「いいですねぇ、僕には絵心がないので羨ましいです」
「でも、雫さんは字が上手ですよね。私はそっちの方が羨ましいです……お互い様ですね」
無い物ねだりというやつだ。
彼は、そうですねと笑った。
「上にも行ってみましょうか?」
彼が言った。
「そうですね、いきましょう」
この坂道が地味にキツイのだ。下駄ならば尚更。さらにぐねぐねと曲がりくねっている。真っ直ぐ作れば少しは楽なのにと、ここに来る度思う。
彼は時折リンゴ飴をかじりながら登っていった。その隣でこちらはカリッと剥ぎ取ったリンゴ飴の飴をポリポリと噛む。
坂道はキツイが口の中は幸せだった。
「これは何の絵でしょう? ……ゴキブリ?」
坂道を登りきって、一番手前の列の真ん中にある灯籠を見ながら彼は言った。
「……違うと思います。カブトムシか、クワガタのメスじゃないですか? 多分」
『ぼくのペット』とクレヨンで書かれた横に同じくクレヨンで甲虫らしき絵が描かれている。
多分、カブトムシかクワガタだ。でも彼がいうようにゴキブリにも見える。
「たとえこの『ぼくのペット』がゴキブリだったとしても今の時代珍しくもないと思います。この前、動画サイトにペットの蛭に自分の血液を与えているシーンの動画がアップされてましたし……」
あれは純粋に驚きだった。思わずサムネイルを二度見した。
「それは、なんというか……凄いですね」
彼はゆっくりと言った。
「もしかして、虫苦手なんですか?」
もしそうならば今後そういう話は避けるようにしよう。
「いえ、カブトムシだとかバッタのような生き物は見るのも触るのも平気ですけど、蛭とか蛞蝓みたいな生き物はさすがに苦手ですね。あんなヌメヌメした生き物、どこを持てば良いのかわかりませんし……そもそも触りたくないです」
彼の言うことには共感できた。確かにどこを持てばわからないし、生理的に嫌悪感を覚える。
「同感です」
しばらくリンゴ飴をかじる音だけが二人の間で響いた。灯籠の揺らめくあかりはずっと見ていてもあきない。
でも、この沈黙はそこまで長くはなかった。
「……桜良さん」
突然彼に呼ばれた。ゆるりと視線を上げて彼を見る。
「なんですか? 雫さん」
彼を見つめて次の言葉を待った。
「あの、ですね……」
彼はそこまで言うと口ごもった。
何か言いにくいことなんだろうか?
「……金魚取り、しても良いですか? そろそろ屋台も終わっちゃうので」
彼は笑って言った。
「ああ、早くから取ってたら酸欠で死んじゃいますもんね、金魚。いいですよ、私もやりたいです」
たったそれだけのことを言うのに彼は何を迷っていたのだろう?
金魚取りではそれぞれ赤い金魚を一匹ずつ取った。それに黒い出目金を一匹ずつおまけしてくれて、しかも金魚の袋に酸素を入れてくれる店主は好い人だと思う。
「飼うための道具は一式揃っていてあとは金魚だけだったんです。まずは薬浴させてあげないと、ですね」
祭りの帰り道彼は金魚の入った袋を顔の前に掲げながら言った。
「そうですね、病気になって死んじゃったらかわいそうですから」
金魚も疲れると免疫力が下がって病気になりやすいとペットショップのおじさんから聞いたことがある。
「あっ、雫さん私こっちなんです」
危ない危ない、このまま彼の店まで行ってしまうところだった。
「ああ、家まで送っていきますよ。夜道はひとりでは危ないですから」
彼は言った。
「でも、今の時代男性も油断できないそうですよ?」
学校周辺で不審者が出た時の担任の言葉を思い出して言った。
「大丈夫ですよ。僕はこれでも高校時代柔道部だったんですから」
彼は安心させるように笑った。
「柔道部……? 文芸部とかじゃなくて……?」
柔道部だった、と聞いて驚いた。彼のような人は文芸部だったと言われた方がしっくりくる。
「ああ、文芸部もしてましたよ。メインはそっちでした。柔道は護身で……」
へぇ、と感心した。要するに兼部していたらしい。
「だから家まで送らせてください」
彼は再び言った。よっぽど心配してくれているらしい。
「じゃあ、お願いしようかな……」
お言葉に甘えることにした。ひとりで夜道を歩くのはやっぱり怖いのだ。不審者と言うよりお化けが出るんじゃないかと。
二人ならんで雑談しながら歩いているとあっという間に家についた。
「今日はありがとうございました。いっぱい奢って貰っちゃって……」
玄関前で言った。
「ぼくの方こそありがとうございました。桜良さんと一緒に行けて楽しかったです」
彼が笑顔で言った。
「私も楽しかったです。また行きましょうね」
本当にまた彼と祭りに行きたかった。
「はい、また行きましょう」
その言葉を聞くと彼は嬉しそうに答えた。
「……お休みなさい。雫さん」
「お休みなさい、桜良さん」
事件が起こったのは、祭りから数週間後の晩秋のある日の朝に『《Une rencontre|ひとつの出会い》』を訪れた時だった。
彼は畳の間のちゃぶ台にうつ伏せになって眠っていた。
「あれ……雫さん?」
今日はお休みだったかと疑った。しかし、すぐに『Open』の木の板が掛けられていたことを思い出した。
「……もしかして、体調が悪い?」
よくよく見れば耳が赤い。とにかく触れて熱があるかどうか確かめようと、土間で靴を脱ぎ畳に上がる。
「失礼しますよっと……」
そう呟き、自分の額に触れながら余った方の手で彼の頬に触れた。
「嘘……どうしよう」
彼は発熱していた。しかも、かなり熱が高い。
「雫さん、起きてください」
彼の名前を呼び、体を揺する。
「……んっ。あ……桜良さん、来てたんですね。すみません、今お茶を……」
声が掠れている。
痛くないんだろうか?
彼はちゃぶ台に手をついて立ち上がりかけた。それを慌てて止める。
「ま、待って下さい! 雫さん、あなた熱があるんですよ!」
「え、熱?」
彼はキョトンとした顔で言った。
まさか、こんなに顔を赤くしてトロンとした目をしているのに自分じゃ気付いていないのか?
「体温計、どこにあります?」
「それならそこの押し入れの中の小さいタンスの上から三番目に……」
彼に言われた通りの場所から体温計を取り出して手渡す。
「はかってください」
彼はそれを受け取ると脇にはさんだ。一分もしないうちにピピピッと音が鳴った。
「さ、三十八度九分……」
彼読み上げた。
それを聞いて思わず呻いた。思ったより高かった。
「雫さん、今日はお店お休みにして病院行きましょう! 私が付き添いますから……」
こんなに熱が高かったら、ひとりで病院に行くなんて無理だろう。きっと、ふらふらだ。
「でも……」
彼は口を開いた。てっきり病院は嫌だとか、嫌いだとか言うのだろうと思った。でも違った。
「今日は日曜日ですよ。近場の病院は、お休みです」
彼に言われて気が付いた。確かに日曜日にはこの町の病院や診療所はお休みだった。どうしてもという場合は隣町の病院まで行かないといけない。しかもここから車を使っても三十分はかかる距離だ。
「……僕、車持ってませんし」
彼が付け足すように言った。
いや、もし持っていたとしてもそんな状態じゃ運転なんかさせられない。公共交通機関を使うにしても今の彼では無理をさせることになる。
「じゃあ、寝てて下さい。私が看病します。布団はどこですか?」
「それは二階の……でも悪いですよ、やっぱり。そこまでしてもらうなんて。移すといけないので桜良さんは帰って下さい」
彼は言った。
「大丈夫ですよ。台所借りますね。薬はありますか?」
帰るなんて出来ない。きっと心配で何も手がつかなくなる。
「……心配しなくても夕方には帰ります。それまでに雫さんがひとりでも大丈夫なように色々準備するだけですよ」
「薬はないです。台所は自由に使って下さい。僕は二階で寝ときますね。夕方までお世話になります」
彼は諦めたように力なく微笑むと言った。
「はい。任せて下さい」
ゆっくりと階段を上って二階に消える彼を見送ると台所に入った。まずは買わなくてはいけないものを見極めようと冷蔵庫を開けた。
「おお、凄い……」
中身がきれいに整頓されていた。どうやら彼は独り暮らしでもしっかりと自炊しているらしい。炊飯器も見てみればちゃんとお米が炊いてあった。
「玉子と粉末だしはあったから、要るのは小ネギにポカリに冷えピタに風邪薬っと……よし」
ブツブツと呟きながら持っていたメモ帳にメモをした。
そして、財布だけを持って靴を履くと店を出た。そのついでに木の板を『Open』から『Closed』にひっくり返す。
「急がないと……」
近くの馴染みの店にいくことにした。そこに行けば全部揃うはずだ。
「あらー、桜良ちゃんじゃない!」
野菜コーナーで小ネギを手にしたとき後ろから声を掛けられた。
「あ、古山のおばさん、こんにちは」
振り替えればお隣のおばさんがニコニコと笑いながら立っていた。
こんにちは、で良かっただろうか? 今の時間は十時四十分で個人的におはようとこんにちはのどちらが良いか迷う時間帯だ。
「はい、こんにちは。もしかして……誰か風邪引いたの?」
古山のおばさんはこちらの買い物かごを見ながら尋ねた。後は小ネギを入れてレジで精算するだけだっただけにそう推理するのはたやすいのだろう。
「はい。友人が風邪を引いてしまって熱があって……」
「あらら、大変。もらわないように気をつけてね」
古山のおばさんはそう言うと去って行った。嵐のような人だと思った。
彼のことを友人と表現したとき少し違和感を覚えた。しかしそれは彼が心配なあまり、すぐに頭の片隅に押しやられてしまった。
「あ、お帰りなさい。桜良さん。すみません、パジャマ姿で……」
店に戻るとどういう訳かパジャマ姿の彼が畳の間で土間にあしを投げ出すようにして座っていた。マスクをつけて。
「なんで……も、もしかして喉が渇いちゃいました?」
慌てて買い物袋からポカリを取り出す。
「いえ、そうじゃないんですよ。これは好機だなと思いましてね、それで僕は用事を済ませてここにいるんです」
そう言って彼は笑った。
「……意味がわかりません」
何がなんなのかさっぱりだ。
「わからなくて良いんですよ。やっぱりそれ貰って良いですか? 喉が渇きました」
ポカリを手渡す。すると彼は一口ずつゆっくり飲んだ。やっぱり喉が痛いらしい。
「ポカリなんて久しぶりに飲みました。五臓六腑にしみわたりますね」
彼が健康な時に比べて少しハスキーな声で言った。どうやら彼は熱が出ると饒舌になるらしい。あと、意味のわからないことを言う。
「お粥作るので待ってて下さい。食べたら薬飲みましょう」
「はい。桜良さんの手料理ですね、楽しみです」
「寝ときます? それならできたら持って行きますよ?」
そう尋ねると彼はゆるゆると首を横に振った。
「いえ、僕は料理する桜良さんを見ながらここで待ってます」
「無理はしないで下さいね」
袋から冷えピタを取り出し、彼の額に張り付けた。彼は冷たそうに首をすくめて笑った。
それから、背中に視線を感じながら卵粥を作ることになった。
時々チラリと振り返れば彼はニコッと笑う。
「見てて楽しいですか?」
数度目にボウルに入れた卵を菜箸でほぐしながら問いかけた。
「楽しいですよ。桜良さんはエプロンが似合いますね。可愛いですよ」
彼は目を細目ながら言った。
「あ、ありがとうございます……」
初めて可愛い、なんて言われた。これも熱のせいだろうか? どうしよう、恥ずかしい。
「雫さん、熱測って見てください」
恥ずかしさを紛らわすように言った。
グツグツと煮たった土鍋に溶いた卵を投入した。少し固まったところでかき混ぜる。続いて小ネギを入れようとしたところでピピピッと体温計がなった。
「何度でした?」
小ネギの入った器片手に尋ねた。少し上がっているかもしれない。
「三十九度二分です」
やっぱり上がっていた。もし、薬を飲んでもまだ上がったり、下がらなかったら一足早いインフルエンザかもしれない。しかもこの町の第一号。まだインフルエンザが出たという噂は聞いていないから。
「僕、風邪はごくたまにしか引かないんですけどね、そのときはいつもこのぐらいは高くなりますよ。これはまだ低い方です」
彼は言った。
「最高は何度なんです?」
今でも充分高いのにそれ以上とは一体何度なんだろう?
「四十度、丁度です」
彼は自慢げに答えた。
「自慢することじゃないですよね!?」
思わずそう叫びぎみに言ってしまった。
「でも、自慢したくなりませんか? だって四十度ですよ? 羨ましいとかないんですか?」
口を尖らせながら彼が言った。
「それは分からないこともないですけど、羨ましくはないです」
四十度なんて高熱出したくなんかない。きっと意識も朦朧とするだろう。
「冗談です。羨ましいなんて言われたら逆にびっくりします」
「でしょうね」
答えると土鍋に視線を戻し小ネギを投入した。軽くかき混ぜたら卵粥の完成だ。
「出来ましたー」
お盆に土鍋と蓮華とお椀をのせて彼に持って行く。
「おお、美味しそうです」
目の前で土鍋の蓋を開ければ彼が言った。
「どうぞ。無理はしなくて良いですからね」
お椀によそったそれを手渡しながら言った。
彼は卵粥を蓮華の上で吹いて冷ますと口に運んだ。
「美味しいです。桜良さん」
彼はゆっくりと咀嚼して飲み込み、言った。
「僕、誰かにご飯を作って貰うなんて久しぶりなんです。嬉しいですね」
ふふっ、と笑いながら彼が言う。
「変かもしれませんけど、熱が出て良かった、なんて思う自分がいるんですよ。今日は良いことだらけです。でも、桜良さんにとっては厄日かもしれませんけど……」
彼はすまなさそうに微笑んだ。
「そんなことないですよ。こうしてお話出来ているじゃないですか。楽しいですよ、私」
それに彼に手料理を褒めて貰えたのは素直に嬉しかった。
「ありがとうございます、桜良さん」
彼は言った。
そのあと彼は黙々と卵粥を口に運んだ。それでも食欲不振でお椀には半分ほど残った。
「すみません、残りは取って置いて下さい。後で食べます」
「はい。ラップをして冷蔵庫に入れて置きますね」
そう言って、彼に準備していた薬とコップ一杯の水を手渡した。ゴクリと飲み込んだところを見届けると、空のコップを土鍋等が乗ったお盆に一緒にのせて、それを持って台所に行く。
「桜良さん、僕此処にいて良いですか?」
その背に彼が問いかけた。
「辛くないんですか?」
振り返って問い返す。
高熱が出ていると座っているのも苦痛だろうと思った。
「辛いです」
彼が言った。
「なら……」
「二階にひとりは寂しいんです……」
寝た方がよくないですか? と続けようとしたとき、彼が言った。
「桜良さんが帰るときまで此処に居たいです。お話しましょう。ね?」
彼が必死さを滲ませながら言った。
「私が二階に行くんじゃ駄目ですか?」
無理をしてほしくない。出来る限りゆっくりと休んで欲しい。
「ちゃんと休まないと治るものも治りませんから」
「……じゃあ、わがままですけど、お願いします」
そして私が二階に行くことになった。
二階の彼の部屋で見たのは壁際の大きな本棚にずらりと並んだ本たちだった。上から下までぎっしりと詰まっている。
「凄い本の量ですね……」
まるで図書館の本棚のひとつをそっくりそのまま此処に移したみたいだった。
「読書、好きなんですよ。図書館で読んで気に入った本を本屋で買うんです」
彼は眼鏡外し、布団に入りながら言った。続いて眠そうに欠伸をした。
「……すみません、寝ます」
スポッと彼は布団に体を完全に預けた。
「良いんですよ。ゆっくりと休んで下さい」
「……本は好きに読んでいいですから」
彼はそう言うとすぐに眠ってしまった。
それから夕方まで彼の側で本を読んでいた。
そして、五時のサイレンが鳴り帰らなければいけない時間になった。本から視線を外し彼を見ればはじめに比べて穏やかに眠っていた。熱も下がっているように見える。この分なら明日の朝には平熱まで下がるだろう。
「雫さんそろそろ私帰りますね」
起こさないように囁いた。
せっかく眠っているのに起こすのは忍びないのだ。
立ち上がり、静かに部屋のドアまで向かう。
「――――桜良さ……」
突然、名前を呼ばれた。起こしてしまったのかと焦ったが、肩越しに振り返れば起きている様子はなかった。寝言だったらしい。
そうして、彼の看病は終わった。
家に帰り着き、家族皆で食べる夕食も終わり、自室でのんびりとしていると、突然かばんの中身を整理したくなった。
底を見れば飴玉の空とかレシートなんかが出てくるかもしれない。
「あっ、忘れてた」
そこまで考えるとそういえば今日入れておいたハンカチタオルを洗濯に出すのを忘れていたのを思い出した。
財布をどかして、それを取りだそうと触れたその時だった。カサッ、と音がした。何かが包まれているらしい。
「封筒……?」
横長の封筒だ。表には何も書かれていなかった。続いて裏を見ればデフォルメされタキシードを着たウサギがハートを持っているシールで封をしてあった。
「あ……えっ?」
見覚えのあるシールと封筒だった。確か、彼の店にあったはずだ。
戸惑い、興奮そして期待に指先が震えた。
期待? 何を? 彼からのラブレターかもしれないって……? 買い物の時微かに感じた違和感、それは私の中で彼が友人の範囲に入っていなかったからじゃないのか? 彼は友人じゃなくて……
「……好きな人」
そう口に出せば自分の中でバラバラだったピースがカチリとはまった気がした。
意を決して中から畳まれた便箋を取り出し開いた。
『桜良さんへ』
彼の字だった。
『突然のお手紙失礼します。驚かせたかもしれませんね。それは……すみません。』
はい。驚きましたよ、とっても。
『これは恋文です。僕から桜良さんへの。』
心臓が高鳴った。
『本当は祭りの日に告白するつもりでした。あの日、金魚を取りに行こうと言った時ですよ。でも、勇気が出ませんでした。』
だからあの時、躊躇っていたのか。やっと理由がわかった。
『だから、手紙にしたためることにしました。』
文字には心がこもると彼が言っていたのを思い出した。
『桜良さん、僕はあなたが好きです。あなたはどうですか? 僕のこと。』
そんなの、決まっている。
『返事は、わがままですが、手紙でお願いします。僕はあなたの字がみたい』
嬉しさに震える手を必死に押さえながらスマホを取り出し、電話をかける。
寝ているかもしれないけれど明日まで待つなんてできない。どうしても彼の声が聞きたかった。
三コール目で彼が出た。でも声はしない。
「……雫さん?」
電話口で彼の名前を呼ぶ。
「はい……」
風邪でかすれた彼の声が聞こえた。
「……手紙を読んだんですね?」
電話の向こうで彼が微笑んでいるのがわかった。
「驚いたでしょう?」
彼の問いかけに素直に、はい、とうなずいた。
「雫さん……」
まだ彼の名前を呼んだ。
「はい」
いつも話しているのにどうしてこうも緊張するんだろう?
「明日、お手紙書いて持っていきます。明日は日曜日にあった参観日の振替休日なので」
なんて書こう。『私も雫さんが好きです』から始めようか。考えるだけで頬がますます熱い。
「はい。楽しみにしています。けれど……すこし怖いですね」
「大丈夫ですよ、雫さん。……そういえば体調はどうですか?」
「ああ、もう熱は下がりましたよ。桜良さんの看護のお陰ですね。ありがとうございます」
「いえ、私が放って置けなかっただけですから」
ごほんごほんと、電話の向こうで彼が軽く咳き込んだ。
「それじゃ、桜良さん。また明日」
「はい。また明日。おやすみなさい」
「おやすみなさい」
通話の切れたスマホを握り閉めたまま、ベッドに倒れ込む。あの店は彼と出会った場所。そして、これからも会う場所だ。
開け放たれた窓から吹き込んだ湿っぽい風が火照った頬を優しくなでていった。明日は雨かもだろうか。もしそうなら、雨がもっと好きになれると思う。
Une rencontre