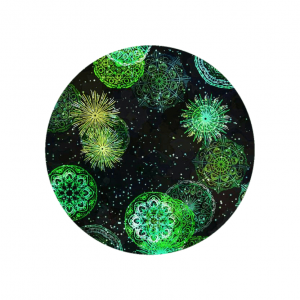桜枝の約束
遠くから豆腐屋の音色が聞こえていた。少しだけ開かれた窓からは甘い花の香りが風に乗り吹き込んでいる。その香りに誘われ、鼻先を窓側に向けた高根瑠璃はその視界にコクリ、コクリと船をこぐ男子クラスメイトを視界にとらえてクスクスと笑った。
「ハイ……じゃあ、終わりまーす!」
担任の合図に前方へ視線を戻すと他のクラスメイト等と共に立ち上がった。日直の号令に皆が口々に「さよなら」を言い、礼をした。このクラスになってから今まできっちり揃った試しはなかった。中には本を読む者や部活のスケジュールを確認をする強者もいる。それを担任教師がとがめることもないのだからすでに末期である。
瑠璃は机の両脇にかけた荷物を手に取った。教科書やノートを入れたそれらはやはりずっしりと重かった。
「またね、瑠璃さん。春休み明けに」
そんな風に声をかけたのはあるクラスメイトだった。
瑠璃はなぜ今日に限って、声をかけられるのかと不思議に思った。彼女とはただ、授業で組むことが多いだけの他人なのに、と。
「ばいばい」
綺麗に笑うと瑠璃はそう返し、家路についた。
「……」
その時の瑠璃の目はまるで濁った水が澄んだ時のような色をしていて、彼女は妙な不安にかられた。
瑠璃は自宅に着くと真っ直ぐと自室に向かった。扉を開けるとその時生まれた風に部屋の観葉植物の葉がサラサラと揺れた。荷物を放り、制服から部屋着に着替え終わると、勉強机前の椅子に腰かけた。引き出しから便箋と封筒を取り出すと、ペン立てからボールペンを手に取った。そして便箋に文字を書いた。「遺書」と。続いて便箋に文字を綴っていく。
瑠璃は生まれたその日に両親を亡くしている。母親は出産に耐えきれず、そして父親は仕事場から母親のいる病院に向かう途中、崖下へと車で突っ込んだ。それから、瑠璃は親戚の間をたらい回しにされながら育てられた。一度、施設にも入れられたこともあったが、今の家に落ち着いている。ここの夫婦は今までの家の者に比べ、良い方だ。腹いせに暴力を振るわれることもない。ただ、かなり養育が放棄されていた。一緒に食卓を囲むことも、言葉をかわすこともない。ただ、常軌を逸した金銭が与えられるばかりである。
――――どうか16年かけて、やっと幸せになれたのだと悲しまないでください。
最後にそんなお世辞ばかりの言葉で締めくくり、瑠璃はボールペンを置いた。丁寧に便箋を折り畳み、封筒に入れる。
なぜ、瑠璃が自殺を決めたのか、その理由は強いて言えば、生きる理由がないことだ。
何をしたいわけでも何になりたいわけでもない。毎日、「仮面」をつけ、本当の自分を隠す日々。ならば、死んで良いだろう。こんな、人並みの愛さえもらえない人生に何の価値がある? そんな心境だった。それゆえに、自殺を決めてしまったのだ。
瑠璃は机の引き出しに、遺書を仕舞い、居間に向かった。照明のスイッチを手探りに押せば、ソファーの前のテーブルに置かれた紙切れと、茶封筒が目に入った。紙切れによるとあの夫婦は今日から一週間ばかりの旅行に出たらしい。茶封筒の中身を確認すれば1万円札が十数枚。半月に一回のペースでこれが与えられる。もちろん、そんな大金使いきるはずもなく、ほとんどが貯金にされる。
夫婦の一週間の不在。絶好のチャンスだった。思わず、死神に愛されているのではと、考えるほどである。
瑠璃は、持っていた茶封筒をテーブルに放り投げた。飛び出した中身がハラリ、ハラリとテーブルの下に舞い落ちた。それを広い集めることなく、瑠璃は居間を出ていった。途中、何か食べようと冷蔵庫を覗くも、お茶とリンゴしか入っていなかった。
それも、当たり前である。あの夫婦は食事は外食で済ませるのに対し、瑠璃は自炊。つまり、買い物に行き、食材を冷蔵庫に詰めるのは瑠璃だけなのだ。そして、ここ数日買い物に行っていないのだから、当然の結果だ。
瑠璃はリンゴを手に取るとそのままかじりついた。パリッという小気味良い音と、共に口の中に甘味が広がった。心地よい香りが鼻腔をくすぐる。なんとも言えない、幸せな気持ちになった。これがあの文豪が言っていた、「末期の眼」とかいうものなのだと瑠璃は今さら気づいた。そしてそれに気づけたことが、なんだか嬉しく思えて上機嫌に笑った。
瑠璃はリンゴの芯をゴミ箱に放り捨て、風呂場に向かった。服を脱ぎ、浴室で熱めのシャワーを浴びる。排水溝に吸い込まれる水を眺め、入水にしようか、と思うもすぐに却下した。近くに海も川もあるが、どちらも人通りがかなりある。他人を巻き込みかねない。自分のせいで人が死ぬなんてあってはいけないのだ。そういうことが、瑠璃にとって死後の見目より大切だった。
さっぱりとした瑠璃は髪を乾かさずに自室に向かった。ベットに座り、考える。感電、服毒、飛び降り、練炭、首吊り……そこまでの方法と必要なものを考え、そして、思い出したように手を打った。ガサゴソと押し入れをあさって出てきたのは黒い縄だった。柔らかくしなり、太さも長さも強度も、充分だ。
その縄は浜辺に散歩へ行ったとき、拾ったものだった。手に取り、なんだか捨てるにしのびず、もって帰ったものが役立つ日が来るなんて、思ってもいなかった。他のガラスのウキなんかはインテリアぐらいしかならないのだから。
瑠璃は縄を手にベットに戻ると、ハングズマンノット、とか言う結びを端の方に作った。初めて作ったにしては上出来だった。瑠璃はあくびを噛み締めた。縄はベットの横に放り、モゾモゾと掛け布団とベットの間をに潜り込む。頭の中で家の中を一通り回ってみたものの、首吊りができそうな場所はなかった。瑠璃は明日山に行くことにした。
誰にも見つけられることなく、腐り果てることになるかも知れないが、それが草木や動物を育む糧になると思えば、おかしなことだが素敵に思えた。
瑠璃はもう一度あくびを噛み締めると、ゆったりと眠気に身を任せた。
窓の外から聞こえるガラスの鳴き声と、羽音に、瑠璃は眠りから覚めた。ベットから起き上がると、少し高めの位置にある窓から庭をみた。そこには、お米をついばむカラスがいた。数日前に撒いて置いたものにようやく気づいたらしい。大きなくちばしで小さなお米をついばむ姿はなんだかミスマッチではじめの頃は笑ったが、今ではこれもこれでかわいいかもしれないと思っていた。
外から視線を戻し、壁にかけた時計を見れば、針は10時を指していた。ずいぶんと遅い起床だが休みの日はいつもこんなものだ。瑠璃は一通りの支度を終え、遺書を居間のテーブルに置くと、縄を追加した外出用のリュックサックを背負い、家を出た。
服装はジーンズに白いTシャツ、水色のパーカーという格好だった。長目の髪は後ろでひとつにまとめられ、清楚な印象を受ける。加えて輝くような笑顔である。全く、自殺志願者には見えない。
瑠璃は頭の中に地図を広げ、手頃な山に目星をつけると、歩き出した。徒歩で行ける距離らしい。住宅街に入ると、猫が車のボンネットの上で日向ぼっこをしていた。猫好きの血が騒いだ瑠璃は慎重に、されど素早く猫に近づいた。猫は「なんだ?」とでもいうように、瑠璃を見たが、逃げることはなかった。存分にもふもふを堪能すると、瑠璃は再び歩き出した。そして大通りを越え、田園地帯に入ると、タンポポの黄色がよく目についた。その先の川では大きな鯉を見つけ、思わず感嘆の声を上げた。今の瑠璃には、世界がなんだか素晴らしいものに見えていた。自殺を決めたことで、曇りがとれたのか、それともそれとも装飾されたのか。過去の辛いことでさえ、どうでもよく思えていた。
瑠璃は山の麓に着いた。山の奥から流れてくる小川は山道の脇を通り、どこかに流れて行く。もしかしたらさっきの川に合流するのかもしれない。その小川の横には看板が立っていて、こう書かれていた。
『ホタルを呼ぶためにカワニナを放流しています。良い環境の維持にご協力下さい』
瑠璃はしゃがみ込むと、水の中をじっと見た。確かに小さな巻き貝が岩にくっついていた。川で見た物と比べるとまだまだ小さい。その時、瑠璃の視界を何か、白いものが掠めた。
「花びら……?」
瑠璃は思わず呟いた。それは間違いなく、桜の花びらだった。立ち上がり、上を見るも、もちろん桜の樹など生えていない。そもそも今年の春は例年に比べ、桜の開花は早く、今はとうに散っているはずなのだ。
また、桜の花びらが流れてきた。
それはこの小川を遡ったどこかに、桜の樹があり、加えて今咲いていることを示していて、瑠璃の好奇心をくすぐった。
瑠璃は斜面をのぼるために手頃な枝を掴むと体をグイッと持ち上げた。足をかけた場所の土がボロボロと崩れたが、問題なく山の中へと入るとことができた。目指すはもちろん、桜の樹だ。
瑠璃はずっと昔、幼い頃に花見につれていってもらったことがある。顔も声も覚えていないが、とても優しくて、暖かい女性に。ずっと、一緒に居たいと幼心にも思っていた。でも、彼女は死んでしまった。
「愛なんて失った時、痛いだけだよ……」
瑠璃は苦しそうに呟いた。ほしいけれど、失うのは怖い。そのくせ、手に入らないと嘆く。まるで、子供みたいだな瑠璃は自嘲した。はじめから、愛なんて知らなければ、きっとこんな苦しいことは無いだろうに。
どうして、そんな昔のことを思い出したのかというと、目の前に山桜の大木がそびえているからだ。空を多い尽くさんばかりに枝を広げ、今ちょうど満開を迎えている。おそらく樹齢200年は越えているだろう。その山桜の大木を中心に春の草花がほころんでいた。
瑠璃は心を震わせた。ここで死にたいと思った、願った。そして、山桜の大木にちょうどいい枝を見つけることができた。その下、少しずれた位置には根が飛び出しており、踏み台になりそうである。縄をちょうど良い長さを残し、枝に結びつけると、瑠璃はそのまま根の上で、浅く早い呼吸を数度繰り返した。(失神しやすくするためだ。)そして、わっかに首を通す。今度は緊張を解すように深呼吸をして、飛び降りた。枝が揺れ、桜が散る。
縄がギチギチッと音をたてそうなほど瑠璃の首に食い込んだ。瑠璃は痛みを感じていなかった。感じているのは浮遊感と体から力が抜けるような感覚。何も考えられず、眠る時のような幸福感に包まれた瑠璃の意識はほんの数十秒で闇に飲まれた。
☆ ☆ ☆
瑠璃が首を吊り、意識を失ってから数秒後、そのそばに青年がたっていた。和服に身を包み、遠くから見れば桜色がかって見える癖のある白髪の長目の襟足を束ねた姿は元の顔立ちの良さもあってか凛々しく格好良い。しかし、近づき難いかと言われればそうでもなく、まるで春の陽気の様にあったかく、親しみやすい雰囲気をまとっているのだった。
青年はため息をついた。それとほぼ同時に瑠璃の下がった枝ががメキッという音をたてて折れた。青年はの眉間にほんの一瞬だけ、痛みに耐えるようなシワが寄った。青年は横たわった瑠璃の首の縄を外すとそのまま隣に座わった。
「痛そうだ……」
青年は瑠璃の首の索状痕に触れた。そこは腫れぼったく熱を持っていた。
「んっ……」
突然のうめき声に驚き青年は手を引っ込めた。
目を開いた瑠璃ははじめ、自分がなぜここにいるのか、ここがどこかわからなかった。感じるのは、手足の痺れと冷たさそして首の熱。徐々に思考力が働きだし、自殺が失敗したのだと気づいた。
「お前……大丈夫か?」
青年はおずおずと尋ねた。目を開けたと思えば、瞬きもせずしばらく空を見つめるもので心配だったのだ。しかし、声をかけてから青年は人間には自分の姿は見えず、声も聞こえないことを思い出した。
「ひゃい……!?」
瑠璃は突然の声をかけられ、素ッ頓狂な声を上げて飛び起きた。急に起きたせいで目眩に教われ、ギュッと耐えるために目を瞑る。治まってから目を開けると真っ白な髪に桜色の瞳を持つ和服姿の青年が見えた。心配そうな顔で首をかしげていた。
「……大丈夫そうだな。それにしても驚いた。お前、俺がみえるんだな」
青年はニコッと笑って言った。人懐こい笑顔だった。
「ああっ……えっ、と……はい、大丈夫です」
「みえる」とはなんだと、瑠璃は混乱し意味がわからなかったがとりあえず、答えた。
「そうか」
青年は瑠璃の頭をグシャグシャに撫でた。
瑠璃は青年の気がすむまでされるがままになった。別に、嫌じゃなかったのだ。
「あの、お名前はなんですか? 私は高根瑠璃といいます」
瑠璃はじっと答えてくれるのを待った。
「瑠璃か、良い名前だな。俺はお前が首を吊った山桜だ。」
へ? 山桜? と瑠璃が心の中で混乱していることも露知らず、青年は笑顔で続けた。
「悪いが、俺は名前を持っていない。だから、教えてやることはできない」
瑠璃の混乱がついに表情に現れた。それを青年は瑠璃ががっかりしたものととらえたのか、眉が申し訳無さそうに下がった。
「すまないな……」
青年の手が瑠璃の頭の上でバウンドした。
「山桜……? 貴方が?」
瑠璃が尋ねた。
「ああ、そうだ。精霊といえば良いのか、アヤカシといえば良いのかわからないが、これが俺なのは間違いない」
青年はそう答えて、山桜の大木の幹に触れた。その表情は真剣そのものであり、加えて不思議な容姿を持っているため、本当のことに思えて、瑠璃は疑うことができなかった。だから信じることにした。
「驚きました。まさか、貴方のような方に出会えるなんて。自殺が失敗して良かったです」
瑠璃は笑って言った。「失敗して良かった」それはなぜか紛れもない本心だった。
「そうか、俺も枝を折るのはそれなりに痛かったからな。そう思ってもらえて良かった」
瑠璃はその発言に目を見開いた。縄を見れば、しっかりと折れた枝がついていた。
「ご、ごめんなさい……」
痛い思いを、自分のせいでさせてしまった。どのくらい、痛かったのだろうか。指を切った位だろうか。いや、折れたのだから骨折と同じくらいだろうか。自分を責める気持ちが溢れて、張り裂けそうだった。
「痛い思いを、させてごめんなさい」
瑠璃の頬を涙が伝った。ボロボロとしずくが地面に落ちて草の葉の上で跳ねた。
「泣かないでくれないか? 俺はそういうつもりで言ったわけじゃないんだ」
青年の顔に焦りが浮かんだ。
「すまない。まさかお前がそんなに責任を感じるとは思わなかった」
ギュッと青年が瑠璃を抱き締めた。瑠璃は青年の肩に額を押し付けた。
「もう、痛くもなんともない。だから泣かないでくれ」
ポンポンと青年が瑠璃の背を叩いた。瑠璃はヒック、ヒックと嗚咽を漏らした。
「何か、償いを、お礼をさせて下さい……」
瑠璃の手が青年の着物をギュッと握り込んだ。
「お願い……します」
瑠璃が蚊の鳴くような声で嘆願した。それに青年が困った様に微笑んだ。
「なら、ふたつ頼み事があるんだがきいてくれるか?」
青年がそう確認すれば、瑠璃は額を青年の肩から離した。そして、嬉しそうに微笑んだ。
「はい、私にできることなら何でも」
瑠璃はそう答えた。
「まず、ひとつは俺と友達になって欲しい」
瑠璃は瞠目した。なぜなら、友達なんてろくに作ったことがないのだ。「なって欲しい」なんて言われてもどうすれば良いのかわからなかった。
「はい、私で良ければ友達になります」
とりあえず、瑠璃はそう宣言した。
「ありがとう。ひとつめの頼み事は叶った」
青年は微笑み、また瑠璃の頭を撫でた。
「終わりにふたつ目、俺に名前をつけて欲しい。お前に呼んでもらいたい」
ああ、なんて責任重大な頼み事なんだと、瑠璃は思わず頭を抱えた。
「どうした?」
青年は不思議そうに首をかしげた。それに、何でもないと瑠璃は頭を振った。
「名前はどんなのが、良いですか?」
瑠璃は尋ねた。
「ん? ああ、俺は何でも良いぞ。それこそ、タマでもポチでも」
いや、全然良くないと瑠璃は思った。しかし、青年は本気でそう思っているようである。
「友達からもらった名前なら何だって素敵だ」
瑠璃は考えた。いくら青年が良いといっても、タマや、ポチなんて名前では駄目だと自分のちっぽけなプライドが許さなかった。
「優桜なんてどうですか?」
瑠璃はぴったりだと思った。
「ユウサク?」
青年は首をかしげながら言った。
「はい。優しいの優ゆうに、桜と書いて優桜です」
青年は黙ったままだった。
「ダメなら他のを考えますよ?」
瑠璃は気に入らなかったのかとそう言った。しかし、別のを考えるとなると小一時間はかかりそうだ。
「いや、それが良い。素敵な名前だ」
青年は嬉しそうに言った。
「では、改めて。俺は山桜の優桜という。よろしくな」
「はい、よろしくお願いします。優桜さん」
これがふたりの出会いだった。
時はあっという間に過ぎ、夕陽が西の空を茜色に染めていた。春とは言えど、日没間近ともなれば頬を撫でる風は少し冷たい。
「随分と、長話をしてしまったな」
優桜は西の空を見ながら言った。
「そうですね」
瑠璃はそう答えた。今思えば色々と話してしまったようだった。死んでしまった両親のこと親戚の間を転々としたことなど、もはや話していないことはない気もした。
「もう帰った方がいいな。今の季節不埒な輩も多い。山道までは送ろう」
優桜は取り立ち上がると、瑠璃の手を引いた。瑠璃は引っ張られるように立ち上がった。
優桜は瑠璃の手を取るなどの一見恋人同士がやりそうな行為も平然とやってのける。馴れているのか、特に意識していないのか。おそらく後者だろうと瑠璃は思った。
途中、「こけるなよ」や「その葉には触れるな、かぶれる」などの言葉を優桜からもらいながら瑠璃は山を下りた。
「明日も、来ていいですか?」
瑠璃は尋ねた。
「ああ、むしろ来てくれ。その方が俺も楽しい」
優桜は答えた。どこか名残惜しそうだが、それに瑠璃は気づいていなかった。
「じゃあ、また明日」
瑠璃はそう挨拶すると歩き出した。しかし、途中足を止め振り返った。
「優桜さん、ありがとうございます!」
瑠璃は少し遠いので叫び気味に言った。優桜は瞠目した。予想外の行動だったのだ。
「明日が楽しみだなんてこんな気持ち久しぶりです。貴方のおかげですね」
瑠璃は微笑んでいった。その顔が赤くみえるのは夕陽のせいだろうか。瑠璃は逃げるように駆け出した。返事も待たずに。
「……気を付けて帰れよ」
優桜はそう瑠璃の背に投げ掛けると、だんだんと小さくなる瑠璃の姿を見ながら幸せそうに笑った。
大通りに出る前に瑠璃はパーカーのフードを首元を隠すように被った。周りのひとを不愉快にさせないためだ。
「……スーパーに行こう」
瑠璃は冷蔵庫が空っぽだったことを思い出しポツリと呟いた。その声は明るかった。
☆☆☆
瑠璃は夕食を食べ終わり、シャワーを浴びていた。そして瑠浴室の鏡で首の索状痕をはじめて目にした。
「思ったよりは……酷くないか」
赤い輪となり、鈍く痛むアザ。白い肌によくはえていた。しかし、後悔はしていなかった。あの場所で首を吊らなければ、優桜と出会うこともなく、明日が楽しみだと再び思うことはなかっただろう。瑠璃は生きる理由を手に入れた。そう考えると、ある意味自殺は成功していた。瑠璃は優桜の笑顔を思い出し、ふわふわとした幸せを感じた。そして、怖くなった。また、この幸せも失う時がくる。幸せが大きいほど失った時の絶望もまた大きい。いくら失いたくなくともどうしようもないことだ。瑠璃はそんな思いを振り払うように頭を振った。パラパラと髪から水滴が飛び散った。
瑠璃は髪の毛の水気を拭き取ると服を来て自室に向かった。ベットにもぐり込み目を閉じる。しばらくすると穏やかな寝息が聞こえた。
☆ ☆ ☆
浮世と常世の間にはアヤカシ達のすむ世界がある。そんな世界の町の片隅にあるかんざし店に優桜は足を運んでいた。
「イザザ、居るか?」
優桜はそういいながら暖簾をくぐった。
「はーい。いるよ、珍しいね。いつもは裏口からくるのに」
そう答えて出てきたのは男だった。ひょろっとした体躯に和服を着て、黒い蓬髪を持ち、その間からピョコンと猫耳がはえていた。そして、ゆらゆらと揺れる二股のしっぽ。こちらもなかなかの美男子だ。
「ああ、今日は客として来たからな。こっちから来ないとおかしいだろ?」
「それはそうだね」
イザザは笑って言った。
「驚かないのか?」
優桜は不思議そうに尋ねた。
「別に驚くことじゃないもの。君も男なんだから彼女のひとりやふたり、できても何もおかしくないし」
イザザはそう答えた。
「……俺を女たらしみたいにいうんじゃない」
優桜は心外だというように顔をしかめた。
「ふふっ。ごめん、君は一途なタイプなんだね」
イザザの言葉に優桜は頷いた。
「それでどんなかんざしを作ろうか? 君の枝を持って来ているあたり、本気なんでしょ?」
イザザは優桜の持つ枝を見ながら言った。イザザはかんざし職人だった。歌舞伎のかんざしを作る職人ではない。呪力の宿る「守護かんざし」を作れる数少ない職人である。そのかんざしは身につけたひとを災いから守るため、恋人同士や夫婦がそれぞれの爪や牙などのからだの一部を入れ作ったそれを交換することが一般的だ。もちろん優桜のように一方的な場合もある。
「洋服にも合わせられるようなものがいいんだが……あと、黒髪によく映えるものが良い」
優桜がそう言えば、イザザは近くの机から紙とペンを取り出し、さらさらとメモをした。その文字の横にはそのかんざしのイメージと思われるイラストがそえられた。
「これでよし」
その紙は小さくたたまれて、再び机の中に仕舞われた。
「とびきり素敵なのを作ってあげるから、楽しみにしててよ」
イザザはニコニコと笑って言った。心なしかその声も弾んでいた。
「ああ、期待している」
「あ、お代なんだけど、先払いね。ということで今から飲みに行こう!」
イザザは優桜の袖を引っ張って外に出た。もうすぐ日没である。
「……どういうことだ?」
優桜は意味がわからず尋ねた。
「だから、私に一杯奢ってくれたら、それがかんざしの代金ってことさ」
優桜は瞠目した。お酒一杯とそのかんざしの値段は雲泥の差、全く釣り合わないからだ。
「……良いのか?」
「いいの! いいの! 君と私の仲じゃないか」
イザザは店の鍵を閉めると優桜をぐいぐい引っ張って歩いた。優桜が歩調を合わせ横に並べば、イザザは袖を離した。
「酒の肴に君が惚れた女の子について教えてよ」
「別に構わないが……」
優桜がそう答えれば、イザザは嬉しそうに笑った。ふたりの姿は繁華街の人混みに紛れて見えなくなった。
その夜、アヤカシの町の繁華街のバー「Karan」のカウンター席にふたりの姿はあった。和洋折衷な店内は和服姿のふたりがいても違和感がなかった。
「へぇー、瑠璃ちゃんは私たちが見えるのかい。珍しいね」
イザザは酒がまわってきたらしく、頬をほんのりと赤く染めていた。その手にはマタタビ酒のロックが握られている。
「だろう? 俺もはじめ驚いた」
優桜は頷きながら言った。こちらの手にはウイスキーのロックだ。
「それにしても、優桜なんて良い名前じゃないか。ねぇー、優桜」
イザザは酒を一口飲んだ。
「そうだろう。俺も気に入っている」
優桜は嬉しそうに笑った。イザザがピーンとグラスを弾いた。
「ねぇ、優桜。今度の祭りに瑠璃ちゃんを誘ったらどうだい?」
「ここの祭りにか? 瑠璃は人間だが大丈夫だろうか?」
「平気さ。出来上がった私のかんざしをつけていればね」
イザザはグラスの中に浮く丸い氷をつつきながら言った。
「そうか。なら、今度会ったとき誘ってみよう」
「ああ、きっとかわいい浴衣姿が見れるよ」
イザザのその言葉に優桜は瑠璃の浴衣姿を想像した。
「……かわいいな。勢い余って告白してしまいそうだ」
「え、告白してなかったのかい!?」
優桜の吐息のような独り言をイザザは聞き逃さなかった。やはり、猫又だけに耳がいい。
「していないが……言ってなかったか?」
優桜はキョトンとして答えた。
「ちょっと待って……! 告白って祝言の方かい?」
「違う」
イザザは信じられないと天を仰いだ。
「聞いてないよ! 何回も会っているって言ったし、かんざしの注文なんてするからてっきり私……!!」
イザザが言った。心なしか声が大きい。
「……なんか、すまん」
優桜は頭をかきながら、イザザの半分の声量で言った。
「で、なんで告白しないんだい? 瑠璃ちゃんそっちでいっぱい苦労しているみたいじゃないか。早く恋仲になって、祝言上げて、こっちで幸せにしてあげれば良いのに。最近は時代も時代だから数こそ少ないけれど、元人間とアヤカシの夫婦なんて珍しくない」
イザザはグラスを持ち、カラカラと回しながら続けた。
「早く決めないと浮世の人の命は短く儚いよ? 優桜」
イザザの瞳が優しげに細められた。
「……わかっている」
優桜がイザザの言葉に頷き言った。
「後悔しないようにね!」
「ああ」
「絶対……しちゃダメだ、よ……」
イザザはスーッと突然寝落ちた。いつものことである。優桜がイザザの手からこぼれる前にグラスを取り上げた。
「マスター、お代はここに置いておくぞ」
優桜はイザザを抱えそう言うと、「Karan」を後にした。その表情は何か考えているようだった。
限りなく黒に近い灰色の雲をたたえた空はとうとう堪えきれなくなったのか、激しい雷を伴わせ、雨を降らせた。あれだけ忙しなく鳴いていた蝉も天候には勝てないのか聞こえてくるのは雨と雷の音だけである。
「濡れちゃった……」
そう呟いて家に飛び込んだのは瑠璃だった。学校からの帰り道で突然降られてしまったのだ。
タオルで頭をふきながら自室の窓から外を見れば叩きつけるような雨。明日まで続きそうな降りっぷりに瑠璃の表情は陰った。明日は学校が休みのため優桜と会う予定なのだ。会うといっても、持ってきた本を一緒に読んだり、他愛もない話をするだけなのだが、それでも瑠璃にはとても楽しく、特別なことだった。瑠璃は優桜の自分に向ける笑顔を思い出して、ふにゃっと幸せそうに笑った。本当に瑠璃は幸せだった。
だが、瑠璃の幸せは長くは続かなかった。
その夜、瑠璃は夢をみた。優桜の夢だ。それは外でバケツをひっくり返したような雨が降り、雷がなっていた。その雨が瑠璃の体を冷たく濡らしていた。僅かな光で少ししか周りは見えなかった。次第に闇に目をが慣れわかったのは今自分は優桜である山桜大木の前に立っていること。瑠璃は突然、耳を覆いたくなるような轟音と激しい閃光に襲われた。その目が眩むような光の中見えたのは山桜の大木に雷が落ちる様子。
「あ……いやぁ!!」
続いて瑠璃の耳に聞こえたのは幹の裂ける音だった。まるで藁山のように断面はささくれ立っていた。そしてふたつに裂けた幹の片方が傾いた。瑠璃の目にはスローモーションのようにゆっくりと見えた。
「ま、待って……!!」
瑠璃は走った。そして止めようとするように手を伸ばす。あれが倒れてしまったらもう駄目な予感がしたのだ。しかし、瑠璃の行為も虚しく、その幹の片割れは土の中から根を引きずり出しながら倒れた。その場光景に瑠璃が崩れ落ちた。
「優桜さん……! 優、桜さ……!!」
瑠璃は悲痛に顔を歪ませながら名前を呼んだ。大切なひとの名前を。そして、場違いながら自覚した。自分は優桜に恋をしているのだと。
瑠璃はガバッと飛び起きた。
「あれは、本当に夢……?」
早鐘を打つ心臓をなだめるように胸の上で拳を握りながらポツリと呟いた。
景色から抱いた心情までありありと覚えている。あまりのリアルさに瑠璃は不安を覚えた。
外を見れば晴天、昨日の雷雨が嘘のようだ。しかし、庭の草木は水に濡れ、艶々と光っている。突然瑠璃の脳裏に夢の中光景がフラッシュバックした。ヒュッと喉に息が詰まる。瑠璃は必死に落ち着くと、ベットから降り、服を着替え始めた。そして、身だしなみを整えるのもほどほどに、荷物を持たずに家を飛び出した。
陽が痛いほど差していた。その中を瑠璃は優桜の元へと走り出した。ただ、あれがただの夢で、優桜は何事もなく元気にしていることを確認したい、その一心だった。
山の斜面は良く滑り、瑠璃は登るのに苦労した。手やひざは泥で汚れ、所々枝や石で擦ったのか怪我をしていた。
「やっぱり、来たのか。どろんこだな」
優桜は笑って言った。
「昨晩お前の気配がした。気のせいかと思ったが、その様子では気のせいではなかったらしいな」
その後ろには見るも無惨な山桜の大木が佇んでいた。
「あぁ……なんで……」
瑠璃は崩れ落ちた。
なぜ世界はこんなにも残酷なんだろうと瑠璃は思った。失いたくないからと、どんなに大切にしても指の間からこぼれ落ちるのだ。
「すまない、瑠璃。俺はもうお前と一緒にいてやれない」
そんな優桜の言葉に瑠璃の瞳からポロポロと涙がこぼれ落ちる。
優桜に助けられて、彼がいるからこそ瑠璃は生きているようなものだった。
彼がいなくなるのならばもう、生きる意味はない、そんな考えが瑠璃の脳裏を掠めた。
「駄目だ。瑠璃」
私も連れていって、そんな言葉が瑠璃の口を出かけた時優桜は言った。
「俺は愛しい者には生きていてもらいたい」
優桜はしゃがむと瑠璃の頬を撫でた。その指は透けている。
「愛しい……?」
瑠璃は信じられないというように反芻した。
「ああ、愛しい」
「ふふっ……こんなバットエンドの恋は嫌だなぁ」
せっかく両思いなのに、と瑠璃は呟く。その時、優桜が瑠璃の唇を奪った。瑠璃の頬が薔薇色に染まる。
「瑠璃、知ってるか? アヤカシも人も死ねば行き着く場所は同じらしい」
愛しそうに瑠璃の唇なぞりながら優桜は言った。
「そこで、夫婦になろう。お前が天寿を全うし、死ぬその時は俺が迎えにいく。だから、今は生きてくれ」
涙を浮かべた懇願だった。
「本当に?」
「本当だ」
優桜が安心させるように微笑んだ。
「なら、待っています。ずっと……」
瑠璃は涙を流しながら言った。その涙は嬉しさと悲しみと両方が流させた涙だろう。
「その言葉が聞きたかった」
優桜が懐から桐の箱を取り出した。そこに納められていたのは桜の花が繊細に彫られた玉かんざしだった。
「綺麗……私に?」
「ああ、お前のために作らせた」
瑠璃はそれを取り出した。でも手が震えてうまく着けることができないでいた。
「……つけてくれませんか?」
優桜は微笑んでそれを受け取り、団子にした瑠璃の髪に差し込んだ。
「良く似合っているな。やはりお前の美しい黒髪に良く映える」
優桜は瑠璃を抱きしめた。もう、別れは近い。
「このままで……」
瑠璃は優桜の胸に顔を埋めた。
次第に背にまわした手のひらから優桜の服の質感が消えていく。
「優桜さん……」
それが寂しくて、悲しくて瑠璃は名前を呼んだ。
「ずっと、見守っている、ゆっくりおいで」
それが、瑠璃が最後に聞いた優桜の声だった。
「瑠璃せんせー、先生は結婚しないんですかぁ」
保健室に来た男子生徒が言う。あれから十年と少し、瑠璃は立派な養護教諭になった。今は高校に勤めている。
「うーん、まだ先の話ですね。相手がいないので……」
心の中でここには、とつけ足す。
「へぇ、じゃあ僕と付き合お……」
その時、閉めきった保健室に疾風が吹き抜けた。男子に向けて。
それに瑠璃は嬉しそうに微笑む。
「ふふっ、冗談でもそういうことは言わない方が良いですよ」
言わずもがな、この疾風は優桜の――正確には彼のくれたかんざしの――仕業だ。
優桜の桜の木はあの山奥で枯れ木に成り果てている。もう、浮世で会うことはない。
男子生徒は何が起こったかわからないようで放心していた。
「もう、教室に戻りなさい」
「……はーい」
瑠璃は男子生徒が出ていくのを見送るとふぅとため息をついた。
「……優桜さん」
たまに、こういう不思議な事がある。
命の危険がある時、さっきのように告白された時。
そして、それは優桜の言葉を思い出すきっかけになる。そんなことなくても思い出さない日はないのだけれど。
「私生きてますよ。やっと、貴方のいない日々が楽しいと思えてきました。生きていて良かったです」
髪にさしたかんざしに触れながら瑠璃は呟く。
実のところ瑠璃は優桜を亡くしてからの数ヶ月何度も後を追いそうになっている。
寂しさと、恋しさと、一度幸せを感じたことによる現状への更なる絶望。その度に、瑠璃は優桜との約束とかんざしのお陰で生にすがり付いた。
『そうか』
そんな声が聞こえて瑠璃は目を見開いた。慈しみと愛情のこもった温かい声だった。初めてだった。きっと空耳だ。そんなことはわかっている。それでもこの胸に溢れる愛しさは本物以外のなにものでもない。
「ああ……やっぱり私、あなたが大好きみたいです」
中庭の樹の枝の上からその様子を見ていた猫は二本の尻尾をゆらゆらと揺らしながら満足そうにニャーオと鳴いて宙に消えた。
桜枝の約束