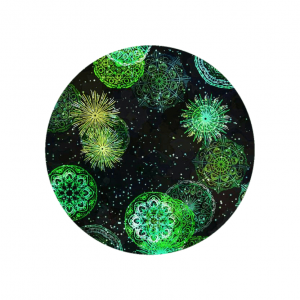めぐる魂
はじめて書いた小説です。
作中の治療方法はある程度調べましたが、盛大に間違っています。
あたたかい目で、読んでくださると嬉しいです。
めぐる魂
僕の二卵性の双子の兄はがんになった。病巣を切除し、抗がん剤の治療も虚しく再発した。骨と肺への転移。しかもこのがん細胞は今までに使った全ての抗がん剤を乗り越えてきた手強いやつで、これ以上の抗がん剤の効果は望めない状態。ステージⅣの末期がんと診断され、兄の意思で痛みや苦しみへのケアだけが施されるようになった。
今日も通学先の高校から電車に乗って兄のいる病院へ向かう。ホームに着くと決まって小走りになる。途中で人にぶつかっても足は止めない。
一秒でも長く兄の隣にいたいから。
兄の病室の前で少し乱れた息を整え、ドアを開ける。
サイドテーブルに置かれた芥川作品集が開け放たれた窓からの風でパラパラとめくれた。近くに置かれた青いガラスのコップが春の光を優しく反射している。
ふと、笑顔の兄と目が合った。
「やっと来たかのか……佑介」
僕は兄が苦痛に顔を歪めていないことに胸を撫で下ろした。
元気な頃と同じ笑顔が見られることは嬉しいけれど、泣きたくなる。本来ならこの笑顔は意識しないほど当たり前に僕の生活の中にあるはずだったから。
「うん。今日は調子がいいみたいで良かったよ、兄さん」
「新しくモルヒネ系の液剤飲んでるんだ、追加でな」
がんが骨に転移すると患者は例外なく激しい痛みに苦しむ。もちろん兄もそうだ。加えて兄は肺に水が溜まり、溺れているような状態だ。だから酸素ボンベから兄の鼻下へのびるチューブは欠かせない。
突然ドアが勢いよく開いた。
「喜べ!! 佐介!! 外泊の許可が出たぞ。明日から三日間だ」
養父は陽気な声で兄に告げた。
「まじで!? よっしゃ!」
兄は満面の笑みでガッツポーズをした。
「すき焼き!! すき焼きは絶対食うからな!!」
外泊一日目の夜はすき焼きパーティーだった。兄は子供のようにいきいきとして、僕は嬉しくなった。
そして外泊二日目の昼、二人で庭を眺めていると兄は突然言った。
「芥川龍之介って知ってるか?」
「たしか……昔の文豪だよね」
「そうだ、でさ、そいつ自殺するとき友達に出した手紙に、世の中は死ぬことを決めた自分には美しく見える、みたいなこと書いてたんだろ?」
「……らしいね」
僕自身うろ覚えで確信はなかったけど、そう答えておいた。
「俺、それ初めて知った時意味が分からなかった。だってそいつを自殺に追い込んだ原因って、この世界にもあったはずだろ? なのにこの世界がいとおしいだなんて、おかしいって思った。昔はそう思ってたんだ……」
「今は違うの?」
「ああ、今ならわかるんだ。俺はこの世界が大好きだ。もうすぐ死ぬって知ったら小さな出来事にも気づいて幸せな気持ちになる。外で小鳥が鳴いたとか、タンポポが咲いてるとか、今日は晴れだとか……お前が側にいるとか、当たり前だったことが特別に変わるんだ」
兄はそういうとふわりと笑った。
「佑介はどうなんだ? この世界は好きか?」
「嫌いだよ」
考えるより先に口が動いていた。
「当たり前だろ。この世界は僕から兄さんを……たったひとりの肉親を奪っていくんだから。」
大切な半身、唯一の存在がこの世界から消えてしまう。
「こんな世界……大嫌いだ」
気づくと僕の両目から涙が溢れて出ていた。慌てて涙をぬぐう。一番泣きたいはずの兄が泣いていないのに僕の涙は止まらない。
「ごめん……兄さん」
「謝るんじゃねぇよ。久々に可愛い弟の泣き顔を見られたんだ」
兄は僕に呆れたように言った。
「あーあ、昔はすぐに泣いたり、笑ったり、もっと素直だったのになぁ。身長もでかくなりやがって!! 兄ちゃんなのに並んだら俺の方が小さいとか……!! 見上げなきゃなんねぇとか……!! すげー悔しいんだからな……!!」
兄は涙目になって言った。いや、泣いていた。
泣くところはそこなのかだろうか……?
「兄さんは怖くないの?」
ずっと思っていたことを尋ねてみる。
「何がだ?」
兄はきょとんとして言った。
「……死ぬこと」
兄は一瞬唇をキュッと噛んで答えた。
「怖いよ。知らないことは怖い。でも死ぬことは終わりじゃないと思うんだ。死ぬことは終わりで始まり……そう思う」
「どうしてそう思うの?」
何か根拠があって言っているのだろうか?
「なんとなく……? 勘だよ!! 勘!」
「やっぱり兄さんは馬鹿だね」
そうだ、兄はそういう人だった。頭は使わない癖に勘はよく当たる人。
「うるせぇな! 兄ちゃんを馬鹿にすんじゃねぇよ!!」
「アハハッ。ごめん、兄さん」
僕は笑いながら小さな希望を持った。死が終わりでないならその始まりの先で兄とまた兄弟になれたらと。
次の日の朝兄は病院に戻った。当然、僕は名残惜しくて朝から夕方まで兄の病室に入り浸った。
「佑介、明日学校だろ? 帰って課題しなくていいのか?」
兄は少し心配そうに僕の顔を見て言った。
「心配してくれてありがとう。でも大丈夫だよ。明日は先週にあった日曜参観の振替えで休みだし、課題も全部終わらせてあるから」
「さすが、俺の弟! 兄ちゃん俺も鼻が高いぜ!」
兄はいつも大げさだ。僕のことに僕より二倍喜んだり、怒ったりする。
それ僕にとって恥ずかしくもあるけど、とても嬉しいことだ。
「ありがとう、兄さん」
僕の言葉に兄は嬉しそうに笑って答えた。
「どういたしまして」
外でカラスが鳴いた後、病室のドアが開き、看護師が顔を覗かせた。
「もう、面会終わりの時間ですよ」
「はい、もう帰ります」
僕の返答に彼女はにこりと笑ってドアを閉めた。
「兄さん、明日なにしようか?」
兄は少し考えた後に答えた。
「漫画読みたい。家にあるやつ全部持ってきてさ……きっと楽しいぜ」
「わかった。また明日ね、兄さん」
僕はそう言って兄の病室をあとにした。
昨日約束した通り、僕は家にある漫画を全部もって兄の病室を訪れた。
「おはよー、佑介」
兄はニコニコと笑いながら言った。
「おはよう、兄さん。……ところで漫画全部ってこうなることわかってて言ったの?」
僕は漫画が詰まったリュックサックを背負い手にも漫画で一杯の紙袋をそれぞれ持っている。
兄の部屋の本棚を見た瞬間よく考えてもせず了解したことを後悔したのは紛れもない事実だ。
「すごく重たいし、この状態で満員電車にも乗ったんだよ? どんなにたいへんだったか兄さんにも理解できるよね?」
僕は少し兄に腹が立っていた。
「ありがとう、佑介。お疲れ様でした」
兄は笑って言った。
「……どういたしまして」
許してしまった。僕はどうも兄の笑顔に弱い。
それから僕たちの漫画タイムが始まった。僕らは漫画の好みは同じだった。だからいつも漫画は兄が買って来て、二人で共有した。
「ギャー!! 逃げろー!」
ただ、兄は独り言でうるさくなるけど僕は静かだ。
今読んでいるのはある日妖怪が見えるようになった恥ずかしがり屋の女の子が主人公の漫画だ。
こんな感じの日常に潜む非日常を描いた漫画が僕らの好みだ。
「ハハッ……げほっ……」
兄がさっきから時々咳き込んで、僕は正直漫画どころではない。
「大丈夫だって……見ろよ、これ。こいつ可愛くねぇ?」
「ほんとだ、可愛いね」
僕は笑って言った。
それからも兄は時々咳き込んで僕は心配だった。
それでも兄は楽しそうで、僕は漫画を頑張って持ってきて良かったと思った。
「ミタゾラムですか?」
五月十九日、医師は呼吸の苦しみを緩和するために兄にミタゾラムの点滴投与を提案した。
この日兄が「息ができない」とパニックになったのがきっかけだった。
「はい。麻酔薬の一つで意図的に意識レベルを下げることで、痛みや苦しみを緩和することができます」
目の前の医師は仮面のような表情で説明をした。
「嫌だ」
兄の顔には恐怖が浮かんでいた。前にモルヒネの点滴を拒んだことがあるが、その時と同じ顔をしていた。
あのとき兄は言った、「意識がなくなったりしたら佑介と話せなくなるだろ。その方が痛いとか苦しいよりも何倍も嫌だ」と。
僕も兄と話せなくなるのは嫌だった。でも、近頃兄は眠れていないみたいだった。
「だったら、寝るときだけしてもらうのはダメかな? 兄さん」
その証拠に兄の目の下には隈がくっきりと、刻まれている。
「僕、兄さんが心配だから今日からここに泊まることにするよ。朝が来たら僕が起こしてあげるから。そうすればこれまで通り楽しくおしゃべりできるよ。だから何も心配しなくていい」
「絶対だな? 約束しろ」
兄は今までにないほどの強い口調で言った。
「うん、約束するよ。兄さん」
加えて兄には痛みの緩和のため、背中から脊椎の周囲に針を刺し、断続的に鎮痛剤を送り込む「硬膜外麻酔」という処置がされた。
兄は高校から兄の病室に帰ってきた僕に絵本をヒラヒラと掲げた。ちなみに僕は病室のドアを開けただけで中に入れてもいない。
「いきなりどうしたの? 兄さん」
天然混じりの兄の行動は説明されないと時々意味がわからない。
僕は一段高くなっている畳の床にカバンを放り投げて尋ねた。
その隅には寝具が一式と折り畳みの机がある。つまり、僕のここでの生活スペースだ。
「読み聞かせしろ」
兄の手にある絵本のタイトルは「にんぎょひめ」、サイドテーブルには「かぐやひめ」、「ももたろう」、「きんたろう」、「したきりすずめ」……と少々くたびれた見覚えのある絵本が乱雑に積み上げてあった。
「兄さん、絵本なんて持ってきてたんだ」
「いや、ジジイに中原中也の詩集を買って来てくれって頼んだら、オマケでついてきた」
兄は養父をジジイと呼ぶ。始めの頃は注意したけど今では好きにさせている……というか、諦めた。
兄が絵本の中から文庫本を掘り出して僕に見せた。
「そうなんだ。で、なんで読み聞かせなの? 僕らもう読み聞かせって年齢としでもないと思うけど?」
「こういうのは他人に読んでもらうからいいんだよ」
兄は笑って言った。
そういうものだろうか?
「わかった、読んであげるよ」
僕は見易いようにベッドの足下の方に座った。
兄は「にんぎょひめ」を手渡してきた。
僕は目で文字を追い、読み上げる中で兄について考えていた。
兄は小さい頃よくけがをして帰ってきた。原因は喧嘩。でもそのすべてが誰か他のひとのためだった。兄は優しすぎた。だから、僕は守りたいと思った。兄自身を、兄の心を。でも、僕は兄より弱い。だから、医者になることにした。そのために、成績学年一位のまでのしあがった。他人は僕を天才だと言うけれど本当はそんなのじゃない。ただ、誰よりも努力してきただけだ。
僕が医者になったとき一番褒めて欲しいひとは一番手当てしてあげたい人はいないけど、それでも僕は――――――
「ごほっ、ごほっ、ごほっ………」
突然、重く濁った咳が聞こえた。
「兄さん!!」
「佑介……背中……」
僕は兄の背中をさすった。兄の背中は凸凹していた。ショックだった。でも手は止めなかった。
兄はただ、耐えていた。
僕は何もできない自分に腹が立った。
この日医師は兄に日中もミタゾラムの点滴投与をすることを提案した。
呼吸の苦しさはもう限界のはずなのに兄は頑として首を縦にはふらなかった。
佑介、上のレストランに飯食いに行こう」
兄は僕の大好きな笑顔を浮かべて言った。
6月2日の今日を含めて、ここ数日の兄の容体はとても安定していた。その理由は医師にもわからないらしい。
「そうだね。行こう、兄さん」
僕は兄を車椅子に乗せてこの病院の最上階にあるレストランに向かった。
「うまいな、これ」
兄は幸せそうに頬を緩めた。
僕らはオムライスを注文していた。
「確かに美味しいけど、兄さんが作ったオムライスの方がずっと美味しいよ」
兄の作ったオムライスはふわトロだ。しかも、デミグラスソースまで手作りするこだわり。あの美味しさには三ツ星のシェフですら負けを認めるだろう。
兄は僕の言葉にはにかんだ笑みを浮かべて言った。
「じゃあ、いつかまた作ってやるよ」
「うん。楽しみにしてるよ、兄さん」
僕はその「いつか」が叶いますようにと、願いを込めて返事をした。
「楽しかった? 兄さん」
レストランから戻った僕は兄をベッドに座らせながら尋ねた。
「おう、旨かった」
「僕もだよ。兄さんのオムライスの残りも食べてもう、お腹一杯……」
結局、あれから兄はオムライスをふた口しか食べなかった。
「なあ、佑介……今の俺って燃え尽きる前のろうそくみたいじゃね?」
実をいうとここ数日僕も同じ事を思っていた。でもここで兄の言葉に頷くと、それを認めてしまうようで怖かった。だから僕はただ黙って兄の顔を見つめ返した。
「最後って話す余裕あると思うか?」
「どうだろうね……」
僕は急に狭くなった喉から必死に声を絞り出した。
本当なら逃げ出してしまいたい。
椅子から立ち上がり踵を返したい、出口の方へ。
そんな僕を現実を受け入れようとする僕が押し留めた。
「……ない可能性の方が高いと僕は思う」
意識がないか、苦しくて話す余裕がないか、そのどちらかだろう。
まるで他人事みたいに思っている自分がいる、僕の兄のことなのに。
「だよな。という訳で今から言うことは俺の遺言」
兄は少し申し訳なさそうに笑った。
僕はいったい、どんな表情をしているのだろう。
「佑介、生きろ。毎日を必死に楽しく生きろ。明日が来ることを当然だと思うなよ。明日が来るのは特別なことだ。それと、家族を作れ。嫁だ、お嫁さん見つけろ。お前は独りだと食事はエナジーチャージとかで済ませそうだし。料理を覚えるのもいいな。ジジイの料理は壊滅的だから喜ぶぞ」
兄はそこまで言うと苦しそうな顔をしてうつむいた。
僕はあまりに急なことに驚き、立ち上がった拍子に椅子を倒してしまった。
「兄さん!!」
僕が兄の肩に手をかけると兄は勢い良く顔を上げた。そこにはいたずらが成功した子供のような、笑みが広がっていた。
「…………騙したの? 兄さん」
僕の怒りのこもった声に兄の表情がひきつった。
「そんなに怒んなって。鬼みてぇな顔してるぞ」
「誰のせいだと――――」
僕は兄に抱きつかれていた。ハグなんてもう何年してなかっただろうか。行き場のなかった僕の腕は兄の背中に落ち着いた。
兄の背中はやっぱりでこぼこしていた。
「幸せになれよ、佑介。兄ちゃん応援してるからな。」
「うん……」
僕にはそう答えてなかないようにすることが精一杯だった。
僕はなかなか寝付けないでいた。眠っている兄を横目に窓辺へ向かう。今日は月の光が明るい。空を見上げると、思ったとおり満月だった。
ポケットからあるものを取り出す。
数年前、兄からもらった誕生日プレゼントだ。それは意思的にクラックを入れたビー玉だった。月の光を受けて僕の手の中でキラキラと輝いている。しばらく眺めると落として砕いてしまわないようにポケットにしまった。
がんになってしまった兄との生活はこのクラックの入ったビー玉に似ていると思う。ただ違うのはいくら大切にしても勝手に砕けてしまうことだろう。
僕は目を閉じてれば眠れるだろうと布団に戻った。心の中は変わらず不安と恐怖で、一杯だった。
翌朝僕が目を覚ますと兄は目を閉じたままだった。
昼頃になっても兄は起きる気配がなかった。
「兄さん、アイス食べない? 僕、下の売店で買って来るよ?」
返事はなかった。
僕の心をどうしようもない不安が飲み込んでしまいそうだ。
「ソーダアイスはどうかな?」
兄はソーダアイスが大好きだ。そのせいで家の冷凍庫にはそれしか入っていない。
兄の唇は少しも動かなかった。僕は唇を噛み締めながらナースコールを押した。
血の味がしたけれど、そんなのはどうでもよかった。
僕は医師から認めたくない反面、予想通りの説明を受けた。
「……わかり、ました。もう少しの間、兄をお願いします」
僕はただ答え、頭を下げた。
ふと見上げた空は一つ、三つ、次々と雨雲に覆われはじめていた。突然、耳に入った子供の声に僕は視線を地上に戻す。そこには兄を追いかける弟の姿があった。弟は兄に追い付くと腕にしがみついた。兄は弟の頭を撫でると、手を繋いで歩き出した。
その姿に幼い日の僕らが重なって、少しだけ懐かしく思った。
再び空を見上げると、すっかり空は雨雲に覆われていた。しばらくすると大粒の雨が降りだした。僕の頬をピチャン、ピチャンと雨粒が濡らし始めたところで病室の窓を閉めた。
後ろを向いてベッドの方へ視線を移すと、やっぱり意識のない兄がいた。
兄はただ呼吸をしていた。
「佑介さん……」
僕はずっと見つめていた兄から視線を外し、声の主へと寄越した。看護師だった。
「何か?」
窓の縁についていた手がすっかり痺れてしまっていた。
「ご家族の方に連絡が取れました。『すぐ向かう』とのことです」
「そうですか。お手数をお掛けしました」
養父の仕事場からここまでは少し遠い。おまけに外はこの大雨だ、時間がかかるだろう。
「あの……お兄さんに話しかけてはどうですか? 人の聴覚は最後まで残るものらしいので、きっと安心されるかと思います」
彼女は「ずいぶんと弟思いのお兄さんですから」と最後に付け足して病室を出ていった。
僕はその言葉を反芻しながらベッドの横にある椅子に腰かけた。
「ねぇ兄さん、聞こえてるかな? 僕、兄さんの笑顔が大好きなんだ。兄さんが大好きなんだ。強くて、優しくて……いつも僕を守ってくれた。僕のヒーローなんだよ……」
僕は兄の手を両手で握って額をつけた。どうか、この思いが届きますように、と。
ふと、誰かが僕の頭を撫でた気がした。なぜか自然に涙が溢れた。
もう、兄は息をしていなかった。ますます涙が溢れた。
ああ、嫌だ。認めたくない。認めたくないのに。
少しでも気を許すと子供のようにと泣き叫んでしまいそうだ。
様子を見に来た看護師が慌てた様子で医師を呼んだ。医師は慣れた手つきで兄の死亡を確認し、僕に慰めの言葉をかけて出て行った。
「あの……」
兄に声をかけるように僕に提案した看護師だった。表情から僕を心配してくれているのはわかったけれど、今の僕に他人の存在は邪魔だった。
「ひとりにしてください!!」
語尾が強くなってしまった。
彼女は一言「ごめんね」と言うと病室を出て行った。
ひとりになった病室で恐る恐る「兄だったモノ」に触れた。まだ、温かかった。また涙が溢れた。
「佑介……」
声のした方を見ると、養父が立っていた。彼もまた、泣いていた。
僕はすっぽりと抱き締められた。
「佑介、良く頑張った。もう我慢なんかするな……」
その言葉で僕の枷は外れてしまった。
「うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁ」
僕は子供のように泣いた。さんざん泣いた。泣き止めた時にはもう、夜中だった。その間養父はずっと僕を抱き締めていてくれた。
「佐介に、さよならは言えたのか?」
養父ちちは少し落ち着いた僕にそう尋ねた。
「僕と、兄さんに『さよなら』なんて、いらないんだよ。きっと兄さんもそんな言葉望んでないから」
僕はそう答えた。根拠なんてない。ただ何かが僕にそう告げていた。
桜の花びらが舞う坂道を一歩一歩踏みしめて歩く。もう何度、この坂を登って兄の墓参りをしただろうか。登り切ったところに兄の墓がある霊園がある。
「やあ、兄さん。元気にしてるかな?」
兄の墓の前で会話をするように話をする。
「ごめんね。花は持って来れなかった。でも兄さんはそんなの気にしないよね。……今日は報告があって来たんだ。」
心の中で「もう、知ってるかもしれないけど……」と付け足した。
「僕もがんになっちゃったんだ。見つかったときには手遅れだった。今日は薬が効いてるから痛くないよ」
僕は幸いと言って良いかわからないけど、肺への転移はまだない。
「医者が病気とか、本当に笑えないよね」
僕は苦笑した。
「あれから医者になって、病院で外科をうけもって。子供も大人もお年寄りもたくさんの人を診たよ。『ありがとう』って言ってもらえたときは本当に嬉しかった。疲れも吹き飛ぶような気分だった。本当に充実した日々だったよ。手放したくないと思えるくらいにね。でも僕、心残りはないんだよ。養父さんには『親より先に死ぬのは最大の親不孝だ』って怒られちゃったけど。兄さんに言われた通り毎日を必死に楽しく生きてきたよ。料理も覚えた。残念なことにお嫁さんはいないんだ。彼女もいないんだから当たり前だけどね」
僕は医師になってどれほど他人ひとの生きる手助けができただろうか。人として誰かの支えになれただろうか。
その答えは誰もくれない。
「僕はこの人生に満足しているよ」
結局最後に答えを出すのは自分自身だった。
「だから、最後は兄さんが迎えにきて」
強い風が吹く。風の音に混じって兄の声が聞こえた気がした。
僕は兄の墓の前でそういう願いを言った。言ったけど、驚いている。空いた口が塞がらない。
「本当に来たんだ」
やっとのことでそう言った。
「なんだよ。『迎えに来い』って言ったのはお前だろ?」
今の僕は自分の体の上に幽体で立っている状態にある。
「まあ、そうなんだけど……」
まさかほんとに来てくれるとは思っていなかった。
「なんだ、文句あんのか?」
兄が拗ねたように言った。
「ない。嬉しいよ、すごく」
僕は笑って答えた。兄はすぐ機嫌を直してくれた。
そして僕にスッと片手を差し出した。
「よし、じゃあ、行くぞ!」
僕は兄に引かれて体を離れた。後ろで心肺停止のアラーム音が鳴り響く。慌てて入ってきた同僚の医師兼友達のやつと養父に小声で「ありがとう」と言った。
兄につれられて歩き出すと周りの景色は消えて、お互いの姿だけが見える暗い空間に出た。兄はどの方向に向かえば良いのかわかっているようでズンズンと進んで行く。
「オムライス作ってね。兄さん」
「おう!」
兄は一瞬考える素振りを見せて先にを続けた。
「でもあと10年は待ってもらわねぇと……」
「え、なんで?」
「10才位じゃねぇと台所に立てねぇだろ?」
僕には話が見えなかった。兄はそんな僕がわかったのか、説明してくれた。
「信じらんねぇかもしれねぇけど、俺らこのまますぐに双子の兄弟として生まれ変わるんだ。ちなみに俺また兄ちゃん」
「え……本当? 生まれ変わるって……」
「おう」
人の魂は輪廻転生すると、聞いてはいたけれどまさか本当とは思ってなかった。兄がまた兄になるのは極当たり前な気がするので特に驚かなかった。
「死んで天国行ったら、神様がすぐに俺を生まれ変わらせるっていうんだぜ。だから、ダメもとでまたお前と双子の兄弟が良いって言ったら、軽い感じでオーケーされた。毎回俺似たようなこと言うらしいぜ。今回で五回目」
「そうなんだ……でも、記憶がないなら意味ないよね?」
魂は同じでも、記憶がないならそれは他人と何も変わらないと僕は思った。
「馬鹿。魂の記憶ってもんはなくならねぇんだよ。頭の記憶は消えても、魂に刻まれた、一番大切なもんはのことは忘れないんだぜ」
兄は僕の頭を撫で回して言った。僕の方が大人で背が高いから背伸びをしていた。それを見るとなんだか笑みがこぼれた。
「嘘じゃねぇぞ? 神様のお墨付きだ」
兄は笑顔で言った。
「うん。ねぇ、次はどんな人生だろうね?」
「さあな。人間なのは確かだけどな。どんな人生になるかは神様にもわかんねぇらしい」
兄は方をすくめて言った。
「僕はお母さんとお父さんが欲しいなぁ」
僕らは両親の顔を知らずにこれまで生きてきた。だから、次は両親に愛されて成長して長生きしても良いんじゃないだろうか。
「そうだな」
兄はうなずいて言った。
「あのな……」
兄は少し、言いにくそうに話を切り出した。
「なに?」
「もしかしたら、生まれ変わった先はこの世界とは違うかもしれないぞ」
「どういうこと?」
僕には意味がわからなかった。
「神様にきいたんだけど、俺らが生きていた世界の他にも世界があって、どの世界に生まれ変わるかは決まってないらしいぜ」
「つまり、僕らはそれこそ僕らが漫画で読んでたような世界に生まれるかもしれないってこと?」
「そういうこと」
兄はうなずいた。もし、妖怪なんかがいたら危なそうだと僕は思った。可能性はゼロではない。不安だった。
「大丈夫だって!」
僕の不安に気づいたらしい兄は笑顔で言った。
「なんかあっても兄ちゃんが守ってやるから」
今までの僕ならここで迷いなく頷いただろう。でも今の僕は違った。
「嫌だよ。僕も兄さんを守りたい」
僕は真っ直ぐと兄の目を見て言った。
「何でだよ! 兄ちゃんは弟守って弟は守られんのが普通だろ!?」
兄は驚いて言った。
「僕はもう守られるだけは嫌なんだ。それに、兄さんが言ってるのは普通の兄弟のことじゃないか」
僕は笑った。
「僕らは双子だよ? もしかしたら僕が兄だったかもしれないし、兄さんが弟だったかもしれない。だからね、もう、生まれ変わるのも五回目だし、次は兄さんと肩を並べたい」
兄は頬を膨らませてすねていた。
「生まれ変わったら記憶ねぇぞ」
「うん。だから、魂に刻み込んでおくよ」
僕は笑った。兄の機嫌は幸いなことに直ぐ治った。
「佑介、出口だ」
兄は突然言った。兄の視線の先には光がさしていた。
僕らの人生は一度終わった。だからこそはっきり確実に言えるのは生きて、明日を迎えられることは奇跡だってことだ。この先どんな世界が待っているか余りわからないけど、なんとなく、楽しい気がした。
めぐる魂
ここまでお読み頂きありがとうございます。感謝。