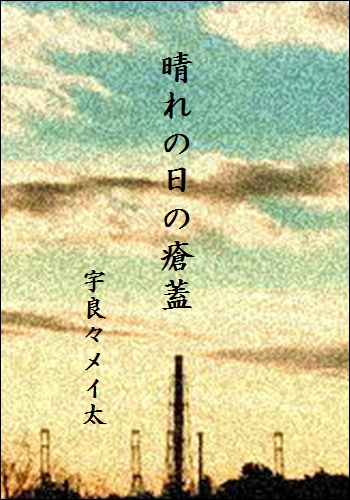
晴れの日の瘡蓋【第十二話】
重い傷/かすり傷
重い傷
1
もう十月も半ば、それなのに海辺の陽射しは私達の肌を焦がそうとする。
それでも時折舞い上がる風が爽やかで、火照りそうな肌を包み込んでくれた。
前日に真木瀬君から「せっかくの日曜日だしどこか行こう」と誘われた。
私としては買い物でも映画でも遊園地でもどんな事でも良かったんだけど、二人して散々悩んだ挙句に、結局またあの海へ行くことになった。
でもこの時のこの選択は正しかった。そう思った。
十月の三浦海岸は潮の香りと、どこからか運ばれて来た金木犀の香りが交じり合っていて、何とも言えないような不思議な気持ちにさせた。
雨女の私が何かする時、大抵の場合雨になる。でもこの日は珍しく快晴だった。
とにかく雲ひとつない秋の青空が広がっていた。
晴れの日は本当に気持ちが良い。
こんなに良い気分になったのはいつ以来だろう。
夏に来た時は終始気持ちが晴れなかった。
それは多分雨のせいだけじゃなかったと思う。
何をしてもしっくり来なかった。
きっと私はこれを望んでいたんだろう。
心の奥底でこうなることを期待していたのは間違いなかった。
波打ち際に沿って二人歩いて行く。
靴が濡れないよう、波を避けながら歩く。
水平線遠くに船が何隻か見える。
人も疎らで静かな秋の浜辺だった。
真木瀬君はずっとうつむいたまま、時折落ちていた貝殻を拾っては海へ放り投げた。
私も彼を真似て貝を拾った。
あの時何を話したんだっけ?
全然覚えてない。
ただ一緒に浜辺を歩くだけで最高に幸せだった。
私の中でもう一人の自分が目覚めたみたいだった。
真木瀬君と初めて会ったその日から、もうすでに動き出していたのかも知れない。
心を焦がすような感覚。
熱に魘されるような、でも何だかとても気持ちがいい。
恋するってこういう事なんだ。
これが人を愛するって感情なのかな。
とにかく居ても立っても居られなくなる。
彼の何に惹かれているかなんてわからない。
理由付けなんて出来るわけもない。
ただ彼に精一杯何かしてあげたい。
それしかない。
たとえこの気持ちが一方通行でも構わない。
一人よがりでも精一杯彼を愛したい。
この時は本気でそう思ってしまった。
彼を想うだけで私の心ははち切れそうになった。
どうかなってしまいそうなくらい気持ちが高揚する。
気持ちのコントロールを失う。
あとは本能のままに身を任せる。
彼の手をそっと握る。
その手が一瞬驚いたようにピクリと動く。
私も彼と同様、頭の中で自分の行動に驚いていた。
それでも私の手は彼の手を離そうとしない。
真木瀬君はとても暖かい手をしている。
その熱が私の掌を通して心まで響いてくるみたいだった。
彼の手に唇を当ててみる。
その間ずっと彼が私のことを、私のことだけを見ていたことは知っていた。
私も彼を見つめる。その瞳をしっかり捕らえて離さないように。
私たちを残して世界が止まる。
水平線に吸い込まれていく太陽が波間に映り、そこから無数の光の粒が弾け飛んで私たちに降り注ぐ。
眩いばかりの世界。
私たちだけの世界。
お互いが引き寄せられて行く。
そっと目を閉じる。
唇を重ねる。
まるで吸い込まれるようだった。
夢の中にいるみたい。
このまま人生が終わってしまっても構わないとさえ思った。
辺りはオレンジ色に染まっていた。
私の知る限り、世界で一番美しく輝きに満ちた瞬間だった。
2
とにかく浮き足立っていた。ふわふわ雲の上を歩いている見たいだった。
あの時のまま時間が止まってしまえばいいのに。
時は残酷。またいつもの日常が追いかけて来る。
二学期に入ると、早々に文化祭の準備が待ち構えている。
中等部二年時代から文化祭のポスターは私が作るようになっていて、誰よりも早く動かなければならなかった。
いつもならとっくに終わっていて、新学期には提出しているのに、十月に入ってもまだまだ終わる気配がない。
完全にのぼせ上がっていた。
作業に集中出来るように気を遣ってくれていたのか、デザイン研究会のメンバーがパソコン室にやって来ることはあまりなかった。
マコトが来なくなった理由もそうであればいいのに。
何だか私のことを避けているような気がしてならなかった。
マコトのそう言ったところはすぐに気付いてしまう。
何かを隠していると、それを悟られないよう無理矢理明るく振る舞うのが彼女の癖だった。
隠し込んでいる〝何か〟に触れると、今度は打って変わって不機嫌になる。
人は誰しも秘密を持っている。私だってそう。
それに触れないようにしてやるのが、一番の処世術なのかも知れない。
真木瀬君は毎日私の元へ来てくれた。
あの日以来お互い心が通い合っているような気がした。
私が作業をしている間中ずっと友達の事とか、家族の事、昨日観たテレビ番組の話、自分が最近何をしたとか、それこそたわいない話を殆ど一人で話していた。
彼の話を聞く限り、彼には秘密が無いように思えた。
真木瀬君は末っ子で上にお姉さんが二人いた。
どことなく希君に似ている気がしていたのも、そういった環境で育ったからなのかも知れない。
私は希君のような素直さを彼に見ていた。確かに彼の性格は素直過ぎると言っていいくらい。
でもその子供のような素直さが時にナイフのように人を傷付けるという事は、彼自身全く気付いていなかった。
彼の性格はマコトとそれとは正反対のような気がした。
やるべき事は沢山あるのに、その全てが疎かになっていた。これは自覚するところだった。
良い意味で彼のせいで気が散ってしまっていた。
彼のことで頭がいっぱいだった。
本当にどうにかなってしまったみたいだ。
「サクラ?」
そう言いながら誰かが教室のドアを開けた。
声の主は笹之辺君だった。彼はドアの向こう側から顔を覗かせて、室内を見回した。
「妹来てる?」
「え?今日はまだ会ってないよ。」
「何だよ、アイツ。」
笹之辺君は顔を顰めて吐き捨てるように言った。
「どうかしたの?」
「いや、アイツ朝起きて来なくてさ、起こしに行ったら、体調不良、遅れて行く。とだけ言われたもんだから、ちゃんと来てんのかなって思って。」
「マコトが無断で休むなんて珍しいね。」
「アイツ携帯出ないし、母親もパートで捕まらないし、先生に何て言えばいいかわかんないよ。」
「何かあったのかな?」
「さあ、よくわかんない。」
そう言いながら笹之辺君はドアを閉めた。
マコトが無断で休むなんて本当に珍しかった。寧ろ初めてかも知れない。
いつも元気いっぱいなマコトが起きれないくらいの状態なんて、何も無いハズがなかった。
心配になったので、すぐに彼女に電話をした。
何回か呼び出したあと留守電に切り替わったので、とりあえず学校帰りに様子を見に行くことを告げた。
3
夕刻。下校時間を知らせるチャイムが鳴る。
真木瀬君の話を聞いているうちに、あっという間に時は過ぎていった。
時刻は午後五時を過ぎていた。
結局この日も何も出来なかった。
正直な話、もうどうでもよくなってしまったのかも知れない。
それより大好きな彼と過ごすことの方が何よりも大事だった。
外は少しだけ肌寒い。ちょっぴり冷くなった空気をめいっぱい吸い込んだら、お腹が鳴ってしまった。
彼に聞かれたかも知れない。
私は何とか誤魔化そうと会話を探した。
それを察したのか、彼は「ああ、腹減った」と独り言のように言った。
薄暗い夕方の帰路を二人並んで歩く。
並木道を抜けて行く。
大学のキャンパスから授業を終えた学生さんたちが一斉に駅の方へと流れて行った。
その流れを避けるようにして私たちは公園を横切った。
彼の人差し指に軽く触れてみる。
彼の人差し指と私の人差し指が絡まると、そのまま彼の細くて大きな手は私の小さな手を包み込んだ。
急に帰るのが嫌になってしまった。
彼も同じ気持ちだったのだろう。
繋いだ手を解いてそのまま近くにあったベンチに腰掛けた。
私も彼の隣に腰掛ける。
そこは私たち二人だけの世界だった。
そのまま彼の肩に寄りかかって眼を閉じた。
現実と幻想が入り混じって行く。
何だか甘過ぎて私はすっかりとろけてしまった。
次第に幻の中へ溶け込んでいった。
気がつけば私は真木瀬君と海辺にいた。
彼は足元に落ちている貝殻を拾い上げて、海へ放り投げる。
私はずっとその姿を見つめている。
強い風が吹く。
その時髪に結んでいたリボンが解けて飛ばされてしまった。
私はリボンを追いかける。
リボンは風に流されて海の方へ飛んで行った。
海の中に入りそうになると、真木瀬君は私の手を掴んで、自分の方へ引き寄せた。
そのまま二人浜辺に倒れ込むと、今度は強く抱きしめ合った。
私たちは見つめ合いキスをする。
折れそうなほど強く抱き合う。
身体が熱くなっている。
肌の温もりを感じる。
誰かが私のことを見ているような気がしたけど、そんなことはお構い無しだった。
一瞬、彼から目をそらす。
視線の先に思わず息を飲んでしまった。
私のことを幼い頃の私が見つめていた。
まだ幼い私は瞬きもせず蔑むような目をしている。
彼女の気持ちは痛いくらい理解出来た。
ちょうど私が母を見ていた時の目だ。
私はその目に恐怖を覚えた。
恐怖は次第に怒りに変わって行く。
私は抱きしめる彼の腕を解くと、彼女の方へ走って行ってそのまま細い首を絞めた。
彼女の顔色は紫色に変わって行くけど、その眼差しはますます力強くなる。
私は戦慄した。手の力が抜けて行く。
強い風が吹く。私の足元に先程飛んで行ったリボンが落ちてきた。
彼が私の肩に触れた。
私は振り返るとそのまま彼にキスをした。
恐怖を拭うように何度も何度も熱いくちづけを交わす。
そのくちづけに違和感を感じた私はそっと目を開ける。
そこにいたのはマコトだった。
マコトは私を押し倒して、何度も何度もキスをする。
それを見て幼い私が笑っていた。
マコトは急に不機嫌になってキスを止めた。
「アンタなんか・・・」
そう言いかけると、立ち上がり幼い私の手を取って二人走り出した。
その姿は幼い頃のマコトと私。
どこか遠くへ行ってしまいそうだった。
「行かないで!」
「マコト!」
4
目が醒めるとそこは見慣れない風景だった。
薄暗い部屋の中にいる。
仄かな明かりが辺りを照らしていいて、ここが私の部屋ではないことだけは判った。
日常とかけ離れた場所。
常軌を逸している目覚めだった。
ベッドの上に寝かされた自分が、その時何も着ていない事に気付く。
心音だけが部屋中こだましている。
頭がクラクラする。考えに理解が追いつかない。
身体を動かすと引っ掻かれたような痛みが走った。
おヘソの下ら辺から脚先までジンジン響く。
私はベッドの上でしばらく蹲った。
今何時だろう。
携帯を探そうと無理矢理身体を起こす。
その時隣で眠る人の姿が飛び込んで来た。
「マコト?」
いや、真木瀬君だ。
僅かな寝息をたてているだけの彼の寝顔は、部屋の仄かな明かりを受けてとても美しく思えた。
しばらくの間、彼の寝顔を見つめていた。
深い溜息が溢れた。
徐々に前日の記憶が蘇える。
携帯を探す。
ベット近くのソファーの上に自分の鞄が置いてあるのが見えたので、痛みを振り切ってベットから出た。
携帯のバッテリー残量は残り僅か。
マコトからの不在着信を見て、彼女に会いに行くつもりだったことを思い出した。
次第に罪悪感がフツフツと湧き上がってきて、私は夢の意味を理解した。
マコトのことを放ったらかしにしてしまった。
自分に嫌悪感を抱いた。
マコトから離れていたのは私の方だった。
あどけなさの残る真木瀬君の寝顔をマコトと重ねる。
なぜかもう修復不可能なように思えて仕方がなかった。
5
文化祭まで残すところ後少し。ポスターの方は何とか仕上げる事が出来た。
実行委員長から何度も催促されて、頭をフル回転させて三パターンのデザインをほぼ一日で仕上げた。
正直やり遂げたとは言えなかった。
まるで夏休みの宿題に追われる子供のようだった。
委員長に原画とデータを渡すと彼はそれを見ることなく「ありがとう。」の一言だけ言った。
遅れてしまった事を怒っていたのかも知れなかった。
三日ぐらい真木瀬君にも会っていなかった。
彼も気を使ってくれていたのだろうと、自分勝手な想像をしていた。
何日か会わない日が続くと、少しばかり冷静さを取り戻す。
物事を違う目線で見てしまう。
もちろん好きという感情は変わらない。
ただ、何となく怖くなってしまった。
もしかして気持ちがあるのは私だけで、彼は決してそんな事はないんじゃないかって考え始めていた。
証明する言葉が欲しかった。
私自身、二人が恋人同士だって証明出来るのだろうか。
付き合っていると自信を持って言えるのか疑わしかった。
あの日の夜、私は高揚する情熱に身を任せて、彼にこの身を捧げた。
痛みも恐怖もすべて受け入れて、その先に確かな喜びを感じていた。
私たちの関係は実際とても青臭いものだったのかも知れない。
けど私にとってそれすらも美しく光輝いていた。
彼は精一杯の優しさを私にくれた。
それだけで私は幸せだと感じる事が出来た。
それがすべて成り行き上起こった事とは思いたくなかった。
そんなことは有り得ないという確信めいたものはあったけど、確信とは裏腹にどこか悪い予感も感じていた。
頭の中では言葉なんてものは要らないと思っていたハズなのに、心はだんだん不安でいっぱいになる。
気持ちというものは言葉にはならないと思う。それにすがると大抵失敗する。
気休めにしかならないのは解っていたけど、その気休めが欲しかった。
言葉がなくても通じ合えるという誤解は、マコトとの関係の中で生まれたものだ。
そうやって育って来たのだから仕方がない。
真木瀬君は私の事を思ってくれているのだろうか。
彼が私に「好き」と言ってくれたことが今まであっただろうか。
そもそも私が彼に「好き」って言ったことがあったのだろうか。
すべて曖昧なまま来てしまった。
愛と欲望は紙一重だと思う。
一体私たちの関係はどちらに傾いているんだろう。
その日の午後、廊下でマコトを見かけた。
マコトは笹之辺君と何やら話をしていた。
私が後ろめたい気持ちでいっぱいになっていると、二人共私の存在に気付いた。
マコトは一瞬冷ややかな目をしたけど、すぐに明るく振舞った。
「サクラ!なんか久しぶり!」
そう言って笑顔になっていたけど、目は全く笑ってなくて、悲しいような怒っているような何とも言えない表情をしていた。
私も彼女と同じように作り笑顔をした。
全部がぎこちなかった。彼女があの時どんな感情を抱いていたかは凡見当が付く。
笹之辺君があの場にいなかったらまともに目も合わせられなかっただろう。
「この前はごめんね。電話くれてたのに出られなくて。」
私は恐る恐る言った。
マコトは何か別のことを言いたげだったけど、それをグッと飲み込むような感じで会話を続けた。
「んー?いや、別に気にしてないよ。だって、サクラ忙しかったんでしょう?文化祭のポスターとか作らなきゃだし。」
「いや・・・」
「あんまり無理しないでよ。」
「ありがとう。」
「本当は待ってたんだけどね。」
マコトはからかうように言った。言い方はおちゃらけてたけど、それは本心だと思った。
私は何も言えなくなってしまった。
ごめんね。
そう言うのが正しかったのか。
いや、何を言っても間違いだっただろう。
正解なんてないんだ。
何も言わなくなった私に、少しだけ不満げな顔をした。
「じゃあ、授業あるから。」
それだけ言うと、その時他の子と話をしていた笹之辺君に何か耳打ちをしてその場を後にした。
去って行くマコトをずっと見ていた。
次第に辺りが霞んで行き、ただ彼女の後ろ姿だけがフォーカスされる。
6
五限目、教室を移動する時にコミュニティルームの掲示板に貼られた文化祭のポスターに思わず驚愕してしまった。
そこには私がデザインしたものとは違うポスターが掲示されていた。
「ねえ、このポスターいつから貼ってあったの?」
私はたまたま通りかかった知らない生徒に尋ねた。
彼女が一年生だということはブレザーの校章の色で判った。
彼女は驚いた表情をしていたけど、丁寧な口調で答えた。
「え?これですか?多分十月の半ばくらいだったと思います。」
「そう、ありがとう。」
私は来た道を引き返して、三年の実行委員長がいる教室を訪ねた。
教室に入ろうとする委員長を見つけると、私は彼を呼び止めた。
「何?」
彼は眉を顰めて言った。
「あの、私のポスター使わないんですか?」
私の言葉に彼は少し間を置いて、軽く頷いた。
「提出が遅かったから他の子にお願いした。せっかく作ってくれて申し訳ないけど。」
その言い方は淡々としていた。
「私のも使って欲しいんですけど、ダメですか?」
私は珍しく食らい付いた。
「うん。もう教務課の掲示申請おりちゃったから、難しいと思うよ。また来年頼むよ。」
彼の言い方は凄く機械的だった。
「でも・・・」
「いや、何度も催促したじゃん。こっちもカツカツなスケジュールでやってるから、期日守ってくれないと困るんだよ。」
この期に及んでまだ何か言いたそうな私に、少し感情的に彼は言った。
仕方がない。
約束を守らなかったのは私だ。
すべて私が悪いんだ。
好きな子が出来て、全部どうでもよくなってしまった自分のせいだ。
全然周りが見えていなかった。
私を置いてでも進まなくちゃいけない。
私が委員長の立場なら同じことをしていただろう。
何度も何度も自分に言い聞かせたけど、納得なんて出来なかった。
その日の夜、悔しくて涙が止まらなかった。
部屋でひとり、自分の不甲斐なさを責め続けた。
ある程度泣き疲れたら、急に誰かに慰めてもらいたくなってしまった。
真木瀬君に電話をする。
彼の電話は留守電にすらならなかった。
生まれて初めて孤独感に襲われた。
寂しさで頭がおかしくなりそうだった。
翌日、階段の踊り場で真木瀬君と鉢合わせた。
真木瀬君は「おはよう。」と一言だけ言うとそそくさと階段を降りていった。
「真木瀬君!」
私は彼を呼び止めた。
「何?」
振り返ってそう言う彼は凄く急いでいるような感じだったけど、何か隠しているようにも見えた。
「今日パソコン室来る?」
「うーん。どうだろう。行けたら行くけど。」
「ちょっと話がしたいんだけど。」
「え?何?」
「ここではちょっと。」
彼は「わかった」と言ってまた階段を降りて行った。
放課後、私はパソコン室で真木瀬君を待っていた。
たわいない会話を期待していたのか、それとももっと違うことを言って欲しかったのか、とにかく気持ちがぐちゃぐちゃに絡まっていた。
一時間くらい経ってから真木瀬君はやって来た。
「遅くなってごめん。」
「いや、来てくれて嬉しいよ。」
真木瀬君は窓側の席に座ると、そのまま外の方を見つめていた。
部屋の中は二人だけ。外から生徒たちの声が漏れている。
数分間沈黙は続いた。
「で、何?話って。」
真木瀬君は窓の外を見ながら言った。
「いや、別にこれといって。」
私は真木瀬君を見ながら言った。
「そう。」
彼は一言そう言うと、ようやく私の方に顔を向けた。
「なんか、雨降りそうだな。」
そう言いながらまた窓の外を見る。
「昨日電話したんだけど、寝ちゃってた?」
「ん?ああ、気付かなかった。」
そう言ったあと小さな声で「ごめん。」と言った。
彼の態度は明らかに違った。
まるで私とは何もなかったという感じだった。
内心焦っていた。彼を失ってしまうんじゃないかと恐怖心で満たされた。
「あの日の夜、私凄く嬉しかった。」
焦りが言葉を繋いでいく。
「真木瀬君と出会えて良かったって心から思った。」
真木瀬君は俯いたままで、何も言わない。
「でも、このままでいいのかなって。私たちの関係って何か曖昧な感じがする。」
彼は時折首を掻く。
「この気持ちが一方的なんじゃないかって。」
ここで言葉が途切れてしまった。
また沈黙する。世界が止まる。
二人俯いたまま何時間も経ったような気がした。
真木瀬君はようやく口を開いた。
「一方的じゃない、と思うよ。」
私は顔を上げた。
「好きだよ。」
私は言葉が見つけられないでいた。
「本当にサクラさんのこと大好きだよ。いつもサクラさんの事考えてる。」
雨雲の隙間から光が降り注ぐようだった。
「ただ・・・」
彼は話を続けた。
「正直わからないんだ。」
「え?」
「サクラさんに気があるのは本当だよ。でも・・・。」
途切れ途切れに話は進んで行く。
「実は、中学から付き合ってる子がいてね、彼女とは別れたり、また付き合い出したりしてて、ずっとその繰り返しなんだ。彼女のことも好きだし、それと同じくらいサクラさんのことも好きなんだ。」
空が厚い雨雲で覆われる。今にも泣き出しそうな空だ。
「サクラさんと出会って本当にどうしたら良いかわからなくなっちゃったんだよ。サクラさんのことばかり思ってるのに、彼女のことも思ってる。」
頭の中と心が離れて行くような感じだった。
それでも彼の話を私の脳ミソは受け入れていた。
「あの日の夜のことも嬉しかったけど、それと同時に後悔もしてるんだ。成り行きに任せて浮気したみたいになっちゃって、サクラさんに対しては俺本気なのに。」
そこから真木瀬君はまた俯いたまま何も言わなくなった。
その数秒間、私は何を考えていたんだろう。
全然思い出せないな。
彼が静かに息を吸って口を開いた。
「もうさ・・・」
雨がポツポツ降り始める。
「俺たち、会わない方が良いんじゃないかな。」
私の目から涙が溢れて頰を伝う。
冷たい涙だった。
「本当に・・・ごめん。」
そう言いながら真木瀬君は立ち上がり、部屋を出ようとした。
「待って!」
私は叫ぶように言った。
真木瀬君は立ち止まった。
「私、真木瀬君のこと大好き・・・本気なの・・・私、初めてだった・・・初めての人が真木瀬君だったから、許せたの・・・。」
涙声を殺そうと必死だった。
「・・・愛してる。」
沈黙。
彼は鼻をすする。彼も泣いているのがわかった。
「ごめん・・・ホントごめんなさい・・俺にはその気持ち重すぎるかも。」
そう言うと真木瀬君は一度もこちらを振り向かずに部屋を後にした。
ナイフで私の心臓は引き裂かれた。
痛みで吐き気を催した。
目の前が深い闇に覆われる。
傷は重く、もう治ることはなさそうだった。
闇の中で立ち尽くす。
雨音の中、生徒たちの声が聞こえる。
それだけが不釣り合いな日常を残していた。
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
かすり傷
1
とにかくお父さんは動揺していた。
慌てふためきながら救急車を呼ぼうと電話をかけ始めた。
腹部に当てられた薄茶色のタオルは血液で黒く滲んでいる。
結構傷が深いのかも知れない。
涙が止まらなかった。
まるで子供のように泣き噦っている。
さっきまで何もかもどうでもいいと思った。
消えてしまっても良いとさえ思った。
お腹から流れ出て行く血液の暖かさを感じると、急に死ぬのが怖くなってしまった。
死にたいなんて思っていなかったんだ。
いや、何がなんでも生きて行かなきゃいけなかったんだ。
急に息が苦しくなった。
息が出来ない。
目の前の景色がだんだん霞んで行く。
ああ、私はこんなところで死んじゃうんだ。
マコトに会いたい・・・
2
二八二〇グラムの元気な女の子ですよ。
咲良。あなたのお名前はサクラちゃん。
産まれて来てくれて本当に・・・
光が見える。
ここはどこだろう?
「咲良?」
誰か私のことを呼んでる。
ぼやけていて良く解らない。
「咲良?ああ、気が付いたか・・・。」
お父さん?
「本当に・・・」
お父さん?
泣いてるの?
「バカだなあ・・・」
白い部屋。お父さんの声だけが響く。
だんだんと景色が明るくなっていく。
私はベットの上。
その隣にお父さんが見える。
右手に暖かさを感じる。
それがお父さんの手の暖かさだとうことは何となくわかっていた。
生きていることを実感した。
「ここは?」
「病院だ。」
お父さんが囁くように言う。
景色がだんだんとはっきりしていく。
「何で病院に?」
「覚えてないのか?」
何となく覚えているけど、夢の中の出来事のような気がした。
「傷はそんなに深くなかったみたいだ。ほんのかすり傷だ。」
お腹に手を当てる。ガーゼの上からでも硬くなった傷跡がわかる。
「お前、小さい時に過呼吸で何度か倒れて救急車で運ばれたの覚えてるか?何年振りだろうな。こんな事。」
全然知らなかった。
「笹之辺さん家にお世話になり出した頃から、そういうの全然無くなってさ、それに良く笑うようになった。」
そうだったんだ。
「お前の笑顔を見られる事が何より幸せだった。だからこれからも笑って行けるように生きなきゃ駄目だぞ。」
お父さんは涙ながらに笑って見せた。
「他人のためじゃなく自分のために、そして自分の家族のために心から笑えるように生きろ。お母さんの事なんか気にするな。君は彼女とは違う。君が笑うだけでこんなにもお父さんは幸せになれたんだ。それだけは絶対に忘れないで欲しい。」
涙が溢れた。
生まれて初めて自分を愛おしく思った。
傷跡の向こうに鼓動を感じる。
そこには確かに命があった。
「ごめんね。」
そう呟こうとしたけど、そうじゃない。
「ありがとう。」
私の言葉にお父さんは笑って頷く。
心の中でもう一度「ありがとう」と呟いた。
お腹の子がお父さんと同じように笑っているような気がした。
晴れの日の瘡蓋【第十二話】


