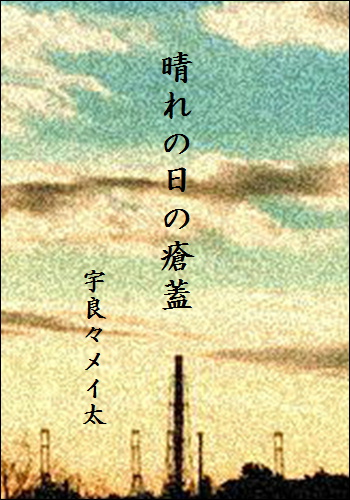
晴れの日の瘡蓋【第十一話】
ガラスの壁
1
「マコちゃん、凄いじゃないか!」
マスターが声のトーンを上げて言った。
「手前味噌だけどね、この子は天才だと思うね。始めてまだ一年足らずだぜ。俺はもっと上に行けると信じてる。いや、もう次は優勝しかないだろうな。」
おじいちゃんは高笑いで言った。
クリームソーダの綺麗なエメラルドグリーンの泡が浮かんで行くのを目で追いかける。
それがアイスクリームと混ざり合って、まるで雲のような不思議な模様を描いていた。
おじいちゃんはいつも私の自慢話ばかりしていた。
私は照れくさくって、まともにみんなの顔が見られなくなってしまった。
こんなことが永遠に続くものだと思っていた。
今思えば本当に幸せだったと思う。
ソーダ越しにあの頃の景色を眺めていた。
エメラルドグリーンのソーダが弾けて飛んだ。すべて流れていく。
幼い私も、おじいちゃんの顔も。
いつもの場所に男の子と一緒にサクラがいた。
私のことは知らんぷり。
グラスに残ったソーダも全部こぼしてやろう。
「マコトちゃん?」
そう言いながら奥さんが私の顔を覗いた。
「な、何?」
私がびっくりして後退ると、奥さんは不敵な笑みを浮かべた。
「何?」
「マコトちゃん。」
「はい?」
「そういう事なのか。」
奥さんは遠い目をした。
「えっ?そういうこと?どうゆうこと?」
「サクラちゃん。」
「えっ?え?サクラがなに?」
「サクラちゃんと仲良くしてるのが気になるのね。」
「え?え?何が?」
「何って、」
奥さんは声を潜めて言った。
「好きなんでしょ?」
この一言が私の心臓を貫いて、さらに次の一言で身体がぼろぼろ崩れて行くような感覚がした。
「真木瀬君の事。」
一瞬だけ〝考える〟という行為そのものがわからなくなってしまった。
「ずっと二人のこと見てるんだもん。凄くわかりやすい。」
そう言いながら目をさらに細くした。
私は急にしどろもどろになりながら全否定した。だけど、この全否定すら自分に付いた嘘のような気がしてならなかった。
多分私は明らかに嫉妬していたのだと思う。
何に嫉妬していたかはわからない。嫉妬の相手は真木瀬かサクラか、それとも二人になのか。
どこに気持ちを持っていってもしっくり来ないような気がしていた。
私はやっぱり変な奴だ。それだけはしっくり来ていた。
もはや変態的と言ってもいいかもしれない。
本当に自分というものが恐ろしくなる。
2
夏休みも残り僅か。何もかもがフルスロットルで加速して行く。それなのに課題はまだまだタップリと残っていて、まったく終わる気がしなかった。新学期早々に小テストもあって、受験の時なんかよりもずっと追い込まれていた。
本当に海に遊びに行った日のことを後悔していた。あの日は無意味だったと思い込もうと必死になっていた。
宿題が終わっていない事実を全部あの日の出来事のせいにしておけば、計画性のない自分のことを少し許すことが出来る。そんな気がしていた。
とにかくその時は本当に誰かの助けが必要だった。そばにいて励ましてくれるだけでもよかった。
ニイはニイで忙しいだろうし、父は絶対に手伝ってくれないだろう。
こういう時母に相談しても「お父さんに話してごらん。」の一点張り。お父さんの事を過信しているのか、それともただ単純に面倒に思ってただけなのか。
サクラは・・・。
・・・うん、気まずい。
とにかく今回ばかりは誰にも頼らずにやるしかなかった。
その日も気が付けば深夜を回っていた。苦手なコーヒーを三杯くらい飲んで、お腹がグルグル唸っていた。あくびが止まらない。
ふと姿見の方に目をやった。そこには疲れ果てた一人の若者が映っていた。
私は立ち上がって鏡の前で大きく背伸びをした。
自分の顔を見つめると、自分が母親と同じ顔をしていることに気がついた。
前に父が言っていた通り、本当にお母さんそっくりだ。疲れている顔は特に母の顔と重なる。
「高校時代のお母さんそっくり」と言った父の言葉の意味をよくよく考えてみると、何とも言えない変な気持ちになった。
うちの母は父の教え子だった。父と母が出会ったのは、母がその時の私の年齢と同じ。高校一年。なんだか気持ちが悪かった。
二人の馴れ初めなんかは、マスターからよく聞かされていた。頼みもしないのに。
これだけは二人の名誉にかけて言うけど、決して禁断の愛ではなかった。犯罪になるようなことは一切なかったとのこと。
二人の恋愛は母が二十歳を超えてから始まったということだ。ここだけはマスターも特に強調していた。
最初は恋愛とかではなく、教師と生徒の強い信頼関係だった。母は先生である父に事あるごとに相談し、父もそれを親身になって聞いてやっていた。
今でも母は父に対して絶対的な信頼を寄せている。
母は気づいていないんだろうけど、大事な話をする時必ず父の事を〝先生〟と呼んでいた。母の言うこの〝先生〟という言葉がひどく耳に焼き付いている。
私にとって先生は父の固有名詞だった。今でもそう。
その〝先生〟と私の間にはガラスの壁のようなものが存在していた。お互いのことは見えるんだけど、触れることは出来ない。無理矢理相手に触れようとするとガラスが割れて、その破片で怪我をしてしまいそうだった。
お互い怪我を恐れて触れ合うことに怯えきっていたのだろう。
それが今日までの父娘関係だった。
知らない間に私は自分が傷付かない術を身に付けいたのかも知れない。
だからサクラとの間に壁を作ることも簡単に出来てしまったのだろう。
3
生まれて初めてした努力で何とか課題をクリアし、無事新学期を迎えることが出来た。
一人で何かやり遂げたのは、これが初めてだったと思う。
私はおじいちゃんからよく「天才」だと言われていた。それで私は自分のことを過信した。実際には私の周りには常に誰かいて、その人たちに助けられて今日までやって来られたのに、その事がまるで見えていなかったのだ。
生きるという事は反省の積み重ねなのかもしれない。
久しぶりにサクラと会う。放課後彼女はいつものようにコンピューター室で作業をしていた。
その姿はますます輝いて見えた。
私は声を掛けようか迷っていると、後ろから真木瀬が背中を叩いた。
「ひゃあ!」
私が発した変な声でサクラはこちらに気づいた。
彼女の目は私を見ているようで、実はその視線は真木瀬の方にあるような気がしていた。
私は急に逃げ出したくなった。
サクラが私を呼んでいるのに気づいたけど、それよりも真木瀬のことが気になって仕方がなかった。
真木瀬の目を見てすべてが明らかになった。
サクラを見る彼の目は、私を見る時とは明らかに違っていた。
私はこの場所にいるべきではない。咄嗟にそう思った。
二人に何か声をかけた事は覚えているんだけど、何を言ったかはわからない。
とにかく無理矢理明るく振舞って逃げるようにしてその場を立ち去ったのは覚えている。
私はガラスの壁越しに二人を見ていたような感覚に囚われた。
もう何もかもあの頃とは違う。
そう思わされた瞬間だった。
晴れの日の瘡蓋【第十一話】


