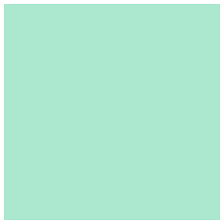一通目
もうすぐ会議の時間だからと出て行った康夫を寝転がったまま見届けて、早紀は読んでいた結婚情報誌を押しやった。先ほどまで貸してやっていたパソコンの前に座り直す。
「家に一度戻るから、ちょっとだけお前のパソコンを貸してくれないか」と彼から連絡があったのは2時間ほど前のことである。出先で急遽客先にデータを送らねばならなくなったのに、端末の調子が悪いのだそうだ。会社に戻るより家の方が近いから、とのことだった。
同棲を始めて一年。何かにつけ結婚を迫る早紀に対し、康夫はなかなか首を縦に振らずしきりに就職を勧めてきた。近頃は諦めたのか一層仕事に打ち込んでいる様子である。
―――もう、こっちはいつでも結婚できるのに。
気晴らしにネットサーフィンでもしようかと青い画面を見ると、ぽつぽつとアイコンの並ぶ中に、何か見慣れないものがある。紺スーツを着た白いヤギのイラストだ。手紙を片手に、ご丁寧にアニメーションでもぐもぐと口を動かし続けている。今までそこにあったのはメールソフトのはずなのだが。
眉をひそめて悪態をつく。
―――やだ、何これ。康くん何かしたの。
Mailという文字の上のヤギは、虚ろな半月状の目をしたままいっこうに口の動きを止める気配がない。まさかね、と終わらない咀嚼を見つめながら早紀は思った。
———これ、来たメール片っぱしから食べちゃってたりして。
二通目
一心に咀嚼している。ちぎっては口に運び、ちぎっては口に運びを繰り返しながら、川村は床を見つめていた。台所の床に敷かれたクッションフロアが、にぶく蛍光灯の光を反射している。
丹念に掃除された床である。「埃はともかく髪の毛が落ちているのが我慢ならない」というのが、妻の口癖であった。だらしないようで、そういう所だけは几帳面だ。
つられて自分もよく掃除をするようになった。妻が若い男の元に走り、帰らなくなってからもそれは続いた。生活はできてるのかと遠慮がちに聞いて来る同僚達に見せてやりたい。
手の中に残った一筆箋を音を立ててちぎる。と、それに何か書かれていることに気が付いた。
『こちらの分は署名、捺印してあります。あとはそちらでお願いします』
くしゃりと口に放り込んで、はて、と男は首をかしげる。何か同封されていたのかもしれないが、腹の中に収めてしまっては分からない。尋ねてみるしか手立てはなかろう。
鼻梁を抜けていく甘いインクの匂い。最後の一口を水で流し込むと、小引き出しから便箋を取り出して再びテーブルに向かう。テーブルの淵に対して便箋が平行になるようにきちんと整えたのち、妻に宛てて丁寧に字をしたため始めた。
三通目
「離婚届を食べてしまうほどに、かつての同僚は追い詰められていた。そんな彼を、もう見ていられなくなったんです。それがあれを試作したきっかけでした」と男は言う。
陽の差し込む開放的なオフィスで、自身はTシャツにジーンズというラフな格好で、さながらろくろでも回すかのように両手を広げてみせた。机の向かいに座っていたインターネットメディアの記者———康夫が頷いて応えながら、ノートパソコンに打ち込んでいく。
「情報を自動的に消去するソフトということで、悪用を危惧する声も聞かれますが」
康夫はパソコン越しに上目遣いで男に尋ねた。
「まあ、社内でもそういった声があがりましてね、リリースには至りませんでした。試作品はわが社で厳重に保管されております」
没になった製品について触れられても、男は嫌な顔一つしない。張りのある声や堂々とした身振りから、自信が伝わってくる。
「先ほどおっしゃっていた元同僚の方ですが…」
ああ、と声を上げて男は困ったように微笑んだ。
「彼は消息を絶ってしまいまして、様子は分からないのです。私もその後すぐこちらに転職をして、この製品の試作に取り掛かっておりましたので。」
ですが、と続ける。
「私にも彼の気持ちが分かるような気がするんです。何もかも忘れたくなるようなことって、誰でも一度はあるのではないでしょうか。記者さん、あなたもそうでしょう?」
康夫は曖昧に笑って頷いた。心なしか震える声で「次の質問を」と切り出す。
「都市伝説のような噂ですが、そのソフトのせいで記憶喪失となった人がいると聞いたのですが、本当でしょうか?なんでもヤギのアニメーションを見てると自己暗示にかかるとかで…」
言い終わらぬうちに大きな笑い声が響いた。
「ご冗談を。そうだとしたら、開発者の私が一番危険ということになりますが、この通り無事でしょう」
「———最後にもう一つだけ聞かせてください」と康夫は言った。少し怯えているような、祈るような眼をしている。
「あなたは本当に川村さんなんですよね?」
「そうですが…」
川村と呼ばれた男は一瞬不思議そうな顔をしたものの、すぐに相好を崩した。
「インタビューを受けるというのは気分がいいものですね。しかも世に出せなかった製品のことを聞いて頂けるなんて、嬉しいですよ。
ところで、あなたは随分あれに興味がおありのようですが…」
四通目
スーツ姿の人々が行き交うオフィス街を、康夫はのろのろと歩いていた。
にわかには信じ難かった。あれが川村なのだろうか。聞いていた印象と大分違う。
面識はなかった。だが相手にとって康夫は妻を略奪した浮気相手である。興信所を頼ってこちらの顔を把握していても不思議ではない。のこのこと目の前に姿を現したが最後、非難を浴びせかけられ賠償を求められる危険もあった。
それでも川村に取材を申し込んだのは、強烈に興味を惹かれたからだ。
いつ訴えられるかと胃の痛くなるような日々を過ごしていたある日、康夫は人づてに奇妙な噂を聞いた。
記憶を消してしまうソフトの存在。ある会社に彗星のように現れた開発者。彼は妻に逃げられたが、ショックのあまりその過去を忘れてしまっているらしいこと。
バカげた話だと思いながら記事のネタとして調べていたが、それが早紀の元夫だと分かった時にはぞっとした。
このまま取材を続けていたら自分の身が危ない。だが、「本当に忘れているのか?」という疑念は膨らみ続けた。噂通り川村が過去を忘れているなら、早紀と康夫のしたことも無かったことになるのではないか。そう思うと、確認せずにはいられなかった。
そして今日会った川村は、かつての出来事を元同僚のエピソードだと思っている———。
通行人とすれ違いざま肩がぶつかり、舌打ちされた。「すみません」と小さな声で呟いて、肩から落ちかけたショルダータイプのビジネスバッグをずりあげる。ふとバッグの中に手を差し込むと、硬いものが指先に触れた。
———川村はどうしてこれを自分に渡してくれたのだろう。
ただの遊びのつもりだった。早紀がこんなにのめり込むとは思わなかった。あっという間に家に転がり込んできて、離婚が成立してからは働きもせず日に日に結婚のプレッシャーをかけてくる。全力でもたれかかってくる早紀から、自分はおそらく逃げられないだろう。罪悪感を持て余しているうちに、徐々にあの女に絡めとられてしまった。
しょっちゅう床で転がっていた早紀の姿と、だらしがないにしては掃除の行き届いた床が脳裏に蘇ってくる。何度も聞いた「髪の毛が落ちてるのが我慢ならない」という彼女の声も、先ほどの川村の声も。
———何もかも忘れたくなるようなことって、誰でも一度はあるのではないでしょうか。
康夫はポケットから携帯電話を取り出すと、操作して耳に当てた。
「ああ、早紀?うん、今取材終わったとこ。
悪いんだけどさ、これから家に一度戻るから、ちょっとだけお前のPCを貸してくれないか」