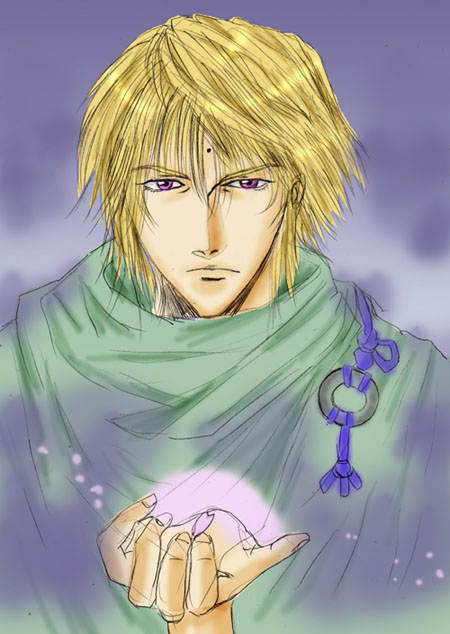
月の桂
2007?年~作品
偏在
「月も笑っていやがる。」
悟浄が苦笑いをしながら、焚き火にかけられた、フライパンを覗きこんだ。
「こんな夜はよ。そうだと思わねぇ?八戒。」
「まあ・・・そうですね。」
今夜は野宿だった。
ジープがガス欠で動けなくなった――空腹で、である。ジープは竜の姿に戻って、丸くなっていた。
三蔵一行もご同様―――先の宿場で八戒が買っていた、缶詰やパンのお世話になることになったのである。
一行の真ん中には小さな焚き火がある。
薄い紫の煙が月夜の夜空に一本のぼっていた。
それは静かな夜だった。
フライパンの上では、缶詰の干し肉がジュージューと煙をたてて焦げている。
まことにひもじい――しかし、仕方がない。
彼らは今「西」に向かって旅をしている。
それは「あてのない」ような、しかし目的はあるような、漠然とした旅であった。
八戒がフォークの先で肉をつついた。
「もういいようですね。悟空、お皿を出して」
八戒が男にしては器用な手つきで、フライパンの上のおかずを取り分けていった。
しかし悟空は皿を見たとたん、ぷぅとした顔でむくれた。
「えっ・・・ひとり分がそんだけかよぅ。」
「仕方がないでしょう。次の宿場町にたどり着けると思って、そんなに大量に買出ししてなかったんですから。みんな均等に分けているんです。」
「ちぇ~っ。」
悟空はフォークを口にくわえて、不満気に八戒の顔をにらんだ。
「三蔵も、ここに置いておきますよ。」
三人から少し離れたところで、三蔵は一服していた。
「ああ。」
と、三蔵は鷹揚に返事を投げて返してよこした。
悟空が三蔵の答えを聞いて、にへ、と笑った。
「三蔵、何してんの?食べねぇのなら、オレ三蔵の分も。」
「こらこら、いけませんよ。悟空」
八戒は言うと、三蔵に近寄り、かがんでいる三蔵の上から覗き込んだ。
三蔵は熱心に愛用の銃の調子をみていた。
唇にくわえたマルボロが短くなっている。
八戒が三蔵にたずねた。
「銃のお手入れですか?」
「たまに見とかねぇとな、ジャミングが甘くなるんだよ。」
「はあ。僕にはさっぱりの世界です。」
三蔵は銃の劇鉄を何度も起こしては、空の引き金を引いてはまた戻している。その動作の繰り返しで、かすかな狂いを見つけようとしているのだ。三蔵は頭をかき、つぶやいた。
「そろそろ分解しなくちゃ、いけねぇか。面倒だな・・・・。」
三蔵はしかめっつらをした。八戒は三蔵をなぐさめるように声をかけた。
「大切なんですね、その銃。」
ケッ、と三蔵は肩をすくめた。
「大切じゃねぇよ。こんなチンケな銃、虎も殺せやしねぇ。」
「じゃあなんでその銃にこだわるんですか?」
「こだわってんのは、こいつとすごした時間だよ。」
「そうですか。でも三蔵さんの腕前なら、もっとマグナムなんかのほうがいいような気がします。その銃、一度装填したら連発で五回しか撃てないじゃないですか。機関銃とまでは言いませんけどもね。だけどそれ、続けて撃ちにくいじゃないですか。」
と、八戒は言ってからしまったと思った。三蔵の目がその時冷たく光ったからだ。
三蔵は押し殺した声で低くつぶやいた。
「・・・・・オレにはそのぐらいがちょうどいいんだよ。」
「そうですか。三蔵さん、料理、さめないうちに食べてくださいね。ここに置いておきますから。」
三蔵の目の前から立ち去った八戒は、また竜の逆鱗に触れたかとひやりとするのだった。
―――どうも僕は三蔵さんが、ああいう時は怖いんだよな。ニガテってわけじゃないんだけど・・・。
悟浄にはああいう具合に、怖い思いをすることはない。悟空はもちろん、ない。
三蔵だけが、時々氷のような瞳になる時がある。
―――だって不思議だ。三蔵さんは、僕たちみたいに半妖じゃない。妖怪でももちろんない。だけど、僕は三蔵さんが怖い。三蔵さんは人間なのに。僕は1000人も殺して妖怪になったってのに。
それは三蔵が仏門の徒であり、高僧だからだろうか。その落差がそう思わせるのだろうか。
八戒にはわからなかった。
―――ねぇ、三蔵さん、そのピストルいつから三蔵さんのそばにあるんです?
尋ねてみたいと八戒は思うのだが、それこそ竜の逆鱗に触れることに間違いなかった。
と、悟浄が戻らない八戒を見て茶々を入れてきた。三蔵はうまいのかまずいのか、わからない顔で、食物をスプーンで口に運んでいる。
「おっ、三蔵サマ愛銃のお手入れの時間?大変だね。オレの鎌なんざ、手入れなしでもいつでも使えるのよん。」
「煩ぇ・・・・。てめぇらみてぇに、妖怪の変な法力でこちとら動いてねぇんだ。」
八戒があわててとりなすように言った。
「悟浄、三蔵さんの機嫌を損ねないでくださいね。」
「ケッ、くそ坊主。そのうちてめぇが妖怪になりやがれ。」
「あいにくあの世でも、オレは坊主で人間だ。」
「おーおー、見上げた精神力だねぇ。なあ八戒、そう思わねぇ?」
悟浄の言葉に、八戒はかすかに笑って答えた。内心少し動揺がある。
「三蔵さんは、大丈夫ですよ。僕とは違いますから。」
「あ?坊主だから?坊主の経文にどれだけの力があんのかねぇ。まったく。」
そこへ悟空が、つまらなそうに言葉を入れた。
「なんの話?オレ難しい話ぜんぜんわかんねぇよ。」
「お子様には難しかったか。」
「なんだと、三蔵。」
「ガキはさっさと寝ろ。」
「うるへー!!!三蔵のバカヤロー!!!!」
悟空はどなって、シュラフにくるまった。
三蔵たちも寝袋に横になった。
悟空と悟浄はさっさと先に寝入ってしまっていた。
八戒は寝袋から見上げた月を眺めて言った。
「望月だなあ・・・・満月ですね。今夜は。」
横に寝る三蔵が答えた。
「月は―――嫌いだ。」
「どうしてです?」
三蔵は月を見ていた。
冷たいレモン色の光が、目に痛い。焼きつくようだ。
三蔵は低くつぶやいた。
「あの夜もオレを見ていた。こんな月だった。」
「あの夜って・・・・・・?」
八戒は考えて、がばっと起き上がって言った。
「そうだ、三蔵さんのお師匠の方が死んだ夜のことですね?」
三蔵はしばらく黙っていてから、つぶやくように答えた。
「・・・・それは・・・・そうだ・・・・そうあるべきだ・・・・。」
「えっ、違うんですか?」
「もう寝ろ。」
三蔵はくわえた煙草を、腕をあげて地面でもみ消した。八戒に違うともそうだとも答えなかった。
八戒は思った。――いつもの三蔵だ・・・・。そう、いつもの三蔵だった。
―――あの月こそ、あなたみたいなのに。嫌いだなんて。
八戒は思い、毛布にくるまった。
やがてその小山の森のあたりを、夜の闇の静寂が包んだ。
三蔵は夢を見ていた。
さらさら・・・・さらさら・・・・と西から流れるような風が吹いていた。
手に持つ箒に、赤い紅葉した落ち葉の群れが当たっては舞い散った。
風は幽冥の方角から吹いてきて、この金山寺の立つ丘の上に吹き付けてくるのだった。
毎年毎年・・・・その砂漠から吹く風が頬を切るようになると、冬の訪れはもう間近だった。
三蔵は風の行方を思う。
何もかもが、無限。西には果てのない砂漠が広がっているのだという。
三蔵は顔をあげた。
幼い頃の自分だ―――まだ江流と呼ばれていた頃の、自分。
額には三蔵法師の継承者の印である、チャクラはまだない。
この寺では、自分は「もらわれ子」の立場であった。
ただ、自分の優しい師である光明三蔵法師だけが、陽になり陰になり自分をかばってくれる。
それ以外の僧兵などの荒くれ僧たちにとっては、自分は「河流れの江流」でしかなかった。
従って江流は寺の下働きとして、今も山門の境内の道を箒で掃いていた。
江流は本当に河でおぼれていたのを、光明三蔵に助けられたと言う。
自分では覚えていない。
なぜおぼれていたのかも、わからない。
記憶はない。
ただ、無限に広がる蒼い薄闇の記憶と、自分をつかむ腕の記憶だけがかすかにあった。
誰が教えるまでもなく、三蔵は自分が「捨て子」であることを、わかっていた。
金色の髪をした、紫の瞳を持つ自分が、この寺だけではなく、この大陸で異端と呼ばれる存在であることを、三蔵はうすうす感づいていた。
町に出れば、自分を見る人々の目が、異端なものを見る目つきであるのを感じ取っていた。
だが、三蔵の師である光明三蔵の髪も金色だった。
さらに、光明はそれを、もうずいぶん歳を取っているのに、女のように三つ編みに編んだり、結い上げてみたりする。
光明はある時、三蔵に言ったことがある。
「あなたは自分のその姿が好きですか?」
三蔵は少し考えてから、あまり好きではない、と答えた。
自分は目も髪も真っ黒なこの国では、目立ちすぎるし、また同胞はいないも同然であった。
光明は嘆息してこう言った。
「あなたの髪と私の髪、少し似てますね。」
三蔵が無言でうなずくと、光明はにこやかに言った。
「私たちはきっと、北冥の地から来たのですよ。」
「ホクメイの地・・・・・?」
「そう、北の冥府の地です。北はこの中華では蛮夷の住む方角ですが、道教の荘子にこんな言葉があります。『北冥に魚あり。其の名を艮と為す。艮の大いさ其の幾千里なるかを知らず。化して鳥と為るや、其の名を鵬と為す。鵬の背、其の幾千里なるかを知らず。怒して飛べば、其の翼は垂天の雲の如し。この鳥や、海のうごくとき即ちまさに南冥にうつらんとす。南冥とは天地なり。』―――あなたも私も、もとは北の大地に住む魚だったのです。それが、大鳥になって、南のこの長安の都にやって来たということなのですよ。」
「魚・・・・・。」
「そう、だからあなたは「河流れの江流」というのですよ。きっと揚子江のような大河を流れて来たんでしょうね。艮の大きさは幾千里もあるそうですから。」
「お師匠様、俺はやっぱり魚ではありません。」
「ああ、あなたはこの呼び名は嫌いなのですね。」
光明はここで、小さな三蔵の前にしゃがみこんで言った。
「忘れてはなりません。あなたは前世では魚であったり、鳥であったかも知れません。この世にある命は輪廻転生を繰り返し、流転しているのです。ですから、命というものはすべてつながっているし、永遠になくならないものなのです。」
「永遠になくならない・・・・?」
「そうですよ。あなたは食べ物を食べたりして、生きていくうえで殺傷しますね。でもその命はまた、この世によみがえってくるのです。必ず。仏がそうしているのです。この寺にいる私たちは、それを守って生きているのですよ。それが仏道です。」
「・・・・・・・・。」
「私はあなたにも将来それを守れとは言いません。だけど、忘れないでほしい。あなたはこれからきっと、大きな人生を歩むと思いますからね。」
三蔵はかすかにうなずいた。
光明の言葉は、好きだった。
岩に清水が染み入るように、三蔵の心の奥深いところにその言葉は届くような気がするのだった。
この人はきっと、俺を裏切らない。
そうあってほしい。
それが幼い三蔵の、願いらしい願いであった。
と、その時二人の後ろに立つ影があった。
黒い髪の眼鏡をかけた僧侶だった。
「転生論は、子供にはわかりませんよ。」
三蔵がむっ、として声のした方角を見ると、一人の子供がその影に隠れて立っていた。
光明が不審げな声をかけた。
「烏哭―――その子供は?」
「町で拾いました。あなたのマネをしてみたんですよ。金髪でかわいい・・・・賢そうだしね。」
クスクスと、からかって笑うような声だった。
その子供も確かに三蔵と年恰好が同じぐらいだった。
子供はウサギのぬいぐるみを手に持っていた。
三蔵は自分よりもその子供のほうが、きれいに思えた。
自分の髪は黄色い金髪だが、その子供は銀髪みたいな金色をしていた。
薄い白金の色が、陽にすけて輝いていた。
顔の色もぬけるように白い。
と、子供がぬいぐるみを三蔵のほうに差し出した。
「これあげる。」
三蔵は、なんとなく受け取ってしまった。
子供がニッと笑った気がした。
と、ぬいぐるみの首がもげて地面に落ちた。三蔵はギョッ、とした。
「――!」
三蔵は嫌なものを見た気がした。
と、横に立つ黒髪の僧侶が眼鏡を手でおさえて言った。
「おびえているんだね。キミにはまだ、早いね。」
三蔵は、目に見えない黒い悪意をその僧侶に感じた。
光明が叱咤するように言った。
「烏哭!」
烏哭は言った。
「やれやれ、先が思いやられますね。ずいぶんと過保護に育てられたようだ・・・・。それでは継承のなんとやらも、受け継ぐことが果たしてできるのか・・・・。」
「あなたは、無天経文の継承者ですね。だったら・・・。」
光明の言葉をさえぎるように烏哭は言った。
「邪魔者は去りますよ。ぼうず、行こう。このおじさんは、口うるさいからね。」
烏哭が子供を連れて立ち去るとき、その名の如く空に黒い烏の群れがギャアギャアと騒いで飛んでいった。
「お師匠様、あの人は・・・・。」
三蔵の言葉に、光明は一言だけ答えた。
「あなたはまだ、知らなくていいのです。」
こういう時は、光明は貝を閉ざしたように何も言わない。
だがそれは、光明が自分を思ってのことだと、三蔵にはわかっている。
「おいでなさい。夜の勤行の支度を。」
三蔵は光明について、寺の中に戻っていった。
それから数日たった日のことだ。
「ねぇ、ねぇ、君、神様っていると思う?」
三蔵がまた寺の本堂の中を掃除している時に、あの銀髪の子供は不意に現れた。
「邪魔だな。」
「だからさあ、君たちの信じている仏様じゃないんだ。神様はもっと偉いんだよ。神様だよ。君は神様の存在を信じないの?君の今いるこの寺って、本当に正しいところだと君は思う?」
「うるさいな。」
雑巾で床を拭いている時に、そいつは雑巾を使う先に現れた。
三蔵が拭く途中の床の上を、ぺたぺたとはだしでそいつは歩いた。三蔵はそいつに尋ねた。
「おまえ、なんて名前なんだ。」
「―――だよ。」
三蔵の耳に確かにその名前は届いたはずなのだが、「胸糞悪いことは忘れるようにしている」と後年言ったとおり、三蔵の記憶の中ではその名前はぬぐいさられている。
代わりに三蔵は心の中でそいつの名前を名づけた―――『カミサマ。』
そいつが「神様」と言ったときの言葉の調子を三蔵は忘れることができない。
くぐもったように、鼻についたような上ずった調子で―――貴族生まれのように気取った風にそいつは発音したのだった。
そいつはさらに言い募った。
「だってねぇ、神様はこの世界の万物をお作りになったんだよ。君の師匠の人が言っている『転生論』では、そのことを看破できないんだ。だって、『転生論』が言うには神様がお作りになった世界が、ぐるぐる魂をやり取りしているってだけだろ?君のお師匠様はきっと馬鹿だね。」
「馬鹿だと。」
「だってそうじゃないか。僕の先生の烏哭三蔵法師様は神様みたいに偉いから、そんなことちゃあんとわかっていて、自分は神様の次の椅子に座るんだ、って言っているんだ。たとえばこの世界にはたくさん妖怪がいるけど、そいつらは神様が間違ってお作りになったんだから、神様の間違いを正すんだって言っていてさ。君のお師匠様は、それに反対しているんだって。臆病だから。」
そいつはかかと歩きで後ろ手で三蔵に言った。
三蔵はそれまで雑巾で床を磨いていたが、突然雑巾を床に投げつけた。三蔵はそいつの顔をにらみつけて言った。
「・・・・おい、お前。人にはそれぞれ縄張りがあるんだ。おまえの立っている場所は、俺の今掃除する縄張りだ。」
「え?」
「邪魔なんだよ。そこ、どけっつってんだ!」
「えっ、いたぁい。」
三蔵が突き飛ばすと、そいつは女みたいな悲鳴を上げた。
「そんなことしたら、僕の先生に言いつけてやるから。」
「うるさい。おまえの言うことなんか・・・・。」
「あっ、君のお師匠を馬鹿って言ったの怒ったんだ?君、あのお師匠様のこと好きなんだね。あんなおじいさんが。」
「俺のお師匠様は・・・。」
おまえなんかにはわからない、優しい人だ。三蔵はそう思ったが、口にすることはできなかった。
恥ずかしかったのだ。
三蔵はだから、目の前のそいつが、手放しで烏哭という男を誉めるのが我慢できなかったのだった。
と、その時三蔵の背中で声がした。
「おいおい、三蔵、そのへんにしてやれ。そいつはお前とは違うんだ。」
朱泱だった。朱泱は棒術などの師範代で、三蔵の稽古の先生でもある。
朱泱はそいつに言った。
「ぼっちゃん、こいつは癇癪持ちだから、あんまりからかわんでくれんかね。こいつは光明三蔵法師のこと、心底尊敬しているんだ。」
「しゅっ、朱泱っ。」
「はは、何あわててんだ、江流?いつか言ったろ。俺はお師匠様の言うことだけは聞くってな。」
三蔵は真っ赤になって怒った。
「そっ、それは・・・・。」
「あ?言っちゃならねかったか?ごめんごめん。しかしなあ・・・・。おまえも素直じゃない。」
と朱泱がとりなすように三蔵に言いかけた時、そいつはだっ、と走って逃げ出した。
「なんだ、逃げ足の早いヤツだな。」
朱泱は言った。そいつは後も見なかった。
と、その首に数珠をかけているのを、その時三蔵はやっと気づいた。黒檀の小さな珠の数珠だった。
――俺にもあんな数珠があったな。
三蔵はその時、ふと思い出した。
――あいつも、あんな事言っているけど、やっぱり坊主になるつもりなんだ・・・・。
俺は?と三蔵は思った。俺も坊主になりたくはないけど・・・・・あの優しいお師匠様を裏切れない。
だって――お師匠様は俺の命の恩人なんだ。だって俺の持っている数珠は――――。
三蔵はふところをまさぐった。
その、「誰か知らない親かも知れない人からの、形見の数珠」は小さい袋の中に入れて、肌身離さずいつも持ち歩いていた。その珠はすべすべしていて、触ると手触りがよく、三蔵は懐かしい気持ちにいつもなったのだった。
あいつとおんなじような、黒檀の小さな数珠―――。
どんな人だったんだろう、これを俺の乗る川の篭に入れた人は―――。
三蔵の心の中で、その時寂寞な想いが渦巻いた。
――どうして俺を捨てたの?捨てるのならどうして数珠を、篭の中に入れたの?
三蔵はじっと数珠を見ていたが、やがて決意したように朱泱に言った。
「やる。」
不意に三蔵はそれを、朱泱に向かって突き出した。
朱泱は三蔵の突き出された腕を、面食らった顔で眺めた。
「何を?この数珠をか?」
朱泱は驚いて、三蔵の顔を見た。紫の瞳が、何時になく激しい光を宿している。三蔵は言った。
「・・・・俺、人に物をあげたりしたことないんだ。あんたにそれ、やるよ。俺をいつも教えてくれたろ?」
「なんでだ。」
何故―――三蔵は何かを断ち切りたかったのだった。
――俺はもう子供じゃない。お師匠様に助けられてばかりじゃない。一人でも生きていける。あんなヤツとは違うんだ。
三蔵はその時そう思ったのだった。
「だから、その恩にあんたにそれやるよ。超レアだぜ。」
「お、おい。いいのか、これ。大事にしてたんじゃないのか?」
朱泱がとまどうのを、無理やり数珠を押し付けると、三蔵は本堂から駆け出した。
三蔵の中で、いろんな想いが駆け巡った。
――泣くもんか。泣く・・・・・・・・もんか・・・・・!
庭の端まで駆けて行って、三蔵は声を殺して泣いた。
なんで朱泱に渡してしまったのか、自分でもわからなかった。
でも、これで自分は何かと別れを告げたのだと思った。
三蔵の師匠の光明三蔵法師が、妖怪から三蔵をかばって絶命したのはその夜だった。
「お師匠様!」
血と叫び声だけしか、三蔵は覚えていない。
ただ、光明三蔵法師が自分をかばって死んだということだけは三蔵にはわかった。
そして―――妖怪が額につけた傷が発熱し、三蔵はその日から三日、生死の淵をさまよった。
――お師匠様・・・お師匠様・・・・・。
暗闇でうなされながら、三蔵は師が指先から紙飛行機を飛ばす夢をうつらうつら見た。
――私にはこんなことしかできないから。
夢の中で光明は、三蔵に穏やかに微笑んで言った。
その指先から放たれた緋色の紙細工は、紺碧の空に何処までも吸い込まれて行った。
三蔵は、わけもなく悲しくなった。
自分の師匠も、何もかもが自分を置いて飛び去っていくようだった。
――お師匠様、待ってください。俺を、置いていかないで・・・・いかないでください・・・。お師匠様・・・・・!
だから、目が覚めておのれの額にその刻印が現れているのを見た時、三蔵は大きな衝撃を受けた。
――なんで俺が・・・。
鏡に映った三蔵の額には、「三蔵法師」の正当な継承者であるチャクラの赤い印がはっきりと刻印されていた。
その印が現れた以上、三蔵はもう「三蔵法師」としての道を歩む以外許されないことになっていた。
師匠を思って泣くことももう許されなかった。
三蔵は光明を継ぐ者であり、魔天経文と聖天経文の正当な後継者である、と三仏神の命により寺の高僧たちから告げられた。
三蔵は居並ぶ僧侶たちの前で言った。
「ならば、お師匠様の仇を俺に討たせてください。そして、野党の妖怪に奪われた聖天経文を取り返しに行きましょう。」と―――。
そして――「カミサマ」とその夜姿を消した烏哭三蔵法師の額には、ついにそのチャクラは現れることはなかったのであった。烏哭はそれでも、無天経文の継承者で「三蔵法師」を名乗っていた。
すべては彼の実力であり、彼の唱える『唯識論』を、論破できる人間が金山寺にはおろか、この三千世界中を探しても見つからなかったからなのであった・・・・・。
それから三蔵は旅に出た。
時々古寺に宿を借り、信仰心の篤い民人の世話になりながら、三蔵は錫杖を手に歩いた。
ふところには、金山寺を出る時に手にした短銃が一丁しまわれていた。
金山寺の高僧は三蔵に言ったものだ。
「下界にはどんな妖怪がいるかわからぬ。どれでも好きなものを持っていきなさい。」―――
三蔵は寺の書庫にこのような猟銃や機関銃がたくさん所蔵されていたことに、あらためて驚いた。
もしかして、光明はこの事も知っていたのかも知れない。
しかし、光明はその事を三蔵に告げたことはなかった。
およそ暴力的なこととは、三蔵の目には光明は無縁に生きていた。
三蔵は壁に並んだ銃の中から、銀色に光る短銃を選び出した。
Smith&Wesson―――銀色の筒先に、その刻印が光っていた。外国製のものらしい。
「やはりこれは、西から?」
三蔵の問いかけに高僧は答えなかった。三蔵は言った。
「俺、これがいいな。」
三蔵はそのピストルを手に取ると、確かめるように手のひらに当てた。ぴったりだ、三蔵の手のひらサイズだった。あつらえたように、その銃は少年の三蔵の手になじんだ。
―――この銃なら、すぐにこめかみを射抜ける。
三蔵はそう思った。
自分が光明の死に泥を塗るような失態をしでかした時には、迷わずにこの銃で額のチャクラを撃ちぬける。
そう思うと、三蔵は嬉しくなったのだった。
――俺の覚悟のような、もの、だ。
俺は俺以外の何者も信じない。そして俺自身のやり方で生き抜く―――。
三蔵は人生の早い時期で、そう己れの信条の決意を固めていた。
誰に言われたものでもなく、三蔵が自らそう望んでいたことであり、それは誰にも止められなかった。
そしていよいよ寺を出る時、僧侶の黒衣に身を包んだ三蔵の肩の上に、布で見えないように高僧は「魔天経文」の経文をかけた。
ずしり、と肩が少しも重くないのに重く感じられた。
これを守るためにお師匠様は―――そう思うと、肩の上に荷がかけられたようだった。
「では、行ってまいります。」
一言そう言うと、三蔵は金山寺を後にした。片手をあげると、後も見なかった。
托鉢僧の身なりで、三蔵は山道を今歩いている。
と、滝があった。
三蔵は一休みするために滝壷のそばに腰をおろした。
寺を出てから、まだ肩の「魔天経文」を狙う妖怪には出くわしていない。
妖怪たちは、高僧らの話によれば、最近凶暴化しているという。
「牛魔王の蘇生実験のせいらしい。」
とだけ、三蔵は知らされている。しかし、誰がどんな目的でそうしているのかは、まだ三蔵は知らなかった。
と、滝壷のそばに、椎の木の切り株が立っているのが見えた。
ほんの出来心だった。
――試し撃ちしてみるか。
まだ三蔵は銃を撃つような危険な事態には遭遇していなかった。たとえ一度も撃ったことがなくても、使えるさ。――そうたかをくくっていたのだが、それは考えれば危険なことだった。
三蔵は立ち上がると、椎の切り株に向かってピストルを一発発射した。
ズギューン。
木立の中に銃声が響いて、森の鳥たちがばさばさと驚いていっせいに飛び立った。
銃は小さいくせに、思ったよりも反動が強かった。弾は三蔵の目がけた的から見事にそれた。三蔵は軽く舌打ちした。
「チッ。」
三蔵はたて続けに二発撃った。腕がしびれた。こんなものが当たらないなんて、と思った。
あまりたくさん弾を浪費したら、また何処かの露店商で弾を仕入れなくてはならない。
そう思ったが、当たらないようでは話にならない。
そのまま続けて撃った。見る見るうちに五発全部を使い切った。
バラッと薬きょうをリボルバーから落とし、三蔵は次の弾を僧衣から取り出して注意深くこめた。
―――次は絶対に当ててやる。
と、その時三蔵の背後に立つ人影があった。
「坊主、そうして撃つんじゃない。もっと脇をしめないとな。」
ザッと音を立てて三蔵は反射的に後ろを振り返った。男だった。耳元を目ざとく見る。
―――妖怪じゃない。
男は角のような耳ではなく、普通の人間だった。三蔵は思わず小さく安堵した。
「誰だ、あんた。」
「名乗るほどのもんじゃないが、子供が撃つもんじゃないし、坊主が撃っていいもんでもないな。」
男は背が高く、頭に見慣れない形の帽子をかぶっていた。カーボーイハットだと後にわかる三蔵だが、その時はわからず、直感的にこいつは「西」から来たヤツだと思った。黒髪で目が青かった。そして頬に古いギザギザの傷が斜めにあった。
――異国から来たヤツか。
三蔵は思い、男に銃を向けた。
「帰れ。あんたには関係ない。俺には俺の理由があって、今銃を撃った。」
「なるほど。しかしそんな撃ち方で撃たれちゃ困る。貸してみろ。」
お節介なヤツだ、と三蔵は思い、どなった。
「なんであんたなんかに、俺がかまわれなくちゃならねぇんだ!」
と、三蔵が思う間もなく、男は三蔵の後ろに立ち、優秀な先生のように三蔵の腕の上に両腕を上から重ねた。太く、がっしりした腕だった。男は三蔵に言った。
「もっとしっかり握れ。撃つ先をよーく見るんだ。ただの切り株だな。最初はそれがいい。人間だと思うな。切り株の上にリンゴが乗っていると思うんだ。」
「リンゴ?」
「ウィリアム・テルは自分の息子の頭の上のリンゴを撃った。そう思うんだよ、ボーイ。」
「うるせぇ。」
三蔵が言うと、男は厳しい声で叱咤した。
「男なら無駄口をたたくな。しっかりと構えろ。劇鉄の上を目標に重ねて狙うんだ。」
三蔵はむかっとしたが、男が自分をどうこうするつもりはなく、本当に教えるつもりらしいと思うと、素直に従った。実はなんにも知らないのだ。
「よし今だ。撃て!」
男が言った瞬間、三蔵は引き金を引いた。
轟音が走った。今度は銃は切り株の上に見事に命中した。三蔵は自然と笑みがこぼれてつぶやいた。
「やった。」
男は三蔵の肩を軽くたたいて言った。
「ビギナーズ・ラックってやつだ。しかしその調子でがんばれ。そうだな。最初は空き缶か何か目印の目標を置いて、練習するといい。」
「あんた、親切だな。」
三蔵が言うと、男は肩をすくめたように言った。
「おいおい、今頃私に礼を言うのか?さんざん俺に向かって憎まれ口をたたいた後でか。まったくボーイは礼儀ってものを知らないな。それにしても僧侶の子供がピストルを撃つ姿はここに来てはじめて見たよ。まったく、東にはいろんなものがある。」
「なんだそのボーイ、ってのは。」
三蔵が尋ねると、男はははは、と明るく笑って答えた。
「小僧という意味さ。」
「なんだとっ。」
「怒るなよ。私のいた国の言葉なんだ。しかし君はまだ少年じゃないか。」
そう言うと、男は軽く口笛を吹いた。林の木立ちの中から、一頭の馬が現れた。寺院で馬の世話をしたこともあった三蔵は、ひと目でわかった。馬はよく飼いならされていた。男は馬にまたがった。男は馬上から三蔵に言った。
「ではボーイ、殺傷はほどほどにな。坊主が銃を撃つのは、やはりあんまりいいことじゃない。まあ危険な輩にも出会うだろうがね。では、アデュー。」
男はさっそうとギャロップで林の中を駆けて行った。
「なんだ、あいつ・・・・。」
――変なヤツ。
三蔵は思った。しかし、銃がうまく撃てたのだから、いいヤツだったのには違いない。
「よし。がんばるぞ。」
三蔵は手の銃を見て、一言つぶやいた。
なんだか今日はついてるみたいだぜ。―――そう思った三蔵だった。
銃を腰におさめると、錫杖を手にし前に歩き出そうとした、その時だった。林の茂みからダミ声がした。
「おい坊主、いい銃持ってるじゃねぇか。」
「坊主、その金目の物をこっちに寄越しな。」
「断る。」
「なに?てめぇナマ言ってんじゃねーぞ。」
三蔵は気がつけば、大勢の男たちに取り囲まれていた。
やはり、妖怪ではないが、男たちがならず者であるのはすぐにわかった。
三蔵の所持している銃や、金品を狙って集まって来ているのだ。
このような追いはぎは、妖怪への負の波動が強まって以来、多くなってきているとは聞いていたが、人間で会うのはこの時がはじめてだった。しかし三蔵は男どもを負けずににらみつけた。
――これは仏罰だ。死ね。
三蔵は銃を撃とうとしたが、やはり初心者の悲しさで、背後から男の一人に飛び掛られ、その手を押さえられた。ほかの男が威勢よく叫んだ。
「おいおい、早速のしかかりやがったぜ。」
「ひゃっほう、こいつはいいぞいいぞ。」
全員が野次を飛ばした。男の一人が喝采を叫んでいる。
三蔵は男に必死で抵抗した。爪をたてたりしたが、それはかえって男を煽る結果になったようだ。男が叫んだ。
「へへへ、手荒にやるぜ、こいつはなかなかの山猿だ。」
ビリッと音がして、三蔵の黒い法衣の裾が破れた。三蔵の白い脚が太ももまであらわになった。男の一人が、その動く太ももに釘づけになったらしい。
「おい、その小僧をこっちによこせ。」
ひげづらの大男だった。だらしなく目元がゆるんでいる。三蔵の上の男が言った。
「またそいつか。」
ひげづらは言った。
「へへへへ、こいつ女みてぇなツラしてっからよ。しっかり押さえてろよ。」
「へいへい、仕方ねぇな。じゃあまずあんたのデカいもので御開帳させてくださいよ。」
「その後おまえたちも楽しむのか。」
「ああ、死んでなけりゃな。」
「おめぇ、死んだほうが締まりがいいこともあるんだぜ。」
「えっへへへ、そうか。こいつまだ小さいからな。そうかも知れねぇ。」
ひげづらと男は交代した。三蔵の上にずっしりとしたひげづらの体重がのしかかった。
三蔵は男どもが野卑な冗談を言っているのを聞いていて、これから自分に何が行われるのか、漠然とわかってきた。三蔵のいた寺はもちろん女人禁制であったが、それが下級僧の間ではかえってこの手の猥談の入り込む温床ともなっていた。三蔵も師匠である光明の「稚児僧」であるとの噂がたっていることもあったのである。無論、三蔵と光明はそのような関係には少しもなかった。
従って、この時の三蔵の心境はただ、驚愕と恐怖のみであった。話に聞いていた、「犯される」ことが実際に自分の身に起きようとしている。それも最悪の形で―――。
三蔵の喉元に、刃渡りが5センチほどもあるアーミーナイフがつきつけられた。まだ三蔵は銃を握っていたが、腕は思うようにならないひげづらの腕の下にあった。
「さあ、坊主口を開けるんだ。おめぇのかわいい口で俺のものをくわえてみろ。」
「い・・・や・・・だ・・・・。」
「なんだと?できねぇってのか?とんでもなく高慢ちきな小僧だぜ。寺の小坊主なんてのは、みんな影で後ろの門じじいの坊主どもに売ってんだろ?俺は知ってるんだぜ。おめぇ、まさかやり方を知らねぇなんて言うんじゃねぇだろうなあ。」
三蔵は続けさまに激しくひげづらに顔をぶたれた。唇が切れて、鼻から血が染み出した。自分の意思とは逆に痛くて涙が出た。くやしかった。犯されるのも嫌だが、力で乱暴に屈服させられるのが、たまらなく不愉快だった。
男の手が三蔵の法衣をはだけた。黄色い歯で、ニヤニヤ笑っている顔が間近に迫ってきた。吐き気がした。
その時、男の一人が抑えている手に、少し隙ができた。このゲームに夢中になって、わずかに気を取られたらしかった。三蔵は手首をひねった。銃を素早く返して、さっきの男に言われた要領で撃った。瞬間、紫暗の瞳が燃えて、すさまじい気迫だった。
ガウン。
男の一人が叫び声をあげた。
「こいつ、撃ちやがった。」
三蔵にのしかかった男は、頭蓋骨から脳漿を飛び散らせて、目玉をぽろりとこぼした。三蔵は総毛立った。はじめて人が銃ではじけるのを見たのだ。それは身の毛のよだつ光景だった。男はガクン、と三蔵の上から地面に転がった。死んだ――死んだのだ、自分が殺したのだ。
しかし、躊躇している間はなかった。間髪を入れずに三蔵は周囲に向かって発砲した。
「て、てめぇっ。」
男たちが後ずさりした。男たちは頭をかかえて逃げ出した。
「おぼえてろよっ!」
捨てゼリフを叫ぶと、男たちは三蔵から遠ざかって行った。
三蔵の前には、ひげづらの死体が白い脳漿を流しながら伸びていた。三蔵はじっとそれと手に持つ銃を見比べた。
――俺が、殺した。
この銃で―――。
――私は、あなたにもそれを守れとは言いません。でも、あなたは大きな人生を歩むことになると思いますからね。
光明の言葉が脳裏によみがえった。
仏道は不殺生―――三蔵はそれを朝夕の勤行で、金山寺で叩き込まれていた。自分はたった今その殺生戒を犯した。
――お師匠様・・・・・俺は・・・・。
三蔵はその時、深い虚無感にとらわれていた。
旅の間中孤独だった。自分は結局、捨てられた小犬のように実は金山寺から放遂されたのだ。飲まず食わずで何日も歩かなければならないこともあった。
自分が今まで生きてこられたのは、自分の力だけではなかった。
こんな事を続けろと、寺の高僧は俺にあの時言ったのだ。俺に拳銃を渡すというのは、そういうことじゃないか。―――――。
三蔵の頭に突然、その言葉がひらめいた。
――俺は、いらない人間なんだ。
もともと捨て子だったんだ。俺なんかいなくなったって・・・・俺なんかを生かすためにお師匠様は大切な命を落としたんだ。俺が悪いからだ。俺が弱くて、どうしようもないから・・・・。
チャキ。
三蔵は自分の耳の上に拳銃の銃口をゆっくりと押し当てた。その瞳は何も映していず、もはや虚ろだった。三蔵の心は暗い虚無感に満たされていた。
そのまま引き金を引こうと指を曲げようとしたが、怖くて体が震えた。とめどなく目から涙があふれた。みじめだった。
こうやってこの地上の片隅で、人を殺して死んでいく俺を、御仏は憐れんでくださるのだろうか。もし天上に神がいるのであれば―――この俺を、この死の淵から救って・・・・・。
その時だった、あの男が現れたのは。
男はその大きな手で三蔵の手から銃を叩き落とした。
「よせ!」
三蔵は声もなくその場に倒れた。
「気になって、とって返してみたんだが・・・悪い冗談だ。死に急ぐなどとは。」
さっきの男が息をきらして三蔵の目の前に立っていた。
三蔵は泣きながら男に言い募った。
「だって俺・・・・殺したんだ。師匠も俺のために死んだんだ。俺なんか、いなくなったっていいんだ。」
「馬鹿!お前のために死んだんじゃない。誰だって自分の命は自分のものだ!その命を自分で奪うなどというのは、愚の骨頂だ。おまえは何のために生きているんだ。」
「じゃあ、俺は何のために生きているんだ。俺のために、みんな死ぬ。死んでいく。俺は疫病神なんだ。だけど・・・俺は自分をとめられない。俺が生きていくために・・・。」
「しっかりしろ。死にたいなんて思うな。さあ。」
男は中腰になり三蔵に背中を見せた。
「乗れ。私のキャンプまで背負っていく。」
三蔵はしばらく呆然と男の背中を見詰めていたが、やがてのろのろと男の背中に身を預けた。男の背中は固く、ごつごつしていた。三蔵は言った。
「あんたも・・・あんたもさっきの男たちのように・・・。」
男は三蔵を背負い、地面に転がっている三蔵の錫杖と銃を拾うと、吐き捨てるように言った。
「私がそんな事をするか!ああいう輩は私は大嫌いだ!」
その言葉を聞いたとたん、三蔵の両眼から涙があふれた。
「俺・・・怖かったんだ・・・・。」
自分がみっともないと思う気持ちもあったが、三蔵は声を殺して肩を震わせた。誰かにこの自分の辛さをわかってほしかった。男は気の毒そうに言った。
「・・・・もう泣くな。お前の後ろに倒れている男は、天罰を受けたんだ。そう思うんだ、ボーイ。」
「あんた、名前は?」
「私の名前は・・・そうだな、ゼロとでも名乗っておこう。『無』という意味だ。インドの天竺でバラモン僧たちは『無』の概念を知り、それが私のいた国にまで伝わった。仏教は偉大な教えだ。お前の殺した男も今『無』に帰った。『無』とは何もない状態だが、これから何かが生まれ出る状態でもある。それでいい。そう思え、ボーイ。」
三蔵は男の背中の上で無言で涙を流した。男の声は低く、その教え諭すような言葉は三蔵には確かな響きとして伝わってきた。それはあの優しかった三蔵の師光明にも、三蔵が見出しえなかった何ものかであった。
三蔵とゼロは、渓谷の中に立てられた小さなテントのそばにたどりついた。テントのそばには、馬が戻って草をはんでいた。三蔵は「もう大丈夫だ。」と言ってゼロの背中から降りた。
「今日は私と一緒に泊まっていくといい。町まではずいぶん距離がある。まださっきの連中がうろうろしているかも知れん。」
と、ゼロは言った。三蔵は同意した。
谷間に水を汲みに行ったり、夕飯の支度をしながら、三蔵はぽつりぽつりと自分の身の上を話した。どうして自分が一人で歩いているのか。何故自分は僧侶なのか―――ゼロは三蔵の身の上話をじっと聞いていたが、やがてこう言った。
「おまえは、じゃあ、運命に選ばれたんだ。」
「運命?」
「そうだ、運命だ。神とは言わん。神と言ったら、語弊がある。おまえには試練が与えられたんだ。その額の印はそういうことだ。」
「御仏が・・・。」
ゼロは三蔵が言いかけると、溜め息をついて言った。
「御仏とは思いたくないな。俺は貴様のいた寺の連中は、うさんくさい奴らだと思っているんだ。」
三蔵が鼻白んだ顔になると、ゼロは煙草をポケットから取り出して口にくわえた。二人は今、夕飯を前に焚き火にあたっていた。ゼロは言った。
「いいか。考えてもみろ。貴様の寺では、人を殺してはいけないと教えている。しかし、貴様には銃を渡して、自分の身は自分で守れ、と言い渡して旅に出した。確かにその、天地開元経文とやらは大切なものなのだろう。しかし、何故貴様一人でやらないといかん。貴様は、はめられたんだ。その寺の坊主どもにな。貴様は人がいいから、そう見抜けなかったのだ。」
「でも、俺が自分で取りに行くって約束したんだから。」
「だからそれだ。貴様が自分でそう言うように仕向けたんだよ。みんなの前でな。」
「そうか・・・・俺、だまされたのか。」
「うーむ、そうだな。しかし貴様の師匠という人は、本当に経文を守るために命を捨てたのだから、その経文がないのは困ることなんだろうな。問題は、師匠以外の人間たちだ。彼らは、おびえるだけで、何もしようとしないように俺には見える。」
「・・・・・・。」
「まあこれは部外者の俺の意見だ。何にせよ、そういう無責任な連中に囲まれて育ったお前は、不幸だったと俺は思う。お前にその光明という師匠がついていたのは、幸いだった。その背中の『魔天経文』は使えないのか?」
「え?」
「さっき何か呪文を唱えると、マジックが起きると言ったな。見せてみてくれないか。」
三蔵はためらった。その呪文は、妖怪にしか使ってはならないと教えられていたのだ。
その頃の三蔵は、本当にまだ寺で習ったことを純真に信じていた。
三蔵はしかし、意を決して唱えてみた。それまでだまされていたとなると、気が気ではないからだ。
「――魔戒天浄!」
しばらく沈黙があった。ゼロは膝をたたいて笑い出した。何も起こらなかった。三蔵は真っ赤になってつぶやいた。
「それは――きっと、あんたが妖怪じゃないから・・・・。」
ゼロは手をあげて言った。
「わかったわかった、お前を追い詰めるのはやめよう。その経文は偽物じゃない。きっと俺が妖怪じゃないからだ?」
「そっ、そうだ。」
「うん。それとも、お前の法力が足らないせいかも知れないぞ?私の国の魔法使いの間では、よくある話だ。もっと鍛錬すれば、使えるようになるかも知れないぞ。」
「そうかな。」
「ああ、きっとそうだ。旅を続けるんだな。たとえ理不尽なものにしても、おまえはおまえの道を自分で切り開くんだ。」
「うん・・・・・。」
三蔵は手に持ったカップをじっと見つめた。手の中のカップは暖かかった。人のぬくもりがこんなに恋しいと思ったことはなかった。三蔵は言った。
「あんたはなんでこのあたりを旅しているんだ?西から来たと言っていたが、天竺よりも西なのか?」
ゼロは笑った。
「そうだ、天竺よりもずっとずっと先だ。その先にはおまえの思いも寄らない場所があるんだ。ここは桃源郷と呼ばれているそうだが、西から流れた品物がずいぶんあるな。おまえのその銃もそうだ。」
ゼロはそう言うと、遠い目をして言った。
「私もそうだ。西から流れてきたんだ。私は故郷の村にいたんだが、そこで妻と息子を―――ちょうど三蔵、おまえぐらいの年齢だった。殺されたんだよ。妖怪の男にな。男の名はマンダリン・Mと言う。腕に十字架と蛇の刺青をしているんだ。逃げていく時に見たんだ。」
「奥さん・・・いたのか。」
「ああ。マンダリンにレイプされた。」
「――!」
「だからだ―――さっきみたいな事態が俺には我慢がならないのさ。さあ俺の話は終わりだ。俺はマンダリンを追ってここまで来たんだ。」
三蔵の目が光った。三蔵は言った。
「そいつ・・・・殺すのか。」
「ああ。妻と子供の仇だからな。私は、人道的な男ではないんだ。奴は妻の腹を刃物で引き裂いた。妊娠していたんだぞ。そんな男を許せると思うか?おまえの信じる仏道では許すように教えるのだろうが―――。」
三蔵はかぶりを振ってゼロに答えた。
「俺・・・・あんたの思っているような人間じゃないぜ。さっきは驚いたけど、これからはあんたみたいに、殺すよ。悪い奴は全部。そうする。そうしなけりゃ生きていけない。」
「ボーイ。」
「ありがとう、あんたに会えてよかった。俺はこれから銃を練習してうまくなる。そして、悪い奴らをやっつけるんだ。俺の生きていく先で邪魔になる奴を―――。」
三蔵は微笑んだ。ゼロはその顔をじっと見つめた。
「強くなったな、ボーイ。」
ゼロは思った。
―――はじめて会った時から、その瞳は純粋に輝いていた。修羅か羅刹のようではあったが、彼の魂は純粋なのだ。―――願わくば、清くあれ―――あの泥に咲く薄桃色の蓮の花のように・・・・。
ゼロはそう思ったが、口に出しては言わなかった。
その代わり、ゼロはこう言った。
「おまえは三蔵法師だが、この世に降りた不動明王かも知れないな。」
「不動明王?」
「そうだ。暴悪な神だ。悪者をこらしめる正義の神だよ。知らないのか?」
「俺・・・・そんなに強くないよ・・・。」
食事を終えた三蔵はうとうとと寝入った。ゼロは三蔵に毛布をかけてやった。
次の日、谷間を降りた砂漠への入り口が、二人の別れ道だった。
三蔵はゼロに問うた。
「ここを、渡るのか?」
「ああ。おまえは町への道を下るといい。砂漠はまだ早い。足がないとどうにもならん。」
ゼロは馬上からそう言うと、手を振った。
「ボーイ、いつかまた会おう。天がそう望んだならな。神は遍在している。仏もまた、そうだ。そして私の心もまたそうだ。いつもおまえとともにある。」
「偏在?」
「空気のように、見えなくとも存在しているということだ、ボーイ。では、さらばだ。」
ゼロは馬を駆った。
そうして砂漠を歩いていくのを、三蔵はゼロの姿が点になるまで、じっとそこで立って見送った。
不意に涙が出た。三蔵は両手を口にあてた。どうして自分がそんなことをするのかわからなかったが、それは衝動的に三蔵を襲った感情だった。
「ゼロ!俺はあんたのことが好きだ!」
三蔵はゼロに向かって声の限りに叫んだ。この声は聞こえない。もうおそらくは二度とは会えない。会うこともない・・・。
自分を死の淵から救ってくれた人―――そして、風のように去っていった人・・・・。ゼロ、あんたのことは忘れない。たった一晩限りだったけど、あんたと過ごした夜のことは俺は二度と―――。
それが玄奘三蔵の、子供時代との別れの瞬間であった。
月の桂


