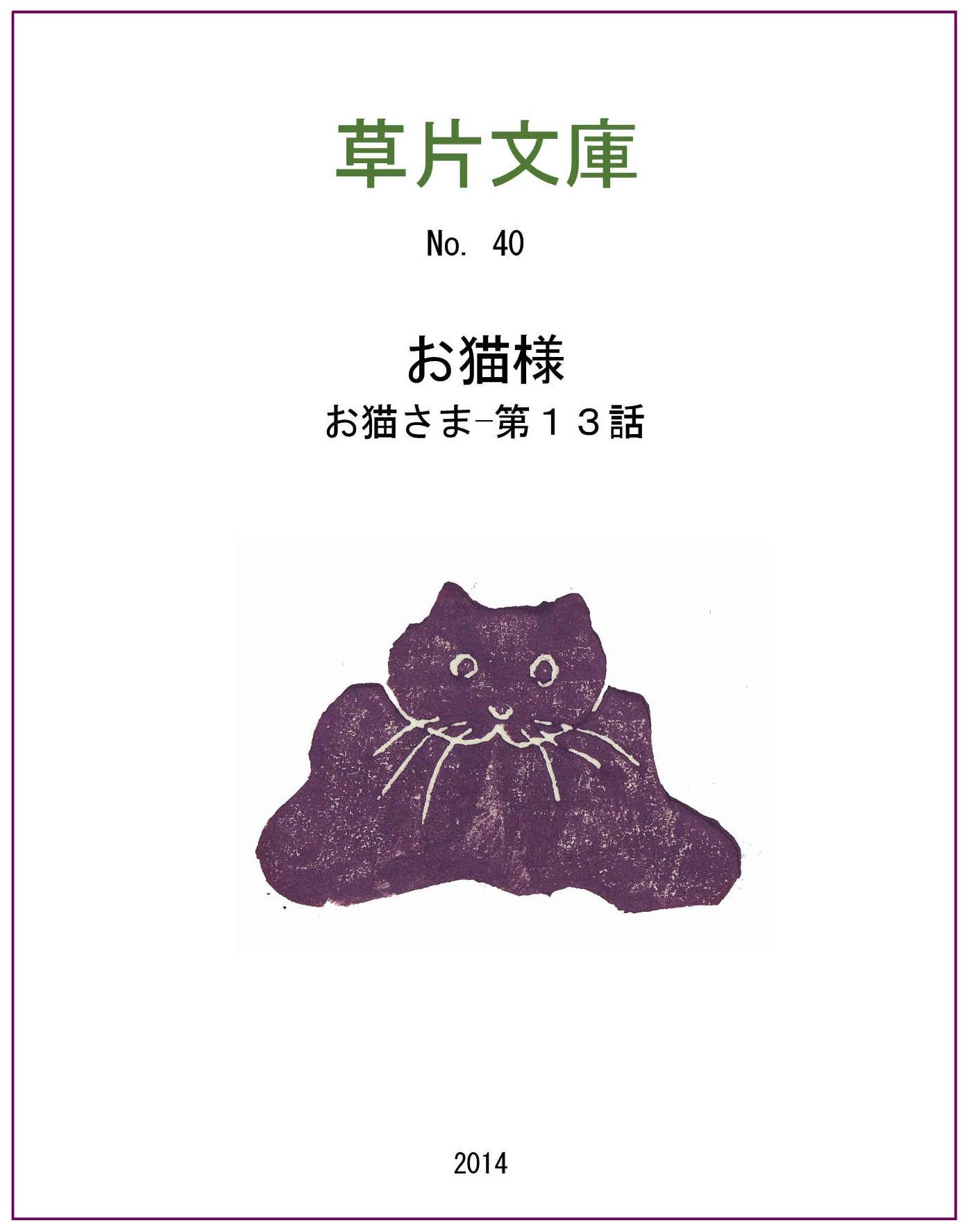
お猫さま 最終話 - お猫様
山寺の和尚さんは、鞠は蹴り足し、鞠はなし、猫を紙袋に押し込めて、ぽんとけりゃ、にゃんと鳴く、にゃんがにゃんとなくよいよいよい。まっこと面白い歌ですな。古くからあった文句をもとに、久保田宵二という人が書いた歌詞でございます。こういうのを、ナンセンス詩の類と申すのでしょうか。猫は袋に入りたがる。猫は丸くなる、鞠みたい。てなところから、余裕のある想像力のある人が、思いついた詩でございましょう。猫をいじめているのではないのですな。面白いだけでいいわけでございます。猫は面白い。本当に面白い動物でございます。想像力が豊かな動物です。遊びの名人です。あの、人生、いや、猫生の豊かさを、人は学ばなければなりませんな。
「玉や」
和尚さんが、縁の下に隠れていた猫を引き吊り出しますと、袋に詰め込んで本堂につれてまいりました。
袋の中で、猫の玉はゴソゴソと外にでようといたします。
和尚さんが、袋の口を結んでいた紐をはずしますと、玉が勢いよく飛び出してきます。
和尚さんは年の割には機敏に、玉をつかまえると自分の目の前におちゃんこをさせまして、お説教をはじめます。
「玉、いいか、鼠はとるでないぞ、鼠にも家族がある」
と申しますと、玉は器用に人の言葉で返答いたします。
「ふん、くそぼうず」
ひどい口をききます。
「玉、おまえは三毛猫、三毛猫と言えば雌、子供を育てるのにそのような口のきき様はいけません」
玉はきょろとした目をして、
「へい、そうかい」
「また、そんな返事をする、はい、和尚さま、と言いなさい」
「はい、和尚さま、昨日、後家さんになったばかりの若い奥さんに般若湯を飲ませて、なにをした」
「なにを言うのかい、この猫は。覗き見をするとは何という了見じゃ」
「あたいがいるのに、はじめたのじゃないか、生臭坊主」
和尚さん、返す言葉がありません。
「その辺の猫はみーんな知ってるんだ、あたいを大事にしないと、みんなに言ってやる」
「脅かすとは不届きな猫じゃ」
「不届きか、不行き届きか、知らないが、あたしゃおいしいおまんまにありつけるならなんでもするさ」
「捨ててしまいますよ」
「捨てられるのかい、どこに捨てても、あんたのことはみーんなに知られちまう、猫はどこに行っても許される。横町の大家の娘は大工の八公をひきずりきこんで、ねんごろさあね、と大家のぶちが言ってたぞ」
「あのぶち猫も雌じゃろう、何というひどい雌猫たちなんだ」
「大家の娘は、和尚さんの種だって、前ここにすんでいた黒猫が言っていた」
「なんと、猫という奴は、かわいい顔をして、みんな覗き見をしているのか」
「おや、人聞きの悪い、いや、猫聞きの悪い、だから言ってるじゃないですか、あたしらがいるのに、無視して悪さしてるのじゃないか」
「まったく、ひどい猫を飼っちまったんだろう」
「こっちの言うせりふさね、なんとけちで嘘吐き坊主のところに居着いちまったんだろ」
「それでなにが望みなんだい」
「あたしゃ、お城にすんでみたい」
「どこのお城のことじゃ」
「あたりまだろう、名古屋城だ、猫好きの姫がいる」
「馬鹿なことを言うんじゃない」
「どうだい、大奥で聞いたことをみんなあんたに教えてやるが」
「そりゃ、どういうことだ」
「あんたが、その情報を売ればいいんだ」
「恐ろしい三毛猫だ」
そんなある日、和尚さんが猫を探しています。
「玉や」
縁の下から鼠をくわえて玉がでてきました。
「また、鼠をとったな」
玉は鼠を床におくと、
「猫は鼠を捕るために飼われているんだ、捕ってどこが悪い、あんたのとこの餌より、鼠の方がずーっと旨い」と悪態をつきます。
「なー玉や、越後屋の奥さんが、大奥に連れていってくれるが、行く気はないか」
「あの、後家さんか」
「これ、もっと、おしとやかに言いなさい、大奥ではそんな言い方ではやっていけませんよ」
「越後屋の後家が大奥に知り合いがいるのかい」
「越後屋さんは名古屋でも一、二を争う呉服屋さんですよ、大奥のお女中さんの着物を一手にお納めしているのです」
「ああ、わかった、それでどうしてあたいを大奥に連れてってくれるんだい、なにかしなきゃいけないことがあるんだろう」
「おまえは悪い猫だが、頭がよいのう、そうじゃよ、大奥の出来事を機会があるごとに越後屋さんに教えるのじゃ」
「そりゃ、あたいが言ったことじゃないか、ゆすりの種を探して、ずーっと越後屋で着物を作らそうというのだな」
「そんなに、はっきりいうものではない」
「そりゃ、あたいはいいよ、もっと旨いものにありつけるわけだ」
「南蛮渡来の雄猫もいるそうだ」
「そりゃ、会ってみたいね」
「それじゃ、さっそく、越後屋さんに行くか」
和尚さんが支度を始めると、玉は自分から袋の中にもぐりこみました。
和尚さんは袋を抱え、越後屋さんにお出かけです。
「もっと丁寧に運びな」
玉が文句を言います。
「なに言っとんだ、もう少しだ、がまんしなさい」
越後屋さんに着くと、和尚さんは玉を袋からだして、胸に抱きかかえます。
玉が和尚さんの顔を見ます。
「気色わりい、いつも首を摘んで吊るすじゃないか、体裁ぶちやがって」
「今奥さまが来るから静かにしなさい」
「何だ、あの後家さんだろ、ここだと奥さまか」
「そんな口を利くのではない」
「なに言ってんだい、これからやろうということを棚に上げて」
そこに、越後屋の後家さんが、いや奥さまが入ってまいりました。
「和尚さま、お待たせいたしました、いつもの客に反物を選んでおりました」
「いや、繁盛でよろしゅうございます、ところで、話をした猫を連れて参りました。頭の良い三毛猫ですので、大奥へお連れになりましても喜ばれると思います」
奥さまが玉を見ますと、玉はしなを作って奥様のそばにより、足にこすりついて膝の上に上がろうとします。裾が乱れて綺麗な白い足がちらっとのぞきます。
「ほんに、かわいい猫ですこと、よく慣れていて、これなら、姫さまも喜ぶでしょう」
和尚さまは、この猫かぶりめと、玉を見ますと、猫かぶりではなく猫だと、玉の目が申しております。
「差し上げますので、かわいがっていただければ幸いでございます」
「はい、ありがとうございます、何かお礼を」
「いや、いつの間にか寺に居ついた猫で、美味しいものを食べさせてやりたいと思っておりました。そうなれば私はもうそれで十分でございます」
「お優しい和尚さまですこと」
玉は口のうまい坊主だと、目で語っております。
奥さまが奥に声をかけます。
「すぐお酒の用意をしておくれ」
お酒が運ばれてまいります。
「和尚さまと大事な話があります、呼ぶまで誰もこないように」
意味深長なことを言って女中を返します。
「和尚さま、どうぞ」
酒をもって、奥さまが和尚さまの隣にすわります。
和尚さまは玉を見ると、小声になって奥様に言いました。
「いや、奥さま、今日の夜にでも寺のほうに」
玉は奥さまの脇で丸くなり、「聞こえてるで」、と和尚さまを見ます。
「和尚さま、お体の具合でもお悪いのではございませんか」
「いや、至極元気で」
和尚さまがそう言いますと、玉が立ち上がり、すーっと、襖の前に進みます。
「おや、外に出たいのかしら」
「小便でございましょう、外に出してやらないと」
「大奥では部屋の中に猫の厠がございます、そこでするようここで教えておきましょう」
「すぐ覚えますから、大丈夫でございますよ、今は出してやってください」
奥さまが襖を開けますと、玉が勢いよく廊下に飛び出ました。
奥さまが「出口を教えましょう」と外に出ようとするのを、和尚さまは「猫は鼻が良いので大丈夫でございますよ、さあ、猫のいない間に」と奥さまを引き止めます。
玉は勝手にお勝手に行きます。鼻が良いことは大変便利です。初めての家でもご飯の匂いがするところに行けば勝手があり、土間に降りれば、そこにいる誰かしらが戸を開けてくれます。
さて、玉がいなくなった客間では、玉が思っている通りのことが行われ、ことがすんだ頃に、玉が戻ってまいりました。
玉が襖に手をかけてかたかたと揺らしました。
奥さまが襖を開けます。
奥さまは乱れた髪をかき上げながら、
「お利口な猫ですこと」と玉の頭をなでたのでございます。
こうして、あたいは名古屋城の大奥に飼われることになりました。
大奥では姫さまが何匹もの猫を飼っていらっしゃいました。三毛猫はすでに二匹もおりまして、あたいで三匹目でございます。
あたいはお城では美美と呼ばれることになり、どのお女中にもこすりついてゴマをすりました。
姫さまの名前は桃姫といいました。もう一八にもなるのに男に全く興味がありません。これにはお城の殿さまと奥方さまは安心半分、心配半分で、どうしようか迷っていたのでございます。
桃姫さまがお座りになられると、その周りには猫たちが集まります。
姫さまの一番そばによる猫は決まっておりました。南蛮渡来の銀色の毛の長い狸のような猫でした。いつもお女中さんにからだを洗ってもらっています。その猫が、お姫さまの膝の上にいつもいるのでした。前からいた二匹の三毛猫は何とかお姫さまのそばに行こうとしているのがよくわかります。
「馬鹿な三毛猫」
あたいは言葉には出しませんがそう思いました。
ほかにもいろいろな色の猫がいました。雄の猫もたくさんいましたが、なかでも青っぽいしっかりした黄色い目の雄猫は格好いいと、思いました。
その猫は仏蘭西という国からきた猫で、シャルトルウとかいいます。江戸のシャラクのような粋な名前です。お姫さまの膝の上の銀色の雌猫はペルシャとかいうようで、生意気そうですが、その猫も、他の雌猫も、みんなその仏蘭西猫に言い寄られたいと思っているようでした。
あたいは、おとなしく一番後ろにいて、身繕いをしたり、ちょっとばかり鳴いてみたり、新参ものらしくしておりました。
ある日、桃姫さまが、あたいを抱きあげて、
「市松模様の綺麗な三毛猫、目が大きい、なかなか良い顔じゃ」とおっしゃったので、姫さまの顎のあたりにこすりついてやりました。いい匂い。
あの雌のペルシャがひしゃげた顔であたいを見ていました。
雄猫もまだまだいました。シャムとかいうところから来た雄猫は喧嘩っ早くて、すぐ引っ掻くし、勝手で、桃姫さまの言うことも余りよくきかないようです。ただ、目は青く精悍で、見ている分にはよい猫です。
そんな格好いい雄猫の中で、いつも隅で、どんよりと座っている垢抜けない黒虎の雄猫がいました。ところが、だんだんわかってきたのですが、そのぶくっと太っている雄猫が、どうやら、大奥の内情を一番よく知っていて、仲良くなっておくほうがよいようです。年をとっているのですが、周りをよく見ていて、桃姫さまもたまに頭をなでにわざわざ黒虎のところに行きます。そうすると、黒虎は大きな頭を下げて姫さまを見上げてにゃあと鳴きます。そのしぐさが爬虫類のようで変に可愛いところがあるのです。
あたいはあのシャルトルウをものにして、黒虎をたてて裏を知ろうと思ったわけです。
「黒虎の旦那、今日は桃姫さま機嫌がいいねえ」
「おや、美美さま、ここで、あたしのことを旦那、なんて呼ぶものはおりませんな」
「いやかえ、黒虎の旦那」
黒虎はへへへと笑うと、
「実はな、こんなとこ面白くもねえけどな、何せうめえもんが喰えるからいるんだ」
美美に打ち明けました。
「それで、旦那どうやって大奥にきたんだい」
「へへ、忍び込んだんだ、追い出されるところだが、姫さんが庭に散歩にでたときに、よろよろと前にいって、とてっところがったのさ、したら、姫さん、猫が死にそう、なんとかしなさいって、お供の者にいいつけて、それからずーっとかわいがってもらってるってわけさ」
「上手だね」
「お前さんだって、どうしてはいったんだ」
「寺の坊主をおどかして、呉服屋のおかみさんにすりよったというわけさね」
ことの次第を話しました。
「ふーんやり手だね」
「ところで、あのプルシャとか、ペルシャとかいう娘、やだね」
「ありゃ、どうってことはない、南蛮渡来のお嬢さんだ、単純さ、それより、日本の雌猫たちゃあ、頭は悪くなさそうだが、じめじめしてやだね、お前さんみたいのはめずらしいよ」
そこへ前からいる三毛猫がやってきました。
「おほほほほ、お二人さまお似合いで」
「はい、菊さま、今、美美さまがここの三毛猫のお姉さんたちはまっこと美しいと申しておりましたですよ」
ふん、嘘ばっか、でもあたいには助かるけどね。この黒虎はなかなかの苦労人だが、それだけでなく頭が良さそうだ。
「それでは、黒虎さま、わたくしは、このお城の中を歩いてみます」
「ああ、美美さま、そうなさいましな、ところで私にも名がありまして、黒たんと姫さまに呼ばれております」
「おや、かわいらしいお名前ですこと」
あたいは笑いながら立ち上がったのです。
黒たんはあたいにウインクをして、三毛の菊と話を始めました。
あたいは廊下に出ると、ちょっと離れたお女中の部屋の襖を前足で開けました。
おやおや、まずいところにはいっちまったようで、お女中の福が男を引きずり込んでいやがる。坊主にいいみやげができた。気がつかないように襖を閉めると、台所にいってみることにしました。
うるさいばあさんが、おさんどんたちに、
「盗み食いをするんじゃなよ」
などと、言っています。
そのばあさんに擦り寄ってやった。
「おや、姫さまの猫がこんなところにきちゃあいけません。汚れますよ、おお、新しくきた三毛猫さま、美美さまでしたね」
あたいを抱き上げた。この口うるさのばあさんは相当の猫好きのようだ。
「なにかやりたいが、そんなことをしたらしかられますからな、でも美味しいものを美美さまに残してあげますよ」
みんなが話をしてくれない孤独なばあさんなのだろう。
そこで、あたいはにゃあと鳴いてしわくちゃのほっぺたに擦りついてやった。塩っから。
「お帰りなさいよ」
ばあさんはあたいを廊下に降ろしました。
あたいが姫さまの部屋に戻ると、姫さまは双六遊びをしていました。あたいは、そばによって、じっとみていました。姫さまがあがったとき、あたいもにゃあって、嬉しそうに声を上げたんだ。すると、姫さまは「おや、美美は頭がいいのじゃね」とあたいを抱き上げ、膝の上にのせました。そこで、あたいは思いっきり甘えて、膝の上で丸くなりました。
そのとき、いつも姫様の膝にいるペルシャは便所に行っていたのです。姫さまがそのまま双六に興じていると、ペルシャが戻ってきました。
ペルシャの名前は、白といいます。白はあたいが桃姫の膝の上にいるのを見ると、がむしゃらに、あたいを押しのけようと頭から姫さまの膝の上にあがろうとしました。姫さまは、「白、いつもお前がいるのだから、たまにはいいでしょう」と白の頭を押さえました。
ざまあみろ。
白はすごすごと、後ろに下がって、空いていた座布団の上で丸くなりました。
双六遊びが終わりになると、姫さまは膝の上のあたいを抱き上げ、のどをさすってくださいました。畳の上にもどされたあたいは思い切り伸びをして、幸せな欠伸をしたのです。
「かわいいのね、美美」と姫さまが笑窪を寄せました。桃姫さまはすごい美人ではないのですが、色が白くて、ともかく、賢い姫さまのようです。きっと何かお隠しになっています。そこは猫でなければ知ることができないでしょう、これからが楽しみ、本当に楽しみです。
ペルシャの白が私の脇をすり抜けて姫さまの後を追いました。そのときあいつは私の鼻先にあのふわふわの白い尾っぽを打ちつけていきやがった。きっと仕返しをしてやる。
さて、もう一度、お女中の福の部屋をのぞいてみますか。あたいはまた襖を少し開けました。もう男はいなくて、福もいません。あたいは中にはいると、衣桁の下に落ちていた紙の切れ端をみつけました。二つ折りにしてあったのが落ちたときに開いたようです。それをみますと、明後日、子の刻と書いてあります。ははあん、またあの男が来るのだなと想像がつきました。
その日になって、あたいはあらかじめ、その部屋の行灯の後ろで寝ていることにしました。そして案の定、男と一緒に福がはいってきたのです。あたいがいるなんて気が付きもしないではじめやがった。色は黄色いし、寸胴で、何でこんな女にこの男はくっついたのだろう。
男のほうは、なかなか凛々しい侍です。着物を見ると三柏の紋がついています。ことを終えると、袴をはきながら男が言いました。
「それじゃ、とりなしてくれるね」
福は名残おしそうに、着物をつけながら、
「いいわよ、徳さまの頼みだから」と答えている。
そういえば、福は奥の人事をまかされているのでした。
「なんだ、こんなところに、猫が寝てる」
徳さまと呼ばれた男があたいに気がつきました。あたいはぐっすり寝ている振りをしていました。福もあたいを見ました。
「桃姫さまの新しい三毛猫ね、美美っていうの、おとなしい猫よ、どうやって入ったのかしら、私たちのこと見られてしまったわね」
「猫にはなにもわからないでしょう、では福殿、私は参ります、くれぐれもよろしくお頼みします」
「まかせてください」
てなことで、あたいも、今目を覚ましたことにして、伸びをすると男の後をついて部屋を出ました。
男は人がいない場所を選んで、奥から出ようとしています。
一つの部屋の襖が開いて、寝ずの番のお女中、志乃が顔をだしました。運が悪いことです。お女中は男が歩いているのを見るとぎょっとして、声をかけました。
「どなたさまですか」
それが役目です。徳さまと呼ばれた男が振り返りました。
「畑中徳義さまではございませんか、今頃なに用に」
男はしまったと思ったのでしょうが、何食わぬ顔で腰を折り、礼の姿勢をとりました。
「ああ、これは志乃殿、こんな夜更けにすみません、今宵のうちに伝えよと、殿から仰せつかり、お言葉を姫さまに伝えて参ったところです」
「それは、ご苦労さまでした。勘定方がこられるとは珍しい、明日の桃姫さまのお着物のことでございますな」
姫さまのお楽しみは、お着物のようです。偶然にも明日越後屋が来るようです。
「ははその通りで、ともかく、用事が終わりましたので、すぐ戻らねばなりません、失礼つかまつります」
男はほっとしたように志乃から離れていったのです。
ほ、勘定方の畑中徳義か、福はなにを頼まれたのだろうか、探ってやろう。
てなぐあいで、あたいは桃姫の部屋に戻りました。
次の朝。
姫さまの部屋では福が姫さまに話をしています。
あたいは姫さまの脇におちゃんこをしました。
「桃姫さま、先日、里帰りした文の代わりが見つかりましたでございます、姫さまから殿にお願いをしていただけませんでしょうか」
「どこの者だえ」
「城におつかえの勘定方の妹ごにございます」
「名は」
「畑中美代ともうします、畑中徳義さまの妹ごにございます」
「あの、まだ若い勘定方ですね、福が良いと思うならかまわぬ、ただ、猫が嫌いではなかろうな」
「大丈夫でございます」
ははん、このことだったのかと合点がいき、徳義という男、自分の出世をかけて福をたぶらかしたのだと言うことがわかりました。
「君香をよんでくださいな」
「はい、お着物を作られますか」
「今日越後屋さんが来るのです、次の月に、父上のもようされる歌の会があるが、そのときに着たい」
「わかりましたでございます」
君香という女中は桃姫の着るものを担当しているのでございます。
ということで、越後屋の奥さまがまいりました。あたいがお城に上がって初めてのことです。
「越後屋にございます」
奥さまが桃姫の前で頭を下げ、隣にいたあたいを見ました。
「玉はいかがでしょう、桃姫さまのお眼鏡にかないましたでしょうか」
「越後屋さん、今は美美という名です、美美は頭のいいかわいい猫じゃ」
「はい、私の知り合いの和尚さまがとてもかわいがっていた猫で、お姫さまにぴったりと思いましたので差し上げた次第です」
嘘ばっかり。
「ありがとう、これからもかわいがりますよ」
あたしは姫様から離れました。着物選びにじゃまになってはいけません。
「さ、それでは、お着物を見せてください」
君香が越後屋さんを促しました。越後屋の奥さまは、丁稚に持たせた沢山の反物や着物を桃姫の前に広げました。
「おお、綺麗、目移りしますね、今度の歌の会は江戸から偉い方を招くとのことでした。目立たず目立つものがよいの」
なんと、うまい表現でしょう、この姫は本当に頭がいい。
ということで、姫さまは淡い桃色に、裾のところとに赤いかわいらしい小さな金魚があしらわれた、出来上がっているおべべを選ばれました。それに朱色の帯をつけると、確かに地味だけど、歩くと裾の金魚が、ゆらゆらと泳いでいるようでかわいらしいし、色の白い桃姫にはとても似合う。
着物を選び終えると、越後屋の奥さんは姫に言いました。
「お願いがございます、この猫の持ち主だった住職さまが、一目、玉、いや美美さまに、会えないだろうかと、申しておりました。猫好きな優しいお坊さまでございます。お姫さまにお目通りなど高望みはしないが、お城の台所ででも、猫に一目会いたいと申しておる次第でございます」。
「ほほ、それはかまいませぬ、誰かに手配をさせますから、それに従ってくだされな」
ということで、越後屋の奥さまは、まんまと、あたいとあの生臭坊主の出会いをうまくまとめてしまいました。ちょっと面白いかもしれません。
それから数日後、若いお女中につれられて、あたいは台所に連れて行かれました。そこで、あのばあさんが和尚と話をしております。
「美美さまをお連れしました」
若い女中があたいを床に下ろしました。
和尚はそれに気が付くと、
「おお、おお、ますます可愛くなって、さぞ姫さまに大事にされておるのだろう」
などと言って私のそばによって来ました。
なんだ、糞坊主、おべんちゃら言いおって、と、まあ思ったが、あたいも和尚の足下に擦りつきました。
「かわいがっていたんだね、和尚さん」
台所をまとめているばあさんが細い目をますます細くする。
「玉や、抱っこさせておくれ」
生臭坊主があたいを抱き上げたのには、ちょっと反吐がでそうだったが我慢をしました。
「さあ、お外に行ってみましょうか」などと言って、坊主はあたいを台所から連れ出し、ばあさんの見えないところに行きました。
「どうだ、なんか面白い話はあったか」
急に言葉遣いがぞんざいになります。
「人選びの女中の福が勘定方の畑中徳義とできていて、今度徳義の妹が奥にあがる」
「もう、そんなことを知ったのか」
「ああ、畑中は偉くなりたいのさ」
「そりゃあわかる、いい情報だ、もっと調べてくれ」
「なんだい、勝手なことを言って、きもいから、早く戻してくれ」
あたいは和尚のほっぺたを軽く引っ掻いた。
「いたた」
ほっぺたから少し血が滲み出た。
「傷ものになっちまったじゃないか」
和尚があたいの頭をたたいたから、草履にしょんべんを引っ掛けてやった。
あたいは和尚から飛び降りると一人で中に入った。
あのばあさんが気が付いて、
「おや、美美さま、和尚さんはどうしました」
と入り口を見ました。
和尚がほっぺたを押さえて、足を引きずって台所に入ってきました。
「和尚さん、どうしたんだね」ばあさんが聞ききますと、
「玉を強く抱きしめたら、強すぎて爪が顔にあたっちまった。それに、おしっこを我慢していたようで、私の草履にもらしちまった」
「ずいぶん可愛がっていたのだねえ、手放すの惜しかっただろう」
「ああ、涙がでましたよ」
馬鹿、嘘ばっかり言いやがって、あたいは和尚のそばによって、もう一度足に爪をたててやった。
さてそれから、一月たったころには、あたいは奥の猫たちから一目置かれるようになっておりました。桃姫があたいをよく抱っこするようになったからです。それに、黒たんと仲の良いのも幸いしました。
あれから、女中の福のところに、一度畑中さまがきました。前と同じように部屋の中で寝ていたら、畑中さまの変な趣味がわかりました。
「福どの、妹の美代をありがとうございました」と、
はだかの福を布団でくるくるまきにして、ころがして遊んでいるのです。ことが終わると、福も嬉しそうにしておりましたから、趣味が一致しての逢瀬のようで、必ずしも妹の職探しだけではなさそうでした。
「美代さまは徳さまに似て、器量良しでございます、桃姫さまもお気に入りになられますよ」
「ところで福どの、台所に人はいりませぬかな」
「また、どうして」
「働き者で飯を炊くのがうまく、料理の腕がいいと評判の娘のことを耳にしましてな」
「器量がよいのですか」
「いや、会うたことはないがな、とっても猫が好きだそうです」
「年はいくつで」
「十五ということでして、奉公させてくださらぬかな」
「そりゃ、台所の人手でしたら簡単です」
あたいはそれが誰か知りたくなりました。
しばらくたって、台所に顔を出すと、あのばあさんに福が、
「今度くる子に、作法を教えてくださいな」
と言っているところでした。
「どこの子でしょうな、福さま」
「なんでも、城下のはずれの、寺の娘とのことでした、料理がうまく働き者のようです」
ははーん、あの糞坊主、畑中をおどして自分の娘をここに送り込んだのだな、と我点がいきました。坊主の娘は坊主に似合わず、猫好きのやさしい娘です。あたいが寺にいた時、可愛がってくれました。確か紫とか言う名前だったと思います。あたいは、その娘を手なずけることにしました。
紫がお城に奉公を始めてしばらくしてからです。
台所にいくと紫が仕事をしておりました。あたいは足に擦りつきました。
「おや、玉じゃないの、久しぶりねえ」と言いながら、あたいを抱きあげようとすると、あのばばあが、
「紫、桃姫さまの猫に触るんじゃない」
と怒りました。まあここでは一つの道理です。しかたありません。
「す、すみません」、小さくなって謝っている紫にあたいは擦りつきました。
黒たんも顔を出しました。
「この猫も姫さまの猫だから、大事に扱うように」
その夕方、あの坊主の寺の近くに住んでいる、顔見知りのぶち猫が城の台所にやってきてのぞきました。紫が気が付いて、魚の食べ残しを庭の隅にもっていきました。紫は「お腹がすいたら、ここにいらっしゃい」とぶちを抱き上げました。紫は猫好きでいじりたくて仕方がなかったのです。
ぶちは飼い猫ですが、お城に来てみたかったのです。実は、ぶちをここまで連れてきたのは黒たんでした。黒たんはこっそり城を抜け出し、城下を散歩するのを楽しみにしていたのです。あたいは黒たんにたのんでぶちを呼んだのです。
それから、次々に、あたいの知り合いが庭に集まるようになりました。茶助、黒ちゃん、おすじ、黄身あん、妙連、琲すけ、みんな寺や寺の近くの猫たちでした。紫はその猫たちに献身的に餌を持ってきてかわいがりました。
一方、あたいは、いつも姫さまのそばで、おとなしく、姫様の猫たちをみていました。
今では、ペルシャの白より、あたいのほうが姫さまと一緒にいる時間が長くなりました。南蛮の雄猫たちもあたいには近づかなくなりました。あの乱暴なシャムの奴は、あたいが、あいつの耳に思いっきりかみついたので、二度と耳がたたなくなってから、あっちの方も全くだめになって、おとなしく丸くなっていることが多くなりました。かの格好いいと思っていたシャルトルウは一度つきあってやったけど、へたっぴーで、単純で面白くないので、「ばか」っていってやったら、しゅんとして、ほかの三毛猫でがまんするようになりました。あの菊という三毛猫は自慢げに、シャルトルウとしたことをあたいに言うものだから、ひげを数本抜いてやりました。
そしてある日、とうとうお姫さまがお休みに部屋に、あたいを連れて行ったのです。
桃姫さまはお休みの時には、薄手の白いお着物をめして横になります。着替えになるとき見ていたのですが、外からは想像できないほど、おっぱいが大きくてきれいでした。あたいは、姫さまの枕元でおとなしく丸くなりました。
そうやって、時々、寝屋にはいることになり、一月もたった頃でしょうか。姫さまの寝ている部屋の天井板が一枚すーっと開くと、黒い影が綱を伝って降りてまいりました。
姫さまは声を出さず、前をはだけて、黒い陰がそれに覆いかぶさりました。音もなくもつれ合うと、影はすーっと、ふたたび天井裏に消えていきました。
桃姫さまのピンク色になった肌がとても綺麗でした。
あれが有名な鼠小僧で、江戸にいたはずですが、どうも名古屋に流れてきたようです。姫さまは男気がないのではなく、鼠小僧が彼氏だったのです。大変な特ダネです。
あたいはときどき、夜になると、台所から庭にでて、昔の仲間と遊びました。庭の椿の木の下で、ぶちたちと川柳をよんだり、今の世の中の愚行をあざ笑ったり、楽しい夜を過ごしました。
庭には、いつの間にか知らない顔の猫たちがいました。友達が城下から呼び集めた仲間でした。月夜の晩などは、車座になって宴を催しましました。新月の時は、猫たちが睦むときでした。そのあと、子猫たちが顔を見せるようになりました。お庭で増えた猫たちでした。
あたいは、みんなに黒たんを紹介しました。あたいの旦那です。年をとっているのに、本当に上手で、優しい上に、力強く、日本の猫の底力を知ったのです。あたいのお腹には八匹の子猫がいます。あと数日で生まれます。桃姫さまも楽しみにしています。
「美美、かわいい子を産むのですよ」
声をかけてそーっとお腹をさすってくれたりします。
姫さまのところにはあいかわらず、鼠小僧が忍び込んできます。
あたいもいろいろな秘密を知ったのですが、和尚に知った秘密をちくったりするのが面倒になりました。鼠小僧のことはあたい一人の胸に納めておくことにしました。
和尚の娘、紫は毎日庭の猫の面倒をよく見てくれています。越後屋の奥さんも呉服がよく売れて幸せです。和尚も満足しているようです。
とうとう子供が産まれました。
四匹の真っ白い猫と、四匹の真っ黒い猫でした。
「美美、かわいい猫たちですね」
桃姫さまが、台所の隅で生んだ子どもをわざわざ見にきてくれました。そして、
「福、この猫たちも奥に住まわすように」と言ってくださいました。
こうして奥では、あたいの生んだ子どもたちが大きくなって、桃姫さまのおそばで、丸くなっています。庭には、たくさんの友達が住むようになりました。名古屋城の内と外にあたいの猫世界が出来上がったのです。
「おや、玉、いや美美さま、どうして戻ってきたのですかな」
寺の本堂の木魚で遊んでいるあたいを見て、和尚が目を丸くしています。
「おや、黒虎のじいさん猫もいっしょかい」
黒たんも本堂の大仏さんの手の上で丸くなっていました。
「おい、糞坊主、また、ここで暮らすからな」
あたいは黒たんをさそって城を抜け出してきたのです。
「また、そんなきたない言葉をつかってはいけませんよ」
あたいは寺の縁の下に鼠を捕りにもぐりこみました。
お城には鼠が一匹もいませんでした。やっぱり、猫にとって鼠を捕ることが一番楽しいことなのです。
「鼠を獲るでないよ」
和尚の声が聞こえてきます。
「フン、糞坊主、鞠でもついてな」
あそこに鼠がいます。さ、追いかけなきゃ。
お猫さま 最終話 - お猫様
私家版 猫小噺集「お猫さま 2017 一粒書房」所収
お猫さま:2017年度、第20回日本自費出版文化賞、小説部門賞受賞
木版画:著者


