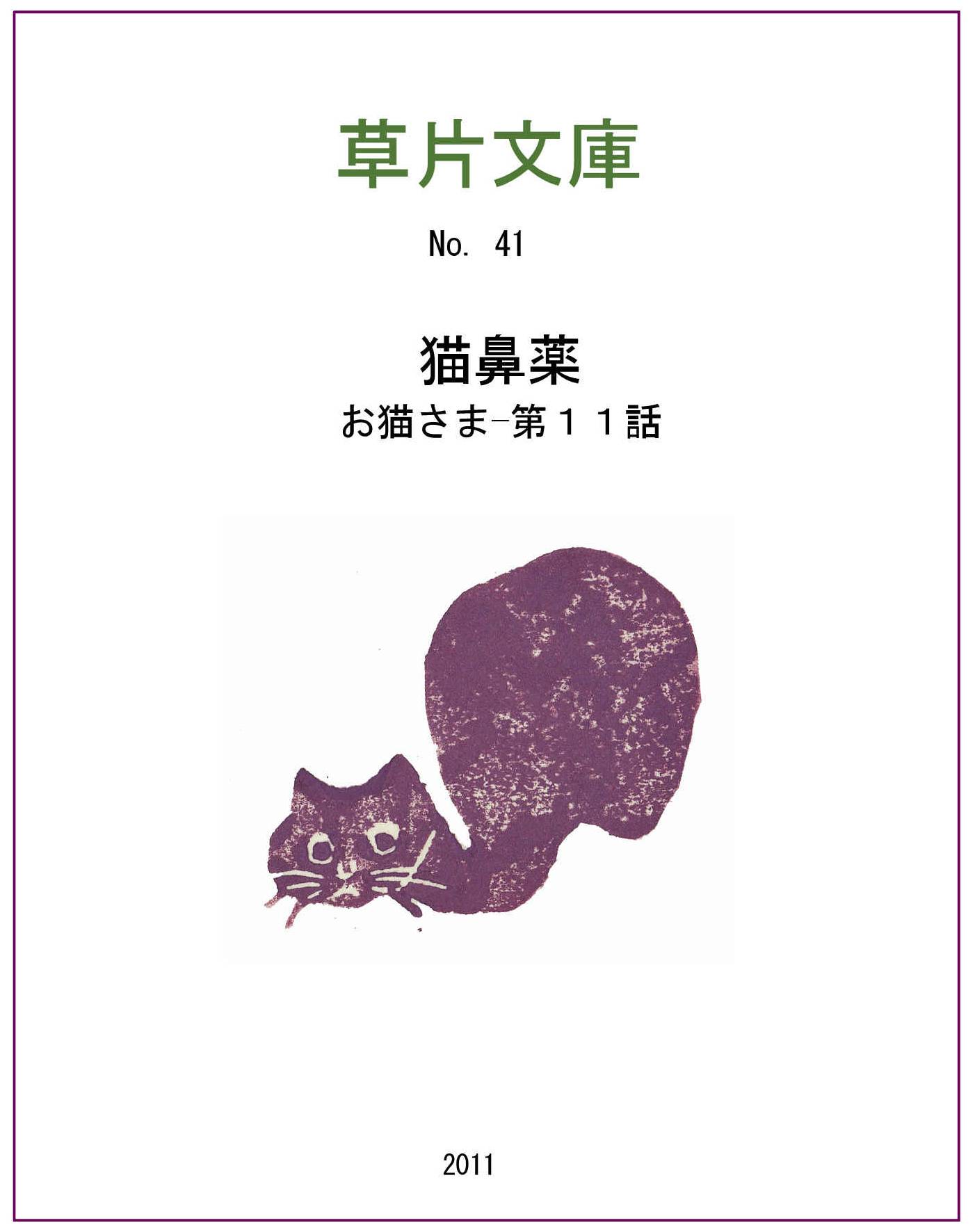
お猫さま 第十一話 - 猫鼻薬
猫の人情小噺です。笑ってください。
猫にマタタビ、どうしてでございましょうな、マタタビてえ植物は猫の大好物。決して食べるわけではなく、匂いだけで、猫の頭の中が気持ちよくなっちまう。
猫にとって鼻薬、麻薬、危険ドラッグでございますな。マタタビの粉をおいておきますと、それに擦りついて、舐めて、涎を垂らして、まあだらしなくなります。
猫ばっかりじゃなくて、猫科であれば、あの偉大なライオンでさえ、マタタビを好むそうです。もっと不思議なのは、あの弱弱(よわよわ)しい草蜉蝣(くさかげろう)もマタタビに寄ってくるそうですが、猫が好きになる成分とは違うということがいわれております。
「おい、八、マタタビ採ってきたから、猫からかおうよ」
熊八が裏山からとってきたマタタビの実を八五郎に見せました。
「猫飼ってどうするんだ」
「飼うんじゃないよ、からかうんだよ」
「からかってどうするんだ」
「面白れえじゃねえか」
ということで、熊さんは、蛸壺の底にマタタビの葉っぱと実をおくと、擂粉木(すりこぎ)で潰して、壷を横にいたしました。
「それでどうする」
八五郎がきくと、熊八は嬉しそうな顔で壷を揺らしました。
「猫が入ったら、こうやってころころと転がすんだ、猫は目を回して踊り出すって寸法だ、それを見て、もっとうまく踊れとか、へたとか、からかうんだ」
「たったそれだけか」
「いや、くすぐってやろうじゃなないか」
「それだけか」
「それじゃ、ヒゲを切っちまう」
「なさけないね、もっと面白いことを考えろよ、猫は酒が嫌いなんだ、だけどマタタビを酒に入れてみろよ、旨い旨いと飲み干して、踊りだす」
八さんは得意げですが、熊さんは「それでどうする」と聞きます。
「もっとうまく踊れとか、へたとかからかうんだ」
「たったそれだけか」
「それじゃヒゲを切っちまう」
「なんだ、同じじゃねえか」
まあ、猫が捕まったら考えようと、その用意をいたします。
ところが、熊八と八五郎のやりとりを、真っ黒な雄猫と三毛の雌猫、いや、三毛は雌に決まっておりますな、その二匹が井戸の陰で聞いておりました。
「おい、ミケ、あいつらからかってやろうじゃないか」と黒が言います。
「そうやわね、黒の旦那、暇だからね、それで何をするかえ」
ミケはシナをつくります。このあたりの猫の間では、猫小町といわれる、人気の猫でございます。今は黒の連れ合いですが、いつ離れちまうか、黒は気を休める暇がありません。面白くないとミケはすぐに離れていってしまいます。人の世界とかわりがありません。
「裏山に住んでいる狸の爺さんをたぶらかそう」
昔はどこにでも狸がいたものでございます。
「どうするのだえ」
「猫に化けてもらうのだ」
「それで、どうするのだえ」
「熊さんと八さんの用意した蛸壺に顔をつっこんでもらうわけだ」
「するとどうなるの」
「あのアホな二人が狸をころがす、どうなるかみものだろ」
「面白いねえ、でもさあ、あの爺狸が猫に化けることできるのかねえ」
「まあ、見ててみねえ」
二匹はうたた寝をしていた狸の爺さんのところにやってまいります。
「おや、おそろいでなんじゃね」
狸の爺さんは猫の匂いで目を開けます。
「いやね、あの長屋の井戸のあたりに蛸壺が置いてある、その中にはマタタビの汁がたっぷり塗られているのを教えようと思ってな」
「それがどうしたんじゃ、マタタビなど知らぬな」
「マタタビは、それはまっことに気持ちの良くなる草で、おいらなんて、ちょっとでもなめると何時もの間、夢の中にいることができるのさ」
「そんなものいらぬわい」
「いや、そりゃそうだろう、猫じゃないと気持ちが良くならない」
「それじゃ、なぜ言いにきた」
「じいさんは、狸の中で一番化けるのが巧いと聞いたから、本当かどうか見たくてきたんだ」
「わしゃ、年季がはいっているからな」
「猫に化けられるかい」
「当たり前だ、一番簡単じゃ」
「形だけではなくて、猫になれるかということさ」
「なんじゃ」
「猫に化けると猫の気持ちになれるのかい」
「そりゃそうだ」
「じゃあ、やってみねえ」
狸はもくっと起きあがると、あっと言う間に茶ぶちの雄猫になりました。なかなか筋肉りゅうとして、いい男です。
「あたしをどう思うかい」
ミケがしなをつくります。
狸の猫は、目尻を下げて、
「うおほほ、きれいだ」
近寄ろうとするのを、あわてて黒が遮ります。
「なるほど、かたちは雄猫になっているが、マタタビで試してみなければわからないね、本物の猫ならマタタビに酔いしれるもんさ」
「それじゃ、マタタビのあるところに案内してくれ」
こうして、二匹の猫たちは、狸の化けた茶ぶち猫を、うまいこと井戸の脇に連れてまいりました。
井戸の脇には熊八と八五郎の用意したマタタビ入りの蛸壺がころがっています。
「おい、ちょっと待ちな」狸猫が立ち止まりました。
「どうしたね」
「いやな、予感がするのじゃよ」
「それよりどうだい、マタタビの匂いはするかい」
「そりゃあ、遠くからしてるさ、なんか浮き浮きしてくるんだが、狸の部分がなにかいやな予感を感じている」
「まあ、マタタビの味を楽しんでみねえ、猫じゃなければわからない快楽だ」
狸猫は蛸壺の口のあたりをふすふすと嗅いだとたん、にゃーごと一鳴きでございます、首を突っ込んで猛烈な勢いでマタタビを舐めはじめました。
さて、それを見ていた熊八と八五郎は、みなれない猫が一緒なのを、少しいぶかしく思ったようですが、そこは呑気な二人のこと、ほれ捕まったと、飛び出すと、蛸壺をころころと転がして、井戸の周りを八周いたしました。
元のところにもどると壷を立てた。
中に入った狸猫はいきなり転がされ、目を回し、今度は逆さまにされ、お尻の穴を上に向けたまま気絶しております。
「ほれ引っ張りだして、からかっちまおう」
熊八が尾っぽをつかんで引きずりだそうとしたとたん、猫は狸に戻ってぽーんと屁をひったからたまらない。
その臭いこと臭いこと、熊八と八五郎は鼻をつまんでひっくり返った。
それだけではありません、爺さん狸は溜まっていた糞を思いっきりひりだしたから、さあ大変。熊八と八五郎の顔にべちゃーっと降り注ぎ、その匂いは臭いを通り越して、気絶寸前、意識のないまま二人はのたうち回ったのです。
陰で見ていた黒とミケは腹を抱えてケラケラ大笑い。
「笑いすぎて顎が外れそう」
ミケは顎を押さえてまだ笑っています。
「ほれ、面白かったろう」
「ほんと、黒の旦那は大したものだ」
黒はミケと手を取り合って、いつもの寝ぐらに帰っていったのです。
壷の外に引っ張り出された狸の爺さんはやっとこ起き上がった。
「人を化かす狸様を拐(かどわ)かすたあ、見上げた猫じゃ」
狸の爺さんは気絶している熊さんと八さんに気がつきました。
「マタタビを使って猫をだまそうとした人間より、狸をだまして、人間をだました猫はたいしたもんじゃな、わしは人間にうんをつけてやったのだから、ずい分親切なものだ、いいことをした後はいい気分じゃ」
ここのところ溜まっていて、苦しかったものが出たのですーっとした狸は、まんざらでもない顔をして、裏山に戻っていったのでございます。
熊さんと八山は、さて、どうなったか、ご想像通りでございます。
お猫さま 第十一話 - 猫鼻薬


