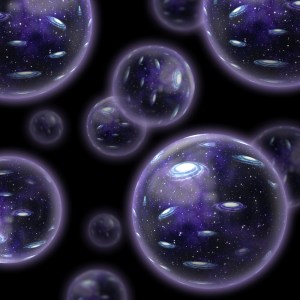第8話-3
3
白い円柱状の建物は天空の核へと伸び、その途中の階層には住人が住んでいる。ただ人間のように入口から入り、階段やエレベーターで上階へ移動するのではなく、水中を泳いで直接、家へ入るのである。
その最上階にドーム型の白い水分子を凝固させた建物がついており、そこがビザンの家であった。彼が議会代表に選出されてから引っ越したので、もう人間の知る年数に換算すると30年は経過していた。
家に入るなり、ビザンは激しい怒りの色、赤で顔を染めて父に怒鳴りつけた。
「絶対家から出るなって、あれほど言ったじゃないか。私の立場も考えてくれよ」
室内に入ると父グザはいつも身体を預けている浮遊力が通常の水よりも強い水をためている、彼らにとってのベッドへ入り込むと、銀色の立方体を抱えたまま、何かをぶつぶつと呟き、息子、娘の事など眼中にない様子だ。
「お前もお前だ。父さんは眼を放すと言えから抜け出すから頼むぞってあれほど言っただろ」
ビザンの怒りの矛先はミザンにも向けられた。
「仕方ないでしょ、食事の支度をしていたら、出て行ったんだから。もう家で介護をするのは無理だって兄さんも分っているはずでしょ」
帰りじたくをしながら妹は、軽い不快感の赤が顔を染めていた。
「わたしはお父さんの面倒を見るために生きてるんじゃありません」
と、きっぱりと言い。帰る準備を終わらせた。これからどこかへ出かけるのだろう、装飾があしらわれた首飾りや腕にリングをはめている。すべて黄金の色をしていた。
「それから明日から調査で惑星を離れるから、頼りにしないでよ。暇じゃないんだから」
そういい捨てるようにミザンは水中を泳ぎ、街に溶け込んだ。
こっちだって仕事がある、心中でイラついた言葉を吐き捨て、ビザンは中空の水の中で身体をゆっくりと回転させながら、立方体を見つめる父を見つめ、水の中にうなだれた。
惑星ダゴルトの表面はもちろん水分に覆われ、その透明度から恒星の日差しが常に水中を垂らしている。その乱反射は観光客にも絶景と呼ばれ、評判になるほどだ。絶景のポイントなどは、観光資源として、観光客をどんどん惑星外から、引き入れていた。
惑星に住む種族に睡眠という概念はなく、時計のように、統一の感覚を作って、1日を区分していた。
間もなく日付が変更する、人間時間で言えば深夜0時。ようやくグザが水中で、銀色の立方体を手放し、それをビザンは父が集めている、あらゆる素材の、何に使うかもわからない、彼にとってはガラクタにすぎないものが並ぶ棚へ、銀色の立方体を並べた。いつものことだ、と水を吐き出し首を振った。
今日の議会の決議を、代表として惑星ダゴルト議会へ伝えるべく、彼は仕事を始めた。
水は彼らにとってあらゆる生活の基盤になっていた。書類、データという概念はなく、長く白い両腕を広げて大きくした水を身体の中に口から入れる。それから軽く水を吐き出すと、その水は水流となり家から排出されて街の空中を流れ、街の中心のドーム型の水分子で構築された議会堂へ入っいった。
その水分子には多くの情報が書き込まれており、直接、議会堂の職員へと伝達された。
水をすべて吐ききった時、方向が終了すると、せて次は、と口の中で呟くと、部屋の奥へと泳いで進み水分子で構築された扉を引いて開く。
するとそこには光を帯びた流水の柱が二重螺旋を描いて渦巻いていた。光は球体のように光り輝き、色、大きさはさまざまである。それが彼の本当の仕事。つまり海洋学者としてのこれまでの経験を記録した水の柱である。ここに記録されている水の記憶から、必要なものを自らの体内に吸収することで、脳内で処理、研究を行うのだ。
人間がコンピュータを使い研究するように、彼らは脳内で研究をする。インターフェースなしで直接、脳が情報を処理して新しい答えを導き出す。彼らはそうした進化の既決として誕生した水に住む種族なのである。
だからこそ彼らの脳は非情に重要であり、それが破壊されるビザンの父の病は、彼ら種族にとって致命的な病なのである。
水の柱を眺めながらビザンはその1つの光を水分ごと口から体内へと吸収した。彼の仕事が始まったのである。
第8話-4へ続く
第8話-3