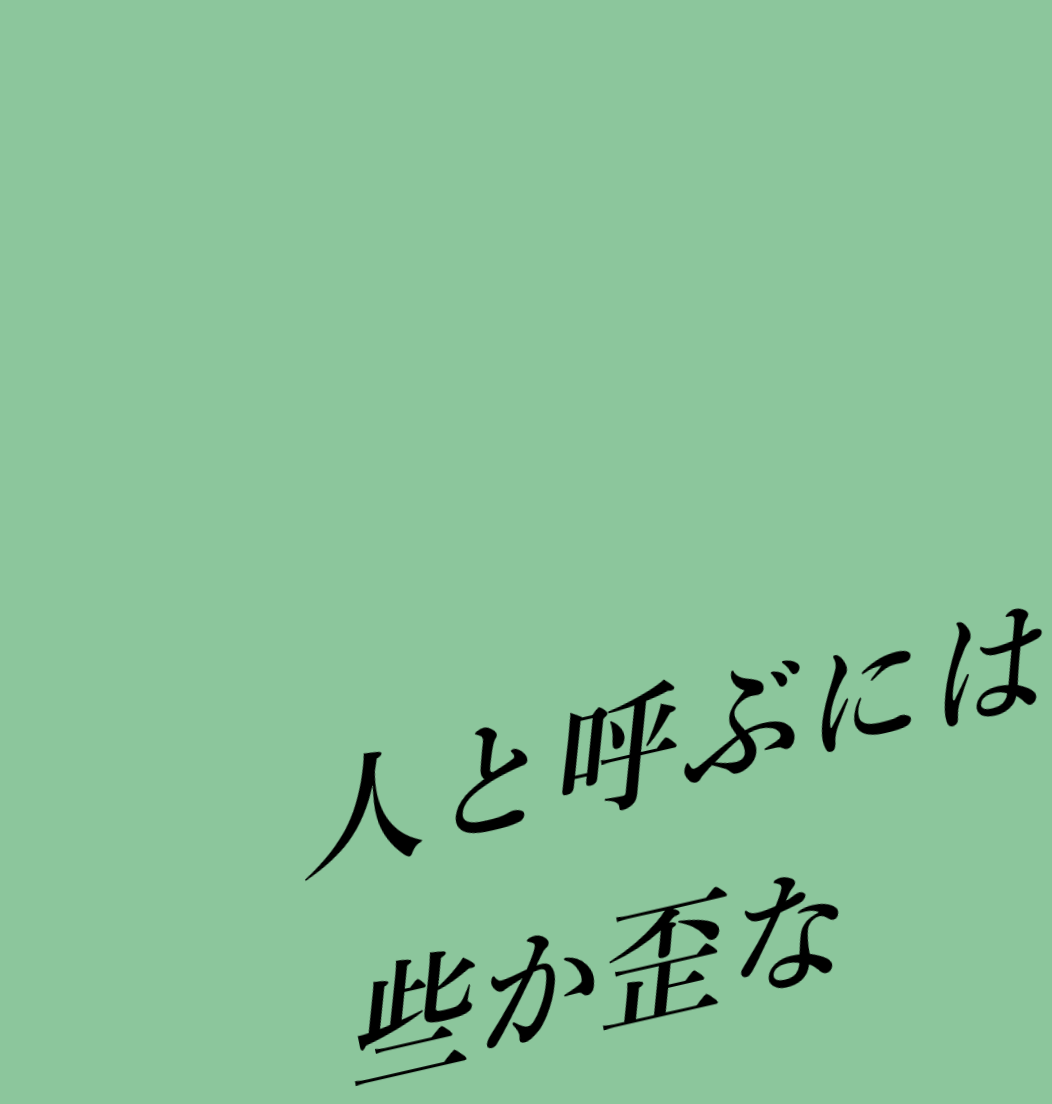
人と呼ぶには些か歪な
一 伽
「何か、ご用ですか」
戸を叩く音に答え、女主人は外へ声を掛けた。
真夜中の事、急ぎ用意した灯の明かりが、手元で踊る様に揺れている。女は聞き耳を立てたが、戸を隔てた向こう側から返事は無かった。
雨の降る晩だった。
訪問客は頻闇に佇み、口を噤んだままじっと耐えていた。
「ご用が無ければお帰り下さい。ここは、生半可な心構えで、訪れる事の出来る場所ではありません」
冷淡な女の声音が磨硝子を微かに震わせる。
客は黙っていた。
女は戸を睨み付ける様に見つめた後、奥の間へと去って行った。
雨音が止む気配は無い。
半時を数えてから再び女は灯を携え、嫋やかに闇に向かって呼び掛けた。
「何か、ご用ですか」
「虫が」
恐る恐る客は言葉を口にする。うら若い男の声だ。
「必要だ」
男は女の返答を待った。
「その意味をお分かりですね」
「ああ、どうしても、息子を」
「承知致しました」
女は錠前に手を掛けた。小声で虫に、別れが近い事を告げる。
虫は肯定の意を示すように、きしきしと笑ったようだった。
「で?」
銜えたままのストローを牛乳パックからするすると外し、璃子が言う。先端からぽたりと落ちた白い液体が、制服の赤いリボンに染みを付けた。
「で? って何」
開け放たれた窓から侵入した蝉の音が、容赦無く教室内に充満している。吸い込んだ生温い空気と一緒に、音が体内をくまなく巡る。自分の輪郭が曖昧になって、夏に溶け込んでしまうような気がした。
「だから、続きは?」
ふがふがと璃子はストローを揺らした。さらに一滴の牛乳が、今度は外されたボタンの隙間から、彼女の鎖骨の下の窪みへ垂れる。僕は思わず目線を斜め上へ反らした。
丁度黒板の上の掛け時計が目に入る。時刻はぴったり十二時だ。
「行儀悪いよ、璃子」
「いーから、続き! はっ、やっ、く!」
「うーんと。男は無事に虫を貰えて幸せになりましためでたしめでたし」
僕は一息に結末を言うと、大きく伸びをした。机の横に掛けた黄色のバックパックを掴む。
「は? めでたしとか意味分かんない。ちゃんとした続きは?」
璃子はバンバンと机を叩いて抗議する。
「気になって夏休みの宿題、手に付かなくなっちゃうからさあ」
ここまで話に食い付かれると予想だにしなかった僕は、苦笑しながら立ち上がった。
「璃子の宿題はいつもの事でしょ」
中身のほとんど無い、使い込まれたバックパックがへなへなと背中へしな垂れた。今日の授業は午前中の終業式のみ、荷物は昨日までに全て持ち帰り済みだ。この軽さなら、割と早く走れるかもしれない。
「あ、ちょっと、あっくん。どこ行くの?」
「もう帰んなきゃ。今日から本格的に店の手伝い。十二時半には開店だから」
一瞬不満げに唇を付き出した璃子は、何かを閃いたようにぱっと表情を明るくした。
「お店って、家と一緒になってるんだよね? 今日はずっと店番?」
「まあ、そうだけど」
「それなら後で、あっくん家行っても良い?」
「だーめ」
「何で? 店番しながらさっきの怪談、続き教えてよ」
「だから、怪談じゃないって」
数分前の、あの話を選択した自分を恨んだ。
友人との昼食時、暑さを紛らわす良い方法は無いか、という話になった。その中で彼女は、背筋のひやりとする話をしようと言い出したのだ。咄嗟に何も思い付かなかった僕は、小さい頃に聞いたあの話を披露し掛けた。
今日という日がそうさせたのかもしれない。だがあれは、軽々しく口にするにはやっぱり相応しくないものだっただろう。
「とにかく駄目ったら、駄目。じゃ、お先」
笑いながら一歩を踏み出した瞬間、どういう訳か足が竦んだ。背中で揺れたバックパックの重みの無さに、急に不安が込み上げる。何か大切なものを忘れている、そんな感覚だ。足りない。中身が、満たされた安心感が、足りない。
「ほらほらあっくん、そんな所に立ち止まらなーい」
背中をばしんと叩かれ、はっと我に返った。
立ち止まったままの僕を追い越して、彼女は廊下へ弾むように駆けて行く。璃子の朗らかな笑い声が人気の無い校舎に響き渡った。
「後で家! 行くからねーっ! それまでそれ、人質!」
「え、人質?」
見ると僕の足元に、璃子の青いスクールバッグが放り出されてある。良く分からないキーホルダーやぬいぐるみがわんさかと実った、実にずっしりとしたバッグだ。
尖っていた感覚が、狭まっていた視界が一気に解けた気がした。
「ちょっと、璃子!」
僕はじゃらじゃらと楽しげな音を立てるスクールバッグを手に走り出す。やっぱり重い。
不思議と蝉の煩さは気にならなくなっていた。
そうして僕らは、一学期の余韻を学び舎に残したまま、真っ盛りの夏へと飛び出した。
二 那
「何か、ご用ですか」
インターホンのマイク越し、一瞬の沈黙に、僕の心臓は大きく跳ねる。
「ちわーす、宅配便でーす」
「あっ」
張り詰めていた緊張が行き場を失い、汗となって額を流れた。
「はいっ、今出ます」
急いで居間に向かう。箪笥の抽斗から印鑑を探し出し、土間に駆け下りて引き戸を開けた。
僕の暮らすこの旧家には、築七十年の木造建築とは似ても似つかぬ最新式のインターホンが二つある。右の戸柱のものには伏乃姫と印字された名前シール、左の戸柱のものには店の名刺が貼ってあった。
上質な和紙で作られた一点物の名刺は、今朝新調されていた。古風な筆文字で“虷”という文字と開店時間、そして店主の名が記してある。そう言えば、店名“虷”はカンと読むのだろうが、正しい読み方は未だ知らないままだ。
「ちぇっ、宅配なら右の押してよ」
ぼやきながら靴を脱ぐ。荷物は伏乃姫鞠宛ての小包だった。ティッシュボックス程の箱だが、大きさの割に随分と重みがあった。
「何だろう、また虫関係かな」
印鑑を仕舞うために一旦居間へ戻ろうと踵を返す。刹那、再度インターホンが鳴った。
心拍数が跳ね上がる。僕は左右どちらのインターホンが鳴ったのか失念したまま、目の前で明滅する通話ボタンを押した。
「なっ、何かご用で」
慌てたせいか言葉が閊える。
「あれ、あっくん? だよね。あたしだけど」
璃子の声だ。直ぐに、鳴ったのは右のインターホンだったと気付き、顔がかっと熱くなる。「何かご用ですか」の一言は仕事用の決まり文句で、知人に向けるには何とも言えない気恥ずかしさがあった。
「璃子、ちょっと、待って」
昼のあの訪問宣言は本気だったらしい。
「カバン、ちゃんと返したのに」
戸を開けると、午前中と同じ着崩した制服姿の彼女が立っていた。半袖から伸びる健康そうな二本の腕が、ハンドボール程の西瓜をぶら下げている。
「あっくん、これってもう開店中?」
「うんまあ」
「で、結局ここ何のお店?」
璃子には店に関する事はほとんど話していない。蠢く後ろめたさから、彼女の目をまともに見ることが出来なかった。
「あー、一般向けの店じゃなくて。専門っていうか、紹介された人が来るとこだから」
「ふーん」
尋ねておきながら、璃子は然程興味のなさそうな声を出した。小玉西瓜を緑の網ごと、ぽんと手渡される。
「これお土産。お祖母ちゃん家の畑で採れたやつ」
「あ、ありがと」
「それで、今お客さんは? 来てる?」
嫌な予感がした。
「いや、まだだけど」
「そうなんだ。じゃあちょっとだけ、上がっても良い?」
矢張りそう来たか。
彼女を開店時間中に家、元い、店に上げる訳にはいかない。どうにか上手く断るにはと口を開き掛けた時、横手からふいに声がした。
「あら、可愛らしいお客様ね。こんにちは」
長い黒髪を優雅に揺らし、縁側を歩いて来た家主が会釈する。菫色のワンピースの裾が南風にふわりと膨らんだ。
「こんにちは」
璃子もお辞儀を返した。肩に触れるくらいの髪が元気良く弾むように揺れる。
「初めまして、姉の鞠です」
「あ、私、憧(あこがれ)君のクラスメートの武忍徒璃子です」
「貴女が璃子さんね。いつも弟がお世話になっているみたいで」
「あ、いえ。こちらこそ、いっぱいお世話になってます。その、憧君ちょっと借りられないかなって思って、来てみたんですけど」
「ごめんなさい、これからお客様が来られるの。また今度お誘い頂けるかしら」
「はい、分かりました。お忙しいところ、突然すみませんでした」
聞き訳良くぺこりと頭を下げた璃子は一度僕らに背を向けたが、そのまま一回転して顔を上げた。
「あの、鞠さん。一つだけ良いですか?」
「ええ、何かしら?」
鼓動が速くなる。
「ここって、何のお店なんですか?」
僕の動揺を他所に、二人は和やかな雰囲気で微笑み合っている。
「そうね、璃子さんはヨウサンって知っているかしら」
「ヨウサン? ヨウサン……」
イントネーションを幾通りにも変えてぶつぶつと呟いてから、漫画のように手槌を打ち、璃子ははしゃいだ声を出した。
「養蚕! もしかして蚕から糸を作るあれですか?」
「あら、物知りね。うちはヨウサン業を営んでいるのよ」
「へー凄い! 本物見た事ないです。家の中で飼ってるんですか?」
璃子、質問は一つだけじゃなかったのか、と心の中で突っ込みを入れる。僕は西瓜の網を引っ掛けたまま、酷い手汗をTシャツの裾で拭った。
「ええ。閉店後なら見て頂く事も出来るのだけれど」
見せられないってば、と喉まで出掛かった言葉を、空気と一緒にぐっと飲み込む。もう無理だ。これ以上、綱渡りな二人の会話をポーカーフェイスで聞き続ける気力は残っていない。
「あー、ううんと、大丈夫です。私、実は虫とかそういうの、ちょっと苦手で」
「そう、それは残念ね」
二人の呼吸がほんの一瞬揃った隙を狙い、僕は口を挟んだ。
「んじゃ、そういう事だから。ごめん璃子。あと西瓜、ありがと」
精一杯の笑顔を繰り出し、璃子に帰宅を促す。彼女はうんと頷き、再度縁側に向かって頭を下げた。
「鞠さん、お邪魔しました。今度はお忙しくない時に伺いますね」
「ええ、お待ちしているわ」
家主の口からごく自然に流れ出て来るのは、勿論社交辞令だろう。だが相手は璃子だ。きっと真正面から受け取って、数日の内に再来するに違いない。
璃子は帰る素振りを見せながら、僕の腕をぐいと引き寄せた。
「ちょっと、あっくん」
「え?」
よろけた拍子に璃子の顔が近付き、耳朶がかっと熱を帯びる。彼女はそんな事はお構いなしに、囁くような声で耳打ちした。
「お姉ちゃんいるなんて初耳だよ」
「……えーと、言ってなかったっけ」
「聞いてない。凄い美人じゃん! 内緒にしてた罰として、駅前のクレープ、今度奢って貰うからね」
璃子の唐突な理不尽に、思考回路が追い付かない。
「え、ちょっと」
当の彼女は言いたい事だけ告げ終わると、呆然とする僕を残し、あっさりと帰って行った。
三 久
「はあぁ」
璃子の後ろ姿が完全に見えなくなったのを確認し、大きな溜め息を吐いた。緑のネットが食い込んで左指の先が少し紫に見える。僕はさらに重くなった気がする西瓜を、よいしょという掛け声と共に縁側に下した。
「焦りましたよ師匠」
「可愛い女の子にデートの約束をされた事かしら?」
僕の師匠、伏乃姫鞠は目を細めて笑っている。
「え、今の聞こえてたんですか、って違いますよ! 師匠が変に璃子の会話拾っちゃうから。突然姉とか言い出すし」
「あら、私はずっと前から貴方の姉のつもりよ。永遠の十七歳だもの」
師匠は太腿辺りのスカートを少し持ち上げ、首を傾げる様な仕草をした。若さのアピールにしては昭和臭い。
「十七って。師匠、それじゃ妹になっちゃいますよ」
「そうだったわね。なら十九にするわ。永遠の十九歳」
「それ、最早永遠じゃないでしょ」
確かに伏乃姫鞠の外見は若い。実年齢を聞いた事はないのだが、亡くなった僕の祖母さえ彼女をお師匠様と呼んでいた程だ。十九は流石に無理がある。せめて三十五といった所か。
「しかも養蚕って」
「サンを養っているのだから、ヨウサンで嘘ではないでしょう?」
彼女はくすくすと悪戯を仕掛けた子どものように笑った。
「璃子は蚕って、はっきり言ってたじゃないですか。蚕とサンじゃ、共通点なさ過ぎて誤魔化せないですよ。色すら真逆だし」
僕はサンの黒光りする表皮を思い浮かべた。
「あら、知らないの? 蚕も孵化した当初は黒いのよ。脱皮毎に白くなるの、絹の様にね。人間とまるであべこべ。そこが好きよ」
「師匠、それは……」
怪しげに輝く彼女の瞳に、それ以上言葉を紡ぐ事が出来なかった。好きと言ったのは虫の方だろうか、それとも人間の方だろうか。僕の中の何方付かずの灰色が、師匠にはお見通しの様な気がする。瑞々しい白でも、芯の通った黒でもない、灰色。それは酷く歪んで映っているかもしれない。
無性に、璃子の声が聞きたくなった。
次の来客があったのは、その数十分後だった。
西瓜を冷やすため、玄関脇の井戸から水を汲み上げていると、俯いたまま通りを歩く人影が目に入った。一人だけ纏う雰囲気が他の通行人と明らかに違う。僕は音を立てぬよう、水を張った盥を手に家屋へ戻った。
それから呼び出し音が鳴るまで、然程時間は掛からなかった。僕は廊下に置いた待機用の椅子から立ち上がり、ゆっくりと店名の書かれた通話ボタンを押した。
「あの、何かご用ですか」
相手は黙っていた。沈黙に鬱屈した重みを感じる。矢張りそういう客なのだ。
「ご用が無ければ、お引き取り下さい。失礼します」
僕は拳を握り締めながら、自室に籠った師匠の元へ向かった。
それから暫く、息を詰め、戸棚の上の置時計を眺めていた。何度も握ったTシャツの裾はすっかり湿ってしまった。それでも、再度通話ボタンを押す頃には、幾分動悸は和らいでいた。
「何か、ご用ですか」
「虫、ここで合ってますよね?」
「はい。今開けます」
戸の前には男が立っていた。髪を染めた若者で、僕より少し歳上に見える。片耳のピアスが日を反射して一瞬だけ強く光った。
「こちらです」
彼は僕の後に付いて靴を脱いだ。横顔を盗み見たが、この半時で決心が揺らいだ様子はない。僕は黙ったまま奥の間へと彼を案内した。
「こんにちは」
座敷の隅から師匠が澄んだ声音で挨拶をした。艶やかな牡丹柄の着物を纏っている。簪から垂れた蝶の飾りが黒髪の上をくるりと舞った。
敷居を跨ぐや否や、男は師匠の方を向き、素早い身の熟しで畳に頭を擦り付けた。
「お願いします! 家族を助けて下さい!」
熱の籠った嘆願に、師匠は涼しげに応じる。
「ご用件は店主がお伺いしますわ」
心做しか胃が痛い。僕は男の後ろを回って上座へ静かに正座した。
「店主の一丹です。まず、具体的な症状を教えて下さい」
男はあからさまに躊躇した。当然だ。きっと悠然と構える師匠を店主だと思ったのだろう。貧弱で頼りなげな学生を宛がわれ、不安を覚えたのかもしれない。僕自身、全くの同意見だった。
しかし昨日まで店主だった彼女は外方を向いていて、助け船は期待出来そうにない。溜息を我慢する僕の顔を数秒間見つめた後、彼は諦めたように話し始めた。
「あー、虫を使いたいのは母です。包丁の刺し傷が十カ所以上と、頭は硝子製の灰皿で半壊で」
それは、殴られたような衝撃だった。
僕は片手で口元を多い、込み上げる吐き気を必死に抑えた。ああ……僕にそれを全て繕えというのか、この男は。
先程見せた激しさはどこへやら、男は事務処理の様に平然と母親の症状について語った。
「……では、今は病院に?」
「いや警察に連絡してたら、ここへは来ませんよ。とりあえず空気に触れないようにして、冷房がんがん効かせてて」
どうも話が上手く噛み合わない。
「傷害事件を通報しなかったという事ですか? 母親を重傷のまま自宅に?」
「死後三日です」
呆気に取られ僕は言葉を失った。流石の師匠もほんの少し眉根を寄せたようだった。
「死後三日って……既に亡くなってるんですか? それじゃあ、あなたのお母さんは救えない……」
この店が扱う虫、サンは高度な擬態能力を持つ。単なる形ばかりでなく機能やその影響力まで、有生物なら何でも忠実に再現出来る。勿論それが人間の臓器であってもだ。
「僕の仕事は修繕です。虫に出来るのは、欠損箇所の血肉となり補填する事。亡くなった人を虫で埋めたって、それは動き回る人形みたいなもので」
「はい、それで構いませんよ」
「え、だからそれじゃあ……」
「それって、とりあえず生きてる風に見えるんですよね? 十分です」
「それじゃあ、あなたのお母さんを救った事にならない!」
僕は思わず声を荒げて立ち上がった。
男は全く動じなかった。こちらを睨み付ける様に見据え、淡々と続ける。
「救って欲しいのは家族なんだって、あれは違う。便宜上母って言ったけど、母親だと思ったことないし。あれが生きてる事にすれば、父は前科持ちにならずに済むし、妹も何も心配せず学校へ通える。それで良い」
「そんなっ」
何時の間にか直ぐ隣に立っていた師匠が、取り乱す僕の肩に手を置いた。彼女は微笑を湛えた顔を隠すように、着物の袖で口元を覆っていた。
「お客様、私共は事情を深く詮索するつもりはございません。虫は勿論お分け致します。そうでしょう、一丹店主」
少しお待ち下さいと言い残して僕は座敷を出た。後を追う様に師匠も廊下へ出て、後ろ手ですっと襖を閉めた。
「僕、今回の件は……」
引き受けたくない、それが本音だった。
肉親を早くに亡くした僕には、家族の記憶は殆ど無い。家族とは言っても人と人の集まりだ。諍いだってすれ違いだってあるだろう、それは理解している。それでも、あんな母子の関係が在って堪るものかと思った。
「僕は間違ってますか」
「いいえ。でも、私は正しいとも言わない。分かるでしょう」
噛み締めた唇から鉄の味がする。師匠の言葉の意味を、本当は痛い程よく分かっていた。
「貴方の遣るべき事は決まっているわね」
店主のすべき事は単なる修繕作業で、対象に纏わる色々について精査する事ではない。
この先の自分のため、一年後の未来のために、この店の店主になった。僕が生まれたあの時から、このレールは敷かれていたのだろう。それでも結局、僕自身が選択した道でもある。僕は心を、そして他人を犠牲にするしかない。得られるのは、鈍い痛みと曖昧模糊とした将来だ。
「正直、初日でここまでの案件が舞い込むとは、私も思い至らなかった。でも良い機会だわ。成人女性ほぼ一人分。これだけの量なら、かなりの虫を一度に手放せる。貴方にとってはそれだけ、目的達成へ近付ける。そうでしょう?」
師匠は優しく、僕の髪を梳く様に撫でた。
僕は、力なく頷くしかなかった。
四 羅
閑静な住宅街の一軒家だった。庭の中央に並ぶ幾つもの薔薇のアーチが、常夜灯の青白い光の中で、まるで神聖なものように浮かび上がって見えた。
依頼人の男の他に出迎えは無く、屋内はひっそりと静まり返っていた。
「この部屋です」
促されドアを開けた途端、むせ返るような異臭と肌を刺す冷気に襲われる。僕の後ろに続いた男は酷く咳き込んだ。
「あー、冷房、要らなかったら勝手に止めて下さい。言われた通りドライアイスは外して、袋から出しときました」
男は口元を手で覆いながらベッドへ近寄り、上布団を捲くり上げる。
「さらにひでぇな。部屋に臭い、残ると困るんですけどね」
僕は感情を押し殺すように、奥歯にぐっと力を入れた。
そこには女性が横たえられていた。事前に指示した通り一糸纏わぬ姿だ。傍らには、生前撮影された数枚の家族写真が無造作に置かれていた。
「後はこちらで行います。ご家族の方は、部屋の外でお待ち下さい」
言われなくても、と低く呟きながら男は足早に出て行った。背後でドアがばんと大きな音を立てて閉まる。
僕は仄暗い室内で彼女と二人きりになった。
肩に掛けた大鞄を下すのと同時に、尻ポケットから着信音が流れ出す。まるで図ったかのようなタイミングだ。
「……師匠、これから修繕に入ります」
「ええ」
「やっぱり、来てはくれないんですね」
「当り前よ。店主は一丹君ですもの。大丈夫、貴方はこれまでの三年間、しっかり私の下で修業を積んで来た。独りでも十分遣れるわ」
「はい」
「帰って来たら、璃子さんが持って来て下さった西瓜を頂きましょう」
「はい……それじゃ」
電話を切り、僕は真っ白なシーツに横たわる女性に向き直った。
亡くなった人を目の前にするのは、これで何度目だろうか。
外傷の一つ一つを、ゆっくり指の腹で撫でる。
「貴女は……」
写真を手に取り、生前の彼女の姿を想像した。
電車の玩具に夢中な少年の隣で、愚図る赤ん坊を胸に抱き微笑む唇。海辺で砂の城を作る子ども達を、海風に煽られた麦わら帽子を押さえながら見守る瞳。有りのままの人間であった頃の彼女は、何を思い、何を感じ、何を考えて生きていたのだろうか。
僕は鞄から銀のアタッシュケースを引っ張り出し、手近なスツールの上に手術道具一式を並べた。そもそも欠損を埋めるのが仕事だ。使い物にならない部位が残った状態では、擬態する虫を住まわせる事は出来ない。
「よし」
この三年間、必死で身に着けた医術知識を基に、破損部位から切除して行く。治療というよりも解体作業のようだった。切除部から順に、虫に変換していく。取り出した臓器が本来在るべき正しい姿、それらが持つ機能を鮮明に脳裏に描き、待機している虫へ伝達する。
「お疲れ様、皆」
新たな宿り場の情報を得たサンは隊列を組む様に規則正しく、僕の内部から這い出ているはずだ。左耳から左腕を伝い、僕の指先から欠損部へと潜り込んで行く。肉眼で捉える事の出来ない微細な一匹一匹が、次なる擬態部位に適応しようと膨張変形を開始する。一時間もあれば、まず頭部の復元は完了だ。
この世に生まれ出た時、僕には脳が無かった。
出産するずっと前から検査で分かっていたのだという。本来脳が在る筈の部分が未発達で、母親の胎から出て生き延びることは有り得ないと。それを承知で母は僕を産み、つかの間の逢瀬と引き換えに自らの命を落とした。
父は僕を生かすため、虫による修繕を伏乃姫鞠へ依頼していた。一丹家の寝所で僕を取り上げたのも師匠だったそうだ。僕の脳は全て、あの時彼女から託された虫なのだ。
サンは擬態先で十八年、忠実に職務を全うする。そして十八年目、一斉に脱皮をする。脱いだ皮は、もうそのものだ。
自然界で脱皮とは、成長するための過程だろう。しかしサンは長年培った全てを脱ぎ捨て、一から新たな生を始める。僕の思考はもう、彼らの抜け殻で展開されているはずだ。
役割を失った虫達は一年間、宿主の細胞の片隅で大人しくしている。だが、脱皮からきっちり一年を過ぎると、それまでの従順が嘘の様に嘗て自分の一部だったものを侵食し始める。元々は彼らのものだったのだから、致し方ないと言えばそうなのだ。
それでも僕は抗う事を選んだ。期限である来夏、七月十五日までに、体内の全ての虫に移住先を提供する。繋ぎ留められたこの命を、彼らと共有していたこの脳を、僕だけのものとするために。
「……ご免なさい」
僕は一体誰に対して謝罪をしたのだろうか。
一心不乱にメスを動かす右手が、僕とは別の意思を持った生き物に思えた。
玄関を出て呆けた様に空を見上げた。
何時の間にか辺りは明るくなっていた。朝日が寝不足の目に眩しく差し込み、思わず顔を反らす。目線の先にはここを訪れた際に見た薔薇のアーチがあった。葉は枯れ掛けており、白いはずの薔薇の花びらの多くが萎びて変色していた。
「ありがとうございました、先生」
しっとりとした女性の声で、僕は振り返る。
玄関ドアを背に、依頼人の男、父親と思われる中年男性、小学生くらいの女の子、そしてあの母親が一列に並んでこちらを見ていた。ただ一体、彼女だけが豊かな微笑みを浮かべ、生気を宿した瞳を潤ませて、深く深く頭を下げた。
帰り道、僕は遠回りをして、河川敷に沿う遊歩道を歩いた。シャワーで濡れたままの髪が、生温い風を受けて膨らむ。酷く不思議な気分だった。
今まで僕を構成していた虫の多くが去って行った。彼らは次の一廻りをあの女性と共に過ごす。虫を移す術を知らない彼女は、その後朽ちる事になるだろう。
果たして誰よりも生き生きと浮世を歩む彼女を、人間と呼んではいけないのか。彼女の紡ぐ言葉は、最早人の言葉ではないのか。
何故、僕の父は、母を繕ってくれなかったのだろう。
脳を虫で代替していると聞かされた六歳の誕生日の、押し潰されるような胸の痛みを、今でも鮮明に思い出せる。
不安、焦燥、悲愴、絶望。その全てが虫を介して発せられる、僕は一体何者なのか。その問いの答えもまた、未だ見つけられてはいない。
近くの野球場から、拡張されたラジオの音声が聞こえた。毎年夏になると繰り返し耳にする、あのメロディが流れ出す。立ち止まり、晴れた空を仰いだ。どうやらラジオ体操が始まるらしい。
「おーい、あっくーん!」
僕を呼ぶ聞き慣れた声がした。
グラウンドの中央、思い思いに散らばった人々の真ん中で、大きく手を振っている人物がいる。
「璃子」
向日葵の様な朗らかさで笑う彼女を、七月の太陽が燦々と照らし出していた。
人と呼ぶには些か歪な


