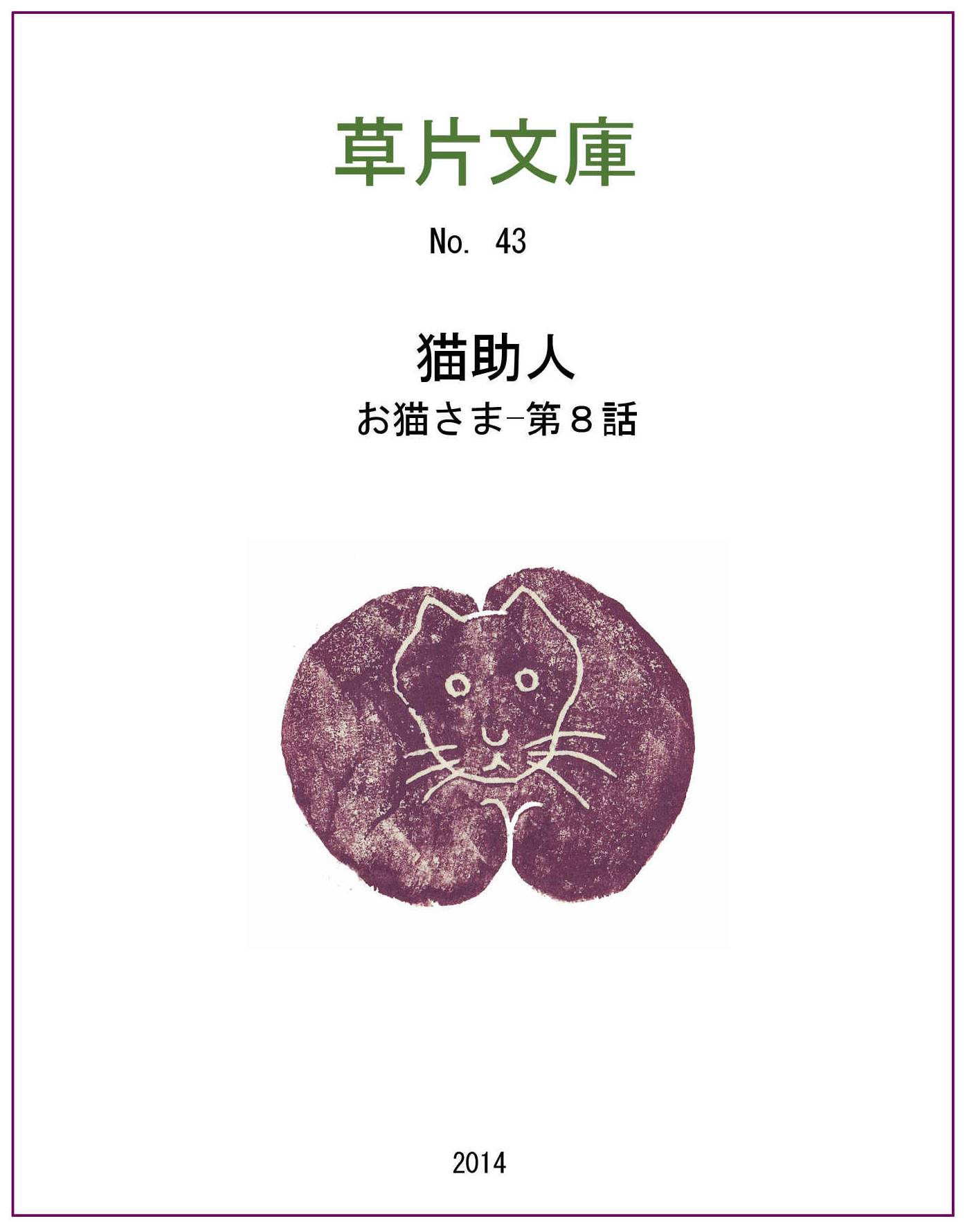
お猫さま 第八話 - 猫助人
世の中、どの国にも仇討ちの話がございます。仇とは、敵(かたき)のこと、敵とは、恨みのある相手のことでございますが、仇討ちとは、両親、兄弟、配偶者、子どもに理不尽な仕打ちをされた時の仇に対する仕返しでございまして、しかも、お上がお許しになった場合のみ仇討ちができるのでございます。日本という国では、仇討ちは面目を施すという、名誉を守るための行為として認められ、やられたからやり返すというのとはちょっと違います。
そこに助太刀という加勢が許される場合がございます。まだ年端も行かない子どもや婦女子が亭主の敵、親の敵を討つなどというときには認められているものでございます。
「熊、知っているかい、家主の衣兵じいさんが、猫に顔中引っかかれちまって、臥せってるんだとよ」
「八、そりゃ誰でも知っているよ、きっと、猫に仇討ちされたって話だよ」
「衣兵じいさんが猫嫌いなのは知っているが、どうして仇討ちなんだ」
「先だって、長屋に住み着いていた雌猫が子供を産んだろう」
「ああ、あの真っ黒な子どもかわいかったな」
「じいさんは、子猫を母猫ともどもとっつかまえて川に流しちまった」
「そりゃあ可哀想なことをしたもんだな」
「それで、子どもの父親猫が仇討ちしたって評判だ」
「猫が仇討ちするはずないだろう」
「わからんぞ」
「その猫はどこの猫だ」
「ほら、たまに秋刀魚を盗む奴だ」
「盗むやつはたくさんいるじゃないか」
「霊巌寺に住んでいる奴の一匹だ」
「顔のでかい虎猫か」
「おそらくな」
「霊巌寺の和尚はいい和尚だよな、猫がいくらいたっておっぱらおうとしない」
「おおよ、だがお経が読めない」
「それで何で、和尚なんだ」
「草取りの名人だ」
和尚さんはいつも寺の庭の草取りをしています。その回りを猫たちが囲んでいるのです。
「まあいいや、大したもんだ」
そこに、噂の虎猫がやってまいります。
「どうだろう、八、俺たちの仇をこの猫にうってもらおうじゃないか」
「あのかたきか」
熊八と八五郎はよせばいいのに、賭場などに行って、稼いだ金をすってんてんにされてしまいました。いかさまであることに気づいたのですが、怖いお兄さんたちに睨まれ、途中でやめることなど出来るはずがありません。なんてったって、ご両人が賭博などに手を出したのがいけないことなのです。
熊八が野良猫の虎に話しかけました。
「虎さま、お内儀さまとお子さまをおなくしになり、心からお悔やみを申しやすです」
虎はふんという顔をして離れたところにしゃがみ込みました。
「熊、通じたみたいだぞ、続けてみな」
八五郎が熊八をうながします。
「実はですね、こうこうしかじかで、すってんてんになってしまいました、あの賭場をとり仕切っている鍛造は悪いやつです、仇を討ってくだされば、焼いた秋刀魚を差し上げます」
それを聞いた虎猫はこっくりと肯いたのでございます。
それから三日後、賭場に猫が押し寄せて、障子を引っ掻くやら、襖を破くやら、床の間は猫の尿だらけ、おまけに、賽子(さいころ)をみんなくわえて持っていってしまうという狼藉を働きました。
「おい、熊、聞いたかい、あの賭場が猫に荒らされたそうだよ」
「あの猫がほんとにやったのか、おー、ざまーみろ」
「それじゃ、秋刀魚をやらなきゃならんな」
「一匹焼いて家の前に置いておいてやりゃあいいだろう」
熊八と八五郎のすまいは長屋の隣り合わせです。
夕方になり、二人は焼いた秋刀魚を一匹、七輪の上に載せたままにしておきました。
一人ものの二人は、一緒にどちらかの家で夕飯をいただきます。今日は熊さんの家で、焼いた秋刀魚でおまんまをいただきました。さて、自分の家に帰ろうと、八が熊の家から出ますと、虎猫が七輪の前で、一匹の秋刀魚を前に、厳しい顔をしております。
八五郎が声をかけました。
「虎さん、ありがとね、秋刀魚食ってくんな」
ところが、虎は牙をむき出し怖い顔をします。そこへたくさんの猫がやってきて、八五郎を取り巻きました。
そこで八五郎はやっと気が付いたってわけです。
「おおい、熊」
大きな声で呼びました。
「どしたい、八」
熊八が戸を開けて顔を出します。
「やや、八は猫にもてるね、囲まれてら」
呑気なものです。
「おい、そうじゃないよ、熊、虎の顔をみろよ、怒ってるぜ」
「なぜだい」
「お前は勘が鈍いね、ほら、他の猫にも秋刀魚を買ってこい」
「あ、そうか、そりゃあ悪かった、ひいふうみいよ、四匹でいいね」
「お前は数が数えられないね」
「もっといるのかい」
「ほら、いち、にい、さん、しい、ご、ととと、虎にはやったから、全部で十二匹だ」
「でも、金がない」
「つけでもなんでもいいだろう、俺が動けない」
「そうか、八のつけにして、買ってくる」
そう言うと、熊さんにしては珍しく、あっと言う間に秋刀魚を買ってまいりました。
「ほら、十四匹」
「何で、十四匹だ」
「俺たちももう一度一緒にお相伴」
「お前はそういうときには勘定ができるんだね」
「それでいくらだった、掛け売りだと、十五文」
「やけに吹っかけられたね、賭ってえのはどんな掛けでも損するね、まあしょうがない、さあ、猫さん、ちょっと待っておくんなさいよ、これから火をおこして焼きますから」
猫たちが見ているところで八五郎が七輪に炭をおこすと、秋刀魚を焼きます。焼けたはじから、猫が秋刀魚の尾っぽをくわえて持っていきます。
猫たちは満足したようで、舌なめずりをして、からだを洗っております。
熊八が自分たちの分をもう一度焼いておりますと、虎がなにやら袋をくわえて、もってまいりました。
「なんでえ」
八五郎が袋を受け取って、中を見ますと、
「お、おれたちが盗られた銭じゃねえか、取り返したくれたのか、ありがとよ」
熊八ものぞき込みます。
「ありがてえ、この月の家賃や食い物代を棟梁から前借りしようと思ってたんで、この恩は一生忘れません、猫様」
「そうだなあ、もう、賭事はいっさいやりません」
八五郎も猫たちに深々とお辞儀をしました。
秋刀魚を食べ終わった猫たちは、霊巌寺に帰っていきました。
熊八と八五郎は、本当は腕の良い、よく働く大工で、棟梁から信頼されておりました。
その日は、侍の家で仕事です。なかなか立派な門構えで、よいお家柄なのでしょう。熊八と八五郎は厨房と内風呂の養生を頼まれたわけです。
ところが、主人がおらず、家守の老人夫婦しかおりません。
二人が手際よく、新しい木壁を張り替えたり、厨房の台などを直しておりますと、「茶を入れたから、一服」というばあさんの声で、二人は手を止め、土間から上がりました。
じいさんも床の上であぐらをかいています。
茶と、ふかし芋が用意されています。
「やってくんねえ」じいさんの声で、二人は茶をすすり、芋をかじりました。
「いい腕してるね」
じいさんがほめます。
「へえ、なげえもんで」
熊が答えると、じいさんが自分のことを話し始めました。
「あっしも、若い頃は大工でね、子供が大きくなって外に出て、二人暮らしになると、ここのお殿様から、腕がいいから、住み込んで面倒をみてくれないかってたのまれてねえ、ここにきたってわけで、そのときはばあさんと喜んだね」
ばあさんも頷いています。
「そうでした、お優しい殿様で、かわいいお嬢様がいらして、お家来衆もみなよい方ばかり」
「へえ、それで、いまは誰もいねえみたいですね」
八さんが聞きますと、
「お殿様が、お腹をめされちまったんで」
「え、そりゃまた」
「理不尽なこったよ、ある偉えお殿様の籠の前を、小さな子供が横切って、籠に当たっちまって、大きく揺れたよ、あわてて、その子のおっかさんが、駆け寄って小さな子をかばったのはいいが、かごの御簾を跳ね上げて、出てきたその殿様が刀を抜きなさったのさ、虫の居所が悪かったのかね、そこへちょうど通りかかった、ここの殿様が、諌めに入ったんだよ、えれえもんだ、それでも、ならんと、刀をひれ伏している母親の首に振りおろそうとした瞬間、うちの殿が刀を抜いて、そのお殿様の刀を振り払った。ほんとうにえれえね、しかしね、殿様の家来がうちの殿を取り押さえ、それで切腹だね」
「そりゃあひでえ」
「それでもねえ、その母子が助かったってえのは、救われるねえ」
「たしかになあ、それでおまえさんがたはどうして、この家にいるのかね」
「長年いた家で、勝手がわかっているのであろうから、家の養生をせよといわれましてね、残ったってえわけで」
「ふうん」
「だがね、十六になるお嬢様はある商家に身を寄せていて、肩身の狭い思いをなさっているんだよ、お可愛そうで」
「奥方様はどうしたね」
「お嬢様が二つの時に病でなくなりました」
「それは哀れだね」
「お家来衆もちりぢりだが、仇討ちの噺も聞こえてこねえわけでもねえ、だけど、難しいだろうや、相手は強ええ刀使いだ」
そのとき熊さんが思いついた。
「おれたちゃ強い助人を知ってるぜ、秋刀魚一匹で助けてくれるやつだ」
「そんなに頼もしい方がいるなら、なんかあったら頼みます」
老夫婦とそんな話をして、家の修理を終えた熊八と八五郎は長屋に戻りました。
それから一月ほど経ったある日のことでございます。
お武家さんのお宅の養生のことなどすっかり忘れていた熊八と八五郎のところに、あの家守の老夫婦がやってまいりました。
「おや、なんかしでかしちまったかね」
熊八がやり残しでもあるのかと心配そうにたずねますと、じいさんは首を横に振ります。
「いいや、腕のいい大工だと、直したあとを見た勘定方がおっしゃておったよ、今日きたのはそのことじゃあねえんで」
「また、どこか直してくれって言うのなら、親方に言ってくんねえ」
「そうじゃねえんで、この場所じゃあ言いにくいので中に入らせていただいていいですかね」
「へえ、きたねえところですんませんが」
熊八は八五郎の家の戸を開けました。八五郎の方がどちからというと整理整頓は得意のようです。それでも物が散らばっています。
八五郎の家で、卓袱台を前にして、四人が神妙な顔をしております。なかなか老夫婦が言い出さないのでそういう状態になったわけです。それでもやっとじいさんが話し始めました。
「こないだあ、ちょっと言った仇討ちのことでございますよ、とうとう、お嬢様の仇討ちのお願いがかなって、お許しがでましてね、ところが、お嬢様がたよりにしていた家老の十衛門様が急にお亡くなりになり、お年でしたので仕方がないのでございますが、頼りになすっていたもう一人の井三郎様がお許しがでたことを聞いて、お一人でことをしようとして返り討ちにあい、お嬢様一人になってしまわれたのでございます」
「それで、他のご家来衆はどうしてるんでえ」
「国に帰られ散り散りでございます、また、他のところで雇われた者など、どなたも助人になってくれそうもありません」
「このご時世だからな」
「それで、あなたさまがおっしゃった、秋刀魚一本で仇討ちを手助けしてくれる方がいるとのことを思い出したんで」
熊八と八五郎は内心こりゃあ困ったとうつむきかげんでございます。真剣なじいさんとばあさんの顔をみると、猫が助けてくれるとは言えません。
「それで、いつ、やるんで」
「あと二十日後の正午、代官様の立ち会いのもと、そのお嬢様が、あのえばった殿様とやるそうで、その殿様は腕が立つ人でとても勝ち目はないでしょう」
「助っ人はいいのかい」
「もちろんで、女子のこと、一人くらいかまわねえと思うがね、どう思いなさる」
どうも老人たちも仇討ちのことはよく知らないようです。
「あたしたちは銭も、力もないからねえ、秋刀魚で助けてくれるなら、頼めると思いましてね、藁にもすがる思いというのは、こういうことですねえ」
ばあさんも頭を下げました。
「さぞお強い方でしょうな」
「そりゃあ、もう」
そういう熊八の足を八五郎がつねりました。
「いてえ」
「なんでしょう」
あわてて熊八、
「いえ、いてえことには、その助人は忙しくてね、暇がとれるかどうかわからねえ」
「秋刀魚じゃだめなら、鯛ならどうでしょう、私らも鯛など祝言をあげたときいらい食べたことがない、でもお嬢さんのためなら、鯛の一匹ぐらいはなんとかします」
八五郎は頭を抱えて、
「そうだなあ、その助人に聞いてみらあ、だが、うんといっても、鯛が十三匹いるぜ」
「え、十三匹」
「鯛というからいけねえんで、でっかい魚一匹かもっと安い魚を十三匹にしなよ」
「なんだかわからないが、何がいいかね」
「どうだい、スルメなんて」
「スルメなら安いねえ」
「まあ、いいや、それより、その助人がうんと言うかどうかだね」
「ところで、そのお武家さん、なんていう方で」
熊八がつい「猫」と、声に出しました。
「え、猫」
「いや、猫左衛門さまだ」
「なに流の使い手で」
「うん、引っ掻き、いや、ひかき流である」
「それは、もしや、桧垣流じゃあないかね、なくなった殿の名前が桧垣史朗、すごい使い手でね」
「いや、それはねえでしょう、いやあるかもしれねえな」
八五郎、困ってそんな返答をしております。猫の助人だとは言いだせません。
「それでは、先様のいい返事をいただきたく、よろしくお願いいたします」
そういい終えて、二人は帰っていったのでございます。
さあ、困ったのは二人です。
「八、どうする」
「どうするったって、猫に出来るわきゃあないだろう」
「だがよ、相談してみねえとわかんにゃい」
「なに言ってるんだ、話してわかるかよ」
「こないだあ、わかった」
「でもよ、鯛をどうする」
「スルメじゃだめか」
「きっと首を横に振るよ」
「それも猫様に聞いてみよう」
てなことで、夕方、秋刀魚を焼いて、猫が来るの待っておりました。あのときから、秋刀魚を焼くと必ず巌生寺の猫たちがやってきます。見張っていないと取られてしまいます。
今日はあのボス猫の虎が顔を出しました。
「お、来なすったね、虎様、実はまた頼みがあるのだがね」
熊八が子細を話しました。すると、虎猫が肯いたじゃありませんか。
そこで、八五郎が、
「スルメでいいかい」と訪ねると、
「にゃんだそれだけか、それなら無理」と横を向きます。
「鯛ならやってもらるかい」
虎猫は頷きます。
そこで、八五郎が事情を話します。
「そんな、銭っこはねえんだよ、何とかスルメでやってくんねえかい」
虎猫も考えている様子。
その時、珍しく熊八がよいことを思いつきました。
「どうでえ、猫様、スルメと鯛の盗めるところを教えるってえのは」
「猫に鯛の釣り場を教えてどうするんでえ」
八五郎も怪訝な顔をしております。
「いやな、おれたちゃ大工だい、家の建前のあるところを猫さまに教えようというのはどうですか、猫様」
「なんだい、それは」
「必ず、鯛の一匹や二匹、神さんに供えるだろう、そいつを食ってくれと言うわけさ」
「なあるほど、熊、おめえさんにしちゃ、考えたね」
上棟式には、米、塩、お神酒、鯛、海のもの三種、野菜三種、果物三種をそなえます。海のものにはスルメも入っています。
なんと、虎猫は頷いて戻っていきました。
「でも、どうやって助太刀をしてくれるのだろう」
「そりゃ、あんときと同じで、猫さまにおまかせよ」
しばらくして、あの家守の二人がたずねてまいりました。
「おー、はなしはついた、スルメ十五枚だ、二枚増えたがどうだい」
「それはありがたいことです、して、来ていただけるのでしょうな、猫左衛門様は」
「それはなあ、内緒だ」
「内緒とは」
「そうだよ、その日になればわからあ」
ということで、二人はあまり納得していませんでしたが、ともかく帰っていきました。
「熊さんなぜスルメ二枚増やしたんだ」
「おれたちのだよ」
そして仇討ちの日になりました。
といっても、熊八と八五郎はそれを見に行くことができるわけではありません。家守の二人にしても同じです。
その夕方、家守のじいさんとばあさんが、顔をにこにこさせて、熊さんと八さんのところにやってまいりました。
「お嬢さんが無事に仇をうちました、どうもありがとうございやした。猫左衛門様のおかげです」
「そりゃあよかった、でどんなだったんで」
熊八と八五郎はほっといたしました。
「聞いてないのかね」
「ああ、猫左衛門さんは無口でね、にゃーんにもいわない」
「へえ、あっしらも、立ち会った方にお聞きしただけだが、仇討ち場に現れた殿様は両方の目の上に切り傷をこしらえていて、あまり目が見えない様子だったとのことでねえ、あの切り傷は桧垣流に違いないということでしたな、どこぞで前もって、悪殿に傷を負わせて下されたのに違いがない、その猫左衛門さんてなあすごい腕前だねえ」
「あたりめえだ」
「あ、ここにあります」と爺さんは、一五枚のスルメを熊八に差し出しました。スルメのことをあたりめとも申します。
「こいつは猫左衛門様に渡しとくからね」
「猫左衛門様に直接会ってお礼を言わなきゃなんねえけど、どうかねえ」
「それは無理だよなあ、熊さん」
「うん、猫左衛門さんは寺に引きこもっていらっしゃる」
熊さんにしては上手に受け答えをしたものです。
「お心を鍛えていらっしゃるわけですな、そんなわけなら、じゃまするわけにはいきませんな、よろしくお伝えください」
「爪を研いでいらっしゃるってわけで、またどうぞ」
「いえいえ、もう仇討ちはけっこうでございます」
じいさんとばあさんは頭を下げると帰っていきました。
夕方になると、熊八と八五郎は七輪の上にスルメをのせ、程良く焼けたところで猫たちに配りました。
その後、このあたりで建前があると、必ず供えた鯛とスルメが消えてしまうようになったという話でございます。
それは、神様が喜んでいるという証拠、縁起の良いこととして、その町では建前には、神様が食べやすいようにと、鯛とスルメを人目のつかぬところに置くようになったということでございます。
お猫さま 第八話 - 猫助人
私家版 猫小噺集「お猫さま 2017 一粒書房」所収
お猫さま:2017年度、第20回日本自費出版文化賞、小説部門賞受賞
木版画:著者


