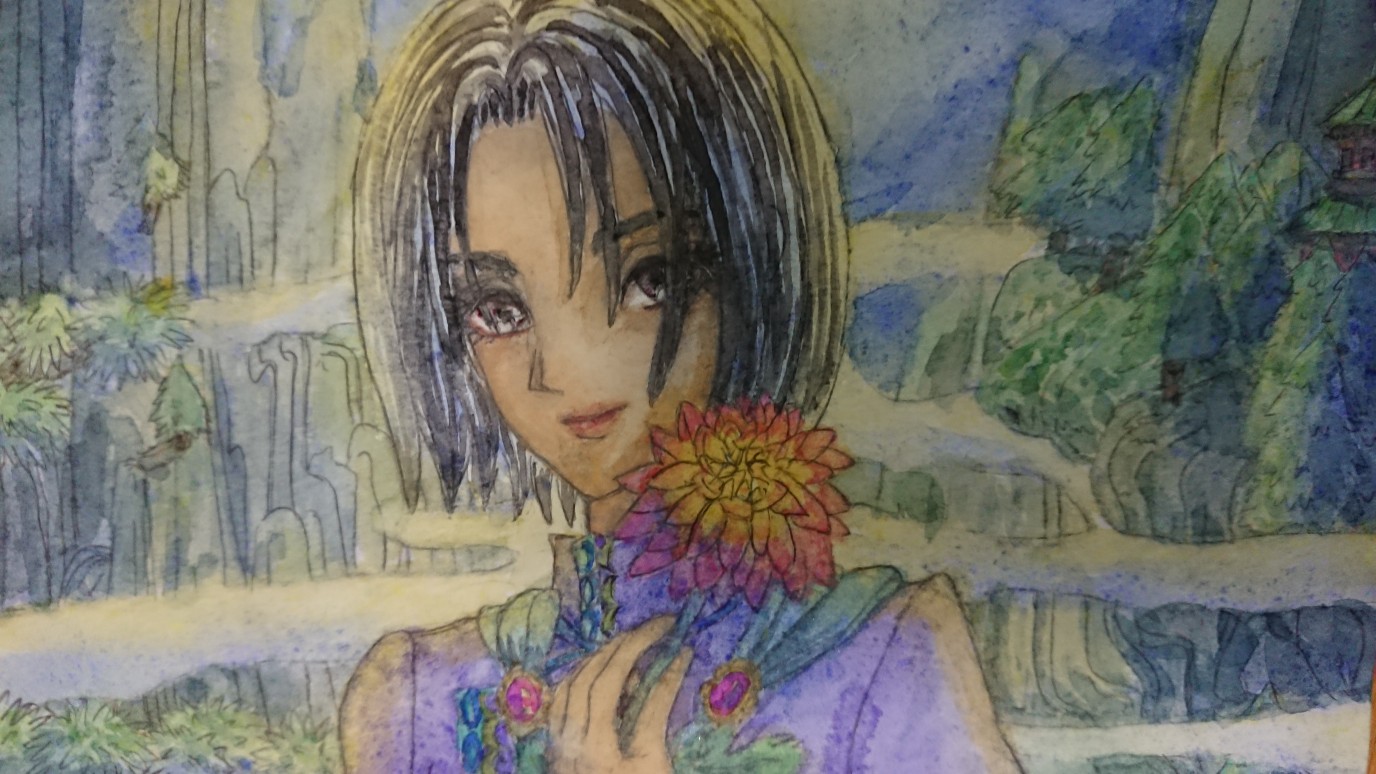
裸足の月
詩人が歌で戦う世界…。詩人のイサヨイは夜の森を歩いているときに、不意に襲う遅すぎる恋に慄きつつ歩いていた。そこで彼は人の体に取り憑いた月精、モチと出会う。彼女の語る言葉から過去の自分の運命を変えた悪魔の所業を悟るイサヨイ。憤りに溺れる彼は彼女と旅することになるが、自分の肉親も絡む策謀に巻き込まれ二人の女性の間で揺れ動いていくことになる。戦うことを忌み嫌いふらふらと揺れる彼に訪れる悲劇とは。吟遊詩人が主人公なので、作中歌にも注目していただきたいです。
第一話 遅すぎる恋と月との出会い
裸足の月
ユキノシタ・ユキワリ
第一話 遅すぎる恋と月との出会い
忘れたはずの、笑顔が浮かぶ。
月を見上げるその刹那。
一瞬前に無かったはずの、その存在が浮き上がる。
彼女はどういう名だったか?「サク」?そう言う名だったか?思い出の中微笑んだ、その眼差と目が合った。
時を隔てた重み分、痛み伴い射貫かれる、眩しく僕を見上げた笑顔。
遠い九月の陽の光。
まるで乾いた枯草に、野焼きの炎をおいたようだ。紅蓮の炎が燃え上がり、僕の心を這い舐める。
炎は後悔その他に、のどの渇きに似たような、体を苛む感情が、名前も持たずに含まれて、その勢いをいや増した。
一体どういうことなのか?今の今まで忘れていたのに。月を見上げるそれまでは、面影すらも抱いてなかった。
まるで矢のよう降ってきた、思いがけない再会だった、記憶の中の邂逅だった。
サク、そういう名の娘。付き合う前に捨てた女。僕の心が変わったことを、聡く感じて自ら消えた、恋仲とすら言えぬ娘。
あれから八年経ったこと、その欠落の大きさに、今更の様佇んだ。
呆然として佇んだ。
八年忘れていられるならば、一生だって忘れてられた。なのにどうして声すらも、便りも消えた今になり、こう鮮やかに蘇る?彼女の眼差し、髪舞わす凬、ほのかな香りも鮮やかに!
口づけさえも、抱擁も、交わしたことのない娘。もうとり返しも無い過去よ。
彼女は生きてこの中に、この僕の中に棲んでいた。何故今更に気づかせる!何故今更に、今更に!
僕は華(か)麻流(まる)へ行くために、魔安(まあん)の森を突っ切って、琉宇那(るうな)の支流をさかのぼり、夜通し歩いていたのだった。
不意に生まれた後悔と、この身を千切る恋情に、僕は唖然と歩いていたのだ。この足の歩み止めたなら、体の血潮が沸騰し、後先構わぬ手段に訴え、どうにかなってしまうだろう。
僕は暗闇見据えつつ、必死に心を御そうとした。僕は自分に問いかける、一体お前は何がしたい?これではさすがに遅すぎる、もう八年もっ経ったのだ!
僕は目の前暗い道に、全ての意識を向けようとした。つまずくことの無いように、迷ったりなどせぬように。
心はそれ程狼狽し、何時ものようには歩けない。綺麗に整備された道でも、歩きを始めた赤子のようだ。
ゆるゆる上る道をよろよろ、僕はみじめに歩いていた。短い草を踏みながら、全身からは汗が噴き出る。
見上げれば僕をあざ笑う様、稀に見るほど大きな月が、僕を煌々照らして笑う。
欠けることないその分に、皮肉に過ぎるその笑みだ。
出来ることなら夜のうち、魔安(まあん)の森は通りたくない。しかし生まれた激情は、僕にたたずみ休むこと、固く禁じて許さなかった。頭がどうにかなるならば、闇に喰われた方がましだろ。
止まるな、止まるな、休まず進め。頭の廻りを休めるな。足を止めたら囚われる。
僕は、心の命ずるままに、心細い灯を手掛かりに、夜の森へと分け入った。魔がうごめくと評判の森。
旅慣れていたはずだった。夜通し歩くも稀じゃない。この街道も整備され、広く平らに伸びている。
しかし心が生む闇は、人となりすら変えてしまう。僕は無様におののいた、何時もの剛毅な僕じゃなかった。
外には深い闇の森、心の内には遅すぎる恋。僕には二つの敵がいて、僕を破滅に導こうとする。
見上げると、木立の合間に満月が、僕を追いかけ微笑み投げた。
嘲笑ってると思っていたが、もしや保護してくれるのか、心細いこの僕の道連れ、買って出てきてくれるのか?
月とは何て気まぐれか?僕が求める役割を、察して合わせてくれたのだった。
僕は足元確認しつつ、ちらちら上を仰ぎ見て、右横を滑る満月を、脇見しながら歩いたのだった。
琉宇那(るうな)の支流はやがて蛇行し、その勢いを緩めだし、凪いだ景色を現していた。
川水は、静かに澱んで囁いた。
木の葉と花びら浮かべつつ、蒼白い月を影に映して、その下にまるで別世界、隠しているというように、波紋水面に立てていた。蒼い月放つ燐の光を、ちろちろ反射し手招きしていた。
人によれば、それは魔界の入り口で、罪にまみれた快楽と、挙句の果ての苦しみに、人を手招きするのだと、説教臭く説く者もある。
普段の僕なら笑い飛ばして、これは優美な妖精の、住処であると歌うだろう。僕に割られた歌の才、詩作の才を駆使しつつ、人をたらして歌うだろう。何を怖れることがある。
しかしこの時恥ずべきも、僕は怖れていたのだった。不意蘇る遅すぎる恋。
忘れかけてた誘惑が、彼岸の果てへの誘惑が、首筋に迫る蛇の様、きな臭い毒を吐いていた。
死の存在を意識すれば、怖れは身近に迫るもの。僕はあちらへ魅せられた分、死と闇を深く恐怖した。実に滑稽極まりなく。
それなのに、僕は闇を行くしかないのだ。己の自然に従えば。心の熱に従えば。
僕はむやみに闇を行く。獣を怖れ、魔物を怖れ、それでも空を飛ぶしか道無い、小さな小鳥のおののきよ。
きっと一晩経ったなら、僕は自分で馬鹿だと気づく。取るに足らない感傷に、浸り絡めて取られていると。
きっと一晩経ったら気づく。これは一時の気の迷い。朝の光が落ちたなら、この感傷も消え失せる。今生きているこの僕の、現実の中に戻るだろう。
ああそうだ、ああそうだ、それなのに、僕の歩みは勢い増して、月光の下をひた歩く。秋の始めの葉陰豊かな、黒々湿る森の中。明日になったら覚めるというのが、命があるとの前提なのに。
得体の知れぬ獣の、吠え立てる声を怖れつつ、闇に潜むという魔物、邪悪な奇跡を怖れつつ。
瞼に宿るその面影を、振り切るように、求める様に、忘れる様に、追う様に。
僕の心は矛盾に満ちて、全てを忘れるその為に、僕は勢い付けて歩いた。満ちた矛盾を解消するには、ただ歩く、そう、それしかなかった。
やがてどれほど行っただろう?琉宇那(るうな)の支流は淵に澱んで、甘く光を漂わせ、波紋を太い樹の根元、包んで夢見て歌っていたのだ。
その水際(みぎわ)、僕ははたりと目を止めた。
水死人が横たわり、腰まで水に洗われていた。浅黒い肌の若い女。
僕の鋭くなった胸、一瞬後に恐怖した。声も出せずに心で叫んだ。
しかし甘美に見惚れていた。夢の様、いいや夢にも見たこと無いほど、それは詩心くすぐる景色。
恐怖の分だけ目をそらせもせず、僕は呆けて眺めてた。
白い衣が水に漂い、体の線を浮かす様。
充実しきった肉体が、皮膚が光を受ける様。
彼女の安らかに見える表情、生まれる前に還ったような、幼い子供のような死に顔。
全てを見守り包むよう、月が光を降らせ続ける。闇に浮かんで発光する様、水死人が光を受ける。
月と彼女とその間、甘美で強い絆があって、示し合わせてそこに在るよう、動かせ得ない景色であった。
これは啓示か罠なのか、僕を異界へ導くための。
だとして視線を動かせぬ、魔界へ引きずり込まれようとも。
僕は呆けて眺めていた。
義務ともいえる感情が、不意に心に戻ってきた。僕も砂漠に生受けた、野蛮の民ではなかったのだ。
弔わなければならないだろう。身元も知っておいた方がいい。家族が探しているやもしれぬ。
僕は怖れつ近づいて、太い樹の根をまたがって、彼女を足元見下ろした。かがんで祈りを捧げようと、手を前に組んだその時に、不意に女は眼を開いた。
「やられたな。奴にかすめて取られてしまった。」
彼女は憮然とつぶやいて、実に不服というように、眉根を寄せて僕を見た。
「然体こんなに重い体で、ここを出るのは一苦労だな。おいそこの君、私を負ぶってこの森を出ろ。」
僕の舌根は痺れつき、ただこの瞼をぱちくりと、しばたかせるしかなかったのだった。
「おい聞こえてる?そこの君?体を負ぶって欲しいんだ。」
彼女はこのよう繰返したのだ。
僕は事実を飲み込もうとした。
つまり彼女は死人じゃなくて、ただそこで寝てただけなのか?
だが何の為?こんなに深く、闇にくるまるこの森で?気弱な男も寄り付かぬ、魔が住まうというこの森で?
「つまりその、君は寝ていただけなのか?死んでるように見えたから・・・。気を悪くしたりしないでくれよ。ただちょっとだけ驚いた。」
僕は彼女の気を害さぬよう、言葉を選んでそう言った。
「死んでいるといやそうとも言えるが、でもこの体は死んでいない。私の命も死んでいない。」
彼女はけろりとそう言った。まるで親しい友人に、説明する様(よ)な気安さだった。
そのわけ無いというその様が、僕を益々惑わせた。
「死んでいるのに死んでいないって?全く訳が分からない!」
僕は半分悲鳴になってた。早く答えを述べてくれ。僕の心は不安定さに、一刻も早い安心を、彼女の言葉に求めたのだ。。
「心臓だって動いているよ、君確かめてみるといい。」
彼女は強い腕を僕の、頭に巻いて抱き寄せた。林檎のような香りとともに、強く脈打つ鼓動が僕の、耳のしじまを満たして溢れた。
血潮が熱く脈打つことを、夏の光のような温度が、彼女の体に宿ること、稲妻の落ちる速さで知った。
「ああ生きている、確かにそうだ。君は生きてる人間だった。」
「だが人間として死んでいる。」
彼女は僕にそう言った。
「この肉体を持っていた、この年齢まで生きていた、この人間は死んでいる。」
謎のるつぼに突き落とす、言葉を彼女はそう告げた。僕の頭の混乱は、僕から言葉を奪ったのだった。
愉快な様子で彼女は言った。
「人間としては死んでるが、この肉体は生きている、私の命も生きている。これが意味するところが分かるか?」
僕は痺れた舌でようやく、こういう答えをつぶやいた。
「つまりは人じゃないということ?君は人ではないということ?」
「半分だけはご明察。この肉体は人間だ。」
僕は慄き半歩後ろに、後ずさりして彼女を見たのだ。彼女はくすりとほほ笑んだ。悪戯した子がするような顔。魔が住む森の眷属なのか?
「私は月精、月魄(げっぱく)ともいう。只今これなる人間の、体の中を間借りした。」
僕の恐れはいったん退いて、光に属する者に対する、本能的ともいえる様(よ)な、安心を甘く抱いたのだった。
「ああそうだ、いつか古老が言っていた・・・。」
月の主の眷属は、人の体に宿ることもある、生まれ変わりのその為に。祖父の知音のその翁、幼い僕らにそう語った。
「つまりこれなる肉体は、『月憑き』、そういう状態に、なって命を落としたと?」
月精は、三十年に一度の周期で、生まれ変わりを繰り返す。人の命を食らいつくして、それを糧としまっさらな、無垢な命を繰り返すのだと。その為に、月精たちは人間の、若い女に取り憑くと。
月に憑かれた娘御は、暗い水辺へ行くという。月精たちはそこで命を、贄に奪って蘇る。つまりは憑かれた人間は、死に至るというその伝え。
「如何にも、私はこれに憑いた。だかそれだけではこうならぬ。私は贄を逃したのだよ。『奴』に横取りされたのだ、この肉体に宿る魂。」
彼女は憤然そう言った。実に不服というように、憮然とした顔声色で。
彼女はすっくと立ちあがり、木立の合間に降りしきる、蒼白い月を受けていた。月と彼女の間には、確かに妖しい力が行き交い、その年齢の女性に受ける、一般的な印象を、僕は全く受けられなかった。超自然である存在と、確かに僕はやり取りしていた。
「『奴』とは一体誰のことだい?」
僕は素直にそう聞いた。希望に応える気が固まった、彼女の答えのその如何。
僕は畏れと恐怖とに、すっかり魅了されていた。小一時間前予想もしない、不思議不可思議運命の、導きはたまた暗転なのか。
「『奴』とは悪魔という奴だ。月精たちの間では、『コレクター』とも、呼ばれているな。奴に私が眼を付けていた、この肉体の魂を、横取りされて奪われた。三カ月ほど探しに探して、やっと見つけた上物なのに。」
彼女はまるで友達に、気になる男を盗られた話を、あけっぴろげに話すよう、僕に対してまくしたて、その最後にはにやりと笑った。
「つまりはね、今の私はこの体、その中でしか生きられないのだ。この肉体に閉じ込められた。人の体は重いんだねえ。この闇の森を抜けるのも、この肉体を引きずれば、きっと二晩かかってしまう。
もう一度言うよねえ君よ、私を負ぶってこの森を出ろ。立っているのもおっくうだ。」
僕は彼女の言うがまま、彼女を負ぶって森を歩いた。踏み固められた道だって、人一人負えば険しくなる。
灯りは彼女が持っていた。それが無くても月精の、彼女の周りの闇たちは、進んでその身を隠すのだった。
僕らの周りをぽっかりと、月の光が守っていた。僕が彼女の重さ分、難儀を感じるその分は、月の光が僕を助けた。
それ以外、僕に利点があるとして、妖しく不気味な夜の森、話し相手が出来たこと。僕は心の細さに任せ、問わず語りを口にした。ちょうど心を占めていた、思い出の中のサクのこと。出会った村のその様子。
「彼女とは、浮(ふ)衛(ぇ)蛾(が)利(り)の州の村で出会った。初めて会ったその晩に、彼女は社の軒先で、十三の月を眺めていたのだ。
頬杖ついて、丸い目を、黒い葡萄のような眼を、渇望する様見開いて、一途に月を眺めていたよ。あんまりずっと眺めてるから、僕はこの様声をかけた、『あんまり見ていると憑かれるよ』。
ああその時のサクといったら、戸惑い、恥じらい、驚きに、泣き出す程の嬉しさを、無理やり収めた様な顔して、何にも言わず去ったのだ。」
「ふうん、浮(ふ)衛(ぇ)蛾(が)利(り)の州でねえ。」
月精はそう相槌打った。彼女の豊かな肉体が、僕の背中に押し当てられてる。僕は心を遠い日の、思い出の中に追いやった。彼女の体を感じつつ、サクの想いで語るのは、何だか罪深く思えた。
しかし彼女の肉体は、僕の重しであったのだ。心が過去へと流れ去り、今が虚ろにならないための、辛うじてその重しであった。彼女の体に触れること、僕を今へと繋ぎ留める。
「その村の、住民たちが彼女に取った、扱いはとても奇妙だったさ。確かに見えてるはずなのに、いないみたいにふるまっていた。まるで彼女が幽霊か、空気であるというように。一っ言すらもしゃべらない。彼女も決して声を出さない。
疑問に思い尋ねたが、黙ってはぐらかされるだけ。結局事の真相を、聞き出せたその相手とは、よそから何度も訪れた、その地を良く知る旅人だった。」
「大体想像ついてきた。その風習なら見聞きしたことある。」
「西から降ろして吹いて来る、嵐の神を鎮めるために、彼女が十二のその年に、花嫁として捧げたのだと。その風習を知っているのか?」
背の月精はこう言った。
「神にささげた花嫁は、人とは違う世界に住まい、姿や声も感じずに、気配も匂いも感じない、そういうものと扱うと。
あれは無意味な風習だ。」
僕は答えてこう言った。
「無意味というより酷いと思う。彼女の家は貧しかった。兄弟の数も多かった。村に水害迫った時に、親にはそれを拒めなかった。彼女の親は辛かったろう。己の貧しさそれ故の、娘の扱いそれを見るのは。
一家は他へと移ったそうだ。目にするだけでも切ないと。ただ見ているのは切ないと。振り切るように他所へ行ったと、サクはそう言い泣いていた。」
僕は吐き出し押し黙った。彼女を捨てたこの僕に、彼女の親をとやかくと、責めごとを言う資格はない。
しかしその時忽然と、僕は疑問を抱いたのだ。一体何があったから、何がどうなりこうなった?どうして心は変わったか?あんなに一途に惹かれていたのに。あんなに短い期間のうちだ。
僕の頭に靄がかかって、事実が曖昧模糊として、整合性を欠いている。
「僕は眼で追う様になった。誰も見ぬ振りするサクを。視界の端に探し求めた。彼女は決して口利かず、社に捧げる供物を食べて、人の世界とかぶらぬように、人の視界のその外に、紛れるように生きていた。
僕は何度も話しかけ、説明できないときめきに、急かされる様笑顔を向けた。人が見てないその時に。誰か見てたら返事も出来ない、それは確かにそうだった。
しかし人気が無い時も、彼女は口を利かずにいたのだ。何に義理立てしていたか?
どうしていいか分からなかった。僕も少年だったのだ。僕はどんどん焦れていた。二十六夜になる頃に、その地を発たねばならないはずで。」
僕は記憶の糸をたどった。編地の糸を解くように、それの続きを追いかけて、順々とそれを整理した。
「君はその子を連れ出せたかい?」
月精はそう僕に尋ねた。
「今宵発たねばならぬ晩、僕は必死にこう言った。策を練るには若すぎて、口説く文句もひだがない。全く直情的過ぎた。
『もしよかったら一緒に来るかい?この山脈さえ超えたなら、そういう馬鹿げた風習は、誰も知らない土地へ出る。そこで生きてはみないかい?』
今にしてみれば僕の心を、心に燃える恋情を、全く伝えていない言葉だ。これじゃあただの親切心か、同情とすら取れる言葉だ。
だがサクはそっと微笑んで、黙って僕についてきた。僕と一緒に山脈を、越えて平野に降りてきた。
そう、山を下りて初めて聞いた、彼女の声を、語る言葉を。」
ここまでは、記憶は確かに整合している。だがその後にどうなった?何が一体どうなった?
「その後は、一体どうなったのだろう?記憶がそこから霧がかってくる。あんなに一途に惹かれてた、サクをどうして今夜まで、思い出せない、それが知れない。」
「君の頭に仕掛けがあるな、誰かが仕組んで仕掛けたやつ。しかも忌々しい気配。解除してみていいかなあ?辛くなるかもしれないが、きっと理由を思い出すよ。」
背の月精がそう言った。
誰かが何かを仕組んでいると?一体どういう目的で?
思い出したら辛くなる、それも予想がついたのだ。僕は何かの罪を犯した。サクに対する重大な。
僕は一瞬逡巡した。だが遅すぎる恋が勝(まさ)った。どうしてサクを忘れたか?それだけが心支配した。
「お願い頼むよ、月の精。」
僕は彼女にそう言った。
月精は、僕の頭に息をかけ、右手でそっと撫でたのだった。
瞬間強い土砂降りが、降り敷くような心地がし、一瞬後に静まった。すると今まで覆った靄は、きれいさっぱり消えていた。
後悔してもしきれない、過去の出来事成り行きを、僕は辛くも思い出した。
「ああそうだ・・・・。」
僕は茫然つぶやいた。
「麓に降りて二月したころ、金の瞳の美女に会った。そいつが僕を誘惑したのだ。
一体どういう名だったか?顔立ちすらも思い出せない。あんなに惹かれたサクから僕を、確かに奪った女だったに。
つまりはそういう成り行きだった…。僕の心が変わったことを、サクは黙って知ったのだ。
二月一緒に旅したが、まだ全くに進展せずに、二人は清いままだった。
ある晩明けて部屋からは、きれいに荷物も消えていた。僕は感慨すら起こさずに、黙ってそれを受け入れた。
一体どういうことだろう!こう何年もたってから、これほど辛く思い出すのに、その時の僕は心も痛めず、黙って素通りしたなんて!」
僕の言葉は最後には、自分とその存在さえも、はっきりしない誰かに対して、激しく怒って憤った。
いいや存在さえも確たる、証拠のないその誰かに対して、怒るというのは罪負いたくない、言い訳でしかないかもしれぬが。ともかく僕は狼狽し、向けどころのない怒りを激しく、自分に向けてぶちまけた。
「その女、金の瞳の美女とはその後、一体どこまで付き合った?」
背の月精はそう言った。
「その後一月付き合った。僕が大人になるうえで、最初の女性であったのだ。だが一月後、彼女は死んだ。理由は全く分からない。朝起きたなら冷たくなってた。」
「君は今まで忘れてたのか?普通なら、サクよりそっちを引きずりそうだが。それに名前も覚えてないと、顔も覚えてないなんて。最初の女を覚えてない?そいつは不自然過ぎるがね。ほんとに今まで忘れてたかい?」
そう月精がからかうように、僕に確認したのだった。
「忘れてた。ほんとに覚えていなかったんだ。自分で不自然そう思う。
君がそう言うからにはさ、心当たりがあるのかい?理由に覚えがあるのかい?」
僕は恐る恐るといった口調で、彼女に尋ねてそう言った。
「心当たりあるよ、偶然に、私と同じ敵だな。」
そう月精は言ったのだった。
「『奴』が頻繁使う手だ。そうやって、人を傷つけようとする。傷つけ命を捨てるよう、そう促して追い立てる。
つまりはさ、君のサク、その子はさ、『奴』に眼を付けられてたんだな。」
『奴』!つまりは悪魔というもの、背の月精の贄を奪った、得体の知れない存在が、僕からサクを奪ったという!
僕は驚愕目を見開いて、足に彼女の体重の、重みを受けて立ち止まった。
背の月精は右肩を、叩いて僕を促した。足の歩みを止めるな、そう言う。
「『奴』がねえ、何故『コレクター』とも呼ばれているか。あいつはそれを趣味としている、傷つき壊れてひびの入った、人の魂集めるの。
これと狙った人を追い詰め、自ら命を絶つように、仕向けて離れた魂を、奪ってコレクトしてるんだ。
私が今いる肉体の、主も奴に奪われた。どちらが先に眼を付けたかは、今となっては分からぬが。きっとあいつの興味を良く惹く、ひび割れ壊れ方だった。
君のサク、彼女は君と出会う前から、傷つき壊れ続けてきたよね?だからあいつがずっと前から、眼を付け狙ってきたんだろうさ。
だからさ、君が彼女の前に、現れ救いが見えかけた時、あいつは邪魔が入ったと、きっと汚くそう思ったろう。
そういう時によく使う手だ。金の目の美女は奴の人形、魂虚ろな眷属だ。ほんとは生きてもいない者。サクから君を奪うため、差し向けられられた罠だったんだ。」
僕は呆然佇んだ。彼女が肩をたたくのも、全く分からぬそのくらい、痛みが体に溢れていた。
「サクは一体どうなったろう・・・?」
僕はぽつりとこうつぶやいた。意志も自制も利かない本音。ただそれだけが気になった。
「それは一体何年前だい?」
背の月精はそう言った。
「もう八年も経つころだ…。」
「それじゃあ多分今頃は、その娘っ子の魂は、コレクションのその一つだろうさ。」
彼女はさらりとそう言った。僕は黙って突っ立った。風が冷たく汗を冷やした。
この世にはもうサクはおらず、体は土に還ったことが、あの世の主の元でなく、邪悪な悪魔の蒐集品に、その魂が奪われたこと、卑怯な罠に自らが、はまりそいつを許したことが、それの全てが悔しくて、僕の目からは涙があふれた。
背に月精を負ったまま、僕はがっくりひざを折った。吹く風も、降り敷く月の光さえ、この僕のことを責めている。
「その『サク』の、彼女を想いだしたのは、ここいら辺に近くなってか。それはあいつがそばを通って、術の一部が飛んだんだろう。半端に外れて記憶が戻った。そいつが全く悔やまれる。それでなければ君も今更、こんなに悩むことも無い。」
へたった僕の背からも降りず、月精はそう言って笑った。まるで試しているように。
「いいや全く悔やまない。僕は覚えていたかったんだ!忘れるなんてまっぴらだ!
その『奴』の住処一体どこだ?行って必ず取り戻す、サクの魂その住処から!そして正しくあの世の主に、託して納めてあげるとも。そいつが僕の罪滅ぼしだ!」
うずくまって泣きながら、僕は見上げて睨みつけた、見たことも無い悪魔に向かって。
僕とサクとの運命を、身勝手な趣味で狂わせた、卑劣なあいつ、『コレクター』!
考えてみれば今更に、それを仕遂げて何になる?サクは戻ってこないのだから。すでに時間は長く経ち、取り戻すすべ失われ、僕の立場も変わっているのだ。
だがそうと思い込んでいないと、僕の心は押しつぶされて、これからの時を後悔で、喰いつぶしてしまうそれ程に、遅すぎる恋は重かった。この想い出は重かった。
背の月精がふっと笑った。軽い吐息を漏らしつつ、日差しのような体を放して、とんと地面に降りて言った。
「そうと決まれば君は同志だ。私の贄を奪って行った、奴に敵対する相棒だ。
これから先は自分で歩くよ。私は私の足で歩く。二人とも、両手を開けておかねばな。」
僕は意表を突かれたまんま、黙って彼女を見上げ観た。髪の縁を、蒼白い月が舐めていた。雲がするする伸びて満月、レースの向こうに遠ざける。
「お前と協力し合いながら、サクの魂取り戻すのか?」
うずくまるまま僕は聞く。月精は軽く微笑んで、僕の頭に手を置いた。
「もちろんだとも、その通り。私にしてもこのままじゃ、命をつなぐ手が無いよ。一人でやるのも難儀だからね。戦力は、なるべく多い方がいい。
私のことはモチと呼ぶんだ。望月のモチ、モチヅキじゃ、長くて呼びにくいだろうからね。」
「モチ?」
「そうモチと呼べ、これからは、協力し合ってあいつから、互いの欲しい魂を、奪う戦いしようじゃないか。」
月精、いいや、モチ、彼女、そう言い僕を覗き込んだ。僕はぽかんと彼女を見上げ、一瞬黙って逡巡したのだ。
言いたいことは分かる、だが、果たして勝算あるだろうか?仮にも悪魔が相手であるのだ。僕は無謀に心を吐いたが、出来ると思って言ったのじゃない。僕はこの身を捨てるつもりだ。
だがモチが言うは当たり前、完全勝利を目指すかのよう。身を削らずに勝ちだけを、甘く手中に収めるつもりか。
「君と組んだら出来るかい?この僕にだって可能かい?」
僕は瞳に力込め、モチを見上げてこう言った。超然たたずむ彼女を見てると、信じる気持ちが湧いてきた。
「多分可能だ、きっとねえ。私も少しは魔力があるし、第一君は詩人じゃないか?当節詩人は強いんだろう?その鍾(しょう)琴(きん)は飾りかい?」
全く涼しく彼女は言った。僕は急激砂を噛む様(よ)な、憤り怒り湧いてきて、噛みつくように彼女に言った。
「僕は歌では戦わない!」
「ふうん、そうかい。」
モチは言った。
「まあいい、君がどうしても、叶えたいことがあるとしたなら、手段なんぞは構わないだろう。言っておくけど『奴』のこと、あんまり舐めない方がいいがね。
しかしそういう訳であっても、望みが少ない訳じゃないかな。あいつが集めたコレクション、数限りなくあるんだし。一つぐらいは目こぼしあるかも。ああいいや、私と合わせて二つだったか。」
モチはこう言い微笑んだ。少し哀しくも見える微笑み。
圧倒的な充実感に、哀愁さえも漂わせ、月を背負って彼女は歩く。ああ間違いなく月の精、まぎれもなくも月の子だ。
「情けにすがるその他に、道はないほど『奴』は強いか?」
僕は素直にそう聞いた。多分そうだと言うだろう、それを聞くためそう聞いた。
「君の実力次第だよ。」
表情変えずモチは言った。
「運にもかなりは左右されよう。こういうことは運命だから。」
サクの魂戻るのも、自分の贄が戻るのも、全ては気まぐれ運命の、気分次第とそう言った、彼女はまるでささやくように、全てを達観したように、それでもちっとも諦めず、僕に答えをそう告げた。
僕は体に力込め、強い決意を口にした。
「分かった行こう、これからは、この僕は君の相棒だ。目的遂げるその日まで、友情以上を誓おうか。」
「そうと決まれば話は早い。これから一緒に『奴』を追うか。奴の居場所は目星がついてる。『奴』が長年巣をつくるのは、大分西の渓谷沿いの、小さな国であるという。奴の気配は記憶してるし、確かに気配は西から呼んでる。」
そう言いモチは僕に手を、右手を差し出し微笑んだ。あのどこかしら哀し気で、達観した様な顔して。
ぼくはしっかり握り返して、覚悟を決めて微笑んだ。諦めないという意思を、瞳に込めて微笑んだ。
モチに引かれて立ち上がり、僕は彼女を見たのだった。改めるよう見たのだった。
完璧すぎる肉体だった。この持ち主の心壊れて、悪魔に狙われてたなんて、想像出来ない肉体だった。
そんな体に月精が、モチが宿っていることで、それは益々完璧だった。強く豊かで朗らかだった。
彼女が光であることは、黙っていたって誰にも分かる。欠けること無い光の女。
僕は足下を見下ろした。影は一体どうなってるか、それが少しく気にかかり。
影は普通の人の様、月と灯りを背に受けて、二つ滲んで伸びていた。
僕ははたりと目を止めた。彼女は靴を履いていない。柔らかそうなかかとをさらし、踏みしめられた道にいた。
「靴は一体どうしたんだい?長旅をするその時は、丈夫な靴が必要だ。森を抜けたら手に入れないと。応急的に布でもまこうか?」
モチはハハハと笑い出した。
「月精に靴は必要ないよ。裸足でいるのが信条なんだ。靴とはしがらみそのものだ。縛られるなんてまっぴらさ!」
モチはそのままスタスと、僕に先立ち歩きだし、右手を振って僕を呼んだ。
「さあ行こう、我が相棒よ、一両日に森を出よう。」
「足が痛くはならないのかい?君の体は人間なんだよ。」
「ならない、ならない、ならないよ!」
モチは手を振り笑っていた。超然とした明るさで、転がるように笑っていたのだ。
その晩僕に相棒が、欠けること無い相棒が、確かに出来た瞬間だった。
彼女が何をもたらしたのか、僕から何を奪ったか、問わず語りに語ろうか、裸足の月のその顛末を。
第二話 「生まれ行く感情と戸惑い」に続く
第二話 生まれ行く感情と戸惑い
第二話 生まれ行く感情と戸惑い
僕らは順調森を行った。魔物はおろか盗賊も、獣とだって行き会わなかった。まるで彼女の存在が、護符でもあるという様に、全ての禍(わざわい)悪運は、僕らを避けて通っていたのだ。
森を抜け出た僕たちは、琉宇那(るうな)の河をたどりつつ、架(か)弦(げん)の国の辺境へ、足を踏み入れたのだった。
国境沿いの城門で、僕らは全く念入りに、入国のための審査をされた。詩人の僕は特に詳しく、持ち物全てをチェックされた。「虹金剛」も持ってないのに。痛くない腹も探られて、氏も素性も根掘り葉掘り、嫌になるほど言わされた。
戦の噂が流れていた。仗(じょう)弦(げん)国との戦の噂。
二つの国の王子たち、一人の姫を争って、愚にも付かない痴情のもつれ、国と国とに持ち込んでると。
そのことのために民草が、被害損害被るの、許せないよと僕は言った。
「でも君は詩を歌うじゃないか?そのお話は格好の、歌の題材なんじゃない?叙事詩の類の恋を省けば、無味乾燥になるだろう。分らず言っているわけじゃないよね?」
モチはそう言い試すよう、僕の瞳をのぞき込んだ。
「歌と現実とは違う。戦いなんて歌の中だけ、夢見てるだけがいいんだよ。現実なんて醜いものだ、世界のありのままなんて。
それでも歌は美しくする、醜い生(なま)の現実も。うんざりする様(よ)な世界でも、耐えてみるよう思えてくるのだ。歌とは本来そういうものだよ、だから歌いで戦うなんて、僕は絶対認めないんだ。歌に対する冒とくだ。」
僕は彼女にそう言ったのだ。そいつが僕の信念だった。それをよすがに生きてきたのだ。
「君はずいぶん頑固なんだね、人は見かけによらないね。」
モチはそう言い苦笑した。
市内に入城した後で、モチは衣を改めた。白い晴れ着を売り払い、男の服を買い入れた。
彼女がそれを着て出てきた時、僕はなんだかときめいた。
そっけないほど飾り気のない、男の服を女が着たら、普通は魅力がそがれるが、モチの光と逞しさ、それらを服が強調していた。それほど似合ってふさわしく、馴染んだ様子に見えたのだ。
「これで素敵に動きやすいな。ひらひらするのは苦手だと、昨日一昨日始めて知った。」
「服を着たのも初めてだったろ?月精たちは裸なのかい?」
僕は高揚隠すよう、軽薄浮調にわざと言った。思い出の中のサクを相手に、決して言わない言葉を吐いた。
「それがエロスと言うものか?人の男は汚らわしいな。そういう穢れた感情を、必要としない霊体なんだ。人の基準で言わんで欲しい。」
僕らは軽口たたきつつ、街で束の間休んだ後で、西へと向かって旅を続けた。モチ言う『奴』のその気配、西の方から呼んでいた。
道すがら、僕は詩人の本業で、歌を歌って路銀を得ていた。
当節戦わない詩人、随分軽く見られてて、幾らか悔しい目も見たりした。
「歌の力が無いからさ。蚊の泣くような声で歌って、虻より弱い幻影が、蛾よりも儚く戦うんだろ。」
そう言う陰口すら聞いた。
僕は黙って聞いてやった。聞いて聞かないふりをしていた。
そんな程度で崩れる様な、信念なんかじゃないのだと、モチには確かにそう言った。彼女は黙って聞いていた。
だから分かってくれているのと、僕はてっきり思い込んでた。
だから小さな村で起こった、あの出来事には驚いた。
彼女は僕に、禁破らせた。半分だけといったって。
僕は久々幻影を、この喉の奥、呼び出したのだ。
件の村に着いたとき、僕らは即座に依頼をされた。毎年秋に現れる、盗賊討伐その依頼。心底困り果ててると、平伏しながら頼まれた。
僕らはこの時たまたまに、路銀が多く必要だった。西方の山を越えるため、装備が多く必要だった。
「ご依頼には添えられません。僕は歌では戦わないのだ。虹金剛も持っていないし。」
僕はそう言い固辞をした。
「石なら村で確保してます。お望みならば差し上げましょう。どうかどうか、お頼みします。」
村人はそう頭を下げた。
僕の背筋に怒りが上り、顔が青ざめこわばるの、確かにモチは見てたのだった。
「いいじゃないか、依頼を受けよう。要するに、賊さえ倒せばいいんだね。歌う歌わぬそこじゃない。
イサヨイは、私を忘れているのかい?私は君の相棒だろう?どっちが賊を退治しても、入るお金の懐は、二人一緒、そうだろう?}
モチはそう言い、試すよう、僕の瞳をのぞき込んだ。
こういうことに僕は弱い。モチに全てを見透かされ、心を裸にされてるようだ。心のうちに巣くってる、下心だとか功名心とか、狡く他人を見下した、うぬぼれた部分見られているよう。
僕は承諾したのだった。結局に、歌わなければそれでよかった。モチの言葉の通りだった。
僕らは装備をそろえてもらった。心づくしの食事も受けた。
モチは前金所望して、村の長から受け取った。その夕がたに僕らは発った。村のはずれの放牧場。石積みの、低めの柵の入り口に。
月が煌々照っていた。あの晩よりは黄色くて、艶を増し行く半月だった。モチと出会って八日経ったの、僕はそこから知ったのだ。
「なあモチ、何か勝算あるのか?昼間こそこそ仕掛けてたろう?君は一体どうするつもりだ?」
僕は尋ねてこう聞いた。
「直前までは秘密にしとく。それでもさ、君は私を見直すよ。」
僕らは村から伸びている、街道沿いに身を潜めた。切り立った、崖の向こうの山奥から、決まって収穫済んだころ、図ったように現れる、賊を待ち伏せするために。
崖の下には放牧の、牛の畜舎が暗い中、むんとする様(よ)な臭いを放ち、その存在を主張した。
モー、モー、牛が鳴く。これから起こる惨劇か、はたまた茶番の目撃者なのか。
「静かだな、不気味なくらい。」
僕は言った。
「だがもうそれもお終いだ。向こうの方から金属音が、確かにこっちに近づいている。」
モチはけろりとそう言った。
「ねえモチ本当に大丈夫かい?僕は信じていいんだよね。」
「君にとっては訳ないさ。これを使えばいいだけのこと。」
そう言いモチは袂から、白く輝く石を取り出し、僕の右手に握らせた。
「これがいわゆる虹金剛か。何だか魂みたいだね。波動が大分似ているね。」
「君は一体何を聴いてた!僕は歌では戦わない、何度も何度もそう言った!」
僕の頭は瞬間に、動揺そして憤りに、泡立ち悲鳴を吐いたのだ。
「手段を選ぶ余裕はあるかい?二人が置かれた状況を、客観的に見ていたら、そういう甘えも言ってられない。」
「昼間一体何をしていた!僕はてっきり君が何か、勝算のある準備をしてる、そう思い込んでいたんだぜ!」
「戦わないうち私に頼るか?手は合わせたら四本だ、四本だけしかないんだぜ!私が使って君が逃げれば、たった二本になってしまう。」
僕らはその場で言い合った。互いに一歩も引かない構え。だがどうしても旗色は、あちらの方に分があった。
モチが正論言っているの、この僕にだって分かっているのだ。僕が言うのは理想論、手を汚すのを良しとしない、半人前の考えだ。
だがこの時までこれをよすが、心の支えに生きてきた。この考えが無かったら、僕は全く違った所で、違う人生生きてただろう。
サクともモチとも出会えなかった。今の自分を否定して、裏切ることになってしまう。
そうこうしてると僕の耳にも、大勢の者がざわついて、武具をガチャガチャ言わせつつ、こちらに歩いて来る物音が、確かに聞こえてきたのだった。
「さあどうするね?イサヨイよ。君はこれでも戦わないか。か弱い私がここで手籠めに、されているのを見ているだけか?こんなんじゃ、サクのとこにもたどり着けない。」
僕はぎりぎり歯を噛んで、必死に頭を巡らせた。
「要するに、戦わなければいいんだよ。歌いはしても戦わない、これなら自分をぎりぎり許せる。」
僕はすたんと地に坐した。右手に握る虹金剛、膝上に置き背に負った、銀の楽器を構え直した。
僕は歌いを始めたのだ。東の果てより押し寄せた、魔の軍勢から国を救った、ムトゥワレ王の物語。
王の十二の旗将の戦い、勇猛果敢な武勇伝。
「女神シパより生まれたる、ネの将軍は鏑矢を びょうと放って開戦の 合図を味方に示し知らせた
何となれば敵の魔物ども、戦の礼儀も無視をして 好き勝手てんでばらばらに、雄叫びあげて押し寄せる
シンガイ君の二の息子 ウシ将軍は屈強の 勇士を百人従えて 谷間の周りを水も漏らさず 蟻一匹も漏らさぬ構え 盾を構えて封鎖した 相対するは 夢魔の王 ノキジの羽持つ影の軍 両者はばっとぶちあって 漣のように泡立った
星散るように両の命が 赤と黒の血に飛び散った ウシ将軍はその父の 武勇の伝を再演された
ロナンの息子 トラ将軍は 一騎当千 敵も無し 精鋭部隊を引き連れて 谷間の真ん中矢のように 一散抜けて突っ込んだ 造り豪華な金の鎧 翡翠の飾りを兜に飾り その精鋭の先鋒を 将軍自ら務められた」
僕は久々幻影を、この声に乗せて呼び出した。
少しは怖くもあったのだ、やらないのでなく出来ないのだと、何度も陰口叩かれた。
僕が避けてるそのうちに、実際出来なくなったのだとは、この僕にだって思いたくない。
尚更今この状況で、僕が出来なきゃすべては終わる。サクには到底たどり着けない。
だから発する歌声に、白く輝く幻影が、歌に歌った戦の様子、再現しながら現れ出た時、僕は素直に嬉しかった。
古に聞くシンガイ王の、雄軍たちが現れて、歌の通りに叫ぶさま、蹄の音や鎧の響き、全てを大気に放ちつつ、僕の頭上に立ち上がり、弧天に向けて昇るのを、僕は高揚しながら見ていた。不思議なことに胸が躍った。
「詩人だ!詩人がいるぞ!」
賊の誰かが叫んでた。
僕は尚更歌いを強め、数限りない軍勢を、月下の大気に放って撃った。
盗賊たちのおびえや怖れ、引き出すために、戦わず、この場を退いてもらうため。
「怯むな!怯むな!」
誰かが叫ぶ。僕はこっそり口を噛んだ。そうは上手くはいかないものか!
突如破裂の音がして、赤い火花が背後に散った。
「そうれ!走れ!」
モチが愉快にそう叫んだ。彼女は牛舎の木の柵を、強い力で外していた。
音に驚く牛たちは、悲鳴を上げつつ走り出した。猛牛というその勢いで。そのまま道なり駆けあがり、盗賊たちに突っ込んだよう。
崖の向こうの賊たちの、慌てた悲鳴が響き渡り、しばらくバタバタしていたが、人の叫びも牛の叫びも、どんどん遠くなっていった。
僕は呆然立ち上がった。幻影はもう消えていた。
厩舎の前にモチがいて、機嫌よさげに微笑んだ。
「案外簡単だったろう。心の壁は越えられそうか?」
「君は火薬を仕込んでたのか。」
「保険は賭けとくものだから。力を合わせて頑張った、そういうことにしておこう。」
モチはこちらに歩み寄り、目の前に落ちた石を拾った。
「こいつはもらっておこうよね。くれるというならもらっておこう。次もあるかもしれないし。」
僕は黙ってそれを見ていた。
一頭の、牛が群れから取り残されて、所在なさげに僕らのそばに、たたずみ鳴き声漏らすのを、モチは認めてこう言った。
「この牛を連れて行こうじゃないか!売り払ったら謝礼の三倍!賊は撃退したけどね、こちらも逃げた、そうしよう。この牛は賊が連れてったのと、そういうことにしておこう。」
「それは彼らに悪いだろうさ・・・。どちらが賊か、判らなくなる。」
僕は戸惑いこう言った。
「いいじゃないかい?目的のため。主も大目に見てくれるのさ。」
モチはそう言い印を切った。月に向かって印を切った。
下弦の不安な半月も、もう段々と西に近く、夜明けが近いそのことが、僕を尚更戸惑わせたのだ。
月が沈んでいく気配、僕の心を所在なく、まるでどんどん欠ける月の、不穏な角度に惑わせた。
僕らは牛を連れたまま、モチの言うよう野を行った。葡萄の蔓を鞭にして、モチは牝牛を追い立てた。
たわいのない歌口ずさみ、罪のないその歌声を、人淋しい野に放ちつつ。
月は段々薄くなり、薔薇の色した雲が東に、縞模様作り現れた。
僕は戸惑い眺めていた。モチの豊かな顔色が、薔薇色の陽に照らされて、段々赤みを帯びていくのを。
悪びれもしない笑顔が僕に、日差しのように注がれるのを。
僕は戸惑い眺めていたのだ。戸惑うことに戸惑っていた。
想い出の中の僕と今、ここに歩いている僕は、一体どちらが本当だろう?
第三話 「戦の声」に続く
第三話 戦の声
第三話 戦の声
南へ上る道すがら、僕は儚い追憶の、中に自分を追い立てた。
心がふらふら揺れていた。振り子のように、木の葉のように。
そこは久しく訪れなかった、佑那(ゆうな)の州のはずれだった。そうあの年にサクと行った、山のふもとの一帯だ。
風景は、その習俗も含めつつ、僕に懐古を促した。黙っていたって思いだす、もう取返しも無い過去を。
だが傍らにはモチがいる。今生きている体を持って、確かに呼吸を続けてる。
夜が来て、上々機嫌でモチが呼んだ。
「イサヨイ起きてる?祭りだよ。これから火祭りあるってさ。もちろん行くよね、すぐおいで。」
ああこの祭りは想い出の、一番心がときめいたころ。もう十分に機が熟し、二人もそれを意識して、互いにどちらが切り出すか、伺っていた時に見た祭。
大きな藁の人形に、火矢を放って体から、炎の付いた藁を抜き取り、男衆たちが振り回す。
サクは初めて見る習俗に、怯えたように僕に寄った。だがその体はぎりぎりに、くっつきさえもしないのだ。
彼女の頬を鼻をまつげを、燃え上がる火が照らしてた。
「サクはそんなに怖いのか?誰も攻撃なんかしないよ。」
「炎が怖いと思うのは、神様を祭る気持ちと一緒よ。どうしてあなたは怖くないの?雷だって怖くないって…。」
サクはこういう言葉を言った。
「僕はだあれも攻撃しないよ。だから他人が怖くないんだ。悪いことなどしないから、雷神たちも僕をほっとく。」
僕はこの様返したのだ。
「それでもね、あたしはやっぱり炎が怖いわ。躊躇のなさが怖くなるの。」
サクはそう言い身を寄せた。
ああサクは待っていたのだろうか?僕が背中に手を廻すのを、照り映える頬に触れるのを。
彼女は待っていてくれたのか?今となっても気にかかる。
どうして僕はその時に、さっさと事を起こさなかった?悔やむ気持ちの種を残した?
刈り入れを待つその日になって、永久に湖底に沈んだようだ。一番きれいな想い残し、永久に失くしたあの少女。
少年時代の一番に、穢れのないその情熱を、化石のように形にとどめて、サクは心に棲み続けるのだ。
「おおいこっちだ、イサヨイこっち。すごく大きな人形だねえ!これが炎と燃えるのは、きっと見ごたえあるだろう。」
モチは屈託なく笑い、僕に右手をぶんぶん降った。
男の衣服の中の体が、豊かに揺れて匂うのを、藁に染ませた燃料が、むせぶさなかに感じ取る。
ああ僕は分からなくなった。今生きているこの僕と、思い出の中のこの僕は、ほんとに同じ人間だろか?
あの時の僕は今もまだ、あの頃のサクとどこかで一緒に、旅をしているのじゃないか?
その晩僕は眺めていたのだ、火を振り続ける男衆と、それをはしゃいで眺めるモチを。
あの年のサクと二重映しで、記憶と今を漂った。
モチが手を振る、サクが微笑む。モチが笑って、サクが怯える。
あの晩とまるで変わらずに、男衆たちは火を振った。丸く群がる村人も、あの日と違う気がしなかった。
夜が更け、僕をこう呼ぶ者がいた。
「ああイサヨイか、久しぶりだな。珍しい人に会うもんだ。随分と、兄さんたちが心配してたぞ。」
それは十二になる日まで、一緒の師匠についていた、兄弟弟子の一人だった。
「あれから一度も帰ってないのか?」
思い出したくない現実に、付き合わされて僕は憮然と、彼に向ってこう言った。
「帰る理由はないからね。兄さんたちとは意見が合わない。」
彼はやんわりなだめにかかった。
「そうだとしても、十年以上、帰らないのは心配するさ。あの人達も人の子だ。血を分けた君を心配するさ。」
「一緒にいたら、水と油で、反発しあうは目に見えてるのに、『心配』『兄弟』『血を分けた』?そういう偽善は沢山だ!」
「お前は相も変わらない。俺はなんだか安心したよ。」
彼はそう言い苦笑した。彼はほとんど変わってなかった。
だが目を引くのはそのなりだった。
「随分と、羽振りがいいように見えるな。戦で儲けているのかい?」
「君が一番嫌う所だ。そうだな、戦というよりは、戦の噂で儲けているのさ。聞いているだろ、仗(じょう)弦(げん)国と、架(か)弦(げん)国との戦の噂。どちらも多くの詩人たち、抱え込みたいそういう訳で、ギルドが優遇されるんだ。」
話す僕らを横目にし、モチが地元のかみさんたちに、酒をご馳走されている。気配を伺う風もなく、はしゃいで陽気に飲んでいる。
知らなかったな月精も、酒を好んで飲むなんて。顔をほんのり染めながら、こちらに向かって手を振った。
「あれは奥さん?」
彼が聞いた。
「それはその、そんなところだ。」
僕は言葉を濁したが、彼はそこから突っ込まなかった。
「聞いてるよ、女を王子が取り合ってると?下らんね。血筋によらず、下賤な奴だ。
どうして高貴な薔薇の蔓に、腐肉の花が咲くんだろうな。泥から生まれた蓮が高貴で、高潔である反対に。」
昔馴染みの気安さに、僕はとがったこと言った。彼はそいつを拘泥しない、そういう確信あったのだ。
彼は再び苦笑して、声を潜めて眉も潜めた。
「それがどうにもそれだけと、言える話じゃないんだな。詩人の俺とお前にも、関わってくる話だよ。
茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国が狙われている。君にはこれの理由が分かるか?虹金剛の産地だよ。」
はっとして僕は彼を見た。彼は笑っていなかった。
「王子が争ってる姫は、茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国のアリアケ姫だ。」
僕は嫌悪に顔歪め、溜息ついてこういった。
「どうやら分かってきたようだ。色と欲との二段構えか。」
「二つの国とも資源が欲しい。産地は限られてるからな。陣取りゲームのその果てに、茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国が残された。
資源が欲しい、姫も欲しい。いずれ雌雄を決するだろう。二つの国はそのうちに、茶渡羅国を飲み込むだろう。」
「実に不快な話だな。」
僕らはその晩これ以上、この話題には触れなかった。どちらも互いに慮って、不利益出ないようにした。
彼とはそういう友情なのだ。友達のまま大人になって、友達のまま別れたのだった。
それきり彼とは会うことなかった。
「イサヨイよ、君の実家はどこにあるんだ?」
僕の分の酒持ってきて、モチはやおらにそう聞いた。どうやらさっきのやり取りは、半端に聞こえた様だった。
「覚えてない。」
僕は憮然とそう言った。嘘であるのは明白だった。
「そんなに不和を抱えてるのか?」
モチは少しく驚いて、僕を案じた顔をした。
「覚えてない。」
僕は再びそう言った。先ほどよりは悲し気に。
「君の実家の家業はなんだ?」
モチは質問変えて聞いた。
「先祖代々詩人だよ。ずっと詩人の家系なんだ。」
僕はその質問にだけ、静かに答えてそれ以上、話を続けぬサインを出した。
「そうかい、そうかい、ずっと詩人か。」
モチはなんだかうれし気に、そう相槌を打った後、心を汲んでそれ以上、質問すること無かったのだ。
ああ僕の家は先祖代々、詩人の家系であったのだ。モチに語った通りだった。
あの発見さえなかったら、僕は今でも心安く、家族と友に囲まれて、歌を歌っていただろう。
詩人の喜びそれの限りに、その純粋な性により、歌いを使命としていただろう。
あの発見さえなかったら、あの発見さえなかったら!
今を去ること二十年、詩人の意味は世界にとって、全く様相変えたのだ。
始まりは、一人の術師が虹色に、白く輝く宝石に、特異の力を発見したのだ。
その特質こそ歌いの力を、極限までに増幅させる。詩人の歌に呼応して、幻影たちを呼び出せるのだ。
歴史の世界に歌われた、英雄豪傑俊軍を、僕らは呼び出す術を得た。歌いの力の強さによって。
それまでは、詩人は平和な職業だった。美しい言葉綺麗なメロディー、人の心を明るく照らし、時にはそっと慰めた。
時にはそれは立ち上がる、力となって人々に、勇気や夢を与えていたのだ。
それが今では歌いとは、血に飢えた武器に様変わりした。
詩人は武人となったのだ。
これが戦を忌み嫌う、僕の意に副うことだというか?
僕は絶対認めなかった、歌いが武器となることを。昔ながらの考えの、師匠について歌いだけ、歌唱と心を学んだのだった。
戦う術など要らないと。歌が許した美だけでいいと。
兄達と、全く違う考えだった。
つまりはそういうことだった。それ以上でもそれ以下でもない。僕らは決別したのであった。
その次の日に僕らは発った。装備は充分食料も、資金も潤沢その訳は、モチが盗んだ牝牛にあった。
前日の酒も抜けていて、僕らの体も元気であった。
モチはあれから何故か優しく、僕に接する様だった。僕に事情があることを、一体どのようとらえていたのか?
今となっては分からない。彼女の心や考えは、人の常識超えていたのだ。
彼女は月精だったのだ。人の女じゃない存在だ。
だがその日から山に入って、『奴』と最後に戦う日まで、彼女は僕の妻とも見えた。表面上に限ってだったが。
僕は彼女に触れもせず、その特権を享受した。
山越えは多分三日はかかる。僕らはそのよう踏んでいた。最初はゆっくり歩きだし、体力気力を温存する。
峯のこちらは針のよう、とがった葉っぱの木が覆っていた。まだ暑さ残る麓から、丈の短い樹の生えた、涼しい高さへ登りゆき、獣と魔物を避けるための、香を焚きつつ先を目指す。
そういう厳しい山場でも、モチはやっぱり裸足であった。不思議なことに傷一つない、つるりと綺麗なそのかかと。
僕が疑問を口にするたび、モチは決まってこう言った。
「それは私が月精だからさ、月精は、裸足でいるのが信条だ。」
やがて樹は切れ平原が、一面綿毛を漂わせ、沼地を方々のぞかせていた。天候などにも恵まれて、そこは涼しい陽気であった。
僕らは楽な道を行った。険しい尾根を避けながら、なるたけ平らなところを進む。
僕らは順調登り続けて、二日目の昼に尾根を抜けた。谷間を沿って降りようと、歩き始めた三日目に、その出来事が起こったのだった。
調度麓に近づくと、葉の平たい樹が密生し、赤や黄色に染まっていた。東方国よりもたらされる、高価な生地の柄の様な、華麗極まりない景色。
モチはオオっと気を吐いた。
「こんなに派手で色鮮やかな、景色は私は初めて見たよ。絵描きの気持ちが分かると言うもの。手元に取っておきたいな。」
「君は色々世界を見ただろ?紅葉ぐらいは見たんじゃないのか。」
歩みを止めず僕は返した。
「私が知っているのはね、月光の下の世界のみだよ。昼間の世界は良く知らない。
だから昼間の紅葉が、こんなに派手で華麗なことも、昼間の空が吸い込まれるほど、青く果てなく澄むことも、今日この頃に初めて知った。」
モチも歩みを止めぬまま、僕に答えて言ったのだ。
「ふうん、そうか、そうなのか。」
上の空の様聞こえたろうが、その時僕は反射的、モチに世界を見せたいと、そういう望みを得たのだった。使命感ともいえるだろうか?
勿論これは勝手な理屈で、モチの気持ちを考えて、いないことなど分かっていたが、それでも自然と湧いてくるのだ。
サクの魂取り戻す、旅でこういう気持ちになるなど、僕は全く不誠実。全く持って不実であるのだ。
僕はふらふら揺れている。
不意に傍ら歩いてた、モチが鋭く息を吐いた。
「おおい見ろよ、あそこを見ろ、誰かが吊られている様だ。」
不穏な様子でモチが言い、僕は現実へと帰る。
彼女が指さすその先に、僕は一人の男を見た。低めの枝にロープを張って、ぶらりぶらりと揺れている。
僕は瞬間駆け下りた。樹に這い登り大急ぎ、男を吊ったロープを切った。
どさり、男は落下した。
「おい大丈夫かい?生きてるかい?」
僕が地上に降りないうちに、モチが駆け寄り揺さぶった。
ゲホッ、ゲホッ、男が咳き込み、僕らはほっと安堵した。どうやら命は助かった様。
僕も地上に飛び降りて、一緒に背中をさすってやった。男はボロボロ泣き出した。滂沱と涙を流し始めた。
「何でだよ…、何で俺など助けたんだ!このまま消えてしまいたかった、このまま終わりにしたかったのに!」
男はそう言い泣きじゃくった。
「何でと言われりゃ説明できない。でも当たり前の気持ちだろ?死にそうな人を助けるの。君にしろ、今は最低かも知れないが、最低だったらこの次は、きっといいことあるはずだ。」
僕は男にこう言った。
「みんな言うんだ、みんな言うんだ、だからこそ俺も耐えてきた、耐えてここまで永らえた。だがそれがどうだ?どんどんと、追い詰められていくばかり、今よりましな時はなかった、時が経つたび思い知る!どんどん悪くなっていく!」
男はこう言い号泣した。何と言ったら分からなくなり、僕は黙ってさすり続けた。
男の苦悩はあずかり知らぬが、よほどのことがあっただろうに。手にも腕にも傷がつき、その懊悩の深さが知れた。
僕は男に注視して、傍らのモチが耳をそばだて、その表情をこわばらすのを、その時気づいていなかった。
「イサヨイ、嫌な気配がするぞ。石を手にして構えとけ!きっとあいつだ、『奴』が来る!」
モチはそう言い腰に履いた、短いナイフを構えて持った。
第四話 「『奴』、もしくは悪魔、そして帰郷」に続く
第四話 『奴』、もしくは悪魔、そして帰郷
第四話『奴』、もしくは悪魔、そして帰郷
紅葉を綺羅と照らしていた、太陽が黒く燃えだした。青く天上高くまで、澄み渡る空は不気味な緑に、毒々しくも色を変えた。
「うひひひひひひ、邪魔が入った。そいつは私の獲物だよ。返しておくれ、月の女。」
陰気で不気味な声が響いて、僕らの頭上に黒くてろりと、ぴったりとした服を着て、まるでゴキブリ照る様に、湿った髪を長くたらした、陰気な男が浮いていた。
「断る!」
瞬間モチが飛び上がった。淡い黄色に発光し、短剣をかざし飛び掛かる。
悪魔は左の手のひらを、ひらひらかざして振り払う。二人は呆然眺めてる、僕らの上で火花を散らす。
僕はとっさに動けなかった。二つのことに驚いた。
一つはモチが飛ぶということ。今まで彼女は普通の人の、体の能力、それ以上は、見せることなど無かったのだっった。あの盗賊を追っ払った夜も、火薬を使い、妖しげな、術は一切使わなかった。
もう一つ、僕を唖然とさせたのは、『奴』、そうあいつが現れたこと、あいつが僕をはめたのだ、あいつが僕からサクを奪った!
あまりに唐突その出会い、僕の心は追いつけなかった。だが追いつけないだけだった。
事態を認識した後は、僕の心は怒りに燃えた。
僕は背中に負っていた、狩猟用の弓手に構え、モチに向かってこう叫んだ。
「モチ!右に離れろ!」
モチは即座に右に飛んだ。僕は弓矢をびゅうと打った。
悪魔は左の手の甲で、そいつをはらりと払いとした。そうして足下の僕を見た。初めて奴と目が合った。
「何だ詩人がいるじゃないか。こいつは少し厄介だ。だが、いきなりは歌わないと?私も舐めて見られるな。」
心の底から嫌悪の情が、湧いて来る様(よ)な声色で、悪魔はそういう言葉を吐いた。
モチが背後に回り込み、素早く強く切りつけた。だがその悪魔は難なく避けて、嫌な微笑み向けたのだった。
沸き起こってくる憎しみに、僕は続けて矢を放つ。だが当たらない。奴は避けた。わざわざぎりぎり当たるよう、見せかけ期待を持たせつつ、寸での所で避けるのだ。
一度ははらりと奴の腰から、何かが落下したようだったが、奴本体は悔しくも、無傷で終ってしまったのだった。
僕は愕然していたとも。悪魔であるから手ごわいと、そう認識をしていたが、ここまで力が通じないと!やはり歌いをしなければ、サクにはたどり着けないか!
焦りを込めて僕は放った、山鷹の羽を飾った矢羽を。
突如背後で呻きが上がった。僕は驚き振り向いた。先ほど首を吊った男が、僕の下げてたナイフを盗み、左の胸を突いていた。赤黒い血がどくどく流れ、枯れた葉の敷く草の上に、黒い溜りを作っていた。
「おい、どうしてだ!馬鹿なこと!」
僕は驚き助け起こしたが、男はすでにこと切れていた。
「うひひひひひひ、そうこなくっちゃ!私は全くラッキーだ。普段行いいいんだね。その魂は私のものだ。我がコレクションに加えねば。」
悪魔は不気味に笑いつつ、その両の手を天にかざした。男の胸から銀色に、輝く何かが浮き上がり、緑に染まる世界の中で、儚い輝き放っていた。
その銀色の輝きは、幾筋幾筋ひびが入り、その中心からぱっくりと、二つに大きく割れていた。それは悪魔の声に従い、すうっと空へと昇って行った。
「おお美しい!何という、芸術的なひびの入り方!命の光を輝かすのは、傷つくに限る、傷こそが、人生を美へと導くものだ。」
悪魔はそれを手に取って、うっとりした様独り言ちた。倒錯的な喜びに、顔は醜く歪んでいた。
「もっともこれは傷欠けの無い、望月の君に分らぬ理屈か?」
悪魔は小馬鹿にしたように、宙に浮いてるモチを見た。
「欠ければ不安、傷は痛い、それだから人は満月を、憧れ込めて観るものだ。傷つかないに越したことない。無事に勝った幸(さいわい)はない。」
モチはそう言い『奴』に答えた。
悪魔は最後に僕を見た。にたりと笑ったその後で、腹の底から冷たくなる様な、声色で僕に言ったのだ。
「なかなか綺麗な壊れ方だね。」
そうしてすうっと消えたのだった。緑に染まった秋空は、元通り青く澄み渡り、太陽も白く照り映えて、綺羅の紅葉、鳥鳴き交わす。
モチはすうっと降りてきた。黙って憮然と降りてきた。僕は尋ねてみたのだった。
「もしかしたなら怒っているか?結局歌いをしなかったこと。」
「いや別に。」
モチは言った。
「あれっ位では曲げないと、私も覚悟はしているよ。それに君にも解かっただろう、歌いをしなけりゃ勝てないと。教育料とも取っておくとも。それにしたって重いものだ。彼の魂盗られてしまった。」
そう言いモチは手を合せた。僕の後ろで言切れた彼。
僕も倣って手を合せ、僕らは彼を埋葬したのだ。木の根の張らない平地を探して、素性も知れない彼を埋めた。誰が弔うあてもない、彼を埋葬したのだった。
「それにして、君は飛ぶことできたのか?さっきは全く驚いた。」
土を掘りつつ僕は言った。
「あれ位なら、魔力があるんだ。」
モチは答えてこう言った。
「この体の中残ってる、魔力の量は微妙でね、元の体でするような、術は多くは望めない。生まれ変わりに必要な、魔力は絶対死守しなきゃ。まあでもね、空飛ぶぐらいは問題ないね。」
「生まれ変わりに必要な、魔力を使ってしまったら、君は一体どうなるんだ?」
僕は怖れつ尋ねてみたのだ。聞きたくない様(よ)な答えを聞くと、怖れながらもそれを聞いた。
「ああそれは君、死ぬだけさ。贄が戻ったとしたって、魔力が無ければどうとも出来ない。生まれ変わりは叶わない。」
モチはさらりとそう言った。
「だからイサヨイ、戦ってくれ。魔力を多く使わせないで。」
モチは最後は試すよう、僕ににやりと笑って見せた。僕に歌いをするように、暗に求めて言っているのだ。
僕は迷っていたのだった。
自分の心情意地を取るのか、サクへと続いてモチを助ける、そういう道を選択するか、僕はふらふら揺れていた。
ここ数日間ずっと揺れてた。いろいろなことのその間。
どれが正しい判断か、僕には判別付かなかった。
自分が幸福なったって、正しい道とも限らない。自分が不幸になったって、世界にとっては正しいのやも。
神様の目から見たのなら、僕の運命導きが、何を求めて伸びるのか、はっきり見えるというのだろうか?
道は幾筋伸びていて、その先は霞かかっているのだ。どの運命も確証持てない、選ぶ勇気は湧いてこない。
僕には何を求めるべきか、何を求めて生きたらいいか、いろんな道のその間、僕はふらふら揺れていた。
「ねえイサヨイ、君の手柄だ、戦利品。」
男を埋葬した後で、モチはこのよう僕に言った。
「一体何が戦利品って?」
「さっき君が矢を放った時に、あいつは何かを落として行った。そこを捜索してみたら、ほらこんな物があったんだ!」
モチは明るくそう言った。
彼女の熱い指からは、蹄鉄と琴を象った、銀の紋章揺れていた。
「こいつは何かの手がかりだよね。一体どこの紋章だろう?」
僕の背中の汗が冷えた。体は激しい動揺と、複雑すぎる憎しみと、郷愁の情に慄いた。
「モチ、それは、僕の紋章、僕の実家の紋章だ…、僕の実家の紋なんだ…。」
僕はうつむきこう告げた。
モチの顔から笑みが消え、静かな顔で僕を見つめる。
「君の実家の紋だって?」
「ああそうだ…、そうなんだ。これから一度、帰らなくては…。」
僕にはそれしか言えなかった。
僕らは山を下りた後、北へと向かって進路をとった。琉宇那(るうな)の河の名前を頂く、独立都市にあるはずの、僕の実家を目指したのだ。
僕はひたすら道を急いだ。余計なことを言う余裕、僕の心に残ってなった。こんな心で軽口を、言い合えるほど強くない。
モチは分かっている様だった。彼女は色々話したが、答えを僕に求めなかった。ただその空気を明るくするため、慮っていたのだろう。
モチの言葉と表情は、救いという様明るかった。
その地域では狭い土地に、果樹や小麦という様な、豊かな畑が広がって、こちゃこちゃ小さな都市が建てられ、覇を競い合っているのだった。
僕はそいつを懐かしく見た。十二の頃にここを出てより、久しく訪ねることはなかった。
捨て去ったはずの故郷でも、それでも苦く郷愁は湧く。
昔馴染みの習俗や、景色自然によく嗅いだ、煮炊きの料理の香をかぐと、僕の心は高鳴った。
ああ懐かしい、懐かしいと。
山降りてから二週間、僕は実家の正門の、ひさしの外にモチといた。
使命感だけでここまで来たが、ここを叩いて門をまたぐ、勇気が何とも湧いてこない。
僕は所在もない様子、ただ門の外に立っていた。
家の外観一見し、変わっていないようだった。黄色い煉瓦を積んだ屋敷。翡翠色したモザイクが、丸くちりばめられている。
屋敷の奥の、楼閣が、少し傾くその様も、そこにオレンジ色した花が、なよりと掛かっているさまも、思い出の中と全て一緒。
「イサヨイ、ドアを開けないの?」
モチがそう言い促した。僕は黙ってうつむいて、それでも足は動かなかった。
「随分立派な家なんだねえ。もっと質素な建物を、私は想像していたよ。」
「ここは本部を兼ねているから。いろんな人が出入りする。」
僕は短くそう返す。語りたくもないことなのだ。
「何かこちらに御用ですか?」
初老の男が声をかけた。
「おや、ジュウサン様、どうされました?そんなところに突っ立って。」
「彼はイサヨイ、そういう名だよ。私が聞くには彼はここなる四男で、大事な用事で訪れたのです。」
僕が何にも言えないうちに、モチが代わりに答えて言った。
「おお!イサヨイの坊ちゃんか!全くご立派になられて、どうされたのです?随分と、久しいお帰りではありませんか!さあさあ中へお入り下さい、お兄様方も随分と、心配なされておられます。」
彼、僕の記憶通りなら、父親の秘書であった男、その招き入れで僕はを門を、久しく遠のくその門を、ようやくまたぐ決意を決めた。
屋敷の中は想い出と、あまり違いはない様だった。僕らを取り巻く状況と、世界は大きく変わっていても、この屋敷に降る時間の質は、そう大きくは違わないのか。
祖父の歌いをよく聞いた、中庭にある東屋を、回廊上で見送った。樹も花の丈も違わない、僕はそんな成長してない。
壁にかかった絵も武具も、きれいに埃が落とされて、掃除の届いているさまは、あの日と何にも変わらない。
「タチマチ様が、よく差配され、事業は順調なのですよ。」
父親の秘書はそう言った。
事業は順調、そのことは、僕の望みに反したことだ。こんな家業は認めたくない。だから実家を飛び出して、今の今まで帰らなかった。
タチマチの、兄は上手にやってるらしい。つまりそれは、僕らの決別深いこと、暗に示していることになる。
今更何を話せばいいか、今からとても頭が痛い。
長兄とは、話す言葉が違うかのよう。全て堂々巡りなの、話す前から知れている。
僕らはやがて、屋敷奥、個人の客が通される、小さな広間に通された。
「中も随分立派なんだね。君が生まれた時からかい?ただの詩人の邸宅が、これ程までとは思えないがね。」
モチがきょろきょろ見回して、僕に尋ねてそう聞いた。
「ここは本部も兼ねてるのです。この家は、西楼亜琉(ろうある)に属する詩人の、ギルドの元締めなのですよ。イサヨイ様から聞かれてませんか?」
代わりに彼がそう言った。
僕はあまりの居心地悪さに、言葉を発すること出来ず、無言でそれを肯定した。
「それで『坊ちゃん』、そういうことか。それならば、現御当主は君の兄か?」
再びモチはそう聞いた。
僕は黙ってうなずいた。
小一時間が経過した。
僕の記憶の中の味と、全く変わらぬ珈琲を飲み、僕らは兄と再会した。
タチマチの兄は中年過ぎてた。十歳以上も上の兄。記憶に残るぎりぎりの、父によく似た面立ちだ。
祖父にも似ている様だった。だがその中身は全く違う。汚く脂肪が増えていた。成りも羽振りも詩人ではない。
「兄さん、白髪が増えたねえ。」
僕はようやくそう言った。それ以外、一体何が言えたというのか。
「お前も十分大人だな。その横の人は奥さんかい?」
定型通りに兄が聞く。
「ああ、私ならお構いなく。ただの道連れ、相棒ですよ。」
モチが明るくそう言った。
兄の笑顔が皮肉に歪む。彼はそういうつながりを、全く信じぬ人間だ。
「ところでね、蛛(ちゅ)冨(ぷ)山中でこれを拾った。黒い服着た男性が、僕らの元に落として行った。
これはあなたの物だろう?お届け先を知りたいんだが。」
僕はいきなり切り出した。苦しむのなら一瞬がいい。どう回り道をしたとこで、このやり取りに行くしかないのだ。
兄とはどうせ分かり合えない。煙たがられても気にすまい。事実さえ知る手掛かりあれば、僕はこの場を良しとしよう。
長兄の顔がピクリと歪む。やはり何かの目的で、『奴』とつながりあったのだ。
「おお、おお、彼に会ったのか。彼は私の提携主だよ。今度の仕事が上手くいくよう、彼が差配し下さった。
失礼などは無かっただろうね。」
「誠心誠意対応したよ。彼はずいぶん個性的だね。変わった趣味をお持ちのようだ。」
「くれぐれも、今度出会ったその時は、ご無礼などは無いように。彼の機嫌のその如何、こちらの儲けが左右されよう。
くれぐれも、くれぐれもだよ、彼の機嫌は害さぬように。」
肝心なことをぼかしたまんま、僕らはのらくら続けた後で、こうタチマチは切り出した。
「ところで帰るつもりはないのか?お前くらいの力があれば、こちらの儲けも一割増えよう。ほんとに大事な商談でねえ。
一個師団でもお前なら、易々顎で使えるはずだ。もしそれなら、お前が合ったという人に付き、教えることも出来ようぞ。」
僕の頭の血管は、百本ばかりは切れただろう。
「兄さん、僕は戦わない、歌では絶対戦わない!」
僕の言葉に兄は言った。
「そうかそうかそう、残念だ。ほんとに私は残念だ。」
心なしかは本当に、心を落とした声色だった。
「兄さん僕はもう帰ろう。もう話すことはないんだよ。久しく会えてうれしかったよ。」
「もう帰るのか?今すぐに?来たばっかりじゃないかねえ!部屋も用意がしてあるんだが。」
「いやいいよ、市中に宿をとっているから。僕らはそこに泊まることにする。さあ、モチ、行こう。」
僕はそそくさ席を発つ。珍しいくらい固い顔した、モチを促し逃げるよう、小さな広間を後にした。
「イサヨイ、ほんとに会えてよかった!」
僕の背中に兄が言った。振り向きもせず僕は出る。
「ほんとに君は良かったの?戻れば待遇いいはずだ。」
回廊の下でモチは言った。
「僕は歌では戦わない。仮に戦うそれにしたって、あの人のために戦わない。僕が命を懸けるのは、サクの魂それのみだ。」
僕はきっぱりそう言った。
「君はほんとに頑固だね。それにしたってお兄さん、君をほんとに拒んでなかった。
気づいていたかい?婉曲に、くるんでいてもそれは君に、大事なことだけ伝えていたよ。」
モチはとっても冷静に、あのやり取りを聞いていた。
「つまりはこういうことだろう?近いうち、戦が起こる、詩人がいっぱい必要だ、その兵力を、ギルドが仕切る、その戦、あいつ、悪魔が一枚かんでる。」
僕は彼女に向き直り、震える思いでこう言った。
「君はそのようとったのか!」
僕は霞に包まれたよう、現在の位置が分からなくなる。人の心は複雑で、数学のようにいかないと、祖父は常々言っていた。
分かり合えない長兄に、割り切れぬ情はあるというのか?祖父を否定し裏切った、あの長兄にあるというのか?
「イサヨイ、待って!」
突然に、中庭の蔭に声がした。かさこそ木の葉を押しのけて、僕と同じ顔をした、一人の男が現れた。
「ええ!君イサヨイ?」
モチが驚き声上げた。
「君と同じ顔をしている。」
「これは双子の弟なんだ。ジュウサンという名前だよ。」
僕は彼女にそう告げた。
「一体どこを彷徨っていた!この家のことを押し付けて!僕の苦労が知れるかい?」
ジュウサンは言い、微笑んだ。
「まあいい、そいつは置いとこう。君が今更現れた、理由はこちらも掴んでる。宿の住所を教えてくれ。今夜こっそり尋ねるよ。」
ジュウサンは言い強く笑った。
僕にもまだまだ身内がいたのだ。決して切れない血の絆。
第五話 「明らかになる策謀と、ジュウサンの頼み」に続く
第五話 明らかになる策謀と、ジュウサンの頼み
第五話 明らかになる策謀とジュウサンの頼み
その晩夜更け言った通り、夜闇に紛れてジュウサンは、僕らの宿を訪れた。
「一体何から話せばいいやら・・・。」
ジュウサンはそう切り出した。
「一つ尋ねてみていいかい?」
僕はこういう質問投げた。
「お前は歌いで戦ってるのか?」
ジュウサンは顔を変えぬまま、一口すっと息呑んだ。
「あの家にいるその以上、兄さんの命は拒めない。だがね、解ってくれるかい、僕にしたって本意じゃないこと。だからこそだよ、今だって、僕は一応自由に動ける。」
僕は安堵し落胆した。
ジュウサンが汚れ負ったこと、失望しながら聞いてたが、その反面に、彼が兄から、警戒されていないらしいこと、それを有利と思いもしたのだ。
「そんなに危ない計画なのか?」
僕は自然と声潜め、細い灯りの向こう側の、僕と同(おんな)じ顔を見つめた。
「こいつが事前に漏れたなら、ギルドは即座に壊滅だ。兄さんも僕も殺されるだろう。」
「それと『奴』とがどう噛んでるって?」
傍らのモチも声を潜める。僕らは三人暗い宿屋の、部屋のまあるいテーブルを、額合わせて囲んでいた。
他の客なら寝静まってるか、下の酒場で馬鹿騒ぎ。部屋の周りにモチが術張り、盗み聞く者ないように、僕らは念を入れていた。
「一体何から話そうか。そうだなこれは聞いているかい?仗(じょう)弦(げん)国と、架(か)弦(げん)国、二人の王子の争いを。」
ジュウサンはそう切り出した。
「二人の王子が茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国の、アリアケ姫を争ってると。彼の国の山に産出される、虹金剛の利権も絡むと。」
僕はこの様答えて言った。兄弟弟子に聞いた通り、それのまんまを言ったのだ。
「そこにギルドが絡んでいるのか?」
ジュウサンはふうと息吐いた。とても言いにくそうだった。
「この僕自身のことも絡んで、僕は全く被害者と、言い切ることが出来なくなった。
ギルドは茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国王と、裏でその手を結んでる。二つの国の共倒れ、その漁夫の利を狙ってる。」
「つまりわざわざ手を廻し、わざと戦を起こそうと?」
モチがその様口を挟んだ。
「ああその通り、そうなんだ。二国の力は拮抗している。対する茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国は弱小。このまま行ったらいずれの国かに、飲まれることは確実だろう。」
ジュウサンは言い少し黙った。
「だがそのことと、悪魔とが、一体どのよう絡んでいるのか?」
「一年ほど前彼が来た。一人の娘を連れていた。その娘、アリアケ姫に瓜二つ。
彼はギルドにこう持ち掛けた。『大きな戦を起こさないかい?西楼亜琉が血に濡れて、人の心が壊れまくる、そういう戦は欲しくはないかい?きっと君らも儲かるだろう。悪い話じゃないと思う』。」
「彼とは悪魔か!」
モチの声音も厳しくなった。
ジュウサンは苦くうなずいた。そうしてこのよう続けたのだ。
「『一体どういう方法で?』兄さん達はそう聞いた。『この娘、アリアケ姫姫に瓜二つ。これを使って諍いを、戦のレベルに高めよう。どちらとも、相手が姫を殺したと、思い込ませて煽ってしまえ。』。彼はそのよう持ち掛けた。」
「しかしそれでは、ギルドの利権が中途半端だ。わざわざ影武者立てる理由も、さしてあるとは思えない。『奴』なら姫の命なんぞに、躊躇するはずないと思うし。もう一枚ほど裏があるな?」
モチはこの様確認した。
「いや、その通り、その通りだよ。この僕に、婚礼話が出ているんだ・・・。」
ジュウサンは言い、しばし黙った。僕は意外な時に出た、意外な言葉に驚いて、不吉な予感を感じて取った。
「一体誰とのお話だい?」
「それはその・・・、アリアケ姫とのお話だ・・・。」
僕らは一様沈黙し、ジュウサンの顔を注視した。
ジュウサンは、少し火照った顔して、それでもとても苦しく見えた。
「二つの国が倒れた後で、僕と姫とが婚礼上げて、茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国と手を結び、虹金剛の利権を一手に、握ってこの地に覇を唱ゆく。それが悪魔の持ちかけた、策謀、それの全容だ。」
僕らは再び沈黙した。
それは大きな策謀だった。それまで想像しないほど。大きな策謀だったのだ。
僕は苦しく失望を、怒りを兄に向けて抱いた。
さっき半端に感じかけた、肉親の情のひとかけら、そいつも苦く悔やむほど、深く失望味わった。
結局儲けることだけじゃないか!儲かったなら人々の、生活、命はどうでもいいのか!
歌に対する冒とくじゃないか!
僕の額に怒りが上るの、ジュウサンはとても悲し気に、沈んだ様子で眺めていた。
「お前もそれを承諾したのか?すべて分かって協力するのか?」
僕は尋ねて聞いてみた。どうしても、聞いておきたいことだった。
「僕には人質いるんだよ。彼女と進む未来の前で、従わない道選べない。」
ジュウサンは言い、首を振った。
「彼女というのは一体誰だ?」
「アリアケ姫だよ、イサヨイ兄さん。」
彼は苦しくこう言った。
「彼女をとても愛しているんだ。失うなんて耐えられない。」
そうして僕に頭を下げた。
「もちろん倫理の上からは、非道であるのも知っている。僕も大きな戦になるのは、望んでいないことだから。
だからお前に話したんだ。お前が悪魔と関わりあるのも、天の差配と思っている。こうしてここに現れたのも、偶然じゃない、きっとそう。
どうか戦を止めてくれ、戦だけなら止めてくれ。僕らに兄に、心の平和を、取り戻し得てくれないか?兄さんだって気づいてないけど、ほんとはとても不幸なんだよ。」
ジュウサンは言い頭を下げた。長い間も下げ続けた。
「断ると言えばお前はどうする?」
僕は尋ねて聞いたのだった。
「このまま道なり進むしかない。運命の矢に従って、突き進むしか道はない。」
ジュウサンはこう答えたのだった。
「僕に一体何が出来ると!」
「イサヨイだったらきっと何か、予測を超えたことをする。しがらみくびきに縛られて、運命の道をそらすも出来ない、僕らに出来ないことをきっと。」
彼が藁にもすがりたい、心であるのは伝わった。だがこの僕にも無理がある。一人で何をなせるというのか?
僕はジュウサン言ったよう、もうそれ程に自由でもなく、予測を超えたこともできない。
僕の心の中の彼と、今目の前のジュウサンが、違っているのと同様に、彼の心の中の自分と、今の僕とは別人だった。
「イサヨイ、行こう、茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国へ。」
モチがそう言い強く笑った。
「さっき絵地図を確認したが、あの悪魔がいるその地こそ、茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国であるはずだ。気配はそこから呼んでいる。」
僕は驚きモチを見た。
「君の運命宿命が、きっとそこから呼んでるのだろう。こういう時に限っては、突っ込んでくしかないものだ。」
「重ね重ねもお願いするよ。どうか回避をする道筋を!僕も出来たら協力するよ。悪魔なんぞは僕も嫌いだ。」
ジュウサンは重ねそう頼んだ。
僕は黙ってうなずいた。破れかぶれという様に。
「試すだけなら試してやるよ。戦なんぞはまっぴらだしな。だが期待するな、僕にだって、無理というのがあるんだぜ。」
「分かっているさ、分かっているさ。」
ジュウサンがそう答えたのち、沈黙が重く僕らに伸びた。
ジュウサンは、夜闇に紛れて帰って行った。
僕は寝床に転がって、天井の染みを眺めていた。昼間屋敷で会った時には、確かに何か温かく、変わらないものを見つけた様な、そうも思えていたというのに。
僕が頑固に変わらぬ間、ジュウサンの上に時が流れて、彼がおかれた状況も、残酷なほど変化した。
僕が知ってる彼じゃないのか。
僕が知っている彼じゃないなら、僕と彼との関係も、僕が知っているものではないのか。
僕は溜息ついた後、ごそごそ寝返り打って夜更けの、ぼんやり細い月を見た。
どういう訳か、サクのこと、僕の脳裏に浮かんできた。
「イサヨイは何故、戦わないの?」
山脈降りてすぐのこと、彼女は僕に聞いたのだ。
未だ熱退かぬ九月のこと。水浴び後の髪が濡れ、雫がきらきら光っていた。汚れを落としたサクは尚更、清く儚く輝いた。
「歌とはそういうものじゃないから。人を癒して慰める歌が、誰かを傷つけ命を奪う、そいつが僕には許せない。」
僕はこう言い答えたのだった。
今とほとんど変わらない、僕の持論であった、だが、あの時はそれにジレンマも、無理も感じていなかった。
望めるがまま生きれると、無邪気にそうと思い込んでいた。
「お金も名誉もいらないの?」
サクは重ねてこう聞いた。
「金なら生きれる分だけでいい。名誉も欲しいは欲しいけど、武勲なんぞで立てたくはない。僕の歌声詩才によって、あくまでそれで立てたいんだよ。」
僕はうぬぼれてたろうか?サクの前ではいい顔したか?
あの時易いと感じたことが、これ程難しかったとは!僕の選べる道の種類は、どんどん狭くなっていく。
サクは何故だか哀し気に、何かを言いかけ飲み込んで、僕を見上げて印を切った。
「あなたのそういう高潔さが、望まない道に導かれ、何かの犠牲になりませんよう。心の高貴で酷い定めを、負ったりなんかはしませんように。」
あの日のサクは僕を案じた。もう亡いはずの彼女は案じた、今永らえた僕のこのこと。
あの日のサクにどう映ったのか?無邪気で無謀なあの日の僕は。
一体何をどう案じたか?サクには見えていたというのか?僕の目指した道がどんなに、無理なものだということを。
今この僕に何を見るのか?
サクの魂求める旅だ。もし戦えば、戦だって、未然に防げるかもしれぬ。
だがそのことでサクが案じた、僕の運命暗くする、「望まぬ道」がひたひたと、この身に迫ってくる気がするのだ。
僕の眼前迫りくる、道はどんどん狭まれる。
戦うことを選ぶのか、戦わないのを選ぶのか、サクを、昔を選ぶのか、今ここにある先を選ぶのか。
揺れてるという場合じゃないのだ。責められ追い立てられているのだ!
選ばないことが自由であるなら、選ぶというのは義務なのだ。義務を喜ぶ者がいるか!
僕は苦しく目を閉じる。
「イサヨイ、起きてる?」
ドアの向こうでモチが聞いた。
「起きているけど。」
僕はぼんやりそう答えた。誰かに話しかけられるのは、何だか救いの様な気がした。
「私の頼みを聞いてくれ。」
モチの頼みと言うものは、歌を聞かせてくれと言うもの。
「君がきちんと歌うのを、私はまだまだ聞いていないから。あの晩、賊を撃退したとき、とっさに歌って戦った、あの時だけだったからねえ。君がしつこくこだわっている、歌の信条そう言うものを、きちんと込めた歌が聞きたい。」
モチはそう言い僕の前、胡坐をかいて座ったのだった。
窓の外には夜半の月、窓に儚く忍び込む。白い樹木の花の香が、むんと香って鼻を突いた。
とても静かな夜だった。別部屋の、誰かのいびきも寝言さえ、聞き取れるほどの平和な月夜。
雲が動き、モチの額に射している、白い光も移りゆく。
僕は楽器を手に取った。膝にそいつを乗せて構え、僕は歌いを行った。
小さな可愛い月精の、果て無い旅を歌った歌を。
「聖なる太陽の主が 隠され月の主さえ 隠されこの世が闇にいた時 小さな光が地を迷う
音に聞こえぬ新月の 生まれたばかりの女神なり 光の見えない朔の夜を 照らすようにと生み出され
名づけも済まさぬそのうちに 父なる月の御方は 魔界の牢に囚われた
心細さに泣きながら 幼い女神はさすらった 二十九人いる姉姫も 父御と一緒に囚われた
この人の世に輝ける 光の眷属見当たらぬ 自分が誰であるのかも ここに生まれた使命さえ 知らずこの世をさすらうばかり
苔の香れる深き森 羊歯の葉陰にいた時に 母なる闇の方様が 小さき光の幼児を 見つけこのようおっしゃった
『おやまあびっくり 光じゃないか まだこの世界光がいたとは お前はどこから来たのかえ?』
『分からないのです、分からないのです。』
小さな光はそう言った『自分の名前も分らないのです』
『名前なんぞは意味を持たぬぞ 光に属する眷属には 呼ばれるほどに 縛られる 光はそれを嫌うのだ』
『私は光であるのですか?』
『お前は確かに光であるよ 闇の私が言うのだからね 闇だけがそれを形作れる 闇が光を作るのだ』
『私は何処へ 行けばいいのか』『お前の命が呼ぶところへ お前の父と姉たちが 呼ぶのがきっと分かるはず』
闇は娘の頬を撫で ふわりとどこかへ流れて行った ただそれだけで 幼い月の 魂はすっと芯持った
森を抜け 野を抜けて 小さな村の入り口で 足を痛めて倒れ居たのを 通りかかるは靴職人 彼は小さな月を拾った
靴職人は小さな月の 足の痛みをとるために 蜂蜜湿布を張り当てた
『大丈夫だよ これで三日 休んでいたなら良くなるはずだ』 小さな月は痛いと泣いて 靴職人を困らせた
それでも三日が立った後 小さな月は微笑んで すっかり痛みは引いたと走った
その笑顔 光の見えない地の国に まあるい月が差したよう 全ての花と獣と鳥が 挨拶をしに来たのだった
靴職人は驚いた 『あなたは一体誰であるのだ ただの迷子じゃないのですか』
『私は光と言うのです あの方は 闇の高貴な貴婦人は そのよう教えて下さった 月の主の娘です』
『何と光栄 驚いた もう絶えて無きものと聞く 光をこの目で見られるとは
全ての光は魔の牢に 閉じ込め囚われていると聞くが あなたはそれでは行かれるのですか 父上様と姉様を 助けるために行かれるのですか』
小さな月はこう言った 『あなたはそれを止めますか』 靴職人はこう言った
『止める道理はありません しかし一人にさせるのは 人情として余りある 私もお供しましょうとも
そうして二度とその足を 傷めないよう靴を作ろう』
靴職人は赤く染む 皮をなめして靴を作った 可愛い小さな足に合った 小さな靴を作ったのだ
小さな月は彼を従え 野を行き 山行き 街を行った 赤い革靴きゅきゅっと鳴らし 小さな月は歩き続けた
東で大きな魔犬から 魔界の門をくぐるための 牙に隠した鍵を得た
西で魔女飼う雄鶏から 深紅の飾りの羽を得た これを使えば悪魔に知られず 魔界に入ること叶うという
北で五色の毒蛇に 魔界の中の有様を聞き 注するべき三点を しかと心に焼き付けた
南で陸の様な緋鯉に 乗って魔界の入口へ 飛ぶ鳥のよう 渡りゆく
魔犬の鍵で中に入り 雄鶏の羽で身を隠し 毒蛇の言葉をよく覚え 二人はずんずん進みゆく
魔のお后の玉座の前 小さな月は歌うたう 薔薇とクジャクの恋物語
魔のお后はあくびして すやすや昼寝を始めるのだった
二人は羽で身を隠しつつ 高く結い上げられた髪から 銀の鍵束探り当てた
その二番目の鍵を盗んで 二人は地下の牢へ行く 羽で姿を隠したまんま
地下牢は 火山の臭いが立ち込めて 月には居心地悪い場所 それでも小さな月は行く 赤い小さな靴に守られ
熱を発する床にも負けず それでも小さな月は行く 小さな赤い靴に守られ
小さな月はたどり着く 父と姉姫囚われる 地下の牢へとたどり着く 盗んだ鍵を仗にあて 全ての光を救い出す
月の主 月の姫たち 太陽の主 太陽の姫 六人そろう陽の王子
全ては輝き暗き地下の 魔の宮殿を打ち破り 全ての光は逃れ出て この世に再び勝利をもたらす
光の勝利 美の勝利 正義の勝利 命の勝利
月の父御は小さな月に 白いやさ手を差し伸べた
『お前が全てを救ったのだね 名前も持たないこのお前 さあ皆とともに帰ろうか 天なる月の宮殿へ
お前の姉が髪を編むだろう 光の菓子もふるまおう ともに楽しく歌を歌い 踊りを踊って暮らそうか』
小さな月の顔は光り 少しばかりは遅かった 幸せ祝福それに酔った
靴職人に向き直り 今までの礼と暇を告げた
『あなたのおかげ ありがとう』
そうして天へと昇りゆく 父なる月に従って 二十九人の月の姫 ゆるゆる渦に登りゆく
一番後に小さな月 その姉たちの後を追う ゆるゆる渦に登りゆき 下を見返すことも無く
地上に何の未練も無いと ただ上方だけ眺めつつ やがてついには見えなくなった
靴職人 ただ呆けた様見送った 見えなくなったその後も ただ呆けた様眺めていた
見えなくなってその最後 何かがはらりと落ちてきた それは朱赤に染められた 小さな皮の靴だった」
僕は歌いを終えたのだった。
この歌は、サクが一番好きだった曲。サクに出会った前の年、苦心し自作をしたバラッド。
「私は今まで灯りの見えない、夜をずうっと生きてきた気がする。だからね、サクという名を持つ私は、朔(さく)の晩照らすそのために、生まれた小さな月の子が、この世に光を取り戻す、それにとっても憧れるのよ。
私もいつか、この世に光を、大きく凪いだ世界を自分で、勝ち取れるような気がするの。何か犠牲を払っても。」
遠い昔のサクの言葉。
ジュウサンとのあの会話の後で、武勇の歌を歌う気になれず、恋物語も僕自身、恋慕の情に疲れてた。
考えてみれば図らずも、本物の月の精である、モチに聞かせるそのために、僕はこの歌歌ったのだった。
あの時は持てる力の全て、これの詩作に注ぎ込んだが、今となっては青臭い。
僕の青春その墓標、それがこれなるバラッドだった。
「何だかいいね、お伽の話だ。」
モチはこちらに拍手して、少し寂しく微笑んだ。
僕の心は不思議と晴れて、迷いの霧が少しだけ、ほんの少し、切れていた。
「何だかすっきりした顔だ。」
モチはそう言い座り直した。
「僕が一体どうするか、今はまだまだ決めきれない。だけどその時最良の、道を選択しようと思う。逃げずに自分の運命と、戦う決意だけはついた。」
僕は彼女にはっきり告げた。モチは笑って拍手を続けた。
どこかの籠の小夜鳴き鳥が、間抜けに歌いを始めていた。
第六話 「茶渡羅国への度と、肉体の不完全性」に続く
第六話 茶渡羅国への旅と、肉体の不完全性
第六話 茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国への旅と、肉体の不完全性
僕らは三日後そこを発った。
準備を進めるそのうちに、ジュウサンからは何回も、追加で情報送られてきた。
大体彼が僕に求める、その役割は飲み込んだ。
アリアケ姫の影武者を、殺す茶番を止めるのだ。
策謀、そいつの引き金は、この一点にかかってる。これさえ起らず済んだなら、戦を先に送れるはずだ。
その後のことはその後で、僕らは決める、ジュウサンも、出来る限りのことはすると、固く約束してくれた。
僕には信じるそれ以外、自分の心を守っていられる、そういう術は得られない。
モチは言った。
「彼は本当(ほんと)のことを言ってる。月精の勘はよく利くものだ。」
僕らは装備を整えた。ジュウサンからは大きな石を、予備に三つも受け取った。
相当重い出費であるだろ。兄に見つかったりせずに、これを調達することは、きっと苦労を伴ったろう。
ジュウサンの決めた決意のほどが、僕にも痛く理解が出来た。期待を裏切る訳にはいかない。
もう後ろへは進めない。僕は前だけ見ることにした。
僕らは西へと旅立った。西へ西へと旅立った。
季節はちょうど九月の終わり。細長い月が有明に、残った朝に旅立った。
目指すは茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国の都、泥安(でいあん)。名にし負う、歩琉(ほる)渡(ど)の渓谷守備にいただく、壮麗華麗な都であるのだ。
西へと続く道のりは、徐々に険しくなっていく。平野を抜けて、丘陵超えて、他に見ぬほど険しい峰が、ずんずん先に迫って来るのだ。
僕らは崖に穿たれた、細いバルコニーの様な、危険な道をひた歩く。
「大体だから、彼の国は、今の今まで他国に飲まれず、独立保っていられたんだよ。
耕地自体は肥沃だが、その面積も猫の額だ。虹金剛が無かったら、誰も欲しがったりせずに、今も安泰だったはずだ。」
僕は後ろを歩くモチに、そういう解説を加えた。彼女は地理や自然には、とても明るい知識があったが、人の世の政治そういうことには、全く持って関心なかった。
「人というのは欲張りなんだね。持っているより多くの物を、もっと持ちたい、そう思うんだ。
挙句の果てに持ち物に、逆に支配をされてしまう、君が政治や商売を、毛嫌いしている理由が分かった。」
彼女はそのよう答えて言った。女性にしては重い荷物を、背負ってはいるが彼女は平気で、ずんずん僕に付いてきた。
「贄の体が丈夫だった。かなり鍛えていたようだ。彼女も苦心し働いてたかな?」
そのことについてモチは言った。
そうしていまだに裸足であった。歌に歌った月の子と、違い、優しいかかとにも、傷一つさえつかないのだった。
登りゆくほど気温が冷えて、冷たい風が吹き下ろす。僕らはその都度衣服を一枚、また一枚と重ね着した。
だがモチは、足が冷えたと言うことも無く、足だけは遂にどんな覆いも、その身にまとうことはなかった。
僕らは小さな集落が、見つかるたびに宿をとった。家あるとこで休まなかったら、疲れが加速し溜まってしまう。
崖の下から見上げながら、煮炊きの煙を探したものだ。案外そういう小さな村は、意外なほどに見つかった。
どこでも人は生きられるのか、人とは案外たくましい、モチもそういう意見を持った。
そういう村に泊まった時は、僕らはたいてい同室に、通される時が多かった。
小さな村の小さな家には、空き部屋の数も多くない。男女二人が一生に旅する、説明しなけりゃ夫婦であると、誤解を招くことになる。
僕は随分言葉を尽くして、別々の部屋にしてくれと、頼み込むことにしていたが、モチはどうにも無頓着、あっけらかんと言い放った。
「別にどうでもいいじゃない。寝床がしっかりあるんなら。私は全然かまわないよ。」
そのたび僕は煩悩を、はらわたの底に押し込んで、背中を向けて眠りをとった。この旅が、一体どういう意味を持つのか、それを頭で繰り返す。
兄らの謀略それをくじき、馬鹿げた戦を避けるのだ。サクの魂取り戻すのだ!他でもなくもサクの為…。
決して不埒な目的じゃない、決して不埒な目的じゃ…。
眠れず後ろを振り向くと、もう易々とモチは寝ている。この月精は不眠とは、無縁の体である様だ。
僕も無理やり眠りの中に、自分の意識を押し込むのだった。落ち着かないその夢の中に。
だがあの村に泊まった時は、僕の我慢は試練を迎えた。
それはとりわけ小さくて、粗末な家の並ぶ村。部屋数も家具も少なくて、僕らが一緒に通されたのは、たった一つのベッドしかない、物置のような部屋だった。
「これではさすがに問題だ!僕は廊下で毛布で寝るよ。」
僕の言葉にモチは言った。
「別にどうともしないんじゃない?床に寝たらば痛いだろう。窮屈だけども一緒に寝たら?」
訳も無いとのその言葉に、僕は顔面赤くした。
「それは絶対無理だと言おう!君は自分の体が与える、刺激というのに頓着無さ過ぎ。僕の心に君に対する、敬意というのが無かったら、とっくに無事ではなかったんだぜ!」
「敬意があるならいいんだろう?」
「我慢も限界あるんだよ!とにかく自分の方からも、節度を守って行動してくれ。」
僕は戸惑うばかりだった。
僕が今まで接した女性は、身持ちを固く持つために、自分の方から制限していた。決して無用な接触や、挑発などは行わなかった。自分の魅力を理解していた。だがモチは、この月精は気にしないのだ!
「男というのはそんなにも、女の体に反応するのか?君には大事なサクがいる。それでも私のこの体を、悩ましく見る、そうなのか?」
モチはどういう訳か哀しく、僕の瞳をのぞき込んだ。
僕はとっても居心地悪く、瞳をそらしてこう言った。
「そうなんだ…。自分の意志とは関係ないんだ。たくさん動けば腹が空くよう、そういう反応であるのだ。」
「つまりは体に強制される、そういう情であるのだな。体というのはすごいものだ、心も支配するのだな。」
モチは大きくうなずいた。
僕は何だか後ろめたく、自分の言葉を思い返した。
「自分の意志とは無関係」、いいやそうではないだろう。僕はモチにも惹かれているのだ。完全に、不埒とすらも言い切れない。
「月精に恋はないからな。私は困惑させたいかい?」
モチは何だか悲し気だった、理由は全く知れないが。
彼女の言葉に僕は聞いた。
「月精は恋をしないのかい?」
「ああ無いよ。第一必要ないからね。君は一体何の為、恋というのがあると思うか?」
モチは真っ直ぐ僕を見上げた。瞳(め)の中に、思慮に輝く光があった。彼女は案外哲学的に、この世を観察していたようだ。
「それは一人で生きるのが、あまりに寂しいからじゃないか?」
「君は寂しい感情が、どこから来るのか分かるかい?精霊は、寂しさなんかは感じない。完璧で、鏡のような満ち足りた、円かな魂だけの存在。人間も、鳥も獣も虫だって、魂だけに限ったら、きっとそもそも完璧なんだろ。
だがしかし、肉をまとったその途端、全ては急に不完全になる。生身の体は要求をする、空腹、恐怖、熱さに寒さ、永らえること、子を残すこと。不完全さを満たすには、誰かが必ず必要だ。
私もしみじみ感じているのだ、この肉体が要求するのに。肉がこれほど切ないものと、今まで思いもしなかった。
自分のように自分を愛して、自分を愛するように愛せる相手、生き物は、不完全であるそれゆえに、恋というのを持っているのだ。不完全である者だけが、恋する必要それを感じる。
完璧である精霊は、だから恋する必要もない。私は体に不慣れなように、色にも恋にも不慣れであるのだ。どうやら君を困らせたかい?」
モチはそう言い淋し気に、僕に片眉上げて見せた。
「分かってくれたらいいんだよ。僕は廊下で転がってるよ。」
モチは何故だか急激に、憮然としたよう、口をつぐんだ。
「体が強制する以上の、欲は私に無いというか?私を見ないそのことで、我慢が出来る感情なのか?」
「君に敬意を持ってるからさ。半端な気持ちで手を出せないよ!」
僕は戸惑うばかりだった。困らせたかいと言う後で、困らせる様なことを言う、モチが全く分からなかった。
「精霊は、欲望なんか持たないんだろ?」
一息黙ってモチは言った。混じりっけなしの真顔であった。
「今の私は体を持ってる。心は体に支配をされる。つまりはそう言うことだった。君と寝るのは嫌じゃない。
自分の言葉に確信したよ、精霊体でいた時の、私は今とは別人だ…。」
つまりそれは、体を持ったということで、僕に想いを抱いていると…?
一緒に寝てもいいというのか!
僕は姿勢を正しく直した。顔がほてってたまらなかった。
「今は駄目だよ、まだ駄目なんだ…。」
蚊の鳴くような声で言う。
僕はごそごそ寝具を出して、廊下に向かって抜け出て行った。後ろめたくてたまらなかった。サクにもモチにもその両方に。
そうだこれではいけないのだった。今はけじめがつけられてない。全てのことを棚上げにして、モチとはよろしくやれないのだった。
その感情の重さ分、僕には容易に手を出せなかった。けじめをつけてまっさらになり、それからことを起こそうか?
サクの魂取り戻したら、あの悪魔から取り戻したら、きっとその時晴れて言える、今はモチこそ愛していると。
僕は勝手にそう決めた。何時かは何時か、何時かでしかない。
恋というのは瞬間の、心の機微であるというのは、僕はそれまで知っていたはずだ。経験だってあったはず。
何時かは何時か、何時かでしかない、何時かは永久に来ぬこともある。
サクとのことで痛感したよう、僕は確かに知ってたはずだ。心が熱を持った時が、最良の時であることを。
あの時一人部屋に残った、モチはどういう顔をしてたか?僕の甘えを理解して、寂しく笑っていたのだろうか?
それとも僕の狡さに苛立ち、哀しく壁を見つめていたのか?
今となっては分からない。
外では晩秋差し掛かる、風が轟々荒れていた。夜明け近くに月が出る、日の出の後も有明に、細い光が残るだろう。
翌朝モチはいつも通りに、明るく機嫌もよく笑っていた。
僕はそいつに甘えたのだった。無かったことにするつもりもない。ただ先延ばししたのだった。
いつも通りに過ごしながらも、僕らは黙って意識しあった。何時かは触れ合うことになると。
僕は未来に期待をかけた。泥安(でいあん)は既に近づいて、成さねばならない時も近づき、使命の重みを刻々感じる。
その先の道に期待をかけた。全てを首尾よくし遂げたら、モチとの日々が待っているかと。
全く虫のいいお話だ。他愛も無くて笑ってしまう。あのままで、ずうっと二人で旅が出来たら…。
よくよくことを考えたなら、どうにも出来ない無理があること、確かに僕は分かったはずだ。
その時の僕は享受した、無邪気な希望に酔うことを、今現在を喰いつぶし、未来に期待をかけたのだ。
僕らはなるだけ村を見つけて、その村々に泊まるよう、心をかけていたけれど、だがそう上手くいかないときも、幾度だったか訪れた。僕らはどうにも野営をしなくちゃ、いけないときにも見舞われた。
そういう時には火を焚いて、炎の周りで色々話した。話さなきゃ、どうにもやりきれないほどに、渓谷の夜は寂しいものだ。獣と夜行の鳥の声、心の隙間に忍び入る。
僕はある時モチに尋ねた。特に意味など無かったが、ただ気になることだったのだ。
「精霊は、死んだら一体どうなるんだい?」
「人とそうそう変わりはないよ。大きな流れに還るだけ。光は闇に還るもの、闇は光りに還るもの。だけど自分がどうなるのかは、私自身も知らないよ。私は死んだこと無いし、死んだ者には聞けないじゃない。」
モチは答えてこう言った。
「精霊だってそういうものか。不死というのじゃないんだな。」
「主様なら、不死であるけど。私たちなら案外と、壊れやすいものだと思う。生まれ変わりをなさない限り、三十年しか生きられないんだ。」
「君は何回生まれ変わった?」
僕は彼女に尋ねて聞いた。
「六回ほどかな。つまりは百と八十年、私は命を永らえた。」
モチは答えてこう言った。
六回、つまりは六人の、娘の命をこのモチは、奪って代わりに永らえたのか。六人殺した、そうなるか。
僕に向かって見せる優しい、友人、はたまた妻の様な、明るい顔の裏にある、その本性をぼんやりと、想像しつつ、僕はなんだか、果てのない穴覗いては、わざと怖れを味わうような、そういう心地でそれを聞いた。
「人の命を犠牲にしても、君も死にたくないのかい?」
僕はついついこう聞いた。言ってしまって、しまったと、舌打ちしそうになったのだったが、口から出たならもう仕方ない。
モチは全く心も害さず、素直に僕にこう答えた。
「積極的には死にたくないよ。生きてるものはみんなそうだろ。だけど肉持つ生き物よりは、執着は大分少ないよ。
私みたいなものにとって、一番恐れることはねえ、命が消える事じゃなく、その魂が還れないこと。あるべき流れに乗れないことだ。天然自然に反したことだ。
だから私は嫌うのだ。『奴』、悪魔のあの所業。あるべき流れに還しもせずに、不当に手元に閉じ込めている。」
僕はぼんやり思い出す、男が自死して果てた時、モチがとっさに言った言葉を。
「彼の魂奪われた」
モチは確かにそう言った。精霊たちの本性に、基く言葉であったのだ。
「君には是非ともこの機会、あいつを消して欲しいんだ。もし仮姫の影武者を、殺す算段回避しても、あいつが生きている限り、策謀は限りなく続く。あいつを消さなきゃ君にとっては、意味ないことになろうとも。」
モチはこう言い、笑みを含まず、僕の瞳を真っ直ぐ見た。僕の体に改めて、苦くて重い緊張走る。
「分かっているさ、分かっているさ。サクの魂取り返しつつ、戦を防ぐ役目なら、頼まれなくてもやってやる。君は心配しなくていいさ。」
モチは少し、ほんの少し、寂しげな顔をした後で、すねた様な顔こう言った。
「私の命の三十年分、それも目的入れてくれなきゃ。私の命はそんなに軽いか。」
「いや、ごめん・・・。」
僕は即座に言い詰まったのだ。ああ無理もないことだった。
思ってみればサクは既に、失われているはずだった。僕が無様にあいつの術に、絡めとられていなければ、まだ僕のそばで微笑んでたか?だがそれはせんの無いことだ。過去は過去でしかないのだった。
だがモチはここで生きている。人の体に閉じ込められて、不完全ではあるけれど、だが確実に生きている。
モチはせんない物じゃない、取り返しの無い過去じゃない。
僕は彼女と進む未来を、思い描いてるはずだった。今この僕の伴侶としたい。
そんなモチを、後回しに言うその訳は、僕の抱いた後ろめたさだ。サクに対する、モチに対する。
サクの魂取り戻すため、そもそもそれの目的で、僕らは一緒に旅をする、そういうことになったはずだ。
だが今この時生まれ行く、モチに対する感情に、僕は戸惑い罪悪感を、サクに対して抱くのだ。
それであるのにモチに対して、最優先になれないことも、それも何だか後ろめたい。
それに何だかくすぐったかった。モチと話していることが、こうして過ごしていることが。それでわざわざ突き放すよう、そっけない様(よ)な態度とる。
僕は幼い子どもみたいだ。素直になれない少年のよう。本当は強く感じている、モチを生き永らせたいと。
「ごめんモチ、本当にごめん。」
僕は真面目に謝った。今述べた様なすべてを込めて。
「いいや、そんなに改まれても。」
モチはそう言い手を振った。僕の心を知ってか知らずか、もうすねたりしていなかった。
秋はどんどん深まって、僕らはずんずん進みゆく。
渓谷沿いにも紅葉が、山の上から降りてきた。視界の先には茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)山、白くとがってそそり立つ。茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国の名前の由来だ。
都が近くなってきたころ、モチはその声低くして、顔を顰めてこう言った。
「嫌な瘴気の塊が、この谷間から吹いて来る。随分厚い闇がある。奴の気配はその向こうから、汚く暗く輝いている。間違いなく、この先に『奴』の巣があるぞ。」
「奴が拠点としてるとこは、茶渡羅国ということか。」
僕はこの頬引き締めて、モチに答えてそう言った。
一体何の申し合わせか、サクを奪った『奴』の巣が、兄弟たちを巻き込んだ、陰謀のその舞台となってる。
サクの魂取り戻すこと、タチマチの兄を止めること、モチの獲物を取り戻すこと、まるで数珠でもつないだようだ、それら全てが同義であるのか?僕の使命はそこに在るのか?
僕の運命そいつがそこから、この僕を呼んでいるというのか?
第七話 「運命の地、泥安、そして再会」へ続く
第七話 運命の地、泥安、そして再会
第七話 運命の地、泥安(でいあん)、そして再会
僕らは渓谷に抱かれた、彼の国の都泥安(でいあん)に、一月近くの旅を終え、無事に入城したのだった。
つるべ落としの秋の陽が、赤く名残を残す頃合い、閉門時間のぎりぎりに、僕らはちょうど到着した。
紫紺に暮れ行く空の上には、明るい星が輝き始め、こんな辺鄙な山間に、忽然として現れる、壮麗過ぎるこの都市に、僕は心を奪われた。
今までずっと、渓谷を、人家のまばらなとこばかり、ひたすら歩いてきた僕らには、これは輝く刺激であった。
繊細華麗な建築物の、意匠と人の衣装の華やぎ、久方ぶりに味わう人込み、多種多様なる煮炊きの香。
街は夕刻夜の始めに、いそいそ活気づいていた。市で売り子の声が響き、花街で客を引く声が、歌うたうように響いていた。
しかし僕らはすぐさまに、街に漂う異様な空気に、驚き眉をひそめたのだ。
仗(じょう)弦(げん)国と架(か)弦(げん)国、二つの国の王子たちの、私兵が市中を闊歩していた。市に広場に住宅街に、あちらこちらで諍いが、ごろつきたちも巻き込んで、火花のように散っている。
茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国の王様の、腹の黒さを知り得ない、城内に住む国民は、不安に顔を暗くしていた。おそらく平時に比べたら、人出も少ない方なのだろう。
「何だか既に、ひっ迫してるな。」
僕は言った。
「ことは急いだほうがいいかも。」
僕らは真っ直ぐ城に向かった。ジュウサンが、鳩を使った通信で、手配をしていてくれてるはずだ。
城の正面、正門から、僕らは堂々入城する。門兵に、ジュウサンが書いた紹介状を、渡して取り次がれるの待つ。
中より侍従の長が来て、僕らに向かってこう挨拶した。
「詩人のイサヨイ様ですね。そしてこちらが奥様の、モチさん、いやいやお美しい。ジュウサン様より伺っています。さあさあ中へお入りください。」
彼はそもそも策謀の、詳細それを知らないようだ。ジュウサンがそう伝えていた。
どうやら件の計画を、知って一枚かんでいる者、思いのほかに少ないらしい。その反面、協力仰げる人物も、いないということだったのだ。
僕らはあっさり中へと入った。中の空気は市内より、なお一層に泡立っていた。
きれいに整えられた廊下で、庭でホールで回廊で、二つの国の武具を付けた、兵らがうろうろうろついている。
他国の兵が、こうして堂々、他国の城にいるなんて。王よりもなお大きな態度で、ふんぞり返っているなんて。
そうしてこれが、このことが、僕が易々潜入できた、言い訳という様なもの。
「今どき歌いで戦わぬ、昔ながらの詩人でらっしゃる。この城に、戦う詩人を招いたら、王子様方双方が、それぞれ戦う詩人を招き、城でも争い始まるでしょう。あなたがいらしてくれて嬉しい。私どもも久々に、歌を聞くのが楽しみですよ。」
侍従の長はそう言った。
とりあえずモチは僕の妻と、そういうことにしておいた。ジュウサンが言うにそれが一番、自然だとのことだったのだ。
「さあさあ広間にお通しします。お疲れととは思いますが、一曲歌って欲しいとの事。王様姫様おそろいで、広間で待ってらっしゃいます。」
ジュウサンの言った言葉によると、アリアケ姫と影武者は、もう入れ替わってるらしい。アリアケ姫は山奥に、幽閉されて、例の悪魔が、何時でも命を奪えるように、目を光らせているという。
見慣れないほど豪奢な城を、僕らは堂々闊歩した。旅装束も解かないうちに、汚れた足のそのまんま。
しかし何をか一体恥じよう!その先を、怖れることはあったとしても。
「ねえイサヨイ、この城の中の気配は異様だ。あちらこちらに足跡がある、悪魔の瘴気でぷんぷんだ。瘴気を感じぬ人は太いな。こんな空気のただなかで、当たり前の様過ごすだなんて。私たちには考えられない。
間違いなく、この城の中に巣があるぞ、あいつの住処がここにある。」
モチが耳元ささやいた。
僕は瞳を見はりながら、豪奢な細工で覆われた、城の内部を注視した。僕には何も感じない、感じられぬが理解した。
僕は自分の運命に、頭の先から飛び込んだこと、ヒリヒリしながら知ったのだった。
広間は緑灰色の石と、色とりどりの玉と金とで、繊細華麗に飾られて、碧い天幕垂れていた。
その下に、やはり優美な玉座が二つ、並んでしつらえられていた。王妃は既にこの世を去って、一人娘が残された。その王女こそが諍いの、焦点となっているのだった。
僕らは顔を伏せたまま、玉座の前に進み出て、並んで膝を折っていた。侍従の長が紹介をする。
「この方は、東の国をさすらって、この現代に有難くも、戦うことを良しとせず、人の心を打ち、癒す、それのみ心に掛けながら、研鑽積んだ詩人であります。当節稀な歌声を、陛下に姫にお聞かせしたいと、方々探してお呼びしました。」
僕は一足進み出て、一礼してから名乗りを上げた。
「イサヨイです。お見知りおきを。」
そうして顔を上げた時、僕の体を雷打った。
王は何だか蒼白く、覇気がない様見受けられた。あの悪逆な策謀を、企むようには見えない王だ。
だがそれは、僕にとってはどうでもよかった。
その横だ。姫様がいる、正確に言えば姫の影武者。青空の色に輝く絹の、豪奢な衣装の中にうずもれ、金銀宝石髪飾り、首に頭に重ねながら、命の炎が消えそうな程、儚く燃えるその体。
白い肌、艶やかな髪、葡萄の瞳、芥子の唇。
「ああサクだ・・・・。」
僕はその目を見つめ続けた。
確信が、大樹の様に育って行った。
サクも真っ直ぐ僕の目を、離れたところで見つめていた。
潤んで深く澄む瞳。
彼女もきっと動揺したのか?潤んだ瞳ははらはら揺れた、全く顔を変えないままで。
表情自体は変わらない、ただその瞳がものを言う。
目だけが語るそのことが、尚更情熱それを伝える。
モチが後ろで名乗るのも、夢か現でぼんやり聞いた。
僕らの間の時間が戻る。間に立った召使、兵士も豪華な宮殿も、モチすらすべて影となる。
一体どういうめぐりあわせか?サクの魂取り戻す、旅路の果てに生きている、サクへとたどり着くなんて。
僕と彼女の運命は、こういうめぐりに仕組まれていたのか!僕の心ですべてのことが、しっかり手に手を結び合う。
ここに僕らの運命がある、ここに僕らの仕組まれた、その運命は沸点となる。
まだ取り戻すこと可能なのか?失ったはずのあの未来は!
僕の心に甘くて弱い、願望が頭もたげだす。確かに八年経ったのに、もう八年も経っているのに。
取り戻すには重すぎる時、それすらすべて無意味となった。
「歌を聞くのは久しぶりだな。さあさあ一曲歌ってくれ。姫や、お前は何が聞きたいか?」
王がにこにこ話しかける。
「可愛い小さな月の歌を…。」
モチは一体どういう顔で、それを聞いていただろうか?
彼女の言葉によるならば、それの言葉でモチは気付いた、姫の影武者それこそサクと。
僕とサクとの運命が、つる薔薇の様絡み合い、引き離そうとて引き離せない、それに気づいた、そう言ったのだ。
僕は時間がたった後、モチの心を思いやったが、その時の僕の心の中は、不意に廻った再会に、サクで心がいっぱいだった。心ときめき胸は躍った。周りは全く見えなかった!
ああ、サクがいる、サクがいる、遠い昔に失くしたはずの。僕の可愛いサクがいる!
歌いを始める僕の周りで、数多の蝋燭ちらちら揺らぐ。この僕の、情熱の火はそれを凌駕し、暴虐に歌に染みだした。
右と左に居座った、二人の王子がにらみ合い、気に入らなそうに僕を見る中、召使らがうっとりと、僕の声音に聞き入る中で、表向きには心を抑え、歌に全ての熱を込め、僕は歌った、歌い歌った。
この世に二人、サクと僕と、ただ二人だけが存在するよう。二人の間に空間が、広く存在することで、尚更二人は一つとなった。甘い絆を確認したのだ。
モチは一体何思ったか?その時僕はちらりとも、モチの心を想わなかった。
心は完全征服されて、他の女性が入る余地を、髪の毛一本ほどにだって、残していない状態だった。
僕はひたすらサクだけを、サクだけ見つめていたのだから。
第八話 「二つの心、二つの想い」に続く
第八話 二つの心、二つの想い
第八話 二つの心、二つの想い
「あれはやっぱりサクなのかい?」
歌い終わって部屋に通され、休みを取っているときに、モチはこのよう僕に尋ねた。
あの時僕を現実に、引いて戻したそのことは、モチのその顔見たことだった。今現在のこの僕の、心がどんと追いついてきて、その衝撃に唖然となった。
全く甘くはない事態だった。ほんとに全く甘くない…。
巡り合えたは運命ならば、この先どう言う運命が、僕らに待っているのだろうか?
悪魔の策謀、サクの立場、モチの命のそれらが全て、避くこと叶わず悲劇に僕らを、突き落とすのではないだろうか?
僕は呆けてぼんやりしていた。床にべったり座り込み、何も焦点結ばぬ目開き、途方に暮れていたのだった。
「確かにサクに違いない…。一目でわかった、彼女はサクだ、第一あの曲覚えているのだ…。」
僕らの前には部屋の中に、運んでもらった夕餉の馳走が、ぐるりと並んでいたのだった。僕はほとんど手を付けなかった。口に運んでみたとこで、まるで砂でも噛んでるようだ。
心は乱れ、呼吸は浅く、ただこの差配に慄いていた。神様は、僕を助けたつもりだろうか?
「彼女は生きていたんだな。悪魔のそそのかしにも負けずに…。強い心で生きていた…。」
モチがぽつりとそう言った。
僕の心に甘くて苦い、慈しむ様(よ)な感情が、湧いては瞳を熱くした。サクを守護する氏神と、サクの強さに感謝した。
全ての時間が戻っていた。この八年の意味すらも、軽く凌駕をする勢いで。
心が、時が、引き戻される。
だが僕はもう昔の僕と、ぴったり重なる訳じゃない。半端に得てきたことらが全て、僕に警告するのだった。
この運命に警戒せよ、お前のなすべきこととは何だ、お前の傍ら心配そうに、見つめる女はどうするつもりだ!
今までは、モチとサクとは両立していた。僕が義務から選択を、しなくてもいいものだった。
サクの魂取り戻し、モチの命も手に入れる、それは一つの事になり得た。悪魔と敵対する訳に。
ああしかし…。
モチなら僕の心の半端な、傾き加減を感じとり、静かに注視をしていたのだった。
彼女の勘は鋭くて、鈍さと無縁であるからに、今までずっと育て続けた、二人の微妙な関係が、否応なくも変化したのを、確かに感じて取ったはずだ。
後ろめたさにぞっとする。モチは何にも悪くない、何にも悪くないというのに。
沈黙が、僕らの間に長く伸びた。言葉を発する勇気が持てない、僕の代わりにモチが言った。
「君は今でも愛しているか?サクのそのこと愛しているか?」
僕は一瞬黙った後で、つぶやくようにこう言った。
「多分そうだといえるだろう。君はこういうことを言ったら、一体どのようとらえるだろうか?
心が幾重に重なって、サクを愛していたころの、僕と現在今の僕の、二人の心が入ってるんだ。僕の体に、今の体に。
そうして二つの僕の利害が、著しくも対立するのだ…。」
モチは皮肉に微笑んだ。初めて会った時の様。
「ああそうなのか。人の心は、そこまで精緻に出来ているのか。心が一つでないことは、私も現在学習中だ。ほんとに巧い口実だねえ。君の心を尊重しよう。それにして…。」
モチはそのよう言葉を切って、瞳に強い力を込めて、僕にきっぱり言い切った。
「君は尚更止めなくてはな。策謀それの内容を、君は覚えているだろう?このままいけばサクは確実、『奴』に殺され奪われる。」
モチは真顔でそう言った。僕の体に電気が走る。
全くモチの言う通りだった。このまま何もせずにいたなら、サクは確実殺される。
僕の心は急激に、急かされる様な心地になった。いてもたってもいられずに、思わず僕は立ち上がる。
「一体どこへ行こうというんだ!もう今日は、何もやらずに食べて寝るんだ!」
モチが苛立ち隠さずに、胡坐を直してそう言った。僕は決まりが悪くなり、座り直してこう言った。
「君は怒っているのかい?」
「ああ怒ってるよ、怒ってる。君があんまり情けないから。何を動揺してるんだい!当初の計画それならば、何も変化はしていない。影武者がサクであっても無くても、彼女の命を救うことは、決定事項のはずだろう?」
僕は黙って従った。僕は絶対モチには勝てない。モチに力があっても無くても、僕には絶対勝てないのだ。
その晩眠れず僕は寝返り、何度も打っては溜息ついた。
僕の二つの心について、思いは千々に乱れていた。
モチに対して昔の僕の、思いがまだここ燃えていると、そうは言ったがそれだけじゃない。
現在の、僕は守ってあげたいのだった、サクを過酷な定めから。
それを愛ではないと言えるか、当てはまらないことだろう。今の僕でも愛してる、サクを愛しているのだった。
だがモチに、対する気持ちは愛じゃないのか?いいやそいつも当てはまらない。
僕は彼女を必要としてる。モチがいなけりゃ成り立たない。今現在の僕を支えて、負荷に耐えうる強さにするのは、モチをおいては外に無い。愛でないとは全く言えない。
両立しないと思ったことが、僕の心で両立していた。
僕は二つの愛を持ってる。どっちが大事であるかなんて、僕には全く判断付かない。
僕は何時からこうなったのか?昔の僕は、潔癖で、こういう狡い男のことを、鼻で笑ったものだった。
自分自身が遭遇しなきゃ、ほんとのことは分からない。僕が小馬鹿にしていた男も、苦しみ悩んでいたかもしれぬ。
僕は悩みに疲れて起きた。モチはすっかり眠ったようだ。何時でもどこでもよく眠れるな。
窓からは、秋の夜空がのぞいていた。月もすっかり沈みゆき、冷たい星が降り注ぐ。
僕の心は過ぎ去った、思い出の中を彷徨った。
あれもこういう晩だった。ふと目覚めると窓際で、サクが涙を流していた。声を殺してすすり泣いてた。
「一体どうしてそんなに泣いてる?」
僕は慌てて起きだした。サクの背中に手を当てて、幼いなりに一心に、サクを慰めようとした。
今夜と同様星空が、窓から滑り込んでいた。
今より季節はあったかく、サクの背中は汗ばんでいた。その感触を今でも憶える。
「あの晩を、今日は何でか思い出したの…。私が神に嫁いだ晩を…。」
恐る恐るにサクは言った。自分の心に考えに、サクはおびえて慄いていた。
サクの目は、吸い込まれるよう澄んでいた。僕の心を映し出し、その時の僕は全くに、恥じる理由を持たなかった。
「あの夜に、私は抜身の剣を抱き、衣装を着けて待っていた。神様は、窓の外から現れて、お前と契りを結ぶのと、神官様から言われていた。
あの時私は分からなかった、神様が、ほんとに来るのか、来ないのか。私はただただ待っていた。待ってるうちに知ったのよ、私は今宵死んだんだって…。」
「君は生きてる!そうじゃないか!僕の目の前生きてるよ!手首に触れたら鼓動も打ってる、君は確かに生きている!」
僕はそのよう反論した。ああ僕は必死だったのだ、サクの涙を止めようと…。
「体としては生きている、だけど私は死んだのよ。私の命は捧げられたの、この世の外の神様に。もうこの世では幸せを、人と同じ幸せを、望んでいてはいけないの。人と同じになれないんだわ…。
神様は、遂には姿を現さなかった。私が村を救えたか、それは全く分からない。実感も、効果も全く知らないわ。
それでも私は確かに死んだの。この世の外の者となった。
私自身の人生は、あの晩終ってしまったの。もうこの命も私のじゃない、祭壇の上の子羊よ。
私は何故かはっきり分かる、体を生かす命もいつか、何か大きなものの為、贄に捧げて屠られるだろう。何か大きなものの為に…。それまでは、燃えかすの生を送るしか、私に道はないんだわ。
苦しみ悩むそのことも、私の命を磨く功徳よ…。刃が振り上げられるまでに、苦しめるだけ苦しめられる。
一体何年生きられるのか、それははっきりしないけど…。どこかで私を呼ぶ声がする、暗くて強いその声が。
私の命はそこを目がけて、雪崩を打っていくんだわ。」
途切れながらもサクは言った。瞳に窓の外にある、星より強い光があった。
僕は必死に言ったのだ。
「君は燃えかすなんかじゃないよ!十分以上の人間だ!運命に、僕は抗い否定する。僕の歌いの世界のように、最後の生の一滴まで!」
「予言できるわ、私の命は、あなたの歌の女性のように、運命に、期待をかけた罰の分、酷い最期を遂げるだろう…。」
サクの瞳は深く澄み、その中に何があるのかは、分からぬほどに暗かった。そうまるで黒い鏡のように。
サクの瞳に映るのは、今現在の僕の姿だ。暴力的な運命に、僕は抗い格闘している。
サクを死なせぬその為に、あの時よりは一途じゃないのか?モチが傍らいることで。
昔の僕は必死に言った。その時なりに考えて、最大限にこう言った。
「君が燃えかすであるなど、そんなの誰が言ったんだ!君はここから生き直すんだ、大丈夫きっとやり直せるさ。
辛い昔が合った分、これからきっといいことだらけさ。僕もたくさん協力するよ。」
ああなんて、無邪気で無知な物言いか、そう言う僕がサクを見捨てて、忘れ去ってくそのことが、全く皮肉に響くほど。
サクが送った人生が、苦痛に満ちたものだったこと、それは察して余りある。ああサクの言葉なぞったように。
ジュウサンが言うことによると、サクは三年ほど前に、この城に連れてこられたという。悪魔がそれを差配したのは、分かり切ってることだろう。
それまでどんな辛酸を、嘗め尽くしてきたことだろう?僕が彼女を忘れた後で、忘れて呑気に歌っているとき。
僕の心に湧いたのは、何としてでもサクを救うと、命に代えても救おうと、そういう固い決意だった。
「君が燃えかすであるなど、そんなの誰が言ったんだ!」
僕はぼそりとつぶやいた。腹に力がみなぎった。
「君はここから生き直すんだ、大丈夫きっとやり直せるさ。辛い昔があった分、これからきっといいことだらけさ。」
僕はすっかり心を決めて、昔の僕と約束をした。右手をがっしり握り合い、固く約束交したのだ。
そうして僕は振り返る、僕の後ろで熟睡してる、モチの呑気なその姿。
このことだけは割り切れなかった。切っても切れない情があった。
見捨てることも、振り切ることも、欺くことも出来ないし、かといいモチを選ぶのも、それもやっぱりできないのだった。
一体彼女をどうしよう?迷いの海に突き落とされる。僕は途方に暮れていた、一人途方に暮れていた。
第九話 「老庭師との出会い」に続く
第九話 老庭師との出会い
第九話 老庭師との出会い
開けて翌朝、起きてすぐからモチは不機嫌、苛立ちを隠すことはなかった。
寝付かれないのも手伝って、朝寝坊した僕に向かって、攻撃的に起こしにかかった。
「ほら起きろ、起きろったら!朝餉がここまで運ばれてきた、君がなかなか起きないから、召使たちが気を廻したんだ。」
僕はガンガン揺り起こされて、寝ぼけまなこで見まわした。モチは侍従が用意した、男の晴れ着にきっちり着替え、何だか一層妖艶に、僕の目の前突っ立っていた。
そういう感想持つことは、僕の心に反したことだ。全てに後ろめたくなり、僕は言葉が出なかった。
黙ってベッドを抜け出して、黙って朝餉を食べだした。モチはそいつも気に入らなそうに、腕組みをして僕を見ていた。
一晩空いたそのことで、大分心が戻っていた。少しだけなら冷静だった。それでとっても空腹なこと、今更のよう僕は気付いた。
昨夜はほとんど食べられなかった、昨日までならろくな食べ物、ほとんど食べずに旅をした。腹が減るのも道理だろう。
「随分がつがつしているね。昨夜は心配などして損した。」
モチがその様皮肉を言った。僕は何とも反応できず、ただ黙々と食べるだけだ。
僕らの間に何とも微妙な、空気が長く淀んでる。モチにしたって気まずいことが、僕にも痛く理解できた。
「考えたんだよ、これからのこと。悪魔の計画くじくための、こちらの出方を考えた。」
少し離れたところに立って、モチはこのよう話しかける。
実際的なことを話すの、心や気持ちを話すより、今はハードル低いだろう。
僕にとってもそれは同様、僕は黙って聞き入った。
「前にも言った通りにね、きっとここには奴の巣がある。悪魔というのは気にいる場所に、居心地いい巣をつくるものだ。
おそらく奴は長い事、この国に巣を置いてきた。そういうしるしが色々あるよ。そうして城の雰囲気が、あいつはとても気に入った。もともと瘴気も濃かったんだろ。
この城の中に今の巣がある。そうしてこちらの出方がどうか、逐一見張るつもりだろう。様々な、邪魔や悪意に満ちた茶々を、きっと交えてくれるだろうさ。
私たちは、『奴』の期待に答えねば。期待以上に振舞って、あいつの鼻を明かすのだ。油断をしているそのうちに、巣ごと叩いてつぶしてしまえ!」
「一体どうしてあいつが僕らに、『悪意に満ちた茶々』というのを、わざわざ交えてくるのかい?」
僕の言葉にモチは言った。
「それが悪魔の性分だ。人の不幸を喜ぶものだ。人が悩んで苦しんで、誰かを憎んで涙を流す、それを何より好んで見るのだ。わざと不幸の種をまき、そういう事態を引き起こし、まるで芝居を観る様に、何よりの娯楽として観るのだ。
この城にもぐりこんだなら、奴がこちらを餌と見て、苦しみの種をまきに来ること、警戒しなけりゃならないよ。
呑気に歌って食ったりしてては、君はあいつのいい鴨だ。」
最後の最後に皮肉で終える。モチはやっぱり不機嫌だ。
僕はなるだけ反応せずに、疑問点だけをこう述べた。
「それなら悪魔の巣がどこに、在ってあいつがどこで僕らを、愉快に見張っているのかは、君の力で分からないのか?」
モチは何だかすねている様(よ)に、口をとがらせこう言った。
「あまりに気配が濃厚で、かえって細かいとろろが分からん。それの他にもこの城は、強い瘴気が満ちている。鼻のよく利く犬が返って、強い臭いにつぶされるよう、私の感覚鈍らせている。勿論あいつは、そのことも、きっと見越しているんだろうさ。」
モチは憮然とそう言った。自分の力が通じないのに、モチもやっぱり苛立っていた。
「君は噂を探ってみてくれ。あいつが黙ってこの城で、サクの命を盗るまでに、大人しくしているとは思えん。きっとこれまでにしたって、何かは悪事をやらかしている。妖しい噂が立ってるはずだ。」
僕は必死に考えて、こういう言葉を彼女に言った。
「君なら僕が宴席や、外出の際呼ばれていたって、自由に動くことが出来よう。君なら誰も、警戒しないさ。」
僕は彼女を見つめて言った。
完璧すぎる肉体に、光の命を宿した女性。僕が光に安心する様、他の誰でも本能的に、彼女を信頼するだろう。それははっきり確信できた。
モチは何だか居心地悪そう、顔を歪めてこう言った。
「分かったよ。君は体が拘束されて、確かに自由に動けないよな。情報集めは任された。確かにきっと役目を果たすよ。」
モチはそのよう言いきった。不機嫌なことを差し引いたって、気持ちの良いその返事であった。
僕の心はわずかに温む。じんわりとした温もりが、心の中に広がった。
ああ僕は、モチを利用しようとしてるか?僕の目的果たすために。サクのこと救うその為に、モチの力を使うのか?
ああそれだけではないのだと、僕は心で繰り返す。モチは彼女は必要なのだ、この僕にとって何よりに。
僕はその日のうちからも、宴席酒席に狩りの会に、歌いをするため呼ばれたのだった。自分の言葉の裏付けする様。
宴の席では当然と、サクを目にする機会を得た。目にする、いいやそうではないか。僕らは見つめ合っていたから。
遠くに距離を置いたまま、僕らは見つめ合っていた。瞳に全ての熱を込め、互いに確信深めつつ。
だがだれ一人気づかなかった。二人の間のこの恋に。
僕らは言葉も交わさなかった。ただ熱を込めて見つめていたのだ。
確かに二人の王子たちは、気に入らなそうにしていたが、僕らの間に隠された、秘密なんぞは知るはずもない。
彼らは全く無神経、鈍くてがさつであったのだ。恋する姫が別人と、入れ替わっても気づかぬ二人。
ぼくなら八年経ったって、華麗な衣装で別人と、見まがうような状況だって、確かにサクだと一目で気づいた。
この感情なら本物なのだ、道徳心に富んだ誰かが、僕の不実を糾弾しても、それだけはそう言い切れる。
僕とサクとの間には、情熱が強く結び合ってると。
請われて歌いを披露するうち、僕は大分貯金が増えた。
それ程に、この城の人は娯楽に飢えて、心を慰めたがっていたのだ。きな臭いことにうんざりしていた。
二人の王子を除いては、誰も戦を望んでいない。覇気無き王はどうだかは、はっきりしないことであるけど、サクの周りの侍女たちは、僕らを世話する召使たちは、皆一様に平穏を、希求している様だった。
サクを救うということは、戦を止めると同義となるのだ。この国の人を救うためにも、僕らはサクを守らねば。
僕は決意を新たとしたのだ。
僕が方々呼ばれているうち、モチはあの朝言った通りに、あちらこちらに顔出して、知り合い増やしている様だった。
その人たちから情報を、草草集めてくるのだった。
「一月前、厨房の隅のかまどから、汚い虫の大群が、わんさか湧いてきってね。」
「それは悪魔と関わりが、ある話とは言えるかい?」
「真っ黒く湿る虫だったって。まるであいつの髪の毛みたく。こいつが『奴』の仕業なら、やっぱりあいつは悪趣味だ。
恐怖や苦痛の叫びじゃなくて、嫌悪の叫びであったって、『奴』の心を潤すんだな。全く理解できないことに。」
「あいつの仕業と決まった話じゃ、それは全くないだろう。もっと実のある話を集めろ。」
モチは憮然と僕を見た。
「私の苦労を知らないな!誰にも怪しまれぬように、話を集めるなんて言うのは、楽に見えるが楽じゃない。
君は呑気に宴席で、歌いを披露するだけだろう。歌っていたなら誰も君を、怪しむことは無いだろうさ。歌いで戦をしない詩人を。
そうしてほとんど例外なく、愛しのサクが君を見つめる。彼女のために歌ってるんだろ!王子も王も置き去りに、二人の
世界を作ってるんだろ。全くこれは腹立たしいな。私が苦労している間に。
私の焦りや退屈しのぎに、お幸せ過ぎるイサヨイ様は、付き合う暇も無いというか?」
そう責められて言い淀む。僕は目線を泳がせた。
「いいや君なら良くやってるよ…。引き続きながらよろしく頼む…。」
「全く君は狡いんだな!」
モチは怒ってどすどすと、大股歩きで窓へ行き、僕の上着をぼふぼふ払った。埃が朝日にきらめいている。
僕は説明しがたい思いだ。なじられるのは心苦しい、モチが怒れば怖いと思う。
だがしかし、ここから得られる安らぎは、どう説明すりゃいいだろう?
このやり取りに心は温む。緊張続きのこの城で、確かに心は安らぎを得る。
さしてめぼしい情報を、得られないまま三日が過ぎた。
僕らは焦りを感じ始めた。時間はどうにも制限されてる。のんびりしている余裕は無いのだ。
だがしかし、三日目の晩モチは言った。
「これが何かの手がかりと、言い切れないけど噂を得たよ。妖しい噂を聞き付けた。」
モチは続けてこう言った。
「上層階で働いていた、侍女が三人行方不明だ。」
「それはあいつの仕業なのかい?」
僕は考え問いかけた。
「まだそうと決まるわけでは無いが、いなくなる理由(わけ)も無いという。三人供に月のない晩、廊下に置いた燭台に、灯を灯しているその時に、いなくなったということだ。それもわずかに一年のうち。」
僕は右手で顎を撫でた。確証持つこと出来ないが、何かのある種の確信が、僕の心にすとんと落ちた。
「確かに何だか妖しい気がする。それは一体どこの廊下だ?」
「上層階にあるとしか、今のところは分かっていない。」
モチはそのよう答えて言った。僕の悩みは深くなる。
「ありがとう、モチ、引き続き、その情報を調べてくれよ。きっといつかはチャンスが来るよ。」
僕は半分自分に言うよう、そういう言葉を口にした。
次の日の午後、僕は庭で、園遊の会に呼ばれていたのだ。
この時期にしては陽気に恵まれ、遅咲きの秋の花々が、霜にも負けずに咲いていた。
晩秋彩る花々は、まるで健気なサクのようだ。霜に耐え、寒風に耐え、それでも花弁落としつつ、瞳を空に向けている。
王はこの日は不在であった。影武者の姫のサクと王子、例の二人の王子らが、家来を従え集っていた。
僕は彼らの要望により、コクリコ姫の歌を歌った。西楼亜琉(ろうある)に名高くも、悲運の定めを負った姫君。
僕はこの日も目の前の、サクに向かって歌を歌った。他の誰かの為じゃなく、他でもなくサク、彼女のために。
コクリコ姫を賛辞する、言葉でサクを賛辞する。僕の声音は僕の恋情、余すことなく載せて鳴る。
悲運の定めを送った姫だが、僕ならきっと君を救うと、そういう願いも託しつつ、僕はひたすらサクへと歌った。
「止めい、止めい。」
仗(じょう)弦(げん)国の王子が突然、僕の歌いを止めさせた。
「全く心が籠っておらぬ。そなたの歌は形だけ、虚ろな中身のまがい物。声だけ良くとも表面だけだ。アリアケ姫の可憐さ、清さ、それには全く不釣り合いだ。ここはひとつ、私が歌でも即興しよう。」
こいつは何を言ってるか?サクに対する僕の想いを、所詮こいつの感性じゃ、感じられぬか、そうなのか?
僕は呆れて歌いを止めて、楽器を膝に静かに降ろした。
試しに聞いてやろうとも、こいつが何を歌うのか。
「それならきっと私の方が、想いの強さに似合った歌を、高貴な我身に相応しい、詩心で生むことが出来よう。私の姫に対する気持ちは、そなたよりもっと熱いのだ。」
架(か)弦(げん)国の王子も急に、対抗心を吐いたのだった。抜け駆けなどは許さぬと、露骨にけん制しているのだ。
「私は薔薇を素材に使う。」
架弦国の王子はそう言い、家来に琴を運んで来させ、頭をひねり始めたのだった。
「ならば私はダリヤにしよう。」
仗弦国の王子も言った。
何を言ってる、こいつらは。サクなら大輪ではなくて、もっと細くて儚くて、群れて咲く花、風に舞う華、風にたわんでそよぐ花。
ああ全くに腹立たしい、違いが分からぬ貴人など!
二人はともに琴を構え、時折家来をののしりつつ、ぶつぶつ曲を作り始めた。
そのまま時間は無駄に流れた。その場の誰もこの二人、自分が自分に期待するほど、優れた歌を作るのは、無理というのを知っていた。
しばし後、僕は思わずあくびをし、高く上がった雲を眺めた。王子らは、きっとそいつが気に入らなかった。
「そなたは私を愚弄するのか!素人の、思い付きだとそう舐めるのか!」
「そのようなことは思ってません。私(わたくし)も、詩を生むときは苦しむものです。愚弄するなど、ご冗談を。」
僕は慇懃そう言った。全ては彼の言った通りだ。心昂る素人の、思い付きだと言うものだ。
「私が曲をよく出来ぬのは、素材がここにないからだ。のう詩人そなた採ってまいれ、深紅の薔薇を採ってまいれ。」
王子が突然言い出した。もう一方も口をそろえる。
「我にはダリヤを採ってまいれ。咲き誇る花が目の前あれば、詩心もきっと湧ようぞ。」
「今の季節に?薔薇を?ダリヤを?」
僕は非常に戸惑った。今は晩秋差し掛かる頃、そういう夏や初秋の花は、もう枯れている頃合いだ。
「そなたは我らを愚弄した、それの償いせねばならぬ。それなる花を採ってまいれば、この度だけは許してやろう。」
僕は居住まい正したのだった。きりりと跪いたまま、平伏しながらこう言った。
「ご要望とあら、御心のまま。」
僕は即座に立ち上がり、園遊会の華の輪を、一人きびきび抜け出した。
サクがこの身を案じたように、おろおろ見つめているのが分かった。
サクの立場じゃそれを他人に、気付かれることは許されない。僕は彼女の不安を和らげ、安心させるように自信を、背中に示して立ち去った。
僕は探しに探しに探して歩いた。もしかしたならこの庭の、どこかに一輪残っているかと。
しかし視線は探しつつ、頭は花が見つからぬ、場合に何と切り抜けるかを、回転速めて考え続けた。
僕らの仕事でよくあることだ。我儘で無茶な貴人に対する、立ち振る舞いならわきまえている。
その合間、僕の頭にふっと浮かんだ、大輪の花であるのはむしろ、モチにこそきっと相応しい。
その色、香りで周り中、明るく照らして平伏させる。
モチの姿を思い出し、僕はじんわり苦しくなる。
モチは苛立ち隠さないが、サクの方ではどう思うのか?モチが妻だということにつき、どういう心を抱くのか?
サクに尋ねる方法はない。僕は想像するしかないのだ。
僕はそのうち北側の、庭の外れに来ていたのだった。そこにはそれほど手が入らずに、庭園の他の区域より、野趣があるよう思われた。
この時分だといくら晴れても、午後遅くなるとひんやりしてくる。木の葉はそろそろ枯れ始め、下草も水を失い始める。
見上げれば日は心細げに、冬の気配を醸しつつ、それでも懸命照っている。
一本の、柘榴の大樹が生えていた。もう大分に葉を落とし、ルビーのような実も見えない。
だが一瞬、真っ赤な何かが見えた気がした。視線を戻しも一度よく見る。
木陰に朱赤の衣服が動いた。こんな所に誰だろう?何だか妙に小さな影だ。
僕は覗いて見たのだった。
それは小さな女の子だった。年の頃なら七つか八つ。見た所、平民であるようだった。
茶渡羅国のお土産の、置物のように素朴で優しく、純粋そうな顔した少女。
何故か彼女は自分の体を、窮屈そうに縮込めて、まるで何かを避ける様に、大樹の陰に隠れていたのだ。
彼女はガタガタ震えていた。顔に瞳におびえがあふれる。
僕はなるだけあけっぴろげに、ガサガサ彼女に近づいた。静かに近寄ったのならば、尚更彼女を怯えさせよう。
それでも少女は驚いて、僕の足音聞いたとたんに、悲鳴を上げて縮み上がった。
だが僕の顔を見たとたん、少女の顔からおびえが消えて、安堵した様な表情に、半端に変わっていったのだった。
「こんな所でどうしたんだい?」
僕は優しく言ってみたのだ。見たところ他に誰もおらず、彼女が何を怖がるのかが、僕には全く知れなかった。
「あそこにいるの、怖い人が…。」
その女の子はそう言って、頭上の塔を指さした。
そこには城の統一建材、緑灰色の石の基本に、色鮮やかなモザイクの、装飾が着いた円柱の、小さな塔が立っていた。
塔は何だか傾き加減で、僕の実家の傾いた、塔を何だかほうふつさせる。
木の枝がそこにかぶさっている、あまり綺麗な紅葉に、変色できない木の枝が。斑に緑の木の葉は何だか、不吉ささえも醸し出す。
だがそれだけだ、それだけだった。僕のみる目は『怖い人』を、全く認識できなかった。
「僕には何にも見えないよ。」
僕はそう言い安心させよと、彼女の背中をさすってやった。
心当たりはずばりと有った。『奴』が何かで絡んでいると。だがこんなにも小さな子供を、怯えさせるは本意じゃない。
僕は小さな少女の背中を、優しくさすって言ったのだった。
「怖い人など僕には見えない。」
「イト、イト、そこか!」
老人にしては堂々と、美しい声を響かせて、一人の男が現れた。強く日に焼け、太い腕(かいな)、髭をもじゃもじゃ生やしていた。声には厚い慈しみ、慈父の心がにじんでいたのだ。
「おじいちゃん!」
小さなその子はそう言って、その老人に飛びついた。
老人にしてはしっかりと、厚みを持った胸板に、薄茶の羊毛紡いで織った、汚れた服をまとった男は、少女を大事に受け止めた。
僕がそこから得た印象は、幼い頃の自分に還って、あの時の祖父に再びに、出会ったような心地であった。
老人と、祖父とはそれ程似通っていた。顔ではなくて印象が。声の醸した印象が。
今彼の腕の中に急いで、飛び込んだのは少女ではなく、僕自身であるかのように、僕の心は引き戻された。
「この子はあなたのお孫さん?」
僕は低調挨拶し、彼に向かって尋ねて言った。僕に湧き出る感情を、極力抑えてそう言った。
「あなたはジュウサン様ではないか!」
その老人は一目見て、驚きかくさず僕に向かって、小さく叫びを投げかけた。
「ジュウサンのことをご存知ですか?彼は双子の弟なのです。僕の名前はイサヨイです。」
「何と何と、そうでしたのか。ジュウサン様の双子の兄と。あなたの家とはおじい様の、代からよくよく知っております。」
「あなたは祖父を、ご存知ですか!」
僕は小さくそう叫んだ。僕の記憶の中の祖父と、今目の前のその老人が、強くしっかり手を握り合う。
こんな所であの祖父と、関りを持っていた人と、導きのように会えるのなんて。僕は心が熱くなった。
それ程に、僕にとってはあの祖父は、偉大な人であったのだ。
「ネマチ様なら存じております。この地にも、何度もおいでになってもらった。」
老人はそう僕に教えた。
落ち着いた声、控えめで、品位に満ちたもの言いは、彼が一介ただの人夫と、思えない様な態度であった。
それさえも、記憶の中の祖父と重なる。その身なりにはふさわしくない、高貴な人であるかのような。
「お爺ちゃん、怖いよ、怖い人がいる、早く早く、帰りたい!街のお家に帰りたい!」
火が着いたよう少女が言った。おびえと安堵で瞳から、涙がぼろりとこぼれて落ちた。
老人は、その子をこう言いなだめすかした。
「お前はまたまた夢でも見たか、ここには悪い者など居ないよ、歩琉(ほる)渡(ど)の夢の都であるのだ。
イサヨイ様と言ったかな、申し訳ない、このイトは、少しばかりに夢見がちでね、夢と現の区別がつかない。ご心配など無用です。すぐに機嫌は直りますから。」
老人はそう言いながら、僕に向かって右手を出した。ガサガサに荒れた手であるが、なぜか優美な風がある。
「私はミカと言う者です。ここの庭師をしております。おじい様には随分懇意に、厚く接していただいたもの。ジュウサン様もこの城に、幾度もいらして下さったのです。」
僕も右手を差し出して、しっかり握手をしたのだった。
信じあえるという予感に、僕の心は高鳴った。祖父が僕らのその為に、導き差配をしたというよう。
「ところでイサヨイ様でしたかな?こんな所で一体何を?」
この質問に、忽然と、僕は厄介ごとのあらまし、思い出しては苦笑してしまった。
ミカと名乗った庭師は僕に、季節外れの薔薇とダリアを、両方揃えて持たせてくれた。
「こんなことならお安い御用。ここだけの話王子たちには、皆うんざりとしておりますとも。」
彼もそう言い笑っていた。
僕は首尾よく二種の花、携え遊びの席へと戻った。
サクならほっとしたように、優しく哀しく微笑んでいた。
王子たち、自分の無理がかわされたのに、そもそも関心持って無かった。
彼らの作った歌がどんなに、滑稽なものだったかは、あえては語らぬことにしようか。
ただそこにいた誰もがが、苦笑を噛んで殺すのに、必死に努力をしたのであった。
僕は素知らぬ顔をして、その後部屋へと戻って行った。
しかし中へと入ったら、顔を火照らせモチを呼んだ。そうして今日の出来事を、話して聞かせたのであった。
第十話 「迫り来る期限と、祖父の影」に続く
第十話 迫り来る期限と、祖父の影
第十話 迫り来る期限と祖父の影
「全く彼と会えたのは、神様の意図を感じるよ。僕らに味方をくれたんだ。」
「ふうんそうか。私は何だか不安だな。そうそう上手くいくのかな?天の主は時に残酷、償わなくてもいい様な、罰を下界に落とすんだ。
それより一番気になることは、イトという子が言ったこと。『怖い人』、それは悪魔のことじゃ、あいつのことではないのかな?」
モチは僕らの出会いには、あまり共鳴できないようだ。
祖父に対する僕の情を、モチはほとんど知らないはずだ。それなのだから仕方が無いか。
それより彼女が興味を持ったは、イトという子が言ったことだ。
モチはこのよう僕に言った。
「小さい子どもは敏感なんだ。大人じゃ感じぬことを感じる。精霊よりは鈍感で、大人たちより敏感なんだ。
私も君が言うように、悪魔の気配を敏感に、感じ取ってる可能性、高いと思う、そう思う。」
「あの塔に、悪魔の巣があるかもしれないと?」
「今すぐ探ってみようかな。」
彼女の言葉にぎょっとして、僕は即座にこう言った。
「僕はこの後酒席があるんだ。一人でなんか行かせられない!」
僕はこう言いモチを止めた。いくら僕でもそこまでは、性根は腐っていないもの。
モチに頼って甘えても、そこまでのことはさせられない。
「いいやこのまま一人で行ける。探りを入れるだけだから。」
モチは強硬言い張った。どうにも彼女もあせってて、余裕が見えないようだった。
僕らはしばらく言い合ってたが、すぐに使いの者が来て、僕を酒席に迎えに来た。僕は何度も止めるよう、モチに言い残した後で、渋々ながら出て行った。
無理などしては欲しくなかった。
宴の席でも僕は案じた。サクの目の前歌いながら、モチのそのこと案じ続けた。
今頃悪魔の手にかかり、無残な姿となっていないか?まだ最悪とは言えないが、人質になど、なっていないか?
僕は必死に振り切って、表面上はいつも通りに、請われるままに歌を歌った。
そのことに、こんなにまでも苛立ちを、感じたことは今までにない。モチを案じるその心、歌うことでは解決できぬ。
歌うというのがこんなにも、か弱く歯がゆい行為であるとは!
苛立ちながらも僕は目で追う、サクが健気に衣装に埋もれ、じっと座ってこちらを見るのを。
僕は不純であるだろうか?二人の女性に惹かれている。どちらも大事であるなんて、言い訳にしかならないだろうか?
相も変わらずサクを見つめて、だがこの心はモチを想った。
僕の陽気な月の精、欠けること無い月の精。輝く眩い光の女。
僕は切なく歌を歌った、モチを想って歌を歌った。
サクは感じて取っただろうか?心がここにあらずなことを。自分のために歌わぬことを。
美姫の姿にモチを重ねて、愛の文句に僕の心を、重ねて僕はモチに歌った、今この場には居ない彼女に。
サクの為には歌えなかった、モチを失う怯えに慄き、心は嵐の状態だった。
サクは感じて取っただろうか?僕のふらふら揺れる心を。
サクはどのよう思っているのか?モチの存在それについて。
彼女は妻だということになり、モチもそのよう名乗っているが、僕が妻帯したことにつき、サクは一体どう感じたか?
苦い痛みが心に走る。
さっきもそういう結論に、達した通りこの僕に、サクの心を確認する術、全くもって無いのだった。
ただ想像をするしかないのだ。そうして僕は卑怯にも、願望だけは持っていた。
悲しんでいて欲しいのに、受け入れていて欲しいだなんて、身勝手極まりないじゃないか!
もし僕がモチを選んだら、サクを自由にしなくちゃいけない。それもはっきり分かっているのに。
僕は切なく歌い終え、酒席もお開きになってすぐさま、目もくれず飛ぶ勢いで、駆けて戻って行ったのだった。
モチはもう無事戻っていたのだ。何てことないという様に、けろりとした顔こう言った。
「悪魔の巣などは無かったようだ。」
僕はへなへな崩れこんだ。足から力が抜けていった。
「だが足跡なら有ったんだ。嫌な気配も残っていた。」
モチはそういう報告をした。
僕は本気で怒っていた、心配した分真剣に。
「もう絶対に無茶はよせ!もし奴を倒すことが出来、サクの命も助かったって、君も助かるのでなくちゃ、僕は絶対嫌なんだ!」
少しの間殊勝な顔し、僕に向かってうなずいた後、何だかとても深刻そうに、モチはこういう言葉を漏らした。
混じりっ気のない真顔であった。皮肉も陽気も垣間見せない、何時に見えない真剣な顔。
「もしどちらか、どちらかだけしか助からないなら、君は一体どうするつもりだ?サクを選ぶか?私を選ぶか?」
僕は苦しく行き詰った。全く言葉が出てこない。
それはずばりと核心だった。今まで避けてた核心だ。僕の狡さと優柔不断を、真正面から突いていた。
何一つ答えられないままに、僕は黙ってモチを見つめた。彼女の瞳は分かったように、何でも知ってるように光った。
「もういいよ、この質問は残酷だった。答えなくてももういいよ。」
モチはするりと自分から、その身をかわしてこう言った。僕は甘んじ尚も黙った。
「君には悪いと思ってるんだ…。生まれ変わりをするために、あいつを追っているだけなのに、僕らの事情に巻き込んだ…。この問題を解決したら、きちんと埋め合わせるからさ…。」
僕はようやくそう言った。言うべきことはそれじゃない、心はもはや気づいている。
だが卑怯にも言葉にならない。僕は猶予を求めていたのだ。選ぶ猶予を欲していた。
この問題が解決したら、僕の心も整理がついて、どちらが一番必要なのか、選ぶ勇気が持てないだろうか?
「そうゆっくりもしてられないんだ…。」
モチはそう言い言い淀んだ。僕は驚き彼女を見つめた。
「あんまり時間がないんだよ。今度の満月その晩に、三十年目が来るんだよ、生まれ変わって三十年目。」
つまりそれは、それの期限を過ぎたなら、問答無用にモチは死ぬのか!
僕は愕然立ち尽くしていた。言葉がとても見つからなかった。
満月までに悪魔を討たなきゃ、どちらの恋も悲劇で終る、そういうことになるというのか。
そういうことになるというのか…。
次の日明けてぼんやりと、僕は光を見ていたのだった。
時間がない、実感もない、ただ現実が、ずんずん前に迫って来る。何も待ってはくれないのだ。
十五夜までに『奴』を倒して、モチの獲物を取り返しても、そこで彼女は去っていくのか?重たい体と僕を置いて、天に帰っていくというのか?
僕らに未来は無いというのか…。
モチの姿が見えなかった。僕はぼんやり彼女を探す。
この部屋に、彼女と二人過ごすことは、甘やかなことに思われた。嘘の夫婦であったって、新婚気分も味わった。
もし本当に彼女が妻なら、こういう時間が過ごせるだろうか?そう不埒にも思ったものだ。
不覚にも思い込んでいた。『奴』を倒せばその後も、こういう日々が続くのではと。
だがそうなってしまったら、モチにとどまる理由は無いのだ。
部屋の外から笑う声が、小さな子供とモチとが笑う、明るい声が響いてきた。
ドアを豪快蹴り開けて、モチと小さな女の子、確かイトそう言った子が、朗らかな様子入って来た。
「イサヨイ、随分だらしがないな。もう日は大分高くなったよ。いつまで寝ているつもりだい!」
モチが布団を取り上げた。
僕はぼんやり狼狽し、二人の様子をただ見ていた。
昨日の夜の、突っ込んだ、話をもはや忘れたように、モチは今なお明るかった。
朝日の様に強引に、僕の視界を埋め尽くす。
一歩遅れて、僕は彼女の後ろに立った、イトという子に目を置いた。
「お嬢ちゃんなら、一体どうして…。」
僕はぼんやり話しかけた。
「君の歌いが聞きたいって。昼の座興に呼ばれないうち、ささっと一曲歌ってくれよ。」
モチは強引僕に迫った。
僕は事情が良く分からぬまま、着替えて楽器を手に取った。
「どういう歌がいいだろうか?」
僕はその子に尋ねてみた。
「小さな可愛い月の子の歌。宮殿奥の友達が、とっても素敵と言っていた。」
イトという子はそう答え、はにかんだよう微笑んだ。この歳の子によくあるように、恥ずかしがり屋である様だ。
「侍女の見習いしているこの子の、友達が君のその歌を、どうやらこの子に教えたらしい。」
モチがその様補足した。
僕は歌いを行った。起きたばかりでよく声が、出ないとこではあったけれど。
昨日の怯えたイトの様子を、思い浮かべて僕は優しく、いつもより気持ち優しく歌った。彼女の怯えを払いたかった。
気休めかとは思ったが、それでも小さなこの子には、深く響いたようだった。確かにこれは小さな子にも、受けがいい物語だろう。
歌い終わるとイトという子は、顔赤くして微笑んだ。
「小さな可愛い月の子は、勇気を持ってみんなを救った。すごいなあ…。あたしもほんとはああなりたいの。
あたしも勇気を持ちたいけどね、だけどいつでも怖くなるの。怖くて涙が出てくるの。」
イトはそう言い瞳陰らす。
「お城は怖いとこなのよ。あちらこちらに悪いものが、身を忍ばせているんだわ。信じてくれる?詩人さん。
お爺ちゃんには見えない者よ!いつも夢だと済まされるのよ!ほんとに怖い人がいるのに!」
僕は何だか痛ましく、優しく笑ってこう言った。
「信じるよ、僕もここには怖いものが、巣くっているって思うんだ。」
イトは安心したように、僕に向かって微笑んで、そうしてモチの腕に抱き着く。
「これからね、お姉ちゃんと一緒に遊ぶの。お姉ちゃんはいい匂い。一緒にいれば怖くないのよ。悪いものは、お姉ちゃんが目を向けたとたんに、消えて隠れてしまうのよ。」
イトの言葉にモチは言った。
「私も退屈してたからね。旦那様なら忙しく、ちっとも構ってもらえない。」
そうして僕に意味ありげに、唇結んで微笑んだ。そうかこの子に関わって、手掛かりを得るつもりであるのか。
イトという子はこう言った。
「詩人さん、あんまり安心してちゃ駄目だよ。お父さんが出て行ってから、お母さんはよその人と、一緒にお家を出て行ったのよ。当たり前だと思っていたら、足をすくわれるんだって、侍女さんたちも言っている。」
彼女のませた発言に、僕は思わず苦笑して、それから彼女の家庭の事情に、少し哀れを感じもしたのだ。
それでおそらく彼女の祖父に、ミカと名乗った老人に、引き取られここに居るのだろう。
「忠告はしかと聞いておくとも。君は賢い子どもだね。モチと遊んでくるといい、あと数日は貸してあげるよ。」
イトの笑顔が輝いた。
それから僕の言葉通り、その後はずっとイトはモチの、そばにべったりくっついていた。どこへ行くにも付いて回った。
モチはこのよう僕に言った。
「私の光の気配にあの子は、本能的に惹かれているんだ。この城には闇立ち込めて、敏感なイトにとってみれば、恐ろしいとこであるのだろう。だから私にまとわりついて、それの恐れを遠ざけるのさ。
彼女は強い力を持ってる。人の体にしてみれば。月精であるこの私と、同系統の力を持ってる。だから尚更惹かれるんだよ、私の強い光の気配に。」
「悪魔の巣とはどこにあるか、そいつは見つけられそうかい?」
「何だかまばらに足跡が、あちらこちらに付いている。どこも怪しく、また怪しくない。あの子の反応一番強い、場所ならきっと東の棟の、一番低い階かなあ?君もいつでも戦えるよう、準備を整えててくれよ。」
モチはしっかり念を押した。僕にノーとは言わせぬつもり。
「石なら誰にも気づかれぬよう、懐の中に隠してあるよ・・・。」
僕は答えてそう言った。
だがしかし、僕の心は再びに、迷いの中に落ちていた。もう亡いはずの祖父の存在、その亡霊が僕を捕らえた。
僕が再びミカと言う、老造園師に会ったのは、その日の夕刻、宴の前の、空いた時間のことだった。
大分寂しくなった陽が、心細げに燃えている。庭木も城も蒼くて黒い、影に色彩落とし行く。紅と黒とのコントラスト。
その中に、ミカ老人は立ち尽くし、じっと夕日を眺めていた。
亡量とすらある立ち姿。
その姿は、僕の心をなぜか打った。
彼の居ずまい風格は、記憶の中の祖父と重なる。彼もいつでも寂し気だった。
僕に気づいて振り向いて、ミカ老人は微笑みかけた。
「良いお晩です、イサヨイ様。昼間はイトがお世話になって。」
「いいんですよ、モチにとっても、一人でいるより楽しいでしょう。」
僕は答えてこう言った。
「僕が彼女を放っておくから、モチも大分不満なんでしょう。」
「あの子については事情があってね…。実は両親ともすでに、あの子を置いて出ていきました。」
ミカ老人はそう言って、寂しく僕に微笑んだ。いいや寂しさそれ以上、苦しさ感じる物言いだった。
「イトちゃんも少し話していたが。」
「私の息子も詩人でね、常に方々回っていたが、遂には帰ってこなくなった。嫁も大分待ってはいたが、一年ほど前出て行きました。
あの子のこともあったので、思いとどまって欲しいと、何度も止めたが行ってしまった。考えたなら、無理ないことと、私にしても分かっているが。」
ミカ老人の言葉に僕は、とある疑問を抱いたのだった。
「あなたは祖父のお知り合いと?もしかして、あなたも詩人であったのですか?」
彼の息子も詩人というなら、もしかしたならそうではないか?
僕は何だか期待を抱いた。彼と祖父との共通項を、僕は求めていたのだった。
彼は控えめうなずいて、僕に答えてこう言った。
「遠い昔は詩人でしたよ。当節これが血なまぐさい、職業になって辞めたのです。息子には、歌で戦うなどという、穢れた仕事をさせたくなかった。
若い者は、全く親の言葉を聞かない。高い名声収入求め、はるばる方々戦場を、渡り歩いていたようだった。
あなたは奇特なお方ですとも。今時に、頑固に戦うことを拒んで、それでもこのよう成立している。
御爺様の、お志を継いでいる。私は感動しているのですよ。長い時間を隔てながら、ネマチの頭(かしら)と再会できたと。」
僕のこの目は浮いていた。どういう言葉を答えたら、いいのかそれが分からなかった。
一度は歌で戦うと、サクの、モチの、命のために、穢れを負うのは避けられないと、そういう決意を決めたはずだ。
だが亡き祖父の信念が、再び目の前現れる。
今まで僕を縛った全てが、裏切ることはならないと、僕の目の前立ちはだかるのだ。
第十一話 「振り子の心」に続く
第十一話 振り子の心
第十一話 振り子の心
その晩僕は上の空、ミカ老人とイトの事情を、モチに話して聞かせたのだ。イトに関することならば、モチはもう既本人から、大方のことを聞いていた。
「ねえイサヨイ。」
彼女は僕に話しかけた。
「君の祖父とはどういう人だ?頑固に歌を戦いに、用いることに反対したと、あの兄さんとは対立したと、それくらいしか聞いていないが。」
モチの疑問はもっともだった。僕は彼女に話して聞かせた、祖父と兄との対立を。
「僕の親父は僕が五つの、冬に病で亡くなった。その時すでに長兄は、成人をしたころだった。誰もが彼が後を継ぎ、ギルドを仕切るそのことを、当たり前だと考えていた。
だがしかし、まだまだ祖父は健在だった。その頃祖父が実際に、ギルドを仕切っていたのだった。恐らく自分は後見として、兄を横から支えつつ、時が来たなら勇退すると、祖父ならきっと思っていたろう。
その頃だった。虹金剛の歌においての、特異な性質発見されたは。」
「お兄さんとお爺さんは、全く違う考えだった。」
モチがその様口を入れた。
「その通りだよ、その通り。兄はこの時現れた、新しいとも言える考え、新たな事業の考えに、すっかり心を奪われた。兄は儲ける道を選んだ。詩人を戦へ送り込み、利益を独占しようとした。
祖父はそのこと激怒した。祖父なら歌の心を重視し、その美に反したことならば、何を言われど認めなかった。怒涛の勢い兄を叱咤し、それを止めさせようとした。」
モチは黙って僕を見ていた。話の先を聞くつもりだが、大体予想がついてることを、語っている様(よ)な目をしていた。
「二人は結局決裂したのだ。古参の幹部を従えた祖父、対する兄は、若いやり手を、従え反旗を翻した。歌いで戦う兄達だ、結果はおのずと見えている。
兄は祖父らを幽閉し、その実権をにぎったのだった。いや、幽閉ならまだ穏便だ。古参の幹部に中には命を、奪われた者もいたからね。
とにかく祖父は幽閉された。屋敷の奥の傾いた、塔に幽閉されていた。僕やジュウサンたちがそこを、訪れるのを許されたのは、きっと兄らの後ろめたさだ。
彼にしたって真からは、正しいことだと思ってないだろ。そんな道、タチマチの兄は選んだのだよ。」
「君らは君らのお爺さんから、歌いを最初に習ったのかい?」
僕は答えてこう言った。
「その通りだよ、ジュウサンと、僕とは共に一番に、祖父から歌いを習ったのだよ。
祖父の歌いは見事だったよ。人生の錆が下りた男の、哀しさ強さが滲んでいた。そうして強く憤っていた。自分の人生運命に、それを強いてる天命に、凄まじいばかり憤っていた。
その憤りは祖父の歌いに、実に深みを与えていた。心に爪を立ててる様に、彼の地声は響いていた。
それでも歌に対しての、考え方は高潔だった。歌いに対する考えを、僕は祖父から教わった。人生の師と思っているよ。
だが正式には祖父を師匠に、することだけは許されなかった。僕らは祖父の親友だった、一人の詩人に師事をした。
そうして僕が十二の年に、無念のうちに祖父が亡くなり、僕は故郷を出奔したのだ。この前君と帰るまで、一度もそこを訪れなかった。」
モチは真面目に聞いていた。真面目に聞いて少し考え、僕にこういう忠告をした。
「ミカさんと、君の祖父とを一緒に見ては、いけない様な気がするよ。
私は何だか不安になるんだ。彼のことを言う君を見ていると。君を見てると心配になる。」
僕は答えてこう言った。
「大丈夫だよ、君のこと、決して裏切ることは無いから…。決心も、それほど揺らぎはしないはず…。」
だがその時にも裏腹に、僕の心は揺れていた。祖父の話を語ったことで、尚更過去へと心が向かった。
血肉となるまで身に注がれた、祖父の想いや信念が、今更のよう身に食い込んで、そいつが僕を作っていること、思い知らされたのだった。
サクとモチとを守るため、戦うことがこの僕の、新たな戦い方だったなら、歌いで戦わないことは、昔馴染みの戦いだった。勝手の知ったることだった。
どちらがしっくり馴染むかは、言わなくたって分かるだろう。
怨念とすら言える様な、祖父の言葉を選ぶのか、自分の愛する女を選ぶか、僕は真実追い詰められた。
目の前残る選択肢は、どんどん狭められていく、じりじり、じりじり、時が経ってく。
僕は彼から逃げたい一方、安心感ともいえる様な、不思議な気持ちを味わった。
こいつは僕の知ってる世界だ、今まで充足してた世界だ。ここに居たなら自分を守れる、ここに居たなら安心と。
次の日も、ミカ老人と顔を合わせた。
僕が時間を見つけ出し、モチと探っていた時だ。不意一陣の風が起こり、僕の帽子をさらっていった。
それは何だか図ったように、二階の窓をすり抜けて、庭で作業をしていたらしい、彼の目の前運ばれてった。泥に汚れたブーツの前に。
「イサヨイ様。」
彼は微笑み浮かべながら、帽子を拾って掲げて見せた。
「誰だい彼は?」
モチが聞く。何だかはっきりしない顔で。
「あれが彼だよ、ミカさんだ。」
僕らは階下に降りて庭に出、ミカ老人と相対した。
彼は慇懃柔らかく、僕らに対して挨拶をした。詩人であったその昔、ほうふつさせる優雅さで。
「奇遇ですなあ、イサヨイ様。奇縁というのを感じます。そちらがイトが申してた、奥様、モチ様でしたかな?イトが散々お世話になって、ご迷惑ではないですか?」
「いえいえこちらが楽しんでいます。もしも娘が出来たなら、こういう感じになるのかと、夫と二人で話しています。」
モチは何だか表面上の、笑顔を作ったものの言い方。僕には分るその違い、僕にははっきり分かるのだ。
だがしかし、彼女はそれを表情や、態度に表すことはなかった。にこやかに、朗らかそうに対応した。
「イサヨイ様はずいぶんに、あなたを愛しておいでのようだ。私が詩人をしていたころは、故郷(くに)に妻子を待たせてた。
大抵の者がそうします。待たせていては心配と、そう思われているのでしょう。
お目にかかって納得しました。あなたであるなら誰であれ、心配尽きないことでしょう。常に手元に目の届くとこ、置いていたくもなるでしょう。」
僕は何だか居心地悪く、目線を泳がせ瞬きをした。
モチは全く動じずに、笑顔を作ってこう言い放った。
「イサヨイが、私を連れて旅することは、それは私が強いからです。大抵の、ことなら彼を守れるくらい、私が強いからですよ。
彼が私をどれほど愛して、安心できぬ程であるか、それはどうだか知らないが、イサヨイは、私に守られてるのです。」
モチの言葉に尚更に、僕が居心地悪くなった。見栄を張りたい人に対し、裏の弱みを見られた気分だ。
ミカ老人は軽く笑った。瞳は笑っていなかった。唇に薄く笑み浮かべ、こういう言葉を言ったのだ。
「あなたはとても賢婦ですね。彼が信念曲げぬよう、夫が歌いで戦いを、する必要を持たせないため、あなたが盾となっているのか。いや全くに偉いものです。
普通の夫人は夫が自分に、どれほど思いをかけているか、形や行為で表すように、暗に陽に示させたがる。
贈り物などを要求したり、世間に対して何かを捨てて、あるいは信念曲げさせてまで、自分を守るそのことを、無理強いしたりするものです。その愛を、人質になどするものです。
そういう無理を言わないばかりか、自分が夫の盾となると!あなたは理解をした上で、イサヨイ様の信念を、支える心でおられるか!いいや、全く偉いもの。」
僕は何だか動揺した。ミカ老人の物言いに、強い皮肉や牽制を、じわじわ感じて体が冷えた。
モチの表面作った笑顔は、少しは凍り付いたものの、それでも大きく崩れなかった。
「いいえ、私はそれ程に、賢婦などではありません。夫に強く要求をする、怖い伴侶であるのです。」
だがその言葉はさっきより、細く心が籠ってなかった。
その場の空気に耐えられず、僕は用事を思い出したと、そういう嘘の言い訳し、モチを急き立てその場を離れた。
それからモチはほとんどずっと、憮然としている様だった。
僕は全く見当つかない。ミカ老人がモチに対して、何故あの態度を取ったのか。
僕と二人でいる時は、思い出の中の祖父をなぞって、哀愁すらも感じさす、彼の姿であったのに。
「ミカさんは、ほんとはああいう人ではないんだ。何だか今日は変だったけど。
きっと多分、彼はとっても高潔なんだ。詩人が戦うようになり、彼はきっぱり楽器を置いた。だからああいう物言いを、君に対して言ったんだろう。」
僕は信じていたかった。ミカ老人のそのことを。淋しい庭で導きの様、出会った時は嬉しかった。
孤立極まるこの城で、味方が出来たと思ったものだ。
無き祖父が、僕らに力を添えるため、大きな天を動かして、この僕に彼を贈ったようだ。
だがそれは、尚更僕の迷いを深め、縛りと縛りの間に僕を、がんじがらめにしていくのだった。
モチと彼とのやり取りで、心は動揺していたが、僕の心は傾いた。祖父の信念その亡霊に。
モチは鋭く感づいた。僕をけん制するように、強い調子でこう言った。
「私は彼は駄目だと思う。何だか良くない意図を感じる。まるでこちらの目的を、察してけん制する様な、まるでそういう言い方じゃない?」
僕ははっきり出来なかった。モチが言うのも分かるのだ。だがミカさんを、祖父の知古を、信じていたい気もあった。
彼はなんだか好きであった。説明できない共感を、僕はぼんやり抱いていたのだ。
僕らはおんなじ角度から、ものを見ているそのことを、理屈でなくて心で分かった。分かり合えるはず、そういう人だ。
「僕は信じていたいんだ…。」
僕はそれだけぽつりと言った。モチはそのことについては、それ以上のこと口にしなかった。
僕が信じていたいのは、果たして彼のことだけか?
祖父のこと、信念のこと、僕自身のこと、自分自身のたどって来たこと。
信じていたい事柄は、全て後ろに属するものだ。未来に決してつながらぬ。
取りも直さずそのことは、信じることの危険さを、僕に示していたというのに。
次の日も、西日差し込む回廊で、ばったり彼と会ったのだった。夕日が斜めに射していた。全く寂しい気候であった。
彼は鋏を手に握り、中庭の木を剪定していた。乾いた音がぱちりと響き、彼は孤独に作業を続ける。
彼が歌いをしていたころは、一体どんな歌歌ったか、昔をほうふつさせぬ程、彼は埃にまみれていた。
「随分広い守備範囲ですね。どこまであなたの職域ですか?」
僕は不安と安心に、引き裂かれつつそう聞いた。彼と会ったら話しかけずに、素通りするなど出来なかった。
「東の四分一ですよ。ここの庭木の手入れなら、随分繊細でしてなあ、若い者には任せられない。」
彼は答えてそう言った。
それから四、五分僕たちは他愛のない様(よ)な話をした。何を一体話したか、今ではまるで覚えてないほど、それはどうでもいいことだった。
その内容に、僕は安心していたのだった。歌いのことに、祖父のことに、話題が行かない安心を。
決意を猶予されているようで。
その時だった、サクがここを、姫の影武者であるところの、サクが数人供従えて、この脇を通り過ぎたのだった。
薔薇の香油が香っていた、華麗な衣装はまるで彼女を、閉じ込め苦しめてるようだ。
だが輝きは消せようもない!そんな邪魔では彼女の魅力は、封印できぬほど強いのだ。
彼女は僕を認めたが、他の誰にもするように、笑みを浮かべて会釈をした。他の誰にもするように。
だが目が合って、ぼくも悟る、燃え上がるようなその心。確かに火花は生まれて散る。
僕は瞬間惹きつけられる、彼女と未来を行く想像に。何に代えても彼女を守ると、そう誓いかけたあの晩に。
背後の彼に後ろめたくも、僕は歌いで戦うことを、半端に決意をしかけたのだった。
無邪気にも僕はまだ揺れていた、揺れる猶予が無くなることを、知りつつまだまだ揺れていた。
彼女が通り過ぎた後、ミカ老人はこう言った。
「はした女が、主の顔をしているな。」
僕は驚き彼を見た。ミカ老人は知っているのか?サクと姫とが入れ替わってると!
この秘密、限られた者のみ知る秘密、大きな陰謀それにつき、ミカ老人は知っているのか?
僕の驚く顔を見て、ミカ老人はこう言った、意味のありげな顔をして。
「きっと驚かれたことでしょう。以前もあなたに言いましたが、ジュウサン様とも懇意なのです。姫様と、彼のことなら案じております。
あなたの企み計画が、成功の裡に終わるよう、陰ながら見ておりました。私は何にもできませんがね。」
僕は不安におののいた。どうして今まで黙っていたのか、何故今になって言い出すのか、それの不安が押し寄せた。
だが反面、僕の心にどういう訳か、甘ったるいその安心感が、満ちて溢れてきたのであった。
彼は味方であったのだ!やっぱりそうだ、そうだった。僕は不安に思った自分の、その半分を葬り去った。
彼を判断するために、鋭くならねばならぬはず、だがその道を放棄した。僕は自分で道を閉ざした。
この人のことを信じたい、僕の脆弱過ぎる心は、疑念の痛みに耐えること、彼を疑うそのことを、それを拒んでいたのだった。
「ところで頼みがあるのです。あなたと話しているうちに、久方ぶりに歌いたくなり…。
あなたと歌いをしたいのです。ネマチ様より受け継いだ、歌の心を持つあなたと、二人っきりで歌いがしたい。
いつか機会を頂けませんか?」
意味のありげに彼は言った。僕は即答できなかったが、確実にそれをすることが、何故か想像できたのだ。
そう、はっきりと、ありありと。
「お爺ちゃん、」
幼い子どもの声がした。イトが回廊向こう側で、モチと一緒にやってきた。ミカ老人は優し気に、哀し気にすら聞こえる声で、イトに呼びかけこう言った。
「イト、そろそろ帰ろうか?」
イトは表情こわばらせ、体をがちりと硬直させた。怯えを瞳に溢れさせ、モチにすがってこう言った。
「嫌、絶対帰りたくない、お姉ちゃんのとこずっといる!」
「わがまま言ってはいけないよ。」
ミカ老人はおろおろと、狼狽したようそう言った。
「嫌!絶対嫌!お姉ちゃんのとこずっといる!」
モチは困った顔をして、イトを諭しているようだった。諄々言ってなだめすかした。だがそれにすら全くに、イトは心を変えなかった。顔を真っ赤にさせながら、強硬にイトはそれを拒んだ。
結局その晩イトは自分の、部屋には帰らず僕らの所に、モチとの部屋へと泊ったのだ。
三人一緒に部屋に戻る、僕らを見送るミカ老人は、いつもよりずっと苦し気に、呆然とすらしてるようだ。
それほどまでにその時の、彼の立っている姿は孤独で、この寂しげな気候と合わせて、僕の心に残るのだった。
イトは僕らの部屋にいて、ずっと無邪気にはしゃいでいたが、自分の部屋に帰らないこと、それについての質問には、結局答えることしなかった。
何を聞いても答えずに、突っ込んだことははぐらかす。どうやらイトも何かに対して、戸惑っているらしいこと、それはぼんやり知れたのだ。
僕は請われて歌を歌った。彼女の好きな月の子の歌。この前よりは声が出て、自分で満足できたものだ。まともな歌が聞かせられたと。
結局それからイトは自分の、部屋に帰ることはなかった。
第十二話 「『奴』との再戦、そして可能性」に続く
第十二話 『奴』との再戦、そして可能性
第十二話『奴』との再戦、そして可能性
イトが寝入ってしまってから、モチはこのよう僕に言った。
「明日は午前が開いていたよね。付き合ってみてはくれないか。一人で動くな、そう言ってたろ。」
僕はぼんやり聞いていた。ミカ老人が頭に住んで、心に靄をかけていた。
心の内の関心は、その焦点をずらしていた。即座に僕は対応できず、一寸置いてこう聞いた。
「何か目当てがつけられたかい?」
「何をぼんやりしているんだい?東の棟の一階のことさ!ついこの間言ったろう。やっぱりそこが一番怪しい。」
僕は必死に自分を保った。ぼんやりとしてる場合じゃないのは、ついこの間にも確認していた。
モチの、サクの、命が危うい。必死に心を奮い立たせる。
「もちろん行くさ、明日の午前か。だけどもイトはどうするんだ?」
「明日は街に、買い出しに、小間使いらと一緒に行くって。一昨日からも楽しみにしてた。」
モチはこのよう僕に教えた。
「城に、なるべく居たくないんだろ。」
「つまりはそう言うことだろうな。」
僕は必死に心を保ち、明日のことだけ考えようと、頭を躍起に回していた。
ミカ老人がサクのこと、サクと姫とが入れ替わったこと、それについてはもう知ってると、そう告白したそのことは、何故か切り出すこと出来なかった。
ジュウサンと、アリアケ姫との仲についても、はっきり言及したことと、彼が僕らに一枚かむこと、それもモチには言えなかった。
普通に考えたとしたら、それは絶対言わなくちゃ、ならないことであるはずだ。まともに考えたとしたら。だがしかし…。
どういう訳か気が進まない、何だか秘密を知ったみたいに、僕は捉えていたかもしれない。
モチに言ってはならないと、口止めされてたわけじゃない、言うも言わぬも自由なのだ。
だから僕なら選んでしまった、言わないというその方を。
モチも聞いたら嫌な気になる。不快なことは言わない方いい。僕は無邪気で無責任な、言い訳己に言い聞かせた。
本当は、モチが反応することにつき、僕は恐怖を感じていたのだ。彼女が彼を悪く言うこと、モチが彼を疑うことへの。
今にしたらば失態だった。疑念に耐えられないこの僕の。
この弱さが、無用な悲劇を招いたことを、後々僕は思い知るのだ。
あくる日に、イトを買い出し連中の、元に託して見送った後、僕らはさっそく東の棟に、探りを入れることにした。
そこは小さな中庭囲み、ちょうどコの字になった棟が、三階建てに建っていた。中の位の使用人が、起居しているその建物だ。そういう訳であまり邪魔なく、僕らはそこへと入り込んだ。
モチは全く抜け目なく、僕に歌いをさせたいようだ。
「石はきちんと持ってるか?」
「ご心配なく、持ってるよ。」
否応なくも緊張走る。襲われるかもしれない不安、戦わなくてはならない不安、どちらもなるだけ避けたいものだ。
だが目的を果たすには、突っ込むことしかありえなかった。
この運命のただなかに。
僕らは少しヒリヒリしながら、まず一階を探り始めた。飾り扉に特徴のある、瀟洒な造りの建物だ。
建材は、統一された緑灰色の、鈍く艶持つあの石だ。扉は谷間の樫材の、薄い茶色の板だった。
タペストリーで飾られた、壁には一定間隔に、又の二つの燭台が、幾つも並んでいたのだった。
一階は、何の異変も起こらなかった。全く異常は見当たらなかった。
モチによるなら汚い足の、踏み散らかした後があちこち、置き土産の様あるというが、僕には何も分からなかった。
僕らは次いで二階へ向かう。そこも一階同様に、整然とした廊下であった。そこも異変は起こらなかった。
僕らは最後に三階に、その歩を進めていったのだった。
三階の、造りも階下と同様だった。ただ少しだけ豪奢であった。下の階より上級の、使用人たちが住むらしい。
きょろきょろしながら歩いていると、不意に誰かとぶつかった。
「痛たた…。」
僕は思わずしりもち付いた。そうして誰とぶつかったのか、知った僕なら驚いた。
「えっ、モチ!」
それは僕の左側、歩いていたはずモチだった。彼女も驚き僕を見つめる。真っすぐ並んで歩いたはずだ。
周りを見回し驚いた。
無限に廊下が続いている!
どこまで行っても飾り扉の、瀟洒で掃除の行き届く、廊下が果て無く続いていた。
まるで幻その様に、延々廊下は続いていた。そうして僕にも解かるほど、そこの空気は死んでいた。
「強い瘴気の塊だ…。鼻が腐ってしまいそうだ…。」
モチの言葉に僕も思う。これが瘴気と言うものか?周りの空気にまるで無言で、押し殺される様な気配。
「これはあいつの術だろうな。」
モチは抑制した声で、僕に確認取ったのだった。
「そうとしか思えないだろう。」
恐怖と焦りに総毛だつ。やはりここなら『奴』の巣か!
あの日対峙をした時の、『奴』の強さを思い出す。石が無くては敵わないのか?石が無くては敵わないだろ!
「君らがあんまり迷っているから、少し遊んであげようともって。そこから出ること叶ったら、我が計画を教えようか?」
『奴』、悪魔の声がした。四方(よも)から押し寄せ響く声。どこでしゃべっているのかも、全く判断着かない声だ。
これが『悪意に満ちた茶々』か!僕らは奴に閉じ込められた!
僕は今更方向感覚、利かなくなったことに気づく。右も左も上も下も、前も後ろも分らない。
それからずっと僕らは出口を、探してそこを彷徨った。
どこまでもそこは続いていた。全く判別付かない扉、等間隔に並んだ燭台、タペストリーの図柄さえ、全く同じものが続く。
僕らは無駄に彷徨った後、この方法の無理を知った。モチはとうとうこう切り出した。
「魔力の流れが閉じ込められてる。この感覚も通じない。強い力でぶち破り、外へ出るしかないと思う。」
モチはきっぱりそう言った。僕をまっすぐ見つめていた。
強い力でぶち破る、それには歌いで戦うしか、手段は無いといいたいか!
僕は心底狼狽していた。弱い所に付け込まれ、いたぶるかの様(よ)な悪魔の所業。
今目の前のモチの顔と、サクの瞳が心をよぎる、ミカ老人の後ろ姿も、頭に焼き付き離れない。
悩んだところを見透かされ、この僕を試しているのか?僕が苦しむ様が好いのか!
僕は憤然怒りを抱く。
見ておれよ!予想もつかぬことをしてやる!
僕は何故だか決めつけて、見えぬ悪魔に怒りを燃やした。
やがて僕らの周りには、顔の表情失くした侍女が、三人供に現れて、無限に続く廊下の燭台、それに灯(ともしび)灯すのだった。
ああこれは、行方不明の侍女たちだ、やはり悪魔に囚われてたのだ。
風にふわりと炎が揺れる。ふわりふわり、薄い煙も。
ああ死んだここの空気でも、こういう風は吹くのだな。風は吹いているというのに、僕も煙になれたなら。
僕の頭に閃きが、その時降りてきたのだった。
やおらに胡坐をかいて座り、背にした楽器を構えて取った。
「一体どうするつもりだい!」
モチの言葉に僕は言った。
「この方法を試してみるさ!」
もしもこいつが上手くいけば、僕は暴力という手段に、訴えずとも歌いの力で、あいつと戦えるかもしれない。
僕は歌う、風の歌を。西の彼方、色とりどりの異国の神々。
「潮満つイサナの洋上に 英雄ハマは漂えり 臙脂の旗で飾られた 軍船は既に見る影無し
星集うような勇士らも 海の藻屑と消えにたり 亡霊船のような船に 英雄ハマはただ一人 空を見上げて落涙す
新婚の、気分も未だ消えぬうち 故郷に残した妻にも会えず 空しく魚の餌食となるのか
ああ慈愛深き神々よ 我が切の祈り聞き届けたもう
陸の優しいグリオーダ様 わが身を哀れに思われるなら 百里の底の海底から 緑の島を浮かせ下さい
しかし慈愛のグリオーダは いなくなった子に気を取られ その嘆願を聞かなかった
海の豊かなユーラプネ様 百里の潮を南に送り これなる船を大陸に 祖国の地へと流して下され
しかしその時ユーラプネは 夫からの罰賜って 砂漠をめくらで彷徨っていた 焼けた熱砂の大地を裸足で
風の自由なスタウン様 海の果てからルルコの岬に 大きく息を吐いて下され 我が故郷たる大陸に 船を送ってくださいますよう
その時風神スタウンは 風のうろ岩のグラウスに、午睡を取っていたのだが ハマの祈りを聞き入れた
息を吸い ふうと吐く すぐに眠りに沈みゆく 強い嵐が吹きおこり グラウスのうろをごうと鳴らして 風は一散吹き抜ける 南から海を吹きわたり イサナの海を吹き抜ける 北の彼方のルルコに向かって
たちまち英雄ハマの船は 故郷の海へ 北のルルコの 碧く塗りたる塔を臨める その沖合に導かれた
故郷へ、故郷へ、有るべき所へ」
僕のたもとの石が光って、僕らの周りに強い風が、強力な風が巻き起こる。
灯(ともしび)が、一気に消える、向こうの方から、一気に消える、その先に、光る廊下の果てが見えた。
光が強い風に乗り、こちらの方へと吹き抜けた。視界が白く輝いた。
それは一瞬だったのだ。僕らは何事なかったように、東の棟の三階にいて、僕は楽器を抱えていた。その傍らにはモチが立ってる。この懐の中の石は、強いその負荷耐えられず、一つ砕けて散っていた。
僕らの周りに三人の、侍女らが倒れて伏していた。
「ははははははははっははは!」
厭な悪魔の声がした。全く生理で受け付けない声。
「詩人の君はなかなかやるね。この間なら見られなかったが。本気を出したら手ごわいか。」
見上げるとあの悪魔が行く手に、膝一つ分浮いていた。彼の周りに毒々しくも、派手な緑の影が滲む。
まるで時間の染みのように、彼は異質に澱んでいた。僕らと全く異なった、存在なのが良く分かる。
「一体何を教えてくれる?」
モチがこう言い問い詰めた。彼女はただでは帰らぬつもりだ。全く恐れず奴に詰め寄る。
「言わないのなら、お前の王に、その伺いを立てるとしよう。」
悪魔は不快な顔になったが、全く動じずこう言った。
「我らの決まりを知っている奴は、ほんとに全く厄介だ。言ったろ、私の計画だ。戦を起こす方法だよ。
君はどこまで知っているか?今度の満月その晩に、月見の宴が開かれる。歩琉(ほる)渡(ど)の渓谷沿いにある、小さな塔がその場所だ。
王子らは、西と東に兵を呼んでる。それならいつものことだがね。だが今回はこの私、積極的に動くつもりだ。
宴もたけなわなった頃、ある一軍が姿を現す。種を明かせば私の化身だ。
彼らは宴に乱入し、姫に刃を突きつけ迫る、
『どちらをお選びするのかを、今宵はっきりお聞かせください』。
姫はこう言う、しかし最も、本物の姫じゃないのだが。
『どちらもお選び出来ません、どちらもお慕いしています』。
軍の頭は憤り、姫を一気にくし刺しにする。だがそれじゃ、確実戦は起こらないよね?」
悪魔はにやりと微笑んだ。
僕とモチとは息呑んで、話の続きに聞き入った。
「件の軍には術により、お互いの兵と見せかけてやる。お互い相手の兵隊が、姫の命を奪ったように、そういうふうに思い込ませる。
彼らはきっと怒るだろうね!あんなに毎日鼻伸ばし、口説きまくっているんだからね。
どちらもお互い相手のことを、姫を争うことが無くても、きっと憎んでいるだろう、目くそ鼻くそ憎み合ってる。
うひひ、馬鹿だね、馬鹿なやつだね!」
そう言い悪魔はうへうへと、どうしようもなく気に障る、厭な笑いを作ってまいた。
「一体どうしてそのことを、僕らに教えるなんぞした?」
僕は冷たい怒りを殺し、震える声でそう言った。
サクの最後を思い浮かべ、心はとても狼狽していた。そんなことなど許さない、そんなことなど許さない!
「もちろん楽しむためだけにさ!君らが半端に期待を抱き、無駄に努力をした後で、空しく絶望する様を、観察しつつ鑑賞するのだ。
甘い期待を抱いてくれよ、期待のままにあがいてくれよ。どうか綺麗に夢を見てくれ。私が砕いてあげるから。
私は人が苦しんで、悩み悲しむ様を見るのが、三度の飯より好きなんだ。
そこにいる、傷欠けの無い完璧な、魂持った女には、何の興味も持っていないが、君の大事なサクだっけ?彼女の傷つき方はいい!いくら私が負荷をかけても、彼女は決して壊れなかった、。
どこまでどこまで壊しても、遂には決して壊れぬ女。顔は青ざめ涙は流れ、だがしかし決して砕けぬ女。
きっと彼女の魂は 素晴らしいひびが入っているだろ、芸術的な壊れ方だろ、私は早く見たくなった。
自然に任せて寿命が尽きる、それを待って居などしたら、あの世の主に持っていかれる。 こんな獲物はまたとないのに。
だから自ら動いたんだよ。彼女を連れて、ギルドに行った。その後は、大体聞いているんだろ?」
汚らわしくも『奴』は言った。
僕はあまりの怒りの情に、自分に課してた禁を破った。もう正常には判断できず、迷いも忘れて胡坐をかいた。
怒りのままにこの身を任せ、武人の歌を歌おうと、楽器を構えて息を吸った。
「アハハハ、怖いな厄介だな!私はここで決着を、着けるつもりじゃないんだよ。
そうだなこれではどうだろう?一つヒントをあげようか?どうしてここが虹金剛の一大産地になれたのか?虹金剛とはそもそも何か?それの疑問に答えられたら、挑戦権をあげなくもない、私を倒す権限を。
最もね、サクを完全手放すことは、ただ倒すだけじゃなくってさ、殺さなければ叶わないだろ。私はそれほど夢中なんだよ。それにねえ…。」
悪魔はふっと言葉を切った。そうして生理で受け付けぬ、厭な微笑み僕に向けた。
「君のひび割れ壊れ方も、私はとっても気に入っている。」
それの言葉が最後だった、悪魔の姿が掻き消えた。
光が戻り、風がぬるむ。
しかし僕のかくこの汗は、真冬の様に冷えていた。動揺が、心臓のリズム乱していた。
「イサヨイ君は大丈夫かい?すごく真っ青なってるよ!」
気づかわし気にモチが言う。
「ああ大丈夫、大丈夫。少し動揺しているだけだ・・・。」
僕はようやくそう言った。
今日は欠けたる十一夜、満月までは後四日。
第十三話 「忘れないでと彼女は言った」に続く
第十三話 忘れないでと彼女は言った
第十三話 忘れないでと彼女は言った
次の日は、空いた時間をなるべく作り、僕はあちこち聞いて回った。城に住まった鉱物技師や、学者の話を聞いて回った。
しかし誰もが首横に振る。虹金剛の正体は、未だ研究中とのことだ。誰も説明できないのだった。
「彼の石は、一つの地層に出ないのです。ありとあらゆる地層から出る。その成分は、宇紗(うさ)の奇跡のアマガサ石と、放つ気こそは似ていますが、あれは聖なる遺物なので、詳しく調べるとこできません。
ただ言えます、何かの神の奇跡がそこに、働いているということです。人や自然に決して作れぬ、奇跡がそこに働いています。今言えるのはそれだけです。」
モチも彼女にくっついた、イトのこと連れ製煉場に、石を調べにいたのだったが、彼女もめぼしい成果を得ずに、僕らは壁にぶち当たった。
「大体こんな土壇場に、制限時間が無くなってから、ヒントをくれてやろうなど、『奴』はやっぱり嗜虐的だな。
私や君が焦りに焦って、ワタクタあがいているとこを、きっとどこかで楽しんでいる。楽しみながら観察している。」
モチは苛立ち隠さず言った。僕も完全同意した。焦りにどうにも悄然となる。
「あいつは全く趣味が悪い…。」
「しかしだよ、『奴』の手口に乗ったって、解いてしまえばこっちのものだ。あいつを倒してしまえれば、あいつも自分の油断に対して、あの世で後悔することになる。」
「分かっているさ、諦めないよ。」
僕は自分に言い聞かす。研究者すら解けぬ謎でも、モチがこちらに付いていたら、奇跡のように解けないだろうか?月精の目から見たならば、その正体は、判明しないか?
希望と焦りが入り交じる。僕は昨日の戦いで、淡い希望を得ていたのだった。石を使って戦ったって、暴力などには訴えず、自然を増幅させる方法。
強力な負荷を石に懸け、多用は無理かもしれないが、奴に対抗できるかも。石はまだここ三つ有る。
その日も僕は城に住む、神官職の学者から、色々話を聞くために、少し離れた棟へと向かった。午後遅くまで話を聞いて、空に赤みがさしたころ、庭を通って帰りに着いた。
僕はぼんやり眺めていた、冬の迫った庭園を。もう朝冷えると霜が降りる。冬に渡ってくる鳥の、鳴き交す声も聞こえる時候。
わずかに雪の積もる気候で、その対策が急がれている。この技も、彼の老庭師の仕事なるか?
詩人の仕事を辞めた後、庭師としての修行もしたのか。僕には想像つかない人生。
僕なら歌いを辞めたなら、まともに生きてく自信が持てない。歌うこと、生きるこことは同義だと、僕は常々思うのだ。
家族を持つということは、そういう義務を課すのだろうか?僕もいつかはそれを知るのか?
自分一人じゃないというのは、自由をそがれることになる。けれどそれすら力にし、僕はこの世を生きれるだろうか?
モチとサクとの顔が浮かんだ。束縛は、喜びにすらなるのだろうか?
晩鐘の音がゴーンと響く。淋しい景色に染み入るように。
この夜も、王子が酒宴を催すはずだ。まったく彼らも飽きないな。
今から準備しなくては、間に合わなくなるはずだった。とぼとぼと僕は夕暮れ時の、庭を歩いて行ったのだった。
部屋の近くへ来た頃に、ふと人影が目に入る。淋しく丈の高い老人。
どうやら頭上の高い階を、気づかわしげに見上げている。
ああ彼だ、ミカ老人だ。僕らが泊まる部屋の下、その窓が見える庭の隅に、ミカ老人が案ずるように、見上げているのが見えたのだ。
「今晩は、一体何をなさっておいでで?」
恐る恐るに話しかける。
「いえ、今晩は、いい宵です。あの子、イトは、ご迷惑ではないかと思って・・・。きちんと聞き分け良くしてますか?」
ミカ老人はそう答え、反対そのよう聞き返したのだ。その顔に、孫を案じる祖父の情が、透けて光っていたのだった。
「ずっといい子にしていますとも。モチがよっぽど気に入った様、片時そばを離れません。」
ミカ老人は苦し気に、溜息ついて肩を落とした。
「私はあなたに酷なことを、さんざん言って聞かせた様だ。あなたにとってネマチ様は、とうに昔の人だというに・・・。」
僕は大変驚いた。彼がそういう言葉を僕に、かけたというのが信じられずに、僕は強い否定を述べた。
「そんなこと!祖父は今でも僕にとり、心の師匠であるのですよ。」
「だがしかし、あなたの未来を縛ること、それは彼には本意ではないだろ。自分の信条信念に、従い愛するものを失う、それは彼にも本意ではないだろ。」
決して言い淀むことなく、彼はゆっくりこう言った。
「男子には、通さなくてはならない筋が、はっきりあると教わってきた。あなたの御爺様とよく、そういう話も語り合ったもの。彼は信条信念に、ことさら忠実なお人だった。
だがしかし、現実はそう単純じゃない。重みを持った感情は、幾つも幾つも心を縛る。妬みや憎しみなんていう、醜い感情でなくとも、例えば尊い愛だって、その信念の邪魔となるやも。
そうしてその時信念を、選ぶというのがそれが果たして、正しい道とも言い切れない。
私は弱い男です。妻と息子を失った後、孫娘さえ失うことを、醜く怖れているのです。
女性というのは不思議なものです、力ともなり、重荷ともなる。本人たちは全くに、それに拘泥していない。奪える分だけ奪い取り、当たり前だとけろりとしている。こちらの払った犠牲など、全く何も介しない。
イトも私の苦しみなど、露とも感じていないでしょう。
そうしてあなたの奥様も、あなたの味わう苦痛に対して、全く理解をしないでしょうよ。」
そういう彼の目には暗くて、圧倒する様(よ)な力があった。何かを失い得た目だった。
彼が人には見えなくなった。
僕は急激怖くなった。暇のあいさつそこそこに、僕は部屋へと逃げて帰った。
部屋の中にはモチがいて、イトと駒取りゲームをしていた。
「イサヨイおかえり、遅かったねえ。少し急いだ方がいい。」
モチはそそくさ立ち上がり、宴に着ていくはずである、碧い上着を取ってきた。
僕は黙って二人を見ていた。二人の作る満ち足りて、平和な空気が今僕を、氷点下まで冷やして燃やした、夕日の下の会話から、日常の中に引き戻す。
「どうした?少し顔が蒼い。」
モチはそう言い額の汗を、温かい手でそっと撫でた。
「ああ何でもない…、何でもないよ。」
僕はようやくそう言った。そうとだけしか言えなかった。
その晩宴の喧騒の中、僕は必死に考えていた。僕にとっても歌の意味、モチの、サクの、持つその意味を。
人生の岐路に立つことを、どうしようもなく理解する。僕は軛を得るべきだろうか?重荷を進んで負うべきか?
モチを選ぶか、サクを選ぶか、それとも祖父との絆から、自分の道を進むのか?
何が一番大切で、どれを優先させるのか、切り捨てるならどれなのか。
僕には全く分からない、どうして両立できないのかが。
一方の僕はこう考える、愛こそ絶対重要なのだ、お前の信念信条など、お前を幸福に出来ない。人並みに、満ち足りた時を送りたいだろ。絆は縛りとなるだろうが、甘い縛りであることだ。子どもじゃないなら分かるだろう。
一方の僕はこう考える、愛などまやかし幻だ、ほんの一時の気の迷い。時間の試練に勝てるのは、信念をおいて他は無い。男子と生まれたその上は、信念こそを何よりに、大切にして生きるのだ。
サクを一生守ってあげたい。彼女の悲しみ払うのは、僕の使命であることだ。その為僕は生まれてきたのだ。
モチには側にいてもらいたい。彼女の光で僕を一生、微笑みの中に照らして欲しい。それこそ僕の幸せだ。
僕は両極引き裂かれ、振り子のように揺れるもかなわず、心がずたずた裂けそうだった。
どうにも猶予が無いことが、僕の焦りを一層深める。事は一刻争う事態だ。
僕の頭はこんがらがって、とうとうまともに考える、それがどうにも出来なくなった。
会場隅でうつむいてると、サクと偶然目が合った。
サクは菫の色をした、絢爛豪華な衣装を着けて、衣装と金銀宝石の、飾りの中にうずもれて、微かに揺らいだ微笑みを、僕に哀しく送って見せた。
その時に、一人の侍女が金の盆に、一つの菓子を乗せてきて、僕にこっそり差し出した。
彼女は僕に目配せし、一言低くこう言った。
「人目の届かぬところでそれを、お召しになって下さいね。」
僕は玉座のサクを見た。彼女の瞳がサインを送った。
僕はぼんやり菓子を手に取り、その中に紙の感触が、確かにかさりとあるのを感じた。
宴が終わり、僕は一番奥にある、上段階の庭園に、こっそりこの身を忍ばせて行った。
サクの手紙によるならば、今宵限りはここで会えると、サクと言葉を交わすこと、今宵限りは叶うというのだ!
ああサクとまた、言葉を交わせる、この僕の名を呼ぶその声が、この耳再び注がれる。
一体何を話せるか?もしなじられたらどうしよう?
ああだが僕の変わらぬ気持ちを、告げられるのは今宵のみ。
僕は期待と不安とに、情熱ゆえの高揚に、ゆらゆら炎を揺らしていた。
モチに対して後ろめたいと、思うことすら尚更に、情熱に火を注ぐのだ。
霜が降りそな気候であった。気温はどんどん冷えていく。
もう花盛りを過ぎ去った、秋の小花が揺れていた。まるで彼女が微笑むように、健気に首をたれながら。
僕は手に息を吹きかけて、晴れた夜空を見上げていた。
満ちそうで満ちぬ月がある。中途半端に満たされて、満ちた気配を予感だけ、匂わせ期待をさせる月。
確かに一番美しいのか、満ちそうで満ちぬときが一番。
僕の想いは今宵成就し、明日には欠けていくのやも。
だがそれすらも止められぬ、そう思うことも止められぬ、サクに対する情熱を。
明日が一体どうなったって、全くどうでもいいぞと思う。
僕が死んだら後のことは、他の誰かが考えるだろう、今宵燃え尽き灰になっても。
刹那的過ぎる考えに、僕は支配をされていた。心に燃える思いの他は、全くどうでもよくなった。
やがて微かな衣擦れが、奥の方から近付いてきた。薔薇の香油が香っている。菊の茂みが揺れてたわむ。
その向こう、サクの姿が現れた。豪華な衣装をきれいさっぱり、脱いで代わりに空色の、平民の服をまとっていた。
その清楚さに、僕は打たれる。あの晩心を捉えたサクの、八年経った姿だった。
ああまるで、想い出の中のサクを切り取り、少し大人びさせたみたいだ。
瞳は暗く深く澄み、僕の心を映し出す。全ての金銀宝石も、及びもつかぬ至高の装飾。
やはりサクには飾りはいらない、野山の花のままがいい。健気に咲いた野山の花の…。
少し離れたところに立って、涙の気配をにじませて、サクは震える声で言った。
「あなたをずっと覚えていたの、ずっと、ずっと、覚えていたの…。」
この僕の声も震えていた。
「僕も覚えていたと言いたい…、だがね、ほんとは忘れていた、忘れていたけど思い出したら、頭に心に離れなかった、君は心に棲んでいたんだ!」
僕は一気に距離を詰め、彼女の腕をつかんで引いた。
一刻も、一刻も早くサクをここから、連れ出したいとの衝動だった。
「こんな所は早く逃げよう!君を弑する計画が、そいつが着々進んでいる、そんなの絶対耐えられない!僕はその為ここへ来たんだ!」
力なくサクは僕を拒んだ。あの晩見せた泣き顔が、今その顔に重なるようだ。
とても苦しく辛そうに、僕にその顔背けながら、サクは拒んでこう言った。
「駄目よ、駄目…、私はここを逃げられない…。」
「どうして!」
僕はかみつく勢いで、サクにこの声荒げたのだ。
「君のその為ここへ来たんだ!君を助けて守るため、僕からそれを奪ったら、燃えかすだけしか残らない!」
「燃えかすなのは私の方だわ、燃えかすなのは私の方よ…。その燃えかすの命がここに、とうとう死場を得たのだわ。
私の命は捧げられるの、姫様のそのお命の為、あの日に予言したように、大きく高いものの為…。」
サクの右腕掴んだまんま、僕は悲痛に叫んで言った。
「あんな卑劣な陰謀の為、それを仕組んだ悪魔の為に、君の命が失われる!そんなの僕に容認しろと!」
サクはがっくりうつむいていた。澄んだ瞳は見えないが、涙が浮かんでいることは、声の調子でよく分かる。
「私はね、ずっと灯りのない夜の様(よ)な、そういう生を送ってきた。あなたと出会ったその時に、少しは光りが見えたみたいに、視界が開ける気がしたの。でも結局は幻だった。
私の命は結局は、もう私ので、なかったの、あれから散々知らされた。望んで生きれる命じゃないの、ただこの道の導くままに…、大きく高い運命の、その声が呼ぶその方へ、私はひたすら流れ続けた。
私の望みや意図にもよらず、全てはまるで仕組まれて、計画されてきたようだった。望みは常に打ち砕かれた。
打ち砕かれるそのたびに、私は自分の命の最後、、終わりについて思いを馳せた。どんどんそれが近づいて来る、でもまだここでは死ねないと、私はそのたび思ってきたの。何度も何度も繰り返し。何度も何度も、そう何回も。
でもこの国に着いたとき、私の心は確信を得た。安らいですらいるほどに。
ここから私の定めが呼んでる、不思議な声でそう呼ぶの、音には聞こえることは無くても、この渓谷から呼んでるの。
それにイサヨイ、私はあなたと釣り合うような、そういう女じゃもうないの。流れ流れるそのうちに、穢れも様々負ったのよ…。もうあの頃の私じゃないの、もうあの頃の私じゃないの…。
そんな私に姫様は、生きていく場所を与えてくれた、姉妹と呼んでくださった。あなたと別れて初めて知った、人の心の温かさ。私があなたと逃げたなら、間違いなくも殺されてよう!
イサヨイ、私は行けないわ、やっぱり私は行けないわ!」
小さく叫んでサクは見上げた、見上げて星の瞳を見せた。涙がそこにこぼれて落ちた。
冷たい月に照らされて、サクの涙はきらめいた。僕が掴んだ細い腕は、確かに熱く燃えていた。
サクの命が確かに燃える。その燃える命永らえるのを、僕の誘いに乗ることを、サクは拒んでこう言った。
「私は強いられたからじゃなくて、望んでここに立っているの。
運命が、呼ぶ声に乗ってここへ流れて、全て受け身であったけど、最後に私は選び直した。私の命が一番に、意味もつ道を、その場所を。
勿論一番幸せだとは、今でも思っていないけど、ささやかならら矜持であるの。自分で選んだそのことは。
私は『彼』の為には死なない、それもはっきり決めているの。私の命の使いどころは、『彼』に任せたりしないわ。
イサヨイは、私を信じてくれるわね?」
サクはそう言い僕を見上げた。強い瞳が決意を込めて、涙を張って輝いた。
鏡のような瞳が僕を、僕の姿を映し出す。僕には翻意されられなかった、サクの心を変えること、とうに遅いと知らされた。
サクは涙で笑顔を作った、大きな瞳に涙があふれ、笑窪の上に流れて落ちた。
そうして僕の頬に触れ、声震わせてこう言った。
「でもね、でも、あなたのことを支えにしてたの、イサヨイ、あなたの思い出を、心の支えにここまで来たの…。
だから、だからね…、一度だけ、一度だけ強く抱きしめて!」
僕は夢中で抱きしめた、サクのか細い体を強く。サクの体は熱っぽく、仮初の薔薇の香油の他に、汗と涙の臭いを嗅いだ。
想い出の中に無い物だった。あの時ならば触れられなかった、触れそで触れない二人であった。
だが今ここに、確かに今ここ、僕の腕に、この腕の中にサクはいる!
神様サクを助けて下さい!僕の命と引き換えに!こんなに健気に生きる彼女を、どうして救って下さらぬ!
僕は必死で抱きしめた、全ての想いを力に代えて、僕は必死に抱きしめた…。
サクは背中で号泣し、その抱擁に酔っていた。体の全てを預けていた。
だがいくばくもしないうち、サクは哀しく無理やりに、僕からその身を離したのだった。
「これをあなたに渡さなきゃ…。」
それは黄金の色した、丸くて割れてる光であった。同じもの、確かに僕は見ていたはずだ。
そうだこれなら魂だ!自死した男と同じ魂。
「奥さんの、これは大事なものなのでしょう?」
僕は驚きサクを見た。モチの笑顔が瞬間に、心に湧いてそして散った。
サクは涙で笑っていた。震えながらも微笑んでいた。
「『彼』から返してもらったの…。これであなたの用が済むって…。
私なんかにかまうより、彼女を愛してあげることよ。もう遅すぎる過去に酔うより…。
大丈夫だわ、私なら、決して『彼』の為には死なない…。」
サクは決意を重く込めた、瞳を強く光らせた。僕の心を引き裂く瞳。
ああそれだけでは終われないのだ…。サクが命を落とすのが、一体何の為であれ、僕にとっては残酷な、結末でないはずがない。
目の前に、こうして目の前立っているのに、僕には何もできやしない。
僕の力は運命を、翻意させられないのだった…。
「ああ私もう行かなくちゃ…。あなたに会えてうれしかった…。さようならなら言わないわ、私があなたの中に棲むなら、別離というのはないんだわ…。」
僕に何にも言わせぬままに、サクは奥へと駆け出した。冷たい月が後姿を、サクの流れる髪を照らす。
体に流れる血が全て、流れ去っていく心地がする。地面に付いているのが足か、頭なのかも分からなくなる。
ああ行ってしまう、行ってしまう、サクがここから行ってしまう、この運命が逃げてしまう!
「サク!一体どうすればいい!君のためにはどうすればいい!」
僕の叫びに一言だけ、サクは一言言って放った。
「忘れないで!」
振り向き一言叫んだあとで、その一言だけ僕に託し、サクは茂みに見えなくなった。
ああ僕のサクは行ってしまった、ああ僕のサクは行ってしまった…。
その言葉だけが頭に響き、僕は呆然立ち尽くしていた。
全てはかいが無くなった…。
第十四話 「月下の歌い」に続く
第十四話 月下の歌い
第十四話 月下の歌い
その晩明け方、僕は寝床で、モチから揺り起こされたのだった。
「イサヨイ一体どうしたんだい?随分君はうなされていた。」
僕は自分の額に触れた。不快な汗がびっしょりと、そこを濡らしていたのだった。
「ああいや、何でもないんだよ…。多分夢でも見たんだろう…。」
「そいつは嘘だろ!さっきから、君は確かにおかしかった。」
モチは怒った顔を作って、僕を見つめてそう言った。
「私は君の相棒だろう?共同戦線張ってるんだろう?」
その言葉に、僕は兜を脱いだのだった。全てをモチへと委ねたのだ。
もう一人ではどうしようなく、選択肢などは思いつかない。僕は全てをモチに委ねた。
サクとのことでモチに甘える、どうしようなく卑劣な僕は、モチにすがって甘えたのだ。
僕は先ほどサクに会い、辛い別れを告げられたこと、サクが全てを理解して、その上でこの役を負うと、悲壮な決意を告げられたことを、それを涙で語りだした。
僕の両目に湧きだした、涙はとめどもなく流れた。夜更けに冷える頃であるのに、僕の頭は汗ばんでいた。
モチは黙って聞いていた。口をはさんで咎めたり、僕を責め立てするような、素振りは全く見せなかった。
僕はそういう反応を、半ばは予測していたのに。
彼女は黙って聞いていた。
「ねえ、イサヨイ、彼女に別れを告げられたって、やるべきことは決まってるよ。
彼女がそういう言葉を君に、告げたはきっとこのことを、君には可能と思ってないから、君が彼女を救えることを。
ジュウサンたちとの計画は、この城の者に届いてないだろ?だからイサヨイ、君のこと、かばってそのよう言ったんだろうさ。君が成すべきことならば、今も明日も変わってないよ。君は戦も止めたいんだろ?」
モチは諭して聞かせる様に、僕にこう言う言葉を向けた。
まだここに望みあることを、まだ遅過ぎる訳では無いと、モチは落ち着き過ぎるほどに、僕に示して見せたのだった。
僕の体に温もりが、色が光が戻ってきた。
僕は彼女の膝にすがった。どうしても、モチに甘えていたかった。
彼女はそれを黙って許した。いつもの通り、黙って許した。
ああ僕ならば幸せだった、モチから全てを貪って、呑気に希望に酔っていた。
選べないという甘えた苦悩に、陶酔しきって貪った、モチの命の輝きを。
しばし後、何とか落ち着いた僕に向かって、モチはこういう疑問を投げた。
「ねえ、イサヨイ、今君が強く動揺したのは、サクのことから来てるんだよね?
じゃあさ聞くけど、夕刻に、戻ってきた時おかしかったの、それは一体どういう訳だ?」
「ああそれは…、ミカ老人に会ったんだ。これを言えば、気を悪くしたりするかと思って、君なら彼のことを良く、思っていないみたいだから。
それでも大した話じゃないよ。彼はずいぶん心配していた、イトがこちらに入り浸ること。それからちょっと女性について、彼の考え聞いたんだ。信念と、愛との相克、そういうことをか?それが少しく動揺させた…。」
僕は答えてそう言った。
モチは先ほどサクのことを、涙ながらに告げた時とは、全く違う顔をした。彼女は明らか不快そうだった。
いいや、今から思えば疑念だ。彼女は僕より心が強く、疑念の痛みに耐えられたのだ。
「ねえ、イサヨイ、彼をあんまり信用してちゃ、私はいけないと思うよ。イトがお家に帰らないこと、それはミカさん避けてるんじゃと、私は段々疑ってるんだ。何だか君に絡み過ぎてる。私の勘は当たるんだ。」
「それならば、僕とジュウサンとがよく似ていて、僕が他人に思えないんだろ。
実のとこ彼は知ってもいるんだ、姫とサクとが入れ替わってると。ジュウサンのこともよく知ってると、姫とのことを案じていると、そこまで彼は知っていたから。」
僕の言葉にモチが驚きこう言った。
「彼がそいつを知ってるだって!それは今まで聞いていないよ。」
僕は瞬間行き詰る。
「ああいいや…、話す機会を逸していたんだ。」
僕は素直に頭を下げた。モチは半分呆れながら、僕にこう言う疑念を投げた・
「もし仮に、ジュウサンと彼が懇意なら、ジュウサンも君に言ったんじゃない?ミカ老人を頼るようにと。ジュウサンならば抜け目がないから。」
モチの言葉に僕は黙った。
「まあいい、そいつは私が直々、調べを取ってあげようとも。明日の晩には分るはずだよ。」
モチがそう言いまとめたのだった。
ああ僕は、彼女に頼りっきりなのだ。別に愛する女のことで、この身の不備から出た不安とで。
もしも彼女がいなくなったら、僕の世界は成り立つだろうか?
僕は再び思い当たる、当然の帰結そのことに。
生まれ変わりをなしたなら、彼女は僕の目の前から、姿を消してしまうだろう…。
先ほどサクから受け取った、金色に光る魂を、僕は頭に浮かべていた。それは楽器の置いてある、茶たくの引き出しその中に、布にくるんで置いてある。あれを使えば今すぐに、モチは目的果たせるはずだ。
僕は彼女に言えなかった。どう責められても言えなかった。
彼女が今すぐいなくなること、それは何より耐えられなかった。サクを永久失うことと、同じ重さで耐えられなかった。
僕には耐えられなかったのだ!
次の日も、時間を見つけて城を彷徨う。モチは新たな試みで、一番近くの採掘場に、イトを伴い探りに行った。
「石が出てくる状態を、見たらば何かわかるかも。君は『奴』の巣探しててくれ。今まで屋内ばかりとは、思い込んでもいたけれど、まずはそこから離れてみよう。」
僕も彼女に言われるがまま、『奴』の巣のこと探しに行った。晩秋の、冷たい風の吹き渡る庭。
日差しと風に置き去りの、晩秋の花が咲いていた。もうどうやっても実を結ぶのは、不可能といえる季節に咲いて、あだ花散らす秋の花々。
良くは手入れはされていても、その寂しさはこらえようもない。空気が日差しが冷たく白い。僕は沈んで歩き回った。
晩秋の陽は短くて、あっという間に暮が来る。僕は空しく夕陽を見ていた。焦ることにもそろそろ疲れ、それでも焦れて諦めつかぬ。時だけ空しく過ぎて行った。
今宵名月十三夜。期限がどうにも近いこと、僕は刻々感じていた。
南の棟の前に来た時、僕は横から声掛けられた。
「イサヨイ様。」
僕はびくりと肩を震わす。
ああ彼だ、信念の、亡霊であるミカ老人。
彼は見慣れぬ衣装を着ていた。いつもの庭師の恰好じゃなく、白い緑の絹の上着。
ああこれは、詩人の正装ではないか。
彼は背に負う鍾琴を、右手に持ってこう言った。
「お約束です、イサヨイ様。私と歌いをしていただきたい。」
彼の言葉を拒めずに、僕は立ち去ることが出来ない。彼は黙って微笑んで、葉を落とすナラの木の根元、小さく開けた芝生の上に、腰を落として楽器を構えた。そうして僕に促した、相対しながら座るそのこと。
僕にはどうにも拒めなかった。心が絡めて取られていた。
僕は誘いに従って、彼の向かいに腰を下ろした。
「まずは私が先に歌おう。」
ミカ老人は楽器を構え、一口すっと息を吸った。次なる息は歌となり、彼の口から放たれた。
「ツリフネ姫は窓にいて 清いその声降らせ続ける 囚われの身の心の細さに ただ慰めは歌の調べよ
城の警備の騎士たちは 皆その声に憧れて 一目でもかの姿見ようと 雲突く塔を見上げたり
それでも姫の心にあるのは 故郷の勇士 リンドウのみ 行方も知れぬ彼を慕って 涙にぬれて歌を捧げる
城の一番外側の 辺鄙な門を任された 老騎士カンギク彼も聞いた 悲嘆にくれるその歌を たちまち心を囚われて 恋の奴隷となったのだ
カンギクの 主はコマのツゲ王子 しつこくツリフネ姫に言いより 三日と開けず 訪(おとな)いぬ
そのたび姫は歌を止め 彫刻のようにじっと黙った 王子にその声聞かせることを 堅く堅く拒んだのだった
城の警備の騎士たちは その日をことさら憎んでいた 日が昇らぬ日 月隠れる日 それと同様憎んだだのだった
『日差しに風に耐えて立つ 我らに花の微笑みの 賞与が無いとはどういう日だ』と 彼らは口々言い合った
もっともそれを憎んだのは、辺鄙な門を守りたる 老騎士カンギクその人だった
主の無体に押し切られ この歌声が汚されて 天津女神の歌声が 奴隷の歌う声に堕ちたら 神の御業に唾棄するだろう 運命を ことさら憎み我が生う所を その根源に徒成すだろう
とある朝 老カンギクは道にいて 一人の乞食と出会ったのだった 垢と髭とに覆われて 誰もがその目を背ける様な 醜い姿の瞳から 英気が凛と輝いていた 老カンギクははたりと気づく 彼こそ勇士リンドウと
何も言わずに彼を連れ 馬小屋の中に庇いたり 老妻はこれを怪しみて 夫をきつく問い詰めた
老カンギクは答えたり 『娘は既に嫁ぎたり 息子は既に成人し 家を継ぐのに適した時 そなたのことも厚く見て 心労などは掛けまいて
我が老いにたる魂は 燃え落つ場所を見つけたり 運命の神の手の中に 自ら飛び込む理由を得たのだ 我が妻と思うそれならば 夫の最後の頼みを聞いて 我がすることを見ていて欲しい』
老妻は泣きて答えたり 『我を妻だと思うのならば 我が見るところで死んでくだされ 老いの時を共過ごして下され
我は老い 春の盛りの花の姿を 当に失い枯れ落ちぬ 今の我には殿方を 捕らえる魔力はありませぬ
でもせめて引き留められませぬか 共に過ごした人生の 重みは幻なのですか』
老カンギクはうつむいて 深く嘆息したのだった
『それでも我の運命は 確かにそこから呼んでいるのだ 確かにそこから呼んでいるのだ』
あくる朝 老カンギクは火を放つ 自分の門の反対から 山から降ろす風に乗せ 紅蓮の炎を放ちたる
その混乱に紛れるように リンドウは姫を連れ出して カンギクは守るその門より 二人を逃れさせたのだ
初めて老いたるカンギクは ツリフネ姫の姿見ぬ 赤き唇 金の髪 翡翠の瞳が気づかわし気に 彼に向かって注がれた 『あなたは一体どうされるのです』
その一言 その一言で彼の生まれた 意味は確たる理由を持った 彼は祝福されたのだ
カンギクは言う 『あと一刻 一刻ばかりは持たせましょうぞ』 『頼んだぞ』リンドウも言う 二人は黙して通じ合う
後ろから 王子の兵らが押し寄せる 老カンギクは仁王立ち 武具を構えて叫びたり
『ここより先を行きたくば この老兵の屍超えろ』
たちまちのうちに襲い来る 雨のような矢と 剣の森
老カンギクは戦えり 最後のその血の一滴が 流れて落ちるその時まで 心臓の音が止まっても 彼は戦い続けたり
それが姿は歌に聞く 八羽の英雄 その乳母の アテルパの姿さながらに 死してもなおその剣振るい 獅子の雄叫び上げにたり 死してもそこを守りたり 遂には一人の騎士たちも 通さないまま一刻持った
姫とリンドウともどもに 祖国の地へと逃れる暇 老カンギクは確かに作りぬ
逃れ逃れてやがて二人は サジュの河口に国を作りぬ 老いたる恋の生んだ奇跡 サジュのその地に息づきぬ」
ミカ老人はこう歌ったのだ。
その声は、枯れてしゃがれて細い息が、幾筋入っていたようだった。肺が衰え息は短く、途切れるように聞こえていたのだ。しかし心は切なくも、老カンギクの情熱を、余すところなく伝えていた。それは迫真の歌であった。
彼の瞳は狂気をもって、僕の心を捕らえていた。何かがひりひり泡立っていた。
月が東に登り始める。満ちる予感の十三夜。
昼と夜とが入れ替わる、黄昏の時、紫紺の色の逢魔が時。
天にはきらり、一つ星。
ミカ老人は僕に言った。
「さあさああなたの番ですよ。その懐に入ったものは、少し避けててくれませんか?御爺様には失礼でしょう。」
僕はぼんやり懐に、隠した石に手を遣った。取り出してみてはたと気づく。
彼は一体どのように、ここにこれがあるということ、気付いたものというのだろうか?
その時二階の回廊に、モチが息せき駆けて来た。
「イサヨイ、分かった、遂に分かった!虹金剛の正体が!あれは年経る魂だ!奴が集めた魂だ!」
モチは叫んで僕らを認めた。そうして顔を険しくし、僕に向かって尚も叫んだ。
「イサヨイ離れろ!その人は、駄目だ、彼なら、ジュウサンは、彼は知らぬと言ってたそうだ!」
その刹那、ミカ老人は飛び掛かった。僕に掴んで組みかかり、その手に持った石を奪って、高く空へと放り投げた。
上空に池に石を落とした、その時見える波紋のような、波がさわりと立って揺れた。
石がそこから吸い込まれる。僕の手元を離れてしまった、石が完全見えなくなって、僕の耳には声が響く。
「うひひひひひひひいひ、かかったね。これで君など怖れるものか!」
厭な声、気に障る声、生理で受け付けない声だ。
瞬間僕の視界が変わる。暗黒に、真っ暗闇に飲み込まれていた。
いいや、光は確かにあった。僕の傍ら、モチがいた。彼女は淡い金の光を、体にまとって立っていた。
第十五話 「祖父の友の最後」に続く
第十五話 祖父の友の最後
第十五話 祖父の友の最後
「どうやら一歩遅かった…。」
モチが悔し気つぶやいて言う。
「虹金剛の正体に、気づいたそのことについては、君らに付いては上出来だ。だからね、挑戦権をあげよう。ここを無傷で出られたら、私と戦う権利をあげよう。難しいとは思うがね。」
奴の不快な哄笑が、暗闇の中わんわん響く。
「そこで待ってりゃすべては終わるよ。私はサクを逃さない、戦のチャンスも逃さない。
どんなに多くの魂が、戦で傷つくことだろう!欠けてひび割れ、砕けて割れる、戦の度に陶然となる、ああ何と何と美しいと!人の壊れた魂程、この世に綺麗なものはない!一つでも多く手元に置きたい、集められるだけ集めたいもの。」
「きっとそれらの成れの果てが、虹金剛であるのだよ。
虹金剛の採掘場には、こいつの汚い足跡が、幾つも幾つも付いていた。こいつの収集室だったんだろ。遠い昔に巣があった場所。それが地層に埋もれて、幾星霜に変化した。変化し石となったのだ。
道理であれと魂の、波動がそっくりだったはず。二つは元は同じであった、同じものであったのだ!」
モチはそう言い悔し気に、全くほんとに悔し気に、顔を歪めて闇を見上げた。
「一体どうしてジュウサンが、彼を知らないことが分かった?」
僕は尋ねて聞いてみた。動揺が、遅ればせながら追いついてきた。声が細かく震えていた。
「月精の姉に聞いたんだ。ジュウサンにそう尋ねる様に、言伝をそう頼んだのさ。」
「一体何里離れてるだろ!」
僕は驚きこう叫んだ。
「月精の、天翔ける速さ知らないな。大した距離に入らない。」
モチはほんの少しだけ、得意げな顔をしたのであった。
「それに彼なら、ジュウサンは、案外近くに来ているよ。」
僕は今更思い知る。騙され欺かれていたと。祖父との絆もその言葉も、全てまやかしだったのか…。
ミカ老人が好きであった。怖れていたのを差し引いたって。遠い昔に亡くしたはずの、祖父が戻って来たようだった。
うつむく僕に、モチは言った。
「さあ早くここを出ようじゃないか!手遅れになるその前に。」
「そんなことなど許すものか!君らはそこで待ってるといい。ここでは時間が圧縮される。少し休んでいるだけで、もうここを出るその時は、大きな戦となってるだろう!
第一あれがない君に、ここを出るのは不可能だ。その月精の力だって、この私には赤子同然。何をどのよう手を打つんだい?」
悪魔が不快に哄笑する。モチが悔しく歯を食いしばる。
ああ全くに不覚であった、石を自ら手放すなんて。
石を使って戦うことを、あんなに恐れていたというのに、一番石が必要なのは、この僕であったことに気づいた。
石が無くては僕は無力だ!
だがその刹那僕の頭に、微かな閃き見えたのだった。
あの石は、人の魂その成れの果て、傷つき壊れた魂の、変化して成ったものであると。
悪魔は言った、この僕に宿る魂も、うまい具合に壊れていると。
それならば、それを代わりに出来ないか?この僕に宿る生きた魂、そいつを歌いに使えないか?
僕は座って楽器を構えた。目を閉じ息を吸い込んで、ここに宿るのに意識を保った。
もうじっくりと考える、暇は無いこと明白だ。試せるだけは試しておこう。
「イサヨイ、一体どうするつもりだ!」
モチがそう言い僕に叫んだ。
「試しにちょっとやって見る!」
僕は歌いを行った。
「その混沌のただなかに 突然光が閃いた」
一声歌うその刹那、体の芯に痛みが走る、燃え上がるような激痛が。
だがしかし、光は確かに閃いた。稲妻が落ちる時のよう、ジグザグ金の光が闇に、割れ目のように光っていた。
その割れ目から、小さな光がとことこと、こちらに向かって歩いてきた。
「イト!」
僕はこの目を疑った。あれは確かにイトであるのだ。淡い光をまとったイトが、こちらに向かって駆け寄った。
「お姉ちゃん!詩人さんに早くこれ!」
「おいこら、お前!何をしている!」
響く悪魔の声ととも、緑の毒の影が激しく、うなりをあげてイトを襲った。イトは恐怖で固まって、避けることさえかなわぬようだ。
その刹那、闇に忽然現れた、白い緑の人影が、イトをかばって立ちはだかった。
年老いてなお、大きな背中、よく鍛えられたその体躯。彼は両手を上に広げ、イトを背中に庇ったのだ。
「お爺ちゃん!」
それは僕らを裏切っていた、ミカ老人であったのだ。彼の体は撃たれたように、硬直しながら崩れて落ちた。
彼はぐったり目を閉じて、慌てて抱きつくイトの前で、ピクリとすらも動かなかった。
「イト、早くそれをこちらによこせ!」
モチが即座に奪い取る、その手に持った布の包み。僕が懐入れていた、虹金剛を入れた包みだ!
僕はすぐさま歌いだす。この場に一番見合った歌を。
闇に閉じ込められた光、それらが一斉逃げ出すあの歌。
「月の主 月の姫たち 太陽の主 太陽の姫 六人そろう陽の王子
全ては輝き暗き地下の 魔の宮殿を打ち破り 全ての光は逃れ出て この世に再び勝利をもたらす
光の勝利 美の勝利 正義の勝利 命の勝利」
僕の周りに幻影が、強く輝き現れる。
音に聞く、聖地の光の神々の、神々しくも明るい姿。
精緻な光の版画の様に、白く輝き闇をかき消す。
光はどんどん眩さを増し、視界が白くかすんで消えた。
一瞬後、僕の視界はすぐに戻った。元の通りの宵であった。
『奴』の気配は消えていた。
「お爺ちゃん!」
涙の混じった声でイトが、ミカ老人をゆすぶった。彼は芝生に転がって、浅い呼吸を繰り返していた。
「お見事ですとも、お見事ですとも…。」
彼は小さな声でつぶやく。
「あなたはイトを盾に取られて、あいつに協力することを、強要されていたのですか?」
モチがそう言う言葉をかけた。僕ははたりと腑に落ちる。
「あなたのおっしゃる通りですとも…。イサヨイ様には申しましたね?私は弱い男であると、孫を失うそのことを、醜く怖れているのだと…。」
ミカ老人はつぶやいた。途切れ途切れに息乱しながら。
「それではあなたは犠牲にしたのか?自分の愛のその為に、信念、それを犠牲にしたのか?」
「あなたに申したことと真逆に、私は選択したのです。御爺様には申し訳ない…、あいつに会うその前までは、私は彼の友であったに。」
僕は驚き声を荒げた。
「それではあなたは本当に、祖父をご存じだったのですか?」
「嘘にまみれた言葉であっても、嘘のみだとは限らない。私は確かに懇意であった、ネマチ様とは友であった…。ジュウサン様についてなら、一方的に知っていたのだ。彼は何度もここへおいでに…、コフッコフッ!」
ミカ老人は血を吐いた。
「いけない、しゃべっちゃいけないよ!」
モチが慌てて彼をとどめる。
「イト…、」
ミカ老人がイトの頭に、弱弱しいその手を乗せた。
「お前は実によくやった、よくあの石を持ってきた…、小さな月の再来だ!」
イトは涙を浮かべながら、ミカ老人に抱き着いた。
「お姉ちゃんのこと、追いかけてたの、ずっと走って行ったから、あたしは少し遅れたの…。でもそのことで、石を拾えた。怖い人が目を離したすきに。あたしは勇気を持てたかな?可愛い小さな月の子みたいに。」
ミカ老人は空を見た。ああ彼に、もうイトの顔は見えていない。
「持てたとも、持てたともさもう十分に…。お爺ちゃんが怖くはないかい?」
「今は全然怖くない!元の通りのいい匂い、優しい優しいお爺ちゃん!」
涙でイトは、彼をさすった。それが最後の言葉になった、ミカ老人がこの世で聞いた。
僕とモチとはイトが崩れて、涙に落ちる様を見た。彼女は両親だけでなく、祖父まで永久に失ったのだ。
「さあイサヨイ、ぼんやりしてる暇はないよ。上を見上げてみるといい、十三の月が満月に!」
モチが鋭く僕に言い、上に注意を促した。
僕は見上げた唖然とした。
先ほどまでは確かに欠けた、十三夜のはずだったのに、今見上げて見る月は満月、確かに満月だったのだ!
第十六話 「『奴』、悪魔との最後の対峙」に続く
第十六話 『奴』、悪魔との最後の対峙
第十六話 『奴』、悪魔との最後の対峙
「時が圧縮されるとは、それはこういうことだったのか!」
『奴』の汚い策略だ、僕らに介入させないための。
「急ごう、イサヨイ、場所なら知ってる、さっき偵察してきたからね。採掘場の近くだよ。」
モチが光って宙に浮いた。飛んで案内する気であるのだ。
「私に付いて来られるように、空飛ぶ歌でも歌ってくれよ!」
僕は今更迷わなかった。悩む余地すらないことが、厳しく突きつけられていた。
ミカ老人とイトの悲劇も、拘泥している暇は無かった。
ぐずぐずしてれば全ては終わる、僕が必死に守ろうと、するものは全て駄目になる。
僕は楽器を構えて歌った。金の羽持つ兎の歌を。
「西の比良流(ひらる)の山奥に 金の羽持つ兎がいたり 西風が駆ける速さで飛んで 水が流れる速さで駆ける」
たちまちのうちに現れる、金の光の兎の幻影。僕はそいつの背に乗って、飛ぶモチのことを追いかけた。
「大事なことを教えよう。」
モチがこそっと耳打ちをした。聞こえぬくらいの小さな声で、短く不気味な言葉を告げた。
「そいつが『奴』の真名であるのだ。もしもあいつが卑怯にも、君との約束、挑戦権を、与えぬままに終えようと、したならこの名を呼ぶといい。そうして悪魔の王の名のもと、正々堂々戦うことを、宣して強制させるんだ。」
僕は驚きモチを見た。
「悪魔とは、己の言葉に拘束される。だから悪魔に対しては、なるだけ言質を取るんだよ。この前あいつは油断をしていた。」
「分かったよモチ、有難う…。君には頼ってばかりだな…。」
僕は苦しく目を伏せた。部屋に隠してあるはずの、魂のことを僕は想った。あれさえあればモチは即座に、自由になれるはずだった。
モチがしがらみ、そう呼ぶ様な、重たい体は不要となるのだ。元通り、自由な精霊体となり、どこまでだって飛んでいける。
僕は苦しく想像する。体を捨てて、僕を捨てて、自由に飛び去るモチの姿。それが自然というのだろう。
だがしかし、ああだからこそ、言えなかった。僕を一人にしないで欲しい、本音がそのよう叫んでいた。
自分一人で戦うことの、心細さに僕は負けた。一人で運命背負うことの、その重圧に負けたのだ。
ああ後悔して仕切れない。
城から街地の空に出て、すぐさま僕らは驚いた。都の市中のあちこちに、煙が立っているのだった。
城壁の門の門兵に、僕らは上から声をかけた。
「一体何が起こっているのだ?」
「仗(じょう)弦(げん)国と架(か)弦(げん)国の、一個師団が激突しました。市中の些細な小競り合いが、城外の兵に波及しました。都の外の渓谷沿いで、戦闘起きてる模様です。」
驚きながらも門兵は、僕らに答えてそう言った。
ああもうすでに戦闘は、始まっている、そういうことか。僕は心にサクを案じ、危機感に身が熱くなった。
「国王陛下と姫様は、一体どこにおいでなのか?」
モチが大きな声で尋ねた。
「陛下はお城におられるはずです。我ら護国の兵士たちは、市中の乱を平定するのに、手一杯となっております。姫様は摩(ま)亜波(あは)の塔においでです。ご無事かどうかは判じかねます。ご無事を祈っておりますが…。」
僕が言葉を発する前に、モチはすぐさまこう叫んだ。
「姫様ならば任せておくれ。すぐさま塔へと向かうから!」
「何卒お願いいたします!」
その門兵は僕らに託した。
モチはこの僕見下ろして、当たり前のようこう言った。自分が僕らに加勢するのは、当然なことという様に。
「さあ急ごう!まだ間に合わないとは限らない。」
僕は即座に後を追う。不思議だった、モチが言うなら、それならきっと大丈夫、そう確信が湧くのだった。
僕らは速度を上げて飛んだ。泥(でい)安(あん)東に延びている、渓谷見下ろすように立ってる、摩(ま)亜波(あは)の緑の楼閣を、めざし一散飛び抜けた。
塔の下、少数であると言うものの、両国の兵が本格的に、戦ってるのが見えて取れた。両陣営にはそれぞれ王子が、旗をふるって指揮をとり、打ち鳴らされる太鼓と共に、獣のような声が響く。かがり火と火矢が赤く光り、闇深き中、きらりきらりと、剣と槍とがきらめいた。
どこかで火薬が鳴っている。不穏な臭いも立ち込めている。歌と楽器の音も聞こえる。どこかで詩人が戦ってるのだ。
このままいけば本格的に、戦となるのは必至だろう。
全てを超えた所に浮かぶ、満月だけが悠々と、欠けない光で照らしていた。麗しいその姿だが、今宵はそれが冷たく映る。 まるでこの世の争いごとなど、人の命の消えるのも、自分は全く介さない、まるでそう言うようにも映る。
「見ろ!サクだ!」
モチが注意を喚起する。
塔の屋上その上に、サクが追い詰められていた。群青の衣装身にまとい、星の如銀の装飾が、赤い炎を反射して、不吉にゆらゆら煌めいていた。
僕の心は悲鳴を上げる。今すぐサクを自由にしなきゃ、冷酷非情な運命から、サクを救って逃がすのだ!
それには絶対必要だった、石と歌いがもたらす力。僕は戦わなくてはならない!
いとも易くに心は決まった。あんなに迷ったことですら、ほんの茶番という程に、僕の心はすっかり決まった。
ほんとに全くあっけなかった。
僕は戦う男の目線で、サクと周りの状況を、瞬時に観察したのだった。
サクを追い詰めているのは、黒い鎧で全身を、ぴったり覆った戦士だった。
まるで闇から切り出して、塗り固めたという様に、不気味に暗いその鎧。こんなに暗い夜にあっても、更にも暗く感じるほどに、暗く不吉なその姿。
僕が見るにはどこの所属で、どういう階級の者かは、判別できない戦士だったが、目でなく直感それで分かった。
あれこそ悪魔の化身であると。
『奴』が剣(つるぎ)をすらりと抜く。サクは恐怖に青ざめながら、それでもきっと『奴』を睨んだ。見かけによらず気丈なサクの、それは決意の表明だった。
それは僕に生まれた覚悟を、なお一層に強くする。
僕は大きな声で叫んだ、先ほどモチに教わった様。
「そちが名は『蝕(しょく)』、むしばむもの、悪魔を統べる赤口(しゃっこう)の名に、その約定にのっとって、正々堂々勝負をしたし。
僕が負けたらこの魂も、お前にくれてやろうとも、だがしかし僕が勝ったなら、お前はサクから永久に、その汚い手を引くことだ!」
暗黒の、戦士の形がぐにゃりと崩れ、汚い緑の影にゆがみ、そうしてまたもや形になった。
濡れたみたいな黒い髪、黒い上下の、「コレクター」、あいつ悪魔の姿であった。
「全く入れ知恵は困るな。上手く早くに戦が起きたに。まあいい、決まりは決まりだからね。我らのおきてに文句は言えまい。分った勝負はしてあげようとも。結果は分かり切っているが。」
悪魔はにやりと微笑んだ。自分が勝つということに、自信を持っていたようだった。事実この時僕は実際、こいつの力がどの程度かを、正しく知ってはいなかった。
いいや正しく知っていても、引くという気になれやしなかった。一体誰が止めたところで、僕は戦い挑んだだろう。
僕に生まれた決意は僕を、捨て身の戦に駆り立てた。嵐のような衝動だった。
まるで老騎士カンギクのよう。
そうして彼を引き留めた、老妻の様見つめる瞳を、僕は全く介さなかった。いいや全てが見えてなかった。
サクと悪魔のそれ以外、僕には全く見えていなかった。
周りを気にする余裕は無いほど、僕の心は一心に、サクへと向かって注がれた。
僕は塔の屋上に、急いで静かに降り立った。それが開始の合図となった。
第十七話 「運命がここで呼んでいる」に続く
第十七話 運命がここで呼んでる
第十七話 運命がここで呼んでいる
奴が何かの言語をつぶやく。おそらく悪魔の言葉であるのか、聞くだけで身が侵される様(よ)な、おぞましいその言葉の響き。
たちまち奴の体は真紅の、鱗に覆われ大きく膨れる。腹はぼってり太くなり、赤褐色の翼が生える。金属性の耳障る音、火山の臭いの息を吐く、巨大な火竜の姿となった。
火竜は僕に炎を吐いた。警備に就いた兵士らと、侍女たちは悲鳴上げながら、下の階へと逃れて行った。
サクだけが、身じろぎもせずに僕らを見ていた。その表情は蒼ざめて、苦痛に満ちたものであったが、この僕を案じ信じる顔と、僕は正しく受け取った。
瞳が火竜の炎を反射し、赤く激しく輝いた。
ああサクはここで生きている、その命の火が消えてないこと、まだまだ希望があることが、僕に大きな力を与えた。
僕は楽器を構えて歌う。懐の石が強く光る。
「全ての水の女王なる ジェルドララ天の水瓶に この世の全ての水をしまって 翡翠の栓を閉めていた
奸智のオセにそそのかされて 漁師の主神 オフトフは 酒宴の座興に誓わせられたる
オセの妻なるセフラのために 翡翠の栓を持ち帰り 魚の針の形に作り 首飾りにして捧げると
酔った勢い酒の間違い のち千年の痛恨事 オフトフはその元を作りぬ 千鳥の足で向かいたる 天の水瓶その深み
人魚の兵士と乙女の見張りに 隠れて彼は潜りゆく 魚影の群れを追いゆくために 鍛え抜かれたその泳ぎ
たちまち栓をやっと抜く さてはやったり 果たしたり そう思ったのは一瞬だった 抜いた直後に水の重みに 天の水瓶底が抜け この世の全ての水が天から 地上に向けて注ぎたる オフトフもその流れに負けて 波(ぱ)戸(と)羅(ら)の海へと沈みゆく 水は七日七晩注ぐ 全ての海と全ての河と 水と名の付くものは全て 溢れこの世を覆いたる
一の波から九の波まで 波頭は高くそびえ立つ 君群(くんぐん)山のてっぺんまで 白く散る波が大地を洗い 魚の群れは森に遊ぶ お城の塔には貝が着く
この世の全ての炎は消える 灯も 鍛冶の炎も煮炊きの火も 非情に水は消し行きぬ 鉄溶かす火山熱の大地も 水の猛威にさらされて 冷たき砂鉄の山となった」
僕らの頭上に雨が落ちる。天の底が抜け落ちた様な、体感したこと無い様な雨。
雨は地上の全てを流す、火竜の吐く息、その熱も、冷たい流れに押し流す。金属製の鱗から、じゅうじゅうという音がして、火竜の瞳の炎が消える。冷たい鉄の塊に、冷え固まっていったようだ。
僕のたもとの虹金剛は、一つぱりんと弾けて割れた。
「末恐ろしい手を知ったもんだ。しかしこれならどうかなあ?君が今まで使ってた、水はこちらが使ってあげよう。」
悪魔の声が響くや否や、火竜は影と滲んで消えた。そうして影は再びに、形を長く現し始める。
それは幾重にとぐろを巻いた、巨大な水の蛇であった。水蛇は、僕が只今呼び出した、膨大な水に取り憑いて、その大きさを増していった。
大地の全てを覆うような、巨大で冷たい水の蛇。
僕は再び歌い始める。
「愉(ゆ)慧(え)弥(や)の肥沃な大地の野原に 盗賊タルが住んでいた イタチの様にすばしこく 猫の如くに狡猾だった
タルの育ての親なるは 河神バダア 彼は息子の危機に際して 最大限の援助を与えた 領地を守る領主も兵士も 何度もバダアの奇跡に負けて 盗賊タルを捕らえられずに 由宇江の野原を自由気ままに 闊歩すること許していた 由宇江の民は困り果てる 蔵の類は荒らされて 行商人も避けて通る 肥沃な大地も商売なくば 富生むこともかなわない
ある晩村に訪れる 灰のマントをまとった老人 髪の毛は全て白くなり 残った前歯は一本だった しかしその目の鋭さは 兎をさらう鷲の様 枯れ衰えた体でも 背中と腰は真っ直ぐだった
その晩のうちに老人は タルに戦い挑みたり 金の入った袋を餌に 丘の一本杉の木の 下にてタルを待ち伏せぬ
賢いタルはバダアに祈る
『父上水をお送りください あの丘にそびえる杉の 根の辺りまで浸して下さい』
バダアはそれを聞き入れた たちまち迫る暴虐の水 老人の足も水に浸り 注視していた村人は もはやこれまでそう思ったり その老人は落ち着いて 足元の土に呼びかける
『豊かな土よ 賢い土よ 水の暴挙を止めるのは 可愛いお前であるのだよ』
彼の言葉に愉(ゆ)慧(え)弥(や)の土は 命を得たり 動いたり 生き物の様盛り上がり バダアの水をせき止めた 更に由宇江の土はうねって バダアの水を切れ切れに ちぎって勢い殺したる 遂には水の上を走って 逃げようとするタルを捕らえり
さても賢き愉(ゆ)慧(え)弥(や)の土 恵みの深き土の御業」
塔の周りの大地がうなる。僕の歌いに盛り上がる。音に聞く彼の由宇江の生きた、土の話のさながらに、生き物の、ようにうねって暴れる悪魔の、水蛇のことを封じ始める。
水と土とがぶつかり合い、薄茶の泥のしぶきが飛ぶ。やがて重たい泥水が、水蛇の動きを鎮圧した。小躍りするよう周りの土は、勝利の気泡をふつふつ湧かす。
僕のたもとの石が一つ ぱりんと弾けて砕け散った。
気付くと下の兵士らが、戦い止めて見上げていた。二人の王子と数人の、兵士が上へと昇ってきて、余りの激しい戦いに、固唾をのんで見守っていた。
「全く、君は躊躇が無いな。なりふり構ってられないか?ところであれはどうしたろうね?そこの傷欠けない月の子の、贄の魂、それはどうした?」
緑の汚い影が泥から、悪魔の形に結集する。土は乾いてひび割れて、砂っぽい風が巻き起こる。そうしてわざと動揺を、誘うようなこと僕に尋ねた。僕は何にも答えなかった。
ただ黙ったまま知ったのだ、モチが秘密を知ったということ。
彼女は一体どう感じたか?僕に振り向く勇気は無かった。僕は黙って悪魔を睨んだ。
悪魔は再びぞっとする、響きの悪魔の言語で唱えた。今度は何に変わるのだろうか。
今度は悪魔の手足の数が、八本に増えて長く伸びる。乾いた土が『奴』の体に、引き寄せられてくっつき始める。
磁石に砂鉄を近づけた様、命を持った土は悪魔の、その影の呪に染まって禍々しい、毒ある虫の姿となった。
悪魔は巨大な蜘蛛となった。背中に不気味な髑髏の印の、浮かぶ茶色の巨大な毒蜘蛛。
「あれを彼女に渡したのは、私の作戦だったんだがね。月の女が加勢をすれば、こちらが不利となるからね。さっさと退場してもらいたくて。
しかしやっぱり君にはできない、私が睨んだ通りだよ。サク一本には絞れないんだ!一途に見えて不純なんだよ!
君は一体どっちを選ぶ?そこの二人、サクと月とのどちらを選ぶ?どっちか一方だけとしたなら。君は一体どっちを選ぶ?」
蜘蛛の口から悪魔の声が、嘲るように聞こえていた。僕の体に動揺が、一瞬走って僕は必死に、その感情を抑えこむ。
あいつにしてもあせっているのだ、だから動揺誘う様なこと、わざと選んで言っているんだ。
僕は自分に言い聞かす。
そうして再び楽器を構える。残った石はあと一つ、出来ればここで決めたいが…。
「施(せ)李(り)二(に)の山で臨月の 妊婦が茸を採っていた 餌を求めて気が立った 大きな熊に行き会った
妊婦は慌てて木に登り 下でぼうぼう吠え立てる 熊におびえて祈りをささげた
『冥府の森をつくりたる 森神ライサ 願わくば わが身を木の葉に変えて下さい その代わり この腹の子はあなたに捧げて その従僕といたしましょう』
ライサはこれを聞き入れた 妊婦の姿を見失い 熊は渋々去っていった 妊婦は胸をなでおろし 姿を戻して降り立った
やがて月満ち生まれきた 赤子の姿は異様であった
若木の様な艶めいた 赤茶の皮膚に木の葉の髪の毛 指の代わりに細い根が 幾つも伸びていたのだった
妻が異なる一族と 不義をしたのと信じ込み 父は罵倒し去っていった 残された 母は息子をかばいつつ 肩身を寄せて暮らしたのだった ことあるごとに母は言う
『お前のことは森神の ライサ様こそ守られる その皮膚も 髪も指ですらかの神の 加護を受けたる証だよ 真っ直ぐ向いて生きるのだ 何時かは皆も理解する お前が聖別されたものだと 誰も恨んじゃいけないよ』
それをよすがに息子は耐えた 大人の陰口差別にも 子供のあけすけ罵倒にも じっと耐えそして耐えたのだ
彼は毎晩祈りを捧げる 彼を加護する森神に 恨みの心を持たぬよう 心を守護してくれるよう 彼は毎晩祈ったり
やがてある年豪雨が襲う 二人の住みたる山間の 小さな村は危機に揺れた 村を守ったはずの山が 水を含んで大きく膨れた もう一滴でも降ったなら 暴虐の泥の水となり 小さな村を飲み込むの 避けられぬほどの雨だった
村人が顔を顰めつつ 気づかわし気に山を見る中 一人息子は母に言った
『母さんきっとその時が来た 僕の生まれたその意味が 遂に形となる時が 僕がこの村救うのだ』
母は涙で抱き寄せた 引き留める言葉口にしつつ 引き留める術の無いことが とうに知れてる母であった
息子はライサに祈りをささげた
『ライサ様 私を覚えておいでなら 私を加護してくださるのなら この足で あの山の土を縛って下さい 土くれ一滴漏らさぬように 堅く堅く結んでください』
ライサは願いを聞き入れた 息子の体が変化する 胴は高く伸び太くなり 赤茶の強い幹となった
腕は爪から葉が生えて 影をやなせる枝となる 足は激しく波打って 枝分かれした根となった 根の勢いは強いもの たちまちのうち泥水を 捉えて激しく吸い上げる 水を吸ったる根はなお伸びて 数刻の内巨大な樹となり 得流駄の山を捕まえて ふもとの村を守ったのだった 得流駄の村の物語 ライサの奇跡の物語」
僕の歌いの言葉に答え、巨大な樹木が現れる。幾重に幾重に根を張りだして、幾星霜に育つような、長い時間をかける成長、それらをわずか数秒で、嵐の勢い遂げたのだ。
僕の樹木の根は蜘蛛を、悪魔の化身の毒蜘蛛を、力強い根に捕まえた。その吸収の強さによって、蜘蛛はたちまち干からびる。
これで決まってくれないか!僕は祈りを心に持った。
僕の最後の虹金剛が、ぱりんと砕けてはじけ飛ぶ。
ひび割れた土がぼろりと落ちて、悪魔の姿が現れる。彼は消耗してはいたが、それでも石が無かったら、勝てる気持ちはしなかった。
絶望的な気分となった。あのやり方で戦えば、それほど持つとは思えなかった。悪魔が使い果たすが先か、僕の命が尽くのが先か。
しかしその時この僕に、一歩も引かぬ覚悟が出来た。命すら捨てる勢いの。
僕にその時生まれた覚悟は、なんとも説明しがたいものだ。
サクのその為戦ってるのに、まるでそれすら凌駕する、訳も分からぬ大きな力、それにたきつけられてるみたいだ。
大きく暗い水の流れ、流星の燃えて尽きる勢い。僕は自分の運命に、飛び込み夢中で泳いでいるのだ。
目的のため泳ぐのか、ただ泳ぐために泳ぐのか、今でも僕には分らない。己の中の衝動に、ただただ従うそれのみだ。
「どうやら私の勝ちのようだ。そいつで石は最後だろう。もうどのように許しを請おうと、君のことなら許さない。」
悪魔が再び唱え始める。僕は後ろに浮かんでる、モチに向かってこう言った。
「ごめんよ、モチ、さっき話を聞いてただろう。君の贄なら持っているんだ。サクから返してもらってたんだ。
僕らの部屋の茶たくの引き出し、その中にそっと入っているんだ。黙ってて、悪かったそう、悪かった…。飛んで行ったら間に合うよ。君はこれから自由になれる。僕のことならもういいんだ。君なら無事に生まれ変われる。」
「君は一体どうするつもりだ!もう石だって残ってないし…。」
モチは悲壮にそう言った。ああ全くに彼女は優しい、こんな僕にも情けをかける。
そういうモチの優しさも、この時僕には効くこと無かった。運命の手は僕の命を、しっかりつかんで逃さなかった。
僕は覚悟を決めて振り向く。彼女と話す最後となるのだ。きちんと顔を見ておこう。
モチは全く苦し気だった。この僕を案じ苦しんでいた。僕がとっくに諦めた命、引き留めようと必死だった。
モチの優しさそれだけで、僕は報いを受けた気でいた。これだけでもう十分だった。僕はそういうつもりでいたのだ。
僕は彼女に微笑んだ。
「僕ならまだまだ戦える。ここに命が宿る限りは。」
「自分の魂使うつもりか!命が幾つあっても足りない!」
モチは悲痛に叫んで止めた。だが僕は、もうこの時既決めていた。
「運命が、ここで呼んでる、運命がここで呼んでいるんだ…。」
悪魔の呪文が僕の木に、取り憑き魔樹へと変貌させる。耳障りな声上げながら、巨大な魔樹は、キャラキャラと、笑い転げて跳躍する。
枝が、根が、なおも残った王子や兵を、暴虐な鞭さながらに、突き刺す勢い暴れだす。
第十八話 「仔羊の最後」に続く
第十八話 仔羊の最後
⒘第十八話 仔羊の最後
僕は再び楽器を構える。自分の中に宿るのに、そこに意識を集中させる。激痛が、僕の体の芯に走る。だがそれすらも構わずに、僕は歌いを始めたのだ。
「世にも巨大な阿魔琉(あまる)の森の 東の原に楽し気に 巨人の親子が歩いていた 父は小さな小山程 息子は杉の若木程
父は大きな斧を持ち 息子はおもちゃの弓持って 抜け目なさそに駆け回る
やがて大きな黒鷺が 二人の真上を横切った 息子の巨人は狙い定めて びゅうと音立て矢を放つ
鷺は真下に落ちなかった よろよろ飛空を続けながら 阿魔琉(あまる)の森の中に落ちた
『父上獲りに行ってきます 実に綺麗に射抜いたの その上達を示しましょう』
獲物を取りに行った息子は 一時経っても陽が暮れど 遂にはとうとう戻らなかった
巨人の父は待ち続け 夜が明けた後森に入り 帰らぬ息子を探し始めた
『森よ森よ 黒い森 俺の息子を見なったか 百歳超えてやっと授かる 可愛い一人息子なのだ』
森は底意地悪そうに くすくす笑いを顰めつつ 悪意を込めて沈黙をした
父親に 教えるつもりのないことが そのひそめきにそうと知れた 父の巨人は激怒した
『阿魔琉の森よ図ったな 俺の息子を盗るために 鷺をここまで招いたな 倅をどこに隠したか!』
阿魔琉の森はわんわんと 嘲るように哄笑した 父の足下に息子の胴着 敗れた靴が顔を出す 森の木の根に吸い取られ 見る影無いほど朽ち果てて
巨人の父は怒ったり まるで孟涅(もうね)の火山の如く 烈火の怒りで背負ったる 巨大な斧を振り回す
『俺の宝を奪ったからには それ相応の報いを受けよう 俺にかかればお前など 刈り入れ前の麦原だ!』
巨人の父は打ち払う 天を目指して生えた樹を 陽が差さぬほど生え茂る 黒く湿った葉陰ごと 根を刈り取って
枝を払う 森はたまらず悲鳴を上げた しかし全ては遅すぎた 巨人の父は怒りに任せ 森の全てを打ち払う
切り株からは嘆きと共に 樹液が黒き血の如く どくどく流れて土に溢れる
憤怒の形で巨人の父は とうとう残さず森の全てを 一本残さず根絶やしにした」
僕の体の痛みに答え、巨人の幻影それが浮かぶ。巨大な斧で悪魔の大樹を、打ち倒し鉈で根を刈り取る。悪魔の木からはどくどくと、汚い緑の血が流れ出る。悪魔はたまらず元の姿に、戻ってこのよう悪態ついた。
「一体どういう反則業だ!自分の魂使うなど!君は全く狂っているな!だがねそいつは多用できない。
持久戦ならこちらに利がある。」
悪魔は再び唱え始める。何度聞いても厭な呪文を。
悪魔の立った向こうには、サクがこちらを眺めていた。呆然として眺めていた。
顔は青ざめ涙は流れ、苦悶の表情その中に、尚更命が燃えること、逆説的に伝えていた。ああまだ僕は戦える、ああまだ僕は戦える…。
僕は彼女に微笑んだ。今助けるよ、今助けるから…。
「まだだ、まだ、まだまだ僕は戦える!」
「イサヨイ、止めろ!血が出ているよ!この戦いでは君は勝てない!」
モチが激しく叫んでいた。何時にないほど悲痛な声で。
ああまだここに見守ってたか…。僕の優しい月の精。
僕は額に手を遣った。冷たい汗で濡れている。目と口からは血が流れ、今の歌いの負担の重さが、ぼくにも重く理解が出来た。
しかし僕なら再びに、楽器を構えて集中した。悪魔はいまだ負けていないのだ。
悪魔の姿は今度は人形、金属製の人形の、軍隊それに変わっていたのだ。冷たい月に照らされて、人形たちが不気味に輝く。命の感じぬその姿。
太鼓の音に合わせて歩き、長槍を僕の喉元に向け、きんきん言うその耳障る声、時の叫びをあげて喚いた。
僕のこの身の激痛は、弓の矢を雨と浴びた様だ、剣(つるぎ)の上を歩いたようだ。
しかしそれすら抑え込み、再び歌いを始めたのだった。
「琉(る)新(しん)の山の沼の地に 女神が一人住んでいた その名は三(さん)火(ほ) 火の神と水の女神の娘であった
勝気と憂いの入り交じる 水と炎の相成す瞳 髪は流れて脚はしなやか どこまでだって駆けて行った
三火に強く打ち込むは 玖宇(くう)の火山の神の王(おう)威(い) 日ごと朝ごと三火を訪ね その愛を乞うたものだった
だがある日 王威は鉄の神都運偶琉(とぅんぐる)と 三火の家のその前で ばったり鉢合わせしたのだ
恋する男の直感で 恋敵だと察しを付けた 彼は王威に手に入れられぬ 色とりどりの花を贈った 良い声で歌を歌って贈った 三火はぐらりと傾いた 無骨に過ぎる王威には 得られなかったときめきだ
王(おう)威(い)は激しく憤る 愛の誓いも得られないのに まるで我が物盗られた如く 憤りのまま戦い挑む 他でもなくも都(と)運(ぅん)偶琉(ぐる)に
琉(る)新(しん)の山の裾野にて 二人の神は戦った 都運偶琉(とぅんぐる)は 隊列組んだ鉄製の 兵士をあまたも送り込む
対する王威は荒ぶりて 真っ赤に焼けた溶岩を 果て無く流して襲い掛かった
木が焼けて 草が焼ける 大地は焦げて悪臭放つ 羽ある鳥は飛んで逃げた 獣も虫も命からがら 逃れられるだけ逃れていった
黒き煙で真昼の空も 黄昏過ぎの夜の闇に その闇の中にきらきらと 王威の流した溶岩が ただそれだけが輝いた
大水の様な溶岩は 鉄の兵らに襲い掛かった 鉄の剣がぐにゃりと歪む 真っ赤に起こった兵達は ずぷずぷ解けて崩れていった 遂には流れる溶岩の その一滴となったのだ 王威の怒りは収まらず ひたすら荒ぶり火を噴いた 三日三晩も火を噴いた 恋の恨みのそのままに
やがて翌朝我に返る はっとなり目を凝らしたが 緑の裾野は燃え尽きて 三火の沼地は干上がった
嵐の悔胸に宿して 散々探してみたのだが 三火の姿もどこにもなかった」
僕の周りに溶岩が、湧いてとめどもない勢い、鉄人形に向かって渦を巻く。月の冷たい光を犯して、禍々しいほど焼けた溶岩、その陽炎の向こうに悪魔の、金属でできた兵隊が、真っ赤な液に溶けて流れる、その有様が見て取れた。
僕の体の激痛は、更に呵責を増していく。血を吐き僕は膝をつく。だがその瞳はサクを追った。彼女も僕を見つめていた。見つめて涙をこぼしていた。
「ああ全くに忌々しい!これほど痛みを感じたのは、八羽の英雄以来だな。だがそれすらもお終いだ、もう一曲でも歌ったら、君の命は尽きるだろうね、私ならまだ、余裕はあるが。」
大分疲弊してはいたものの、悪魔にはまだ余裕があった。消耗戦では分が悪かった、ああせめて、せめても一つ石があったら…。
「いや、まだだ、いやまだだ、まだまだ僕は戦える!」
僕は最後の覚悟を決める。一体何のためにそうして、何を理由に戦うか?
運命のための運命か、いいやそれとも愛の為か?僕の急いだ頭では、そいつははっきりしなかった。
ただそうしなきゃならないのだった。それだけはっきり解かっていた。神様は、僕にそいつを要求していた。
覚悟を決めて楽器を構える。息を吸い込むその時に、サクの言葉が耳を捕らえた。
彼女は石の欄干に、登って凛と声を降らせた
「お止め下さい!止めて下さい!私の命が欲しいなら、あなたにくれてやりますとも!もうどうせ、捨てたみたいな命ですもの、何時捨てたとて悔いはない…。私ごときの命のために、命懸けるはおやめください。
それでも私も虫一寸の、誇り矜持がございます。全てはあなたの思い通りに、ならぬことのみ憶えてください。」
サクはいったん言葉を切って、大きく息を吸い込んだ。
「王子様方お聞きください!」
鬼気迫るその勢いで、サクは王子に呼びかけた。隅に下がった王子らは、警護の兵のその後ろ、虚を突かれたのか驚いて、サクの言葉に聞き入った。
一体何が起こっているのか?サクは一体何をするのか?僕には測りかねていた。
「あなた方は、私を愛してくださいますね?はっきりそうだと誓えますわね?」
王子らは、動揺したよう口々言った。
「もちろんですとも、アリアケ姫よ…。」
「あなたこそ我が命ですとも…。」
「それならば…。」
サクは言葉を止めて続ける。
「どうか戦を止めてください。私が諍いその元ならば、私が死ねばいいのです。誰の物にもなりません。私がいなくなったなら、争う理由も意味も無くなる、戦う意味も、殺し合うのも…。私がいなくなったなら…。」
サクはそう言い虚空を見た後、僕をまっすぐ見つめ直した。
「詩人様、最後にあなたの歌声を、聞けたそのこと幸いでした、私ごときに命を賭して、血を吐き歌うはもったいないこと、私はとても幸せですわ…、誰が一体何を申せど!世間の人がどう言おうとも…。
でももうそれもよいのです、もう戦わずとよいのです…。幸せになって下さいませ…。」
最後に彼女は僕を見た。僕をまっすぐ見つめて呼んだ、サクは微笑み浮かべていた、雛罌粟(ひなげし)の様な微笑みを…。
「さよなら!イサヨイ!」
それの言葉が消えないうちに、石の欄干その上の、サクはふわりと宙に舞った。谷間の風にあおられて、青い衣装がはためいた。一瞬で、サクの姿は見えなくなった。
王子らが、悲鳴を上げる。供の者も、慌てふためき駆けよった。
僕の体は動かなかった、あまりのことに動かなかった、命を賭して守ろうと、した存在が消えてしまった…。
僕が戦うその理由、ここまで自分を痛めつけてまで、戦う理由を失った…。
サクを永久失ったのだ!
僕は楽器を取り落とした。ゲンという嫌な音がして、弦が一本切れて飛んだ。
王子と御付きの者たちは、取り乱しながら階下へ降り行く。一人の侍女が泣きながら、欄干にしがみついていた。
「うはははははははははは!」
悪魔が盛大哄笑した。
第十九話 「別れ」に続く
第十九話 別れ エピローグ 円環
第十九話 別れ
「うはははははははははは!」
悪魔が盛大哄笑した。
「全く美味しいドラマだね!君の大事なサクは君を、かばって谷へと落ちて行ったぞ!助けることが出来なかったね!そんなにまでなり戦って、全てはかいが無くなったねえ!うひひひひ、楽しいな!他人の不幸は蜜の味!
サクの魂回収する前、君の命もいただこう。上手い具合に傷ついたろう、きれいなひびが入っただろう。もう抵抗などしないよね?」
悪魔はそう言い近づいた。その通りだった、僕にもう、抵抗する気は残ってなかった。
もう生きていたくなかったのだった、一瞬だって生きたくなかった。命を捨てるつもりであった。
悪魔はひたりと近づいて、その左手を僕に向けた。僕の瞳は光り失い、それをぼうっと見るだけだった。
強い光が閃いた。僕は驚き目を見張る。
「ゴホッ、ゴホッ、カハッ!」
強い光の槍に刺されて、悪魔はがっくり膝をつく。
「私のことを忘れていたな。」
その声に、僕は驚き振りむいた。モチが光の槍を出し、悪魔をくし刺し貫いていた。
「馬鹿な…、生まれ変わりの…、力を…。」
悪魔のうめきに僕は気付く。生まれ変わりの力だって?それを残していなければ、モチの寿命は尽きるじゃないか…。
悪魔の口から毒々しい、緑の液が流れ出た。目からも同じ緑の涙が、ドロドロ流れて出て行った。
悪魔の体は解けて流れる、緑の汚い液体の、小さな溜りになった後、臭い臭気をまき散らす、蒸気に変わって消えていった。全く後は残さなかった。
悪魔が蒸発するのと同時、背後の城から数多の光が、夜空に向かって幾筋も、まるで打ち上げ花火の様に、歓喜の叫びをあげながら、七色とりどり飛び去った。
泥安はおろか渓谷沿いまで、暁の如に光が照らす。だがそれはほんの一瞬だった。すぐに光は夜空の彼方に、吸い込まれる様消えゆくのだった。
あああれはきっと魂だ、『奴』に閉じ込められてた魂、それが只今自由となって、正しく天へと帰るのだ…。
一つの光が金に輝き、天ではなくてこちらの方へ、まっすぐ軌跡を描いて飛んだ。
金の光は傍らに立つ、モチの体に吸い込まれ、モチの体は一層艶濃く、輝きを増して僕を照らした。すべてが遅くなってから、モチは彼女の獲物を得たのだ。ああ何という、定めの皮肉…。
「モチ…、一体どうしてなんだ?」
僕は呆然声に出した。口中は既にカラカラだった。激しい歌いに声はかすれて、いつもよりかはひび割れていた。
彼女は涼しく微笑んでいた。
「どうしてかって言ったって、君の魂『奴』に取られる、それは絶対許せなかった。
それより私は謝らなくては、サクが命を絶った時、彼女を受け止めなかったことを。動けることは動けたけどね、『奴』が君から目を離さずに、私に隙が出来たなら、いつでも君を襲えるように、目を光らせていたものだから、私はサクを救えなかった…。」
モチはそう言いうつむいた。
「謝らなくてはならないのは、僕の方だろ、僕の方だろ!君の大事な贄を隠して、引き留めようとしたんだからな!そのせいで、君の命が尽きてしまう!」
僕は涙を隠さず叫んだ。全ては僕のせいなのだ、サクを失い、モチも失う、中途半端な僕のせいで。
一体どうして二人とも、この僕のことを責めないのか!いっそなじってくれた方が、僕の心も晴れるのに…。
「私はそれを選んだのさ。人の体を持ったことで、いろんな心が体験できた。ここに燃えてる暖かい、この感情はなんていうのか?私はそれを選んだんだよ。」
モチは左の胸に手を、当てて優しく微笑んだ。初めて出会った頃の皮肉で、哀し気な顔が目に浮かぶ。
今モチは、何故か満足そうだった。自分に対する自信を感じた。正しいことを選んだと、そう心から思ってるのだろ。
ああモチは、全てを許容しそれを選んだ…、モチはそいつを選んだのだ…。
「精霊体でいた時は、こんな気持ちは私に無かった。体というのは面白いね、肉に縛られ制限される、だから生まれる感情も、確かにあるっていうことだ。
私はあの時生まれたんだよ、君が私を覗き込んだ時。冷たい水の中に生まれ、初めて世界を見たんだよ。君の背中は暖かかった、それが最初さ、最初だった。私の選んだ感情の。
私は只今気づいたよ、今この時のその為に、私は生まれて生きてきたんだ。今この時のその為に…。」
モチは上空満ち足りた、欠けの無い月見上げて言った。
「この月が、中天に浮かぶその時に、私の寿命は尽きるのだ。」
僕は呆然膝突いたまま、彼女を見上げていたのだった。モチの頭に月がかかって、後光のように光が差した。
ああもう時間がないじゃないか!あと数分でモチは死ぬ、あと数分のその後は、モチまで永久に失うのだ。
モチはしゃがんで覗きこんだ。僕の背中に手を当てて、小さな包みを差し出した。
「これをご覧、君に最後の頼みがあるんだ。この靴を…。」
モチは小さな紙の包みを、破いて中を僕に見せた。
それは朱赤の布で出来た、錦糸の刺繍が縫ってある、若い女性の靴であった。
「私が死んだら贄の命も、無事に体に戻るだろう。その時この靴履かせてやってね、是非にも君の手によって。
この子の命は輪に戻る、この子の場所へ、人の輪へ。その為の、証が靴だよ、詩人さん。」
モチはそう言い悪戯に、僕に向かって片眉あげた。
今まで当たり前の様、享受したその幸せが、どんどん脳裏によみがえる。
モチはいろんな顔を見せた。初めて会った哀し気な顔、陽気で悪戯好きな顔、残酷冷たい裏の顔、僕の狡さを許した顔。
全てが得難い幸せだった。何と多くのことを僕は、モチから奪ってきたのだろうか?
彼女は何時しか変化していた、この僕が奪うことのせいか?彼女の無邪気を喰ったせいか?
たった一つのその疑問、僕はようやく口にした。しかしそいつはどうしても、聞かなきゃいけないことではなかった、どうでもいい様(よ)なことだった。
「これは一体どこで買った?こんな趣味だと知らなかった。」
モチは普段の通りに明るい、声の調子でこう言った。
「イトが町から買ってきたんだ。ほら前に市に、買い出しに、付いて行ったことあったろう?その時私に買ってきたんだ。だけど私は履かないし、必要のないものだった。だけど体の持ち主は、きっと裸足じゃ痛いだろうさ。」
僕も普段の通りに聞いた。どうしても涙あふれて、しゃくりあげ、声は震えていたけれど。
「君は痛くはなかったかい?君の体は人間なんだよ、どうして足に傷がつかない!」
モチは哀しく微笑んだ。弱気で痛みに満ちた笑顔。見たこと無い様(よ)な表情だった。こういう顔をすることを、僕は今まで気づかなかった。
「足には傷はつかないよ。私の命が守っていたから。だけども痛みは感じたよ、足ではなくて、別の所に。
あの悪魔、私に傷や欠けが無いと、嘲って言ったようだったけど、傷なら有ったさ、確かにね、心に痛みが走ったものだ。
人の心は壊れやすいね、ほんの些細なことですら。だから綺麗に輝くと、私はそれを知ったんだ、だってさあ、君と一緒にいるだけで、傷つかずにはいられない…、傷つかずにはいられないよ。」
モチはそう言い首を振った。傷つきやすい少女の様な、笑顔にならないその笑顔。初めて見せたモチの弱気。
ああ何と、僕は沢山奪ってきたのか、モチの優しさ、モチの希望、それらをあさってここまで来たのだ。
独りじゃないのに甘えながら、食い散らかしてここまでこれた。そしてとうとう独りになるのだ。
僕は涙をこらえて笑った。かがむ彼女の手を取った。
血の涙さっき流した後で、熱い涙が流れ出る。鼻水が血と混じって口に、流れて入るがどうとも出来ない。
僕は相当ひどい顔だろう、歯が噛み合わないほど寒気が走る、それでも心は熱を持つ。
この情熱の持って行き場は、この先どうすりゃいいのだろう?二人がともにいなくなったら、僕は一体何をよすがに、この先生きればよいだろう?
心の整理がつかない僕に、最後の時は、刻一刻、刻一刻と近づいた。
モチは黙って僕の涙を、温かい指で拭って取った。
「さよなら、イサヨイ、詩人さん、とっても楽しい人生だった。」
月がとうとう中天に、かかりその影短くする。
モチの体は崩れて落ちた。体は死んではいなかった、穏やかに息をしていたから。
だがしかし僕は知ったのだ、モチの魂そっちの方は、確実に生を終えたこと。
僕は地べたに伏して叫んだ。叫んで吠えて泣き続けた。
僕の心は砕けてしまった!
僕の心は砕けてしまった!
僕の心は砕けてしまった!
もう永久に戻らない、全てはかいが無くなった!もう生きる意味も理由も無いと。
明けて翌朝ジュウサンが、詩人の仲間を連れながら、この都の中入城した。ジュウサンは兄とその一党を、制してギルドを制圧し、僕の所へ駆けつけたのだ。
「僕はどうやら遅かったんだね。後一日だけ早ければ…。せめても少し、もう少しだけ、虹金剛を渡しておけば。」
ジュウサンは僕の惨状に、悲しげな顔でそう言った。
僕は全く抜け殻だった。どんな言葉も届かない、深い所に心を落とし、ただ義務的に言葉交した。
「イサヨイ、僕は何が出来るか?何を一体してほしい?君は願いを聞いてくれた、僕らのことも救ってくれた。アリアケ姫はご無事だよ、全ては君のおかげなんだ。せめて君には報いたい。一体僕には何が出来るか?」
ジュウサンは、僕にその様尋ねたのだ。
僕は言った。
「モチの体を無事に故郷へ、帰してやって欲しいんだ。それからイトの引き取り先を、どうか世話してやってくれ…。」
「君自身には何もないのか?何の望みも無いというのか!」
悲し気に聞くジュウサンに、僕ははっきりこう答えた。
「ああ、無いよ。」
それ以上、僕らは何も語らなかった。黙って互いを思いやった。
モチの体が目覚めた時に、僕は再びモチを失う。
彼女の体に宿るのは、見知らぬ娘であることを、全く赤の他人であること、僕は痛くも感じて取った。
モチの表情包んでた、輝かしいほどの輝き、他を圧倒するその空気、それは綺麗に消え失せて、生命力がわずかに強い、ただ凡庸な娘となった。
僕は娘の顔見て泣いた。失ったことの重みに泣いた。泣き崩れながら靴を履かせた、モチの最後の頼みであった。このことだけは成さねばならない。
全く不思議な表情で、娘は僕を眺めていた。彼女は僕を知らないし、僕も彼女を知らないのだった。知りたいとすら思わなかった。知って今更モチではないこと、思い知るそのぐらいなら、全てをジュウサンたちに任せて、僕はひっそり退場しよう。
あの時に、塔から飛び降り死んだのは、アリアケ姫としておくと、ジュウサンがそう言っていた。
サクの死により王子たちは、戦を止めることを誓った。全ての兵を引き上げて、茶(ちゃん)渡(ど)羅(ら)国に平和が戻った。こういう事態を利用するため、覇気に乏しいあの王を、叱咤し脅して決めたという。
前例ないほど壮麗な、国葬がサクのその為に、執り行われるその中で、僕はほとんど逃げるよう、逃げるようなその勢いで、泥安(でいあん)の都後にした。
もう一瞬でもこの地には、いられやしないとそう思った。景色が空が、建物が、木や花や風が僕を責めた。
初冬の厳しい寒さの中を、身を切る風が刺す中を、渓谷ほとんど一気に抜けて、西楼亜琉(ろうある)の中心地区に、僕は再び舞い戻った。
それからは、風にふらふら、雨にしおれて、日差しに惑い、雲に沈んで、僕は流れに流れ続けた。
もう名声や富などは、僕の心を捉えらなかった。酒も女も気晴らしに、気晴らしにすらならなかった。
ただ生き続けるだけだった。息を吐き、そして吸う、ものを食べ、排せつする、ただそれのみを行うだけだ。
僕はひたすら恋の歌だけ、いろんな土地で歌い続けた。もう絶対に歌いでは、戦わないと決めていた。富も名誉もいらぬなら、それでもちっとも不都合はない。
僕は二人を想って歌った、サクと、モチ、二人の大事な僕の愛。
二人を想って歌うことは、僕の心に凄まじい、苦痛と後悔それを与える。それでも歌っている間、二人を間近に感じられた。確かにここで生きていたと、僕の傍ら生きていたのと、この天の下で共に生きたと、そう実感を得られるのだった。
歌いを行う僕の目からは、何時も決まって涙があふれた。それを見て、人々はみな迫真の、歌だと感じて聞き入った。
だがそれすらもどうでもよかった。僕は黙って待っていたのだ、瞬くの間の生が終わって、大きな流れに還る時を。
エピローグ 円環
それから四年、ただ経った。僕にとってはただ経った。他の世間は色々な、事件や戦を過ごしたようだが、この僕の心とらえる様な、出来事は起きることはなかった。僕にとっての人生は、あの時終わっていたのだから。
だが去年、大帝国が押し寄せた。
東の果ての平原から、大帝国が攻め寄せた。仗弦国も架弦国も、茶渡羅国もすべて飲まれる、西紋枢の全ての国が、大戦乱に襲われた。まるで破竹の勢いで、彼の帝国は攻め寄せた。
サクとモチとの命の上に、成った平和は五年と持たず、その戦乱の勢いは、僕のこの身も巻き込んだ。
僕はぼんやり薄れゆく、意識の中で右を見た。
壊れた楽器が転がっている。僕の右手はちぎれてしまった。左の足の感覚もない。
僕が泊まった街の宿屋に、帝国兵が現れて、狼藉の限り尽くしていった。それの結果がこういうことだ。歌いで戦うことない僕の、当然の結果だったのだ。
ぼんやり薄れる意識の中で、僕ははっきり待っていた。待っているのを知っていた。
ああ今だ、今その時が近づいている。
あれは振夢の渓谷で、精霊の死のそのことに、話をしていた時だったろう。
僕は彼女に尋ねて聞いた。
「光が闇に還るなら、君は死んだら闇の精霊、死の精霊になるのかい?」
「そういう説明それも出来るか。でもはっきりとは分からないよ。何しろ死んだらどうなるかなんて、生きてるものには説明できない。」
モチは明るくそう言った。ああありありと、浮かび上がる。あの声、あの髪、あの瞳。
風の匂いと星の光、秋の更け行く渓谷の夜。まだなお水を含んで冷たい、青々しいその草の感触。
僕に希望が残っていたころ。
「僕は死んだらどうなるだろうね?精霊と、別のあの世があるのかな?」
「いいやそいつは一緒だろうさ。いいか、イサヨイ、私たちは、同じ流れに生まれたんだよ。命の源そいつは一緒だ。
木も草も虫も獣も鳥も、全ては一緒の流れから来た。全ては一緒に還るんだ。
案外肉持つ生き物と、我ら精霊それの垣根は、幻なのかもしれないね。距離も、体も、その差異も、見かけだけであるかも知れない。」
モチは夜空を見上げて言った。煌めく渓谷の星空。火がぱちぱちと燃えている。彼女の命も燃えている。モチの丸い頬の端に、赤い光が照り映える。
僕は何だか胸が熱くて、照れを隠してこう言った。
「だったらさ、もしも僕より君が先に、死んでしまって死の精霊に、そういうものになったなら、僕の命を刈り取りに、刈り取りに来てくれるかい?」
モチはなんだか意外そうに、目を丸くしてこう言った。
「いいけどさ。だけど随分不吉な物言い。君は一体どうしたね?精霊が死ぬはよほどのことだよ。この私が、生まれ変わりを成せないと?詩人の君も付いているのに!」
僕はとっても決まりが悪く、言葉を濁して誤魔化した。
「別にどうともしてないよ、喩えの話、喩えの話。」
ああまるで、ついさっきあったことの様。僕の体が冷たい石に、転がり全ての血が抜けて、命の薄れ行くことの、そっちの方がまるで幻。
僕の命は永遠に、あの頃のモチと旅をするのか。そうして僕の半分は、サクと楽しく旅し続ける。
段々と、徐々に意識は薄れゆく。視界もすぐにかすんでいくだろ、痛みももうすぐ感じなくなる。
僕の前、一つの影がぼんやり浮かぶ。ちょうど女性の身の丈の、黒い衣をすっぽりかぶり、泣いてるように見える影。
「ああ来たね、約束憶えていてくれたんだね…。」
ずっと前から知っていた。死とは彼女の顔をしている。僕の命を刈り取るの、彼女でなくてはならないはずだ。
影は黙って微笑んだ。黙って鎌を持ち上げた。
ああそうだ、僕は君へとようやく還る、君たちのいるその場所へ。
「さあ還ろう、君の話した通りの場所へ、僕らは一つへ還るんだろう?僕は君へと還るんだ…、そうだろ?モチ…。」
完
裸足の月
お付き合いいただきましてありがとうございました。内容や文章にスキキライのありそうな作品ではありますが、現時点での自分の持てる力の限りを尽くした作品です。後書きを読んでくださっている方には、浸って読んでいただけたと考えてもいいでしょうか?webに載せるのは初めてですが過去作も大分溜まっているので、これから順次載せていければと考えています。これからも宜しくお願い致します。

