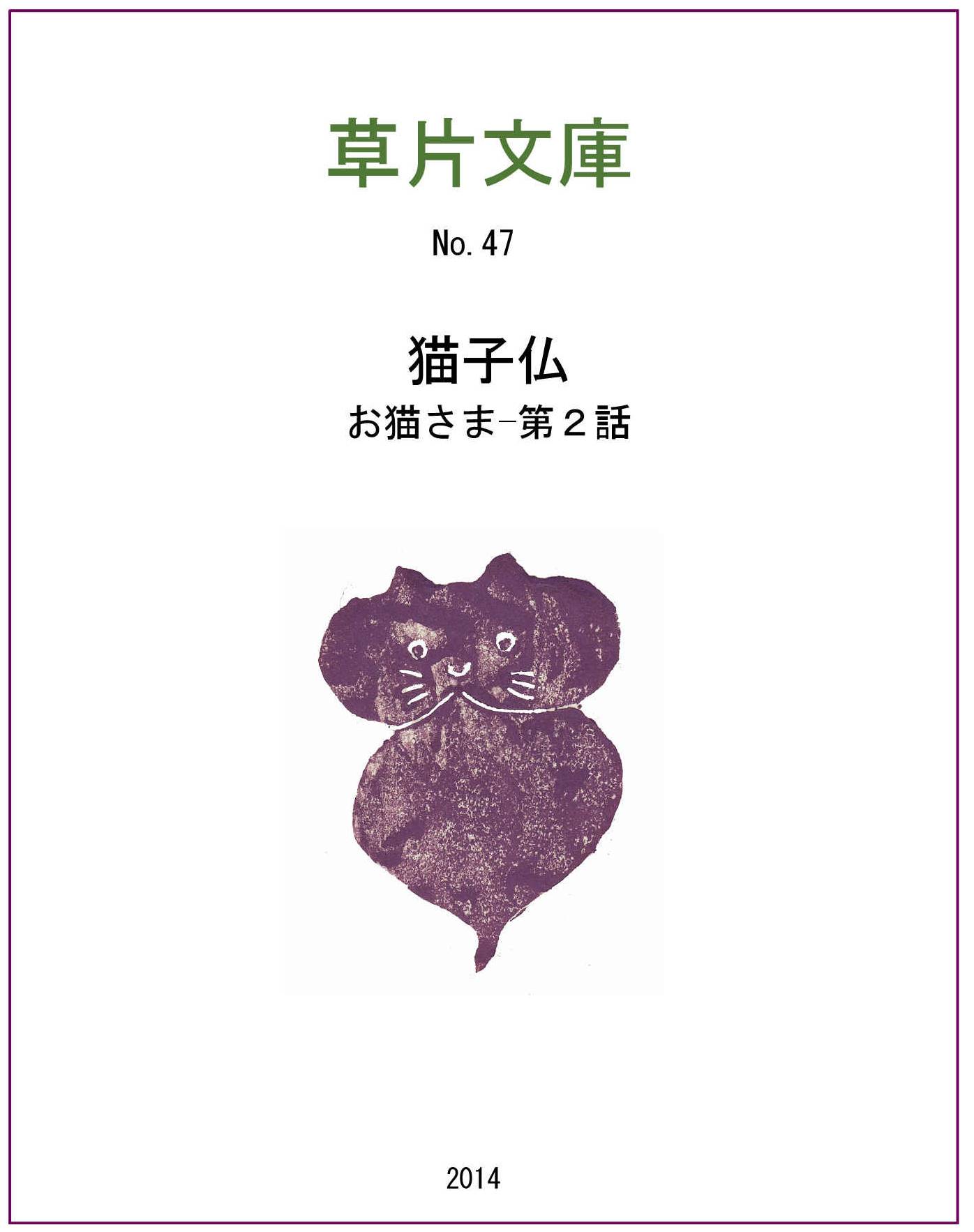
お猫さま 第二話 - 猫子仏
長屋の大家さんといいますと、業突く張りで、金の取立ては厳しいし、店子につらくあたる。逆に人が良くて面倒見がいい、なんて、お話の中にはいろいろ登場いたします。
大家さんは、貸家の持ち主とは限りません。持ち主から頼まれて管理している人で、家主とか、差配人などとも呼ばれまして、そうなるとやはり店子の個人的なことまで相談にのるなど、かなりの教養人や顔の効く人ではないと勤まらなかったようでございます。
深川に通称堀抜け長屋てえのがございます。そこの大家の伊助じいさんってえのはやけにきれい好きで、店子が部屋を掃除をしなかったりしますと、がみがみうるさいうるさい、猫を飼うなどということをしたらそれこそ追い出されてしまいます。
自分の持ち家ということもあったからでしょう、それはもう細かくて、いやな爺と評判でございます。ところがそのわりには、借り手がいるってえのは、江戸の七不思議。
それには理由がございます。伊助じいさんはどこか間抜け。勘定が苦手の上に、忘れっぽいところもありまして、家賃を払っていなくても、おととい払ったといえば、払ったことになることが間々あったようです。
そのようなことから、お堀の近くの抜作大家の長屋といわれ、掘抜け長屋でとおっていたようでございます。細かいところばかりに目がいく人ってのは、大きいところをすぽっと見落とすってことがございますな。
人様はそんな大屋をうまくやり込めることができますが、猫はそうはいかないわけでして、堀抜け長屋の隣の大家の家でこのようなことがありました。
大家の縁の下で子どもを産んじまった三毛猫が大変な目に会ったのです。
みゃおみゃおと猫の赤ん坊が鳴きます。煩い、汚いと、伊助じいさんは縁の下に潜り込むと、親がちょいと餌を探しに離れているすきに、生まれてすぐのまだ目が開いていない子猫を六匹引きずり出しました。しかも、六匹とも川にぼちゃんと放り投げてしまったのです。それを見ていた長屋の子どもが、大家が猫を川に捨てたと触れ回り、誰もが大家の行いを知ったわけでございます。
といっても、またかと言った具合に、周りの大人は相手にいたしません。
大変なのは親猫、自分の子どもがいない、こりゃ猫さらい、誘拐されたと、大声で鳴き歩いた。母猫にとっては一大事どころではありません。すると、猫の子を川に捨てたのを見ていた子どもが、あ、あの子猫の親だということで、ここの大家が子猫を川に捨てたことを母猫に告げ口したというわけでございます。
母猫は大そう悲しみまして、それはもう怒りました。それはそうでしょう、人間だったら、自分の子どもがさらわれて、殺されたら怒るどころではありません。
三毛猫も復讐を企てたのでございます。寝ている伊助じいさんの部屋へソロリソロリと忍び込みまして、顔を思いっきり引っ掻きました。伊助じいさんは飛び起きると三毛猫をふん捕まえ、庭の外に放り投げました。それがまた、打ち所が悪かった。庭石に頭をぶつけた母猫はあっと言う間に昇天しちまいました。
伊助じいさんの顔には五本の爪の痕、血が滲みだしております。もちろん、母猫のなきがらも川に捨てられてしまいました。
伊助じいさんの顔の傷が大分癒えてきたある夜中のことでございます。寝ている部屋に六匹の子猫がびしょぬれになって現れますと、伊助じいさんの胸や顔の上に座ってしまいました。
あー息苦しい。冷たい。そう思った伊助じいさんが目を開けると、六匹の子猫が自分の顔を見下ろしております。
わっと、驚いて飛び起きると、六匹の子猫はすーっと天井の四隅に消えていきました。
子猫の幽霊です。
ああ、いやな夢を見た。目があいた伊助じいさんは、とうとう朝まで寝ることができませんでした。
次の夜も六匹の子猫が出てまいりました。
真夜中のことでございます。真っ黒な子猫が伊助じいさんの鼻の穴を尾っぽでくすぐり、伊助じいさんはくしゃみをして目を開けました。
目の前には子どもの黒猫が浮かんでいます。
見ておりますと、浮かんでいる黒猫の首がすーっと抜け、その首が宙に舞うと、伊助の鼻の上で止まりました。黒猫の首は長い舌をだすと、伊助じいさんの目玉をぺろりと舐めました。
ヒャ、っと、一瞬目をつむり、再び開けますと、天井下の暗がりに他の五匹の子猫があらわれ、首が胴体からすぽっと抜けると、すーっと降りてまいります。
茶虎の猫の首が血を垂らしたまま、伊助のおでこに止まります。三毛猫の首は右のほっぺたに、黒虎の首が左のほっぺたに吸い付いちまう。白とぶちの首は右の眉毛と左の眉毛にくっついたのです。
伊助じいさんはあまりの気味の悪さに目むりましたが、すぐにまぶたが引っ張られ、開いてしまいます。
子猫の首は一斉に大家を見ると、にたりと笑います。伊助じいさんは、体中鳥肌がたち、身動きも出来ない。
子猫の首はいったん舞い上がり、すっとおりてきて、布団の中にもぐりこみ、伊助じいさんの手足にがぶりと噛み付きました。
痛てえ、伊助じいさんは飛び上がり、やっとの思いで布団から転がり出た。
連れ合いのお亀ばあさんの部屋の襖を開けると叫びました。
「助けてくれ」
伊助爺さんが這いつくばって、部屋を覗いたものですから、お亀さんは気味悪くなり、あわてて起き上がると、伊助じいさんの部屋を覗きました。しかし何もおりません。
「爺様、夢を見たのかい」
その声で、伊助じいさんも我に返って、はっとなり、「そのようだ」と言って、また布団に入りました。その夜も朝まで寝ることができませんでした。
次の日も、次の日も子猫の首は宙を舞い、伊助爺さんに噛み付いたのです。
満足に寝ることの出来ない伊助じいさんの頭に大きな円い禿ができました。今でいうストレス性脱毛症でございます。
子猫に呪われた伊助じいさんは、坊主に拝んでもらったり、神主にお払いをしてもらったのですが、一向に効く様子がありません。子猫は毎晩現れます。
今度は頭の天辺が禿げてまいります。
近頃は、夜毎に違った子猫の首が飛んで来て、話しかけるのです。
真っ黒い子猫の首が、血を垂らしながら言うのです。
「大家さん、私の胴体がどこかにいきました。探してください」
茶虎の子猫の首は涙を流しながら言うのです。
「尾っぽがほしい、探してください」
三毛の子猫の顔から、目がぽとりと落ちて、伊助じいさんの目の中に入りました。
「あれ、私の目玉を返して」
黒虎の子猫の首は涎を垂らしながら耳に食いつきます。
「歯が延びてこまるんだ、耳をくれ」
伊助じいさんの耳から血がぽたぽたと滴り落ちます。
真っ白の子猫の首が血で真っ赤に染まって浮いています。
「大家さん、手がないので顔を洗うことができません。顔を洗ってくださいな」
斑の子猫の首が居眠りをしながら、布団の中に入ってくると、伊助じいさんの枕を枕にして眠り始めました。
伊助じいさんの目が虚ろになっていきます。
我慢に我慢していると、どうやら朝日がさしてくる。朝日を浴びると子猫達の首は煙のように消えてしまいます。
ご飯も喉を通らなくなり、どんどん痩せてまいります。
ある夜、布団の中でうごめくものがいるので、伊助じいさんは、掛け布団をはぎました。
「ぎゃあ」
伊助じいさんの声が奥にまで聞こえました。
布団の上には、六匹の首のない子猫の死体が横たわっていました。
伊助じいさんは横になったままとうとう目を開けなくなってしまいました。
頭に大きな禿を作った伊助じいさんが冥土にやってまいります。
閻魔様に、地獄に行くように命じられた。釜茹でなるのではと、びくびくしながら地獄の門をくぐりますと、火も燃えていなければ、針の山もありません。それに鬼も出てきません。そこには自分の長屋がありました。
やれやれと思い、伊助じいさんは長屋の端の家の戸をたたきました。
「だれだい」
出てきたのは、真っ黒い猫でした。
「おや、野良人かい、まっといで」
そう言うと、黒猫は奥から、煮魚の骨を持ってまいります。
「ほれ」
伊助じいさんの前に置きます。
なんということを、伊助爺さんは腹を立て、隣の家の前に来ると、戸が開きました。
真っ白な猫が、焼き魚の骨を大家の前に差し出しました。
伊助じいさんはまた怒って、隣の家にいきました。
戸が開いて、茶虎の猫が現れると、ほらと皿を伊助じいさんの前におきました。皿の上には秋刀魚の頭がありました。
伊助じいさんは隣の家に行きました。
三毛猫が出てきて言いました。
「野良人(ひと)にはもったいないわねえ」
皿の上には生の鰯が乗っています。
伊助じいさんは顔を背けると、隣の家に行きました。
乱暴に戸を開けて黒虎の猫が出てくると、伊助じいさんを、しっ、しと追い払います。
次の家からは、斑の猫が出てくると、追いかけて打とうとするので、伊助じいさんはあわてて逃げました。
行き着いたところは自分の家でした。
水を一滴も飲んでおりません。喉がからからです。伊助じいさんは家の戸を叩きました。
誰も出てきません。
幾度か叩くと、声がしました。
「うるさいねえ、今頃なんだい」
まだ、明るいのにと周りを見ると、夜になっています。
「水を飲ましてくださらんか」
「なんだい、水って言うのは、そんなものはこの世にありゃしないよ」
「そんなことを言わないで、水を飲まねば死んじまいます」
伊助じいさんが懇願すると戸が開きました。
大きな三毛猫が顔を出しました。
「おまえさんかい、あたしがひっかいた傷がまだあるね、とうとうあの世にきたのかい、ここにゃ水はないよ、死んだものに水はいらないさ」
伊助じいさんは喉がひりひりして、苦しくなってきました。
「どこに行けばあるのか教えてくださらんか」
「黄泉の国は、三途の川を渡ったところさね」
「おお、そうだ、三途の川の水が飲みたい」
「子猫たち、つれてってやんなさい」
母猫が言うと、長屋から子猫たちがでてきました。
母猫と子猫たちは伊助じいさんを三途の川の見えるところに連れてきました。
「ほれ、あそこにある」
崖のはるか下の方に、三途の川がみえました。
「こんな高いところから、どうやって行けばいいのかい」
「そうさね、こうやって捨ててやるさ」
親の三毛猫がそう言うと、子猫がみんなして、伊助じいさんの背を押しました。
「うわー」大きな声とともに伊助じいさんが、三途の川に向かって真っ逆さまに落ちていきます。
伊助じいさんは目をつむりたくても閉じることができません。
恐ろしい最後が待っています。川の水が目の前に迫ってくるのが見えました。
あー死ぬーと思って、いや、死んでると思い返し、そのとき、ボチャンと大きな音と共に三途の川に落ちました。
伊助じいさんはぶくぶくと沈んでいって、水が喉に流れ込み、あーこの水はうまいと、思ったとたん、天井板の木目が目に入りました。
生き返ったのか。
みゃーごみゃーごと、子猫の声が聞こえてきす。
「あんた、目が覚めたの、また、野良が子どもを産んじまったよ」
お亀ばあさんの声です。
伊助じいさんは起きあがると、縁の下を覗きました。三毛猫が六匹の子どもにお乳を与えております。
「おい、秋刀魚もってこい」
伊助じいさんはお亀ばあさんを呼びます。
「どうするんだい」
「子どもを産むと栄養がいるんじゃ」
お亀ばあさんが秋刀魚をもってくると、伊助じいさんの顔をしげしげと見て言いました。
「おまえさん、いつの間にか禿が治ってるじゃないか」
伊助じいさんは自分の頭に手をやると、禿げていたところに毛が生えたのを知りました。
母猫のそばに、秋刀魚を置くと言ったのです。
「あたしゃ目が覚めた、お前さんたちに毎日餌をやりますよ」
「あんな猫嫌いが、どうしちゃったのさ」
お亀ばあさんは不思議そうな顔をしています。
伊助じいさんがしみじみと言いました。
「あたしは、一度仏になった、これからもずーっと仏だよ」
こうして、伊助じいさんは、野良猫をかわいがるようになり、仏の大家と呼ばれるようになったのでございます。
掘抜け長屋は猫仏長屋と呼ばれるようになりました。
お猫さま 第二話 - 猫子仏
私家版 猫小噺集「お猫さま 2017 一粒書房」所収
お猫さま:2017年度、第20回日本自費出版文化賞、小説部門賞受賞
木版画:著者


