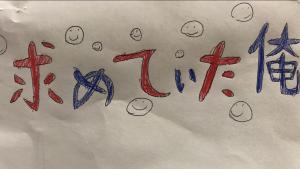求めていた俺 sequel
第三部 「黒崎寛也編」
十三話 強さを求める理由
✳︎ ✳︎ ✳︎
『ここがお前の新しい住まいだキリュウ。』
キリュウと祠堂が出会って一週間。祠堂がキリュウを連れてきたのは、アジトから車で約二時間移動したところにある、『川東市』という街に位置する、至って普通のアパートだった。祠堂とキリュウは階段を上って二階106号室の扉の前までやってきた。
『ここが俺の・・新居?』
『そうだ。俺達だってお前一人をいつまでも面倒見きれるほど楽な仕事はしてねーんだからな。』
ピンポーン・・
祠堂は106号室のインターホンを鳴らす。
ガチャ・・
『はーい・・ああ、祠堂さん』
出てきたのは30代後半くらいのの男性だった。祠堂よりも遥かに年上である。
『久しぶりだな、悟(サトル)。悪りぃ、しばらくの間このガキの世話をお願いしたいんだがいいか?』
ほら挨拶しろ、と祠堂はキリュウの背中を押す。
『こ、こんにちは!!』
『はっはっは。中々かわいい男の子ですな!
ウチの子もちょうど弟が欲しいってねだっていたところですぞ』
悟と名乗る男性は見知らぬ幼児キリュウを歓迎し、彼の扶養を躊躇なく容認した。
『キリュウ。これを渡しておく。』
祠堂はポケットから携帯電話を取り出しキリュウに手渡した。
『次にお前に会って仕事を任せるときはお前が今よりずっと戦闘能力を高めた時だ。』
『じゃあ・・』
『ああ。しばらくはお別れだ。 大丈夫だ。悟は日本一有名な武道家である『瓜生』の系譜を継ぐ者だ。強くなったお前に会えるのを楽しみに待ってるぜ。 そのケータイは何かあった時用に持っておけ。じゃあな』
そう言って祠堂は二階のマンションから飛び降り、タタタタッと壁を垂直に駆けおりて行った。
『いつか俺もあんな風になれるのかな・・』
壁を駆け抜ける祠堂の背中を眺めながらキリュウは武道家『瓜生悟』に訊ねた。
『君しだいさ』
瓜生悟はにっこりと笑い、答えた。
『ささ、中にお入りなさい』
悟はキリュウを小さな部屋に案内する。
『父さん、この子誰?』
小学生くらいの少年がゲーム機を片手にキリュウを指差して訊ねた。
『忠、今日からこの子はしばらくうちの居候だよ。キリュウくんって言うんだ。仲良くしてやってくれ』
『やったぁ!父さん、俺にも弟ができるんだね!!』
『あくまでこの子は居候だぞ。・・でもまぁお前が満足ならそういうことでいっか』
こうして武道家の息子・瓜生忠はキリュウに手を差し出しこう言った。
『よろしくな、キリュウ』
『う、うん』
差し出された手を小さな手で握るキリュウ。
この時、キリュウと瓜生忠という名の少年は義理の兄弟となった。
瓜生忠の父である瓜生悟と祠堂とはどんな間柄なのか訊ねると、”ただの古い友人関係“との事だった。ますます祠堂という男が分からなくなった。
こうして、瓜生悟の指導のもと、武者修行に明け暮れる日々が続き・・・
早い事にキリュウは14才になっていた。年齢だけでなく、「経験」も重ねた彼はもはや幼い頃とは比べ物にならないくらい武術に長けていた。 義理兄の瓜生忠との絆も日を重ねるごとに深まっていった。
そんなある日のこと。キリュウの電話に祠堂から久々の着信が届いた。
『キリュウ。久しぶりだな。どうだ?実際に戦場に出れるくらいには成長したか?』
キリュウはこう返事をした。
『まぁ・・それなりにはな』
『ほぅ、お前声変わりしたな。風格が変わったように見えるぜ。 さて、本題に入るが一週間後に異能犯罪組織 ”メイプル“ のアジトに乗り込み組織を壊滅させろという内容の依頼が入った。お前にはその仕事に当たってもらう。だがその前にウォーミングアップだ。明日、俺のアジトの地下にある大広間に来い。俺の手下ども数名をお前と戦わせる。そこで強さを証明して見せろ。』
・・との事だった。
翌日。祠堂に言われた通り、瓜生父は車でキリュウを少し離れたアジトまで連れて来た。
そして、約束の地下大広間にやってきた。壁は一面真っ白に塗装されて何の装飾もされておらず、窓の一つも見当たらない。あるのは
キリュウを囲む20人の武装した戦闘員のみだった。
どこからかアナウンスが聞こえた。
『久しぶりだなキリュウ。早速だがお前の強さ、試させてもらうぞ。ああ、それとお前にはコイツを支給する。』
祠堂の声だった。
アナウンスが終了すると同時だった。ちょうどキリュウの足元。ウィーン・・という機械音とともに真っ白な床がパカリと開き、顔を守る防具と忍者が使っているような、手に嵌めて敵を引き裂く手甲鉤(てっこうかぎ)が床下から現れた。コレを使って戦え、という事か。
『そんじゃテストを始める!』
祠堂の号令と同時に20人もの戦闘員達が一斉にキリュウに襲いかかる。
キリュウは防具を纏い、両手に手甲鉤を装着し、敵に備える。
『う、うおお!!』
自分でもにわかに信じ難い速度だった。ブォッ、という風切り音が響くと同時にキリュウの手は戦闘員20人全員の脇腹に深い引っ掻き傷を刻み込んでいた。
『うぐぉおお!?』
戦闘員達が脇腹を抱え、痛みに悶える。
『テスト終了だ。お疲れさん』
祠堂のアナウンスが流れた。これ以上キリュウに暴れさせると流石に戦闘員達の命が危ないと判断したのだろう。
『祠堂、俺は約束通り強くなった。コレで満足か?』
キリュウはアナウンスのスピーカーに向かってその場にいない祠堂に訊ねた。
『ああ、充分だ。これならお前も一週間後の
“メイプル” 掃討作戦にも投入できる。』
『(これでやっとアイツに助けてもらった借りが返せる)』
キリュウは装備を外し、そのまま試験場を去った。 来週はいよいよ ”実践“だ。今回のような模擬戦とはワケが違う。命のやり取りをするのだ。
・・こうして早いこと時は流れ、”メイプル“ 戦当日がやってきた。案の定、瓜生家で積んだ鍛錬の成果が見事に発揮され、決着はほんの30分程度で着いてしまった。 キリュウは恐るべき速度で成長していった。 しかし一方で、数多の屍(しかばね)を積み上げていくうちに感覚が麻痺していき、“メイプル”戦から2ヶ月経った頃にはもはや手を血で染めることにも抵抗は無くなった。 “自分のやっている事は本当に正しい事なのか?” 当初はそんな疑問が頭の中でウヨウヨ漂っていた。 だが祠堂と行動を共にする内に ” マグナムもメイプルも、世界に混沌をもたらし、人々の平和を脅かす異能者(ガイチュウ)だ。殺したって誰も悲しまないんだ。寧ろ喜ばれるものだ“ と
自分の中で割り切るようになっていた。
”自分のしている事は世界にとってプラスであり正しい事だ“ と。
ー そう、 少なくとも祠堂に真実を告げられるあの瞬間までは。
いつものように、仕事を終えた後の事だった。その日祠堂やキリュウ達はとある町の離れにある小さな村を強襲した。この村の村人達は全員、特殊な力を持っていただけで一般社会から迫害されてきた哀れな者たちだった。つまり彼らも”能力者“ なのである。 幼年の者から年寄りまで、老若男女あらゆる年代の人間が ”能力者だけでも平和に生きる事ができるようにする“ という共通目標を抱えて結束し、集落を作っていった。 それらが次第に拡大していき一つの村として成立したのだ。 今回祠堂とキリュウはそんな彼らに目をつけた。
キリュウはまるでルーチンワークであるかのように集落を破壊し、逃げ惑う村人達を蹂躙していった。
そして残る最後の村人の息の根を止めた。
「祠堂、確か今日はこの村で終わりだったよな?」
キリュウは暑苦しい防具を脱ぎ捨て、両手の武器を外す。
「ああお疲れさん。これ、報酬だ。」
祠堂は報酬が入った袋を投げて桐生に手渡した。
『こんだけか・・』
キリュウはあまりの報酬の少なさに辟易していた。 少ないといっても、金額面だけで見れば普通のサラリーマンよりも高い報酬で、生活をする分にも支障はなかったが、わざわざ人を殺して得た金という点ではイマイチ腑に落ちない所もあった。
祠堂が言った。
『贅沢言うな、次の村を滅ぼせばさらに報酬が上がるぞ。』
キリュウは祠堂に対してずっと抱いていた疑問をぶつけることにした。
『・・・なあ、今更だけど本当にこんな仕事意味あるのか? 能力者なんて今じゃ星の数ほどいるから一人一人しらみ潰しに消していったら拉致があかないんじゃないか?』
『この世界に意味のない事なんて存在しないさ。実際に戦地に赴き戦闘経験を重ねれば重ねるほどお前は強くなり、作業効率も上がる。作業効率が上がればより多くの人々を異能者から守れる。一石二鳥だろう』
ああそうか。もはやこの人にとって、能力者を殺す事はあくまで“作業” の感覚なんだな。
キリュウは心の中でそう呟いた。そして。まるでその内心を見透かすかのように祠堂は一言を放った。
『 ・・でもまぁお前の言う通り、いちいち一人一人相手にしてたらキリがないのも頷けるな。 出来る事なら “この世から全ての人間から異能を取り去る力” なんてものが有れば便利なのになぁ。例えばそう、 お前の身体の中に眠る ” 黒い炎 “ みたいなものが・・』
『え・・・』
いや待て、 この男は一体何の話をしているんだ?
『 ・・ところでキリュウ。俺は丁度一週間前、 とある2人の強力な異能者を殺した。』
突然話題を転換する祠堂に少年キリュウは困惑していた。
『 それが・・どうしたんだ?』
キリュウはとりあえず耳を傾けることにした。
『 男と女の異能者で、2人は夫婦だった。 しかも彼らは俺達異能力者殲滅部隊 “清掃員” 上層部の人間だった。』
『なに?』
『 異能力者を忌み嫌う組織の幹部でありながら、秘密裏に違法な異能力開発機関に対して資金援助をしていた事が発覚したんだ。』
キリュウの眉が一瞬ピクリと動いた。
祠堂はやっと気づいたかとでも言うような顔でキリュウの顔を見た。
『 ・・そういえば俺達が所属する“ 清掃員 “にも異能力者はいたよな。』
指先から細い糸を繰り出す能力者、酒井。
気温を操る能力者、八坂。
引力を操る能力者、砂沢。
そうだ。他にも異能を持った仲間達はいたはずだ。
矛盾していないか? 祠堂は全ての異能力者を根絶させることが目的のはずだ。異能力者を殺すために異能力者を雇っていたと言うのか?
だがそんな疑問を抱く理由はどこにもなかった事を、祠堂の次の言葉で思い知った。
『 ああ、だから俺が全員殺しといたよ。酒井や八坂も、幹部の”神田トウジ“と”神田鈴華”の夫婦も。この世から異能力を根絶させる。それが俺の最終目標である事には変わりない。』
かつて、”神田シンジ“と言うやんちゃな少年がいた。その両親は、仕事の都合で長い間シンジと顔を合わせることが出来なかった。物心ついた時には死んでいると思っていた。
だが違った。目の前の男が今挙げた2人の名前をみすみす聴き逃すわけにはいかなかった。
『・・祠堂。お前とは少しじっくり話をしたいな・・。』
キリュウの頭の中でプツリ、プツリと。なにか糸のようなものが一本ずつ切れる音がするのを感じた。
2人は今まで並んで話をしながらしばらく道を歩いていた。祠堂はちょうど道端に横長のベンチがあるのを見つけたので、そこにゆっくり腰掛けた。そしてまた一言放った。
『昔話をしようか。昔々あるところに、1人の若い女性がいた。彼女はとある異能力を持った能力者だった。それは ”他人の死相を見る事ができる“ 能力で、小学生の頃、その忌々しい能力のお陰で友達も先生も次第に彼女から離れていき・・・、しまいには彼女の居場所はどこにも無くなってしまったそうだ。 そして彼女は金輪際能力を使用するのを避ける事を決意し、孤独な人生を歩んで行った。そして人と接するのが元々好きだった彼女は辛い孤独から抜け出すために、大学卒業後、ある職業に就く事にした。それは保育園の先生だ。両親にさえ見捨てられ、自分と同年齢の人間からも相手にされなかった彼女は、自分よりも遥か歳下の無邪気な子供達と触れ合う事ができるその仕事に幸福を感じていた。』
ブルブルと、キリュウは全身が小刻みに震えている事に気付いた。
『 ・・当時 “清掃員” の一員だった俺は、彼女の異能力に目をつけ、手下を送り彼女を瀕死状態に持ちこませた。彼女をあえて殺さなかったのには理由があった。それは後に俺の計画に役立ってもらう予定だったからな。さて、キリュウ。お前なら知ってるんじゃないか?哀れな彼女を殺しかけた俺の手下の顔や特徴を。』
まるで、最初から分かっていたように。
この事実を話す事を用意していたように。
白髪の男、祠堂は好物の飴玉を口の中で転がしながら平然と訊ねた。
『そいつはピエロのような外見をしていなかったか?』
プツン、と。少年キリュウの頭の中で最後の糸が切れた。
『・・・テメェだったのか・・・?あん時・・笹原真弓を誘拐するよう仕向けたのも・・・ ”俺”の父さんと母さんを殺したのも・・・全部全部全部テメェの仕業だったのかぁあああああああああッッッ!!!!!!!』
キリュウは手甲鉤を片手に装着し、気が付いたら目の前でベンチに腰掛けている男に襲いかかっていた。
祠堂は今油断している。やるなら今しかない。
『うぉおおおおあああああ!!』
咆哮とともに、手甲鉤は凄まじい速度でベンチを粉々に切り刻み、粉砕していた。だが肝心の標的である祠堂は既にその場にはいなかった。 直前に大きく跳躍し、回避されたのだ。
『まずいッッ』
キリュウは振り返ろうとするも後の祭りだった。背後に素早く回り込んだ祠堂の手刀が彼の頸椎をとらえていた。
『ぐぁッ・・・墜ち・・・る・・・』
クラッ・・
意識が吹き飛ぶのをキリュウは感じた。
✳︎ ✳︎ ✳︎
「あの後、俺がどうなったのかは何故か思い出せない。だがはっきりしている事は俺は今生きている事と、そして祠堂(アイツ)に生かされている事だ。」
桐生は覚えている限りの過去を打ち明けた。
復讐だけに人生を賭ける事を誓った、自分と似通った境遇の少年、黒崎寛也に。
「何となく、分かったんだ。怒りや憎しみだけに任せて戦ったって結局誰1人守れやしないんだってな。確かに、大切な人を失うのは辛い。だからこそ今まで出会った人達を、自分を支えてくれた身の回りの人達を大切にしなきゃいけないんだ。だから寛也。そのためにお前自身が強くならなきゃいけないんだ。」
この一言は黒崎寛也に伝える教訓というよりも、寧ろ桐生の心の中にずっと巣食っていた蟠(わだかま)りを解くための自分自身に対する言い聞かせであった。
「強くなりたいと願う事は素晴らしい事だ。でも、お前はまだ半人前だし俺よりもずっと若い。だから俺としてもお前に道を誤って欲しくはない。自分を見失って欲しくない。それでもお前が、お前自身と向き合う覚悟があるっていうのなら俺は出来る限り全力でお前をサポートしてあげたい。 さぁ、黒崎寛也。お前は ”どうなりたい “ ? 」
求めていた俺 sequel