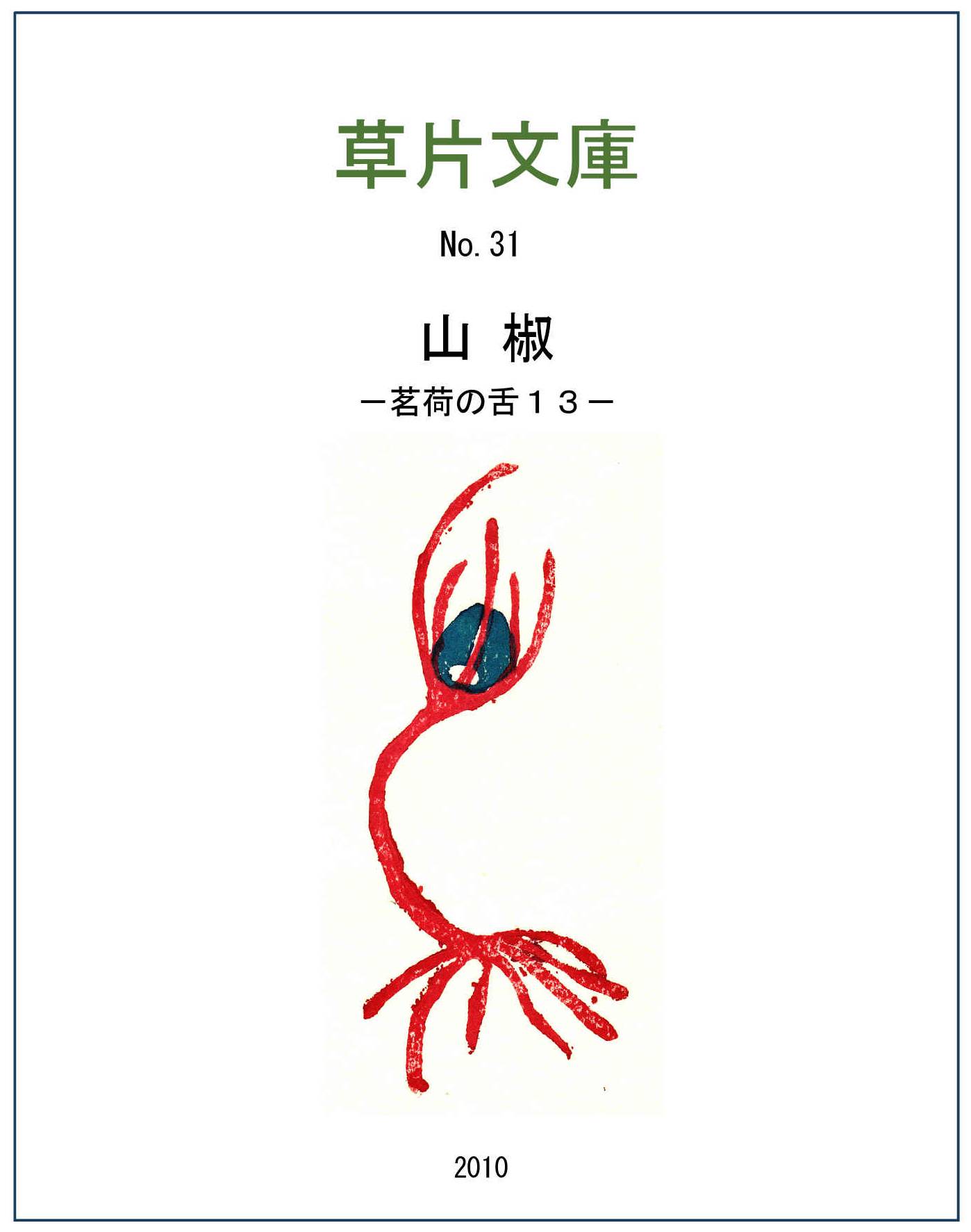
山椒 - 茗荷の舌13
子狸の摩訶不思議なお話。
玄関を開けると目にまぶしいほどの青い空が広がった。何本もの筋になった薄い雲が流れている。秋晴れの気持ちのよい天気となった。
今日は円美(まるみ)ちゃんを東京見物に連れて行くことになっている。
多摩子さんと円美ちゃんの二人と京王線新宿駅西口改札口で朝九時に待ち合わせだ。
南平の駅まで歩いていく途中に庭がとってもきれいな家がある。
鉄柵でできている塀の脇に大きな山椒の木があった。チラッと見ると一本の枝が丸坊主になっている。おやおやと見ると隣の枝の葉の上に茶色の芋虫がいる。ぼちぼちとげとげしていて、『ナウシカ』のオームの目のようないぼいぼが頭のところにならんでいる。白い襟巻きをしたような模様もついている。隣の葉を見ると、大きな緑色の芋虫が葉っぱをすごい勢いで食べている。膨らんだ頭の脇には目のような黒い模様があり、もこもこした足の付け根に白い模様がある。頭にはアルファベットのようなものも見える。どちらも揚羽の幼虫だ。弟と兄だろう。見ていると揚羽の幼虫たちはもしょもしょと、すごい勢いで山椒の葉を食べている。面白いくらいに枝から葉っぱがなくなっていく。秋の中ごろにもかかわらず、揚羽の幼虫がいるのはどうも不思議である。ずいぶん遅い生まれだ。
芋虫のお食事を飽きずに見ていたら電車に乗り遅れた。新宿に着いたのが九時を三十分も過ぎてしまった。電車から降りて走るように改札口に急いだ。ところが、まだ円美ちゃんたちも来ていなかった。
それから待つこと二十分、JRのほうから急ぐ様子もなく、真っ赤なスカートをはいた円美ちゃんと青い和服のようなドレスをきた多摩子さんが、にーこにこして話しながら僕の待つ改札口にやってきた。
「ごめんなさーい、芋虫見てたら遅くなっちゃった」
多摩子さんが言った。
「多摩子さんの家の庭にね、こーんな大きな芋虫が」
円美ちゃんが大きく手を広げた。大げさな子である。三十センチメートルもある芋虫がいたら大変だ。
「ほんとうよ」
多摩子さんがひゃっと驚く僕を見て円美ちゃんを擁護した。
「しかも、真っ赤なの、お日様のような芋虫よ。きっと真っ赤な蝶々になるのよ」
モスラじゃあるまいし。
「ははは、うそ、うちの山椒についていた揚羽の幼虫、かわいいのよ、こんなに秋遅くになったのに一生懸命葉っぱを食べてるの」
なーんだ同じじゃないか、でも言わなかった。ということで、やっと会えた。
「どこに行きましょうか」と僕が聞くと、
円美ちゃんが
「東京の五色不動にいきたい」
と言った。
はて、それはなんだろう。
「あたし、東京に来たら是非行ってみたいと思ってたの、五色不動って」
「僕は行った事がないんだけど、多摩子さん知ってる」
「わたしも知らないのよ、五色そうめんなら知っているけど」
多摩子さんが教えたのかと思っていたのだが違った。
「どうして行きたいの」と聞くと、円美ちゃんは、
「アンチミステリーを読んでいたら出てきたの」と大きな目をくりくりさせた。
不思議な本を読む子である。中井英夫の「虚無への供物」に五色不動がでてくるそうである。多摩子さんは読んだことがないという。僕もまだない。中井英夫の「とらんぷ譚」は読んだけど、「虚無への供物」は読んでない。是非読んでみたい本の一つではある。円美ちゃんはもう読んだのだ。
「東京には目白不動、目黒不動、目赤不動、目青不動、目黄不動があるの。江戸城を守るためのお不動さんなんだって」
目白や目黒は場所は分かるけど、目赤、目青、目黄という場所は知らない。
「へー、面白そうだな、でも一日でいけるのかな」
円美ちゃんは地図まで持っていた。現在の五色不動は世田谷区、江戸川区、文京区、豊島区、目黒区にわたってあった。目黄不動は複数の不動があって台東区にもある。となると、どのように回ろうか。円美ちゃんは目青に行きたいと言った。ということで最初に世田谷三軒茶屋の目青不動に行くことにした。
京王線に乗り下高井戸に出て東急世田谷線で三軒茶屋に行った。渋谷周りの方が近かったかもしれないが世田谷線が好きなのだ。
三軒茶屋の駅を出てちょっと歩くと目青不動である最勝寺教学院の参道があり、すぐにゆったりとした不動堂にたどりついた。銀杏の木が高くそびえている。
円美ちゃんは、これ縁結びの神様なのと手を合わせ、
「御縁がありますように」と拝んだ。
「でもこのお不動さん青くない」
円美ちゃんが言うと、黄色くなった銀杏の葉が一斉に緑色になって、枝にふさふさと青い実が生った。
驚いていると、木の枝がわさわさと動いて、青い実が次々と頭上に降ってきた。
円美ちゃんはびっくり、多摩子さんは大はしゃぎ。
二人して青い実を拾って、
「染色に使えるかもしれないものね」と袋に詰め込んでいる。
境内一面が青い実で敷き詰められ、お不動さんの目にも実が当たった。
「あ、目が青くなった」
円美ちゃんが叫んで、
「ありがとうございます、もごもごもご」とまた手を合わせた。
目黄不動の一つは江戸川区の平井にある。三軒茶屋から渋谷に出て地下鉄半蔵門線で錦糸町に出ると総武線に乗りかえ、二駅いって平井でおりた。商店街を二十分ほど歩いて、目黄不動のある最勝寺の不動堂についた。
円美ちゃんは、
「むかし、街道を守っていたのよこのお不動は、だから車の安全ね、フィガロ守って頂戴」と拝んだ。ちょっと目的が違うかもしれない。
「やっぱり、このお不動さんも黄色くないのね」
円美ちゃんが言うと、またしても、不動堂の脇の松の木が、ガチャガチャと音を立てて揺れた。松ぼっくりがたくさん降り注いだ。円美ちゃんの頭にぽこっと当たった。
円美ちゃんは、松ぼっくりを拾うと、「松の種はおいしいのよね」と松ぼっくをぽりっとわってしまい、中から黄色の種を取り出し食べた。ほんとよと多摩子さんも食べている。松ぼっくりは次から次へと落ちてきて、みんなはぜて中の黄色の種があらわれた。あたり一面黄色になり、お不動さんの目が黄色になった。
「あ、お不動さんが黄色になった」
円美ちゃんは、もう一度手を合わせると、口の中で何かもごもご言った。
ままよ、幸せなもんだと、次の不動に行くことにした。
今度は目赤不動に行こうと円美ちゃんは言った。南谷寺(なんこくじ)は地下鉄南北線の本駒込駅を降りるとすぐのところにあった。根津神社や多くのお寺が近くにある。
円美ちゃんは不動堂の前で、
「みな幸せでありますように」と祈った。
そのとき、どこからか一羽の鷹がとんできて、円美ちゃんの白い、少し太い腕に止まった。くちばしには赤い実が咥えられていた。円美ちゃんはにこっとほほえみ、鷹から赤い実を奪うと食べてしまった。多摩子さんがびっくりしている。
鷹もびっくり、飛び上がると、ふたたび、どこからともなく赤い実をくわえてきた。
「あら、わたし間違えたみたい、ごめんなさい」
円美ちゃんが鷹に謝っている。食べちゃったからだ。
円美ちゃんは赤い実を受け取ると、「えい」とお不動さんの目にぶつけた。片目が赤くなった。鷹はまた赤い実をくわえてきた。円美ちゃんはその実もお不動さんにぶつけた。両目が赤くなった。
「お不動様、もごもごもご」
と円美ちゃんは呪文のように祈った。円美ちゃんはそ知らぬ顔で、そのまま次に行こうとうながした。
何の実だったのだろう。南天の実だったかもしれない。
山手線に乗り換えて目白駅で降りた。かなり歩くが、慈眼寺の目白不動尊に行った。
霊験あらたかな目白不動に手を合わせると、多摩子さんは来年も面白い染色ができますようにとお願いした。円美ちゃんはおいしいお米が食べられますようにと手を合わせた。
早稲田のほうから稲穂が空を飛んで、我々の頭の上にくると、白いお米だけがぱらぱらと降ってきた。多摩子さんはハンカチを広げて受けている。円美ちゃんはブラウスの襟元を広げて胸の中に受けている。なんか恥ずかしい。後でどうするのだろう。境内は真っ白になってしまった。しかし天からたくさんの緑色の雀が舞い降りて、これまた、境内を埋め尽くした。白い米はあっという間になくなり、我々が受けた米も雀たちにあげてしまった。雀はどこかに飛び去った。
お不動さんの目だけが白くなっている。
「変ねー」
多摩子さんは、空を見上げている。
「あの雀、鳴かなかったわね」
円美ちゃんは、「目白だったのよあれ」とわけのわからないことを言って納得している。目白がお米を食べるだろうか。
ここでも、円美ちゃんは「もごもご」言って手を合わせた。
さてそのようなことで、最後の目黒不動に向かったのだ。山手線で目黒駅に下りて、歩くこと二十分、五色不動最後の瀧泉寺についた。石段をのぼって境内に入り、不動堂でお参りをした。
円美ちゃんは手を合わせると、「世の中平和になりますように」と拝んだ。
鳩が二羽飛んできた。烏賊をくわえている。なんなんだと見ていると、烏賊がシューと墨を吐いた。お不動さんの目に当たり、真っ黒になった。
円美ちゃんが、「もっともっと」と叫んだ。
烏賊はシュウシュウ言いながら墨を吐き散らした。墨は空気中を漂い、境内の中が薄暗くなってきた。
円美ちゃんが手を大きく広げた。
「青、黄、赤、白、黒の不動様、結界」と大きな声で叫んだ。
多摩子さんもあっけにとられている。この先何が起こるのだろう。
円美ちゃんがこっちを向いた。
にこにこと「さーかえりましょ」と、多摩子さんに言っている。
意外と早く五色不動を回ることができたし、お腹もすいてきた。もうお昼をだいぶ回っている。
仁王門を出ると、門前の店のお茶漬け屋の看板が目に入った。
店の前でしわくちゃのおばあさんが前掛けをかけ直している。
「茶漬けを食べましょう」提案すると、円美ちゃんも多摩子さんも大賛成、中に入って、思い思いの茶漬けを頼んだ。
円美ちゃんは昆布と山椒の実と葉の佃煮「芽煮」の茶漬け、多摩子さんはちりめん山椒の茶漬け、僕は三重の有田町で取れた葡萄山椒の実、山椒佃煮茶漬けにした。
おばあさんは注文を聞くと奥にはいって、めに、ちりめんに、みさんしょうと厨房に声をかけた。
しばらくすると、茶漬け、添え物の梅山椒が出てきた。
一口すする、なかなかおいしい。
するする食べられてしまう。
もう一杯御代わりが欲しいほどだ。
あっという間に食べてしまった。
「そろそろねえ」食べ終わった円美ちゃんが言った。
「なにが」円美ちゃんにはなんだか隠し事があるようだ。
多摩子さんも食べ終わった。
「目黒を散歩しましょう」と円美ちゃんがさっさと歩き出した。
「そうね、ちょっと歩きましょう」多摩子さんも歩き出した。
お昼を食べると眠くなる僕とは違って二人とも元気である。
古い住宅街の路地を歩いて行くと、秋刀魚の匂いがしてきた。
「目黒の秋刀魚ねー」
円美ちゃんが食べたそうだ。
家々の間をぶらぶらと歩いていくと、小高い丘の上に小さな神社があった。
「ここだわ」
円美ちゃんが石段を見上げた。、鳥居に目無し不動と書いてある。秋刀魚の匂いは石段の上から漂ってくる。
こんなお不動さん聞いたことがない。五色不動の後は目無し不動だ。
「登ってみましょう」
多摩子さんが石段を登りだした。秋刀魚の匂いが強くなる。
そんなに高いところではないのであっという間に境内に入った。
高い杉の木に囲まれて、小さな社があった。
境内の石畳の脇で、太った小父さんが丸椅子に腰掛けている。秋刀魚の匂いはそこから漂ってくる。焼いた秋刀魚を売っているのだろうか。
小父さんの後ろには大きな水槽が置いてあり、秋刀魚が元気良く泳いでいた。
前には焼いた秋刀魚が新聞紙の上に乗せてあった。
やっぱり秋刀魚屋か。
大き目の七輪の上には網が載せられ、青い火がぼうぼうとたかれている。
小父さんが境内に入った我々に言った。
「青、黄、赤、白、黒と順に回ると結界を作れるのじゃよ」
円美ちゃんが白い顔にえくぼを寄せて聞いた。
「どちらからいらしたの」
小父さんは目を細めると、
岡山湯原温泉からきたのじゃよ」と円美ちゃんに返事をした。
「お前さんかな、結界を作ったのは」
円美ちゃんが頷いた。
「この結界は小さいのう、はじめてじゃろう」
円美ちゃんがまた頷いた。
何の話をしているのだろう。多摩子さんも不思議そうに見ている。
「わしは結界ができるとそこに店を出すのじゃよ、祭りの屋台のようなもんじゃ、しかし、最近は結界を作ることができるのがおらんで、年に数回になってしまった」
小父さんは焼いて並べてある秋刀魚を一匹、七輪の金網の上にのせ、山椒をかけた。
じゅうという音がして秋刀魚の匂いが強くなった。
焼き返しているのだろうか。
見ていると、秋刀魚は網の上で反り返り、今度は反対側に反り返った。何度か反り返りを繰り返すと、秋刀魚の色が青っぽくなり、やがてぴくぴくと動き出した。
「ほりゃできた」
小父さんは、秋刀魚をつかみあげると水槽にポチャリと投げ入れた。秋刀魚はすいと泳いで、中で泳いでいる秋刀魚たちの群れに入った。
「この秋刀魚は目黒の街の魚屋で、焼いて売ってるのを買ってきたのじゃ」
小父さんはまた焼いた魚を七輪の上にのせ山椒をかけた。同じように、ぴくぴくと反り返り秋刀魚は生き返った。
多摩子さんと僕はびっくりしていて言葉も出なかった。
小父さんは別の包みから、大きな金目の干物を取り出して、七輪の上に載せ、山椒をふりかけた。開きになっていた金目鯛は、ぱったと閉じ合わさると、目をぎょろつかせ、ぱたりぱたりと生き返った。小父さんは秋刀魚の入った水槽に金目を放り込んだ。金目鯛はゆるりと水の中で泳ぎ始めた。
多摩子さんが我に返った。
「何でも生き返らすことができるの」
「ああ」小父さんは当たり前のように答えた。
多摩子さんは木の下から干からびたカナブンを拾ってきた。
小父さんは黙ってカナブンを網に乗せ山椒を振りかけた。ひっくり返っていたカナブンは足をばたばたさせ、やがてくるっと回って、ブーンと飛んで行ってしまった。
「人も大丈夫」
「ああ」
「おばさんお小遣いたくさんくれたから生き返らせてもらおうかな」
円美ちゃんがそう言うと、小父さんは笑った。
「骨か皮があるならできるさ、さて、この結界はもうすぐ消えるから、わしは帰らないとな」
「その前にお願い」
円美ちゃんがポケットからなにやら取り出した。
「かわいがっていたのが死んじゃったの」
「そりゃかわいそうに、どれ」
円美ちゃんの手の平の上では、首と体がばらばらの四足動物が死んでいた。
小父さんはそれを円美ちゃんから受け取ると、七輪の網の上に載せ山椒をふった。
頭がするすると動いて胴体にくっついた。手足がピクリと動いた。首を持ち上げて目を覚まし、ぴょんと跳ね、差し出す円美ちゃんの手の平に戻った。
守宮の子どもだ。
「生き返った」
円美ちゃんは嬉しそうだ。でも変な趣味だ。
「私の友達なの、戸に挟まれて切れてつぶれちゃったの」
「そりゃ、良かった、それで結界を作ることを学んだのだな」
円美ちゃんは頷いた。
小父さんは笑顔で、「またやってごらん」と言った。
「なぜ山椒をかけるの」
円美ちゃんが聞いた。
「山椒にはサンショオールといってな、すごい毒があるのだよ。毒は薬にもなる」
そう言ったとたん、小父さんがもやもやとぼやけはじめた。結界が解け始めたのだ。あたりに山椒の匂いが立ち込めると、小父さんは大きな山椒魚になった。
山椒魚は「はんざき」とも言われ、半分に裂けても生きていることのできる妖怪でもある。
境内の入り口にある電柱に電気が点いた。
「帰ろう」
我々が目無し地蔵の鳥居をくぐると、境内にはもう誰もいなくなった。
いつの間にやら、外は夕暮れになっていた。
円美ちゃんの肩には守宮の子どもがかじりついている。
多摩子さんもぼーっとしている。
二人は鎌倉の多摩子さんの家に戻る。明日、円美ちゃんは赤いフィガロで谷川の九茶路子さんのところに帰るのだ。
摩訶不思議な経験をしたものだ。
そういえば、目無し地蔵尊を拝顔し忘れた。まあいいか。
家に帰ると、玄関に小さな閻魔様が立っていた。閻魔様の頭をなでて、家に入った。
茗荷の茶漬けを食べてすべて忘れることにした。寝ていると夜中に多摩子さんから電話がかかってきた。なかなか寝付けないのだという。円美ちゃんは守宮をおでこにのせ、ぐっすり眠っているそうだ。一時間ほどしゃべっていたら、眠くなったわと、多摩子さんは電話を切った。僕が眠れなくなった。
山椒 - 茗荷の舌13
私家版 子狸不思議物語「茗荷の舌 2016 一粒書房」所収
木版画:筆者


