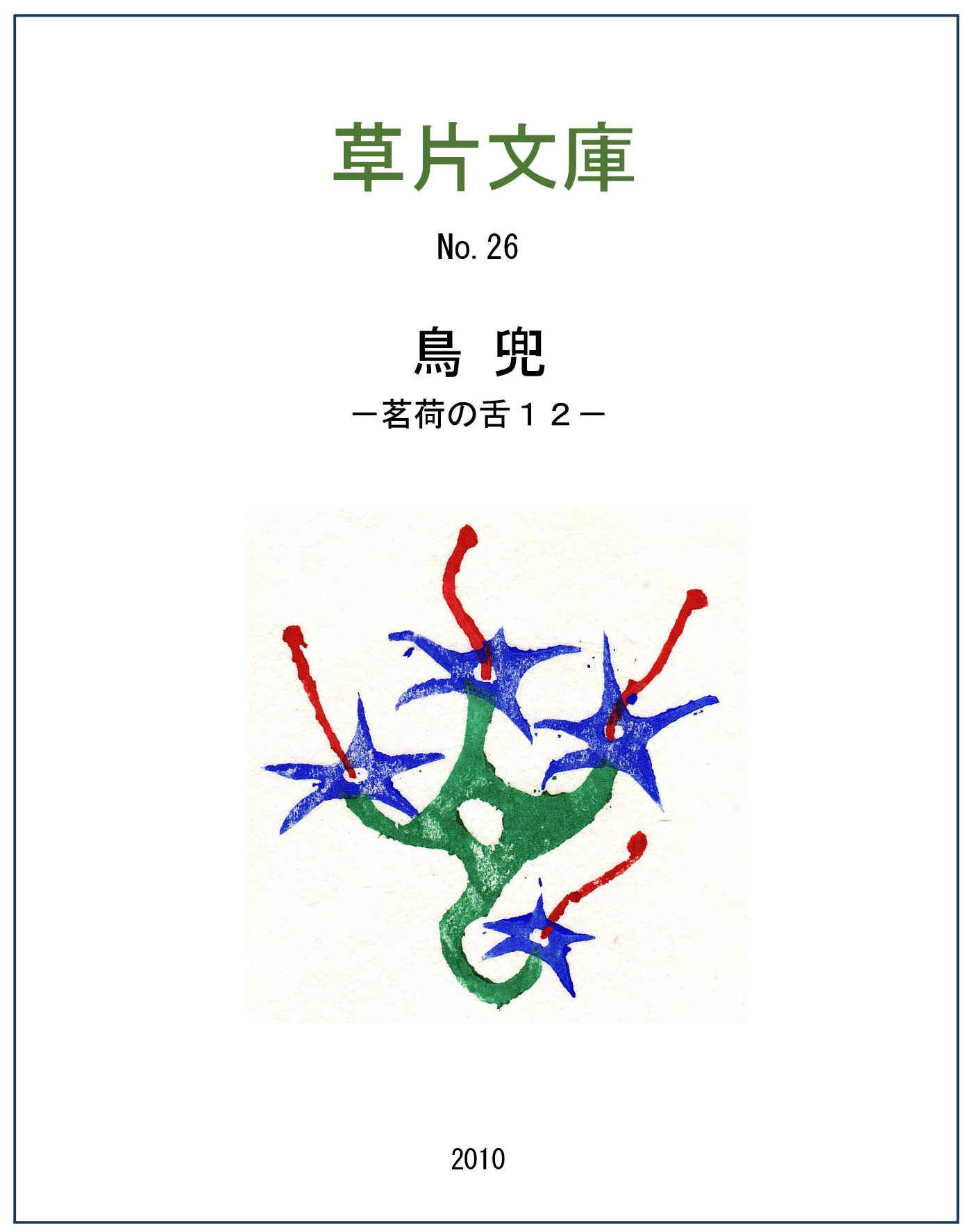
鳥兜 - 茗荷の舌12
電話が茶リーン茶リーンと鳴った。九茶路子さんだ。
電話を取ると、
「私とすぐわかったでしょう、私の脳波は強いから、新しいお茶を作ったのよ、また恐竜の骨を拾ったの、頭の骨」
「恐竜の頭って大きいでしょう」
「頭の骨の一部よ、前頭骨」
「前頭骨ってどこです」
「おでこのとこよ、脳の一番大事なところを守っているのよ、脳の前頭葉っていって、自分が自分であることを認識するところ」
ずいぶん難しいことを知っているものである。
「その骨をお茶に入れたら、頭がすっきりしちゃったのよ、首切り地蔵のおかげかもね」
さらに続けた。
「そのお茶をねえ、円美ちゃんに持たせたから、円美ちゃんの東京案内お願いね、今日お昼頃つくように行くって言ってたわ、愛車でいくみたい、ほんとかどうかわからないけど東京はじめてなんだって、きっと嘘よ、何だか私よりよく知っているみたいだもの」
それで、かちゃん、と一方的に切れてしまったのであった。
さて、どんなお茶だろう。
お昼ごろに来るのならお茶漬けの用意でもしておかなければ。円美ちゃんは食べるのが好きなようだ。何のお茶漬けがいいのだろうか。
コロッケも用意しよう。
南平駅近くの肉屋さんの昔ながらの手作りコロッケを買いに行こう。
エコ袋を持って家を出ると、家の脇にお観音さんが立っている。またあの狸の子だ。観音さんの頭を軽くたたいて駅に向かった。
道の角で振り向くと観音さんはもういなかった。
駅の肉屋さんでコロッケを五つ買った。ついでに焼き鳥も買ってみた。僕は食べないが、円美ちゃんは食べるかもしれない。
帰りに熊野神社の中を通ると、草むらの中に赤いものが見えた。そばによって見ると赤いチャワンタケである。ヒイロチャワンタケといったとおもう。日本では食べないが食べても大丈夫な茸である。おまけに朽木に木耳(きくらげ)がついている。それもとった。どちらも千切りにして梅干に和え、お茶漬けの具にしよう。鰹節も少し混ぜるといいかもしれない。
家に帰り、支度をして恒川光太郎の小説を読んでいると、車の止まる音がした。
窓から外を見ると赤いフィガロから円美ちゃんが降りるところだ。
玄関が開くと、円美ちゃんが白いふっくらとした顔をにこにこさせて、
「こんにちわああ」と叫んで入って来た。
「この間はお世話になりました、遠いところすみません」
「先生ったら、おいしいお茶できたから、もって行ってえって突然言うのよ、ほんとは自分が持って来たかったんでしょ、でも用事があるんですって」
九茶路子さんはいつもそうだ。面白いお茶ができると、急に僕をお茶会に呼び出したり、宅急便で送ったりしてくれる。今回はお弟子さんができたものだから頼んだのだろう。
玄関先で円美ちゃんは手に持っているものを差し出した。
「はい、これどうぞ」
棗に入った青いお茶だった。
「きれいな色だ、鎌倉の多摩子さんが、染めに使いそうだ」
僕が何気なく言うと、円美ちゃんが頷いた。
「そう、お師匠さんもそう言ってたの、だから多摩子さんにも持って来てるの」
九茶路子さんはその昔し、多摩子さんの家で紹介されたのだ。
「だから、この後に鎌倉へ行くの、いっしょに行くようにお願いするようにって、師匠から言われているの」
「はい、その前にお昼食べましょう」
僕は頷いた。
「嬉しい、お昼食べられると思ってなかった。車を脇に寄せてきます」
円美ちゃんはにこにこして外に出た。
岐阜からここまで運転して来たのに疲れた様子が全くない。
戻って来ると、円美ちゃんは赤い靴を玄関先にそろえて居間にあがってきた。
「南平の家よくわかりましたね」
「師匠が丁寧に教えてくれたの」
九茶路子さんは一度しかこの家に来たことがない。よく覚えていたものだ。
「車にナビがついてるし、インターネットでも調べましたの、昔、庭に竹が藪になっていたのね」
最近は立体地図画像で場所が特定されてしまう。
この細長い庭の角には細い竹の小藪があったが、根っこを伸ばして他の植物を枯れさせてしまったり、家の下までもぐりこんできて家を倒してしまいそうで、竹があまりにも強すぎてやむなく取ってしまった。
根を掘りだすのに一年もかかった。みんな取ってしまったが、なんとなく寂しいと思い大きな鉢に少し植えて残してある。
円美ちゃんにちゃぶ台の前に座ってもらった。
コロッケと焼き鳥をおくと、
「あら、おいしそう、南平のコロッケね」
円美ちゃんは笑窪を寄せた。あれっと見ていると、手を伸ばしコロッケをつまむとムシャッと食べてしまった。焼き鳥も食べた。僕が見ているのに気がつくと、円美ちゃんははっとして、
「あ、お箸使うの忘れてた、いつも九茶路子先生に叱られているの、でも手で食べるのおいしいわ」
顔を赤くした。
湯がいたヒイロチャワンタケと木耳を刻んで味噌に和え、おかかをかけてご飯の上に乗せると、お茶とともにちゃぶ台においた。
「おいしそう、これに、先生の青玉露をかけるといいのよお」
円美ちゃんは僕のほうを見た。
僕は頷いて、台所からお湯をもってきた。
円美ちゃんは茸とおかかに青いお茶を振り掛けお湯を注いだ。
ご飯が青く染まり、茸とおかかが浮き出てきた。
円美ちゃんはさらっとご飯をかけこむとクチャッと噛んだ、口の中の舌の上に刻んだ茸がおどっている。
「おいしい、私ばかり食べていていいのかしら」
食べているところをボーっと見ていた僕は、はっと気がついて、自分のお茶漬けの用意をした。円美ちゃんのように、お茶漬けをおいしそうに食べる娘(こ)ははじめてだ。見とれてしまった。
僕も青玉露をかけて食べてみた。
「これはおいしい」
後片付けは円美ちゃんがしてくれた。
さて、円美ちゃんのフィガロに乗ると鎌倉に向かった。
円美ちゃんの運転はなかなかすごい。二車線の国道に入るといくつもの車を追い抜いてどんどん進んでいく。いっぺんに三台もの車を追い越した。次はトラックだ。その次はあっという間にパトカーを追い越してしまった。
「あら、パトカー」なんて言いながら円美ちゃんのふっくらとした白い足がアクセルを踏んでいく。
目の前にまたパトカーが現れた。円美ちゃんの赤いフィガロはそれも追い抜いた。すると、また、パトカーが目の前にいた。
パトカーだらけだと思ってみると、隣の車線を走る車も、後ろも前もみんなパトカーになってしまった。子狸のいたずらだろうか。
「私、パトカー大好きよ」と円美ちゃんはどんどん追い抜いていく。
すると、今度は全部色違いのフィガロになった。
「つまんない」円美ちゃんは追い抜くのをやめた。
そうこうしているうちに、北鎌倉が近くなってきた。
北鎌倉の駅の際の道に入り、名月院に行く脇道に入ると、すぐのところを左に曲がり、さらに右に曲がったところに多摩子さんの作業場兼用の家がある。見晴らしのよいところだ。
フィガロを下に止めて階段を上がると入り口を勝手に開けて中にはいった。
「今日わあ」
「いらっしゃい」
奥から多摩子さんが出て来た。多摩子さんは何かを染めていたようだ。
「おや、円美ちゃんよく来たわねえ、どうしたのかしら」
「多摩子さん円美ちゃん知ってるの」
「はじめてよ、でも九茶路子さんが、お弟子ができたって嬉しそうに電話してきたのよ、色の白いぽっちゃりさんって」
円美ちゃんが顔を赤くしている。
円美ちゃんは青玉露を多摩子さんに手渡すと、「新しいお茶です」と言った。
多摩子さんは怪訝な顔をして、「九茶路子さん何も言ってなかったのに、不思議ねー、新しいお茶ができるとすぐ電話してくるのに」そう言って棗(なつめ)を開けた。
「きれいな青ね、染色に使えそう」
「先生もそうおっしゃってました」
「何から作ったのかしら」
円美ちゃんは困った顔をした。「私聞いてないんです」
「僕も九茶路子さんから教えてもらえませんでした。お茶をたてて当ててみたらということでしょう」
円美ちゃんも頷いた。
「私いれます」円美ちゃんが、お茶の用意をはじめた。
「お願いするわ、私は途中の染物仕上げちゃいますね。いただいたお茶も使ってみようかしら」多摩子さんは小さな入れ物にお茶を取り分けると、それを持って作業場に戻った。
円美ちゃんはさすがに九茶路子さんのお弟子さんである。昔から知った場所のように、多摩子さんの自慢の茶器を持ち出してお茶会の用意をはじめた。
作業場から多摩子さんが叫んだ。
「戸棚の左側にうちのお菓子が入っているわよお」
僕が戸棚を開けてみた。みかん色の和菓子があった。ぶよぶよとしているけれど、ゼリーや寒天でもないようだ。杏の干したものに少し似ている。
「これなんです」
不思議なお菓子だ。
作業場から多摩子さんが叫んだ。
「うちに生えた橙色の木耳を甘く煮たのよ」
橙色の木耳など聞いたことがない。白かこげ茶のものしか知らない。
「新種かもね、うちの柘榴が枯れちゃったの。そしたら、橙色の木耳がたくさん生えたのよ。科学博物館の都縞君に電話したら、いくつか持って行ったわよ」
都縞間造だ。彼はいくつもの新しい茸を発見している。専門は冬虫夏草だが、どの茸についてもとても詳しい。多摩子さんは津島君の見つけた茸で染色をしたこともある。それにしてもおいしそうだ。
「この茸は染色には使わなかったの」
そうつぶやいたら、多摩子さんが四角い橙色の布を持って作業場から出てきた。
「ほら、その茸で染色したの、きれいでしょう。またフランスで売れるわ」
橙色といっても墨流しのような濃淡が少しある。たしかに、日本人からも西洋人からも好まれる国際色である。
「マーブル染よ」
多摩子さんは「九茶路子さんに、袱紗に使ってもらうの」と手に持った布を広げた。
「都縞くん、この茸の名前をねえ、タマコキクラゲにするって言ってたわ」
なんか茸らしくない。海のクラゲみたいだ。
お茶の用意のできた円美ちゃんが、多摩子さんが持つ布を見た。
「すてき」円美ちゃんの目がもっと大きくなった。
「私も欲しい」
「円美ちゃんにもあるわよ」
「うれしー」
「さー、お茶にしましょう」
テーブルには、白い志野焼の皿に橙色の木耳のお菓子がのせられ、やはり白い志野の小ぶりの茶碗に青い茶が立てられ用意されている。
木耳のお菓子を口に入れると、口の中で甘酸っぱくとろけた。フランス的だ。
九茶路子さんの青いお茶を飲んだ。柔らかい苦味が口中に広がって、えもいわれない香りが鼻をついた。木耳のお菓子と相まって、ふっと幸せになる。
「何から作ったお茶でしょうね」
多摩子さんも首をかしげた。
そのとき、多摩子さんの電話が茶リーン茶リーンと鳴った。
「あ、九茶路子さんからだよ」
僕が言うと、「ほんと」と、多摩子さんが不思議そうな顔で電話を取った。
「アーラほんとに九茶路子さん、今お茶いただいてます。とてもおいしいわ、ありがとう。何で作ったの」
「鳥兜、野葡萄の実、馬酔木よ、全部毒。ふふふ、毒味茶というの、青いのは野葡萄の青い実をつかったの。それも毒よ、みんな死んだ、死なないでしょう、恐竜の骨を少し削って混ぜると毒が消されておいしいお茶になるの」
電話で九茶路子さんが言っているのがもれ聞こえてくる。
僕は円美ちゃんと顔を見合せた。
電話をおいた多摩子さんが聞いた。
「どうして、今の電話が九茶路子さんとわかったの」
「茶リーン、茶リーンとなったから」
「ふーん」
やっぱり、九茶路子さんの脳波と僕の脳波によって鳴っているのだ。
円美ちゃんは多摩子さんの家に泊まることになり、みんなで多摩子さんの海鼠茶づけをいただいた。
僕はお茶の青で染めたハンカチをもらって家に帰った。
明日は円美ちゃんと多摩子さんと東京散歩だ。
鳥兜 - 茗荷の舌12
私家版 子狸不思議物語「茗荷の舌 2016 一粒書房」所収
木版画:筆者


