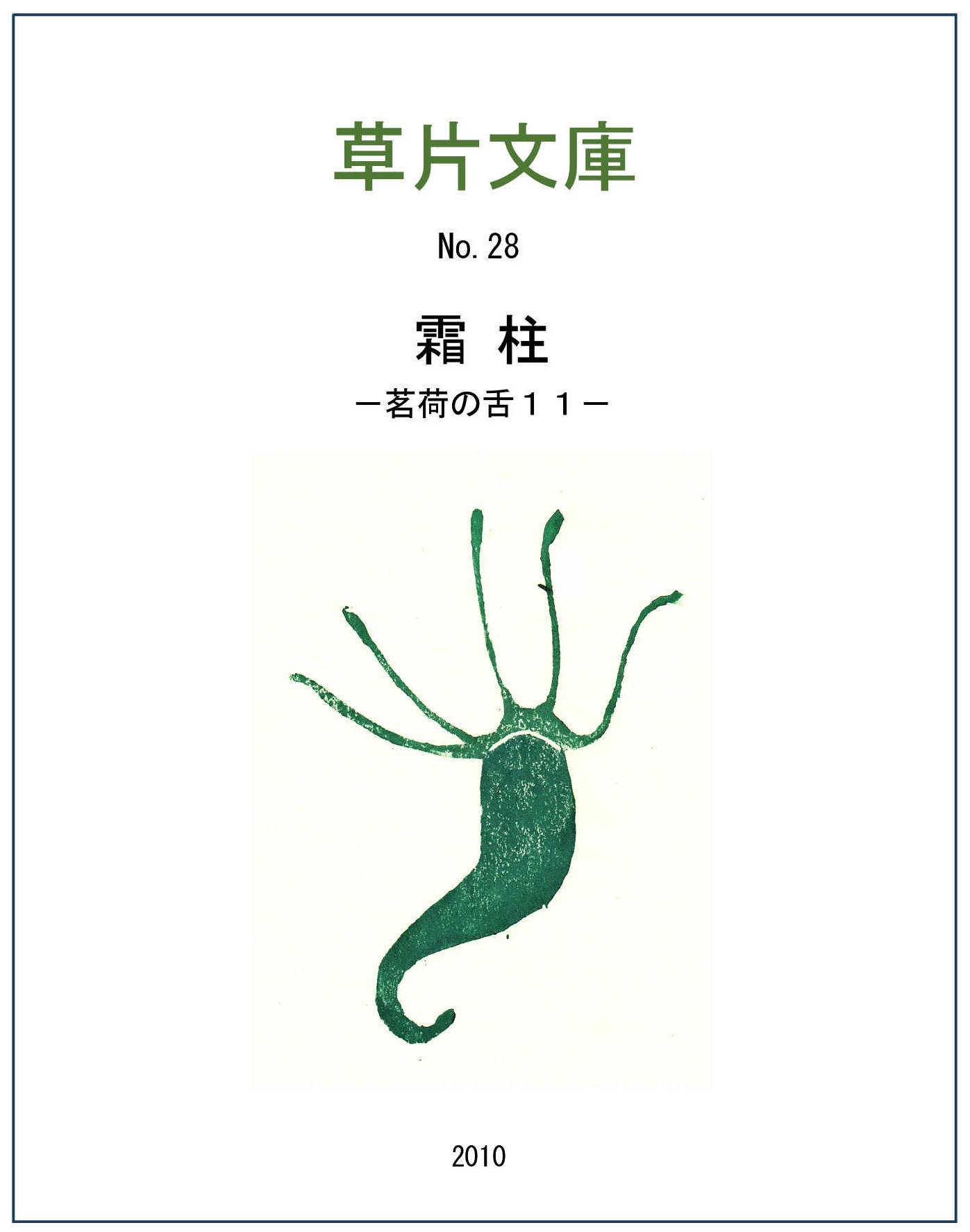
霜柱 - 茗荷の舌11
京都土産のこぶの佃煮で朝のお茶漬けをつくった。ちゃぶ台の前で二杯目を食べているところに電話が鳴った。
茶リーン茶リーンと変な鳴り方をする。
これはお茶の先生をしている九茶路子(くちゃろこ)さんからの電話だ。九茶路子さんの電話は必ずこう鳴る。電話に特別な細工をしているのではない。
九茶路子さんにそのことを話したら「それは第六感と、脳の放電のせい」だという。もう少し詳しくいうと、僕の脳の持つ第六感が九茶路子さんの脳が放った脳波をとらえて、僕の放った脳波によって電話のベルの音を茶リーン茶リーンと鳴らせたのだそうだ。なんだかだまされているようだがそうとも思える話だ。
ともあれ、電話を取った。
「今日、お茶の会よ、いらっしゃあい」
だった。
「何時から」
「夕方」
九茶路子さんは電話を切った。
と、また茶リーン茶リーンと鳴って、九茶路子さんが「若いお弟子ができたのよ」と嬉しそうに言ったのだ。
「それはおめでとう」と言うと
「はーいありがとう」と電話を切った。
九茶路子さんのお茶はとてもおいしいときがあって、それは誰にもまねができないようなすばらしいものなのだが、とても奇妙なときのほうが多い。お茶の雑誌でとてもほめられたりすることがあるが、今まで弟子になろうという冒険心のある若い人はいなかった。よほど元気な人なのだろう。
さて、残ったこぶ茶漬けを片付けると、出かける支度をしなければならない。九茶路子さんの庵は丹波の谷川(やがわ)にある。日野の南平からだと新幹線で大阪に出て、宝塚線で谷川駅まで七時間ほどかかる。それに九茶路子さんのお土産を集めなければならない。九茶路子さんはどんな植物でも上手に乾燥させ不思議なお茶に仕立ててしまう。
いつぞやお邪魔したときには、タマノカンアオイの葉を摘んで持っていったら、それは極上のお茶になって数ヵ月後に送られてきた。煎れて飲んでみたがいわゆるお茶の香ではなくたとえようのないもので、表現することができない。飲み終えると目にするものがすべてくっきりと冴えわたり、頭もすっきりする。不思議な味のお茶にしあがっていた。お茶の雑誌にも紹介されていたが何の葉っぱだか書いていなかった。みんなが採ってしまうと貴重なタマノカンアオイが絶滅してしまうといけないという九茶路子さんの配慮である。タマノカンアオイは多摩丘陵にある寒葵で、南平高校の校章のデザインにもなっている。
寒葵はなかなか殖えない植物であることから、他のものと混ざりにくい。そのようなことから地域ごとに違うものがあり、遺伝の研究に用いられたりしている。
春早い頃、土に埋もれて、ラフレシアを小さくしたような紫色の原始的な花が咲く。葉を鑑賞する古典園芸植物でもあり、徳川家の葵の紋はフタバアオイという寒葵の仲間である。
寒葵にはカフェインが無い。だから九茶路子さんの作ったお茶を飲んでも眠れなくなることは無く、むしろ気持ちよく眠れる。それにこれもこのお茶の不思議なところなのだが、気に入った夢を見ることができる。しかし人によってその効果が違うようだ。何の成分のせいなのだろうか。
今日持っていくのは、庭に生えている霜柱にしよう。
昨年の冬はかなり寒く、しかもいきなり寒い日が訪れた。そのためなのだろう、はじめて数本の霜柱の枯れた幹に氷の結晶がついた。朝日に輝いてきれいだった。
霜柱は秋に花の咲く五十から八十センチほどの山野草である。庭のものは園芸屋で購入したものだが、高尾山にもあったし、どこかの公園でも見た記憶がある。ストローのように枯れた幹から、根から吸い上げた水が染み出し、それが凍っていろいろな形の氷の結晶を作る。花も雪のような白さである。しそ科の植物で、白くかわいいひげのある花がたくさん並んでつく。九茶路子さんのおみやげにはうってつけだ。花も満開なので少し切って持っていこう。
ということで、あわてて出発の支度をした。
京王線で新宿へ、東京駅でのぞみに乗り、新大阪、大阪―尼崎を経由して一時間に数本しかない福知山線で丹波市の谷川(やがわ)までの長旅である。朝十時に南平を出たのに、もう夕方の五時である。どんよりと曇った山間を電車はのんびりと走っていく。山間にたまに見られる家が靄に霞んで妖怪でも出そうな雰囲気になってくる。
やっと谷川の駅につくと、いつもながらのお出迎えだ。駅前に置かれているちょっと漫画的な丹波竜の親子の像が観光客の目を捉える。このあたりは恐竜の骨が眠っているところだ。恐竜の親子はどちらかというと質素な駅にそぐわない明るさがあって滑稽だ。
駅を出たところにいつもならいるタクシーがいない。
駅前でぼんやりしていると、真っ赤なフィガロがわき道から現れた。赤いフィガロははじめてみる。
目の前に止まると、フィガロから降りてきたのは丸ぽちゃの色白の女の子だ。僕のほうにやってくると、大きな明るい声で、
「こんにちは、九茶路子先生からお迎えするように言われました」と言った。
ははあ、この子がお弟子に入った子なのだな。女の子はフィガロのドアを開けてくれた。四人乗りといっても後部座席はお飾りのようについているだけで、ほとんど二人乗りの車だ。
「どうも、ありがとうございます」僕は頭を下げた。
車に乗ると女の子も運転席について、
「ちょっと行きたい所がありますの、そこに寄ってから先生のおうちにご案内しますわ」と、ドアを閉めた。
黒いスラックスに白いブラウスの女の子は、白いふっくらとした手でキーを回してエンジンをかけた。フィガロは勢い良く動きだした。
車は町を出ると坂道に入った。九茶路子さんの庵に行く途中だ。さらに脇道に入ると、首切り地蔵の方に向かった。
ここには首切り地蔵という、首のないお地蔵さんを祀った地蔵尊がある。平家の落人がここで首をはねられ、それを村人が弔ったといわれる場所で、首より上の思いをかなえてくれるという。頭の病気ばかりではなく、頭がよくなるように、受験に受かりますようにと願を掛けに来る人でにぎわっている。一度来たことがあるが、そのときは赤ちゃんを連れた夫婦や女学生らしき集団がいた。
女の子は首切り地蔵尊の下にある小さな駐車場にフィガロを停めた。
エンジンを切ると、「ちょっとお待ちくださいまし」と車を降り、小走りに首切り地蔵の階段を上がっていった。
しばらくすると、茶色の壺を抱えて降りてきた。
「お水ですの、先生に頼まれて」
「ここは、よい水が出るのですか」
「はい、大昔に処刑された人たちの清い心の水ですの」
難しい言い回しだ。察したかのように、女の子は大きめの口をあけて笑った。
「あはは、処刑場に湧き出たお水で、とてもきれいでおいしいの」
なんてことはない、墓場の湧水なのだ。
その後、フィガロは無事に九茶路子さんの庵に着いた。
「先生、おつれしました」女の子が庵の戸をあけた。
「円美(まるみ)ちゃん、ありがとう」
円美ちゃんていうんだ。彼女は水を玄関に置くと車に戻っていった。
僕は勝手知ったる九茶路子さんの家にあがった。
「久しぶりねえ」
九茶路子さんは、竈で何やらを煮立てていた。
「ちょっと待っててね、今すぐ終わるから、夕ご飯の支度してるの、あなたの好きなこごみの塩漬けと、今煮たてている山菜スープよ」
「今日は、霜柱を持ってきました」
「まあ、ありがとう、あとでお茶を作りますね」
九茶路子さんは即席にお茶を作る技術を持っている。
お茶会は夕ご飯をいただいてから夜の十二時頃に始まる。
「今日は何人集まりますか」
「あなたと円美ちゃんをいれて五人よ、あなたも会ったことがあるでしょう、京都の西子さんと本栖さんご夫妻、それにここの村長さんよ」
西子さんと本栖さんは黒豆屋さんをやっている。丹波の黒豆はとても有名だが、その中でも不思議な味の黒豆を作ることで有名だ。前に来たときにご馳走になったが、口に入れると崩れ落ちるように口の中で溶け、しっかりとした和風の甘みと豆の香りが広がる。黒というより黒緑色に近い豆で、その家でしか栽培していない。
まずは夕食をいただくことにする。
ちゃぶ台にお茶漬けの用意がしてある。
こごみの塩漬けをご飯の上に乗せて、煮込んだ山菜スープをかける。このお茶漬けは九茶路子さんのところでしか食べられない。
そこへ、円美ちゃんも来た。
「あなたもお茶漬けお食べなさいな」
「ハーイ」
目を輝かせて円美ちゃんもちゃぶ台の前にすわった。まん丸の眼をしている。
九茶路子さんが円美ちゃんに言った。
「この人が南平に住んでいる人よ」
「南平って日野市でしょう」
「よく知ってますね」
円美ちゃんは僕を見て微笑んだ。
「円美ちゃんが私のお弟子なの、一週間に一度か二度きているのよ」
九茶路子さんはとても嬉しそうだ。物好きな子もいるものだ。
「物好きでしょう」
九茶路子さんは、僕の考えていることがみんなわかるみたいだ。
円美ちゃんは、僕と同じようにこごみの塩漬けをご飯に乗せて、山菜スープをかけた。じゃぶじゃぶじゃぶ、と音をたててお茶漬けをかき込むと、
「おいしーーい」と言って、またお櫃からご飯をよそった。
九茶路子さんは笑いながら、
「食べ過ぎると太るわよ」と、自分は小ぶりの茶碗に少しご飯を入れ、こごみの塩漬けを二つ乗せると、スープをかけてさらさらと食べた。
「このお茶漬けはおいしいわあ」
円美ちゃんはお茶漬けが好きなようだ。話し方までくだけてきた。そっちが本当なのだろう。
「このスープにはねえ、丹波竜が入っているのよ」
九茶路子さんが言った。
「私ねえ、裏山で恐竜の骨を見つけたの、でもね、そうっとしまってあるの」
「どこの骨」
「骨盤」
「教育委員会に言わなくていいの」
「だって、食べたかったんだもん」
九茶路子さんはお茶だけではなく、食べるものにも通なのである。
「削ってスープに入れると、縁(えにし)の味になるでしょう。ご飯のお米は古代米よ」
縁どころではない、ブラックホールの味になる。
食事が済むと、九茶路子さんと円美ちゃんはお茶の用意をしに隣の茶室に消えていった。
夜も更けてきた。雨も落ちてきているようだ。少し肌寒い。
車が止まる音がした。戸が開くと西子さんと本栖さんが入ってきた。
「久しぶりですねえ」
お二人は僕にお土産を渡してくれた。例の緑の黒豆である。僕は何も持ってこなかったのを悔やんだが、それを察したように、
「霜柱を持ってきてくださったそうですねえ、楽しみですな、今日のお茶会は」
と本栖さんが言ってくれた。いい人たちである。
また、車の止まる音が聞こえ、でっぷりと太った赤ら顔の人が入ってきた。村長さんだろう。
「足野です、どうぞよろしく」と僕に向かっておじぎをした。
村長さんは、西子さんと本栖さんとは知り合いのようだ。ようっと手をあげて挨拶を終わりにしている。
戸が開いて、隣の部屋から九茶路子さんが出てきた。その拍子にその部屋から熱い風がふーっとこちらになだれ込んできた。なんだろう。
「お揃いですねえ、どうぞ向こうの部屋へ、皆さん上着をとって、うでまくりをして、いらっしゃいな」
九茶路子さんも薄いカーディガンを脱いで半そでになった。
僕も上着を脱いでみなの後をついて茶室に入った。
茶室にはテーブルがしつらえてあり、円美ちゃんがノースリーブで、薪ストーブに薪をくべていた。部屋は真夏だ。
「ほー、こりゃまた、はじめての試みですな」
村長さんは興味しんしんにあたりを見渡しテーブルについた。テーブルの上には丹波焼きのお茶の茶碗が人数分用意してあった。確かに九茶路子さんのお茶会はいつも真っ当ではなく、一つの茶器に抹茶を立てるというのとは少し違う。それにしても今日の洋式のお茶会は全く不思議だ。
みんなの顔が赤くなっている。色白の円美ちゃんのほっぺたはピンク色の桃のようになっている。
「冷えたビールが欲しくなりますな」
村長さんが言うと、ご夫妻も頷いている。
九茶路子さんが、「これは、もってきてもらった霜柱を、即席に乾燥させて抹茶に仕立てたのよ、他にも少し入れたものもあるだけど、言っちゃおうかしら、軒しのぶの葉っぱと丹波竜の骨を少々」
そういいながら、緑色の粉を自分の前においた大きなお茶椀にいれると、鉄瓶のお湯をいれ、大きな茶せんでかき混ぜた。
「これはさっき円美ちゃんが汲んできた首切り地蔵のお水」
勢いよくかき混ぜ泡が立つと、円美ちゃんが、ウヰスキーのロックのときにつかうように丸く削った氷を、九茶路子さんが立てているお茶の中に落とした。九茶路子さんはさらにかき混ぜる。この氷は同じ水で作っておいたものよ、氷が解けると、円美ちゃんがもう一つ入れた、それを何回か繰り返すと、氷が解けなくなり、緑のお茶の中に透明の氷が浮いているようになった。
円美ちゃんが、緑色の丹波の黒豆の乗った丹波焼きのお皿をそれぞれの前においてくれた。
円美ちゃんが言うには、ただの黒豆ではなくて、古酒につけた黒豆だそうである。
九茶路子さんが、「お茶の前に食べるのではなくて、お茶をお配りしてから、飲みながらお召し上がりましな」と言った。
円美ちゃんが、みなのお茶椀に丸い氷を入れると、九茶路子さんが、立てたお茶を小さな柄杓をつかって注いでいった。
みなにいきわたると、自分の茶碗に注いで、さらにそれぞれの茶碗に霜柱の小さな白い花を浮かべた。
九茶路子さんが「さあ、黒豆を召し上がりながら、お茶をどうぞ」と言った。
黒豆を口に入れたところ、黒豆がじゅうといって、舌の上でつぶれ、酒の香りが口中に広がった。お茶を一口飲むと、お茶の香りと冷たいお茶が喉の奥の道を冷やしながら胃に落ちていく爽快さを味わった。からだがスーッと冷えていく。
「ビールなどより数倍もうまいですな」
足野村長が赤ら顔に万遍の笑みを浮かべて黒豆をもう一つ口に入れた。
「これは、お茶会でもあるし、飲み会でもありますねえ、あなた」
「そうだなあ」
西子と本栖のご夫妻もまた黒豆を口に入れた。
「夏だととてもいい冷茶になりますねえ」
円美ちゃんは顔を赤くしてお茶を口に含みにこっと笑った。
そのうち僕の目の前に不思議な生き物が現れた。恐竜の赤ちゃんのようだ。
「おや、恐竜の赤ちゃん」
西子さんも気がついた。
「おいで、おいで」と言っている。
恐竜の赤ちゃんが西子さんの足元にやってきた。
「かわいい」
西子さんがなでた。本栖さんもなでた。
恐竜がごろごろいった。猫みたいな恐竜だ。
円美ちゃんが恐竜に黒豆をやった。恐竜の子どもはぺろぺろと黒豆をなめ、やがて飲み込んだ。円美ちゃんはまたあげた。今度は上手に噛み砕いて飲んだ。その時、恐竜がふわっと膨らんで、大きくなった。
村長さんが、「一杯どうだ」とお茶が入っているグラスを持ち上げた。
恐竜はそれをグイーと飲むと丸くなって寝てしまった。
すると、また小さな恐竜がやって来た。
「あら、また来た」
西子さんはよほど恐竜が好きだと見えて、つかまえると膝の上においた。
本栖さんが黒豆をやると、恐竜の子どもがくちゃくちゃ噛んだ。
また村長さんがお茶を恐竜の子どもに飲ました。
恐竜の子どもはふーっとため息をつくと丸くなって寝てしまった。
それからは大変だった。恐竜の子どもたちがぞろぞろとやって来て、黒豆とお茶をねだった。九茶路子さんと円美ちゃんはお茶を作るのに大忙しだった。
そうこうしているうちにお茶がなくなり、夜は更け、いつの間にやら朝になっていた。
「それじゃ、私たちはこれでおいとましましょう、九茶路子さんとてもおいしかった」
本栖ご夫妻が席を立った。
村長さんも立ち上がると「円美ちゃんもありがとう」と帰り支度を始めた。
「楽しいお茶会でした、また呼んでくださいな」
だれもが顔から湯気を立てて玄関のから外に出た。
九茶路子さんと円美ちゃんが見送りに出て行った。
部屋に一人取り残された僕がテーブルの下を見ると、生まれてあまり経たない狸の子どもがごろごろと寝ていた。
九茶路子さんと円美ちゃんが戻って来た。
「お茶からさめたのね」と僕に言った。
「このお茶飲むと、みんな恐竜に見えてしまうのよ、幻覚ね、たまたま一週間前に狸の子どもが生まれてね、時々遊びに来てたのよ」
それじゃあこのお茶は幻覚剤か、脱法ハーブ、いや危険ドラッグになってしまう。
九茶路子さんには僕が考えていることが分かってしまったようだ。
「警察には内緒よ、でも、村長さんも飲んじゃったからね」
と、けろっとしている。
円美ちゃんが狸の子どもを一匹ずつ抱っこすると、
「朝になったから自分のお家に帰りなさい」と言って庵の外につれていった。
こうしてお茶会は終わりとなった。
僕は九茶路子さんがつくった残りの霜柱のお茶をもらって帰ることにした。いつもこういう不思議なお茶会なのだ。
だけどいつもと違うのは、朝の一番電車に間に合うように、円美ちゃんが赤いフィガロで谷川の駅まで送ってくれたことである。
「ありがとう」
「また来てください」
円美ちゃんが手を振った。少し眠くなってきた。電車の中で寝て帰ろう。
霜柱 - 茗荷の舌11
私家版 子狸不思議物語「茗荷の舌 2016 一粒書房」所収
木版画:筆者


