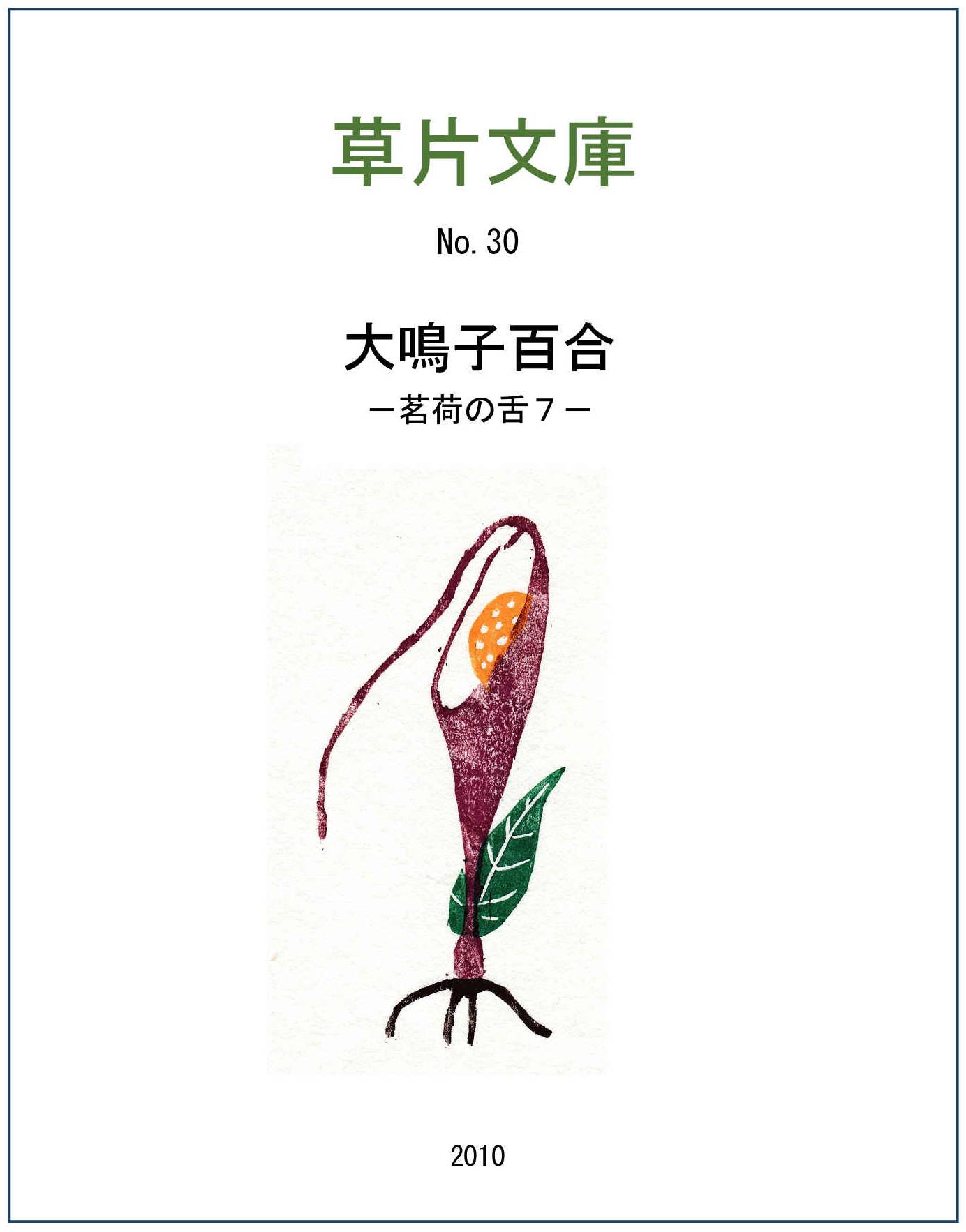
大鳴子百合 - 茗荷の舌7
今日は目白台にある古本屋さんに、植物の本を探しに出かけることにした。
よく晴れている。筋のような雲がうっすらと張っているだけである。
熊野神社の階段を降りていると、後ろから誰かがついてくる気配を感じた。振り返った。
猫らしき動物がひゅうっと階段から神社の下草の中に消えていった。きっとあの狸だ。猫にでも化ける練習をしているのだろう。
京王線南平駅から目白台まで電車で十五分位だ。
目白台駅を降りると広い道を西八王寺に向かって歩いて行き、ちょっと脇道を進むと柿屋さんという古本屋さんがある。橙色に塗った店でよその古本屋には置いてない面白い植物の本がある。
その斜め向かいに、間口は小さいが、太い材木を使ったがっしりとした建物の酒屋がある。数ヶ月前に通ったときには、硝子戸越しに日本酒が並べてあり、その隣に地ビールとアイラのウイスキーが置いてあった。不思議な取合せだと感じたことを覚えている。桃屋と看板が出ている。
桃屋の店先にあまり見かけない草が鉢植えにしてあった。
人の丈ほどにも伸びた幹に、笹のような葉が左右についており、その真ん中にすずらんのような白い花が一列にぶら下がってゆらゆら揺れている。
どこかで見た記憶がある。そうだ、思い出した。大鳴子百合だ。秋田の山で羊歯の間から顔を出していたのを見たことがある。
柿屋さんの戸を開けると、奥から「いらっしゃい」と声がした。
「久しぶりです」
「また、植物の本かね」柿屋さんの小父さんは眼鏡の上から僕を見た。覚えているようだ。
「ええ、野草の図鑑でいいのがありますか」
柿屋さんは番台のようなところから降りてくると、踏み台を持ってきて、棚の上のほうから一冊の本をとってくれた。
見ると、著者が丹念に植物をスケッチしてそれに解説をしたものである。『野の草の図』とある。奥付には昭和三十年の出版とある。ずいぶん古い。その頃のカラーの本である、相当高いものであろう。定価千五百円だ。今だと一万五千円ほどのものだろう。自分の財布には二千円しかない。とても買えないだろうと思って、値札を見た。千円とある。
柿屋さんも笑っている。
「買える値段だろ」
「でも、どうしてこんなに安く」
「へへ、拾ったんだ」
柿屋さんは嘘をつけない。柿屋さんは牛乳屋さんもやっている。ある日、朝早く軽トラックで牛乳配達をしていると、玄関の前に捨てる本が山積みになっている家があったそうである。本を見ていると、新聞を取りに玄関からお爺さんが出て来たので、譲ってもらいたいと申し出たところ、ただでくれたそうである。いい本が多く、この本もその一つだということである。牛乳を二本差し上げただけで申し訳ないと柿屋さんは頭を掻いていた。
「写真ではなくこの本のように写生した図のある図鑑が欲しかったのです」と言うと、柿屋さんは、
「そうだね、今はみんな写真になってしまった、それもいいけど、絵に描いたのは本として暖かいね、結構絵のほうが分かり易いところもあるしね」と頷いた。
「ください」とお金を渡すと、その本を包もうとしたので、「すぐ使いたいのでそのままでいいです」と本をもらった。
お礼を言って外に出ると、酒屋の前に置かれている大鳴子百合の鉢の前で、さっそく図鑑を開いてみた。すぐに大鳴子百合の綺麗な絵が見つかった。目の前のものそのものである。上手な絵だ。説明を読んでみると、ユリ科アマドコロ属とあり、北海道から九州まで、韓国、中国に産すとある。若芽は甘くて美味しく、根茎は生薬となり、黄精と呼ばれよく使われるものの一つと書いてある。黄精は滋養強壮、リュウマチや通風にも良いとある。
あらためて目の前の大鳴子百合を見たら、すずらんの花を大きく細長くしたような花の中に、蝿が入っていくところだった。
はっとしたのは蝿が入ったときである。花がいきなり「くちゃっ」と、音を立てて萎れて丸まってしまった。ハエはその中に閉じ込められたままだ。
蝿を閉じ込めた花は、次第に萎びて茎の中に吸い込まれていってしまった。するとその脇からまた白い蕾がもそもそと伸びてくると花が開いた。
また、蝿がきた。
蝿は同じように釣鐘のような花の中に足を突っ込んだ。とたんに、花はくちゃっと閉じて、足を挟まれた蝿は宙ぶらりんになった。すると、隣の花が伸びてきて宙ぶらりんの蝿をぱくっと中に取り込んでしまい、二つの花は萎びて茎の中に吸収されていった。
この植物は大鳴子百合にそっくりだが、食虫植物の一種のようだ。
今度は天道虫が飛んできた。大鳴子百合の花に潜り込むと花がくちゃっと閉まった。
次は蟻が登ってきて犠牲になった。
虫たちには可愛そうであるが、あまり面白いので、我を忘れていると、大鳴子百合がいきなり、ユッサユッサと揺れた。
酒屋の硝子戸が開いて、ふくよかな白桃のような女性が出てきた。真っ白な狐のような猫を抱いている。桃屋さんの女将さんらしい。
「呼んだのね」
女将さんは大鳴子百合に声をかけた。ふと、僕に気がつくと、
「面白いでしょう、大鳴子百合を仕込んだのよ」
そう言いながら女将さんは僕のほうに歩いて来た。
それをきいて大鳴子百合がユサユサと揺れた。
「ほほほ、いい子よ、この大鳴子百合は」
女将さんは白い猫を下におろすと、大鳴子百合の葉っぱをなでた。
白い猫はヒューと店の中にもどると、狸のようなふっくらした黒い猫をつれて戻ってきた。
「珍しい食虫植物ですね。何処に生えている植物ですか」
僕は聞いてみた。
「大鳴子百合よ、虫を食べるように教えたの、そのほうが美味しいお酒を作れるの」
「普通の大鳴子百合ですか」
「そうなのよ、小さい大鳴子百合をもらったので、水代わりに清酒をかけて丹念に育てたの、そうしたら、食虫植物になったのよ」
日本酒をかければみんな食虫植物になるのだろうか。と不思議に思っていると、女将さんは、
「普通のお酒ではだめね、わたしの手作りのお酒よ、雄の蚊を捕まえてお酒に仕込むのよ」と説明してくれた。
「なぜ雄の蚊入りのお酒は植物を食虫植物にするのだろう」僕がつぶやくと、女将さんは説明してくれた。
「雄の蚊は草の露を飲んで生きている運命なのね、雌の蚊は血を吸うのにね。雌は卵を産むために血を吸っていると言われているけど、やっぱり血は美味しいのよ、でも雄がもし血を吸おうとすると雌が雄の体液を吸っちゃうのよ、雄を殺しちゃうの、だから、雄は血を吸いたくてしょうがないわけね、それで雄の蚊をお酒にいれて、それを吸い上げた植物は虫を食べるようになるの」
なんだか理屈が通っているようでもあるが、なんとも奇妙である。
「どのような植物でも虫を食べるようになるのですか」
「いろいろやってみたのよ、うまくいったのはこの大鳴子百合だけ、しかもこの大鳴子百合はお酒も作るようにもなったのよ」
「でも雄の蚊をたくさん集めるのは大変ですね」
「あーら、簡単よ、蚊柱を見つけて一網打尽に捕まえるのよ。
雄の蚊が集まって蚊柱を作るのは、血の吸えない憂さを言い合って慰めあうためなのよ」
雄の蚊がかわいそうになってきた。
白と黒の猫が女将さんの足元に擦りついた。
「パーティーをはじめましょうね」
女将さんは二匹に言うと、大きな丸テーブルを店の中からひっぱりだして、道の真ん中に据え付けた。
椅子もいくつか用意された。
それからが大変だ。
女将さんは鉢を持ち上げるとテーブルの真ん中に置いた。すごい力だ。
ふふふといった顔で彼女が僕を見た。
白と黒の猫がテーブルの上に飛び乗ると鉢の脇に寝そべった。
女将さんはぐい飲みが入っている籠をつるして店から出てくると、どっかと椅子に腰掛けた。
「あなたもお座りなさいな」
女将さんは見ていた僕にも座るように促した。
「さああ、お願いよ」
女将さんはそう言うと、白いふっくらとした親指と人差し指に挟んだ志野焼のお猪口を一本の大鳴子百合の前に差し出した。
彼女の声で大鳴子百合の葉先がテーブルの上のお猪口にしなだれると、その先から、ぽたっと一滴、透明な液体を滴らした。二滴三滴、ぽた、ぽた、ぽたと、少しずつ綺麗な水がお猪口の中に溜った。
「出たわねえ、今日はとても澄んでいるわ、続けて」
女将さんが言ったとたんに、ぽたぽたぽたと液体がたれ始めた。
ぷーんと酒の香りが辺りに漂った。
残りの七本の大鳴子百合もしなって葉先をテーブルの上にたらした。女将さんはそこにもお猪口を置いた。大鳴子百合の先から酒がぽたりぽたりと落ち始める。
「やってますなー」
柿屋さんが店から出てくると椅子に座った。太い指で目の前のぐい飲みを持ち上げるとぐいと飲んだ。
「こりゃあ、うまい」
柿屋さんの奥さんも出てきた。演劇をやっている女優さんだ。
「女神子(めがみこ)さん、私にも頂戴ね」
「もちろんよ、どうぞお好きなところにお座りになって」
女将さんは女神子さんというらしい。
柿屋さんの奥さんが持ってきた包みを開いた。
「はいみなさんどうぞ、昨日蓼科の友達が野沢菜を送ってきたのよ。地元でしか手に入らないものですって」
僕の前にも紙の上に野沢菜と楊枝が一本置かれた。
「すみません、僕まで」と頭を下げると、
「運がいいね、大鳴子百合の酒が飲めるのは年に一回しかないんだよ」
柿屋さんが笑顔で僕を見た。
女神子さんが
「一番最初の雫がまた美味しいのよ」
と、僕の目の前の志野焼きのお猪口を指差した。大鳴子百合がつくった透き通った酒があふれそうになっている。
猪口を手に取り、ちょっと口に含むと、少し草の香りの混じった、とろける匂いが広がった。スーッと舌の上を酒がころがって咽がひんやりとすると、ごくんと咽が動き、酒が食道に沿ってお腹の奥のほうに消えていった。ほーっと息に混じって、もう一度、とろけるような酒の香りが、今度は鼻から抜けて目にまで漂ってきた。
「あーあ、美味い」
日本酒を飲んで溜息が出たのは始めてである。それほどに美味い。
柿屋の奥さんも目の前のお猪口をとった。
「ほんと、今年のは格別だわ」
女神子さんが大きな目をぱっと見開いた。桃のような顔中が目になったような感じだ。
柿屋さんが言った。
「この酒は世界に一つしかない貴重なものだよ。女神子ちゃんが、大鳴子百合を飼いならして、こんな旨い酒を作るようにさせたのだよ、私なんて最初飲んだときには、おしっこを漏らしてしまったよ。何せ大脳皮質の感覚をすべて麻酔にかけてしまうくらい旨かったんだよ、だからさ、がまんできないで、おしっこ漏らしたのさ。なぜ漏らさなかったのかね君」
少し酔っ払っている。
女神子さんはそれを聞くと、ふっくらした笑窪を寄せて、
「ほんと、そうだったわね、奥さんに叱られて大変だったわね。美味しいもの食べたり飲むといつも漏らすって」
「へへへ」
大きな顔をした柿屋さんは照れ笑いをした。
通りすがりの二人の女高生が興味深そうに立ち止まって見ている。
女神子さんは「ちょっと飲んでみる」と大きなガラスのコップに大鳴子百合の酒を受けて差し出した。
コップにあんなに沢山のお酒を入れて、高校生なのにいいのかなと見ていると、女高生は一口飲んで、
「おーいしいジュウス」と叫んだ。
「暑いときは美味しいでしょう、このジュース」
女高生は頷いている。
女神子さんは僕に
「二十歳より前の子にはジュウスになるのよ、鳴子百合ジュース」と女神子さんは言った。
白猫と黒猫が立ち上がって欠伸をした。
白猫は大鳴子百合の茎の先に口をつけるとぺちゃぺちゃと酒を舐めた。
黒猫も同じように大鳴子百合の葉先に舌を出して舐めた。
白猫と黒猫はいきなり二本足で立ち上がった。
二匹はひょいひょいと飛び上がると、手と手を取り合って踊りだした。
なんてこった。
女神子さんは手拍子を始めた。それにそって、黒白のワルツが始まった。
「猫にはまたたびの味がするのよ」
二匹は髭をすりあって踊っている。我々はそれを見ながら盃を空にした。
女子高生も椅子に座って面白そうに猫の踊りを見ている。
日焼けした中学校の制服を着た女の子が通りかかって、興味深そうに近寄ってきた。どこかで見たような子だ。
「こちらにいらっしゃい」
女神子さんが、どうぞと椅子を勧めた。
中学生の女の子は遠慮しながら腰掛けて踊っている猫を見た。
女神子さんは赤いお猪口に大鳴子百合のお酒を満たし女の子に渡した。
女の子はお猪口を受け取ると匂いをかいだ。不思議そうな顔をしてお猪口の中を覗きこんだ。そういえば、高校生にはコップでジュースを渡したのに、なぜ中学生にはお猪口なんだろう。
僕は自分のお猪口を口に運んだ。美味しい。
それを見ていた女の子もくいっと飲んだ。
中学生の顔がぽっとなって、いきなり、「ういーーーい」と言った。
お酒だ。なぜだろう。女神子さんが笑っている。
「おいしいでしょう」
中学生は頷いている。
女神子さんがもう一つお猪口を渡した。
「中学生なのにお酒になったの」と僕が女神子さんに聞くと、
女神子さんはにこっと笑って、
「年っていろいろ違うのよ、大鳴子百合の判断ってところ」
そんなよくわからない返事を返した。
中学生の女の子はまたくいっと飲んだ。
「おいしい」
頬が赤く染まってきた。
中学生の女の子ところに白と黒の猫がやってきて頬ずりをした。
「かわいい猫ちゃん」白と黒の猫の咽の下をなでた。猫たちはごろごろ咽を鳴らしている。猫に好かれる娘だ。
女の子は野沢菜をつまむと、また一杯飲んだ。
何杯か勢いよく飲むと、「ひょー」と言って、いきなり立ち上がり、
「ご馳走さま」と女神子さんにお辞儀をすると駅のほうに向かった。ちょっとよろっとしている。大丈夫なのかな。
真っ赤な顔でチラッと僕のほうを見た。
やっぱりどこかで見たことがある。
柿屋さんが言った。
「女神子さんが知っている娘かい」
「はじめてよ、でも飲みたいって顔をしてたの」
柿屋さんの顔は夕日のように赤くなっている。
宴会は続き、いろいろな人が訪れて大鳴子百合のお酒を楽しんで帰って行った。僕と柿屋さんが最後まで残った。
夕方になり、大鳴子百合が疲れてきた。
「さあお開きよ、また来年来て下さいね、いつになるかわからないけど」
女神子さんは大鳴子百合の鉢をお店の中に入れ、白と黒の猫は店の中の酒樽の上に寝そべった。
柿屋さんは奥さんに抱えられて自分の店に帰った。細身の奥さんには重そうだ。
僕もお暇をした。
「またいらっしゃいな」
女神子さんが笑窪を寄せた。
「はい」
野草の図鑑をかかえて京王線の目白台まで歩いた。
ちょうど良く新宿行きの各駅停車が来た。
南平の駅に着くと、夕日が山の陰になろうとしていた。
熊野神社の石段を登っていくと、狛犬の脇で誰かが寝ている。そばによって見ると、大鳴子百合のお酒を飲んだあの中学生だ。
女の子が寝返りを打った。
スカートの下から太い尾っぽでてきた。
あの狸の子だ。
まったくこんなところで寝てしまっては、からだをこわす。女の子を背負うと、家に帰り布団の上に寝かせた。
大鳴子百合のお酒は、飲んだ後の香りがいつまでも口に残る。
貝新のアサリの佃煮の茶漬けにしよう。日本橋の貝新にしよう。
居間で茶漬けを食べていると、隣で寝ていた中学生が子狸になって居間をのぞいた。
「茶漬け、食べるかい」
と声をかけてみた。
だけど、狸の子は下を向いてペロッと舌を出して、ちょっとばかりおじぎをすると玄関を開けた。
「気をつけてな」
きっとはずかしかったんだ。
玄関を閉める音がした。
大鳴子百合 - 茗荷の舌7
私家版 子狸不思議物語「茗荷の舌 2016 一粒書房」所収
木版画:筆者


