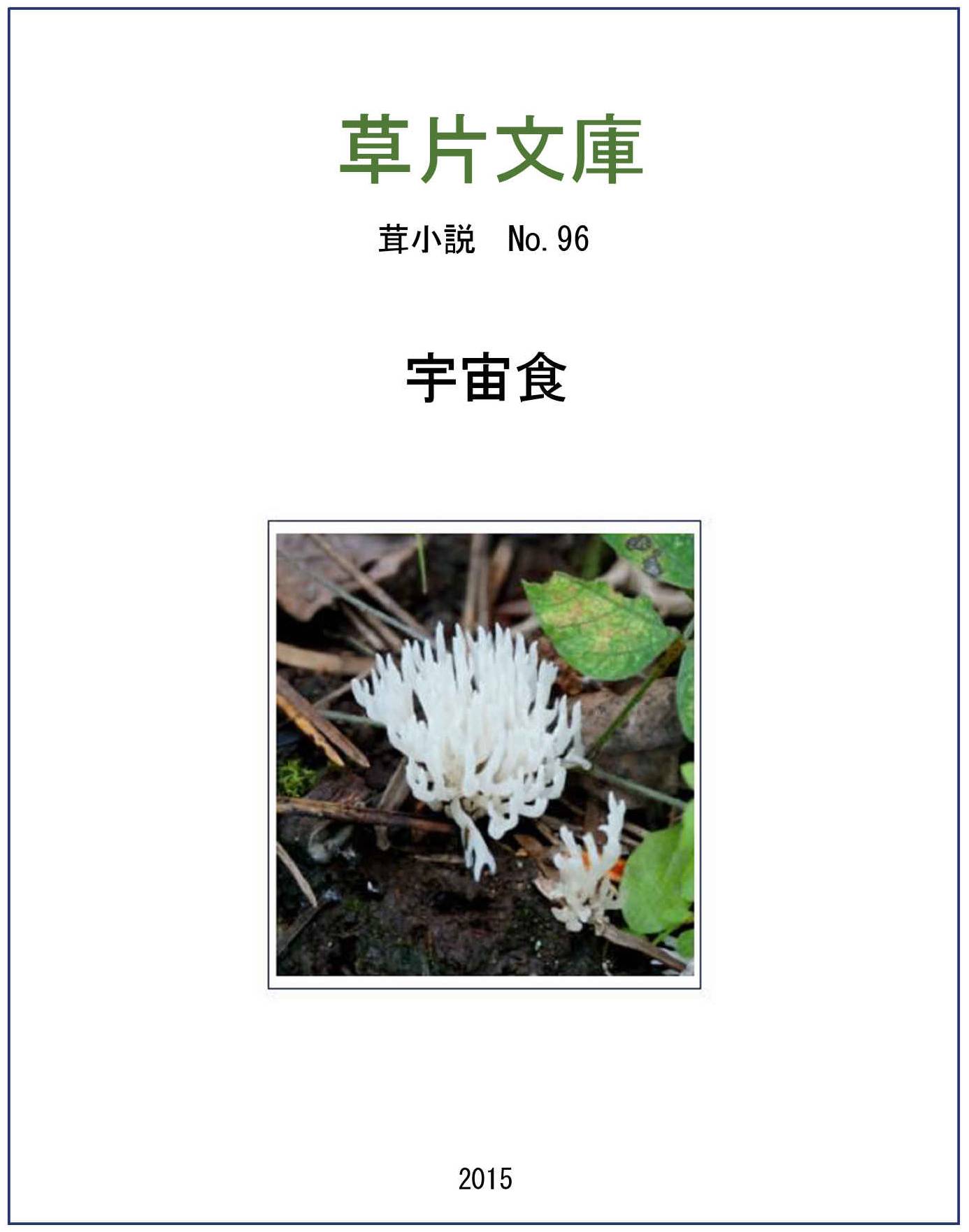
宇宙食
百光年先にある星に旅立つことになった。
地球にある最も早い宇宙艇に乗って旅に出る。地球としてはじめて開発された異次元空間を利用した超光速宇宙艇である。
この宇宙艇にのるために血のにじむような辛酸をなめた。様々なトレーニングを受け、すべて最上級の評価をもらわなければ第一段階をパスできない。
その昔、アメリカという国が地球の周りに宇宙ステーションを浮かべ、スペースシャトルという自力では地球から発進できない乗り物をつくってステーションへ行った。それに乗るためにはそれぞれの国で代表として選ばれ、アメリカであらゆるトレーニングを受け、その上で抜擢されなければ乗れなかった。
超光速艇にのるにはそれよりもっと狭き門である。地球にはこれ一台しかない貴重な船である。はじめて太陽系をでて、外の星に行こういうのである。技術的なトレーニングの後は、コミュニケーションのトレーニングである。女性だけの集団に一年間、男性だけの集団に一年間、さらにトランスジェンダーの集団に一年、合計三年間そこで働かされ、宇宙人と遭遇したときに相手とつきあう技術を学ばされた。国際宇宙大学をでるのに十年かかる。全世界からきた卒業生は一万人、その中からたった十人が選ばれる。乗組員は百人なのだが、人間十人以外の九十人は脳の部分だけ人間のものが使われたサイボーグである。脳の構造以上のコンピューターはつくることができなかったのである。人の脳の千分の一の機能を持つコンピューターが最高のもので、それも一つのビルの大きさになってしまった。光速宇宙艇よりも大きい。
宇宙艇の中には、百名分の個室が備わっていた。2DKで、リビングは50平米とかなり広い。基本的にストレスがかからないように配慮されている。自分の趣味のものも持ち込んで良いことになっている。九十名のサイボーグになぜ個室が必要なのか、人間を知るものならわかるであろう。人間の脳には遊びが必要である。ストレスは脳の機能を低下させる。それを阻止するには遊びが必要だ。人の脳が入っているサイボーグは人と同じようにストレスにかかると機能が低下してしまう。
我々十名の人間はサイボーグのメンテナンスが一つの仕事でもある。科学的な判断はサイエンティストと名付けられたコンピューターに近いサイボーグがする。足はなく車のついた四角いコンピューターであるが、中には人間の脳が八つ入っており、人口神経繊維でつながれている。感覚器の役割を持つリサーチャーというサイボーグが実際の観察や、メーターからデータを読みとって、それをサイエンティストに送る。すると、サイエンティストはその科学的意味を解析し論文にまとめる。純粋な人間一人より、八人の脳をもつサイエンティストの判断力は抜群によいバランスを持つ。
艇内には病院もあり、医師免許のあるサイボーグがつとめている。そういったサイボーグたちは人間の形をしている。
飲み屋もいくつかある、サイボーグたちは仕事が終わると、そこで好きなものを飲む、もちろんお金も払う。地球での生活を再現しているのである。四角い箱のようなサイエンティストにも手もあり、口目鼻耳があり、それぞれ感覚器がそなわっている。味がわかり、飲むこと食べることは、宇宙旅行の一つの楽しみとして、その仕組みが組み込まれている。脳に潤いと活力をあたえることになる。
このように、サイボーグとともに、厳重に管理された光速宇宙艇で、初めて未知の宇宙への旅立ちである。しかしなにが起きるかわからない、従ってそれぞれの肉体なり、脳は厳しくトレーニングされている必要がある。科学的な判断もそれぞれでしなければならなくなることも想定される。サイエンティストに頼らないでもやっていける体制も必要である。人間の役割はやはり大きい。将来、異星人との遭遇も想定しなければならない。どのような異星人がいるかわからないが、最終的に人間が地球の代表、責任のある生き物として挨拶をすることとなる。
サイボーグの重要な役割の一つに船の防御がある。戦闘が必要になったときに働けるようにも戦闘機能が組み込まれており、すべてのサイボーグが、いざというときには戦闘員になる。
サイボーグにとって性の問題はなかった。脳のその回路は遮断されている。異性を意識したり欲したりすることはない、人間の乗組員も同様である。十年におよぶ旅では、一回飲むと一年は作用する性遮断剤がある。宇宙艇の中では毎年医師によって処方される。地球に戻ってきたときそれは回復する。
人間ばかりではなくサイボーグの中の脳は生きている。宇宙船の生活がストレスフリーになるように工夫されているが、脳の性能を維持するには医療的配慮も必須である。ストレスは大脳皮質の容量を越えた使い方をすると生じるものである。大脳新皮質のトラブルは自律神経系に強い影響をおよぼす。大脳新皮質のオーバーワークが自律神経機能に伝わらないような遮断剤も開発された。変調を来たした場合、それを飲み一晩睡眠をとると、脳も含めからだも正常に戻る。
気に入ったものを食べるのは肉体の維持だけではなくストレスを和らげる。宇宙旅行では食事の材料を供給する仕組みは重要である。多くの食材が室内での栽培や、細胞培養で作ることができるようになった。人々が欲していたのは、栄養があり、味が良く飽きることなく、いつも新鮮な食べ物である。いつも一定の品質と収穫を確保する機械が開発されており、宇宙旅行に欠かせないものである。
室内での栽培、培養を行うサイボーグは五人もいた。さらに、それに人間が一人ついている。宇宙旅行で最も重要なセクションとしてとらえられている。
そこに私がいるのである。フードチーフと言うポジションである。これはただ食材を生み出すだけではなく、料理を行うセクションでもある。給食係なわけである。
そう言ったポジションであっても、宇宙艇の操縦も一応マスターしている。それなのにこのポジションは最も競争率の低いところである。だれもが宇宙艇の主任操縦士や調査主任になりたがる。帰ってくれば、英雄の中の英雄と言うだからだ。どちらかが船長になることができる重要なところだ。その次に希望者が多いのは防衛主任である。軍隊と言うことになる。操縦と調査に副主任が一人ずついるが、防衛は二人いる。あとは主任だけしかいないが、折衝主任、通信主任、アンドロイド担当主任、それに食料主任、要するにフードチーフで私である。
宇宙艇の打ち上げまでに、すでに艇内でいろいろな食用野菜、特に茸類は生産を始めていた。消化がよく、滋養に富み、それに味が良くなければならない。サイボーグたちにもそれらを含んだ液を、味を感じる装置を通して血液に送り込む。脳が喜ぶわけである。一杯飲むと言うことも許されている。
昔、SFの中で、人間を冬眠させ、何十年も旅をさせる話がたくさんあった。研究が進められた結果、いくらそのような装置ができても、化学物質の劣化は抑えられないということが明らかにされた。今では、我々の寿命である125年の中で、長くて20年の旅が程良いと考えられている。むしろ、光速度の何百倍もの早い宇宙艇を作ることで早く遠くにいけるようにすることが要求されている。
脳の安らぎをもたらす条件で旅を続けるのが一番良い。その条件の一つが食べることである。生きるための究極の本能にともなう楽しみである。性の楽しみは脳とからだの疲労がともなうことからカットされたのである。
乗組員全員、一月前より宇宙艇に住んでいる。十人の人間は時々、自分の家に帰ったりしているが、独り者の私は一度も地球の上に降りていない。家も引き払い、戻ってきたときはしばらくホテル暮らしのつもりである。
明日、朝早く宇宙艇は離陸する。送別会は一月前にすでに終えている。今日もサイボーグの栽培係がいつもと変わりなく、人工栽培の野菜、茸、細胞培養の牛肉、豚肉、鳥類の肉を管理している。私も時々見回る。
出発の朝の食事は流動食のみで、宇宙空間に達したとき、あらためて、各人の部屋に給仕が朝食を運んでいくことになっている。それまで人間は宇宙艇の最前部のビュールームで、太陽系のはずれの宇宙空間に達するまで、周りの様子を観察する。私も含め乗っている人間は、すでに太陽系内航行の豊富な経験がある。しかし太陽系からでるのは誰もが初めてである。大気圏をでると、光速になり、五時間ほどかけて太陽系からでると、光速の二十倍になる。光よりはやく飛ぶことはできないという物理学は、異次元利用により否定されたのである。銀河系は十万光年の大きさがあるが、銀河系の中の百光年先の星には五年かかるということになる。往復十年である。
この技術は日本地域が開発したものである。神風速度と呼ばれている。昔日本と呼ばれていた国で、国制度がなくなってから、日本、ハワイ、台湾、などの太平洋の島々すべてが日本地域になった。他に、イーユー、アフリカ、昔のカナダを含むアメリカ、チャイナ、インド、ロシア、アマゾン、オーストラリア地域があり、この宇宙艇に、それぞれのところから一人、それに、地球ユニオン組織から一人で十人の人間が乗っている。私は日本地域から選ばれた者である。
出発の朝、全員予定の時刻にビュールームに集まった。
八時になったとき、昔ながらのベルがなった。これが出発の合図である。船長のアメリカ地域のフォックスがスタートのボタンを押した。ナマズのような格好をした宇宙艇はふわりと地上に浮き上がりそのまま大気圏外にでた。このときが一番きれいである。大昔、初めて宇宙にでた人間が地球は青かったと言ったようだが、いまでも誰でもこの瞬間が宇宙への旅の中で一番印象的である。
宇宙艇は太陽の脇を通り、一目散に太陽系をでようとする。太陽の脇もきれいだが、すでに加速されている宇宙艇から直接見ても感激は強くはない。ただスクリーンが時を止めながら映し出す。
我々は太陽系からでる時まで、ビュールームで外の様子を直接見る。
太陽系をでる時間にせまった。
十人の人間が壁一面に広がったスクリーンを見る。冥王星が近づきあっという間に後ろにさっていく。ここで船長がフロントの赤いボタンを押した。神風ボタンである。これから光速の二十倍の早さで航行する。五年間すすみ、その間に空気のある適した星がキャッチされると、減速し詳しく観察しながら、目的の星につき、そこで観察を終えると帰る旅となる。
サイボーグたちは逐次状況を地球に送り続ける。それは、地球の管制塔でも我々乗組員と同じ体験ができる。それに加え、十人の人間は自分の感想を交えた日記のような記録を書くことが義務付けられている。人によって同じ物でも見え方、考え方が違うからである。
そのように一日一日が過ぎていった。
退屈しないように自分の趣味を部屋に持ち込んでいるが、それでもあきる。そのために運動や娯楽の施設にいく。
毎朝の会合をのぞいて、自分の部屋を中心に生活をすることになる。部屋備え付けの計器類で培養室の様子はわかるので、見回りも日に二三度である。
朝起きてしばらくすると給仕が食事を運んできた。
「今日のメニューはなんだったかな」
女性の姿をした給仕はハスキーな声で、
「はい、マスターの献立はスクランブルドエッグに茸サラダ、ハムを挟んだバケット、それに紅茶でございます、果物は林檎です」
優雅にテーブルの上にトレイを置いた。
「栽培はうまくいっているね」
このサイボーグはマリリンと呼ばれているフードサプライのスタッフで、給仕もするが、茸の栽培係でもある。さらにパブの経営者でもある。パブにはほとんどの酒がそろっている。酒マシーンがあり、あらゆる国の領域の酒を、しかも、昔からの有名な醸造所のものを作り出すことができる優れものである。この機械も日本地域がつくりだした。
ゴンバという名前のマリリンのパブは、人間にもサイボーグにも人気で、夜になると満員になる。ゴンバはハンガリー地方の言葉で茸を意味する。
マリリンは優雅におじぎをしてでていった。マリリンは誰の脳をもっているのだろう。サイボーグの脳の提供者は秘密になっている。生前から脳を提供することを希望し、サイボーグ法で定まっている脳の機能を有する者の脳である。脳に器質的な異常がないこと、一定以上の教育を受け、公平な判断力を持つ脳でないと使われることはない。高級なサイボーグほど上質な脳をもっている。この宇宙艇に乗っているサイボーグは全員超特級クラスの者たちである。
朝食をゆっくり食べたあと、栽培のスタッフと朝の見回りに行った。それぞれの畑(畑と呼んでいるが、水耕栽培の棚である)の野菜の発育状況、肉の細胞培養状況などを、細かな数値を見ながら、外観を観察するのである。ほうれん草も、ピーマンも、セロリもよく育っている。茸も良い。担当のサイボーグも一緒に様子を見回る。
「ハンク、果物の様子もいいようだね」
「はい、マスター、桃が食べごろです」
「今日あたりの料理に出せるだろう」
ハンクは果物全般の専門サイボーグである。
調査する星が見つかるまでは、ともかく、フードサプライの我々の部署が最も忙しいわけである。
こうして一年が過ぎようとしたとき、一つの星がアンテナにとらえられた。地球の半分の大きさほどの惑星で、二つの恒星のまわりを八つの惑星が回っており、恒星から三つ目の惑星である。地球と同じような条件である。
宇宙艇はその星に接近する準備をはじめた。光速の二十倍ですすむ宇宙艇を止めるのは大変な作業である。その星はそこから光速で一月かかるところにある。そのままで行けば二日あれば付いてしまう。順次速度を落とし、三日後に付くように停止命令を出さなければならない。
こうして、一日でその星に到達するところまでになった。
「あの星は、生き物がいる可能性が高い、コンタクトがどのようになるのか、今地球ともやりとりをしている、もし高度な生きものであるならば、まず友好的に、不可侵の条約を結べとはいわれている」
折衝の主任の役割が重要である。コンタクトをする前に、相手を研究しなければならない、防衛担当からもらう情報に、自分でその星から得たデータをくわえ、言語を理解し、話すことができるようにならなければならない。もっとも言語を解析するのはコンピューターの役割であり、話すようになるのはサイボーグの役割である。折衝主任は、その星の住民を見て、直感を働かせなければならない。
その星をとらえたときから、映像を拡大する能力を持った特殊な望遠鏡でその星の状況をスクリーンに映し出している。
その星の映像を見ると、地球とほぼ同じような大気組成である。拡大でみると、水があり、陸があるが、緑色が見えない。植物が見当たらない。だが、生き物がいて、町を作っているという解析結果である。人工物があるのなら、必ずその映像はとらえられているはずである。しかし視覚的には、土、水のみである。海ではない、淡水である。この星の半分ほどは水、湖であり。半分は土である。地殻の中はマグマのようである。
「おかしいな」
ウイリアム船長のつぶやきが聞こえる。
いくら倍率を上げても生き物らしき物が見つからない、それに水の中にも全く生き物のいる気配はない。空中にもいない。
「やっぱり、どうかしている」
コンピューターとサイボーグによって解析されたデータを見て、船長は何度も首をかしげ、解析画面を睨んでいた。
「空気があるのに動いていない、風がないようだ」
「と言うことは、温度の変動がないのですね」
私も船長のもとによってデータを見た。
「そうなんだ、この星全体がコントロールされている、おそらく、水にしても、土にしてもすべて、ここの住人たちによって調節されている」
「それは、今見えているこの星の様子は本物ではない可能性もあるのですね、我々が見ていることを知っていて、分かりやすい形に調節しているということですね」
「そうだ、もし、この星に降りたとすると、今の状態ではなく、その星の住人の環境に降りることになる。空気もなく、水もないかもしれなということだな」
「我々の予想を超えた生きものですね」
防衛主任がやりきれないような声を上げた。予備知識なしの状態で船を守るのは容易なことではない。
「降りるのを避けましょうか」
「地球と連絡をしてみよう」
ウイリアムスが状況を地球に通知をした。科学的な解析データだけではこういうことは見えてこない。ある意味では地球が持っている解析機能をだますことのできる科学力を持っている星ということになる。
地球からの返事はちょっと時間がかかる。それでも数十分の後に連絡があった。
返事は、地球からのその星(N1)の解析結果は、星から発進された虚構の映像と言うことではないことないだろうという結論である。船長たちが想像したような生命体による陸空海のコントロールもないだろうということだが、なぜ空気や水が動いていないかということに関しては不可知という結果である。このギャップの理由が分からない以上、着陸は控えるべきである。
地球からは、この星と必ずコンタクトをとるようにとある。
これは難題である。
「星そのものが生き物なのでは」
副操縦士のアランが言った。
「そういう、SFが大昔あったな」
「もしそうなら、星自身が自由に動いていても不思議がないが、データによると、恒星の周りを一定の物理の法則に則って回り続けていることは間違いがない」
「どうしてもわからないな、ともかく、こちらから通信をし続け、もし反応があり、大丈夫そうなら着陸の許可を得るようにしないといけないな、あらゆる言語方式でその星に向かってこちらの意思を発進しておこう、ともかく我々は侵入者ではないことを納得してもらわねば」
通信主任のデルネルは別の画面にいろいろな言語方式を映し出した。
「もう、文案はできています、後はタイミングを見計らって、発信するだけです」
「いつでもいいから、発信してくれたまえ」
船長の言葉でデルネルはパネルを操作した。
「どのような反応があるのか楽しみだがな」
「そうですね、どのような能力を持つ生命体か全くわからない状況ですので、何度もいろいろな形で連絡を繰り返すしかないでしょう」
デルネルはいつ返事が来てもうけられるように、スクリーンを調節した。
その返事は意外なほど早くきた。
夕食を部屋でとっていると、部屋の壁に設置されているスクリーンの一つに十の言語で返事があった。マスターたちの言葉である。
どの言語でもだいたい読めるようにトレーニングを受けているが、私の国の言葉は日本語である。
それにはこう書いてあった。
「あなた方を歓迎します。遠い宇宙からいらした方とは不可侵条約を結ぶようにしています、それさえ終われば、ゆっくりと我が星、菌星でお休みください」
とあった。
私もそうだが、みな急いでビュールームに集まった。
「何という早さだ、しかも、すべての言語で返事があった、いったいどのような文明があるのだ」
「それに、人間が十人乗っていることを相手は知っている」
「気味が悪いくらいだな」
「彼らはこの星のどこにいるのだろう」
「土の中にもそれらしきものがありません」
星の探索は微細な部分まで行なわれた。
そうこうしているうちに、宇宙艇は星の近くに達してしまった。船長は船を止めた。星を肉眼でも見ることができる。茶色の土に覆われている星である。真水の海が広がっている。
防衛主任のオバマは困っていた。
「これ以上の情報を入手するのは困難です」
「まず、相手と会話を続けよう」
副主任のカーターが言った。
「不可侵条約をどのように結んだらいいか聞いてくれ」
「はい」
デルネルが星に向かって連絡をした。
研究主任のハラースは疑問を投げかけた。
「この星の住人は自分の星のことを菌星とよんでいる、菌でできている星という意味ではないのだろうか」
「とすると、この星の住人は菌類かも知れんな」
「しかし、映像には全くそのようなものは映っていないばかりか、顕微解析でも菌類のいる反応はなかったな」
「それにしても、地球の菌類のことをなぜ知っているのだい」
「翻訳を間違えたのではないだろうか」
しかし、ハラースの発想は後で正しいことがわかるのである。
そこへ、菌星からメッセージがはいった。
「よくいらっしゃいました。我々の星の周りを回る必要はありません、直接着陸してください、誘導します、その後、不可侵条約を結びましょう」
折衝主任のロドリゲスがどうしましょうと、船長を見た。
「どのような誘導なのか、心配ではあるが、どのような形であれ、我々は捉えられているのと同じかもしれない」
船長が決断を下した。
「行くしかないだろう、これだと、いくら星の周りを回っていても同じような気がする」
それを菌星に伝え、宇宙艇のプロテクトバリアーのスイッチを切った。宇宙艇は自動的に操縦され始めた。
「どうやって、我々の船を操縦しているのだ、恐ろしい」
「成すすべがないな、相手を怒らせないようにするしかない」
みな頷いた。
サイボーグたちがあわただしく動き、宇宙船は、静かに大気圏に向かって降りていった。
ここで不思議なことに科学者の主任が気がついた。大気圏と宇宙空間の境が突如現れ、その大気の組成が一様なのである。重力があれば、空気の中の成分にグラデーションができるはずである。それがないようである。
解析をしているサイエンティストが「重力がほんの少ししかありません」と連絡して来た。もしそうなら、生き物は巨大なものになっているはずである。
宇宙船はゆっくりと陸地におりていくが、地上には生き物らしきものを見ることができない。
空気組成を解析していたサイエンティストが結論をまとめた。
「酸素分子、窒素分子、空中のあらゆる化学分子が固定されています。振動はしていますがフラフラしていません。何かによってつなぎ合わされています」
「では、熱がでないと思うが」
「いや、大気の温度は上も下も、なぜか一定になっています」
そう言っているうちに、宇宙艇は陸に着陸した。完全に誘導されており、着陸したときの衝撃が全く感じられなかった。
宇宙艇の操縦室のランプが、着陸のシグナルを発した。
ビュールームから見た景色は、植物がないだけで、地球とよく似ていた。
スクリーンに映像が映し出された。しかも音声もながれてきた。
「よくいらっしゃいました、空気組成は、地球のみなさまに害にならないものと思います。どうぞハッチをお開けください」
文字が流れると同時に、スクリーンに地球人と同じような、小さな顔が映り、無数に整列している顔が同じ形で口を動かしていた」
分析をしていた調査主任が驚いたように言った。
「この映像は空気を超高倍率で映しだしたものだ、あれが、ここの住人だ、酸素分子や窒素分子の間にいて、みな手をつないでいる」
「ということは、ここの空気は住人と言うことになる」
「もし外にでたら、我々の肺の中にここの住人が入ってくるのではないだろうか」
スクリーンに字幕が流れ、この星の住人が声を出した。
「そろそろハッチをあけましょう」
私はすぐにこれは危険だと思った。叫んだ。
「防御服を着て、空気を濾過する装置を働かせるようにしないと危ない」
だが、防衛主任や、船長は笑っていた。
「フードサプライ主任、それは大丈夫だよ、彼らが我々の肺に入ったりして、からだの中にはいっても、免疫機能が働いて、彼らは死んでしまう、きっと、我々に供給してくれる酸素は住人のいないものなのだと思うがね」
「そうでしょうか」
私は自分の部屋に戻ると、ヘルメットをかぶり宇宙服を着用した。
その格好でビュールームに行くと
「日本地域の一郎君は怖がりだね」
と笑われてしまった。
そうこうするうちに、菌星の住人によって、宇宙船のハッチが開かれてしまった。
菌星の大気が船内を満たした。
船長が先に外にでた。
「出迎えの人は見えないが、少なくとも空気は大丈夫だ」
その声で皆も外にでた。私は宇宙服を着たままでた。
そこで我々の目の前の空気が凝縮し、人間と同じような形の者が出現した。
「よく、いらっした、これから不可侵条約を結ぶとしたいが、いかがかな」
その影がそう言うと、影の手には紙とペンが用意されていた。しかもそこに机が現れ、不可侵条約の文の書かれた紙が十枚置かれていた。
「まず、こちらのほうから、サインします」
影はそれにサインをした。船長もサインをした。菌星のサインは、指紋のような渦巻きが書かれていた。
「我々は、どことも戦争はしません、あなたがたもそうでよかった」
その影が言った。さらに、
「皆さん全員にサインをお願いします」
皆もサインを始めた。最後の私の番になったのだが、私は宇宙服を着ており、脱がないとサインが難しい、私は「服を脱いできます」と宇宙艇に戻ろうとしたとき、船長が影に尋ねた。
「みなさんの住まいはどこなのでしょう」
「大気、水、土、すべて我々のすまいです、原子レベルの住居が空気の分子の中にあります」
「私たちはあなた方を吸い込んでいる、これはどうなるのでしょう」
「今、不可侵条約を結びました、お互い、相手の星を攻撃しないことになりました、それは往来自由と言うことです。地球の方々の分子の中に私たちははいりこみ、一緒になるのです」
そう言ったとき、船長の体が倍に膨れた。他の者たちもどんどん膨れていった。最後は霧のように消えてしまった。
この星の住人が地球人の体を大気にしてしまったのである。体は分子になり、菌星の住人とともに大気の分子の間に入り、手をつないだのである。それが不可侵条約だった。
私はあわてて宇宙艇に逃げ込むとハッチを閉めた。宇宙船を離陸させるように指令し、菌星からの誘導を断ち切るよう、サイボーグに言った。サイボーグは宇宙艇にバリアーをはり、離陸の準備をすすめた。
ただ一つ問題があった、宇宙艇の空気の中にはここの住人がいた。宇宙艇の空気は固まっているということである。宇宙艇の中の空気はいつも作り出されているからなくなることはないが、このまま地球に帰ると、地球の大気で菌星の住人が増えることになる。高度な文明を持っている菌類なのであろうから、地球がどのような状態になるかわからない。おいそれとは帰ることはできないだろう。
まず、状況を地球に報告した。返事はすぐ帰還するようにと言うことであった。それと、「菌類ならば消毒をしてみること」と連絡があり、アルコールをはじめいくつかの殺菌薬を空気循環器の中に入れてみたが、かわりはなさそうである。
スクリーンには菌星からのメッセージがときどき届く。
「あなたの仲間は菌星人になって、幸せに暮らしています、あなただけは、私どもと不可侵条約を結ばなかった、残念です」
とあり、そのあと、「この星の住人になって、とてもハッピー」と船長からのメッセージがとどいた。
分析のサイボーグが、船内の一部の空気が固まったままであることを報告してきた。そこに菌星人たちがいるのである。
その間に、宇宙艇は宇宙空間に飛び出た。
途方に暮れているとき、マリリンが培養室に入っていいかどうか聞きにきた。開けないように言っていたのであるが、もう管理をしないとすべてだめになるリミットである。
光速の二十倍になった。一年ほどの帰還の旅である。
いったん真空にするという手がある。ちょっと命がけではあるが、試してみる価値はあるであろう。十年の旅の予定であったので酸素を作る装置はまだまだ余裕がある。どのみち宇宙服を着ていないと私が消滅する。
サイボーグに言って、超光速停止を命じた。まず、超光速ではハッチをあけることはできない。宇宙艇を止めなければならない。それにはしばらくかかる。減速をし、惰性で動くのを停止することで宇宙空間に浮かぶことができる。
その間ともかく生き延びなければならない。
マリリンが野菜がだめになっていくことを報告してきた。どうせすべて真空にして、菌星人たちを追い払うのである。
マリリンに戸を開けて培養室の中を調べるように言った。
マリリンがまず、肉質の培養室をあけると、牛肉、豚肉の固まりが半分消滅している、魚類も同じであった。戸を開けて、空気が入ると、その肉類たちは、膨れていき、やがて消滅した。菌星人たちに入り込まれ、膨らんで分子になって、菌星人のあいだに入り込んでしまったのである。おまけに、菌星人がどんどん増えているようである。
野菜類の培養室をマリリンが開けた。
野菜も茸類もみなしおれている。ところが開けたとたん、野菜は消滅したが、茸の類はだんだんみずみずしくなってきた。マッシュルーム、ボルチーニ、椎茸、杏茸、網笠茸、衣笠茸、しかも分裂を始めた。
それだけではない、茸たちが培養から飛び出し、宇宙船の中を飛び回った。ぴょんぴょんととびはねるのである。そのうち、茸に手が生え目ができて口ができた。
大きな網笠茸が私のところにやってきて、
「宇宙服をおとりよ、もう大丈夫だよ」
と言った。
驚いた私は「どうして」と聞き返した。
そこへ防御担当のサイボーグがきて私に言った。
「空気の中の菌星人はいなくなりました」
「どうしてだ」
「わかりません」
それを聞いた茸が言った。
「おれたちがみんな吸収した、そうしたら、ほら、動くようになった。菌星人は茸をつくることのできない菌類だったのだよ、我々地球の茸がその能力を吸い取ってしまった。菌星人は我々茸の中にいる。とても便利だ、頭もいい」
私は宇宙服を脱いだ、久しぶりの空気をすった。
気持がいい、衣笠茸が二つよってきて、培養室に茸の栄養素を入れるように要求してきた。
マリリンに頼むように衣笠茸に言うと、うなずいてマリリンを探しにいった。
動くことができるようになった茸は私にいろいろな知識をさずけてくれた。
菌星の文明は発達している。物質を分子レベルでコントロールする機械を作り出す能力を持っている。それらの機械はやはり分子の大きさのもので、人間の目には見えない。それを使えるようになった茸たちは動けるようになり、自分の体から映像を送ることもでき。宇宙船を誘導することもできる。ただし、自分たちで何かを作ることはできない。そこにある物を自分で動かすことはできる。その点、人間は脳という指令装置をもち、体を動かし、物を作ることができる。動く茸と人間が手を組めば、あらたな地球が誕生するだろう。
菌星人は自分の星からでることができなかった。菌類だが子実体、すなわち茸を作ることができない。ところが地球から来た生き物の中に茸がいた。その茸に空気の中の菌星人は吸い取られ、同化してしまった。地球の茸が動く生き物になった。動くのだから動物である。
私は、その動茸(どうじ)たちと仲良くなった。彼らはよくしゃべり、素直に私たち人間のことを尊敬してくれている。地球に戻っても、人類と仲良くやっていけるだろう。
気になったのは人間である。人間は排他的である。動く茸を素直に受け入れてくれるだろうか、見下したりしないだろうか、それが心配であった。そんなことを動茸たちに聞かせたら彼らは笑った。
「おれたちの考えを地球の生き物たちに直接伝えるよ、我々には誰とでも仲良くする能力があるんだよ、それが伝われば、争いもなにもかもなくなる」
将来、動茸たちと手を組んで、異星の生物達に平和を伝える役割を我々は担うことになるのだろう。
それに、彼らは月に住みたいと申し出ている。月に大気を作り出すことが出来るとも言っている。
それらのことを、地球に通信した。
地球からは、大統領府からそのようにしたいと、返事があった。
これでやっと地球に帰ることが、怖くなくなった。
初めて自分の手で超高速宇宙船の赤い出発ボタンを押した。
宇宙食
私家版 第八茸小説集「遊茸空、2020、一粒書房」所収
茸写真:著者: 山梨県北杜市小淵沢 2013-9-16


