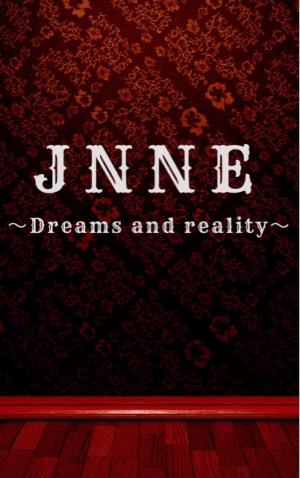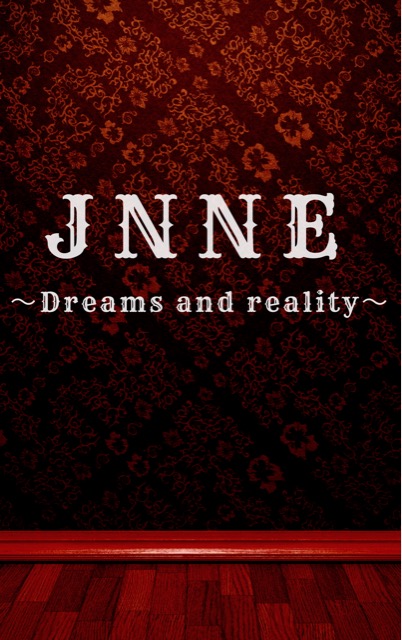
JNNE〜Dreams and reality〜
Episode1 〜記憶のはじまり〜
「血と闇、そして絶望に飢えているその目をもっとよく見せてくれ…」
「違う!俺じゃない!」
私ははそう叫び、目を開いた。時計に目をやると午前2時。
「またこの夢か…」
そう呟き、深いため息をつきながら疲れた身体を無理に起こした。
「もう、うんざりだ…」
ぽろりと言葉がこぼれる。
私は連日、気が狂いそうなほど同じ夢をみていた。
「いったいなんだよ…この夢は」
額に手を当て考え込む。毎回こうだ。
夢をみては考え、なにもしていない時でも無意識に夢のことを考えている。
そして再び眠りにつく。そんな毎日を送っていた。
眠りたくない。だが、疲れた身体は悲鳴をあげる。今日も意識を飛ばすように目を閉じた−
「…たか」
身体を裂かれるような低く、冷たい声。
それは連日耳にする、聞き慣れた声。
「来たか。会えるのを楽しみにしていたぞ」
その声はそう語りかけてきた。
「またか…。一体、お前は誰で、この夢はなんだ…」
私は疲れ、冷え切った声で男に問いかけた。
この夢は妙だ。夢の中では自分の意識は現実のように制御できる。それに、夢の中で起きたことは事細かに覚えており、忘れることができない。まるで記憶に鋭いナイフで刻み込まれているようである。
「お前は過去から続く呪い。俺とお前は同じ存在…。お前の知りたいことはじきにわかるさ…」
男はそう言うと、なにやら不気味な笑みを浮かべているようだった。
姿は見えないが、その男からは、どことなく悲しそうな、暗闇の中に囚われているような、だがそれを楽しんでいるかのような雰囲気が伝わってきた。
「俺は、お前みたいな奴は知らない。それに、これはただの夢だ…」
私は少しだけ口調を強くし、男に言った。
すると男はしばしの間無言になり、静かに囁いた。
「本当にこれは夢か?」
男の口から出た言葉に、思わず黙り込んでしまった。
以前、夢の中で怪我をしたことがあったが、些細な怪我だった為、気にせずにいた。しかし、それは目が覚めても残っていた。知らぬ間に傷つけたのだろうと気にせず放っておいたが、それにしては不自然な傷だったのだ。
男は更に話し続けた。
「記憶は風化するものだが、この夢の記憶は決して風化することはない。お前がこの世界を訪れるたびに、この世界の記憶は濃くなる。そして、お前のいる現実は徐々に薄れ、いずれは無くなる」
私はその言葉に固唾を飲んだ。男の話は、理解するのも難しい上に、到底受け入れられるような話ではない。だが、なぜかそれを信じてしまう。その理由はいくら考えても分からなかった。
「現実が無くなる?そんな事があり得るか…ある訳がない…」
男は楽しげに、そして試すように言った。
「お前は、現実が本当に現実だと思っているのか?そんなものが存在すると?」
常識を逸脱した質問にため息をついた。現実が本当に現実かと言われれば、答えは決まっている。
「あるに決まっている。現実が存在しなければ、俺たちはどこに住んでいて、何者なんだ?」
だが、そんな当たり前の考えと同時に、男の言葉を納得し得る考えも持つようになっていた。
夢は夢、現実は現実なのはわかっていた。
しかし、連日同じ夢をみて、その夢の中で会話をし、現実の事かのように脳裏に刻まれ、忘れることの出来ない体験をしている。
なにが偽りでなにが真実か、困惑していた。
「仕方がないな。これが現実だと分からせてやるよ」
少しだけ間をおくと、男が暗闇の中から姿を現した。深い闇のように漆黒のローブを身に纏い、顔は深いフードで覆われ確認できない。その者はまるで闇そのもの。
「腕を出せ」
男の要求に私は抵抗できず、右腕が不自然に差し出された。なにか見えない力が働いているようだった。
男は物静かに私の右腕を手に取った。男の手はまるで死人のように冷たく、生気が感じられない。全身が冷え切ったような感覚に陥った。
男は細かい細工が施された鋭利な刃物をちらつかせ、私の腕にその刃を走らせた。
肉を裂かれる痛みが襲う。激しい痛みに、額に汗を滲ませながら男から腕を振り解こうと必死に抵抗した。
男は楽しんでいるかのように私に言った。
「この傷と痛みがお前に分からせる。また会おう」
そう言うと、男はゆっくりと暗闇の中へ消えてしまった。
ふと足元に視線を走らせると、そこには古ぼけた木製のロザリオが落ちていた。ロザリオを拾い上げると、激しい頭痛と共に目の前が真っ白になりその場に倒れこんだ。
―ジリリリリリ!
静けさを切り裂く甲高い音で私はベッドから飛び起きた。
周りを見渡す。そこは当たり前のように生き、生活している世
界。
いつものように疲れた身体を無理に起こした。
その時、右腕に鈍い痛みが走った。夢の中で謎の男に切りつけられた傷跡。
傷口からは燃えるような真っ赤な血が滴り落ちている。
私はその時確信した。夢と現実の繋がりを。
痛みに震える腕を必死に堪えながら手当てをし、着替えを済ませ自宅を後にした。
いつものように仕事をし、当たり前のように時間が過ぎる。
自然とあの男の言葉が繰り返し頭をよぎる。
―本当にこれは夢か―
現実と夢の違いはなんだろうか…。現実が存在しないのなら、いったい私はどこに生きていて、何者なのだろうか…。
そんな考えばかりが思考を支配する。
そして、右腕の傷が語りかけてくるように、鈍く痛む。
当たり前のように生きているこの世界に対して、疑問を抱かずにはいられなかった。
あっという間に過ぎさる毎日。
そして今日という日も終わりを迎える。
暗闇の中ー
「待ってたよ」
待ち焦がれたように男は言った。
私は力無くため息をつきながら周を見回した。
そこはいつものような暗闇の中ではなく、朽ち果てた大きな建造物。まるで、中世ヨーロッパの闘技場を連想させる。
建物の支えだろうか、大きく、今にも崩れそうな支柱が所狭しと並んでいる。
目の前に空高くそびえ立つ支柱のてっぺんに、男が座っている。
喪造作に流れる黒い髪、全てを見通しているような鋭く赤い目、全身には漆黒のローブ。男の風貌を見た私は。思わず息をのんだ。
「来たくもないのに来てしまうのが夢。夢と現実の見境がつかなくなるのもまた夢。現実では起こりえないことが起きるのも、夢だ」
男は口元を三日月のように緩め、淡々と話す。
「…お前は誰なんだ。それに、目的はなんだ…」
とっさに男に言い寄る。
私の問いに男はにやりと微笑むとその場に立ち上がり、こちらを見下ろしながら口を開いた。
「教えてやる。この夢はお前が過去に存在していた世界で、お前の記憶そのものだ。俺はこの世界に囚われた存在」
突き刺すような鋭い目でこちらの様子を伺いながら話続ける。
「お前の名はエルオーデ。そして俺の名は、ジャヌだ」
Episode2 〜外れる鍵〜
「エルオーデ!いるんでしょ?遊ぼうよ!エルオーデ!」
目の前に見知らぬ風景が広がる。
白く大きな、まるで古城のような建物の前で少年が声を上げ叫んでいる。
エルオーデ、エルオーデ、その声はどこまでも響き渡っている。
それに応えようと、建物からもうひとりの少年が顔を覗かせる。
「ジャン!ちょっと待ってて!今行くから!」
返事から数分経ったが、少年はまだ姿をみせない。
しばらくすると、建物の入り口あたりにある小さな扉から男が出てきた。守衛だろうか、男が少年に向かいのろのろと近づいた。
「今日はどこに行くのです?あまり遠くに行ってはなりません」
男の問いに少年は一瞥し、声を荒げた。
「わかってるよ!ところであいつ、遅いね」
「エルオーデ様は多忙な方なので」
男はムスッとした顔でぼやくと、建物の奥から少年が勢いよく走ってきた。
「ごめん、遅くなって」
「遅いよ!どれだけ待ったか!じゃあ、行こうか!」
ふたりの少年は勢いよく駆け出し、海がある方へ風を切りながら精一杯に走る。
草原を駆け抜け、大きな岩が犇めく海岸近くにある森を身軽に通り抜け、やがてふたりは視界いっぱいに広がる青々とした大海原の前にいた。
「はぁ…はぁ…ねぇジャン、ここになにがあるの?」
エルオーデは息を整えながらジャンに尋ねた。
「この近くに誰にも知られてない洞窟があるんだ。そこを僕たちの秘密の場所にしよう」
ふたりの少年は、自分たちだけの秘密ができたことに、喜びと興奮に溢れていた。
「そういえば、君と出会ったのもこの海岸だったね」
エルオーデは静かに呟き、永遠に広がる大空を見上げた。
「ジャン、君はどこから来たのかまだ思い出せないの?」
エルオーデの問いに、ジャンは深く息を吐き、ゆっくりと口をひらく。
「まだなにも…。僕の本当の名前だって思い出せない。でもいいんだ、君が名前と居場所をくれたから。僕の名前はジャンで、確かにここに存在してる!」
満面の笑みでジャンは答えた。
ふたりが出会ったのは数カ月前、エルオーデが護衛を連れて海へ釣りに出ている時、海岸に打ち上げられている少年を見つけたのがきっかけだった。エルオーデは少年を連れ帰り、寝る間も惜しんでめんどうをみた。エルオーデがここまでするのには二つの理由があった。
エルオーデは貴族の生まれで父、マクイナス・バンシュタインの方針で、同じ年頃の子供たちとの交流を禁止していた。その理由は誰にもわからなかったが、父は頑なにそれを守らせた。更に、エルオーデの住居は、誰も近づかない切り立った崖の上にあり、人との交流がほとんどない環境で育ち、友と呼べる存在が一切いなかった。
そして、連れ帰った少年を受け入れるのを父は断固として認めず、少年を海へ流すと言った。
エルオーデはそれに猛反発し、母親のリズ・バンシュタインへ助けを求めた。母は、少年を迎え入れるのならば、家からほど近くにある粗末な小屋に住まわせるという提案をし、マクイナスはそれをしぶしぶ了承した。こうして少年はバンシュタイン家に迎えられることとなった。
少年が目を覚ましたのはそれから数週間後のことだった。
少年の悲しげな真っ赤な瞳に、エルオーデは引き込まれた。
目を覚ました少年の瞳を見るや、マクイナスは声を大きく荒げた。
「悪魔の子だ!」
リズは沈黙を守り、冷静に少年を見つめている。
大声をあげるマクイナスを横目に、エルオーデは少年に一言尋ねた。
「言葉はわかる?」
少年は力無く頷いた。
「この子供をこの家から出せ!今すぐにだ!」
マクイナスの怒声を耳にした守衛らが勢いよく部屋に飛び込んできた。それを見ていたリズが遂に沈黙を破った。
「いい加減になさい!何もわからない子に出て行けと言うのですか!のたれ死ねと言うのですか!あなたはいつから心に悪魔を飼っているのですか!?」
突然の罵声にマクイナスと守衛らは口を噤むと後ずさりした。
母の初めて見せる姿にエルオーデは呆気にとられ、一呼吸置いてから少年に尋ねた。
「名前も、わからないの?」
その問いに少年はゆっくりとうなだれ、頭を縦に振った。
少年の悲しげにうなだれる姿をまっすぐ見つめて、エルオーデは考え込む。そしてしばらくしてからこう告げる。「じゃあ、君の名前は…ジャン、ジャンって呼ぶよ」
不思議そうに見つめる赤い瞳。そして少年は呟く。「ジャン…ジャン…」
この世界で古くから聖なる花と知られ、神々の落し物と言われる真紅の花【ジャン・ルナール】から取ったものだった。
それから数ヶ月、ふたりはまるで兄弟かのように接し合い、今に至る。
「なにかあったら、ここで待ち合わせよう」ジャンの生き生きとした瞳は、数ヶ月前とは比べものにならないほどだった。
エルオーデは力強く頷いた。
それから数日後、ふたりは屋敷から数分ほど離れた石造りの小さな小屋にいた。
「これ、何に使うのかな?」
ジャンは床一面に犇めき合う物の中からひとつの焼きごてを拾い上げた。
【J】と刻まれた酷く錆びついたその焼きごては何に使われたものだろうか、ひんやりとした空気を醸し出しているようだった。
それを見たエルオーデは部屋の隅にある暖炉をちらりと見た。「それ、つかってみようよ」と好奇心をみせながら呟く。ジャンは薪木を、エルオーデは火種を見つけ、煤だらけの暖炉に火を注いだ。ゆらゆらと揺らめく炎が、ジャンとエルオーデの顔を火照らせる。
赤々と色付いた焼きごて手に取り、エルオーデは小走りにジャンに駆け寄る。その時、部屋中に散乱する物に足を取られ、ジャンめがけて勢いよく倒れこんだ。
「ああぁ!」
静寂を切り裂く叫びが瞬く間にあたりを包み込む。
焼きごてはジャンの胸を押し付け、どす黒い煙を吹き上げる。
「ああ…そんな…」小さな身体が恐怖と混乱が支配する。エルオーデはジャンの胸に焼きつく焼きごてをの引き剥がし、怯えきった声で言う。「ああ…ああ…僕はなんてことを…」
エルオーデはどうしたらよいか分からず、震える足でその場に立ちすくんでいた。
ジャンは意識が遠のいていくのを感じながら、激しい痛みと熱さに悶え苦しむ。
―ジャヌ…
苦痛が支配する頭の中で微かに女性の声を聞いた。
―あなたよ…
その声はぼんやりと、ゆっくりと近づいてくる。
―あなたは…この世界の―…
ジャンは苦しみに意識を飛ばした。
Episode3 〜【J】の烙印〜
ガサ…ガサ…
草木を踏み分ける鈍い音が聞こえる。
軋む音と共にゆっくりと開く扉にエルオーデは静かに息を飲んだ。
「エルオーデ?あなたなの?」
「母さん…」震える小さな声でエルオーデは答えた。
「ああ…大変、何があったの?誰にやられたの」リズはすかさずジャンに駆け寄り、息があるのを確認しエルオーデに言った。「守衛を呼んできなさい。急いで」
草木をかき分け屋敷へと急ぐ。
「なに…?」
途中のうっすらとした森の中に、ひとり佇む女を見た気がした。しかし、もう一度視線を送るが女はいない。気のせいだと思い、エルオーデは守衛を数人連れ小屋へ戻り、ジャンを屋敷の一室へと運び込むとリズは手慣れた様子で手当てをはじめた。そこへ、マクイナスが何事かと言わんばかりに部屋に飛び込んできた。
「こいつは面倒事ばかり起こす!だからあの時言ったのだ!」マクイナスの罵声が屋敷中にこだまする。
リズはマクイナスを一瞥すると、ジャンの手当てに再び手を動かした。
数時間後―。
静かな屋敷に恐ろしい悲鳴が轟く。
「やめろ!やめてくれえ!」
突然の出来事に驚いたマクイナスは悲鳴のする方へと急ぎ向かった。
壁に広がる真っ赤な鮮血。床に散らばるバラバラになった人の身体。苦悶の表情をした男の首を持つ血に染まった小さな手。
「お前…何をした!?」
目の前には胸に焼け付いた【J】の文字。そして、不敵な笑みを浮かべるジャンの姿。
「ジャン!」エルオーデがマクイナスの後方から青ざめた顔で叫ぶ。
「何をしたの!その首は!?ジャンがやったの!?」声にならない声で必死に呼びかけるその姿を見て、ジャンは言った。「そうだよ。僕がこの男を殺したんだ。すごいでしょ?」返り血を浴びた顔で自慢げに話す様子を見てマクイナスは激怒し、近くにあった大振りの斧を手に取ると、ジャンに飛びかかった。
「父さん!やめて!」
息子の声に耳を貸さず、思いきり振りかざされた斧はまっすぐにジャンへ向かった。
「やめたほうがいいよ?おじさん」冷静なその声にマクイナスは身動きが取れなくなった。
抵抗できない力に身体は悲鳴をあげるように妙に捻れていく。全身の筋肉が裂け、骨が折れていく音が周囲を包む。「が…こんなことが…有り得ない…」苦しみに耐える声が、苦悶に満ちる顔がエルオーデの瞳に焼け付く。
「おじさん、海に流してほしい?それともここで殺されたい?」
大きな身体は止まることなく鈍い音をたてながら捻れていく。
「なんてこと…」リズが真っ青な顔で言った。
ジャンはエルオーデとリズの顔を舐めるように見ると、マクイナスの握っている斧を取り上げ、重い刃を思いきり振りかぶった。
父の頭部が身体を離れ、ドサリと床に落ちた―。
なにもない存在しない、白く塗りつぶされた空間。私の前に女性と子供がこちらを見つめ力無く佇んでいる。ゆっくりと私に向け指を指す。
「…あなたが殺した」
その言葉が指す意味を理解出来ずにゆっくりと時間が過ぎていく。
「あなたは苦しみの底へと沈む…マレウス…」
マレウス…。私の瞳をまっすぐ見つめ呟く。
ゆっくりと瞬きをする。そこは黒に支配された空間。
「おかえり」
聞き慣れた声。いつも夢に出てくる謎の男の声。
「懐かしいな。昔の事がついさっきの事みたいに感じる」
ジャヌの言葉に私は応じなかった。頭の中を誰かに掻き乱されているように、様々な記憶が走馬灯のように駆け巡り、言葉を発することができなかった。
呆然とする私の前でジャヌはローブを脱ぎ捨て、胸元を開いた。
深く焼き付けられた【J】の烙印。
私は無理に言葉をひねり出した。「お前が…」
ジャヌはニヤリと顔を緩めた。
「そうだ。俺がジャンだ」
力無く尋ねる。
「お前が見せたのか…あれは…」頭の中を駆け巡っていた走馬灯は徐々に薄れていく。思考が戻り、意識がはっきりとしてくるのがわかった。
「ああ、その通りだ。お前はそろそろ思い出さなければならない。全てを」
「思い出す…?いったい何を…」私の言葉を遮るようにジャヌは言う。
「言っただろう。お前がここに来るたびに俺は濃くなると。俺を存在させるにはお前の記憶が必要なんだ。その為ならなんだって見せてやる」
なぜ今になってあんなものを見せるのか。もっと早い段階でも良かったはずだと、疑問を抱きながら私は沈黙する。
ここへ来てはダメ―…
暗闇の奥からぼんやりと聞こえてくる、透き通るような高い声。
「…邪魔が入ったようだ。また会おう、マレウス」
そう言い残し、深い闇へとジャヌは姿を消すと、辺り一面に風が吹き荒れる。全てを拐ってしまうほどの激しい突風が周囲を容赦なく飲み込んでいく。
闇を打ち払うかのような眩しい光。緑豊かな木々が生い茂る森の中。新鮮な空気が肺を満たし、身体に染まった闇を洗い流す。
「今度はなんだ…。ここは一体…」
初めて訪れる清らかなその場所は、不思議と身体に溜まった疲れを癒してくれる。
「おい」
突然後方から聞こえた男の声に私は素早く振り向いた。
そこには汚らしい衣服を身に纏った一人の男がいた。
「森を抜け、西にある古城へ向かえ」
男の突拍子もない言葉に、私は呆気に取られた。その場に沈黙が流れる。そして男は再び口を開いた。「西の古城へ向かえ。わかったのか?」
その問いかけに、私は静かに応じた。「お前は誰だ?ここはなんだ?」
男は首を横に振りながら答えた。「当然の疑問だ。だが、その質問には答えられない。西の古城、確かに伝えたぞ」男はボサッと言うと森の中へ消えていった。
私は男を引き止める事もなく、ただ去っていくのを見ていた。
「西…」私は力無く呟く。
ここが何処であの男が何者なのか。伝えたとはどういうことか、ただ考えていた。
この世界は夢なのか、あるいは、別の何かなのだろうか…いくら考えても答えは出ない。
ただこれだけははっきりしていた。
これは、現実ではない。
Episode4 〜辺境地〜
知らぬ土地を休む事なく歩き続ける。鉛のように重くなった足を一歩、また一歩と突き出す。
「西の古城へ向かえ」その言葉に素直に従い、ただひたすら歩き続ける。
だが、どこまでも広がる世界は私に牙を向ける。数日は歩いただろうか。これが現実であればとうに倒れているだろう。不思議と、水も食料も身体は必要としなかった。
しかし、そんな身体も、この焼けるような暑さには悲鳴をあげている。皮膚がじんわり焼け、
今にも爛れ落ちるかのように熱を帯びていた。
「どれだけ歩けばいいんだ…」その場に立ち止まり、俯き呼吸を整える。
なにか助けになるものはないか、ズボンのポケットを探る。「これだけか…」
古ぼけたロザリオ。それは、しばらく前に夢の中で拾った物だ。
次の瞬間、ロザリオが勢いよく弾け散ると、轟音と共に、目の前に突如として大きな古城が姿を現した。「どうなってる?!なにが起きた…」私は驚きを隠せず、たじろいだ。
これほど巨大な建造物が、一体どうやって隠れていたのだろうか。現実では到底起こりえない事に、ただただ驚いた。
「あれが、鍵だったのか…?」
私は驚きに満ちた身体を古城へと向かい進ませた。
古城の入り口を探し、壁沿いを進む。
大きな門などは無いようで、その代わりに大人ひとりが通れるほどの小さな木製の扉を見つけ、建物へと踏み込む。
暗くジメッとした長い通路を慎重に進む。突き当たりにある階段を上がり、本棚が犇めき合う部屋に辿り着いた。本棚に無造作に詰められた本は、どれも酷く汚れており破れているのも数多くあった。ゆっくりと無数の本を見て回る。
その中の一つに手を伸ばした。革表紙の厚い本の中には、興味深い内容が記されていた。
―彼は、眠りにつく度に別の世界へと旅立ち、過去を旅する。そこで、己の残した罪を呼び起こす。やがてその罪は現実となる。
「まるで俺の事みたいだ…」私は更に読み進める。
―繰り返される世界から、彼は目を覚ます事はなかった。
夢中になりページをめくる私の背後から女の声が静まり返る部屋の中に響く。
「あなたはわかっている」
その声に、とっさに身体が反応し、本を落としてしまった。振り返った先には見知らぬ女。冷静なその顔からは優しさを感じた。
「…誰だ?」私の問いに、女は静かに答えた。
「この世界がなにか、あなたとの繋がりはなにか、わかっているはず」女は名も名乗らず私を見つめながら話す。
ここは夢で現実ではないことは分かる。だが、私とこの夢の繋がりは分からない。考え込んだ私に向かって女はため息混じりに言った。「とにかく、ここへ来てはダメ。あなたがこの世界を訪れる度にあなたの世界は薄れてゆく。」
「薄れる?どういうことだ?」
「この世界は夢じゃないんだよ」
突然響く声。勢いよく振り返ると、そこにはジャヌの姿。
ジャヌの姿に女は驚きを隠せない様子だった。
「あなた…なぜ…」信じられないといった様子で女の口から言葉が漏れる。
ジャヌはその鋭い瞳を女に合わせ、自慢げに話した。「マレウスのおかげでお前を気にせず姿を見せられるようになったよ。俺はもう、この世界の忘れられた過去なんかじゃないんだよ」
私はこの状況を飲み込めずにふたりの会話をただ聞いていた。
「ジャヌ…あなたはこの世界の罪…。マレウス、私の言葉を覚えておきなさい。この世界には来ないで」そう私に伝えると、女は逃げるように部屋を出た。
ジャヌは後を追うこともなく、私の方へ視線を変えた。
「あの女は信用ならない。なにを聞いたが知らないが、お前はこの世界に来るのを拒めない。絶対にな」突き刺さるような視線で私に言う。
「ここは、この世界は夢じゃないのか?だとしたらここは…」
「現実さ。お前にとってはもうひとつの」
現実…。夢ではない何か他のものだと、頭では分かっていた。しかし、この夢が現実とは思えずにいた。あり得ない事だ。私には私の生きている世界がある。その世界で眠りにつき、夢であるこの世界に来てしまうのは当然考えられる。この世界が私の過去であり記憶だとジャヌの口から聞いてはいたが、夢が現実なんて事は…私の中ではやはり、あり得ない事だった。
「お前は常識に囚われ過ぎだ。もっと頭を柔らかくして考えてみろ。夢の中で負った傷が現実でも残っていて、毎日同じ夢を見てはその中で旅をし、しかもそれを事細かに覚えているんだ。それに、お前はもうどのくらい目覚めていないんだ?」
その言葉に私はやっと気が付いた。最後に眠りについてからかなりの時間が経っている。現実ではどれだけの時間が過ぎているのか、検討もつかなかった。私は死んだのか…そんな考えが一瞬頭をよぎる。
そんな私をよそ目に、ジャヌは私が落とした本を拾い上げた。
「過去を旅する…まさしく今のお前じゃないか。どんな気分なんだろうな、自分の無くした記憶の中を旅するのは」ジャヌは本に視線を送りながら私に言う。
無くした記憶…。この夢は私の過去…私の記憶…。現実とは、夢とはなにか…当たり前の事が全て覆り、それら全てに裏切られたような思いになった。
「俺はここで…」頭をあげると、そこにジャヌの姿はもう無かった。
私は深いため息をついた。
これから何をすべきか、何処へ行くべきなのか全くわからないまま、古城の中を歩き回る。
細かな装飾が施されたテーブルや椅子。床一面に敷かれた赤い絨毯。豪華なシャンデリア。
ここが廃墟と化す前はこれらは城内を豪華に見せていただろう。しかし今は、厚く積もった埃に輝きを失い朽ちた城内により一層の退廃感を醸し出す。物も、記憶と同じように風化するものだと物語っていた。
長い通路の中ほどにある部屋で私は一枚の紙切れを手に取った。「これは、地図か」
古ぼけた羊皮紙に書かれた地図を眺める。そこにはかなりの広域が描かれている。
私は古城までの記憶を頼りに現在地を探した。小高い丘に位置し、小川に囲まれた城のような印の周りに何かないかと確認すると、山を越えた先に家のような印が示されている。村か街だろうか、この場所が今も存在しているか不明だったが、今はここへ行くしか道は無いようだった。
羊皮紙を折りたたみ、私は燦々と降り注ぐ陽光の元へ戻った。
その時、鈍器で叩かれるような激しい頭痛に襲われ、その場に膝をついた。突如として襲う激痛にぼんやりと視界が霞む。
目の前が真っ白な世界へと変わる中、私は必死に意識を保とうとするが、やがて全身の力が抜けその場に倒れこんだ。
Episode5 ~救い~
―ジャヌ…あなたはこの世界の…
「やめろ!」
その叫びに私の身体は反応し、目を大きく見開いた。
そこは温かな陽が差し込む部屋。手製の粗末な寝床の上に横になっていた。
状況が分からず周りを見回す。
「目が覚めた?」声のする方に目をやると、長い髪を後ろに束ね、半袖にショートパンツを履いた女が水気を帯びたタオルを絞りながらこちらの様子を伺っている。
「ここは…?」力の抜けた声で女に尋ねる。
絞ったタオルを丁寧に畳みながら私に近付き私の額にそれを乗せると、近くにある丸椅子に腰をかけ、呆れた様子で私に話した。
「あなたが倒れていたから連れてきたのよ。あんなところに放置していたらあなた今頃死んでた」
彼女が何者なのかは気にしなかった。それよりも、麦の焼ける、鼻を誘惑する美味しそうな香りに気を取られた。
「ちょっと、聞いてるの?」女がむすっとした顔をする。
テーブルに上に置かれた、湯気が立っている焼きたてのパンに目を奪われる。女の声など私には聞こえていなかった。倒れる前までは空腹など感じられなかったが、今は空になった胃を満たしたくて仕方がなかった。
「ちょっと!」声を張り上げ私に怒鳴る。
私はハッと我に帰り女の顔を見る。「ごめん」
女は呆れたように息を漏らす。「あなた、名前は?私はカトリーネ、カトリーネ・オリアン」
「俺はマレウス」私はとっさに言った。
「マレウス、なぜあんな所に倒れていたの?」カトリーネの問いに私は答えようとしたが、自然とテーブルの方へ視線を逸らす。
カトリーネは私の視線を追いかけると、立ち上がりテーブルからこんがり焼けたパンを手に取り私に差し出した。
「お腹が空いてるなら早く言ってよ。食べて」
パンを受け取り、口にほおばる。口いっぱいに広がる麦の香ばしい香り、カリカリの表面にモチモチの生地。私はこの世界で始めて幸福感に包まれた。
「それで、なにか覚えている?」
口に詰め込んだパンを飲み込み、口を開く。「城から出ると、頭痛がしてその場に倒れた」
「…あなた大丈夫?」心配そうに見つめる薄い青色の瞳に、私は戸惑う。
「だから城から…」言葉を繰り返す。
カトリーネは言葉を遮り言う。
「城なんてこの辺には無いよ」その言葉に私はすかさず反論した。
「大きな古城が、あったはずだ。俺はその前で倒れたんだ」
「いいえ、あなたは何もない平地で倒れていたのよ」カトリーネの言葉を信じられなかった。
確かにあの時、私は城を見つけ、城内でジャヌと謎の女に会った。それははっきりと覚えている。私はそれらをカトリーネに伝えた。
しかし、私の言葉に疑念を持っているのか、カトリーネの顔は曇る。
どうしたら信じ得てもらえるのか、口を閉ざす私にカトリーネは疑いの目を向ける。
「…地図」城内で手に入れた地図の事を思い出し、ポケットから乱暴に取り出しそれを広げた。
「これ…何処で見つけたの」カトリーネはシワだらけの地図に興味を示した。
私はもう一度この地図を手に入れるまでの経緯を話した。
「城の事は信じられないけど、ここでは地図は貴重品よ。それも、こんなに広域な地図なんてなかなか手に入らないわ」
現実では当たり前のように流通している地図がそれほど貴重な物だとは思ってもいなかった。なぜ、地図がここでは貴重なのか私は尋ねた。
「地図なんて、普通の人には必要のない物だし、そもそも誰が作っているかも分からない。地図は貴重な物だと、母から聞かされて育ったから」
漠然とした答えに私はいまいち理解が出来なかった。地図なんて誰でも見れて、容易く手に入れられる現実とどうしても比べてしまう。
「…この世界は本当に分からない事ばかりだ」
「え?」カトリーネは私の言葉を聞き眉間にしわを寄せた。
カトリーネに私自身に起きている事実を伝えるべきか、迷っていた。悪い人間では無いと分かっているものの、やはり出会って間もない人間に事実を話すのには抵抗があった。
「いや…」私は口を噤んだ。
「訳ありか…。無理には聞かないけど、秘密を抱えながら生きるのは辛いよ。って、誰にでも秘密はあるか」カトリーネはそう言うと腰を上げた。
「少し、出かけてくるね。ここは好きに使って。どうせ誰も来ないし、私ひとりしかいないから」カトリーネが出て行くのをただ黙って見ていたが、倒れていた見ず知らずの私を助けてくれたカトリーネに、負い目を感じた私はカトリーネの後を急いで追った。
「カトリーネ!」私の声に驚いたように振り返る。
「俺に、何か出来ることがあったら、手伝うよ」
「じゃあ、一緒に来て」
早足で進むカトリーネの後を追い、生い茂る林へと歩を進める。道中に会話は無かった。
「よし。薪にする材木が欲しいの。これで切ってくれる?」そう言うと小ぶりの片手斧を差し出した。
それを手に取り、辺りに倒れている木に振り下ろす。黙々と腕を動かす私に向かい、カトリーネは口を開く。
「あなた、生まれはどこ?」
その問いに私は腕を止め答えた。「俺は…この世界の人間じゃないんだ」
その答えにカトリーネは再び眉間にしわを寄せた。
「ここの人間じゃない?どういうこと?」
私は、カトリーネに全てを話した。
この世界は私の夢であり、この世界に存在しているかも分からない事、現実と夢を行き来きし、現実では起こりえない体験をしている事、これら全ては私の過去で記憶の世界なのかもしれない事をありのままに伝えた。
到底信じられるような話ではない。しかし、カトリーネはそれに反論することもなく静かに私の話を聞いていた。
「つまり、この世界は、本当はあなたの夢で、存在すら疑わしい、そういうこと?」
その言葉に私は首を縦に振った。
「どんな話でも大抵の事は受け入れるでも、この世界があなたの夢だなんて、ちょっとね…」
確かにその通りだ。この世界に生き、生活し、終わりを迎える者にとってはこれこそが現実なのだから。私と何ら代わりはないのだ。
カトリーネは青々とした大空を見つめ、静かに言った。
―その話がもしも本当だったら、私たち…この世界の人たちは全て、偽りの創造物よ…。
Episode6 〜偽りか、真実か〜
蝋燭の灯りがゆらゆらと揺れる。
小さな炎に照らされたぼんやり明るい室内でカトリーネと私は手作りの暖炉に薪をくべていた。
「あなたの言っている事、どう信じたらいいのか…」薪をくべながらぼやく。
「いや、信じなくてもいい。とても信じられるような話しじゃないから…」私は静かに答えた。
炎が作り出すふたりの影が背後で揺れる。
私が現実で見ず知らずの人間にこの世界は偽物で、お前は存在しないと言われれば、信じられない。当然のことだ。私は彼女に存在を否定するような事を言ったのだ。私は後ろめたい気持ちでいっぱいだった。
静けさの中で、パチパチと小さな破裂音を出しながら薪が燃える。
それを眺めながら私は彼女の火をちらりと見た。
その顔はどことなく悲しげだった。
「私、母が死んでからずっとひとりだったの」
カトリーネはぽろりと言葉をこぼす。
「父親は私が子供の時に行方がわからなくなったって、母から聞いた。顔も覚えてない」
私は彼女の話を黙って聞いた。
「父がなにをしていたかも分からないし、どこへ行ったのかも知らない。母もそれは教えてくれなかった。知ろうとも思わないけど。母は死ぬ直前に私に言ったわ、人生を孤独で終わらすな、それほど悲しい事はないって」カトリーネは暖炉に薪を放り投げながら小さな声で語り続ける。
「でも、結局ずっとひとりで今まで生きてきた。あなたと会ったのは母が死んでから始めて。だから、ちょっと嬉しいんだよね」数年の時をたったひとりで過ごし、久しぶりの話し相手に嬉しさがこみ上げてきたと、カトリーネは話した。
彼女の顔には少しだけ笑みが浮かんでいた。
私も彼女と同じく、この世界で普通の会話が出来る相手に出会ったことを嬉しく思っていた。
「でも…あなたの話はやっぱり現実離れし過ぎてる。それが本当だとしたら、私も、この世界も、何もかもが偽りってことじゃない。これが全部、あなたの夢だなんて」
私はその言葉に、どう答えていいのか分からなかった。
―ありのままを話せばいいんだ…
「え?」
カトリーネは不思議そうに私に視線を向ける。
―エルオーデ…惑わされないで…
―この世界がどういうものか…分からせろ…
頭の中に男と女の声が響く。
―エルオーデなんて名なん忘れろ…今はマレウスだ…
―エルオーデ!
―この世界はお前を欲している…惑わされるな…
女の声はしきりにエルオーデと私に言葉を投げる。
男の声には聞き覚えがあった。ジャヌだ。
―エルオーデ…エルオーデ…!
その声は狂ったように繰り返される。
次第に激しさを増す呼びかけに私は叫んだ。
「違う!俺は…!」
「…マレウス?」
カトリーネの声に私は我に帰る。私を心配そうに見つめるカトリーネを一瞥すると、私は呼吸を整えるようにゆっくりと息を吐いた。
「俺は…何者なんだ…」
「どういうこと?」私の問いかけにカトリーネは困惑しているようだった。
「俺は…エルオーデと呼ばれたり、マレウスとも呼ばれたりする…。自分が分からない。何が真実で何が嘘なのか」
頭を抱え込む私に、カトリーネは少しの間無言になり、優しく私に言った。
「誰になんと言われても、どんな名前で呼ばれても、あなたはあなた。自分が見て、感じることが真実」
「いいこと言うじゃないか」
聞き慣れた声が、カトリーネの話に割って入る。
「誰!?」
カトリーネは驚き周りを見回す。だがそこには誰も居ない。しばらくすると、ドアがゆっくりと開く。
「ジャヌ…」
私はジャヌの顔に視線を向けた。
「ジャヌ?誰なの!?」
カトリーネ甲高い声に、ジャヌは呆れた様子で答えた。
「そう慌てるなよ。今は夜だ、静かにしよう」ジャヌの言葉にカトリーネは納得できる筈もなく、更に噛み付くようにジャヌに怒鳴り散らす。
「ここは私の家よ!あんたなんか知らない!早く出て行って!」
ジャヌは首を横に振りながら、私たちへ近付いてきた。
「家?あばら家じゃないか」
その言葉を聞き、カトリーネは怒りをあらわにする。
「何の用だ。話すなら外で話そう。ここはカトリーネの家だ」私はジャヌに言い寄る。
「だからなんだ?それに、ここが誰の家だろうが、そんなことはどうでもいい」
ジャヌは感情のこもらない言葉を投げ捨てた。その瞳は、見るもの全てを無へと返すような冷たさを放っている。
「その女に用があって来たんだ」その言葉にカトリーネは身構える。
「もう聞いているだろうが、ここはこいつの夢だ。今はな。お前はこの世界にとって、ただの薄っぺらな記憶でしかない」
大切なものを切り裂かれるようなその言葉に、カトリーネはしばらく言葉を失う。そして、重い口を開いた。
「そんなことを信じると思う?突然現れたあなたに私の存在を否定される覚えはないわ」
殺伐とした空気がその場を覆う。私は口を閉ざし、ふたりのやり取りをただ見ていた。
「じゃあ聞くが、お前は母親の顔を覚えているか?なぜ死んだ?母親の墓は何処にある?」
「それは…」ジャヌの言葉にカトリーネは反論せず、視線を足元に下げ黙り込んだ。
「覚えていないんだろう?なにもかも。お前の記憶は未完成だ。だが、その閉ざされた記憶を取り戻せる」
カトリーネは視線をジャヌに戻し、そしてゆっくりと私を見た。
その青い瞳が何を伝えたかったのか、私には分からなかった。
「…どうやるの」
期待通りの言葉だったのだろうか、ジャヌの口元が僅かに緩む。
「その男が、お前の記憶を取り戻す鍵になる。そして、お前の父親がどうなったのか、今ここで知るんだ」燃えるような真っ赤な瞳でカトリーネを見つめ、ニヤリと不敵な笑みを浮かべると、カトリーネに告げた。
カトリーネ・オリアン・バンシュタイン―
Episode7 ~悲しき記憶~
―カトリーネ・オリアン・バンシュタイン。
その名を聞き私は思わず息を呑んだ。
「お前は、バンシュタインの血を引く、忘れられた存在だ」
カトリーネは初めて聞くその名を、すぐには受け入れる事が出来ないようだった。
「お前の存在は誰にも知られる事はなかったんだよ。…母親を除いてな」ジャヌの言葉にカトリーネはひどく困惑し、なにを話せば良いのか分からない状態だった。
「バンシュタイン…」混乱する頭を落ち着かせ、カトリーネは静かに言った。
その様子を視線をそらす事なく見つめる赤い瞳はどこか満足しているようだった。
「そうだ。そして、マレウスの姉。バンシュタイン…その名は俺にとって貴重だ。それで、お前の記憶を取り戻す方法だが…」
ジャヌはその鋭い目で私の顔へ視線を変えた。その時、カトリーネが口を開く。
「ちょっと待って…マレウスが、私の弟ですって?そんなことある訳が…」
再びカトリーネに視線を戻した。「あるんだよ。お前が知っている以上にこの世界は複雑で、広い」
カトリーネはしばらく黙り込み、重い口を開く。
「じゃあ…彼の言っていることは事実なの?」
カトリーネが私の顔をちらりと見る。
「その通りだ。そいつは事実を言っている」
信じられないと言った様子で、その場に立ち尽くすカトリーネ。
自分が生きてきた世界が、自分自身が他人の夢であったことにショックを隠しきれず、全身から悲しみや混乱が溢れ出しているのが感じ取れた。
「だが…なぜそれを教える必要がある?お前は敵なのか味方なのか…」私の問いに、ジャヌは間髪入れずに答えた。
「どちらでもない。それに言っただろう、俺の存在が確かなものになるのであれば、何でもすると」
ジャヌはそう言いながら指をパチンと鳴らした。
突然視界が変わる。
そこは、人気のない森の中にある小さな建物。
「カトリーネ、ごめんね。こんな森の中で暮らすのは嫌でしょう?」
みすぼらしい服装の女が、少女に優しく話す。少女はその言葉に思いきり首を横に振った。
「ううん、わたし、お母さんと一緒に居られればそれでいいの」
少女の言葉に、目に涙を浮かべる女。
「お母さん…」隣に立っているカトリーネが呟く。
どうやら、カトリーネも私と同じ光景を見ているようだ。
「信じられないけど…あの首飾り…」カトリーネの胸元には、石がはめ込まれた質素な首飾りがある。その石はくすみ、輝きを失っているが、それに負けじと、存在感を出しているように見えた。
「ねえ、わたしは大きなおうちには入れないの?」
その言葉に、戸惑いながら母は答えた。「あの家はね、怖い人たちが居るから入ってはダメなの。私はカトリーネに危ない思いをしてほしくないのよ」
少女は母の言葉に軽く頷いた。
「あなたには幸せになってほしい。こんな風に隠れながら暮らさないでほしい…」
「かくれる?」少女は首をかしげた。
「いえ…なんでもないわ」
―エルオーデ!いるんでしょ?エルオーデ!
遠くから聞こえる少年の大声を聞くと、女は少女の頬に優しく手を添えた。
「カトリーネ。あなたは私の希望よ」
母の言葉に自然と口元が緩くなり、娘は母に抱きついた。
母も力強く娘を抱きしめる。
「…私は、少しだけ出かけてくるわ。いい子にしてるのよ。遠くに行ってはダメよ。それから、他の人を見たらすぐに隠れてね。いい?」
「うん、わかった」
娘の返事を聞くと、辺りの様子を注意深く確認し、ゆっくりと建物を後にした。
―カトリーネ…。あなたにはバンシュタインの名は忘れてほしい…。
リズという名も…忘れてほしい…―。
私は…あなたの中に存在していればそれで…十分だわ…―。
悲しげな声が頭の中にこだますると、目の前に広がっていた光景が徐々に薄れ、再びジャヌの姿が視界に入ってきた。
「これはお前の記憶のほんの一部だ。もっと自分のことを知りたいか?」
カトリーネのからの返事はない。うつむくその姿に目をやると、彼女の頬には涙が流れていた。途絶えることなく流れ続けるその涙を見て、私はなにも言ってやれなかった。
自分の中に居た母親がなんだったのか…。
知っていたはずの自分の過去はなんだったのか…。
カトリーネは悲しみと悔しさに胸が張り裂けそうだった。
「孤独を捨てる時が来たんだ」
ジャヌはカトリーネの涙など気にもしない様子で冷たく言った。
「お前の記憶を取り戻す方法だが…」
「どうするの…なにをすれば私の過去を取り戻せるの…」
カトリーネは震える唇で言った。
「お前は話を遮るのが好きなのか?」
ジャヌは呆れ顔で首を横に振る。
「まあいい。お前の記憶の扉を開ける鍵は、その男だ。そいつがこの世界のことを知るたびに、お前は自分の過去を思い出すだろう」
「具体的になにをすればいいの」
カトリーネの口から出た言葉に、またもやジャヌは首を横に振る。
「気に障る女だ」少しばかり苛立った口調で言うと、私の方を指差した。
「こいつと行動を共にしろ。そして、こいつの苦しみ、悲しみ、喜び、怒り、恐怖…全ての感情を受け取れ」
カトリーネは私を見た。「どうやってそんなこと…」
「自分で考えろ。何処へ行くべきか、なにをすべきか…お前らが考え、決めろ」冷たい瞳はまるで私たちを試すようだった。
「さて…必要なことは済んだ。最後にひとつ教えてやる。お前の名だ。エルオーデ・バンシュタイン…そしてもうひとつが…」
―マレウス・アマルティア・エクシリオ…
Episode8 〜現実への扉〜
マレウス・アマルティア・エクシリオ―
その名を伝えるとジャヌは黒い影となり消えてしまった。
私は初めて知らされるその名に混乱させられる。自然と自分の名をマレウスと名乗っていたのが不思議に思えた。
このふたつの名はいったい何を意味しているのだろうか。今の私には到底理解できないことは分かっていた。
考え込んでいる私をよそ目に、カトリーネはボソッと呟く。
「消えた…」カトリーネは魔法のように人が消えるのを見て、ぽかんと口をあけている。
私とカトリーネは顔を見合わせる。
「家族…」小さな声でぽつりと呟くカトリーネに、私はどう反応すれば良いのか分からなかった。
出会って間もない目の前にいる人間が姉だと言われれば当然だ。
気まずい空気が私とカトリーネの間に流れる。
何か言ってくれ。私は切に願った。だが、時間ばかりが流れ、お互いに口を開こうとしない。
私はとうとう我慢できなくなり、重い口を開いた。
「…ジャヌの言っていたことが本当なのかは分からないけど、俺と一緒に来てほしい…もし良ければだけど…」
私は自分の言葉に急に恥ずかしくなった。まるで愛の告白ではないか。だが、それ以外の言葉は頭に浮かんでこなかった。
沈黙を守っていたカトリーネが私に答える。
「家族だなんて…あなたが弟なんてすぐには受け入れられないけど、本当の私を探す為には一緒に行くしかなさそうね」
予想外の冷静な言葉に、私は自分が更に恥ずかしくなる。
もっと他の言い方はできなかったのだろうかと、必死で自問自答をした。
「とりあえず、この場所にも思い入れはないから、すぐにでも出発できるわ。どこか行くあてはあるの?」
行くあてなどある訳がない。ここは来たのも、カトリーネに会ったのも偶然の産物だ。
古城へ辿り着く前には見知らぬ男に指示をされたが、その男にもあれ以来会ってはいない。
私は、地図をその場に広げた。
ふたりで地図を覗き込む。だが、この場所がどこに示されているのかも分からない。
「地図なんて今までに一度くらいしか見てないから…」カトリーネは首を傾げながら地図と向き合う。
「近くに、村や町…なにか建物はないか?」
何かしら人工的なものがあれば、とりあえずはそれを目指せる。
だが、カトリーネは首を横に振りながら言う。
「分からない…。自然と人を避けて生きてきたから。でも、人が作ったようなものは見たことがある。私と行った森を抜けた先におかしな大きな岩があるの。あれは自然に出来るようなものじゃない」
私たちは他に行くあてがなかった為、カトリーネの言う「岩」を目指すことにした。
目的のはっきりしない旅はまさに手探り状態だった。
地図をたたみ、部屋の窓から外を眺める。この先になにが待っているのか、終わりはあるのか…。そんな答えの出ない考えばかりが思考を支配する。
「ちょっと待っててくれる?」カトリーネは使い込まれたバスケットに入ったパンを麻袋に入れていた。
「長い道のりになりそうだから」麻袋に形の不揃いなパンを詰めながら言う。
長い道のり…どこが終着点なのだろうか。私が現実へ戻り、この夢を見なくなったらこの旅はどうなるのだろうか。それは誰にも分からない。
カトリーネは住みなれた家に別れを告げる。私たちは森へと足を進めた。
薄暗く湿気に包まれたその森はとても不気味で、人ではない何かが身を潜めているかのようだった。カトリーネを先頭に、足元に注意しながらゆっくりと森の中を進む。
適度に休息をいれ、身体を蝕む疲れを癒した。
数時間は歩を進めただろうか、崖沿いにぽっかりと口を開く小さな洞窟へたどり着いた。
「ここで朝になるのを待とうよ」カトリーネは背中に背負った荷を解く。
私はあらかじめ持ってきた薪木を取り出し、湿気たマッチで火を焚こうと試みる。
しかし、何度こすっても火がつかない。繰り返しマッチをこする。
「貸して」マッチを半ば強引に取り上げられる。
カトリーネが手慣れた手つきでマッチをこすり、一発で火をつける。
「マッチの使い方も分からないの?」その言葉に私は耳を疑った。
マッチの使い方くらい心得ている。しかし、湿気たものに火をつけようとするのがそもそもの間違いなのではないのだろうか。
私は言い返したい衝動を必死に堪えた。
赤々と燃える炎に照らされながら考える。
今頃、現実の私はどうなっているのか、どれだけの時間が過ぎているのか…。心配にはなるものの、私は現実で長い時間を過ごすよりも、夢の中で過ごすことに安心感を抱き始めていた。
「あの男…ジャヌって言ったけ。何処で出会ったの?」
カトリーネの問いかけにハッと我に返る。
「何処でというか、俺の夢の中にいつも出てくるんだ」私は炎を見つめながら答えた。
「夢って、この世界のことだよね?」
私はこれ以上カトリーネの存在を否定するようなことは言いたくなかった。
存在しているものがそれを否定されることよりも辛いことはない。私は慎重に言葉を選んだ。
「あぁ…。夢は夢でも、俺には現実と変わりはない」私の言葉にカトリーネは黙り込む。
夢が夢でないことが、カトリーネやこの世界の者には理解できないのだろう。
「この世界が夢…か。…私たち、本当に家族なのかな…。」
人との関係も築けずに生きてきたカトリーネにとって家族とはなんなのだろうか。家族がある当たり前の暮らしを送ってきた私には分かるはずもない。どれだけ辛く、孤独だったことか。
「もしも、本当に家族だったら嬉しいな。それがどんな形であっても」そう語る彼女の瞳は、少しだけ希望が芽生えているように見えた。
私たちはひとときの休息に身を委ね、身体を横にした。
―鳥のさえずりが心地よく耳に入ってくる。
カーテンの隙間から陽光が差し込む。
私は全身を包み込む柔らかい布団をはねのけ飛び起きる。
そこは夢の世界ではなく、現実だった。
Episode9 ~迫る影~
テーブルに置いてあるスマートフォンを取り上げ、画面を確認する。
「マジか…」
私が最後に眠りにつき、目覚めるまで7時間程しか経っていない。
夢の中では数日、だが現実では一日の半分も経っていない。
わずか
7時間の間にあれだけの夢を見ていた事に、私は少しばかり驚いた。
カーテンを勢いよく開ける。
部屋いっぱいに差し込む眩しい日差しに、目がくらむ。
私はグラスに飲み物を注ぎ、使い込まれたソファーに深く腰掛けた。
やはり、夢の出来事は全てはっきりと覚えている。夢での疲れや身体の痛みも残っている。
夢と現実の違いが曖昧になってから、今日で数週間が経とうとしていた。
ピリリリ!ピリリリ!
突然スマートフォンに登録されていない番号から着信が入る。
「もしもし」私は眠気が覚めきれてない声で電話に出た。
ツー…ツー…。
「なんだよ…」間違い電話だろうか。
ピリリリ!
すぐさま同じ番号から着信が入る。私は苛立ちを露わに電話に出た。
しかし相手からは何の言葉もない。いたずら電話だろうか…私は一方的に電話を切った。
その後、数時間が経ったがその番号からの着信はなかった。
正午――。
私は緑豊かな山道で車を走らせていた。連日の寝不足(実際は寝ているが)で身体が悲鳴をあげていたこともあり、長期間の休養を取っていた。
燦々と照り付ける陽光が木々の緑をより一層際立たせ、素晴らしい景色を作り出す。
路肩に車を止め、外へ出た私は山下に広がる景色を眺めた。
どこまでも続く地を見つめ、ふと思う。
この世界に生きている人間は実にちっぽけな存在だ。宇宙に無数とある中のひとつの星で、自分の人生を奔走して生きている。
そんなことを考えていると、また着信が入る。例の番号からだった。
電話に出るべきか迷った私は鳴り続けるスマートフォンをじっと見ていた。
着信が切れる気配がない。私はため息混じりで電話に出た。
お前が欲しい―…。
うめき声のような老婆の声に私は驚きスマートフォンを地面に落とした。
「なんだよ…なんだこれ…」気味の悪い電話に全身の毛が逆立つ。
恐る恐る落ちたスマートフォンに手を伸ばす。幸い、生い茂った草がクッションになり壊れてはいない。
私はゆっくりと耳を当てる。だが、既に通話は切れていた。
恨みに満ちたようなあの声が耳から離れない。
全身に帯びる寒気を払うように、私は足早にその場を離れた。
自宅――。
夜も更けた頃、私はパソコンに向かっていた。
正夢―
死後の世界―
タイムトラベル―
前世―…
思いつく言葉をひたすらキーボードに打ち込む。自分が体験していることがなんなのか、少しでも知りたかった。しかし、いくら検索しても望む答えは見つからない。
「だめだな…」
窓を開け冷えた空気を部屋に流し込む。夜の街に輝く光を見つめながら深呼吸をする。
お前が欲しい――。
忘れた頃に思い出すあの言葉が全身に悪寒を走らせる。
あれはいったいなんだったのか。霊的な現象なのか…夢となにか関係があるのか…。
ガチャ――…
ドアの閉まる音に私は振り向く。
「…鍵、かけたよな…」
警戒しながら玄関へと様子を見に行くがそこには誰もいなかった。いつも見ている、何ら変化のない玄関。
隣の部屋だろうと思いリビングへと戻る私を、それは待ち構えていた。
やぁ…マレウス――。
Episode10 〜再び〜
衝撃的な展開に動転する私を、面白そうに見つめる男。
「ジャヌ!どうなってんだ!?これも夢か!?」
私は夜の静寂をぶち壊すような大声を張り上げる。
「そんなに驚くことか?大袈裟なんだよ」落ち着き払った口調でジャヌは言う。
「大袈裟にもなるだろ!この状況分かってんのか!?お前は現実にまで現れた!」
ドン!
壁を叩く音が部屋に響く。その音は恐らく隣部屋からだろう。夜も更けきったこの時間にこれだけの大声を出せばうるさいに決まっている。
私は動揺しきった心を落ち着かせ、声を低くした。
「なんでお前がここにいるんだよ…!」
ジャヌは周りを見回しながら言った。「これがお前の世界か…嫌な所だな」
「現実でまでお前に否定される覚えはない」
張り上げそうな声を必死に堪えながら反論する。
「それで、なにか用なのか。どうして現実に来れる…!?」
「なにを言ってる。そろそろ出発の時間だぞ」
…ウス…マレウス!
その呼びかけに私はハッと目を開けた。
「やっと起きた。魘されてたよ」カトリーネが私の顔を覗き込んでいる。
「俺は寝てたのか…。あれは夢か…」私は上の空で独り言を呟く。
「…なんだか分からないけど、そろそろ行くよ」地面に広げた荷物を手早くまとめながらカトリーネは言う。
私はいつから眠りに落ちていたのだろうか。現実と夢の見境がつかなくなっているのを感じながら、再び歩を進めた。
木々の隙間から差し込む朝日を身に浴びながら軽快な足取りで森の中を進む。
「あと数時間も歩けば着くわ」
心なしか、カトリーネの口数が少ない気がした。
なにか話題を出したほうがいいか、それとも余計なことは言わないほうがいいか…彼女の背中を見つめながら思う。
昨夜の出来事でカトリーネの運命は変わったはずだ。今までの生活を捨て、正しいと思っていた過去や思い出も否定されたのだ。そんな思いをした人間に私はどんな言葉を投げかければよいのか頭を悩ませる。言葉を選ばずに適当なことは言えない。何も考えずに言葉を出せるジャヌが今は羨ましく思えた。
なぜあのように相手の感情に惑わされずに言葉を発することができるのだろうか。ジャヌには感情というものがないのだろうか?そんな人間がいるのだろうか?
人間…彼は人間ではないのかもしれない…。
「エルオーデ・バンシュタイン」なんの前触れもなくカトリーネが私の名を口にする。
「カトリーネ・オリアン・バンシュタイン」自分の名を口にする。
「不思議な感じだね。私たち家族なんだよ?信じられる?」
今更信じるなと言う方が難しい。現実ではあり得ない体験をしているのだ。この世界で姉がいようが、自分が化け物だと言われようが信じるだろう。
「家族か。俺は信じるよ」私は微笑みながら答えた。
私の微笑みを見たカトリーネは照れくさそうに頬を赤らめる。
母親が亡くなって以来、孤独に生きてきたカトリーネにとって家族とは人生を一変させるもので、なにより大きな存在なのだろう。
多くの人々が存在する世界に彼女のような人間はどれくらいいるのか、ふと思う。
「母親のこと、聞いてもいいかな」私はリズ・バンシュタインがどんな母親だったのかカトリーネに尋ねた。
「優しい人だったけど。よく家を留守にしてた。」カトリーネは顔をしかめる。
「どこに行ってたのか…何をしていたのか…結局、最後まで教えてくれなかった」
淡々とした口調で語る。
「…この話はやめよ。そろそろ着くよ」
まずいことを聞いてしまったか。私は口をつぐんだ。
私たちは開けた場所へとたどり着いた。森の中に円を書くように木々がひとつの岩を取り囲む。
その岩は2メートルほどあるだろうか。楕円の形をし、上部、下部にはひどく錆びた太い鎖が巻き付けてあり、中心にはなにやら文字のようなものが刻まれている。
更に、岩の周りの植物は生気を失ったように枯れており、重苦しい雰囲気を醸し出す。
まるでこの岩が命を吸い上げているかのようである。
中心に刻まれた文字に目を近づける。
―パレルソン・マルディシオン――
名前、言葉、地名…様々な意味にとれるそれに、私とカトリーネは頭を悩ませた。
「ここでなにをしてる」
突然、後方から聞こえた声に素早く振り向く。
「お前は…」
Episode11 〜甦る衝動〜
ボロボロの衣服を身に纏った大男。
あごひげを生やし、敵意を持った面持ちでこちらを睨みつける。
私に古城へ行くよう指示した男だった。
「今すぐここから立ち去れ」男は唸るように言った。
「待ってくれ。俺たちは…」
「立ち去れ!」
私の言葉を強引に遮り、男は思いきり怒鳴った。
その怒鳴り声たるや、まるで嵐の日に鳴り響く雷の轟音のようだ。
「ちょっと…話しを聞いてよ!」カトリーネは男に乱暴に言葉を吐いた。
男はカトリーネの言葉を聞くと、背中に担いでいた大きな石で出来た大槌を両手で握る。
「おいおいマジかよ…」
「聞きなさいってば!」カトリーネの男に対する態度は、他人を避けて生きてきたとはとても思えない。
男は手に持った大槌と共に、私たちへと突っ込んでくる。
「ちょっと!どうするの!」
私たちは戦えるような武器など持っていなく、それに代わるような物も周囲には確認できない。
このような場合、答えはひとつだ。
「逃げろ!逃げろ!」私は大声で叫ぶ。
大槌が勢いよく振り下ろされる。宙に舞い上がる土煙。
こんな物がまともに当たればただでは済まないだろう。逃げ惑う私とカトリーネを鬼のような形相で追いかける男の姿はまるで恐怖だ。
見ず知らずの男に追い掛け回される恐怖を味わう日が私の人生で訪れるとは、予想すらしていなかった。
獲物を仕留められない怒りで男は更に乱暴に大槌を振り回す。
「マレウス!私が引き付けるからなんとかして!」男に追われながら必死に叫ぶ女の姿は映画などでしか見たことがない。
それよりもカトリーネを助けなくてはと必死に走り続けながら周囲に目を凝らす。
やはり武器になりそうな物はなにも見つからない。
私は仕方なく手のひらほどの石を掴み取ると、それを握りしめ男に向かい走った。
「立ち去らぬなら、ここで死ね!」男がカトリーネに大槌を振り下ろす。
だが、カトリーネの俊敏な動きにまたもや地面から土煙が舞い上がる。男がよろめいた所をすかさず手に持った石で殴りかかる。
ズゴ!
男の後頭部から鈍い音がし、巨体がその場に膝をつく。
必ずしも大きな武器が優位に立てるという訳ではない。そして、時には小さな石も人を殺すことのできる凶器へと変わる。
「貴様ら…!」獣のように荒々しく息をあげる男に追い打ちをかける。
何度も男の頭を殴りつける。その度に返り血が勢いよく飛び散ちり周囲を赤く染める。
「マレウス!もういいよ!」
カトリーネの声にも私は手を止めず殴り続けた。
――そうだ…それでいい…―
私は男を殴ることに快楽を感じていた。
血に染まってゆく男の顔から喜びを得る。
男は既に死んでいるかもしれない。それでもいい。
――もっとだ…お前の血に…闇に染まれ―…
私は暴力を楽しんでいた。
「マレウス!」
頭に鋭い痛みを感じ、視界がぼやける。
「ごめんなさい…!」
カトリーネは男の大槌を手に取り、力任せに私の顔に打ち込んだ。
―どうだ…血に染まる感覚は…。
―衝動に身を任せるのはいいものだろう…。
「俺は…殺したのか」血に染まった自分の手を広げる。
―殺したとしても…自分を責めることはない…それが本当のお前だ…。
「お前は…人を殺したことがあるのか」
―大勢殺した…必要なことだった…。
「俺はどうなっているんだ…」
目の前に、血に染まったジャヌの姿が現れる。
「お前は残酷な人間だ。俺と同じ、大勢殺している。罪のない人間を虫のように殺してきたんだ」
「嘘だ…」
「嘘?お前は覚えていないだけだ。その手を見てみろ…懐かしいだろう?お前は血に飢えた獣だ」
私の顔をなめまわす様に覗き込むジャヌの瞳は、恐ろしいほど赤く輝いていた。
「お前と一緒にするな…俺は殺してなんかいない!」
「その根拠はなんだ!なぜ殺してないと言いきれる!なぜお前は受け入れない!」
いつもの冷静な姿からは想像もできないほどの荒げた声でジャヌは叫ぶ。
「お前は俺と同じだ!素直にそれを受け入れろ!」
「黙れ!俺はそんなこと受け入れない!」私は真っ赤に染まった両手で顔を覆う。
「…まぁいい。お前は残酷な自分を受け入れなければならない時が必ず来る。その時、自分の罪を知ることになるだろう。どれだけ否定しても、それは必ずお前を飲み込みにやってくる」
私の罪…。
人殺し…。
残酷な自分…。
私は…獣なんかじゃない…―。
Episode12 〜守られる起源〜
大木に縛られた男を見下ろすカトリーネの姿。
私は立ち上がろうとするが、身体がいうことをきかない。
「気が付いたのね。さぁ」
カトリーネは私の肩に手をまわした。
「大丈夫?でもああしなかったらあなたはこの男を殺していたかもしれない」
私は男を殺していなかったことに安心感を抱いた。
人を殺さずに済んだ。それだけも救われた気がした。
「俺はなぜあんな…」
「人が変わったようだったよ。それに、殴ってる時のあなた、笑ってた」
脈打つたびに頭の奥に鈍痛が走る。
「俺はそんなつもりじゃなかった。君を助けようと…」
「分かってる。でも、怖かった」
笑いながら人を殴り続けるのを目の当たりにすれば、誰だって恐怖を覚えるだろう。
その時、縛られている男が目を覚ました。
先ほどまでの怒り狂っていた男の姿は消え、意識がもうろうとしているようである。
顔は大きく腫れあがり、痛々しい面持ちだった。
「貴様らは…ここでなにをしている…」力なく話す男に私は近づき言った。
「俺たちは旅をしていて、あの岩になにか手掛かりがないか調べていたんだ」
私の言葉に男は岩を一瞥すると、私に向かって口を開いた。
「お前はアルパガスではないのか…」
「アルパガス?」
男はため息をつきながら俯き、しばらくしてから顔を上げた。
「…すまなかった。お前はアルパガスだと思い込んでいた。オリヘンを奪いに来たのかと…」
男は縛られた身体に視線を送る。「これを解いてくれないか」
私とカトリーネは目を見合わせる。縄を解いた途端に襲い掛かってくるのではないかという不安を持っていた。だが、このまま男を縛り付けておく訳にもいかない。
「解いてもいいが…」
「なにもしないさ。」男はまっすぐに私たちを見つめる。
カトリーネは男の縄を解いた。
男はふらつく身体を支えるように大木に両手をつき、ゆっくりと立ち上がる。やはり大きい。このような巨体の男を殺しかけたとは信じられない。
人は実に脆いものだと、その時実感した。
男は巨体を動かし岩へと近づくと、ゆっくりとこちらに振り向いた。
「アルバノスだ」太い声で言った。
「カトリーネよ」
私はどの名を口にするか迷った。マレウスか、エルオーデか…。アルバノスは私が話すのを待っているようだった。
「マレウスだ。その…殴って悪かった」私は申し訳なさそうにアルバノスを見た。
「気にするな。俺が先に手を出したんだからな。それよりも…マレウス、会うのはこれで二回目だな」
カトリーネがぎょっとするような目で私を見た。
「古城へ行くように言われたんだ。だが、その時はそれ以上話さなかった」
「そうなんだ…。アルバノス、聞いてもいい?」
アルバノスは首を縦に振りながら返事をした。
なぜ襲ってきたのか、【アルパガス】と【オリヘン】とはなにかを聞いた。
オリヘンとは、この世界を存在させており、世界の基礎とも言われる物らしく、それを狙うのがアルパガスという存在らしい。
ニーデは世界を再構築するためにオリヘンの奪取を目的にしていると、アルバノスは言う。
そして、彼に伝言を頼んだ謎の人物に関しても教えてくれた。
この先に男がひとり立っている。その男に伝えれば、オリヘンは無事だと。
謎の人物はそれ以上話さず、姿を消した。
アルバノスはその人物とは初めて会ったと言った。
オリヘンは無事だと聞かされていたが、私たちがここに居るのを見てアルパガスと勘違いをし、襲ってきたと話した。
「普通の人間はオリヘンになど用がないからな」アルバノスは肩の力を抜きながら言った。
「あの岩が、オリヘンなのか?」
「そうだ。オリヘンは世界にとって欠かせないものだが、同時に、周りにある命を奪う」
周囲の植物が枯れていたのも、オリヘンの影響だった。
「ニーデは、世界の再構築の他に、オリヘンの持つ力も狙っている」険しい面持ちでアルバノスはオリヘンを見ながら話した。
「あなたはこのオリヘンを守っているの?」カトリーネの問いにアルバノスは頷く。
「俺たちは【シュッツヘル】と呼ばれている。オリヘンを守る人間のことだ」手で顔の傷を確認するように触りながらアルバノスは言った。
「シュッツヘル…聞いたことがある」カトリーネはシュッツヘルという言葉を聞くと、顔を曇らせ静かに言った。
「母が、シュッツヘルと言っているのを何回か聞いたわ。その時はなんの事だかさっぱりだったけど」
アルバノスはカトリーネが下げている首飾りを見ると、少しだけ目を見開いた。
「母親とは、リズ・バンシュタインのことか?」
私とカトリーネはその名を聞くなり、勢いよく言葉を発した。
「知ってるのか!?」
「母を知ってるの!?」
アルバノスはその場に座り込むと、私たちを見上げた。
「知っているとも。彼女はよき友であり、仲間だった」
驚きに満ちた私たちの顔をじっと眺めるアルバノス。
「どうやら…お前たちには話すべきことが多いようだ」
Episode13 〜明かされる秘密〜
オリヘン……それが存在した瞬間、世界が創造され、あらゆる命が生まれたと言われる。
それが存在する場所こそが世界の中心だと、人々は考えていた。
だが、オリヘンの前にひとりの男が現れる。男がオリヘンに触れると、それは目をそむけるほどの眩い光を解き放ったのち、砕け散ると世界に闇が存在した。
闇は世界を瞬く間に飲み込んだ。光を失った世界は悪を生み出した。
人々は互いに殺し合い、終焉への階段を登りはじめる。そんな中で、砕け散ったオリヘンを探すものが現れる。広い世界へと消えたオリヘンの欠片を見つけ出すには何年にも及ぶ時を必要とした。それを見つけ、守る者を人々はシュッツヘルと呼んだ。
しかし、光に影があるように、それに敵対する者も現れる。その者達はアルパガスと呼ばれた。シュッツヘルは、オリヘンの力を知りそれを奪おうとするアルパガスと幾年の時を争いで血に染めた。
世界に散ったオリヘンの欠片は13存在すると言われた。そのうちの半数はアルパガスの手に渡る。
光と影を作り出したオリヘンは、現在に至ってもなお、その力を失っていない。
それを語るアルバノスの目は怒りと悲しみが入り混じったようだった。
「リズは俺たちと同じ、シュッツヘルだった。だが…オリヘンに近づき過ぎたリズは、命を奪われてしまった…」
「奪われたって…オリヘンに殺されたっていうの…?」カトリーネは震える口で言うと、その場に呆然と立ち尽くす。
「オリヘンは、命を与え、奪いもする。その力は世界そのものだ…」肩をすくめながらオリヘンを見る目は、恐怖を感じているように震えていた。
「オリヘンが無くなると、この世界も消えるのか…?」私はオリヘンを見つめながら言った。
「それは分からない。世界が終わるのか……なにかが起きるのか。馬鹿げた話だろう、大切な友の命まで奪ったこの岩を、今でもこうして守っているんだ」
「そんなこと言わないで。母は命をなげうってまでこの岩を守ったんでしょ? それを無駄にしたくない」
パチパチパチパチ……
「泣けるな。母の意思を継ぐか?」
両手を叩きながらオリヘンの陰からジャヌが姿を見せる。
「オリヘンの真実を知った今、お前たちはどうする?」挑発するような笑みを浮かべオリヘンに手を付けるジャヌにアルバノスは唸った。
「貴様は何者だ…。アルパ…」
「アルパガスアルパガスうるさいんだよ。俺をそんなゴミみたいな奴らと一緒にするな」
アルバノスはジャヌの言葉に眉間にしわを寄せ、立ち上がる。
「なんの用だ?」
私の言葉にジャヌは残念そうな表情を浮かべる。
「お前はいつもそうだ。俺が会いに来るたび、何の用だ? ここで何をしている? それは口癖なのか。もっと歓迎してくれてもいいだろう」
「ジャヌ…」カトリーネはなにか言いたげな表情をしていたが、言葉は出さなかった。
「知り合いなのか?」アルバノスは私とカトリーネの顔を交互に見た。
私はこれまでの経緯を説明した。
「信じられん…」
常識では考えられない話に不信な目で私たちを見る。
「何も知らずにオリヘンを馬鹿みたいに守っているお前に嫌気がさすがな」
ジャヌは呆れた目でアルバノスに言った。
「オリヘンのことは俺たちシュッツヘルが良く知っている」牙を向くその姿に、ジャヌは更なる呆れ顔で答える。
「お前らが持つオリヘンへの考え方が間違っているとは思わなかったのか?」
ジャヌと、アルバノスのどちらが正しいのか。オリヘンのこと理解していない私たちには、当然その答えを出すことが出来ない。
そのもどかしさにカトリーネは苛立っているように見えた。
オリヘン、シュッツヘル、アルパガス…色々なものが同時に頭の中を駆け回る。
それはまるで、私の行く道を邪魔しているようだ。
―こんな夢…無くなってしまえばいい。
完全に私の常識の範囲を超えている出来事に自暴自棄な思いが頭をよぎる。
一つ謎を解けば二つ、三つと謎が増える。現実でもごくありふれたことだが、それがこの世界では不愉快で仕方がなかった。
私はなんの答えを求めてこの世界を旅しているのか、時々分からなくなる時がある。
この世界は私の過去。それ以外の目的はあるのだろうかと思ってしまう。
―俺の存在を確かなものに……。
ジャヌは最後に何を求めているのか。そして、その目的が果たされた時、何が起こるのか。
想像すらもできない。
カトリーネは私に「大丈夫か」と言わんばかりの視線を送る。難しいことは考えずに今起きていることを見よう。
「ジャヌ、お前はいつもなんの前触れもなく現れるが、俺たちを助けているのか?」
「理由もなく、俺がお前らに会いに来ているとでも思ってたのか?」
その挑戦的な言葉に負けてたまるものかと言い返す。
「お前が俺たちの前に姿を見せる理由なんて分かるはずがないだろう。そもそも、敵か味方かもわからないやつを信じろと言うほうが難しい」
ジャヌの口からは「どちらでもない」と言葉が出るだけで、はっきりとしたことは言われない。その時点で怪しすぎるのだ。今まではあまり気にせずにいたが、さすがにジャヌがどういった立場に属するのか明らかにしたい。
私は目を鋭くし強い口調で言葉を投げかける。
「お前は敵なのか、味方なのか」
いつもの達者な口を閉じ、片手でオリヘンを子供でもあやすようにさすりながら、もう片方の手を自分の懐に忍ばせる。
獲物を槍で刺すような視線をこちらに送る。その目は感情など感じさせない。
懐から小さな袋を取り出すと私へと放り投げた。
袋を拾い上げ、中身を取り出す私を黙って見守る三人。
「なんなの?」カトリーネが私に歩み寄る。
「鍵だ。ただの鍵の束だよ」使い道の分からない錆びだらけの鍵束を見つめる私たちに、ジャヌはゆっくりと近づいてくる。
「その鍵をただの錆びた鉄の塊だと思っているなら、それは大間違いだ。そこの大男になら使い身が分かるんじゃないか?」ジャヌの挑発的な言葉に遂にアルバノスは激怒した。
「黙って聞いていれば! 突然現れたお貴様など信用できるものか! それに貴様もだマレウス! この世界が貴様の夢だと? ふざけるな!」暴れる獅子のように辺り構わず怒鳴り散らすアルバノスに私は声を張り上げた。
「落ち着いてくれ! こんな所でわめき散らしてもなんの意味もないだろう!」
大声を上げたのはどれくらいぶりだろうか。争いごとを好かない私は、普段から声を荒げるはない。久しぶりに発した大声のおかげか、少しだけ気分が晴れた気がした。
「確かに、マレウスの言う通りよ。言い争っていてもどうしようもないわ」冷静さを保つカトリーネだが、内心は私たちと同じように何かを叫びたくてたまらないのだ。ジャヌが現れたかと思えば渡されたのは錆びた鍵束ひとつ。自分の身に起きたこと、母親のこと、これからのこと……なにをすべきか分からず、憤りを感じているのはカトリーネも同じだった。
「デカいの、エデシアにある地下牢は知ってるな」アルバノスはジャヌの問いにすぐには答えなかった。威嚇するようにジャヌを睨みつける。
「俺の声が聞こえないのか?」ジャヌは迫る口調で言葉を吐く。
「……知っている。ここから数日はかかる」
「なら、その鍵の使い道も分かるな。エデシアで会おう」
言葉にはしなかったものの、ジャヌの言動は、自分が敵ではないと証明してみせたように感じた。
Episode14 ~エデシア~
ジャヌの言葉に従い、エデシアへと歩を進める。期待に胸が膨らみ、その足取りは徐々に早くなる。街ならば人も居る。ゆっくりと横になれるベッドや、空腹を満たしてくれる食料もあるはずだ。なにより、この世界のことについて情報を得る絶好の機会だ。
私は良いことを考え、悪いことは考えないようにした。そうでもしなければ身が持たないからだ。
アルバノスやカトリーネは全くと言っていいほど疲労感を見せない。すでに数日、少ない
休憩を取りながらひたすら歩き続けているというのに。
カトリーネは、疲れを見せる私を気遣ってか、歩行速度を下げるようにアルバノスに伝えた。
エデシアまでの案内を率先して引き受けてくれたアルバノス。その重そうな身体に似合わない足取りの軽さ。
〝人は見かけによらない〟とはまさにこの事だ。
「アルバノス、無理に私たちと行動することはないのに、ありがとう」
優しい言葉をかけられたアルバノスの口元は微かに緩みだ。
「俺が好きでやっていることだ。気にしなくていい」
さらっと言うアルバノスだったが、〝ありがとう〟の言葉に照れているのが態度から伝わった。
夜明け前の薄明りに照らされる街並み。
その風景に、私は心底救われた。この世界で初めて目にする街灯り。闇や荒廃といったものしか見てこなかった私の目には、爛々(らんらん)と輝く宝石のように見えた。
一方、カトリーネは不安そうな表情を抱えていた。人との関りを避けてきた不安感が押し寄せたのだ。アルバノスと出会った時とは状況が違う。人の住む地へ自ら足を踏み入れることに躊躇していた。
私はカトリーネに言葉を投げかけた。
人と接することは、自分の不透明な未来への道を作ることが可能になると。
しばらくその場を動かなかったカトリーネだが、意を決し、歩を街へと進めた。
街中は早朝のこともあり、ごく僅かな人間しか見ることができない。街並みを眺めながら進むと、ひとりの老人がのろのろと近寄ってくる。
「ここらじゃ見ない顔だね。旅の方かい?」老人は私たちを珍しいものでも見るよう目つきで話しかけてきた。
「さっき着いたばかりで。街なんて久しぶりだ」老人に笑顔を見せ、愛想よく振る舞う。
そのやり取りを見ていたアルバノスは老人に尋ねる。
「この街に。地下牢はないか」誰も想像しなかった直球な質問に、その場を静寂が包む。
いきなり街にやってきた者から「地下牢はあるか」などと聞かれれば当然の反応だ。
それに、そんな場所に用がある者などとはできることならば関わりたくない。老人も恐らく同じことを思っているだろう。
しかし、老人の口からは私の予想しなかった答えが返ってきた。
地下牢のことはともかく、早朝から開いている宿に案内すると言ったのだ。
なんて心の広い人だ、心の底からそう思った。
のろのろと歩く老人の後を追いながら、カトリーネの様子を伺う。
俯(うつむ)き加減で歩き、人とすれ違うたびに表情をしかめるその姿は、なにかに怯えている小動物のようだ。
老人が足を止め、前方を指差す。赤茶色の木造建物に、年季の入った看板がぶら下がっている。
〝ルーエン〟
老人に感謝を伝え、私たちは宿へ入る。扉に下げられた鈴が音色を奏でる。木造建物の独特な香りが漂う空間に、張り詰めていた神経が安らぎ、全身の緊張が一気にほぐれた。
幸福感を抱きながら周りを眺めていると、部屋の奥から黒髪の可愛らしい女性がこちらの様子を伺いながら出てきた。
「……お客?」ぼそっと呟き、力の抜けた瞳で品定めをするように視線を泳がせた。
アルバノスは女性の視線を感じるや、恥ずかしそうに顔をそむける。女性と目線を合わせないためか、しきりに自分の身体を触ったり、荷物袋の中を確認したりしている。
見た目こそ屈強だが、女にはめっぽう弱いのかもしれない。
「……あなたがリーダー?」女性はアルバノスに視線を注ぐ。胸に突き刺さるように見つめられたアルバノスはたじろぎながら答えた。
「いや……その、俺は案内役で……そこの……」
女性はアルバノスの言葉を無視し、私に視線を移し、先程と同じことを言った。
私は事の事情を説明し、泊まれる部屋はないかと女性に尋ねた。
だが、女性の口から出た言葉に黙り込んでしまう。
「1500アリン……」
なんのことかと思ったが、〝1500〟という数字を聞き、今まで忘れ切っていたことを思い出す。
金だ。
なにかを得るには金が必要だと、忘れきっていた。
現実では当たり前のことが、ここでは通用しないが、得るためには資金が必要……それだけはどんな世界でも変わらない。
私はどうしたものかと沈黙し、必死に考えた。だが、この世界の通貨など少しも持ってはいない。助けを求めるようにカトリーネを見るが、首を横に振る。
人に頼らず生きてきたカトリーネも、資金は無かったのだ。
女性は怪しい者でも相手にしているかのように、冷ややかな視線を送る。
完全にお手上げ状態だ。宿代に代わるような物も持っていない。安息を目前にして、最大の敵が立ちふさがった今の気持ちは、今までのなにより残酷に感じた。
「1500アリンならここにある」天使の囁き(ささやき)が聞こえたようだった。
懐から小さな革袋を取り出し、硬貨をジャラジャラとテーブルの上に広げる。硬貨がこれほどまでに神々しく見えたのは人生で初めてだ。子供の頃に数枚の硬貨を握りしめて漫画本を初めて買いに行った時でも、そうは感じなかった。
私たちを救ったアルバノスにこれでもかと言わんばかりに尊敬の眼差しを送った。
「名を……聞いてもいいか」頬を赤らめながら女性に名前を聞く姿は、初々しい子供のようだ。そして、失礼極まりないが、少し気味が悪かった。
「……クレデリア」そうぽつりと呟きながら硬貨を数えた。硬貨のぶつかり合う音が部屋に響く中、カトリーネは外の空気が吸いたいと、建物を静かに出た。
早朝のひんやりとした冷気が肌に当たる。どこまでも広がる空を澄んだ瞳で眺める。
―リズという名も、忘れてほしい―……。
母親の言葉が脳裏に染みついていた。
なぜあんなことを口走ったのか、理解ができない。娘に自分の名を忘れてほしい母親は決してして多くはない。
その言葉を理解できないもどかしさで、カトリーネはどうにかなりそうだった。
今そんなことを考えても答えなんか見つからない……そう自分に言い聞かせた。
だが、親の言葉は子に大きな影響を与える。
カトリーネは母親の言葉に押しつぶされそうだった。誰にも打ち明けることができず、ひとりで抱え込む辛さは相当なものだ。無情にも時間だけが過ぎていった。
クレデリアは硬貨を数え終わると、私たちを部屋へ招いた。三人で過ごすには少し狭かったが十分だ。横になり、周りを気にせず眠れることが出来れば今のところ、それ以上の幸せはない。
カトリーネを呼び、部屋に戻ると不穏な空気が立ち込めていた。
「食事代は別だと言うんだ……」
1500アリンは宿泊代であり、食事は一食につき200アリン必要だと、クレデリアはアルバノスに迫っていた。
私とカトリーネは必要ないと言ったが、アルバノスはそれに苦渋の表情を浮かべる。
クレデリアに渋々400アリンを手渡した。「気にするな……。なにか食べないと身体がもたん」受け取った硬貨を満足げに握りしめクレデリアは部屋を出た。
宿代と食事代で〝1900アリン〟……この世界ではどれほどの価値なのだろうか。とにかく、助けられたこの恩は必ず返すと心に誓った。
Episode15 〜カテーナ地下牢〜
久しぶりのまともな食事が、飢えた喉を通るたびにこの世の恵みに感謝した。
人が生きていけるのも、豊かな恵みがあってこそのことだ。
つかの間の休息を無駄にせずに過ごす。本来の目的を忘れそうになるくらい平和だった。
通りを行き交う人々。賑やかな市場。心地よい陽光に照らされた街。全てが新鮮で、とても穏やかな気持ちになれた。
私は活気が溢れる市場通りを見て回ることにした。たまには息抜きも必要だと思い、旅行気分で通りを歩いた。果物……洋服……雑貨……様々な店が軒を連ねる。
果物屋の前で足を止め、どんな果実があるのか覗いた。
リンゴに似たもの、無数の棘で覆われているもの、小さな種のようなものまで、多種多彩だ。
新鮮な果実の味を楽しみたかったが、これらを買う金などない。ため息をつき、手に取った果実を戻した。
「うまいな。この店は最高だ」その声の主に視線を向ける。
なんとも美味そうに果実にかぶりつくジャヌの姿がそこにはあった。
こんな所で果実を頬張るジャヌの姿を目にするとは想像すらしなかった。
私は冷静に、ジャヌを見つめた。
「お前も食うか?」目の前に差し出される真っ赤な果実。私は自然と果実を手に取った。
もう驚きもしない。ジャヌがいつ、どこで、どんな形で現れようが、飛び上がるほどの驚きはないだろう。
果実を口へ運ぶ。甘酸っぱさと独特な香りがいっぱいに広がる。
「うまいだろ。やっぱり〝ミリャ〟は最高だな」
赤々とした楕円の果実を2、3個手に取ると、私へと身体を向ける。
タカのような目で私に視線を突き刺してくるが、ジャヌはなにも言わずにミリャを食べ続ける。
「地下牢は見つけたのか?」突拍子もない言葉に、私は周囲を見回す。
人でごった返す所で〝地下牢〟などと話しているのを聞かれでもしたら不審者扱いになってしまう。街での行動も制限されかねない。
その時、市場を巡回する兵士らしき男がふたり、こちらに近づいてくるのが目に留まった。
全身黒ずくめの男と一緒に居るのを見られれば怪しまれるに決まっている。更に、ジャヌはひときわ人目を引く。
〝通り過ぎてくれ……〟心の中で兵士に投げかける。
一歩、また一歩と近づき、ついに私たちの前で立ち止まった。
「失礼」兵士のひとりはそういうと、私とジャヌの間に身をねじ入れ、並んでいる果実をふたつ、手に取った。
それを見て安堵の息を漏らす私を、面白いものでも見るようにうっすらと笑みを浮かべるジャヌ。
よく考えてみれば、私はなにも悪いことなどしていない。それなのに妙に兵士を恐れたりするほうが怪しいではないか。
しかし、兵士が取り出した硬貨を奪い取って逃げたいと思ったのも事実だ。
ジャヌと私は市場を離れ、人気の少ない通りへと移動した。
「地下牢はまだ見つけてない。それと、こいつをどうも」ミリャをかじりながら言った。
地下牢はどこにあるのか尋ねると、呆れた顔でジャヌはため息混じりに言う。
「探せ」
なんと感情のこもっていない、冷徹な言葉だろうか。地下牢の場所を知っているはずなのにそれを教えないのは、なにか意図があってのことなのだろうか。
アルバノスが地下牢の存在を知ってはいたが、場所までは分からないと言っていた。
この広い街の下にある牢獄を探し出すのはかなりの労力を要する。
苦い表情を浮かべる私に、ジャヌは口を閉ざす。そして言った。
「……地下牢に案内してやる。だが、〝ひとつ条件がある〟」どういう風の吹き回しだろうか。たったさっきまで、自分で探せと冷たく言葉を吐いていたのに、なぜ突然協力しようなどと言い出すのか。
「条件ってなんだ」
ジャヌは私に一歩近づき、小声で話した。
「俺は地下牢に入れない。だが、この目で確認したいものがあるんだよ」
地下牢があるのは街の外れほどにある〝カテーナ礼拝堂〟の地下にあるらしい。
そして、その礼拝堂を血で汚せというのだ。聖なる場所を血で汚すなど、神の怒りを買いそうだったが、私はしぶしぶそれを了承した。
ジャヌが地下牢に立ち入れない理由は定かではないが、それを聞いたところで素直に答えるような人間ではない。それ以上は聞かず、ジャヌを宿に案内した。
恐ろしい剣幕でこちらを睨みつけるアルバノス。不信感をあらわにするカトリーネ。
当然だ。街を見て回ると言って出かけたはずが、ジャヌを連れ戻ってきたのだ。
〝何を考えているんだ〟と誰でも思うだろう。それが気に入らない相手であれば尚更だ。
私は慎重にことの事情を説明する。しかし、ふたりの私に向ける視線は、冷たかった。
なんの相談も無しに、私の独断で決めたことに憤りを感じているとアルバノスは言った。
一方、カトリーネは私の判断よりも、ジャヌがそこまでして行きたがる地下牢になにがあるのか、いてもたっても居られない様子だった。
「デカいの……」ジャヌの言葉にアルバノスは噴火した火山のような大声をあげる。
「俺の名は、アルバノスだ!」その大声に何事かと、クレデリアが緊張した面持ちで部屋のドアを開き、顔を覗かせる。
その顔をみるなりアルバノスの怒りは鎮火したように見えた。だが、心では怒りの炎が燃え上がっているはずだ。
「クレデリア! ……すまない。驚かせてしまった」必死に感情を抑えクレデリアの目をまっすぐに見つめる。
「……他のお客が怖がるわ」冷ややかな目でアルバノスに言うと、静かにドアを閉めた。私、私たちはアルバノスの顔を何も言わずに見つめる。
「シュッツヘルがエデシアで恋に落ちるとはな」なにかの催し物でも楽しんでいるようにジャヌはクスクスと笑っている。
カトリーネがアルバノスの肩にそっと手を添える。その優しい手はなにを語っているのか。
怒りに震える身体はしだいに収まっていった。
カトリーネはジャヌを一瞥し、口を尖らせた。「人の気持ちを少しでも考えたらどうなの」
ジャヌはその言葉を聞いて、なにか心に訴えるものを感じたのか。生きている以上、感情が全く無い訳ではないだろう。少なくとも、感情が皆無であれば、あの時……アルバノスを殴り続けている私に、声を荒げたりはしない筈だ。
感情無く生きることなど無理な話だ。
皆が出発の準備を整えていると、クレデリアが小さな包みを持ち、部屋へやってきた。
それを受け取り、中身を確認する。
部屋中にパイ生地の焼けたいい香りが立ち込める。
「……旅、気を付けて」
数種の果実が詰められたパイを、生き生きとした表情で私の手から受け取った。
クレデリアに別れを告げ、私たちはカテーナ礼拝堂に向け、出発した。
Episode16 ~パレルソン・マルディシオン~
カテーナ礼拝堂―。
町の活気から追いやられたように、鬱蒼(うっそう)とした茂みの中にひっそりと佇む、荒廃した石造りの礼拝堂。
屋根には子供と母親だろうか、訪れる者を見つめているような彫像がある。
無数にあるほとんどの窓には板が乱暴に打ち付けられ、大きな扉は太い鎖で塞がれている。まるで、中にいるものを逃さず、外からくる者を拒んでいるような重苦しい雰囲気が流れていた。
この廃墟に足を踏み入れるのかと思うと、気が重かった。
歴史的な建造物は嫌いではないが、いつ崩れるかも分からない建物に入るのはどうしても気が進まなかった。しかも、行き先はこの建物の地下だ。なにかの拍子に崩れでもしたら脱出はほぼ不可能、命でさえ助かるかも分からない。
危険を冒すだけのものが地下牢にはあるのだろうか。〝大丈夫だ〟 そう自分に言い聞かせる。
アルバノス、カトリーネも同じことを考えていることだろう。
不安を隠しきれない表情からそれが読み取れた。
ジャヌは礼拝堂の入口へと向かった。足を進めるジャヌは、どことなく緊張しているように見えた。
大きな扉は人ひとりの力では到底開けるものじゃない。おまけに太い鎖で塞がれているのだ。この鎖をどうしたものか。
頭を迷わせていると、アルバノスが鎖を握りしめ、こめかみに青筋を浮かせ、これでもかと言わんばかりに力を込め引いた。
轟音と共に外れ落ちる鎖。この男の馬鹿力と言ったら尋常ではない。普通の人間には不可能なことをやってのけるその様は、まるで神の力でも持っているのではないかとさえ感じてしまう。
鎖の外れた扉を全身の体重を利用して押し開いた。
その瞬間、そこに囚われていた何かが一気に溢れ出してくるような威圧感を感じた。
全身に走る悪寒に、身震いを起こす。
荒れた広い空間の中央に女性像が佇み、それを囲うように背の高い燭台が設けられている。
ゆっくりと中に入る私に、アルバノスとカトリーネも続く。
それを冷たい視線で見守るジャヌ。
乱雑に並ぶ長椅子の間を通り女性像へ近づく。足を踏み出すごとに床の軋(きし)む音が不安に追い打ちをかける。
その時、静まり返る空間に大きな音が鳴り響く。
「すまない……」
アルバノスの体重で床が抜け落ちたのだ。その音にカトリーネは、驚きで飛び出した心臓を押し戻すように両手で胸を覆っていた。
呼吸を落ち着かせ、再び像へと足を進める。
「その像は、手になにか持っているか」ジャヌの問いに答えるべく、私は像の手を確認する。
そこには見覚えのある物があった。古城を出現させた物。
細工の施された小ぶりの刃物にロザリオが巻かれている。
〝ロザリオ〟と〝ナイフ〟だ。
ジャヌはそれを聞きにんまりと微笑むと、手の平をナイフで切りつけ、ロザリオを握るよう言った。
自傷行為をしろというのか。冗談ではない。
血で汚せとは言われたが、〝自分の血〟でという意味には捉えていなかった。
だが、よく確認もせずに条件を飲んだのは私だ。約束を守らなければ、なにをされるか分かったものじゃない。
皆の視線を浴びながら、私は深く息を吐き、手の内に刃を押し付けた。
肉が裂け、神経が切断される痛みに手を震わせながら、ロザリオを力いっぱいに握りしめる。
……パレルソン……マルディシオン――
突然頭の中に流れ込む、枯れた女の声に身の毛がよだつ。
「今の……なに……」カトリーネが真っ青な顔をして震えた声を出す。
「気のせいではないな」その言葉に続きアルバノスが警戒するように呟く。
パレルソン・マルディシオン……オリヘンに刻まれた言葉だ。
そして、この女の声……。
現実で聞いたあの恐ろしい声。
――お前が欲しい……。
恐ろしい老婆の声と共にその言葉が蘇り、恐怖が身体を支配する。
「なにがどうなってる……」
「呪われた言葉」振り向くとジャヌがすぐ近くまで来ていた。足を踏み入れられるようになり、満足げな笑みを浮かべている。
「過去から来世にまで続く呪いだ。それはとてつもなく強大で、消えることはない」
ジャヌのその言葉に続き、アルバノスが重い口を開く。
「オリヘンの力の源とも言われている言葉だ。過去の呪い……詳しくは知らないが、この世界に闇を作り出した者は、前世、現世、来世までも続く、耐え難い苦しみを負うこととなったと、聞いたことがある」真剣な面持ちで語るアルバノスにカトリーネは頭をかしげた。
「ってことは、この場所が、その闇を作り出した人に関係があるってことだよね」
「察しがいいな」ジャヌは感心したようにカトリーネを見る。
「まさにここは、この世界の〝呪い〟のひとつがあった場所だ」
「ひとつ?」カトリーネは更に首をひねった。
「呪いは全部で13ある」
その数字を聞き、興奮したようにアルバノスの顔色が変わった。
「オリヘンの数と関係があるのか?」
〝呪い〟と〝オリヘン〟の数が同じなのは偶然などではなく、オリヘンこそがその呪いだとジャヌは言う。
呪いの保持者はオリヘンを砕いた人物にあり、その者はこの世界にとっての始まりでもある存在だと言うのだ。
しかし、その者が何者で、目的やどこに居るのかはやはり教えてくれない。教える気もないのだろうが。
〝お前が欲しい〟とうめく老婆の声については、あえて触れなかった。時が来れば、その声についても分かるだろうと自分に言い聞かせる。だが、得体の知れない存在が私に迫っていると思うと、やはり大きな不安が残った。
オリヘンについて、知らないことが多すぎる。この世界……夢の真実を導き出すには、重要な鍵となるはずだ。
「これ、地下へ続いてるんじゃない?」
知らぬ間に探索を進めていたカトリーネが低い声で言う。
深い闇が蔓延(はびこ)る地下へと続く階段は、今にも崩れそうなほど劣化している。湿気を帯びた冷気が地下から漏れてくるのが分かる。
降りることに抵抗を感じるカトリーネは〝先に行け〟と目で訴えてくる。
私は、気持ちの悪い空気を肌で感じながら、地下牢への階段を踏みしめた。
Episode17 〜深みへ〜
ひんやりとした鉄格子に挟まれた狭い通路を、慎重に進む。
かつての囚人たちの嘆きのように、天井から滴り落ちる水滴が不気味に音を立てる。
しばらく歩き、通路の終わりに差し掛かるが、目立った物は何もない。
牢獄を順に見て回るが、やはり手がかりになりそうな物はない。
ジャヌはここで何を見たいというのか。これほど殺風景だとは想像していなかった私は、期待に裏切られ、肩を落とした。
「お化けとか、出ないよね……」カトリーネは弱音を吐く。
恐らく、この場所で獄中死した者も居るだろう。幽霊が出ても不思議ではない。ましてやこの世界は普通では無いのだ。なにを驚くことがあるだろうか。
ひとつ、またひとつと獄中を見て回るジャヌを目で追った。
しきりに床を手でさすっては、次へと移動する。
しばらくすると、ドアをこじ開けるような音が聞こえた。音のする方へ向かうと、床に隠された鉄製の扉をジャヌが重そうに持ち上げている。その顔には、いつものようにうっすらと笑みが浮かんでいる。
地下から更なる地下へと続く扉。ジャヌを先頭に、私たちは狭い入口に身をねじ込ませた。
「カトリーネ、マッチ持ってきた?」
「ちょっと待って……蝋燭(ろうそく)もあったはず……」
視界のきかない暗闇で荷物袋の中身を手探り、マッチと蝋燭を取り出し、火を灯した。
辺りが小さな炎で明るく照らされた。
壁一面に広がるどす黒い血痕。降り立ったその場所は真四角の部屋。正面には鎖がかけられた重厚な扉。
また鎖か……。ここまで続けざまに出てこられたら、そう思いたくもなる。
なにかを封じているかのように頑丈に閉ざされた扉に目を凝らす。
〝デリット〟
「これだ。この先にあるものを見たい」血で書き殴られた文字に瞳を近づけ、呟くジャヌ。
鎖に手をかけるが、その頑丈な鎖は普通の人間にはなんとかできるものじゃない。
私は希望を込めた目で私はアルバノスを見た。アルバノスの怪力であれば、この鎖も断てるかもしれない。
「ふん! ぬうう……!」またもやこめかみに青筋を立てる。今にも血が噴き出してきそうである。
ありったけの力を込め、全身が強張る。いくら力を入れようがびくともしない。
そして、全身の力が一気に抜け落ちた。
アルバノスの怪力でさえ、この鎖を断つことはできなかった。
全員で鎖を引っ張るも、鉄がぶつかり合う音だけが無情に響く。冷たい扉の前で私たちは立ち尽くすことしかできなかった。
爆発物でもない限り、この扉の向こうに行くことは難しいだろう。謎の力を持つジャヌであってもこの扉は破れないと言葉を吐く。
この先に何かがあるのは間違いない。しかし、これ以上はどうしようもない。
完全に方策尽きた私たちは他の方法を探すべく、来た道を戻った。
「ジャヌがあんな風に力を貸すなんて、今までもあったの?」カトリーネが私に耳打ちする。
これまで見せたこともない協力的なジャヌの態度。今回は共に扉を開こうと自らの手を汚してまで協力したその目的はなんなのか。そればかりが気になり、周りのことに集中できずにいた。
地上へ戻ってきたはいいが、他の入口があるとは思えない。無駄骨だと分かっていながらも、
礼拝堂を隅々まで調べた。
結局、なんの成果も得られないまま、私たちは礼拝堂を後にした。
「……戻ってきたの」
一日も経たないうちにクレデリアの顔を再び見ることになるとは、誰が思っただろうか。
アルバノスは口にはしないものの、その顔は至高の喜びに満ち溢れている。
「1500アリン……」
ジャヌを除いた皆は互いに顔を見合わせる。さすがのアルバノスもその言葉に顔を曇らせる。沈黙する私たちと流れる気まずい時間。そんな空気をカトリーネが破る。
「今回は泊まらないわ。そんなお金ないもの」
さらっと言いのけるカトリーネを賛美すべきか、非難すべきか……。少なくともアルバノスは非難の眼差しを送っている。
その言葉にクレデリアは面白くなさそうに顔をしかめる。
この状況にどう対応すべきか、私は目を落ち着きなく泳がせる。
「愛か、金か」
クレデリアはジャヌの顔に視線を向けた。
「……愛?」
「アルバノスはお前に恋……」
「お前は黙っていろ!それ以上言ったら舌を抜くぞ!」
ジャヌを深々と見つめるクレデリアの瞳は、どことなく輝いているように見える。
アルバノスはそれを見て懐に乱暴に手を突っ込み、金の入った革袋を取り出した。
「1500アリンだな。 食事も付けてくれ」硬貨の束をクレデリアに差し出し、凛とした態度を見せる。
それを受け取ったカトリーネは宿の中へと私たちを招き入れた。
前回と同様、テーブルの上に硬貨を広げ、一枚、また一枚と喜びに満ちた顔つきで硬貨の枚数を確かめる。その姿を上の空で眺めるアルバノスを、ジャヌはからかった。
「恋は盲目と言うが、お前はそのいい例だな」
カトリーネは呆れたようにジャヌを見て、首を横に振った。
「俺は……力になりたいだけだ」
自分では恋心を隠しているつもりだろうが、傍(はた)からみれば感情剥き出しの恋する男だ。
動物が対象を目前に盛りをあらわにしているようである。
硬貨を数え終わったクレデリアが、前回より広めの部屋に案内してくれた。
前回ほどの安堵感はないものの、やはりくつろげる場所があるというのはいいものだ。
各人それぞれ荷を解き、疲弊した心身を休める。
なにも考えずに休みたいところだが、そうはいかなかった。
金をどう手に入れたらいいか。
ルーエンに滞在するのにも当然ながら金が必要だ。
働いて手に入れればいい話なのだが、こんな私を日雇いでも雇ってくれる者などいるだろうか。ましてや、この世界のこと、通貨の価値すら分かっていない人間など、誰が相手にするものか。
行動よりも先に自信の無さが優位に立ってしまう。
働かずに金を手に入れる方法は限られる。
その時、私の中に〝悪〟が生まれた。
「金を手に入れる」
Episode18 〜大罪への歩み〜
「手に入れるって……どうやってだ? 旅人が働けるような場所はないぞ」
アルバノスの資金源は用心棒、傭兵など、依頼を受けて稼いだと言う。シュッツヘルという立場もあるのだろうが、安定した収入を得ることは難しいと話した。
だったらジャヌはいかにして金を手に入れたのか? 私たちはジャヌ視線を合わせる。
「俺がまともに金を手に入れるような人間に見えるか?」
ごもっともだ。このような謎だらけの人間(人間かどうかも怪しいが)が身を投じて金を稼ぐ訳がない。だが、それこそが私の望むことだ。
犯罪に手を染めるのは気がひけるが、手っ取り早く金を手に入れるには止むを得ないだろう。
「おいおい、俺はお前の思っているような化け物じゃないぞ」
人の心を読む時点で十分化け物じみていると思うが、口には出さなかった。言わずとも考えていることが読めるのだから。
そして、私に待っていたのは非難の嵐だった。
「貴様正気なのか? 私はそんなことに手は貸さないぞ!」
「私もごめんだわ。お金なら他にも方法があるはずでしょ」
アルバノスとカトリーネは犯罪者でも見るような目で私とジャヌを見る。
ジャヌはともかく、私は〝まだ〟犯罪者ではない。だが、罪を犯そうとしている事実を前に反論する答えが見つからない。
「お前たちに調達できるのか?」ジャヌの言葉にふたりは困り顔で私を見る。
ふたりの言っていることは決して間違いではない。それは私も重々承知だ。しかし、綺麗事だけでは前へ進めない時もある。今がその時なのだ。
目前にある物に、手が届きそうで届かないもどかしさに、私は正気を失っているのかもしれない。
一刻も早く礼拝堂へ戻り、この目であの扉の先にある物を確認したい衝動に駆られていた。
金があれば解決策が見つかる筈だ……そう考えていた。
「それで、金のために罪に身を投じる覚悟がお前にはあるのか?」
ジャヌの言葉は善の心に深く突き刺さる。だがその時は善よりも悪のほうが勝っていた。
私の心は決まっている。あとはアルバノス、カトリーネだ。説得してもふたりは首を縦には振らないだろう。
どう説得すればいいか分からない私を悟ってか、ジャヌがぶっきらぼうにふたりに言葉を投げる。
「くだらない正義感で答えへの道を潰すのか。 お前たちは分かってない」
ふたりは心の中で葛藤しているのだろう。沈黙を守り、珍しくジャヌの言葉に耳を傾ける。
「世界はお前らが思っている以上に残酷だ」
この時ばかりはジャヌの言葉に妙に納得できた。世界は正義だけで成り立っている訳ではない。残酷さも兼ね備えているのが現実だ。悪があるからこそ、正義があるように。対となるものが存在するからこそ、世界の均衡は保たれている。
「盗みや殺しがなんだっていうんだ? お前はもっと悲惨なものを見てきただろう?」
シュッツヘルとして生きてきたアルバノスは現在に当たり前に起こる罪よりも遥かに酷い惨状を目に焼き付けてきた。裏切りや殺しが蔓延する暗黒時代に身を委ね、生き残る術を学んだ。人の罪がいかなるものか……人がどれだけ残酷になれるか、経験し、目の当たりにしたからこそ、人道を逸れるような行為は許せないのだろう。
しかし、そんなアルバノスでも、私とカトリーネに問答無用で襲い掛かってきた事実がある。それこそ非人道的行為だ。
「俺は絶対に手を貸さん。 罪に手を汚すくらいなら……」
「理由も聞かずに人に襲い掛かる奴がよく言う」
さすがはジャヌだ。人の揚げ足を取るのにも全く抵抗はないらしい。その一言はアルバノスにとっては致命的な言葉だった。
言葉を詰まらせ再び黙り込む。
「仮に、マレウスの考えてることに手を貸したとして、それで捕まったりなんかしたらどうするのよ? それこそ一巻の終わりじゃない」
カトリーネの言い分も痛いほど分かる。こんな所で捕まればなにもかもが終わるだろう。
だが捕まらなければ終わりではない。旅を続けられるのだ。
一呼吸置き、カトリーネは呆れ顔で言った。
「弟を見放す姉は居ないよね。 はぁ……私は協力するわ」
なんと心の広い姉だろうか。兄弟というのも忘れつつあったが、今はその絆に心からありがたみを感じる。
「弟? 姉? なんの話だ?」
「私たち家族なの。 話してなかったっけ?」
その事実にアルバノスは半信半疑のようだ。自分に協力させるために適当な話を作り、欺こうとしているのではないか、そういったことを考えているのだろう。
「手を貸すのか、貸さないのか、はっきりしたらどうなんだ」
断固として自分の正義を譲らないアルバノスにジャヌは見下すように言った。
黙々と考えた結果、結局私たちへの協力を拒んだ。
自ら進んで罪に身を汚そうとは、誰も思うまい。
それよりも、アルバノスは私とカトリーネが兄弟だということに執拗に固着する。
行動を共にする者の素性は明らかにしたいものだが、説明は今度にしてくれと頼んだ。
アルバノスにとっては納得できるはずもない。エデシアまで案内をし、宿と食事まで身銭を切ったのだ。その上、犯罪に加担しろなど冗談の域を超えている。
どうせこれは私の夢なのだから、なにをしても構わない……その愚かな考えが行動に映し出され、結果的に力を貸す者に対して無礼な言動を行なっている。
そんな自分に今はまだ気付いていなかった。
私たちは金を得る手段を考えた。
詐欺か、盗みか、あるいは強盗か……。手段は限られるが、人を傷つけるのだけは避けたい。
「この街には金持ちが牛耳ってる地区がある。 そいつらから金品財宝を奪えばいい」
ジャヌになら朝飯前だろうが、そう簡単に行くとは思えない。人目に触れず、確実に金品を持ち出せるよう綿密な計画を練らなければ、牢獄で朝を迎えることになる。それだけはなんとしても避けたかった。
「お前も手を貸してくれるんだよな?」
「俺は見張りをしよう」
なにを言っているのだろうか。私たちの中で最も罪に近しい人間が、最も危険性の低い役を引き受けるとは。
冗談ではない……私はそう目でジャヌに訴える。
「どう考えても見張りは私でしょ。 ジャヌはマレウスと行って」
ジャヌの鋭い視線がカトリーネに刺さる。
「なによ」強気な口調でジャヌに噛みつく。ふたりの間にピリピリした空気が流れる。
「……いいだろう。 指図されるのは気に入らんがな」
私たちは金を手に入れるべく、富裕層が集まる地区へと足を運ばせた。
富裕層区――〝ディーウェス〟
私たちが足を止めたそこは、緑生い茂る敷地に豪華に佇む屋敷。敷地の広さは、一般の住居5~6軒は軽々入るだろう。大きな門を守るように巨大な戦士像がどっしりと両側に構えている。
まるで、盗みに入る私たちを予期しているかのようだ。
屋敷の中には必ず金目の物があるはずだと確信した。
「それで、作戦は?」
作戦など考えていない。綿密な計画をと思ったが、そんなものは考えても出てこない。
屋敷まで伸びる見通しのよい庭をどう抜けて、どこから屋内に忍び込み、いかにして金品を持ち出すか、必要最低限のことすら頭に浮かんでこない。
やはり忍び込むのならば夜だろう。白昼堂々盗みに入るのは自殺行為だ。
屋敷の周りを人目をきにしながら見て回る。
忍び込めそうな所は見た感じでは確認できない。屋根へと続く梯子が一箇所あるだけだ。だがそこはなにも遮るものがなく、夜間でさえ梯子を登っている者がいれば遠目からでも気が付くだろう。目立たぬように屋根へとたどり着くのは難しかった。
それでもやらなければならない。私たちの今後を分ける重要なことなのだ。
「正面から入ればいいじゃないか」平然な顔で無謀なことを言うジャヌの考えはいつも理解に苦しむ。なにをどう考えればそのようなことが言えるのか。
ジャヌの言葉を軽く受け流し、私たちは一旦宿へと引き返した。
「なにを深く考える必要がある?」
カトリーネはほとほと呆れているように口を開く。
「あんたなに考えてるのよ。 そんなことできる訳がないじゃない。 正面からですって?馬鹿じゃないの?」
カトリーネの言っていることはもっともだ。
ジャヌになら可能かもしれないが、私たちに死ねと言っているようなものだ。
方法は一つ。梯子を登り、屋根へ出て、そこから屋内に忍び込む。
「面倒だな。 金を奪うくらいでなにをそんなに怯える必要がある?」
「はぁ……。まともな意見が出せないなら少し黙っててくれる?」
「なら好きにしろ」
カトリーネに対しては深く反論せず、ある程度は黙認するジャヌが不思議に思えた。アルバノスや私に対する態度とは明らかに違う。女だからか、それともカトリーネの言葉になにか力があるのか。
どちらにせよ、それが不自然でならなかった。
日も沈んだ頃―。
アルバノスは自ら会話に入ってこようとはせず、敬遠した眼差しで私たちを見ている。
正気なのかと、その目で訴えてくる。
それを気にすることなく、椅子に深々と座るジャヌ。
張り詰めた空気が流れる中、盗みに必要な道具を片っ端から袋へ詰め込んだ。
準備を済ませ、宿を後にする私たちをアルバノスはただ黙って見ているだけだった。
深い闇の中にぼんやりと光を放つ月のもとで、大きな罪への第一歩を踏み出した。
Episode19 〜逆らえない代償〜
月夜に照らされる戦士像。
その脇を暗闇に紛れて通り過ぎる。
街灯の薄明かりが私たちの存在を周りに知らせているようだった。
今からやろうとしていることは本当に正しいのか? 今更になって自分の行動に疑問を持ち始める。
余計なことは考えないにしよう。やらなければならないのだ。
そう自分に言い聞かせた。
屋根へと伸びる梯子を街灯の光が照らしつけるのを見て、一気に不安感に襲われた。
周囲の家の窓からは明かりが漏れている。これでは〝見つけて下さい〟と言っているようなものだ。
カトリーネは落ち着きなさそうに辺りを見回している。
この一本の梯子が、私たちの未来を分けるのだ。極度の緊張で鼓動が早くなり、息苦しさを覚える。
冷たい梯子に手をかけ、一段、また一段とゆっくりと登る。周囲に目を凝らしながら、音を立てないように細心の注意を払った。
屋根へ到達し、下に居るジャヌに手で合図を送ろうとしたが、そこにジャヌの姿はなかった。
カトリーネもいつの間にか消えたジャヌに戸惑いを隠せない様子で右往左往している。
その時、背後から私の肩を誰かが掴んだ。
――終わった―…。
盗みまではいかなくとも、不法侵入には変わりない。言い訳をしたところで、他人の家の屋根でなにをしているのかという話だ。
カトリーネは私の異変に気付き、足早に木の陰に身を隠した。
私は抵抗することなく、振り向いた。
「驚いたか?」
私はその相手を本気で殴ってやりたいと思った。
クスクスと笑いながら私の絶望に満ちた顔を見ているジャヌの姿を今すぐ消し去りたいと願った。
「ふざけんな……それになんで俺より早くここにいるんだよ……」
状況が呑み込めず理解ができないうえに、心臓が普通の何倍も速く脈打っている。
今にも昇天してしまいそうな勢いだった。
突然現れ、突然消える……いつものことだ。それよりも今はジャヌが裏切らなかったことに感謝しなくてはならないのか。
「お前らのような低能と同じにするなよ。 瞬間移動でもなんでもやってやるさ。 それにしてもお前の顔、笑える」
ケラケラと不気味に笑うジャヌを見て、顔面に一発お見舞いしてやろうかと思ったのは言うまでもない。
驚きに荒れる呼吸を落ち着かせ、目立たぬよう姿勢を低くし、屋根を慎重に見て回る。足でも滑らせればそれこそ〝本当の終わり〟だ。
時折ジャヌに視線を移す。まだ唇を三日月に緩めている。不気味だ……。
人の不幸が楽しいのだろう。質の悪い性格だ。
屋根から直接の入口はない。屋根の直下にある、狭い窓から入るしかなさそうだ。
私はジャヌにこちらへ来るよう手招きをした。
壁沿いの縁に足をかけ、慎重に足場を確認しながら窓へと近づく。この時ばかりは重力がとてつもなく大きな脅威に感じた。
普段当たり前のように感じているものが、その時々の状況によって大きく変化する。世界そのものが猛威を振るう瞬間だ。
片手で身体を支えながら、無理やり窓へと手を伸ばす。
その時、手をかけていた縁が崩れ落ち、私は真っ逆さまに地面へと落ちていった。
顔を照らすパソコンの眩しい光――。
窓から吹き込む冷えた夜風――。
水面の波紋のように広がる頭に響く痛みを堪えながら立ち上がり、窓へと近づいた。
カーテンを開け、道路を行き交う車を眺める。
ヘッドライトの明かりが目への刺激となり、頭痛を一層に引き立てる。
懐かしさを感じる現実の空気を大きく吸い込んだ。
「……汚れてる」
夢のような、新鮮で透き通った空気が、たまらなく愛おしかった。
付きっぱなしのパソコンの前へ、再び身体を戻し、椅子に力なく座り込みながら天井を見上げ考えた。
夢で私がやろうとしていたことは、誰かの人生を壊してしまう行為。人の人生に傷を付けてまで自分の求める答えが欲しいのか。
人が逆らうことのできない〝欲〟に飲み込まれて、間違った道を進むのが本当に正しいのか。現実に引き戻された今は、夢の中の考えが間違いだったと不思議なくらい強く認識させられる。罪の意識が、あの世界では欠損していたと感じた。
世界が違えば、これほど思考も変わるのかと、身をもって体験させられた。
ふと時計に目をやると、針は深夜0時を指していた。
私はスマートフォンを手に取り、友人へ発信した。
しばらく呼び出し音が続いたあと、眠そうな声で相手から応答があった。
「遅くにごめん。今から会える?」
深夜にも関わらず、友人は私と会ってくれることになった。
「俺のとこに来てくれるか? 出たくないんだ」
「もちろん」着替えを済ませ、私は友人宅へと車を走らせた。
友人宅――。
懐かしく感じる友人の顔に、私は心が落ち着いた。
――斎条 優二。
私の人生の中で最も信頼できる親友で、十数年来の付き合いだ。
バーベキューや登山、海水浴、キャンプ、ドライブ、旅行……色々なことを共にやってきた。
そんな優二は私の人生の一部だった。
友人が淹れてくれたコーヒーの良い香りが脳を刺激する。
「それで、なにがあった?」
私の表情からなにかを察したのか、コーヒーをすすりながら呟いた。
「ちょっと、色々あってね」ため息混じりに私は言った。
「長い付き合いなんだ。その悩みが単純か複雑かくらい、お前の顔見れば分かる。どうしたんだよ?」
優二の問いに、今体験していることを打ち明けるべきか悩んだ。
長年付き合いのある親友にも打ち明けられない理由があった。
私は幼い頃から、人には見えない何かが見えていた。人から言わせればそれは〝霊感〟と言うのだろうが、私にとってそれはごく当たり前のことだった。ひとりで遊びながら見えない誰かとよく会話をしていたと、母親からよく聞かされたものだ。
だが、それが普段の日常であっても、それらが見えない人間にとっては普通ではない。
人とは違う私に疑念を抱き、責め立て、あげく精神病院へ入れとまで言われたのだ。
そのような環境で何年も過ごしてきた私は、人を信用することができなくなっていた。
そんな自分を理解し、受け入れてくれた優二だが、夢と現実を行き来しているなどといった話を真剣に聞いてくれるのか不安だった。
私はコーヒーをすすり、深呼吸をし、口を開いた。
「夢が……その、夢がもうひとつの現実なんてこと、あり得ると思うか?」
優二は言葉に困ったような顔をした。
「あー……、正夢ってことか?」
「少し違うんだよな……。夢と現実が両方存在していて……」
自分の身に起こっていることを優二に説明する。
「つまり……夢がもうひとつの現実で、お前はその世界を旅していると、そういうことか?」
私は頷き、右腕に残る傷を見せた。
まじまじとその傷を見る優二はなにを考えているのか。
証明や確認のしようがない世界の話など、誰が信じるか。信心深い人間ならば、精神世界や死後の世界……地獄や天国なども信じるだろう。
だが優二はそういった人間ではなく、別世界などの存在には関心がない。
私が優二の立場だったら、簡単は信じられないだろう。
その時、なにかに喜びを感じているかのように、優二の口元が緩んだ。
「いい傷だな」
優二の言葉の意味が分からない。〝いい傷〟とはどういう意味か。
「早く戻ってこないと手遅れになるぞ?」
「おい……なに言ってるんだ」
明らかに様子のおかしい優二は、私の言葉を無視して話し続ける。
「ここでくつろいでいる暇なんてお前には無い。早く戻ってこい」
優二の言葉と共に身体が強張り、見えない力でベランダへと引き寄せられる。必死に抵抗しようとするが、身体が反応しない。
「やめろ、やめろ……」
自由の利かない身体はベランダへの引き戸を開き、手すりから身を乗り出した。
「戻ってこい……!」
その声に抵抗できず、私は4階から身を投げた。
Episode20 〜輝きを放つ希望〜
地面を引きずられる感覚が、全身に伝う。
地面に叩きつけられた私の身体を、カトリーネが乱暴に引きずる。
誰かに見られないよう必死だ。
近くの茂みに私を押し込み、身を隠した。
「……誰だ?」
屋敷から中年の男が現れ、辺りをランタンで照らしながら声を上げる。
私たちのいる茂みへゆっくりと近づいてくる。
暗闇であっても、近くまでくれば気付かれてしまう。
カトリーネは息を殺し、男の動向に目を見張った。
来ないでくれ……切に願うも、それは叶わなかった。
カトリーネの顔をランタンの光が照らしつけた。
「ここでなにをしている!」
男はカトリーネをみるや声を張った。
私は声を発することができずに、ランタンの光をただ見ていた。
屋根から落ち、現実へ戻り、親友の変貌を目の当たりにし、ベランダから身を投じ、挙句見つかってしまったのだ。ここまで災難が重なると、もうどうなっても構わないという気持ちになる。なにをしても、順調にことが進むことなく、悪い結果が待ち受ける。
そういう人生なのだろう。カトリーネを巻き込み、今の状況になにも対応ができない自分に腹が立った。
男が息を吸い込み、叫ぼうとした時、後ろから手が回った。
ジャヌが男の首に腕を回し、動きを封じた。
「静かにしてくれよ」
抵抗する男の耳元でジャヌは囁く。
しかし男は抵抗をやめず、腕を振り解こうと身体を暴れさせる。
その時、骨の折れる鈍い音が響き、男は地面に倒れこんだ。
ジャヌが男の首を捻り折ったのだ。
「あんた……なにしたのよ」
「殺したんだ」
カトリーネの言葉にジャヌは不愛想に答えた。
なんてことをしたんだ……私は目で訴えた。盗みで終わるはずが、人を殺してしまった。
直接手をくだしていないとは言え、私たちが罪なき人を殺したことには変わりがない。
あり得ない事態だ。カトリーネも唖然とした顔で横たわる男の姿を見つめている。
私は身体を起こし、力尽きた男の身体を仰向けにひっくり返した。
頼むから動いてくれ、目を開いてくれ……そう心から神に祈った。
だが、どれだけ祈ろうと、消えた命が再び吹き返す訳もない。
当然だろうという面持ちで私たちを見るジャヌは、命を刈り取る悪魔のように見えた。
「なにをしたのか分かってるの……!? 殺すなんて……!」
周囲を気にしながらカトリーネは必死に声を殺してジャヌに食ってかかる。
目の前で、一切のためらいなく人を殺すのを見せられればそうなるのは当然だ。
「危機から友を救ったんだ。 感謝するべきだろう?」
ジャヌは顔色ひとつ変えずにカトリーネの目をまっすぐ見つめた。
人の命など、ゴミ当然だと語るように。
私は乱れた呼吸を整え、男の死体を探った。
「ちょっと……! なにしてるのよ……!」
異常者でも見るような目つきで私に唸るカトリーネに、私は冷静に答えた。
「今逃げようが、金品を奪って逃げようが、結果は同じだ」
「正気なの!?」
正気だからこその行動だった。
「ない……なにも持ってない……。 屋敷に入ろう」
その場に立ち上がり、青ざめた顔でしゃがみこむカトリーネに手を差し出した。
手を掴み、ふらふらしながら立ち上がるカトリーネを見て、ジャヌは口を開く。
「しっかりしろよ。 人が死んだだけだろう」
その一言に、カトリーネはジャヌを睨みつけるように一瞥した。
「お前もくるよな?」
「もちろんさ。 お前の成長を見てるのが楽しいからな」
成長? 成長しているとは私のどこを指しているのか。成長と一言にしても色々ある。
外見や内面、精神力や考え方……様々な成長がある。
「お前の残酷さだよ。 日を追うごとに本当のお前が見えてきていることに嬉しさを感じるんだ」
私は罪に染まった赤い瞳をしっかりと見つめた。
「心を読むのはよしてくれ。 さっさと終わらせよう」
屋敷へと向かう途中で振り向くと、カトリーネは元いた場所から動かず、私とジャヌを見ていた。カトリーネの元へ足早に戻ると、混乱と恐怖で支配された顔で私に言った。
「私……怖いわ。 お金を手に入れるだけだったはずが、人が殺されて……。 きっと捕まる」
取り返しのつかない状況に陥ってしまったことを、後悔してもしきれない。
そして、恐怖を前に背を向けても、殺しをした事実は変えることはできない。
人道を外れても前へと進むしかない。
私の言動はとても理解できるものではないだろう。
良心の呵責を捨て、どれだけ残酷であっても、今は前に進みたかった。
それが最悪の未来を招こうとしても。
「ここで待っててくれ。 必ず戻る」
カトリーネにそう言い残し、私はジャヌと屋敷へ足を踏み入れた。
屋敷の中に人気は感じられず、静寂な空気が流れている。
中央の大きな階段を取り囲むように背丈の高いショーケースが並でいる。
丁寧に陳列された価値の高そうな物が屋敷内をより豪華に見せた。
金貨、石膏、骨董品、古文書など、どれも歴史的価値のある物ばかりだ。
偽物か本物かは定かではないが、これだけの屋敷であれば、本物だろう。たとえ偽物であってもそう思いたかった。本物でなければ、ここへ来た意味が全くなくなるからだ。
これらを売れば金になる……だが、〝欲〟が私を突き動かす。
欲は身の破滅を招く。だが、命あるものは欲に逆らうことができない。
他にも高価な物があるはずだ……そんな愚かな考えを持ち、私は二階へと足を進めた。
階段を登りきると、きめ細かな刺繍が施された美しい絨毯が私を迎えた。廊下に並ぶ大きな扉は、意匠のこもった模様が彫り込まれている。
ここにある物すべてが芸術だと、屋敷は物語っていた。
ひときわ豪華な彫りが入った扉を開き、暗い室内へ入る。
荷袋から蝋燭を取り出し、火をつけ近くに置いてあった燭台に蝋燭を刺した。
背の高い書棚にはありとあらゆる種類の本がぎっしりと詰まっている。
中には貴重なものもあるのだろうが、大量の本を一冊ずつ確認している時間はない。
部屋の隅に置かれたずっしりとした書机の引き出しをに調べるが、金目の物はなにも見つからない。
その時、爪が底板に引っ掛かり、板が外れた。
二重底だ。底板を外し、隠されている物を手に取り、蝋燭の火に近づけた。
手の平ほどの銅板に【N】と刻まれている。私はそれを荷袋へ放り込み、部屋を後にした。
「いい物はあったか?」
駆け足で階段を降りる私を見て、落ち着き払った口調でジャヌは言った。
「面白いものは見つけた。 全部の部屋を見るのは無理だ。 ここにあるのを持っていこう」
ショーケースに並んでいる品を手当たり次第に荷袋へ突っ込み、足早に屋敷を出た。
「お前はどうだ。 ただ突っ立って俺を待ってた訳じゃないだろ」
「当然だ。 俺をなんだと思ってる。 ここを離れたら見せてやる」
木の陰からカトリーネがそっと顔を見せ、早く来いと言わんばかりに手を招いている。
金品の詰まった重い荷袋が、身軽さを奪い、カトリーネまでの距離が何倍も長く感じた。
息を切らし走る視線の先に、私たちとは違う人影が見えた。
急いで近くの茂みに身を潜める。
その人影はじっとその場に立ち、私たちを見つめているように見える。
「なにをしに来たんだ。 サリッサ」
ジャヌの言葉に、サリッサと呼ばれる人影はこちらへと歩み寄ってきた。
「あなたは、この世界で罪を犯した……。 マレウス……」
明かりに照らされたその姿を見て、私は茂みから這い出た。
カトリーネと出会う前の、古城に現れた女……。
透き通るような白い肌に、青い瞳、すらりとして背は高く、その身を華麗に見せるように白いロングドレスを纏っている。
前のような優しい顔はなく、今は怒りと悲しみが混合した面持ちだ。
サリッサは私からジャヌへと視線を移した。
「ジャヌ……」
「前みたいに逃げないんだな」
サリッサは見るものすべてを凍らせるように冷たい瞳でジャヌを見る。
それを不快に感じているのか、鋭い目を更に細くし、サリッサを睨みつけるジャヌ。
その背後から不安そうに近づいてきたカトリーネは私とジャヌの様子を伺い、口を開いた。
「この人は……?」
善悪を分けるようにカトリーネを見つめる。
人を殺し、盗みに入り、やっと戻ってきた思えば、知らぬ女が現れた。カトリーネの思考は混乱を極めていた。
「……あなたは純粋な人ね。 私が助けてあげるわ」
優しそうに口元を緩めるサリッサに、カトリーネは自分の母の姿を重ねた。
素性も知れぬ、なにひとつ分からない人間だが、どことなく、そして自然とそう思ってしまう。優しさに包み込まれるような感覚に、不思議とカトリーネは心をを穏やかにした。
「この女の言うことは信用ならない。 見た目は良くても、中身は魔物だ」
ジャヌの言葉に説得力が感じられない。自分のことを言っているようではないか。
この男こそ、魔物ではないか。
その挑発的な言葉に、サリッサは笑みを消し、ジャヌに向き直ると、目を細くした。
「私に姿を見せることができるのも、今だけよ。 マレウスの記憶が無くなれば、あなたの存在も消えて無くなる」
私の記憶が無くなるなど冗談ではない。私の記憶は私のものだ。
いきなり現れ、人の記憶が無くなればいいなどと、なにをどう考えれば言えるのか。
ジャヌに引けを取らず、この女、サリッサも酷いものだ。
……私のやっていることも非人道的極まりないが。
「マレウス。 この世界に来れないようにしてあげる……そうすればあなたも、この世界も救われる。 あなたの為なのよ」
そう呟き、サリッサは私に向かって腕を上げた。
手中から眩い光が解き放たれる。それを受け、脳裏から様々な記憶が引き出され、それが映像として視界をもの凄い速さで駆け巡った。
ダムが決壊したかのように、記憶が次々と頭の中から流れ出る。
その時、私を襲っている光がなにかに遮られる。
それは、サリッサと私の間に飛び込んできた、ジャヌだった。
Episode21 〜獅子〜
「殺さないでくれ……」
命乞いをする男の首を躊躇することなく切り落とす。
死んだ方が楽だと思わせるように、ゆっくりと、時間をかけて。
苦悶に歪むその顔が、最高の快感を生む。
死体の山に囲まれて、今まで経験したこともない優越感に浸る。
「いたぞ!」
殺されるとも知らずに、虫のように集まってくる男たち。
槍を手に、身構える男たちの背後から、空気を切り裂く甲高い声が響いてくる。
「待ちなさい!」
額を汗で濡らし、男たちの間をすり抜けてくる女。
「ジャヌ……。 どれだけ殺せば気が済むの……。 もう辞めなさい……」
ジャヌは周囲を包み込む絶望に歓喜した様子で女を見た。
「サリッサ・ウーデン……お前に俺は止められない」
狂気に満ちる赤い瞳をサリッサに向ける。
漆黒の髪が、外から吹き入る風を受け、生き物のようになびく。
その姿は人ではなく、全てを支配する最悪そのものだった。
「人が殺されるのを黙って見てはいられない。 刺し違えてでもあなたを止めるわ」
黒光りの鞘から、鏡のように磨かれた鋭い刃を抜き、ジャヌへと向けた。
「ピュニシオン……それを持つほどの価値が、お前にあるのか」
価値を問われたサリッサは、目を鋭くし、ジャヌを睨みつける。
人に価値を問うのは間違っている。同じ空気を吸い、命を食べ、生きている。
人は皆、平等な生き物だ。
だが、人ではない心を持つ者もいる。
悪の具現化。
ジャヌは、その中のひとりだ。
「オリヘンの破壊……どうやったの?」
サリッサの言葉を聞き、意味深な笑み浮かべ、ジャヌは答えた。
「なにもしてないさ。 あれが勝手に砕けただけだ」
「そんなことがある訳がない……」
「本当さ」
望む答えを得られない苛立たしさを堪え、サリッサは刃を再びジャヌへと向けた。
周りの男たちも、それに合わせ身の丈ほどある長い槍を構える。
周囲をぐるりと見回すジャヌに、焦りや恐怖は一切感じられない。
それどころか、この状況を楽しんでいるようだった。
サリッサは静かに息を吐くと、目を見開き勢いよく足を踏み出した。
鋭い切っ先がまっすぐにジャヌへ向かう。
真っ赤な血しぶきが、その場を包んだ。
夜の街をひた走る。
カトリーネの足の速さといったら尋常ではない。
まるで〝風〟そのものだ。
そのあとを無我夢中で追いながら、時折後ろを振り返る。
だがそこにジャヌの姿はない。
人知を超えた力を持つジャヌを、心配などしたことがなかった。
しかし、今回は別だ。
私をかばい、自らが盾となったジャヌが気がかりだった。
私の後を追ってきてくれ、姿を見せてくれと願う。
だが、その姿を見ることなく私たちはルーエンへとたどり着いた。
扉を勢いよく開き、ルーエンへ飛び込んだ。
クレデリアが身体を跳ね上げ、目を丸くして私たちを見る。
「……なにがあったの」
カトリーネはそれに答えることなく、アルバノスの元へ向かった。
なにも知らないクレデリアに、盗みをして人を殺した、などと言える訳もない。
挙動不審にカウンターに近づき、猫の置物を手に取り気を紛らわせた。
「……それは売り物じゃない」
不思議な子だ。あれだけ血相を変えて飛び込んできたというのに、今は落ち着き払っている。
肝が座っているのか、鈍感なのか、興味がないのか……。なにを考えているのか読めない。
置物を元に戻し、部屋に向かおうとしたがクレデリアに引き止められた。
「……あの人は?」
誰のことを言っているのか一瞬分からなかった。
「……黒い髪の」
「ジャヌか。 名前はジャヌだ。 今は一緒じゃない」
「……ジャヌ」
クレデリアは少し残念そうに肩を落とした。
「あとで戻ってくるよ。 ……戻ってくるさ」
「……そう」
私は肩を落とすクレデリアを横目で見ながら部屋へ向かった。
扉を開けると、アルバノスが物凄い剣幕で出迎えた。
「なにを考えている!」
眠れる獅子を呼び起こしてしまった。
怒りに震える身を見ながら、私は向かいの椅子に座った。
事情を事細かく説明するが、燃え上がる怒りの炎は鎮まる気配がない。
どう説明すればアルバノスの怒りが鎮まるのか。
私に任せたと言わんばかりにカトリーネは部屋の隅から黙ってこちらを見ている。
噴煙を上げる火山を鎮火させろと言われているようなものだ。
そもそも、暴れる獅子を相手にするのが間違っているのだ。
頭が冷えるのを待つべきか、このまま話しを続けるべきか教えてくれとカトリーネに視線を送る。
私に視線を合わせると、口をパクパクさせるが言葉が出てこない。
アルバノスの憤怒に圧倒されてのことだろうが、一言二言くらい言葉が出てきてもいいものだろう。
カトリーネの口から言葉が出てくるのを沈黙を守り待つ。
「その……落ち着きなさいよ……」
なに? やっとひねり出した言葉が 〝落ち着きなさい〟 だと?
もっとまともな言葉が出てこなかったのか。
当然、その一言でアルバノスの怒りが鎮まる訳がない。
言葉の主がクレデリアであれば話は別だろうが。
獣のごとく鼻息を荒くし、アルバノスは私とカトリーネを交互に見る。
ジャヌの無感情さがたまらなく欲しい。
感情が邪魔をしてろくに話をするどころか、言葉さえまともに出てこない。
私とカトリーネは手を出していないと何度説明しても全く聞く耳持たずだ。
アルバノスから見れば、私、カトリーネ、ジャヌは同罪なのだ。
正義感の強さが、分厚い壁を作り邪魔をしている。
―コンコン。
優しいノック音が聞こえ、扉が開く。
「……夕食」
神の使いだ。
なんと最高のタイミングか。怒りに燃える獅子も、天使の顔を見れば冷静さを取り戻す筈だ。
カトリーネもほっと胸を撫でおろす。
殺伐とした雰囲気の室内を見回しながらテーブルに食事を運ぶ。
これほど人を神々しいと感じたことがあっただろうか。
期待を込めて、アルバノスに視線を戻した。
血の気を帯びた顔で荒々しく息をするアルバノス。
なんということだ! クレデリアを前にしても怒りは全く鎮まっていないらしい。
それどころか、話しの邪魔をするなと目で訴えているようである。
出来立ての食事が乗った皿を運び終えると、クレデリアは問い詰めるように言った。
「……普通の空気じゃない……。 なにをしたの……」
その言葉に誰も答えることなく、沈黙だけが流れる。
「あのクソ女。 今度会ったら殺してやる」
静けさを切り裂く惨たらしい言葉。
私たちはとっさに声のする方を見た。
ジャヌが戻ってきたのだ。
この状況に気を遣うことなく、いつもの態度で部屋に入ってくる。
衣服が破れ、顔はひどく汚れている。
泥遊びを終えて帰宅した子供のような有様だ。
「……ジャヌ」
ぼそりとクレデリアが呟く。
その後ろから威圧感を剥き出しにジャヌへと迫る巨体。
「貴様……なにをしたのか分かっているのか!」
「この身で仲間を救った」
ジャヌの答えがアルバノスの怒りをより強くする。
「貴様のやったことだ! 人を殺しただろう!」
「あぁ。 殺した」
それを聞き、クレデリアは身を震わせる。
抑制のきかない怒りに支配されたアルバノスは遂に事の真相を言ってしまった。
しかも、クレデリアの前で。
「……殺した?」
すかさずカトリーネが話に割って入った。
「クレデリア、違うの。 あれはジャヌが……」
そう言うカトリーネに疑惑の念を抱き、距離を取るクレデリア。
その姿を見て、ジャヌは言った。
「人を殺すのに抵抗があるか? 危機に瀕しても正義感を通せるか?」
「それが人道というものだろう! クレデリアにそんな質問をするのはよせ!」
横から割り込み、ジャヌに罵声を浴びせるアルバノス。
首を横に振りながら、見下した態度で、ジャヌはアルバノスに言う。
「人道? そんなものは持ち合わせていない。 そもそも人は互いに争う生き物だ」
ジャヌの言葉は間違っているようで間違っていない。
人間同士の争いは何百、何千年と繰り返し行われてきた。
不思議なものだ。一つ争いが終われば、また一つ争いが起きる。
そこにもやはり、人の欲があるのだろう。欲がなければ、争いなど起きないのかもしれない。
数時間後―……。
冷静さを取り戻しつつあるアルバノスは、腕を組み、ジャヌに睨みをきかせている。
事実を知ったクレデリアは客の対応で席を外していた。
この状況など知ったことかと言わんばかりに、ジャヌはミリャをかじっている。
どうしたものか。言い争った後の沈黙が、言葉を発するのを妨げる。
私は、荷袋から盗んできた銅板を取り出した。
刻まれた【N】になにか意味があるのか、これに価値はあるのか、銅板を見ながら考える。
「N……?」
カトリーネが私に近づき、銅板を覗き込む。
「屋敷で見つけたんだ。 隠されていたから、貴重なものだと思うけど……」
私とカトリーネの会話に興味があるのか、アルバノスは聞き耳をたてる。
「確かに貴重だ」
銅板を見たジャヌは宝でも見るような目で言った。
「これがなにか知ってるのか?」
「当然だ」
Episode22 〜逆戻〜
文字の刻まれた銅板のどこが貴重で、それほどの価値があるのか。
金や銀なら分かるが、銅はほとんど価値がない。
だがジャヌが目を光らせて貴重だと言うのであればそうなのだろう。
私よりこの世界に詳しいはずだ。歴史や文化に関しても知識は豊富だろう。
「これが俺の思ってる通りの物なら、焼きごてがある筈だ」
焼きごて……エルオーデとジャンが遊び半分で使っていた【J】の焼きごてと同じものか。
そうだとすれば、どういった関係があるのか。
銅板から私に冷たい視線を移すジャヌ。
「あの屋敷へ戻る気はあるか?」
死体が放置されている所へなど戻る気はない。
犯人が犯罪現場へ戻る心理はよく知られている。それによって捕まる確率が高まる。
そんな愚かな行動は控えるべきだ。
ジャヌであれば、現場へ戻ったとしても何事もなく帰ってこれるはずなのに、なぜそれをしないのか。それに、私たちには屋敷へ戻る理由がない。
焼きごてだろうとなんだろうと、そんなものは関係ない。
捕まるのだけは御免だ。
カトリーネは首を横に振り、アルバノスは深いため息をつく。
私はジャヌの視線から逃げるように目をそらした。
「なにがあっても戻らない。 自殺行為だろ? やっとの思いでここまで逃げてきたんだ」
「あの屋敷にお前の求めるものがあっても戻らないか?」
求めるものは欲しいに決まっている。だがもう目的は果たした。
金になる物を持って帰れただけで十分だ。
それ以上に今はなにを望むものか。
断固として拒否する私に、ジャヌは追い討ちをかけるように言った。
「人を殺したと、大声で歌い回ってもいいんだぞ」
殺したのはジャヌではないか。しかもなぜ脅されなければならないのか。
「殺したのはお前だろ。 戻るならひとりで戻ればいいだろ」
ジャヌの言葉に苛立ちをあらわにし、私は強い口調で言い返した。
私とジャヌのやり取りをこれまで黙って見ていたカトリーネが遂に口を開く。
「完全にどうかしてる。 元はと言えば全部あんたが悪いんでしょ」
「全部? 金を手に入れると言い出したのはマレウスだろう。 それにおまけが付いただけの話だ。 物事を捻じ曲げるのは関心しないな」
カトリーネは言葉を詰まらせ、無言に戻った。
罪を感じていない者に、なにを言っても無駄だ。罪の意識を感じさせることもできなければ、それを認めさせることもできない。
「ならこうしよう。 今、お前が最も求めているものをくれてやる。 その代わり、お前は屋敷へ戻る。 等価交換だ」
ジャヌは淡々とした口調で話しながら、ずっしりと重い小さな袋を私に向かい放り投げた。
中には金貨がぎっしりと詰まっている。
大津波のような誘惑が押し寄せる中、私は金貨とジャヌの顔を交互に見る。
屋敷へ戻れば更なる富が手に入り、銅貨の謎が解けるかもしれない。
旅の終止符が打たれる可能性もかなり高くなるが。
ジャヌと一緒ならば平気か。私を必要としているのであれば、危機に陥ったとしても助けてくれるだろう。
だが、ジャヌはいつ裏切るか分からない。今までのジャヌの行動を振り返れば、私たちに道を与え、危機的な状況があれば助けてくれた。それは確かだ。
しかし、それはジャヌ本人の目的の為だ。いつ気が変わり、裏切るかも分からない。
金貨を一握り取り出し、己の欲と葛藤する。
十分な金に変えられる物があるにも関わらずに。
「もう十分でしょマレウス。 盗ってきたものを売れば旅は続けられる。 たかが焼きごての為に戻る必要なんてないわ」
カトリーネの意見はもっともだ。そんな事は承知している。
アルバノスは私がどう判断を下すのか重い眼差しでじっと見ている。
黙り込み、考えた。
戻らなくとも、金には不自由しない。しかし旅の目的はどうか。【N】の焼きごてが、あの時見た【J】の焼きごてと関係があるなら、戻るべきだ。旅の目的はまさにそれだからだ。
金は二の次だ。
屋敷に焼きごてがある確証はない。だがそれがあれば、新しい道がひらける筈だ。
目的か、安全か……。
ジャヌに視線を戻し、私は言った。「屋敷に戻る」
満足そうに口元を緩め、窓際へと近づき外の様子を確かめるジャヌ。
屋敷の方向へ目を凝らし、振り向き言った。
「まだ気付かれていないな。 今なら大丈夫だ。 すぐに戻るぞ」
俯きため息を吐くカトリーネ、呆れたように首を横に降るアルバノスを横目に、私はジャヌと共に部屋を出た。
階段を降りると客と会話をするクレデリアがちらりと私とジャヌを見る。
その目は恐れと戸惑いが入り混じっている。
誰かに私たちのしたことを話してはいないだろうかと、気がかりだった。
クレデリアの視線を気にしながら宿を後にし、足早に屋敷へ向かった。
離れた所から屋敷の様子を伺い、辺りに人気がないことを確認しながら暗がりを低姿勢で進む。
視線の先には横たわる死体。なるべくそれを見ないように扉へと急いだ。
「さっさと見つけてここを出よう」
「簡単に見つかればいいが」
ジャヌに一階を探すよう伝え、私は二階へ急いだ。
部屋を片っ端から見て回るが、それらしき物は見つからない。
ありもしない物を探しているのではと時折不安になる。
しきりに窓から外の様子を確認しては部屋の中を右往左往した。
棚の上や後ろ、ベッドの下、壁や天井に隠し扉が無いかまで念入りに調べるが、何もない。
一階に戻り、ジャヌを探しながら部屋を見て回った。
焼きごて一つにこれほど時間がかかるとは思ってもいなかった。
早くしなければ夜が明けてしまう……そうなれば放置してある死体も見つかり、ここから逃げるのも困難になる。
そんな焦りと不安で今にも狂ってしまいそうだ。
「なにか見つかったか? マレウス」
「いや、なにも」
背後から聞こえた声に適当に返事をした。
「マレウス、お前の相棒はどこだ?」
「なんだって? なに言ってるんだよ」
意味の分からない問いに、足を止め振り向くが、そこには誰も居ない。
極度の緊張状態で幻聴すら聞こえてきたか。
私は正気を保つよう頭を叩きながら前方の扉を開いた。
視界に入ってきたものを見て、思わず息が止まった。
私の顔をまっすぐに見る人物。
屋敷の者か、警備兵か……。そんなことはどうでもいい。
私の中の悪が、語りかける。
殺せ。
息の根を止めろ。
駄目だ。
今すぐに、殺すんだ。
目撃者を始末しなければ。その一心で目の前の者に殴りかかった。
Episode23 〜【N】の烙印〜
頭の中を裂くような耳鳴りに耐えきれずに、その場に膝をつき頭を抱え込む。
そんな私を見物するように頭上から眺める人物。
深くフードを被っており顔は見えない。細身の身体に艶のある革製の衣類を纏い、手にはグローブをはめている。
「お前の相棒はどこにいる」
私を見下ろし、低い声で語りかける。
それは感情のこもっていないジャヌの口調に酷似している。
「ニーデか?」
突然のジャヌの声に、その人物は顔を上げた。
「久しぶりだ」
顔を上げジャヌを見る。
同時に、切り裂くような耳鳴りが止んだ。
「なにも変わっていないようだ」
私の横を抜け、ジャヌへと近寄った。
眼前まで顔を近づけ、睨みを利かせるように深々とジャヌの目を見る。
「お前の探しているものはここには無い」
それを聞き、ジャヌはうすら笑みを浮かべ鼻で笑った。
「お前も変わってないな。 相変わらずの変態だ。 人の考えを読んでなにが楽しいんだ? 気持ち悪いだけだ。 寒気がするよ」
「それを言う資格が、お前にあるとは思えないが」
「脳みそが沸騰してるのか? 自分の方が上だと思ってるのか? とんだ勘違い野郎だ」
お互い一歩も引かずに食ってかかる。
ふたりのやり取りは終わりがないように思える。
よくもこれほど反論の言葉が出てくるものだと、関心するところもある。
だが、互いに罵り合うだけでは話が進むわけもない。
子供の口喧嘩と同じだ。
「だいたい、いきなり現れて気味が悪いんだよ。 お前は……」
「やめろ、やめろ。 いつまで言い争う気だよ。 この男はなんだ? どうなってる? ……いや、それは後だ。探してるものがないならここにいる意味がない。 早く離れよう」
ジャヌの言葉を遮り口調を強くして言った。
それが面白くないのか、ふたりは私に睨みを利かせた。
睨まれても困る。しかもここは殺人の現場だ。こんな所で堂々と口論するなど正気の沙汰ではない。
「なんだよ」
「確かにこいつは、俺たちの探してるものは無いと言ってるが……。 それ以上のものが目の前にいるぞ」
ジャヌの言葉に、いつもなら飛びついただろう。
今はそれよりも早くこの場所から離れたくて仕方がなかった。
この男が誰であれ、安全な場所で話をする必要がある。
ふたりにどんな力があろうが、私にはなんの力もない。
この状況を切り抜ける力さえも。
私はふたりに背を向け、ひとりで屋敷を出た。
後ろから私を追ってくる様子もなく、姿すら見えない。
気にするだけ無駄だ。屋敷を離れ、ルーエンへ急いだ。
夜中で人通りは少ないものの、それでも人が多く感じ、私への視線が気になって仕方がなかった。
頼むから見ないでくれ……。そう願ってもすれ違うたびに視線を感じる。
これほどストレスが溜まることはそう無いだろう。
うつむき加減で歩みを進める私の後を、怪しげな人物が付いてくるのがわかった。
歩みを速くするが、やはりその者も同じペースで付いてくる。
嫌な予感を抱きながら、人通りのない路地へと素早く入り込んだ。
身を隠し、追ってくる者を待ち伏せたが、現れない。
数分が経過しても姿を見せない。
私の勘違いだろうか。身の回りのもの全てが脅威に感じている今の私に、冷静な判断などできる訳もない。
それから更に数分、様子を見ていたが、やはり誰も現れない。
私は大通りを避け裏通りからルーエンへ向かうことにした。
私が物陰から身を出したその時だった。
「隠れても、逃げようとしても無駄よ」
私の行く手を阻むように、裏通りへの道を塞ぐ女。
サリッサだ。
最悪だ。こんな場所で、しかもこのタイミングでなぜこの女と会ってしまったのか。
いや、会ってしまったのではない。ここで顔を合わせるのも決められていたことに違いない。
運命か、サリッサの思惑通りか。
何はともあれ、危機的状況だ。今の私に、サリッサへの対抗手段などあるはずもない。
得体の知れぬ力を持つ者に、どう抗えばいいと言うのか。
……考えても仕方がない。逃げられるわけもない。
私はサリッサへと近付いた。
「好きにしろよ」
「なんですって……?」
私の言葉を予想していなかったのか、サリッサは少しばかり困った表情を見せた。
なぜそんな顔をするのか。
好きにしろと言われれば、そうすればよいではないか。
私を狙っている者からすればこれ以上に都合のいいことはない。
「好きにしろと言ったんだ。 お前の好きにすればいい」
サリッサはもっと別のことを予想してたはずだ。そう表情から読み取れた。
拍子抜けした様子で私を見るサリッサは、しばし黙り込んだのち、口を開いた。
「そう……。 抵抗する力すら無くなった?」
「いや違う。 俺には何もできないからだ。 なんの力もない俺が、お前に勝てるはずもないだろう? できることと言ったら……この夢を終わらせることくらいだ」
情けないといった面持ちで私を見る。
サリッサの目的は不明だが、やりたいようにすればいい。
「わかったわ。 これ以上の機会は滅多に無いだろうから」
漆黒の鞘を取り出し、私の目をまっすぐ見つめながらゆっくりと刃を抜き、私の首元へ突きつけた。
「本当にいいのね? ここであなたの人生が終わっても」
嫌に決まっている。まだ人生に幕が降りるには早すぎる。
しかし……この状況では私の人生は終わったのも同然。
だが、あくまでも〝この夢の中では〟の話だ。
私は度重なる問題でこの夢に嫌気がさし、投げやりになっていた。
「この世界だけではないのよ? あなたの世界も、終わりを迎えることになる」
「なに?」
ここでの死が、現実でも起こるというのか。全てが繋がっていると言いたいのか。
あり得ない……。そんなことは絶対に起こりえないと思っていた私にとって、それは見過ごせない事態だった。
確かに、この世界での記憶、痛み、傷に至るまで現実に引き継がれている。
が、〝死〟までも影響するとは考えてもみなかった。
いや……それも、ありかもしれない。
これから先、生きたとしても待っているのはたかが知れている。
生きるために必死になって、困難や苦境を繰り返し乗り越えるだけの人生だ。
もちろん、良いこともあるだろう。だがそれは、過酷を乗り越えた〝褒美〟でしかないではないか。
こんな人生に意味があるのか、疑問だ。
「あぁ……好きにしてくれ。 やれよ」
「……本気なの?」
なぜだろうか。追っていた獲物が目の前に、しかもいつでも狩れる状態にあるというのに、サリッサの額からは汗がにじんでいる。
刃を握る手は先ほどまでとは違い、小刻みに震えている。
サリッサを動揺させるようなことがなにかあっただろうか。
しばらくすると、サリッサは刃を下ろした。
なにがどうなっているのか。
なにが原因で意気消沈したというのか。
「今回は退くわ……。 次に会う時までに、自分のことについてよく考えておくことね」
そう言い残すとサリッサは夜の闇に消えていった。
「病んでるな」
「お前に言われたくない」
サリッサが立ち去ったのを見計らったようにジャヌが現れた。
「避けてたのか?」
なぜサリッサの前に姿を見せなかったのか、ジャヌに尋ねた。
「なんの話だ?」
「サリッサだよ。 さっきまでここに居た。 分かってただろ」
「クソ女がここに? それを知ってれば、飽きるほど痛めつけて八つ裂きにしてたさ」
どうやらジャヌは本当に知らないらしい。
何かがおかしい。サリッサの存在にジャヌが気付かないはずがない。
それどころか、つい先ほどの出来事の一部始終すら把握していなかった。
なんでもお見通しのジャヌに限ってこんなことがあるのか。嘘をついたり隠すような理由も思いつかない。
考えても無駄だ。
ジャヌを一瞥し、ため息を吐いた。
「あいつは?」
「誰だ?」
「屋敷で会った男だ」
「あいつなら消えちまった。 俺が怖くなったんだろうさ」
相変わらず達者な口だ。
「あいつは何者だ?」
「ニーデ・リーゼン。 変態さ」
「お前と同じように、人の心を読む。 それに、無感情だ」
「そうだ。 あいつは、表には出ない人の本質を覗き見て、快楽を得てる」
「お前と、関係のある存在か?」
ジャヌはそれ以上聞くなと言った目で私を見る。
〝それ以上のもの〟と言われれば、気になるのは当然だ。
「あの目、あの挙動、お前と同じに感じた。 無感情な言葉も、全部含めてな。 それに、付き合いが流そうじゃないか」
私はジャヌに話を遮られよう、思い浮かぶことをを片っ端から言葉にした。
「なぜ心を読める? お前らの得体の知れない力はなんなんだ? サリッサもそうだが、奴らの目的は一体なんなんだよ」
負の感情をここぞと言わんばかりに吐き出した。
「そんなに知りたいなら教えてやるさ。 そうすれば少しは黙ってくれるか」
両手を広げ、首を横に振りながらジャヌは言った。
「確かにあいつとは、嫌になるほど長い付き合いだ。 お前も分かってるだろうが、俺には烙印がある」
私は軽く頷いき、ジャヌの胸に目を向けた。
「あいつにも、同じように烙印が押されてる。 Nとな。 俺たち烙印を持つ者は特別なんだ」
「特別? なにが特別なんだ?」
「存在自体が、特別なんだよ。 その辺を歩いてる肉の塊共とは訳が違う」
見下したような目で語るジャヌに、少し腹が立った。
肉の塊だと?
与えられた人生を生き抜くために、日々を過ごす者達への冒頭だ。
中にはなに不自由なく生活している裕福な者も、顎で人を使う者もいるだろう。
だが、どんな人間であれ、生きることを否定することはできない。
それを、歩く肉の塊などとは、あまりにも酷いではないか。
今に始まったことではないが、時々ジャヌやその周りの者の発言に心底腹が立つ。
人生を軽く終わりにしようとした私が言える立場ではないが……。
「何が特別なのかは、そのうち分かるだろう。 そして目的だが……はっきり言うと分からん。 俺の目的は分かってると思うが、奴らも同じ目的とは限らない」
「奴ら? その特別な存在が、他にもいるのか」
ジャヌのような得体の知れない者が、まだいると思うと嫌気がさす。皆、ジャヌのような人物なのか。勘弁してほしいものだ。
「目的不明の特別な存在……。 敵か味方かも分からないが、少なくとも味方ではなさそうだな」
「どうだろうな。 どちらにせよ、あいつらを甘く見ないことだな。 殺されかねない」
「お前も含めてか?」
ジャヌは深いため息と同時に首を振った。
「俺があいつらに殺されるとでも? あり得ない、それだけは絶対にな」
なぜそう言い切れるのか。仲間だからか? 特別な存在同士だから? 互いに殺し合いはできないと? 次々と疑問が押し寄せる。
珍しく素直に説明したかと思えば、疑問を残すような言い方をする。
いい加減にしろと言いたいが、問い詰めたところで意味がないだろう。
普段のジャヌを思えば、これだけ聞ければ大収穫だ。
「それで、なぜ殺されないと分かる?」
私は期待せずに聞いた。
「よく考えてみろ。 あいつらに俺を殺せるほどの力があるか? 少し考えれば分かるだろうよ」
そんなもの分かるはずがない。奴らが何者で、どれだけの力を有しているのかさえ、検討もつかない。ジャヌの力すら未だにどれだけのものか、分からないのだから。
その時、警備兵が慌ただしく屋敷の方へ向かい駆けて行く姿が目に入った。
屋敷で起きたことなど忘れていた。
できれば思い出したくなかった。忘れたまま旅を続けられればどれだけ楽か。
どんなに願ってもそれは実現しない。人を殺したという罪に苛まれながら生きていくのだ。
私はそれを受け入れるしかない。
「話は後だ。 ルーエンへ」
「待ってるぞ」
そう言うとジャヌは闇へ消えた。
「全く……。 他人事だな……」
闇に溶け込んだ影は、立ち去る私をただ見ていた。
―マレウス……。 またすぐに会える……。
Episode24 〜衝突する思い〜
「マレウス!」
ルーエンの前で私に気付いたアルバノスが、血相を変えて声をあげた。
いつものような獅子ではなく、額に汗を滲ませ、血の気の引いた顔だ。
私のいない間に一体何があったのか。
「やっとの思いでここまできたんだ……! 大声を出さないでくれ。 まわりの気を引きたくない」
アルバノスにそう唸り、私はルーエンに入ろうとした。
しかし、そんな私をアルバノスは制止した。
「待て! 話がある。 こっちへ」
アルバノスと私は、すぐ傍にある細い路地へ入った。
呼吸を整え、言葉を選ぶようにアルバノスは口を開いた。
「カトリーネが、連れ去られた。 俺が居たにも関わらず……すまない」
「なんだって? 誰にだ?」
私の様子を伺いながら慎重に話すアルバノス。
少し前まで猛獣のように敵意を剥き出しにしていた者とは思えないほどだ。
私が怒鳴り散らすとでも思っているのか。
「女だ。 背丈はお前と同じくらいで、細身。 顔は分からん、口元に革製のマスクをしていた」
「話したのか?」
「いや、話していない」
「なぜ女だと分かった? 男の可能性もあるだろう」
「それはない」
私の見間違いか、アルバノスの顔が赤みを帯びているように見えた。
そして恥ずかしそうに言った。
「……露出が、多かったんだ」
このような時に恥ずかしがっている場合か。露出度がいくら高かろうが関係ない。
カトリーネを連れ去った人物には変わりない。
「抵抗しなかったのか? アルバノス……お前の方が力はあるはずだろ」
「あの女……ただ者ではない。俺には何もできなかった」
アルバノスに勝る女……。またもや力を持った者か。
「次から次へと……」
私は額に手を当て、その場にしゃがみ込んだ。
浅はかな考えで、深みへはまってしまった。そして、事は最悪な事態にまで陥った。
己の愚かさを責め立てる。
だがいくら責めたところで過去の過ちを正すことはできない。
「ジャヌを見てないか?」
「見ていない。 あの男のことなどどうでもいい! 今はカトリーネの行方を……」
「分かってる」
アルバノスの言葉を遮り私は立ち上がった。
今はカトリーネが無事なのを祈るしかない。まずは情報を集めるのが先だ。
「クレデリアがその女を見ているかもしれない」
ルーエンへ戻ろうとする私を、アルバノスは再び制止した。
「待ってくれ。 クレデリアを巻き込むのはよせ」
「他に方法があるのか? 他の誰に聞けばいいんだ? 教えてくれ」
わたしはアルバノスに苛立ちをあらわにした。
度重なる負の連鎖に私の心は歪み、それが表へ顔を覗かせている。
冷静な行動はおろか、まともに考えもできない状態だ。
しかしアルバノスはそれを察することなく、分かりきっていることをあたかも私が知らないかのように言ってくる。
降り注ぐ槍に突き刺されているようである。
アルバノスに罪が無いのは分かっている。私が全てを招いた元凶なのも承知している。
頭では理解していても心が追いつかない。
いつもと違う私を見て、アルバノスは眉をひそめる。
わたしはそれを気にすることなくルーエンの扉を開いた。
出迎えたのはクレデリアではなく、にんまりと笑みを浮かべた美女だった。
「こんばんは。 ここのお客さん?」
「店主はどこだ?」
美女の言葉など耳に入っていない。一刻も早くカトリーネを見つけ出したい、その一心で周りを見回す。
だがそこにクレデリアの姿はない。
「クレデリアは……彼女はどこだ」
「ちょっと、私の声聞こえてないの?」
後から入ってきたアルバノスは美女を一瞥し、カウンターへ目をやる。
クレデリアの姿が見えず、少し慌てた様子で再び美女を見た。
「宿の者か?」
「私? 違うわよ。 ここのオーナーに用があるの」
「クレデリアに?」
「あら、名前知ってるのね。 お友達かなにか?」
「違う。 俺たちはここの客だ」
毅然とした態度のアルバノスを見つめながら、美女は言った。
「お客さんね。 それは残念。 あの子、友達が少ないから」
「そうなのか? 友達になれるものならなりたいが…」
緊張で強張った身体をほぐすように左右に身を捻りながらそう言うアルバノスの目は落ち着きなく泳いでいる。
美女の言葉に反応し、クレデリアとの発展の可能性を感じているのか。
そんなことは問題が片付いた後にしてほしいものだ。
「あなたは? クレデリアの知り合いのようだが」
「エクレールよ。 エクレール・フィアンソロ」
エクレールは笑みを浮かべ、ハキハキとした口調で答えた。
「俺はマレウス、彼はアルバノスだ」
「フルネームは?」
私とアルバノスは顔を合わせた。
名前を聞いてくる者は多くいるが、フルネームを訪ねてくる者など滅多にいるものではない。
アルバノスは少々戸惑いながらも、エクレールの問いに答えた。
「アルバノス・オレガノ・ヴィゴーレ……」
良い(オレ)香り(ガノ)がしてきそうな名だ。
エクレールは満足げに頷き、私を見た。
「……マレウス・アマルティ……シリオ?」
自分のフルネームなど覚えていない。おかしな話だろう。自分の名が分からない者など普通はいない。
その時、アルバノスが横から割って入ってきた。
「マレウス・アマルティア・エクシリオ」
「珍しい名ね。 そんな名前、今までに聞いたことがないわ。 興味をそそられるわね」
興味を持たれても困る。
エクレールは名前フェチなのか。
アルバノスが身を寄せ、静かに耳打ちをした。
「お前の名、カトリーネから聞いたんだ」
カトリーネの名を聞き、私は本来の目的を思い出した。
エクレールのペースに完全に乗せられてしまっていた。
「人を探してるんだ。 髪を束ねた……」
カトリーネの特徴を伝えるが、それらしい人物は見ていないとエクレールは答えた。
カトリーネはもちろんのこと、クレデリアの身も心配だ。買い物袋を抱えて、帰ってくればそれに越したことはない。
「そういえば、さっき警備隊が血相変えてディーウェスの方へ走っていったわね。 あの子が巻き込まれていないといいけど……」
「……とにかく、ふたりを探そう」
エクレールの言葉を無視し、私は話を逸らすことだけを考えた。私のしたことを知られては、エクレールも脅威になりかねない。
アルバノスは口を閉ざし、横目で私を見ていた。
このような状況で外を出歩くのは気が進まない。一刻も早くエデシアから離れたいが、そうもいかない。
仲間を見捨てるなど、できるものか。
「そうね。 街の人に聞いてみましょう。 この騒ぎなら人もいるはず」
騒ぎの当事者が、堂々と街の人間に話を聞くなど、気が進まない。 他に方法はないものか。
どうしたものかと、アルバノスに視線をやる。
「……そうだな。 それがいいだろう」
ぼやくようにアルバノスは答えた。
その声には焦りと緊張が混じっているように思える。
ルーエンを出るふたりを見ながら、魂が一緒に出てしまうほどの深いため息をついた。
「勘弁してくれよ……」
近くにあった帽子掛けから、へたれたつば付きベレー帽を手に取り、ルーエンを出た。
夜更けにも関わらず多くの人々が表に出て、何事かという面持ちでディーウェスの方を見ている。
まるで地獄のようだ。
今にも後ろから肩を掴まれ連れて行かれるのではないかと不安に襲われる。
アルバノス、エクレールは誰かれ構わず聞いて回っていた。
ベレー帽を深く被り、人気の少ない所で身を落ち着かせた。
周囲に目を凝らしながらふたりを見守る。
今の私にはそれしか出来ない。これまでの一部始終を第三者に見られている可能性もある。
人の間を縫うように、私に近づいてくる男が目に留まった。
見た目は警備隊ではなさそうだ。だが、威厳のある顔にしっかりとした体格。他とは違う、高級そうな背広がやたらと目立つ。
「俺はお前を追ってきた」と言っているようだ。
「関わらないでくれ」そう思いながら私は男と目が合わぬように顔を下げた。
しかし、そんな思いとは裏腹に、男は私の前で足を止めた。
「エデシアの者か?」
「……」
男の問いに、私は答えることなくその場を離れようと機会をうかがった。
それを不審に思ったのか、男は更に質問した。
「見慣れない……いや、見たことのない服装だ。 もう一度聞くが、エデシアの者か?」
「……違ったら、なんなんだ」
「どうもしないさ。 少し気になってな」
男は私を舐めまわすように見ると、再び口を開く。
「君には興味がある。 なにか……不思議なものを感じるんだ」
「なぜだ」
「初めて見る衣類、他とは違う空気……なんというか、別の世界から来たような、そんな感じだ」
その言葉に顔を上げ、男の目をまっすぐ見た。男も同じく視線を合わせる。
この男には見透かされている気がする。
「それで、俺に何の用だ」
「この先で男が殺されてな。 その犯人を追っている。 何か知らないか?」
真実を追う者が、追われる者になった瞬間だった。
Episode25 〜追う者追われる者〜
「……マレウスを見つけました。 男と一緒です……シュッツヘルかと」
「アマルティア……。 まだエデシアに?」
「おそらく。 連れの者が姿を消し、それを探しているかと……」
「なにか、気になることでも?」
「……サリッサ・ウーデンと話していました」
「なにを話していた」
「マレウスを、殺そうとしているようでした。 しかし、そのまま去りました」
「……ピュニシオンを持っていたか?」
「はい。 間違いありません」
「そうか……。 まだ、アマルティアを狙っているようであれば、殺せ。 サリッサは脅威になりかねない」
「わかりました。 ジャヌはどうします?」
「手を出すな。 あいつは必要だ。 それに、お前に対処できる相手ではない」
「私では、ジャヌに勝てないと?」
「そう言っている。 シュッツヘルにも手を出すな」
「……わかりました。 エデシアへ戻ります」
―夜明け前のエデシア―
太陽が顔を見せる前の、瑞々しい空気が漂う。
「そろそろ聞かせてくれないか? エデシアになにをしに来たんだ」
しつこい男は嫌われるとはよく言ったものだ。
背広の男は長々と私に付きまとい、遠回しに同じ質問ばかりしてくる。
「名前も知らない奴に、答えるとでも思ってるのか?」
私の言葉を聞き、男は目を丸くし、咳払いをした。
「これは失礼した。 私はヴァイゼン、 ヴァイゼン・クルーク」
「ヴァイゼン、お前の質問に答えるつもりはない」
「待ってくれ。 私は名乗った。君の名も教えてくれないか?」
「……マレウスだ」
私を追っている者に名を教えることなどしたくなかったが、教えないのも不審に思われる。
疑われるような真似はできない。
協力的な態度を見せたいが、それによって墓穴を掘らないかが心配だ。
ヴァイゼンがこの世界においてどういった役割を担っているのかは定かではないが、私にとって都合の悪い人間なのは確かだ。
慎重に言葉を選び、行動する必要がある。
「マレウス、君に声をかけたのは、他の人間には無いなにか特別なものを感じたからだ」
「そう言われて嬉しいが、ここには旅の途中で寄っただけなんだ。 あそこに部屋をとってて、外が騒々しいから出てきただけだ」
ヴァイゼンはルーエンを一瞥し、ため息を漏らした。
「そうか。 時間をとらせてすまない。 しかし、犯人はこの手で必ず捕まえたい……宿を尋ねるかもしれないが、構わないかな」
「……好きにしてくれ」
ヴァイゼンは私の顔を記憶するようにじっと見つめたのち、人混みに消えていった。
額に滲んだ汗を拭い、息を深く吸い込み、ゆっくりと吐き出した。
緊張と焦りに震える身体を落ち着かせようと、必死だった。
遠目からチラチラと私を見るアルバノスは、こちらへ来いと私に手を振ってみせた。
「あの男はなんだ?」
大きな顔をすぐ横まで近付けてアルバノスが言った。
私は一歩、アルバノスから距離を取った。
「名前はヴァイゼン。 殺人犯を追ってるんだそうだ」
「新たな脅威と言うわけか。 ヴァイゼン……用心せねばな」
「アルバノス……お前はこの件には関わっていないだろ。 気にすることは……」
「例え俺が直接的に関わっていなくとも、俺にも責任がある。 それが仲間というものだ」
目を大きくし、力強く言うアルバノスは私の顔をまっすぐに見た。
アルバノスは、私が思っている以上に皆のことを思っている。
ルーエンに部屋を借りるのも、アルバノスがいなければ叶わなかったことなのに、私はその恩を返すどころか、厄介事に巻き込んでしまった。
罪を犯していない者が、仲間の犯した罪を自ら背負い、行動を共にしようと言うのだ。
生半可な覚悟ではできないことだ。アルバノスの意思の強さが、痛いほど伝わってきた。
「……ありがとう」
「今更なんだと言うんだ。 俺は、俺にできることをしているだけだ。 お前達には腹が立つこともあるが……これまでも、これからも、仲間ではないか」
この世界で涙腺が緩んだのは初めてだ。その相手がアルバノスになろうとは、神であろうとも予期していなかっただろう。
私の涙は枯れたと思っていたが、そう簡単に人の涙は無くならないらしい。
あくまで、今は涙腺が緩んだだけだが。
「それはともかく……この辺の者はカトリーネとクレデリアの姿は見ていないそうだ」
「エクレールは?」
「この先にいると思うが……なにか情報を得ているかもしれん、探そう」
アルバノスを先頭に街の中心部へと進んだ。
現実世界での〝朝市〟と言ったところか、早朝にも関わらず既に多くの露店がひしめき合っている。
活気ある通りを眺めながら私はふと思った。これほど大きな街であれば〝闇市〟も存在するかもしれないと。盗品を一刻も早く金に換えたかった。殺人の証拠など持っていたくない。
そんなことを考えながらしばらく歩いていると、前方の店にエクレールの姿が見えた。なにやら店主と揉めているようだ。
「エクレール。 なにがあった? なにをそんなに揉めている」
「1000アリンで情報を売ってやると言われたの」
「それで、情報は手に入れたのか?」
エクレールはアルバノスに向き直り、両手を大きく広げた。
「情報を得てれば、こんなに言い争うこともないわ! 見て分からないの? 私はちゃんと1000アリンを渡したのよ! でもこの人、それほど重要な情報だったら、もう1000アリン上乗せで渡せと言い出したのよ! あり得ないでしょ! これじゃ詐欺師と一緒よ!」
早朝から怒声が響く市場も、そうあるものではない。
普段見ぬ光景に困惑の表情を浮かべる者もいれば、面白がって笑いながら見物している者もいる。
他人の不幸は蜜の味。争いや揉め事を好んで見る人間は多いが、悲しいことだ。
確かに、他人の不幸を見ることで自分が救われることも少なからずはあるだろうが、それは自分自身の心を汚してしまう。霞んだ心に輝きを取り戻すことは、非常に難しいことなのだ。
今までにそんな人間を何人も見てきた。
私自身も、心が霞んでしまった人間の一人だ。
エクレールと店主の言い合いをただ黙って見ながら、私は脳裏に深く刻まれた過去の出来事を思い返していた。
仲間の揉め事を静観している私は、周囲から見ればとても不思議だろう。
「マレウス! なにを突っ立っている! このままでは警備隊が来てしまうぞ!」
アルバノスは私の肩を鷲掴み、身体を激しく揺さぶった。
この状況で私はなにをしているのだ。過去を振り返っている場合ではないではないか。
とっさにエクレールと店主の間に飛び込んだ。
「あいにくだが、1000アリンは持ち合わせていない。 ……これでどうだ?」
店主は私の差し出した大きめの指輪を受け取り、品定めを始めた。
金の装飾に、綿密な彫りが施された指輪、間違いなく高価な物だ。1000アリンどころの代物ではないだろう。
アルバノスはエクレールを店主から引き離し、険しい顔でなにやら話している。
しばらくして、店主が笑みを浮かべた。
予想もしいなかった高価な物を手中に収めたことに、さぞご満悦なことだろう。
だが、この指輪は盗品で、持ち主は死んでいる。
指輪にその怨念が宿り、店主になにか起こったとしても……知ったことではない。
これは取引だ。
「教えてくれ」
「あんたらが探しる人は向こうに行ったよ。 妙な雰囲気だったよ、最初にきた二人は重苦しい感じで、それを追うようにルーエンの嬢ちゃんがコソコソと……」
店主は指輪を自分の指にはめ、至高の喜びを感じているのか、高ぶった口調で楽しげに話す。
これで一人の男の人生に華が咲き乱れるのであれば容易いことだ。
「ありがとう。 指輪、似合ってるよ」
アルバノスとエクレールを呼び、店主から引き出した情報を説明した。
「本当に向こうに行ったと言ったの?」
「間違いない、そう聞いた」
「そんな……」
エクレールの表情は瞬く間に険しくなった。
「リゲイリア地区……。 あそこに用があるのはヤバい人達だけよ」
「どういうことだ?」
困惑と不安が溢れ出る顔で、エクレールは私に向き直った。
「犯罪の温床地帯よ。 あんな所に行ったら半日……いえ、1時間だって安全ではいられないわよ。 とにかく、リゲイリアはヤバいのよ」
「だが、二人はそこへ行ったんだろう? ならば、行くしかない。 クレデリアは助けを待っているに違いない。 ……カトリーネもな」
「カトリーネ? ……あなた達の仲間ね」
アルバノスが〝クレデリア〟と口にする度に〝男〟が成長しているように見えた。
力の源となる者がいるのは素晴らしいことだ。
不可能だと思うことも可能にし、自ら危険に飛び込んでも正義として帰還する。
「とにかく、そのリゲイリアって所に向かおう。 手遅れになる前にな」
「あなた達はリゲイリアがどんなに酷い場所か知らないから、簡単にそう言えるのよ……」
「では、お前は残るんだ。 俺とマレウスは、問題事には慣れている。 それに……この世界はマレウスの……」
アルバノスが次の一言を口にする前に話を遮った。
「エクレール、あとは俺達に任せてくれ。 身を危険に晒すことはない。 だから……」
「私をただの女だと思ってるのね! あなた達がどこの誰だかは分からないけど、私は強いわ。 それにクレデリアは〝妹〟よ! 放っておける訳がないでしょう」
エクレールの突然の豹変ぶりに私とアルバノスは目を丸くした。
そして、アルバノスは戸惑ったように口を開いた。
「な……い、妹? クレデリアの、姉なのか……」
「そうよ」
「いや、その……そうとは知らずに、失礼なことを……姉とは……」
先程までの威勢はどこに消えたと言うのだ。
確かにクレデリアの姉だとは驚きだが、アルバノスの変わりようにも驚きだ。
「気にしないで。 私のことを心配してくれたんでしょ。 それに、妹の為に身を投げ出すあなたは気に入ったわ」
「それは……嬉しい限りだ。 だが……俺は、クレデリアとはなにもないんだ……」
「当然でしょ。 妹の好みじゃないもの」
天高くから、降り注ぐ一本の強烈な稲妻が、アルバノスの脳天を撃ち抜く。
「好みでは……ない……。 ……そうか」
アルバノスにとって、エクレールの言葉は渾身の一撃だったに違いない。
みるみるうちに力が抜けるアルバノスが切なくてならない。
どう言葉を投げかけてやれば良いか……いや、投げかける言葉などない。
余計なことは言わず、今はただ見守るのが、最高の処方箋だろう。
〝口は災いの元〟だ。
呆然と立ち尽くすアルバノスを正気に戻し、私達はリゲイリアへ向け出発した。
―リゲイリア地区―
荒廃した路地に吹き抜ける鉛を含んだような冷たく、重い風。
エデシアには様々な顔がある。
リゲイリアは、その中でも邪悪な部分だ。
「中心街とは、まるで別世界だな」
「イデリア地区のこと? そりゃそうよ」
「……イデリアと言うのか」
覇気がないアルバノスなど、アルバノスではない。
完全に意気消沈している。
いつも通りのアルバノスに戻るまでは時間がかかりそうだ。
「人気がないな。 リゲイリア自体が死んでるみたいだ」
「そんなとこよ。 ここは〝死〟そのものだもの」
それ聞き、不安にならない者はいないだろう。
しかし、私は興味を沸かせた。
死の地区に何が待っているのか、何が隠されているのか……それらを考えると良からぬ好奇心が湧き出てくる。
高揚感にも似たような感情。
冒険心をくすぐる何かが、ここにはある。
私は高ぶる気持ちを抑え、一歩を踏み出した。
Episode26 〜ようこそ、地獄へ〜
荒れた路地を慎重に進む私に、エクレールは静かに聞いた。
「あなた達は、何を目的に旅をしてるの?」
その問いに私は言葉に詰まった。
馬鹿正直に「この夢の謎を解こうとしている」などと言えない。
言えば変人扱いか、精神を病んでいると思われる。
この場にジャヌが居ない事に、心底感謝した。
ジャヌが居れば、エクレールの問いに間髪入れず即座に答えるだろう。
「この世界はこいつの夢だ」と。
アルバノスと目が合うが、何も言わずに視線を逸らした。
それを見過ごす事なくエクレールは更に噛み付いてきた。
「人には言えない? ただの旅ってわけじゃなさそうね。 ……気になるわ」
気にしなくともよい。 人には様々な事情があるものだ。
それにわざわざ首を突っ込んで聞く事でもないだろう。
エクレールは少々質問が多い。 知りたがりが悪いわけではないが、知らない方が良い事もある。
エクレールの質問を適当に受け流し、私達は路地を抜けた。
イデリア地区とはまるで別世界。
暴動が起きた後のようにほとんどの建物は廃墟同然、ゴミが散乱している通りには現実で見るよりも一回り大きいネズミが這い回っている。
このような劣悪な環境で暮らしている者が居ることが信じられない。
誰も見当たらない現状では、危険は感じない。
このような環境に慣れたように、アルバノスは辺りの廃屋を見て回る。
それをエクレールは心配そうに固唾を呑んで見守った。
「あるのはガラクタだけだ」
「何を探してるのよ?」
「……手掛かりだ」
アルバノスは眉間にしわを寄せ呆れたように呟いた。
アルバノスもエクレールの質問の多さに少々疲れている様子だ。
その時だった。
前方の崩れかけた建物の中に、人影らしきものが動いたのが見えた。
「見たか?」
アルバノスは頷きながら私の横に立ち、建物を凝視した。
しかし、何分経っても再びそれを確認する事は出来なかった。
この状況にしびれを切らしたのか、エクレールは私を押しのけ力強く歩き出した。
何を考えているのだ。
いつどこから奇襲されてもおかしくない状況での無謀な行動に、アルバノスはすかさずエクレールの肩を掴んだ。
「何を考えている……! 自殺行為だぞ!」
「じゃあどうしろって言うの?」
アルバノスの腕を振りほどき、威圧的な目つきを見せた。
その力強い眼力に圧倒され、反論する言葉が出てこないアルバノスは、母親に叱られる子供のようだ。
男勝りなのではない。女として、真の強さを持っているエクレールを、心の中で賞賛した。
「エクレール、その辺でいいだろ。 アルバノスは心配して……」
「ちょっと、あれ見て」
よほど人の話を遮るのが好きらしい。
それが趣味なのではないかと思うほどだ。
心の中でこれでもかと大きなため息をつき、エクレールの指差す方へと顔を向けた。
「ただの煙じゃないか」
エクレールの威圧感が私の背後からも読み取れる。
言葉を誤ったか。
「煙が上がってるってことは、あそこに何かがあるのよ」
「それくらい……いや、行ってみよう」
後ろで不満そうにしているアルバノスを呼び、エクレールの後に続いた。
「エクレールは苦手だ」
「……俺もだ」
肩を落とし、力無く言うアルバノスと同じ意見だ。
決して悪い人間ではないが、いささか言葉が過ぎる。
ペースを乱される事に慣れていない私にとって、それはストレスになった。
やがて私達は煙を発する主に辿り着いた。
逆十字型の大きな磔柱に人が括り付けられ燃やされている。
その光景を見たエクレールはその場に倒れこみ口を押さえ込む。
なんと悲惨な光景だろうか。酷すぎる。
死んでから焼かれたのか、行きながら焼かれたのかは不明だがどちらにせよ惨すぎる。
「また美味そうなのが迷い込んだのか!」
その声は耳障りなほど高く、人を不愉快にさせる。
奇声にも似た声を持つ男は、続けざまに言った。
「肉は新鮮なほど美味い! それが焼きあがるまで大人しく待っていてくれ!」
男は焼かれる人を指差しながら笑いを含み大声で叫ぶ。
エクレールは我慢ならず遂に胃にあるものを地面に吐き出した。
人を食うなど正気の沙汰ではない。
死の地区……名ばかりではないようだ。
鬼の形相をしたアルバノスが猪の如く男に向かい突進するが、周囲から湧き出てきた者たちに囲まれてしまう。
彼等は銃火器のようなものを手にしており、抵抗の余地がなかった。
息を荒くしたまま、アルバノスは彼等に怒声を浴びせた。
「クレデリアとカトリーネはどこだ!」
「あん? 美味そうな名前だ!」
ふざけた奴だ。
完全に頭のネジが外れている。
「ふざけるのも大概にしろ! お前のような……っ!」
アルバノスは膝に重い一撃を与えられ、その場に倒れ込んだ。
「兄貴に敬意を払え」
取り巻きの一人、華奢な体の男が堂々とした態度でアルバノスを見下ろす。
敵を見上げる事など無かったアルバノスは、プライドを傷付けられ、怒りに震えた。
獅子が再び顔を見せるのも時間の問題だ。
「兄だと? あれが貴様の兄だと言うのか。 愚かな兄だ!」
「俺達の兄貴だ」
男の言葉に感極まった兄貴は、けたたましく叫んだ。
「ジーク! お前は俺の誇りだ! そう、俺はお前達の兄貴!」
その言葉に、周囲の者達は一斉に声を合わせ、狂ったように叫び始めた。
「サナラ! サナラ・デル・ドレ! サナラ! サナラ・デル・ドレ!」
カルト集団なのか。皆、狂っている。
リゲイリアが死の地区と呼ばれるのは、これが所以か。
リーダーである、サナラを崇める者達は、顔を赤くし、必死に叫ぶ。
「ジーク! お前は俺の最も身近なシティアだ! こいつらはお前が料理してみせろ!」
「兄貴の為なら」
どうやら、取り巻きの事を総称してシティアと呼ぶらしい。
そして、シティア達はサナラの為なら何でもする……死ぬ事さえ厭わないのだろう。
カルト集団と言うのは非常に厄介な存在だ。
表面上だけではなく、心、深層心理に至るまで洗脳され、自我を失い忠誠を誓うのだ。
人は脆く、弱いものだ。
「立て。 早く!」
カルトの言う事など聞いてたまるものか。
断固として無視を続けていると、ジークが乱暴に私の腕を掴んだ。
「後悔するぞ」
私は一言、ジークに言った。
その言葉に深い意味はない。とっさに出た一言だった。
後悔させるどころか、私が後悔することになるかもしれない。
「俺に逆らうことは、兄貴に逆らうのと同じだ。 早く歩け」
「一つだけ、教えてくれないか? 俺を焼き殺す前に」
ジークはサナラを一瞥し、どうしたものか少し考えているようだ。
彼の挙動からして、まだ自分の意思は残っているだろう。
「女が三人、来なかったか?」
「……知らない。 無駄口を叩くな」
周りを気にしながら、口を小さく動かしジークは言ったが、それをサナラは見逃さなかった。
「ジーク。 俺に隠れて内緒話か?」
「とんでもない、兄貴」
強引に身体を引っ張られ、地獄の業火の如く燃え盛る大きな炎へ連れていかれた。
炎の中にいる者を間近で見て、私の心は激しく乱れた。
「生きたまま、やったのか」
「悲鳴は、料理の味をより一層引き立てる」
「……お前等は悪魔だ」
「悪魔? 俺達は何より崇高な行いをしてる」
「人を食べる事が、崇高だと?」
「力を得る為だ」
私に続き、アルバノスも炎の前に立たされた。
しかし、エクレールだけは別の所に連れていかれた。
「彼女をどうする気だ」
私達のやり取りを見かねたサナラが、遠くから叫びながらこちらへ近づいてきた。
「俺の言ったことが理解できなかったのかジーク。 俺は腹ペコだ!」
「兄貴。 今からやるところだ」
サナラに怯えを抱いている様子で、ジークは頷いた。
「お前達! 新たな力を得る時だ!」
「やめろぉ!」
サナラの言葉に続き、ジークは私を炎の中へ蹴り入れた。
アルバノスの声がリゲイリア全体に響き渡る。
全身の毛が瞬く間に焼け、次第に皮膚が爛れ、血を含んだ真っ赤な肉が剥き出しになる。
熱さや痛みでは表現しきれない、いっそ死んでしまった方が楽だと思うほどの苦しみが肉体と精神を襲う。
赤々と煮えたぎる溶岩の中で永遠の拷問を受けているようだ。
「マレウス! マレウス! 貴様ら後悔させてやるぞ!」
アルバノスの怒声が、炎の壁を貫き私の耳へ入ってくる。
夢の世界で、私は死ぬのだ。あと数分で、命も、この世界も、現実も、消えて無くなる。
身体が苦痛に耐えきれず自然と暴れ出すが、頭は冷静でいられた。
これも夢の中で起きている事だからだろうか。……現実ではない事に感謝だ。
カトリーネ、アルバノス、クレデリア、エクレール……そしてジャヌ。
私はここで終わりのようだ。また何処かで会える事を、心から願っている。
Episode27 〜根を失う渇望の世界〜
部屋に設けられた錆びた鉄格子から、陽光が差し込む。
普段なら身体に染み渡る気持ちの良い光のはずが、今はそれが苦で仕方がない。
両手は縛られ、口にはテープが貼られろくに息もできない。
目の前に設けられた奇妙な祭壇を見るのにももう飽きた。
数日間飲まず食わずで、屈強な身体も限界を迎えそうになっていた。
すると目の前の扉が、音を立て開いた。
入ってきたのはサナラだ。
「アルバノスと言ったな? どうだ、ここも悪くないだろう? 肉を熟成させるには最適な場所だ!」
サナラはアルバノスの顔からテープを剥がし、水の入ったグラスを差し出した。
「……これでどうやって飲めというんだ」
「そうだった。両手が使えないんじゃグラスも持てない!」
両手を縛っている縄を切り、再びグラスをアルバノスに差し出した。
それを手に取り一気に口へ流し込む様を見て、サナラは満足げに微笑んだ。
「肉は腐りかけが一番美味いんだ。 屍肉は食べない主義でなぁ」
「…貴様には死がお似合いだ」
アルバノスの言葉に、気分を害す事もなくにんまりと微笑む。
ここまで精神的に異常をきたしている者には何を言っても無駄だ。
中でもサナラは特異で、被虐的な言葉を快感に変える事ができるようだ。
「相棒のことは残念に思うが、俺達の力を増幅させる為には仕方のない犠牲。 イデリアに返り咲く日の為に!」
このような者がイデリアに解き放たれてしまえば、エデシア全体は瞬く間に混沌に陥ってしまう。
警備隊が出てこようと、紛争が起き混乱を招くのには変わりない。
アルバノスの正義にかけて、そのような事は起こさせないと心で固く誓った。
だが、まずはここから如何にして脱出し、カルトを全滅させるかが最大の課題だ。
簡単な事ではない。外には無数のシティア、こちらには武器もない。
巨大な蜂の巣へ裸で突っ込んで行く真似などできない。
それに、縄の解けたアルバノスが抵抗しない理由が他にもある。
エクレールだ。
この拠点の何処かに囚われているはずだ。
アルバノスが行動を起こせばエクレールの身はもちろんのこと、カトリーネやクレデリアにまで危険が及ぶ可能性がある。
それが枷になり、自由に事を起こせないのだ。
「貴様には鉄槌が下る。 必ずだ」
「もう下っている! イデリアから追放されたあの日から!」
サナラは目を血走らせながら叫び始めた。
「貴様は叫ぶことしかできないのか。 ……無能な奴だ」
「俺は! 再びイデリアへ戻り、当時の威厳を取り戻す!」
この男のどこに威厳があったのだろうか。
見る限りでは人間離れした異常者としか思えない。
人の過去は様々だが、この男に限っては自慢できる過去など持ち合わせていないだろうと、アルバノスは思った。
「兄貴、女の件で話が」
「ジーク、話の途中だぞ?」
「分かってるが、重要な事で」
サナラは物足りなさそうな面持ちで再びアルバノスに縄をかけ、ジークと共に部屋を出た。
二人の足音が聞こえなくなるのを待ち、扉を足で蹴った。
しかし扉は開くことはなかった。
八方塞がり。
打開策となるものが何も無いまま時間だけが過ぎることに、アルバノスは憤りを感じた。
アルバノスが監禁されている部屋よりも少し大きめで、寝具やテーブルなどの家具がある部屋に、エクレールは囚われていた。
「女! ジークに言った事は、本心か?」
「女じゃない。 エクレールよ」
名前で呼べと、サナラを威圧的な目で見る。
それを面白くないと感じたのか、サナラは気分を整えるように一呼吸置き、再び口を開いた。
「エクレール。 ジークに話した事は本心か?」
「もちろん、私はあなた達のやり方が好きだわ。 あなた達の言う力が、私も欲しい」
確かめるような目でエクレールを見つめ、しばらく黙り込むサナラ。
その横からジークがサナラに耳打ちをした。
「女は貴重だ。 男には無いものを持っている」
「分かっている! この女の言葉が真実か確かめているところだ、ジーク!」
横槍を入れたジークは静かに部屋を後にした。
「さて……俺たちだけだ。 本心を語り合おうじゃないか!
「だから、本心だって言ってるじゃない? 何度言わせるのよ」
「俺の聞きたいのは、お前の意気込みだ! エクレール、力を得たら何をする?」
エクレールは姿勢を正し、サナラの目を真っ直ぐ見つめた。
「あなたのシティアになるわ。 力をつけて、組織に貢献したいの」
「組織? あぁなるほど俺達のことか!」
サナラはこれでもかと目を大きくし叫んだ。
エクレールの組織という言葉に強く反応し、表情を緩める。
カルト集団ではあったが、名称は無かったのだ。
「俺達にも名が必要だな!」
頭を悩ませているのか、浮かれているのかよく分からないサナラは楽しげに右往左往した。
カルトの主導者がこのような男では、部下が可哀想だと、エクレールは思った。
一方のアルバノスは、自慢の怪力で縄を引き千切る為、渾身の力を両腕に込めた。
しかし、どれだけ力を入れようが、縄はびくともしない。
何かがおかしい。体力が消耗しているとはいえ、アルバノスであれば容易い事だ。
もう一度、全身に力を入れる。額に浮かぶ青筋が今にも破れる勢いだ。
「ぬうぅ……! ……なぜだ……なぜ力が入らん……」
「シュッツヘル。 数少ない生き残り」
「誰だ!?」
突然の声にアルバノスの身体は強張り、鼓動が早くなる。
視線を上げると、革製の衣類を身に纏い、深くフードを被った者が、アルバノスを見下ろしていた。
「私はニーデ。 アルバノスだな?」
「何者だ……。 カルトの者か」
「私は【N】の烙印を持つ者。 それが何を意味するか、お前には分かるはずだ」
「烙印だと……? 何を言っている。 貴様は一体……」
ニーデが何を言っているのか理解が出来ないアルバノスは混乱の最中にいた。
突然現れた謎の男、己の力が出せないこと、カルトからの脱出……。
一人では抱えきれない問題に、アルバノスの思考と精神は追い込まれていた。
「アルパガスを殺す者ならば、烙印を持つ者も知っているはずだ」
「貴様はアルパガスか……」
「違う。 もっと上の存在だ。 ジャヌは知っているな」
「あぁ……。 マレウスの友だ」
「友か……」
友と聞き、ニーデはため息混じりに口元を緩めた。
「奴に友は居ない。 居るのは敵だけだ」
「あいつに興味などない。 腹立たしいだけだ……」
「それもまた、お前の運命に大きく関わりがあるからだ」
「何が言いたいんだ」
意味深な事ばかりで、確信に触れないニーデの目的は一体何か。
アルバノスの前に現れたのならば、目的があるはずだ。
「お前を自由にすれば、私の力になるか?」
「力だと? 俺に何をやらせる気だ?」
「無理にとは言わない。 ここで奴等の餌になりたいのなら、それでもいい」
「……ここで死ぬつもりはない。 貴様の力とやらに、なってやろうじゃないか」
アルバノスとニーデの、取引は始まった。
サナラはエクレールを瞥見(べっけん)しながら部屋中を落ち着きなく歩き回っている。
「〝パニコス〟! 俺達は今日からパニコスだ!」
「パニコス……。 センスあるわね、さすがだわ」
〝リゲイリアのパルコス〟。
エデシアの新たな脅威が今、生まれた。
「お前は俺達に希望をくれた! 俺達もお前に希望をやろう!」
「感謝するわ。 具体的に、希望ってなに?」
「お前の友、アルバノスを料理しろ! そうすれば、お前も今日からパルコスのシティアとして、迎え入れよう!」
「アルバノスを……」
不意をついた要求にエクレールは言葉を失う。
アルバノスを料理……殺す事など出来ない。
そんな事をしてしまったら、サナラと同じ側の人間になってしまう。
自らカルトへ入りたいと言うエクレールの思惑に反している事だ。
エクレールは自分が洗脳されたふりをして、リゲイリアを抜け出す気だった。
しかしそれが墓穴を掘った。悪い状況を更に悪化させてしまった事を悔やんだ。
「出来るか? お前にあの男を料理出来るか?」
「出来るわ……」
答えは一つしかなかった。
「パルコスの諸君!」
高みからの叫びに、シティア達は顔を上げた。
サナラを見るその眼差しは、神でも見ているようだ。
「俺達は今この時からリゲイリアのパルコス!」
パルコスとは何かと、シティア達は戸惑うように互いに顔を合わせた。
突然の事で頭が回っていない様子だ。
そして、サナラの横に立つエクレールにシティアの視線が集まる。
「この女はエクレール! 今日、仲間の男を料理し、新たなシティアとなる! ……な、なんだ!?」
その時、サナラの周囲に深い闇が現れ、それに飲み込まれた。
行き交う車に目を奪われるサナラは、奇声を発した。
「なんだ!? 鉄の……鉄の塊が動いている!」
そのうち一台が、サナラの前で停止した。
「車道に突っ立てんじゃねぇよ! 危ねぇだろうが!」
「なんだと! この俺に向かってそんな口を聞くな!」
しかしサナラの言葉を聞くことなく車は走り去った。
「ここはなんだ! この世界は! ……俺の、俺の新しい世界! そうなのか!?」
JNNE〜Dreams and reality〜