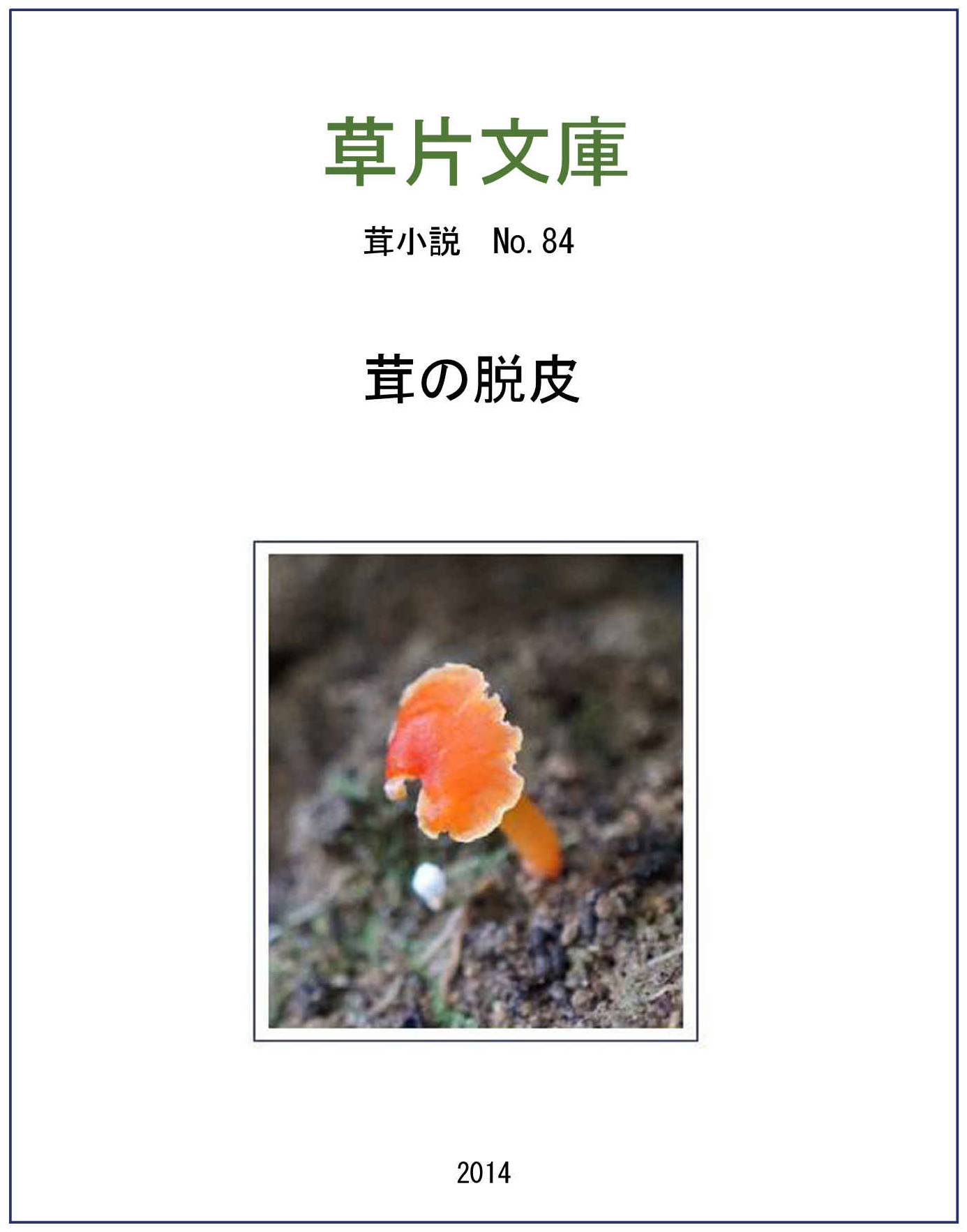
茸の脱皮
春先のことである。庭の青木の下に小さな蛇の抜け殻が落ちていた。アオダイショウであろうか、まだ子供のものである。
部屋に持って入り、空いている瓶に入れ、日付を書き入れた。家のまわりで見つけたカタツムリの殻や、死んで落ちていた玉虫など、空き瓶にいれて本棚に置いてある。日付を書き入れてあるので、それを見るとそのときのことを思い出す。
周りに緑の多い丘陵地帯の団地であるため、昆虫や野草、茸は豊富である。今年は近くの神社や我が家の庭にまで網笠茸がたくさん生えた。おかげで何度かおいしい思いをした。
蛇の抜け殻はここに越してきた二十年前には、春になると必ずと言ってよいほど道に落ちていたものである。しかし近年はほとんど見かけない。道に落ちていた抜け殻を拾って瓶に入れてあるが、十数本ほどになった。ということは五年ほど前から蛇の抜け殻を見かけなくなったということだ。その頃にしても庭先に落ちていたことはない。はじめてのことである。
庭を眺めていると変なものがあった。オブラートのようなものでできた真っ赤な風船のような袋である。寒葵の花の近くにおちていた。三センチほどの大きさである。拾ってみると、オブラートと違って、かなりしっかりしていて、ゴムのような感触である。先がふくらんでいて、ぽちぽちと穴が開いている。
寒葵の生えている奥には椿の木があって、その下の数本の海老根に立派な蕾がついている。今年も良く咲きそうだと見ていたら、見慣れない赤い物が脇に立っている。近づいてみると赤い網笠茸である。赤い網笠茸など聞いたことがないし、図鑑でも見たことがない。
拾った赤い袋がよく似た形をしている。私は赤い袋をガラス瓶にいれ日付と採取場所を記入した紙を脇に貼った。
次の日の朝、椿の木の下をのぞいてみると、また赤い網笠茸の袋が落ちていた。木の下には赤い網笠茸が立っている。昨日より大きくなったようだ。手に取った網笠茸の袋を見ると、昨日拾った物より少し大きい。
それから赤い網笠茸は毎日少しずつ大きくなり、必ずその前に赤い袋が落ちていた。
袋の出所を知りたくなった私は、夜中に懐中電灯を持って庭に出た。夜の十二時である。赤い網笠茸を懐中電灯で照らすと、なんと、もこもことからだを動かしている。根は張ったままでからだがくねっているのである。しばらくすると網笠茸の頭の方から、服を脱ぐように赤い袋がせせりだし、前にぽとりと落ちた。網笠茸はそのあと、ぐんと大きく膨らんだ。
網笠茸が脱皮しているのである。私は毎日夜中に網笠を見に行った。拾った網笠茸の殻が十数個になった。それだけ日数が経ったということである。今では背の高さが二十センチメートルほどになった。ずいぶん大きな網笠茸である。食したら美味しいだろう。だが色が赤くて食べるのは躊躇する。
とうとう網笠茸の殻が三十になった、すなわち一月経ったのである。網笠茸そのものは三十センチほどに成長している。
それと同時に、どういうわけかカタツムリの殻が毎日茸の脇に転がっていた。
私は朝早く日の出の頃に庭に出てみた。カタツムリが赤い網笠茸に近づいていくところであった。フタスジマイマイである。
フタスジマイマイが網笠茸の下にいくと、網笠茸の頭がおじぎをしてカタツムリを飲み込んだ、いや、吸い込んだ。そのあと茸はもこもこと動いていたが、ぷっと言う音とともに、カタツムリの殻を吐き出したのである。
食虫茸だ。信じられない。夢でも見ているのだろうか。この茸は蝸牛をおびき寄せる匂いを出しているようだ。それから毎朝見ていたが、カタツムリがやってきて、食われてしまった。
梅雨になり、カタツムリの殻が増え、夏がきても、赤い網笠茸の脱皮は続いた。そのころになると、私がのぞき込むのを覚えているようで、カタツムリを食べるのをそれまで待っていて、私が顔をだすと、飲み込んで殻をぷっと吐き出し、それも高く吹き上げ、私の目の前に落ちるようにした。まるで自慢しているようだ。
そこで、それを受け止めてやったところ、なにか嬉しそうに、からだをくねらせた。どうもコミュニケーションをとりたいようだ。
最近、脱皮を見ることができないが、今日は久しぶりに抜け殻が自分の前に綺麗に横たえて置いてある。どのように茸に気持ちを伝えることができるのか、皆目見当がつかなかったが、とりあえず話しかけてみることにした。
「おはよう」と言ったところ、網笠茸がうなずいた。
わかっているようである。
「いい天気だね、今日も暑そうだね」
と言ったところ、やっぱりうなずいた。
「夏は好きかい」ときいたところ、いやいやをした。椿の木の下は日陰ではあるが、土は乾ききっている。
そこで、ジョウロで水をかけてやった。
網笠茸は実をよじらせて喜んでいる。
すると、見ている間に赤い茸は脱皮をして、ちょっとばかり大きくなった。ここのところ脱皮をしなかったのは水不足だったのだ。
そのときから、たまに水をかけてやった。
赤い網笠茸の抜け殻はずいぶんの数になり、途中から押し花にしてある。まだ五十センチほどだが、それ以上になると押し花用の紙がなくなる。
秋の気配が感じられるようになったときである。赤い網笠茸が、椿の下にやってきた四十雀(しじゅうから)を吸い込んで食べているのに出くわした。
どうなっているのだろう。これは茸なのだろうか。
本格的な秋になり、網笠茸の隣に、名のわからない茶色の小さな茸が生えた。赤い網笠茸は首を伸ばして、その茸も吸い込んでしまった。共食いである。虫や鳥を喰うだけではなく、仲間も喰う雑食の意地汚い奴である。周りに草が生えていないのはみんな喰っちまったのだろう。
無駄と思いながら、聞いてみた。
「なにが一番好きなんだ」
そうしたら、茸がおじぎをし、頭の頂上の口をあけて舌をだした。その上には茸がのっていた。茸が一番好きと言うことなのだろう。舌があることは初めて知った。舌があるのなら、しゃべれるのだろうか。
「おまえしゃべれるんじゃないか」
赤い網笠丈はうなずいた。
「それじゃなんかいってみなよ」
それを聞いて、横に傘を振った。
「どういう意味だい、しゃべれるかときいたら、うなずいたじゃないか。今はしゃべることができないということか」
また、うなずいた。そのうち話ができるようになるのだろう。茸と話ができるのは面白いかもしれない。
庭にでるのが楽しくなった。朝まだ暗いうちから茸に話しかけた。
「まだしゃべれないかい」
だが、なかなか、声がでない。秋も深まったある日、同じように話しかけると、
「うーん、うん」
と声を出したときには、大いに驚いて、楽しくなった。しかし、まだまともに話しができないようだ。
雪がちらつき始めた。
「寒くないかい」ときいたときには、うなずいて、「うん」
と言った。その声は、あどけない子供のような声だった。そこで、藁のようなもので囲おうとしたら首を横に振った。暗くなるのがいやなのかもしれない、そこでエアークッションで仕切ってみた。光を通すが風は通さない。
少し嬉しそうだ。
寒くなったら、脱皮もしなくなった。食べるものも少なくなったはずである。試しに猫の餌をおいてみた。茸は興味深げに頭をまげ、ちょっと含んでみたようだが、いやいやをした。そこでアスパラガスをおいてみたらうまそうに食べた。ささみ肉をおいてみた。これも食べる。毎日、私の食事から残りを与えることにした。私は独り身なので自炊をしている。時間のないときには弁当などを買ってくることもある。
クリスマスイブになった。夕方は大学のクラスメートたちと飲み会だったので、帰りは夜中になった。帰る頃には雪がちらつき始めた。家に入る前に庭をのぞくと、薄くつもった雪の中で、茸はどうも寝ているらしい。いびきのような音が聞こえる。
もう十二時近い、家に入って風呂を沸かした。風呂であったまったあとすぐにベッドにはいった。年をとった仲間たちの自慢話やら、グチやらを思い出しながらあっと言う間に眠りに落ちた。
夢の中で、だいぶ前に死んだ猫の白が枕元にきてくしゃみをした。
「おい、風邪引いたのか」と夢の中で猫に話しかけたところ、
「ああ、寒い、ここにいたい」
と白が言うので
「いいよ、ほら、入るか」と布団の脇を持ち上げると、白がぴょいと飛び上がって、布団の中に入ってきた。夢はそこでうち切られ、朝までぐっすりと寝た。
窓の外が明るくなって、目が覚めると、今日はずいぶん冷えている。リモコンをベッドの脇の机の上から手探りで捜し当て暖房のスイッチを押した。リモコンを戻すとき、自分の脇をみると布団が盛り上がっている。ちょっと持ち上げてみて驚いた。
赤い網笠茸が布団の中に潜り込んでいた。
ちょっと気味が悪いが、なにも悪さはしないようである。かすかないびきをかいている。起こさないようにしてベッドからでると、キッチンで朝食の用意をした。いつもトーストに果物、レタスやトマトの野菜類、たまにゆで卵、ちょっと気がのるとベーコンエッグぐらい作る。それにコーヒーである。
網笠茸はまだ寝ている。
トーストを食べて、コーヒーを飲んでいると、赤い網笠茸がキッチンの入り口に顔をだした。
「いい匂いだな」
しゃべることができる。
「コーヒー飲むか」
カップを持ち上げて見せた。
「いや、ちがうようだ、お前の食べているものだ」
「これか」
トーストを見せると、「そのようだ」とうなずいた。
「つくってやろう」
食パンを電子レンジにいれトーストのボタンをおした。
茸が椅子の上に飛び上がった。
「歩けるようにもなったんだな」
「ああ、おかげさまでな、昨日は寒かった、悪いと思ったがあんたの後について入ってしまった」
「そりゃかまわんが、茸がしゃべるのはとても不思議なことだ」
「ちっとも不思議なことではない、俺たちはいつもしゃべっている。お前たちに聞こえないだけだ」
「茸同士で話をするのか」
「そうだ、俺たちはだれとでも話をしている」
トーストができた。バターを塗って差し出すと、頭をこちらに向けて、大きな口を開いた。
トーストを入れてやると
「うまいもんだ」と舌をペチャペチャさせた。
「お前の脱皮殻を全部とってある」
私はガラス瓶に入っている小さな頃の脱皮殻から、大きくて瓶がないために、押し花のようにしてとっておいた脱皮殻を見せた。
「おお、これは貴重だ、私の成長記録じゃないか、ありがとうよ」
網笠茸はぴょいと飛び上がった。
「それで、どうして脱皮なんかするんだ、普通の茸はしないよ」
「わからない、確かに、土から生えたとき、茸同士で話はできた。なんの拍子からかないが、いきなり頭が動いて前にいた虫を食った。そうしたら次の日から脱皮をするようになった」
「突然変異かね」
「いや、わからない、なんだか無性に周りのものを口に入れたくなって、今度は口を動かしてしゃべりたくなった」
「植物と動物の合いの子だ」
「茸は植物じゃない」
「そうか、今は菌類だな、ならば、菌類と人の合いの子だ」
「まあそうか」
網笠茸はちょっと黙ると考えるような仕草をした。
「そうだ、あの蟻だ、真っ赤な小さな蟻だった、そいつが、俺にかみついた、おれはいやいやをしたのだが、からだの中に入り込んで、それからわからなくなった」
「その蟻はいつもいるやつか」
「いやちがう、そいつだけは始めてみる蟻だった。最初俺が顔をだしときやってきて、頭に乗ったり飛び降りたり遊びおったが、そいつらはその辺にいる蟻だった、からだの中に入ったのは真っ赤に透き通るようなきれいな蟻だった。そういえばそれから俺は赤くなった」
「それじゃ、きっと蟻の細胞と、あんたの網笠茸の細胞が何かで融合して、今の赤いあんたがあるのだな」
「なんかわからないが、きっとそうだ、俺もやっと自分がわかってきた」
「これからどうする」
「どうするって、困る、行き場もない、働くことで稼ぐこともできない」
「見せ物小屋でもやるか」
「なんだそれ」
「しゃべる茸でござい、ってみんなに見せて金を取るんだ」
「やだよ、そんなはずかしい、どうだ、何かお前の仕事で手伝うことはできないか」
「冗談だよ、俺はもう退職している」
「俺はちょっとばかり未来を見ることができるがどうだ、便利だと思うがな」
「それじゃ、株や競馬の予想ができるのか」
「それはなんだ、仕組みを教えてくれれば予想もできる」
「それじゃ、食事をしたら俺の部屋で教えてやるよ」
コーヒーを頭から飲んだ網笠茸は
「何だ、この飲み物は目がぱっちりとする」と言った。
「どこに目があるんだ」
「からだ全部が目のようなものだ、あんたの顔やからだはすべて見ることができるんだ」
「ほー、眼がつむれなくて大変だな」
そのあと私の部屋に行った。PCのスイッチをオンにして、株の画面をだして、株について説明した。その予想を聞いた。
「はは、そんな予想はできないよ、明日は天気になるとか、台風がくるとか」
「そうか、原始的な第六感だな」
「何だ、原始的なというのは」
「要するに、遺伝子の中に組み込まれた、自然への予測だ」
「難しい言い方するな、人では退化した感覚だろ」
「確かにそうだ」
「明日は天気か」
「いや、雪だ」
「それが当たれば便利だな」
「一週間くらいはわかる」
「そりゃたすかる、旅行業者や農家に必要だ」
ということで、一週間分の天気予報を聞いた。大晦日も元日も晴れである。
網笠茸が我が家にすむことになり、彼に部屋を一つ与えることにした。昔の子供部屋でベッドもある。ぬいぐるみなども残っている。
網笠茸は部屋に入ると、猫のぬいぐるみのそばに寄った。頭をこすりつけている。猫が好きなのかもしれない。
網笠茸との共同生活が始まり次の年になった。元旦である。朝、網笠茸の部屋をのぞくと、脱皮した殻がころがっていた。
「脱皮したのか」
「ああ」
声をする方を見ると、まっぱだかの手足の生えた赤い網笠茸がぬぼーっと立っていた。おチンチンも生えている。
「お、人間に近くなったな」
「どうもそうらしい」
「気分はどうだ、今着るものをもってきてやろう」
私は、自分の下着と、普段着をもってきた。
「これを着たらいい」
網笠茸を見ると若い女の子が喜ぶかもしれない。今、茸ガールといって、茸の好きな女の子が増えているということだ。
ぎごちなくからだを動かして、着物を着た。
頭部の前面にあるしわの中に口がひらいて、左右のしわの中に目もできた。
「この方がしゃべりやすいし、動きやすい、人間というのはよくできている」
「これからどうする」
「仕事を探したい」
「なにができる」
「天気予報」
「気象予報士にならなければいけないが、戸籍もないし、資格を取るのはむずかしいな」
「どうだろう、もう腕も指も動かせる。そこにあるキーボードも打てる。なにかできないか」
彼に、文章を打ってもらったところ、かなり正確に打つことができた。
「そうだな、仕事を探してきてやろう」
私はむかし出版社の編集部に勤めていた。退職して五年になるが、たまに編集の手伝いに呼び出されることがある。二人の子供は外国暮らしをしており、家内は退職する十年ほど前に亡くなった。
私は今では珍しい手書きの原稿をワープロに打ち入れる仕事をもらってきた。それを網笠茸の彼に頼んだ。彼は分けもなくその原稿をワープロに打ち入れた。微々たるものであるが、彼に謝金を渡した。
「あんたにあげるよ、食費だ」
彼は受けとらなかった。人間に近くなった網笠茸は何でもよく食べた。ただ不思議なことに全くトイレにいかなかった。
一月の終わり頃、人間の形のまま脱皮した。珍しい人のような形をした脱皮の殻がころがっていた。真っ赤な人間である。
一回り大きくなった網笠茸人間は私と同じほどの背丈になった。
網笠茸の彼は貸し与えたPCに向かって毎日何かを打っていた。時々、彼にできそうな仕事を持って帰ると嬉しそうに、あっというまに仕上げてしまった。
四月になった。木々の芽吹きがとてもきれいである。ある夜、彼が長い間書いていた原稿を打ち出して、私に見せてくれた。タイトルは、地球での生活とあった。エッセイなのだろうか。
「これはなに」
私が聞くと、「ここではSFのようなものだと思うけど」
「小説書いて、どうするの」
「読んでみて、本になるならそうしてください」
網笠茸の彼は丁寧語で言った。
「長い間世話になったけど、僕は帰らなければならないんだ」
「どこへ」
「星へ、これから、迎えにくる」
しゃべっているのは網笠茸ではないようだ。
「何を言っているのか僕には分からないよ」
「私は網笠茸の細胞に融合して、人間に近くなり、星と連絡を取ったのだ、私は宇宙船の故障で小型船に乗り換えて地球に降りたのですよ、地球はなかなか住みやすかったんだが、地球の主の人間とは話ができない。人間が見ると、われわれは蟻だからね、網傘茸の中に潜り込んでみたら相性がよくてね、私と茸の細胞を融合させたんだよ、そうすると茸が変化して、脱皮するようになったんだ。あとはお宅も知っての通り、口ができて手足ができて、人間のようになったのですよ、このPCでもちょっと調整すると我々の星と交信できたんだ、ほら」
彼はPCを操作すると、どこの国のだかわからない文字を画面にだした。それが終わると画面がかわり、町が映し出された。近代的なビルの入り口から真っ赤な蟻たちがでてくる。
「僕の星だ、地球の言葉で『土玉』というんだよ」
彼が窓を大きく開けた。すると直径五十センチメートルほどの玉が窓の外にいきなり現れ、ひゅーっと中に入ってきて床に降りた。
「それじゃ、僕は帰るよ、ありがとう、その本はあなたが書いたことにすればいい」
網笠丈は洋服を脱ぐと最後の脱皮をした。赤い網笠茸はもう一回り大きくなったとたん、ぐずぐずくずれ、何万匹もの赤い蟻になった。細胞すべてが蟻になったんだ。
蟻たちは丸い宇宙船の入り口からつぎつぎに乗り込んでいった。
宇宙船は宙に浮き、いったん私の目の高さで停止すると、ひゅんと窓の外に消えていった。
点いたままのPC画面に日本語で、ありがとう、また連絡しますとあった。
私はあっけにとられた。ちょっと寂しいとも思った。
網笠茸のおいていった小説を読んた。宇宙をさまよって、地球に不時着した話から、地球の中をさまよって私の家の庭で網笠茸をみつけ細胞融合したことから人になるまでのことが書かれている。地球の動物の多様性の面白さに感激し、特に茸は彼らの繁殖に最も適した生き物であることがわかったときの彼の喜びが述べてある。蟻のような異星人はなかなか増えることなく、滅びる寸前だったそうである。それが、茸の細胞と融合し、細胞すべてが彼らに変化することで。いっぺんに人口を増やすことのできることがわかったことは、子孫存続への道が開けた。彼らが地球に再び現れ、網笠茸の栽培法を確立して自分の星に帰り、人口を増やすというストーリーである。SFと彼は言ったが、彼にとってノンフィクションである。本当のことであれば、向こうの星でも彼は英雄になるのであろう。
本にもあるように、彼らはまた私の前に現れるに違いない。
地球ではSFである。出版社を探しいつかを出版してもらおう。
彼らからの連絡が楽しみだ、本当に首が長くなった感じがする。まってるよ。
茸の脱皮
私家版 第八茸小説集「遊茸空、2020、一粒書房」所収
茸写真:著者: 秋田県湯沢市小安 2017-9-16


