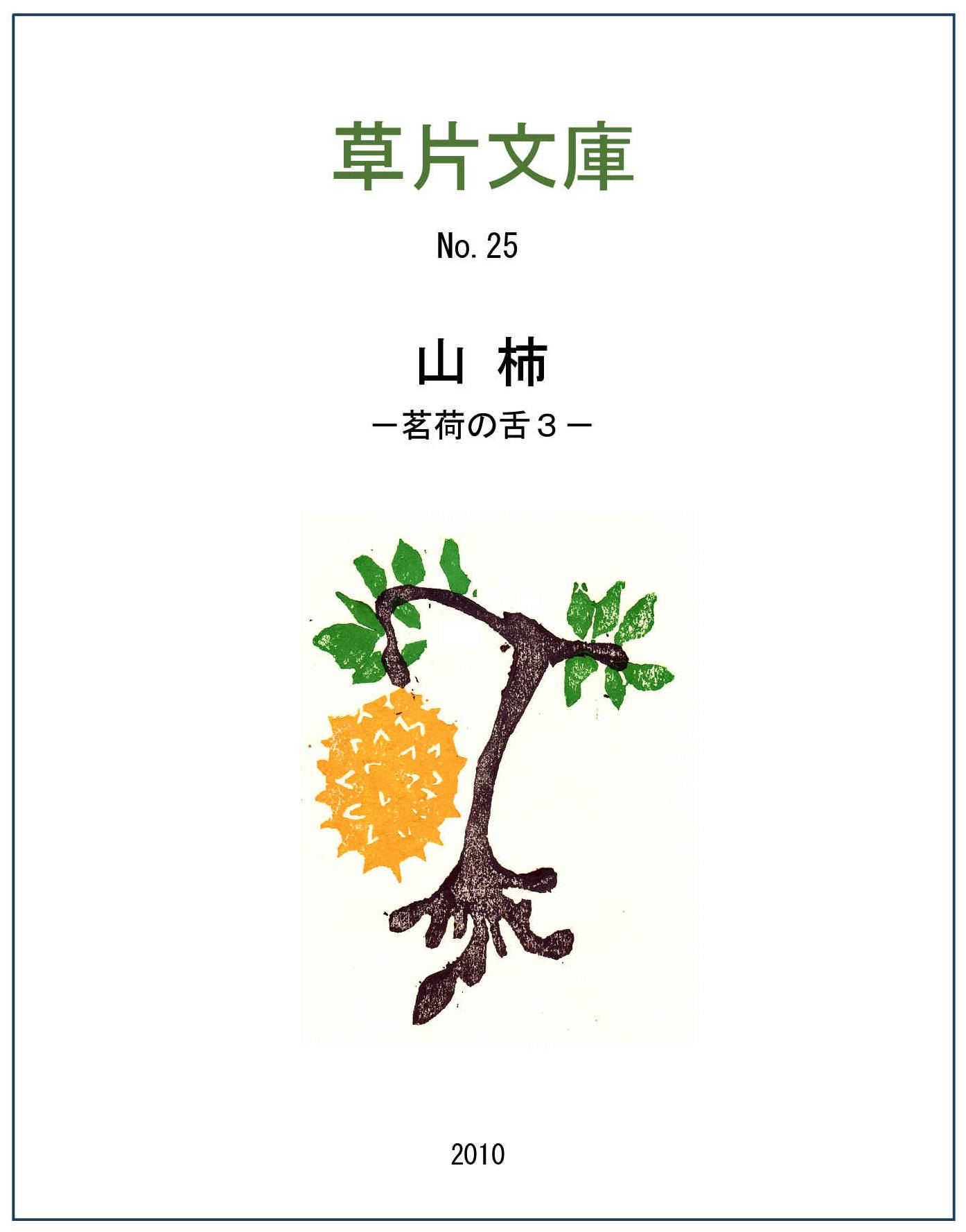
山柿 - 茗荷の舌3
南平駅前の本屋から出ると、向かいのコンビニの前で制服を着た女子高生たちが三人しゃがんで話をしていた。
「あのさ、丘陵公園さあ、行ってみない」
「なにしにさあ」
「猫が心中したんだってさあ」
「なにそれ」
「だからさあ、猫が心中したんだって」
「ほんとおお」
「ほんとだってさあ、校長先生が言ってたもん、校長先生は見に行ったらしいよ」
「どうしてさ」
「知るわけないじゃん」
「どこの猫」
「知るわけないじゃん」
「心中ってなに」
「あんた馬鹿ねえ、男と女が手を取り合って死ぬんだよ」
「そんじゃ、雄猫と雌猫が手取り合って死んだのお」
「首つったんだってさあ」
「猫がどうやってさ」
「しんない」
「見に行く?」
「やだ」
多摩動物公園の北側に位置する丘陵公園は、その昔、この辺りの人たちからは蝮谷と呼ばれていた。谷間には水が浸み出していて沢蟹をつかまえたこともある。子どもたちの探検の場であった。
数年前のまだ春早いころ、自然公園にするため蝮谷は掘り起こされた。その時、何百匹もの冬眠中の蛇が掘り出されたという話である。その蛇をどうしてしまったのか聞いていないが、蛇の幽霊が出るという噂もある。今でも「マムシに注意」の看板が立っている。これはマムシの幽霊に注意かもしれない。
僕は久しく行っていない蝮谷に行きたくなった。
駅から程遠くない丘陵公園にはいると、すぐのところに丸太で作られた作業小屋とトイレがある。そこを過ぎて、斜面の丸木で囲われた階段を登っていくと、谷であったところを見渡すことができる。小さいながらも瓢箪池がある。山から浸み出す水が瓢箪池の水源である。夏になると瓢箪池はかなり小さな池になってしまう。
瓢箪池の脇で女子高校生と高校の先生が上を見上げていた。
山柿の木が枝を茂らせている。
僕も下に降りて山柿を見上げた。
斜面に生えているアケビのからんだ山柿の枝に、二匹の猫がぶらさがって揺れている。山柿は小さな実のなる、原種に近い柿の木だ。ただ大きくなると十メートルにもなるらしい。
三毛猫とデブのグレーの猫だ。遊んでいるんだ。
「落ちるなよ」
先生らしき人が声をかけた。
そのとたん、二匹の猫はアケビの蔓に首をかけてだらんと垂れ下がった。
「心中したあ」
女子高生たちの悲鳴が蝮谷に跳ね返った。
駅のコンビニにいた女子高生たちではない。でもみんな同じしゃべり方をする。
その声で猫たちは逆上がりをして、山柿の枝にからだを乗せると、今度はアケビの蔓をつかんでターザンごっこを始めた。
「おっもしろそう」
女子高生たちが斜面を登り始めた。
「やめなさい」
先生らしき人の制止なんぞ聞くわけがない、みんな山柿に登った。女子高生たちは山柿に絡んでいるアケビの蔓を解いて、ぶらんぶらんとぶら下がった。短いスカートで見ているほうがはずかしい。
山柿の木に二匹の猫と女子高生たちがつかまって揺れている。
いつの間にやら僕の周りにはいつもの人たちが集まってきた。
「あの子達はなにをしているんです」
「遊んでいるんですな」
写真屋のおじさんが写真機をバックから取り出して、写真をとりだした。
肉屋のおじさんはデジタルビデオカメラを取り出した。
「すごいパーフォーマンスですな。天井桟敷や黒テントもかないませんな」
猫と女子高生はアケビの蔓につかまって大きく揺れ始めた。途中で猫とアケビの蔓を交換したりしている。
コンビニにたむろしていた女子高生たちがやってきた。
「心中なんかしてないじゃん」
「遊んでいるだけジャン」
「おっもしろそう」
「やる?」
「やだ」
「あたしやる」
「あたいも」
「そんじゃあたいも」
三人の女子高生たちも山柿に登ると、アケビの蔓にぶら下がった。
先にぶら下がった女子高生よりスカートの丈がもっと短い。
みんなポカーンと眺めている。
「やってみたいですな」
和菓子屋のおじさんが斜面を登り始めると、おばさんがシャツを引っ張った。
「年を考えなさい」
「うん」
おじさんはあきらめた。
女子高生たちがスカートをひらひらさせて舞っていると、山柿の木がゆっくりと回りだした。
猫と女子高生たちがぶら下がったまま回っている。回旋塔のようだ。山柿の動きは早くなり、猫と女子高生たちはびゅんびゅんと横になって回っている。パンツが取れてしまいそうだ。
「止まれ」
このままでは、猫と女子高生たちが怪我をすると思い、僕は声を上げてしまった。
しまった、逆効果だ。
山柿はいきなり止まり、女子高生たちは空高く放り出された。
デブの猫が落ちてきて、僕を突き飛ばし一緒に空に舞った。僕は山柿の根元に不時着した。
ふと見ると、山柿の根元で狸の子が目を回していた。この子が回旋塔だったんだ。
ぼちゃんと音がして、猫と女子高生たちは瓢箪池に落ちた。
「きゃあ、おもしろい」
女子高生たちが瓢箪池で蛙泳ぎをはじめた。
見ていた人たちが一斉に移動して瓢箪池の周りに集まった。
写真屋のおじさんはシャッターをぱちぱちきった。
「これは傑作ですな。猫と女子高生たちが一緒に泳いでいるところなどなかなか撮れるものではありませんな」
肉屋のおじさんはビデオカメラに集中して滑った拍子に池に落ちた。
「やだね」肉屋のおばさんが手を伸ばしておじさんを引きあげた。
おばさんが叫んだ。
「校長、なにしてる、みっともない」
見ていた校長先生ははっとして女子高生に声をかけた。
「あがりなさーい」
女子高生たちは蛙泳ぎで校長先生に手招きをした。
「先生もやろーよお」
そこへ消防車が到着した。
公園の入り口に止まった消防車から長いホースが引き出されると、消防団の人が瓢箪池にホースを突っ込み水を吸い出した。
あれよあれよという間に水が吸い出され、泥の中に蛙や誰かが放した金魚や亀がひっくりかえってばたばたしている。女子高生たちも泥の中に埋まっている。
写真屋のおじさんは、いい光景だと、シャッターを押すと、満足げに頷いた。
僕は目をまわしている子狸の顔をぽんぽんとはたいた。
狸はキョロッと目をあけると、へへとあわてて山のほうに走っていった。
そろそろ帰ろう。今日は何の茶漬けにしようか。
山柿はなにごともなかったようにつっ立っていた。
山柿 - 茗荷の舌3
私家版 子狸不思議物語「茗荷の舌 2016 一粒書房」所収
木版画:筆者


