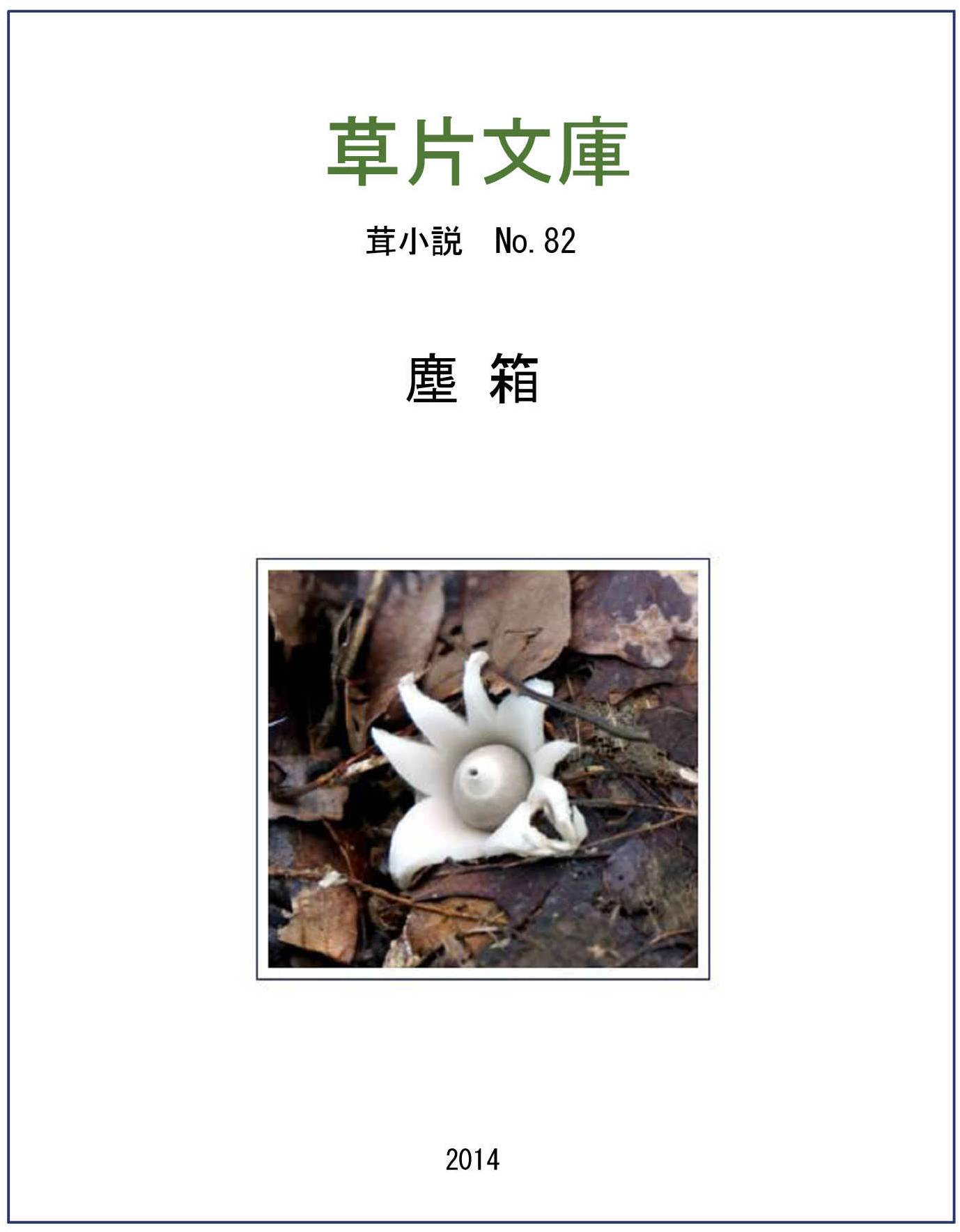
塵箱
「この家にも入っているぞ」
「赤いのか」
「いや、白いよ」
「子供がとってきたのを塵箱に捨てたんだろう、いたずらだよ」
「そうだな」
退職後、塵収集車で働いている。ここのところ、この区画一帯で、毎日のように、家々の塵箱に必ずいくつかの茸が入っていた。野山に生えている自然の茸であり、売っている培養ものではない。
「でも、こんなのよく生えているな」
「今年は茸の当たり年じゃないか」
「そうかもしれんが、このあたりだと、どこに行って採ってくるのだろう」
「長野や、秋田の実家に帰って車に積んできたのを捨てているのかもしれんしな、このあたりだと高尾山だとかじゃないかな、結構近くの丘などにも生えているのかもしれんよ」
茸のことはよく知らないこともあり、捨てられている茸が毒なのか食べられるのかもわからなかった。
家に帰って、家内に茸が捨てられていることを言うと、「食べられるのならもったいない、今度あったら拾ってらっしゃい」と言われた。明日もいくつかは拾えるかもしれないが、ゴミ箱の中のものだから食うのはいやだな。
次の日、予想通りその一画の塵箱には茸が捨てられていた。不思議なのは採りたてのようにしゃきっとしている。これなら食えるかもしれない。私はビニール袋に茸を集めた。相棒が、「なにするんだ」と、興味深げに聞いたので、「名前を調べてみるんだ、単なる興味」と答えておいた。相棒も茸を拾うのに積極的に協力をしてくれた。なんとその日は三十本ほどになった。
「毒々しいな、こりゃあ食えないよ」と、相棒は忠告をしてくれた。
家に茸を持ってかえると、家内は、ほら、と本を一冊持ってきた。
「あたし、前からもってたんだ」、見せてくれたのは、山形の茸と題された小型の本であった。うちのは新庄の出身である。
「あたし、高校の時に生物部にいたんだ、茸を調べたことがあるのよ」
山形は茸が豊富である。
還暦を超えた家内はちょっと得意そうに本を開いて、塵箱から拾ってきた茸と見比べた。
「この箒茸は食べられる、この真っ赤なのも食べられるわよ、卵茸」
図鑑には真っ赤な傘で、柄がまるで蝮のようで、底には白い壷がある茸の絵があった。たしかにその茸だ。食とある。隣のページをのぞいてみた。やっぱり真っ赤な茸がのっていた。それには猛毒と書いてある。
「おまえ、これ、こっちの猛毒の奴じゃないか」
家内は「あら、これは紅天狗茸、猛毒よ、ほら、拾ってきたのを見てごらんなさい、壷があるでしょう、柄の色が違うでしょう、傘に白いものが残ってないでしょう」といった。
確かにそうである。
「これはだめね、食べられない」
「でも、椎茸みたいで、食えそうじゃないか」
「これね、夜光るのよ、月夜茸っていうの、昼間みると普通の茸に見えるけど、猛毒なのよ、結構間違えて中毒する人がいるの」
「よく知ってるね」
家内がこんなに茸通だとは思っていなかった」
「東京にでてきて、茸に出会う機会がなかったもん」
家内はいつもより生き生きしている。山形の山暮らしを思い出しているのだろう。
「これも食べられると思うわ」
橙色の茸を手に持って、しきりと匂いを嗅いでいる。
「なんだい」
「ほら、匂いを嗅いでみてよ」
その茸を私の前に突き出した。どこかで嗅いだことのある匂いだ。果物のようだ。
「杏の匂いがするでしょう」
そうだ。私はうなずいた。
「アンズタケっていうのよ、日本じゃあんまり食べないみたい、でもおいしい茸らしいわ、山形でも食べたことないけど」
「あまり旨そうじゃないね」
「日本と外国だと好みが違うみたい」
ということで、五種類の食べられる茸が見つかった。家内は早速すべて一緒くたにして、バターでいためてくれた。それが、何とも、ビールにぴったりときた。
家内も珍しくビールを少し口にした。
「ねえ、何で、こんな茸が捨てられているのかしら」
「どうしてかね、誰が捨てているのかもわからないんだ」
「毎日捨てると言うことは、毎日採ってくるということよ、捨てなくてもいい茸があるのに捨てちゃうのは、茸のことを知らない人ね」
「それか、捨てなきゃいけない理由がある」
「ねえ、塵箱に茸の入っていない家もあるんでしょ」
「そりゃたくさんあるよ」
「今まで塵箱に茸が入っていない家が怪しいわね、捨てる犯人よ」
「そうだな、今度気をつけてみるよ」
次の朝、塵の収集に回っていくと、その区画にある十数軒のうち三軒の塵箱には茸が入っていなかった。山本さんと、白井さんと、鈴木さんである。あと空き家が一軒ある。空き家は問題外として、他の家の人は時たま顔を見る。どの人もかなりのお年寄り夫婦である。
家に帰ってから家内にそのことを報告した。
「ほかの家の人たちはどんな人たち」
「共働きの人が多そうだね、塵の収集の時にはほとんどいないよ。子供は保育園だね、きっと」
「ふーん、とすると、私の推理ははずれね、でも、何時も家に人がいない塵箱に捨てているということなのかしら」
「何時から探偵になったんだ」
「だって、面白いじゃん」
その日は食べられる茸はなかった。
ある日、山本さんのおばあさんが戸口に出ていた。
「ごくろうさまです、あのね、ちょっといい」
と呼び止められた。
「なんでしょう」
「今年になってから、あの空き家になんかいるようなのよ」
「え、どうしてです」
「塵の収集車が来る前になると、黒っぽいものが門の外にでてきて、お隣の塵箱に何か捨てているのを見たのよ」
「え、どんな人です」
「人だかどうだかわからないの、おとなりの塵箱に何か変なものが入っていないかなと思って、呼び止めたわけ」
「何もなかったですよ」
少しばかり嘘をついた。
「あの家の持ち主を知ってますか」
「住んでた方は亡くなって、お子さんはオーストラリアにいらっしゃるの」
「それじゃ、市にでも相談するといいかもしれませんね」
「そうね、そうしようかしら」
「私の方から伝えておきましょうか」
「お願いできるかしら」
「いいですよ、その前に。仕事が終わったら、私がみてみましょう」
今すぐにでものぞいてみたい気がしたが相棒がいるし、一人の方がやりやすいと思ったのだ。
夕方になり、山本さんに言われた空き屋に行った。窓はツタに覆われていたが、かろうじて中を覗くことができた。中は薄暗く、よく見えないが、黒っぽい影がゆっくりと動いている。やっぱり中に誰かいる。浮浪者だろうか。反対側に行ってみると、そちらにツタはなかったが、窓はなく中を覗くのは難しかった。
どのような人間がいるのかわからないので迂闊に声をかけることができない。市か警察に届けた方がよいだろう。
そう思って引き上げようとしたときに、いきなり玄関の戸が開いて、真っ黒いものがでてくると、私をわしずかみにして中に引っ張り込んだ。私はあまりの驚きに声をも上げることができず、その力の強いことから、振り切ることもできなかった。
黒い影は私を床に放り投げると、部屋の至る所に生えている茸をわしずかみにして飲み込んでいた。
茸をとったあとにはまた小さな茸が生えてきた。
黒い影は私を見た。
「お前も食え」
私は首を横に振った。黒い影には形がなかった。黒い霧のようでもあり、一時はやった真っ黒なスライムのようでもあった。
「うまいぞ」といいながら黒い影は茸を吸い込んでいった。
しばらくすると、茸の生えるのが遅くなった。
「こっちにきてみろ」
黒い影は私を隣の部屋に引きずっていった。その部屋の中には多種多様な茸がぎっしりと生えていた。
「明日これを捨てるのだ」と黒い影は言った。
「こっちにこい」
黒い影は二階に私を連れていった。三つある部屋の二つには茸がかなり詰まっていた。最後の一つの部屋の中の金属製のドアを開けると、黒い影は手招きした。その部屋の壁には計器がところ狭しと並んで光が点滅している。私が驚いていると、黒い影は私にこういった。
「この星に不時着したのだ、今、機械の具合を調整しているのだ」
私はやっと落ち着いてきた。
「どこから、来たんです」
「違う銀河系だ、この星の者が関知できないほど遠いところにある」
「何しにきたのでしょう」
「来たのではない、通り道にこの星があり、機械の不調でちょっと降りただけだ」
「それで、どうして茸を」
「我々の食えるものはあれしかない、培養液を作って、家の中に塗ったのはいいが、効きすぎて、どんどん生えてくる。旨いのだが多すぎる、食いきれんので毎朝すてなければならん」
「それで、塵箱に」
「やむを得なかった、隣の老人のところは悪いと思って捨てなかった」
「それでいつ帰るのですか」
「もう、数日で帰る。この星の茸というのは美味なのでいいみやげになる、菌を持って帰る。しかし、この家には数年間茸が生え続けてしまう」
「食べられる茸ならいいのですが、毒の茸もたくさんあって、私たちも困ります」
「おお、我々にはみんな同じに見えたが、違うのかい、食べられるのだけ採ってもっていけばいい」
「しかし、この家は、他人のもの、勝手に入ることはできないのです」
「そうなのか、それならば、自分の家にすればいい」
「家って言うのは、この国では高くてなかなか買えないのです」
「そんなものか、だが、古い家のようだが安くないのか」
「もし、あなたが星に帰ってしまったら、どうなるでしょうか」
「茸が満杯になって家が爆発する」
「どのくらいでそうなるのでしょうか」
「計算だと、わしが帰って、五日後にはなるだろう」
「何時お帰りで」
「まだわからない」
黒い影はまた下の部屋に行って茸を食べ始めた。
「私は帰ってよろしいでしょうか」
「そりゃかまわんよ、だが、どうだい、わしの星に来ないかい、ここの星の住人が好きそうなものがたくさんあるぞ」
「でも、あなたの星で生きていられますか」
「そりゃ大丈夫だ、この星の大気の情報はすべて解析済みだ」
私はこの異星人の星に行ってみたいと思うようになった。
「だが、私には、家内がいます」
「生殖の相手か」
「はい」
「一緒に連れていってもよいぞ、死ぬことはなくなるぞ」
「それでは、家内に相談してきます」
「うむ、そうか」
私は家に戻って、そんな話をした。
「嘘でしょう、変な作り話」
「それじゃ、行ってみるかい」
「その家にならいくよ」
次の日曜日、家内を連れて、空き家に行った。戸をたたくと、黒い影の手が伸びて、私と家内は家の中に引っ張り込まれた。
「よく来た」
家内はびっくりしてひっくり返っている。黒い手は私たちを二階の宇宙船操縦席にひっぱりこんだ。
私たちがその部屋に放り込まれると、赤い閃光がほとばしり、窓には星くずが一面に散らばった。
「これから、数日かけて、我々の星に行く」
「え、まだ、行くと言っていないのに」
「そりゃ困った、行くつもりできたのかと思ったじゃないか、もう戻れないよ、次にこっち方面に来る宇宙艇に乗せてもらうしかない、いつになるかわからないが」
「でも帰れるならいいわ」
いきなり家内がそういった。確かに、こんな経験はおいそれとできるものではない。
「それならよかった、向こうに宿舎を用意するように言っておく」
数日が過ぎた、宇宙艇の窓に、真っ黒な星が見えてきた。
黒い影は、
「あれだ」といった。
あっというまに、その星の中にはいりこむと、ただ、真っ暗だった。
「なにも見えないの」
「お前たちには見えないのか」
「何にも見えない」
「部屋に入りたいと思ってみろ」
私も家内も部屋には入りたいと思った。すると、目の前に戸が現れた。戸を開けて中にはいると、真っ暗だった。
「なにがほしいか」黒い影が言った。
「明かりと食べるものと寝るところ」そういうと、光がつき、周りの部屋がダイニングルームになり、隣に寝室ができた。
「その要領だ、それじゃ、お前らの星の近くを通る次の宇宙艇が来るまでここでくらしていてくれ」
「食べるものはどうしたらいい」
「さっきの要領だ、ほしいと思えば現れる」
こうして私たちは、この星の客人になったのだが、それ以来、あの黒い影は現れず、全くこちらの星の人に会うことはなかった。外は真っ黒で、ただ、景色がほしいと思えばどのような景色でも現れるのには驚いた。それで生活が飽きることはなかった。試しに、猫がほしいと思ってみた。部屋に猫が現れたが、一日で消えた。だが、会いたいと思うと足元にいた。食べ物はいつでも現れ、美味しく食べることができた。
ほしいと思ったものは必ず現れるが、しばらくすると消える。想像力が豊かなほど楽しめる星だ。昨日はビートルズが部屋の中で演奏をして、ポールやジョンと握手をした。ラグビーの試合を見たいと思うと、窓を開ければやっていた。
そのようなとき、地球の我が家のある町では、大騒ぎが起きていた。
地球の新聞が読みたいと念ずると、新聞が現れる。
新聞のみだしには「家が大爆発、茸が天から雨あられ」とあった。
あの空き家が大爆発して、木っ端みじんになり、茸が天から降り、木片がその一画に散乱して、そこから、茸が次から次へと生えているという、奇怪な出来事とあった。
家内が地方版を見て言った。
「私達のことも載ってるわ」
「一組の夫婦が突如失踪」と小さく書いてあった。
しかし、誰もその二つを結びつけるようなことはしないことだろう。そのうち地球に帰ることが出来るだろうけれど、いつになるかわからない。だが、その時地球がどのように変わっているのか楽しみである。この星、我々は影星と呼んでいるが、慣れると生活は楽で楽しいものである。
一つ残念なのは、この星の住民と顔を合わすことができないことである。一度会いたいと念じてみたら、部屋中闇になって、中で何かうごめいているだけであった。それ以来会いたいと思うことはしないことにしたのである。
塵箱
私家版 第八茸小説集「遊茸空、2020、一粒書房」所収
茸写真:著者: 東京都日野市南平 2016-9-26


