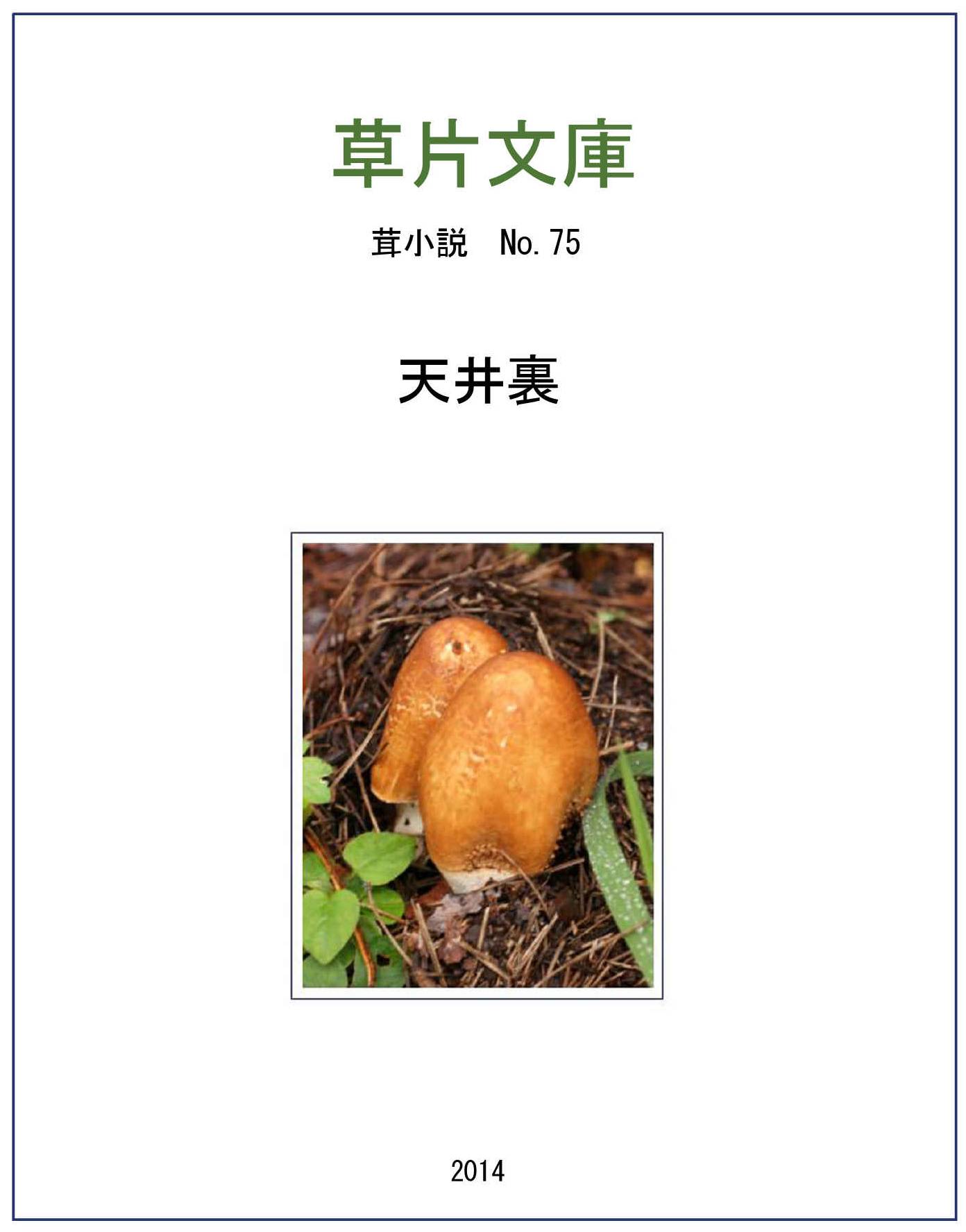
天井裏
夜中にふっと目が覚めた。ごそごそと音が聞こえてくる。天井の上からだ。鼠かとも思ったが走り回ってはいない。寝室の上はちょっとしたロフトになっている。ロフトの中になにかいる。朝おきたら覗いてみよう。また眠りに落ちた。
目が覚めると昨夜のことを思い出した。パジャマのままロフトに上がった。家の前の持ち主がおいていったものや、自分のいつも使わないキャンプ道具やらを山盛りに押し込んである。音のしたあたりを見るには、かなりのものをどけなければならない。見える範囲では、生き物がいる気配はない。鼠の糞も落ちていない。何かが入り込んだのだろうか。屋根からロフトに入るような隙間はない。部屋からも入ることはできないはずだ。仕事から帰ったらもう一度見てみることによう。ロフトから降りた。
その日、鼠捕りを買って帰った。寝る前にロフトの中においた。その時点ではなにもいなかった。ロフトには古い人形なども入れてあるので齧られるともったいない。
夜中になると、またもや天井からごそごそと音が聞こえて眼が開いた。音は長く続くわけではなく三十分ほどだろうか。すぐに寝てしまう。そのような状態が毎日続いた。鼠捕りには何もかからず、入れておいたジャガイモが干からびた。
ある夜のことである。ぽとぽとといつもとは違った音がして眼があいた。天井を見あげると、ベッドの上辺りの天井に四、五センチほどの丸い穴が開いている。なんで穴なんかあるのだ、と見ていると青っぽいものがその穴から顔をだした。
ぞくっとからだが寒くなり、半身をおこして電気を点けた。穴は覗いていた青いやつがいなくなり黒く開いたままだ。気味が悪い。あ、また何かがのぞいた。こんどは黄色っぽいやつだ。鼠ではない。ただつるっと丸っこい。目や口や鼻があるわけではない。なにがいるんだ。
ベッドの上であぐらをかいて穴を見ていた。
あ、布団の上になにかが落ちた。逃げようとベッドからあわてて降りると、そいつは布団の上で起き上がった。布団の上でゆれている。茸じゃないか。青色のひしゃげた傘の茸だ。どうして天井裏に茸がいるのだ。そう思ったとたん、茸がスーッと空中に浮遊した。僕の眼の前の宙に浮かんでにたっと笑った。目鼻口が茸の傘に現れたのだ。そうして、
「寝相が悪い奴だ」と口を大きく開けて笑った。
これは夢ではない。と思ったとたん、
「そうだ、夢ではない、現実だ」
茸がそう言った。こんな奇妙なことがあっていいはずはない。夢だろうと考えると、落ち着くことができた。聞いてみた。
「どこからはいってきた」
「おまえはどこから来た」という返事がかえってきた。
一昨年、この一戸建てに越してきたのである。都内のマンションに住んでいたのだが、仕事の都合上と、そろそろ嫁さんを迎える準備ということもあり、この郊外の中古の一戸建てを購入したのである。
「新宿から来た」
「ほら、あんたのほうが来たんじゃないか、おれたちゃもともとここにいたんだ」
僕の方が進入者だったのか。
「そりゃ知らなかった、前の持ち主からも、不動産屋からも住人が居るなどと聞いていないぞ」
「前の持ちぬしは俺たちで、お前に売った前の持ち主は本当の持ち主ではない」
「前の持ち主の人間は、茸たちが居るのは知っていたのか」
「知ろうともしなかった、俺たちがあいつらの前にいくと、しばらく目をつぶって、はい、いなくなった、と見ない振りをした」
「どうしてだろう」
「頭がおかしくなったと思ったのだ」
「僕も夢だと思っている」
「あんたは、楽天的だから、夢のせいだと思い込もうとしているんだ」
「茸がしゃべるのは夢か、絵本やアニメの中だけだ」
「世界が違うんだ、俺たちの世界では、動物が光合成をして酸素をつくって、植物が動物を食うんだ」
「僕のすんでいるところの茸は植物ではない、菌類という別の区分だ」
「俺らの世界では、植物の頭領が茸だ、いうなればこの世界のほ乳類、霊長類、そして人類といったところだ、植物や動物より茸のほうが後に進化したんだぜ」
ぽとりと何か落ちてきた。また別の茸だ。真黄色だ。
「兄ちゃん、人類と話をすると怒られるよ」
「ああ、でも大丈夫だ、こいつはいい加減だから」
失礼な茸である。
「あんたたちの世界っていうのは遠いのかい」
「遠いわけがないだろう、その穴だから隣だよ」
「ロフトをみたけど、いなかったじゃないか」
「ロフトはあんたの世界だろう、たまたま俺たちの世界の、便所だ」
「トイレに来てのぞいていたのか」
「そうだよ、おれたちゃ、ここでガスをひる」
「屁のことか」
「音もでなけりゃ、匂いもないよ、この星の空気には入らない」
「どうしてだい、あそこに穴が開いているじゃないか」
「見ることができても、違う世界だから入れない」
「お前たちが入ってきただろう」
「俺たちだけが行き来できる」
「なぜだ」
「あんたのいい加減な頭と、楽天的な性格と、まあ、いろいろ重なって、あの穴ができたのだ」
「ところでなあ、この部屋でときどき、液体を飲んでいるだろう」
「酒か」
「あれはいい匂いだ」
「アルコールだ」
「知っている。玉子を発酵させたものだろう、どうだ、一杯くれないか」
「そりゃいいが、発酵させているのは玉子なんかじゃない、米や、麦や、果物だ」
「おい、おい、そりゃみんな、植物の子どもなんだぜ」
「ああ、そういわれりゃ、そうか」
僕はキッチンにいき角瓶をもってきた。グラスに注いで茸の前に置いた。
「お兄ちゃん、大丈夫」
「大丈夫だよ、茸族ではじめて酒というものを飲んだ英雄になれる」
「だけど、死んだ玉子から作ったものだから、共食いだろう」
「こっちの世界をみてみろよ、人間がほかの動物をみんなくっちまう、食うために飼っているんだ、ほかの動物だって、肉を食らうのは沢山いるじゃないか」
「たしかにな」
お兄ちゃんと呼ばれた青茸の傘の真ん中に口が開くととんがって、蛸のように伸びて、グラスの中の小金色のウイスキーの中につっこまれた。
「うまいな、体の中がきゅいーっと熱くなる」
「茸でもやっぱりそうなのか」
「おい、この世界の茸とは違うんだ、俺たちの世界ではこのように水も飲むし、動物も食らう」
「酒は造っていないのか」
「動物をすりつぶして発酵させたって、臭いだけだ、こっちの世界の死臭だよ」
「そうか、ほかのも飲んでみるか、葡萄を発酵させたのがあるが」
「そりゃいい、頼む」
「お兄ちゃん、僕も飲んでみる」
「ああ、うまいよ」
小さい方の茸も口を伸ばしてウイスキーを飲んだ。
「ほんとだ、おいしい」
僕は栓の開いているぶどう酒を冷蔵庫からもってきて、グラスについでやった。
「紫色か、いい色だ」
そういいながら大きい茸が口を伸ばした。
「まずかないが、すっぱいし、アルコールが弱い」
「ウイスキーの方が好きか」
「ああ、あの濃いのは最高だ、身体がしびれる」
「もっと強いウイスキーを飲んで見るかい」
「そんなのがあるのかい」
「イギリスという国の、小さな島で作られたもので、薄めてない、そのままの強いやつさ」
僕はラガヴーリンの樽だし58%というのをグラスに入れた。
「すごい匂いだ、いいね」
茸は口をとんがらせて、ラガヴーリンを吸った。と、突然大きな声をだした。
「おー、効く、うまいねえ、身体が崩れそうだ」
そして、茸はその場にばったり倒れた。
「あ、兄ちゃん」
小さな茸が大きな茸の上に飛び乗って揺さぶった。
「寝ている」
「酒を飲むと眠くなる、お兄ちゃんというのは兄弟って言うことなの」
「そうだよ、僕より一年前に菌糸から生まれたからお兄ちゃん、一年より後に生まれたのは僕の弟」
「それじゃ、沢山兄弟がいるんだね」
「そうだよ、でも、違う種類だと兄弟じゃない、いとこになるのかな」
「なるほどね」
「君は男の子なの」
「なあに、それ、男の子って」
「君の世界でも植物にはなくても動物にはあるでしょう」
「ああ、きっと、こっちの言葉で、異性っていうことね」
「そうだよ」
「あるよ、一性、二性、三性、四性、五性までね、一性と一性で二性の子供ができて、二性と三性で五性ができる」
「なんなのそれ」
「DNAが五重螺旋なのだ」
そのとき、お兄ちゃん茸がむっくりと起き上がった。
「もう、覚めた、腹が減った、もっとウイスキーくれ」
ぼくはまたウイスキーをそそいでやった。
「ウイスキーはうまいね、なにかつまみはないか」
大きな茸はだんだん大胆になっていった。
「いつもはなにを食っているんだ」
「動物だよ」
「どんな虫が好きなんだ」
「ばかいうなよ、哺乳類だよ、よく食うのはこの世界で猫と言っている奴だ」
ぼくはちょっと驚いた。
「猫をどうやって食べるんだ」
「生で食うんだ」
「うちには猫はいない、ところで、あんたたちの世界には人間はいるのか」
「いない、動物はそこまで進化しなかった、だから俺たちが進化した」
「猿はいるのか」
「いる、だが、絶滅危惧種だ、腹減ったなんかないか」
「肉の買い置きはない、そういやあ、ビーフジャーキーがあった」
僕はそれをもってきてやった。
大きい茸と小さい茸はかぶりついて、
「うん、なかなかうまい」
あっと言う間に食っちまった。
「ところで、猿はどうして減ったんだ」
「食っちまったんだ、旨かったから、でも、今じゃ動物園で大事に飼われている、もっとなんかないか」
青い茸は口をとがらせて、ウイスキーを吸っている。
「猿がうまいのなら、人間はもっと旨いのじゃないか」
そういって、傘に目玉ができると、僕を見た。
あっ、傘に大きな口が開いた。あっ、飛びかかってきた。僕は頭から飲み込まれてしまった。
いま、茸の腹の中で、僕は溶け始めている。でも痛くも何にもない。
「お兄ちゃん、ぼくも食べたい」
小さい黄色の茸の声が聞こえる。
「天井穴はなくなりゃないからよー、次の人間がきたらおみゃあにやるよー」
大きな青い茸が酔っ払い声をだした。
腹の中にいる溶け始めた僕の心臓に響いた。
そして青い茸はねちまったようだ。僕も腹の中で横たわっている。
天井裏
私家版 第八茸小説集「遊茸空、2020、一粒書房」所収
茸写真:著者: 山梨県北杜市小淵沢 2013-9-16


