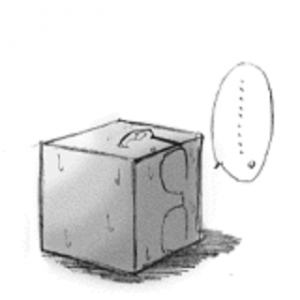死神
僕は今、どこにいるのだろう?
カプセルのような狭いところに、手足を折り曲げてじっとしている。ほとんど身動きはできない。不思議と息苦しさはないけれど、光がないので今が昼なのか夜なのかもわからない。ただ、ぼんやりと暖かくて、なんとなく安心できる。
でも、僕はなぜこんなところに閉じこもっているのだろう?
僕が彼女に出会ったのは少し前のことだ。
前後の記憶が曖昧なのでなんでそんなことになったのか、いまいちわからないのだけれども、僕はがらんとした部屋に座っていた。目の前にはガラステーブルと1脚の椅子。他には何もない。ひどく現実感がないその部屋で、僕はただぼうっと座っていたのだった。
…あの日は仕事はどうだったんだろうか?
僕は会社の中でも一番忙しいといわれていた部署にいたので、ほとんど休みなしで仕事をしていた。確かに忙しかったけれども独り身で身軽だったし、収入も増えたのでとりたてて不満はなかった。ただ、増えた収入を使う暇もなくなってしまったけど。
忙しくて大変な仕事だったけれども、それなりのやりがいもあったような気がする。ただ、時々自分が何のために仕事をしているのかわからなくなることもあったけど、そんなときはきっと疲れているんだと思ってあまり気にしなかった。
そう、それで彼女の話。
気づいたらいつのまにか僕はそのがらんとした部屋で座っていた。
窓はあるけど外の様子はよくわからない。
寒くもないしかといって暖かくもない。
とにかく僕はいつのまにかその部屋にいて、ぼうっと座っていた。
「気づきましたか?」
と、いきなり背後から声をかけられて僕はドキッとした。
慌てて振り返ると、背の高い女性が立っていた。それが彼女だ。
すらりとしたシルエット、はっとするような美人。黒のパンツスーツに黒ネクタイ、黒のパンプスというまるで葬儀屋のような格好だが、さらに腰までありそうな彼女の長い髪は、艶やかな黒髪。それはもう見事としか言いようがない。一度会ったら絶対に忘れられない人だが、僕はそれまで彼女に会った覚えはなかった。
「気分はどうです?」
「ええ、まあ悪くはないです」
我ながら曖昧な答えだなあと思いながら僕は答える。彼女の声はあくまで落ち着いていた。
「そう、それならよかった」
彼女はそう言うと僕の目の前の椅子に腰掛け、手にしていた書類のフォルダをガラステーブルに置くと、じっと僕の顔を見つめた。まるで僕の魂まで見通してしまうかのような深い瞳に、僕は思わず怖くなって目をそらしてしまった。
「怖いですか?」
彼女は口元だけで笑ってそう言った。
すべて見透かされているような気分だ。
「あの、ここは…?」
僕は気を取り直そうと思って彼女に質問した。
「そうね、控え室…のようなものかしら」
決して高圧的な態度というわけではないし、口調も表情もごく穏やかなのに、僕は彼女から底知れぬ恐怖を感じた。すぐにでも逃げ出したい気分だ。
そんな僕の内心を知ってか知らずか、彼女はテーブルに置いたフォルダから書類を取り出して眺めている。
「ふぅ…ん、ずいぶん若いのにこんなところに来るなんて…」
彼女はそうつぶやいて僕のほうを見る。僕は動くこともできない。いつのまにかこぶしを固く握り締めてその中にびっしょりと汗をかいていた。
そうか、これは内密の面接か何かなのだろう。僕の知らないうちに会社のどこかでそんな話があったのかもしれない。
「あなた、自分のこと大事にしてあげてましたか?」
「は?」
彼女の思いもよらぬ質問に、僕は間の抜けた声を出してしまった。
「あの、質問の意味がよくわからないのですが…」
僕がそう言うと彼女はひどく哀れんだ表情で僕を見た。
「自分を大切にしていましたか、と訊いたんです」
彼女は繰り返した。
自分を大切に…と言われても。
そういえばそんなこと考えてもみなかった。
友人も少ないしつきあってる彼女もいないけれど、別に今までもそうだったからそれほど気にならない。特にやりたいこともないから仕事をしていればそれで十分だと思っていたし、そのためにずいぶん無茶もしたけど、結構平気だった。
ただ、自分を大切にしてきたかどうか、と言われるとあまり自信がない。
「では質問を変えましょう。あなたは、一体何のために生きてきたのですか? 仕事のためですか?」
僕が何も言わないうちに彼女が問い掛けてきた。
でも、これにも僕は答えることができない。
僕は仕事をするために生まれてきたのか? 今の仕事は僕にとって天職だろうか?
いや、僕の代わりになる人が他にいくらでもいることを僕は知っているし、僕自身も別に今の仕事でなくてもそれなりにやっていけるだろう。
でも、それでは僕が今の会社にいて今の仕事をしなければならない理由なんてないことになる。だったら僕は一体何のために生まれてきたのか…?
彼女は僕が必死で考えているのをじっと見ている。彼女には僕の考えていることが手にとるように見えているらしいのに、僕は彼女が一体何を意図してこんな質問をしてくるのかさっぱりわからない。なんだか妙な面接だ。
「…もう、いいですよ」
僕が答えられそうにないと見たのか、彼女は素っ気なく言うと立ち上がって窓のほうへ歩いて行った。
「最近こんな人が多いんです」
彼女は窓の外を眺めながら言った。
「自分が何をやりたいのかわからないまま、何かに追いかけられるように毎日生きている。でも、それが当たり前だと思っている」
「当たり前じゃないんですか?」
僕は思わず訊き返した。
彼女は窓の外を見たまま目を細めた。僕には彼女の横顔が笑ったのかそれとも悲しんだのか、よくわからなかった。
「まあ、そんな人たちを拾い上げるのが私たちの役目ですけど」
僕には彼女の言ったことの意味がまったくわからなかった。
彼女はしばらく窓の外を見たまま何も言わなかった。
「カラスについて、どのくらい知っていますか?」
唐突に彼女がそう訊いてきた。
「え? カラスって、鳥のカラスですか?」
「そう、そのカラスです」
「えっと、黒くて、カーと鳴いて、よくゴミをあさってるってぐらいしか…」
「それだけですか?」
「…そうですね」
僕がそう答えると、彼女は再び僕の前に戻って腰掛けた。不思議とさっきのような恐怖感はもうなくなっていた。
「ヒトって案外身の回りのことを知らないものですね。こんなにもヒトの近くにいるというのに…」
彼女は僕に語るというよりは自分自身で言い聞かせるような口調で続けた。
「例えば、カラスの親はヒナが生まれるととても神経質になるんです。困ったことにカラスは意外に人通りの多いところに巣をかけてしまいます。ヒトはカラスの巣がどこにあるかなんて関心がないですから、知らず知らずにうっかり近づいてしまいますが、そんな時カラスの親はヒトを猛然と攻撃します。自分の子供を守ろうというごく自然な行動ですけど、ヒトにしてみれば何の理由もなくカラスが突然襲ってきたように思えるのでしょうね。カラスにはちゃんとカラスの事情があるんです」
「そうなんですか。初めて知りました」
彼女は再び僕の顔を覗き込んだ。
「カラスは自分を偽ったりはしませんよ、ヒトのように」
そう言うと彼女は意味ありげに口元だけで笑った。
僕は、自分を偽ってきたのか? 本当にやりたいことはなかったのか?
彼女の言葉をきっかけに、突然僕の中にいろいろな思いがいっぺんによみがえってきた。
子供の頃になりたかったもの。初めて女の子を好きになったときの気持ち。学生時代に楽しかった思い出、苦い経験。社会人になったときの新鮮な気持ち。
すべて忙しさを言い訳に忘れていた。仕方ないんだと言い聞かせていた。
彼女の言う通り、僕は自分のやりたかったことをずっと抑えつづけてきたのだ。ただ、それが当たり前だと思っていたから気がつかなかっただけだ。
そこまで思い至ったとき、僕は激しく後悔した。
もっと出来ることがあったんじゃないか、やりたいことがあったんじゃないか。なのに、僕は一体今まで何をしてきたんだ!
「いまさらそんなことを考える必要はありませんよ」
彼女が冷たく言い放った。
「もう決して戻ることはできないのですから」
僕は混乱した。一体どういうことなのだろう?
「あなたは私の子になるのです」
彼女は僕のそばに来ると、そう言ってすっと僕を抱きしめた。
ごく自然に、親が子を抱きしめるように。
その後、僕の記憶は途切れ、次に気づいたときには今のカプセルの中だった。
一体、あれはなんだったんだろう。
会社は僕がいなくなってどうなっただろうか? きっと誰か代わりの人が入って仕事自体は途切れなく続いているのだろう。僕は多分もうそこに必要ではない。
でも、それはもうどうでもいいことだ。
少なくとも、僕はあの場所でなくても生きていける。
そういえば、さっきから周りがなんとなく明るくなった。少し寒くなったような気もする。
ああ、なんだか息苦しい。
ここから出なければ。
身体を伸ばそうともがいてみるが、息苦しさは増すばかりだ。
このままでは死んでしまう。死ぬのはイヤだ。どうにかしなければ。
首を伸ばして外へ出ようともがきつづけていると、何かが当たってカプセルにヒビが入ったようだ。
いいぞ、この調子でやれば外に出られる。
僕は夢中になってもがきつづける。
コツ、コツ…と根気よく叩き続けているうちに、ヒビは穴になり、そこから光が入ってくるのを感じた。もう少し。あと少し。
開いた穴から頭をひねりだした瞬間、外の強烈な光を感じた。
目が開けられない。
が、自分のそばに大きな何かがいるのを感じた。僕のすぐ近くにいる。
「ようこそ、新しい世界へ!」
ばさばさっという羽音とともに、彼女の声がした。
うっすら目が開いて僕の視界に飛び込んできたのは、大きなカラスの顔だった。
ああ、そうか。やっとわかった。
大きく息を吸い込むと、僕は新しい命の声を上げた。
死神
※ この作品は2005年2月に執筆したものを、一切編集せずに再掲したものである。