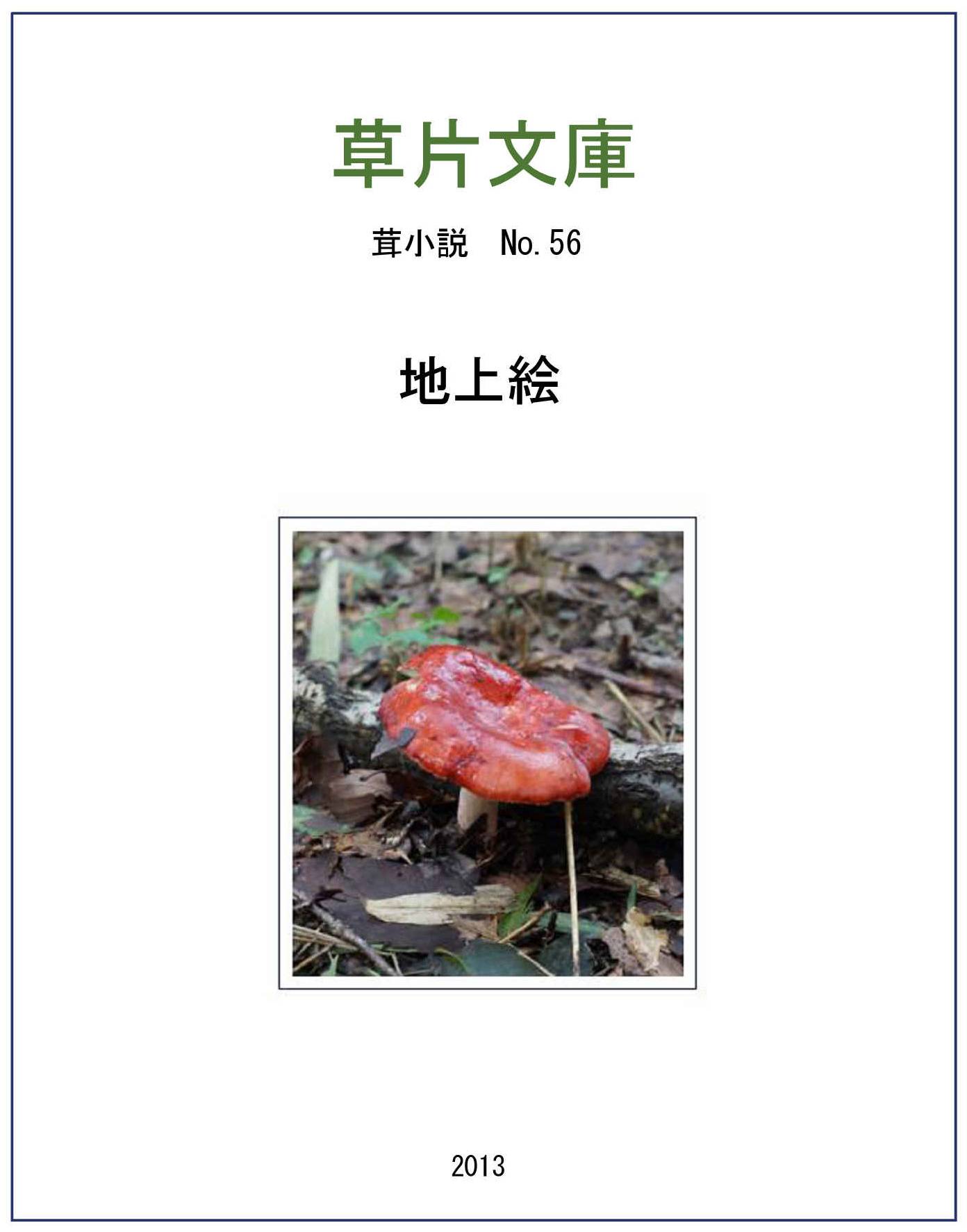
地上絵
上昇した熱気球から遠くアンデス山脈が見える。
気球の下をのぞくと草原がひろがる。リャノ平野と呼ばれる果てしない平原である。
牛の仲間が集まってのんびりと草をはんでいる。
日本ではとても見ることのできない迫力のある景色である。
気球は風に流され、南の方向にゆっくり動いていく。丘と呼ぶほうがよいほど低い山の上を越えた時、突然横から風が吹いた。ゴンドラががたっと揺れ、目的とは離れた方向に飛び始めた。連なる山の脇を飛んでいく。
「山沿いに飛ぶなんて珍しいな、こんな時は、風任せだよ、無線機もあるし心配いらんさ」
一緒に乗っていた従兄弟の灯森(ひもり)はのんきに口笛など吹いている。熱気球十五年のベテランである。彼のいう通りなのであろう。
「そうね、また風が変わるかもしれないしわね」
「そうだよ、未来(みき)ちゃん」
灯森は双眼鏡を目にあてて丘の上を見た。
「すごいぞ、きれいな鳥が木の枝に無数にいるよ、俺も初めてだなこの鳥は」
私も双眼鏡をとった。
のぞくと木の枝にいたのは、見たこともないようなあざやかな青い鳥であった。鴉ほどの大きさだろう。尾はクジャクのように光に輝いている。それが何百もいる景色は表現が出来ないほど華麗である。カメラを忘れてこなければぱちぱち撮ったのに
気球がいきなり方向を変え、目的に向かって飛び始めた。
「ほら、もどった」
「そうね」
方向はいいのだが、数キロも東に寄ってしまっている。しかし、灯森ならばその程度の調整は朝飯前なのだろう。角度を変えようともしない。
「いつもと違うところを飛ぶのも面白いね」
灯森はこの国に二十歳の頃に遊びに来てそれ以来居ついてしまった。とうとうこちらの大学院まで出て人類学博士になり、今大学の講師をしている。大学はコロンビアの首都ボゴタにある。熱気球が趣味でいつも飛ばしているらしい。
私は日本の大学四年生、卒業記念旅行に友人とここによった。友人は風邪を引いて今日はビリャビセンシオのホテルで休んでいる。友人の方が楽しみにしていたのに、私一人である。だが残りはまだ三日ある。彼女が直ったらまた飛んでくれるということになっている。
「おや、あそこに遺跡らしきものがある」
灯森が双眼鏡を手に取った。彼方の草原の中に石が積み上げられた構造物がある。城壁ではなく大きな箱型の建造物だ。私も人類学に進んだのだが、形質人類学で、人や猿の骨が専門でもあり、学部を卒業した程度では、南米の歴史ある遺跡については素人といっていい。
「面白そうな遺跡なの」
「うん、というより、このあたりは、遺跡はないことになっているんだ。海の底だったところで、隆起し地上に出てきたのは比較的あたらしい」
「降りてみたいんでしょう」
「でも今日はこの場所を覚えておくだけでいいよ、遺跡はなくならないからな」
そう言いながら、地形図を取り出し、場所に赤丸をつけた。
「未来ちゃん、君の友達も人類学なんだろう」
「ええ、春藻もそうよ、でも同じ形質人類学、彼女はわたしよりもっと、生物学に近いことをやってきたの、遺伝子に強いのよ、彼女は大学院に進むの」
「そりゃ頼もしい、骨でも拾えるといいね」
「面白そう、彼女、風邪なんかふっとぶよ」
気球が漂っていくと、石が積まれた構造物が目の前に迫ってきた。よく見ると、草原の中にぽつんと立っていて、壁一面に石がつまれており、入口のようなものは見えない。
「四角いピラミッドのようだわ、でもどこから入るのかしら」
その時突風が吹き、熱気球が上に上昇し、遺跡の上を通り越し、反対側の上空から草原を見下ろすことになった。驚く景色である。眼下に現れたものは建造物の脇に広がる奇妙な地上絵であった。
「なんだこれは」
背の高い緑の草に覆われているが、その中に真っ赤な絵が浮きだしていたのである。それも二匹の鼠が向かい合っている絵である。
灯森がカメラを構えて舌打ちをした。充電を忘れていたようだ。
「未来ちゃん、気球をすこし下げるよ」
気球がゆっくり下りていく。地上の草がはっきりと見えるようになってきた。
「こりゃあなんだ、どうしてこんなことができるんだ」
赤い絵は赤い茸が並んで作られていた。
「赤い茸で絵を描いたのかしら、偶然じゃないわよね」
「奇妙なことだな、模様もだけど、乾季なのになぜ茸が生えているのだろう」
灯森も写真を撮りながら首をかしげている。
「下に降りてみるか」
灯森は気球を操作した。そのとき、また急に風が吹き上げてきた。気球が上に飛ばされた。
気球は構造物の真上にきた。ほとんど四角形に近い形をしている。石が敷き詰められている。
「屋上にちょっと降りてみよう」
灯森はそういうと熱気球を操作した。
「降りても、上がることができるの」
心配になった私が聞くと、彼は、「ガスはたっぷりはいっている、大丈夫だよ」と、笑いながら首を縦に振った。
気球は何事もなく屋上の真ん中あたりにゆっくりと着陸した。先に降りた灯森は気球を畳むと、私にでていいよと合図をよこした。
籠から降り、周りを眺めると、ずいぶん広い石造りの広場である。野球場ほどもあるだろうか。
「あそこにいってみよう」
屋上の縁には胸の高さほどの石の壁ができていた。近くまで行くと、しっかりできた石の壁で落ちる心配はない。灯森と周りを眺めた。遠くまで続く草原を望むことができた。それ以外何も見えない。
「かなりの高さがあるのね」
「そうだね、ビルの五階分もあるね、落ちたら危ないよ」
五階というとことは、少なくとも十メートルはあるだろう。
「この建物を作っている石はこの国ではみたこともない緻密な石だ」
「どこから運んできたのかしら」
「わからないな、それにしても今までなぜ知られなかったんだろうな。それも不思議だよ、急に現れた感じだ」
「人間が作ったものじゃないのかしら」
「そうなっちゃうね」
話しながら屋上のふちぞいに歩いたが、何もなく、だだっ広いただの石だたみである。
熱気球が折りたたまれているところに戻る途中で、私が石にけつまずいてよろけた。
「だいじょうぶかい」
灯森が笑いながら支えてくれたが、足元をみると、かすかだが段差があった。
「ここ、ちょっと盛り上がっている」
けつまずいたところを見ると、二メートル四方にわたり、そこだけ石が赤っぽく、ほんの一センチほども高くなっている。
「そうだね、なんだろう、蓋をしたようなかたちだな」
我々はその上にあがった。
灯森がその真ん中あたりに丸い白い石がはめ込まれているのに気づき、人差し指を伸ばし触れた。
そのとたん、彼は、あっといって、手を離した。
「びりっときたよ、なんだろう、感電したみたいなかんじだった」
彼の人差し指の先が赤くなっている。
「だいじょうぶだった、やけどじゃないの」
そのとき、からだがぐらっとして、彼と私は四角い蓋のところから放り出され、石畳の上に転がった。
目の前で、四角い蓋が上のほうにせりあがり、金属でできていると思われる丸い筒が目の前に現れた。
三メートルほどにせり上がると、ぽっかりと扉が開いた。まさにエレベーターであった。
「何という仕掛けだ、誰が作ったんだ。今のものじゃないか」
灯森は起きあがると、中を覗いた。入っていきそうだ。
「入るのはやめて」
私は叫んだ、そのままどこかに連れて行かれそうで怖かった。
「君はここに残ってくれ、中に入るだけだ」
「でも、もし、しまってしまったらどうなるの、あなたが出てこられなくなったら、私は気球を操れないから、私もここで死んでしまう、よして」
灯森はそれを聞いて躊躇したが、「そこに無線があるだろう、赤いスイッチを押すと救助信号がでる。ここは秘境じゃないから、ヘリコプターがすぐ来てくれる」
そう言った。
「でも、そのエレベーターにはスイッチもなにもないみたい、危険よ」
「きっと触れると動くのだろう、行き先は一つだから、ボタンもなにもないのではないだろうか」
冒険家でもある彼はいいだしたらだめだろう。私は気を付けてとしか言えなかった。
彼は中に入った。そのとたん、その筒の扉は閉まった。それだけではない、筒は沈んでいき、四角い石の蓋が閉まってしまった。
私は彼がしたように、蓋の真ん中にある白い石に触れた。感電するかと思ったが何もおきなかった。
私は途方に暮れた。十分待っても戻ってこなかった。心臓がどきどきしてくる。救援信号の赤いスイッチを押そう。
そう思ったとき、また蓋がせり上がり、円筒形のエレベーターが現れた。扉が開くと、彼が顔を出した。
彼はにこにこしている。私は心臓に手を当てて自分の動悸を抑えるのにやっとだった。それにしてもほっとした。
灯森の手には骨があった。動物の頭蓋骨だ。
「ほら、これ何かわかるかな」
「猿人とは違うみたい、形は鼠に近いけど、前頭骨がやけに大きいし」
「そうだね、今の動物じゃなさそうだ、地球の動物じゃないかもしれない」
「戻ってこないと思って、救難信号出すところだった」
「いや、ごめん、僕も驚いたよ、急に動き出して、でもあっという間に下について、扉が開いたんだ、スイッチもないし降りてしまったら大変だし、どうしようか迷ったよ、だけど、扉の前に、動物の骨があってさ、それでちょっと出たんだ、そしたらね、やっぱり閉まってしまって、驚いたな、でもしまった扉に触れたらまたあいたんで、急いで骨をひろったんだよ、そこはとても広い空間でさらに地下があるようだ」
「でもエレベーターなんて、今の人が作ったのじゃないとすると、宇宙人じゃない」
「そうなっちまう、まずこれをもって帰って、文化庁の役人を連れてくるよ」
今度は私に興味がわいてきた。灯森がいれば安心という気持ちがある。
「このエレベーターは自由に動かせたの」
「大丈夫のようだよ、中と外を行き来するだけのもののようだ。扉の内壁と外壁にタッチするだけで開閉するようだから」
「その部屋は広いの」
「ああ、体育館ほどかな、この構造物の大きさからすると、もっとたくさん部屋があるだろうし、下のほうにもあるだろうね、エレベーターの蓋のように、壁のどこかにスイッチがあって他の部屋に行く扉が開くのだと思う、エレベーターからでたところはこの建物の入口で、死んでいたのは、警備の担当の者だったのではないだろいうか。奥に入れば何か見つかるな」
「私も行ってみたい」
「そうだな、俺ももっと見たい気持ちなんだが、本当に安全かどうか分からないから、君を連れて行くのはきになるな」
「灯森さんと一緒なら大丈夫」
彼は笑いながら、行こうと指差して、鼠の頭蓋骨を石畳の上におくと、エレベーターに乗った。私もあとについた。彼が扉に触れるとすぐに動き出した。今考えると彼の頭の中では、かきむしりたいほどの葛藤があったに違いない。危ない行為である。私はまだ若かった。
下につくと出口が開き彼が先に下りた。私がでるとエレベーターが閉まったので、手で触れてみると扉が開いた。これなら大丈夫だ。
その部屋は不思議なことに、電気がついていないのにもかかわらず明るかった。
「この壁を作っているのは、外を囲っている天然の石ではないね、おそらく、ナノの世界の水晶のようなものが配列されていて、外の光を部屋に取り入れているのだろうね。ということは、この石には他にもたくさんの機能があると考えられる。こりゃあやっぱり遺跡じゃなくて、超近代的な建物、本当に宇宙船かもしれない」
彼の拾った頭骨の胴体の骨もあった。近くにもう一体あった。大きさは中型の犬ほどである。ゴールデンリトリバーほどだろう。しかし、この広い部屋にたった二体の骨だけであった。
「まず、壁に沿って歩いてみよう、何が起こるかわからないから、二人で一緒に歩こう」
「この生き物が高等生物だとしたら、四つ足だったから、あまり高いとこりにスイッチなんかないわね」
「未来ちゃん、いいところに気がついたね、僕も考えつかなかったよ、これだけ、高い天井の部屋だから当然高いところにあると思ったんだ」
私は壁の下の方を見ながら歩いた。あの白い石でもはめてあるのではないかと思った。だが見つからない。ところが、おかしな匂いがするところがあった。かすかだが線香のような匂いだ。
私はかがんで匂いの出所を探った。壁のかなり下の方から匂ってくる。手をそこにかざしたそのときである。その壁がぐーっと左右に開き、奥の部屋への入り口が開いた。あまり高さはないが、長い廊下があった。かなり奥に明るい部屋がある
「未来ちゃん、すごいね、どうしたらみつかったの」
灯森が反対のほうからかけてきた。
「匂いみたい、きっと嗅覚も発達していたのよ、視覚だって、その頬骨が前につきだしているところを見ると、側面に眼窩があるけど、目が横に飛び出して前を見ることができたのよ、立体視もできたはず」
「すごい推測だ」
「灯森兄さん、どうする」
「帰ることができなくならなければいいけどな、僕は鼻がよくない」
「私鼻はいいのよ」
「それじゃ行くか、楽観的になろう」
彼はちょっと間を置いて決心したようだ、一緒にその入口をくぐった。光の見えるところまでは結構ありそうである。ちょっと行って振り返った。入り口は開いたままである。
早足でかなり歩いた。先にある部屋の前に来た。振り向いて見ると、遠くの入り口はそのまま開いていた。
その部屋はずいぶん広く、一つの壁に大きなスクリーンがあり、周りの壁の下半分は計器類で埋まっていた
「これはであきらかになった、乗り物だ、宇宙船に違いない」
われわれが部屋に入って一分ほどしたときだろう、スクリーンに画像が現れた。目が横に飛び出して前を向いている鼠の顔が現れた。
「未来チャンが想像したとおりの鼠宇宙人だ。
音も出ているが、私の耳にはキンキンと響くだけである。おそらく超音波によるものなのであろう。
その生き物の顔が消えると、地球と同じような星が映し出された。きれいな町並みがみえる。皆石造りで、大きな鼠のような生き物が色とりどりの着物を着て歩いている。中には二本足で立っている者たちもいた。ほんとうに立ち話をしているようである。歩いているときには四つ足である。
「驚いたね、その星の映像だね、どこから来たんだろう」
映像が変わって、その鼠人間(と呼ぶことにした)が食事をしている場面に変わった。三人の鼠人間がナイフのようなもので大きな赤い茸を切り分けている。それに、ドレッシングのようなものをかけて、なんと、箸のようなもので食べている。食べながら三人で会話をしているようだ。地球上の家庭での食事風景と何らかわるところがない。時々ガラスのように透明なコップに入った液体を飲んでいた。この生き物も空気を吸って、水を飲んで人と同じ生活をしているようである。
「あの赤い茸は地上絵の茸のようね」
「大きさが違うが形も同じだね、栽培したもののようだ」
映像がまた変わった。
工場のようなところでの作業が映し出されている。
「茸の栽培工場のようね」
「そうだね」
広い苗床のような場所に、鼠人間が粉のようなものをまいている、映像は違う部屋に変わり、すでに大きくなってきた茸を映している。鼠人間の食料生産のようだ。
「きっと同じような食料生産工場が宇宙船の中にもあるのじゃないかな」
灯森が言った。私も頷く。
「海の底で暮らしていて、海地が地上にでてきてからも、石を持ってきて回りを囲み、そのまま生活していたのね、地上絵は仲間に報せるものかしら」
「そうだね」
地球上でも生えるように茸を開発したのだろう。いずれ鼠人間たちは地球人になるつもりだったのかもしれない。何か思わぬことが起き、滅びたのかもしれない。ウエルズの火星人来襲では地球上の細菌によって滅びたが、本当にそんなことがあったのかもしれない。
「この部屋から他のところに行けないのかしら」
「そう、未来チャンの嗅覚がたよりだね、だけど一度戻ろう」
彼の方が慎重である。私も頷いた。
エレベーターのあるエントランスに戻ると、不思議なことに、その部屋の壁に出入り口がすべて開いていた。八つもある。一つ一つのぞいてみると、今行って来たところのように遠くに部屋が見えたが、一つだけ下に降りる階段があった。
二人で下に降りてみた。そこにはもう一つのエレベーターがあった。彼が触れるとエレベーターの入り口が開き、私たちは躊躇なく乗った。
エレベーターは驚くほどの早さで下り始めた。今まで乗ったことのある高速エレベーターの何倍もの速度である。そしてついたところは、野球場が何十もはいるような石造りのドームであり、茸の養殖場であった。光が入り、辺り一面に茸が生えている。おそらく生きていた鼠人間は、エントランスより上の階に住んでいて、二人を見張りにたてて生活していたのに違いがなかった。
さらに、茸の工場には驚くべきものが散らばっていた。
それは、小さな鼠の骨であった。茸の棚の下に無数というほどの鼠の骨があった。
「この鼠の骨はどうしたのかしら」
私は鼠の頭骨を拾った。
「この鼠は現代のではないわね、鼠になったばかりの奴だわ。どこからか、地球の鼠が入ってきて、栽培していた茸を食べてしまい、さらに鼠人間を滅ぼしてしまったのではないかしら」
「鼠がばい菌を持ち込んだ可能性があるかな」
「そうね」
「茸の地上絵はどんな仕掛けかしらないが、時期が来ると、あの大きな赤い茸が鼠の形に生えるようになっているのだろう。あの草原を調べるとわかるだろうな」
灯森は赤い茸を採るとポケットに入れた。
「もう帰ろう、だんだん怖くなってきた、またこよう」
私たちはエレベーターに乗り、エントランスにでた。地上に行くエレベーターも入口が開いていた。
私は鼠の祖先の頭骨をもって中に入った。彼が後について入った。ところが、下に降りるときは、乗るとすぐに動き出したエレベーターが動かない。
「どうしたのかしら」
灯森はエレベーターの内側の壁をくまなく触っている。
「未来ちゃん、匂わないかな」
私は下の方で何か匂いがしないか嗅いでみた。
特別な匂いはしない。
「これは大変だな」
と灯森が言ったとき、エレベーターがぐらっと大きく揺れた。私は持っていた鼠の祖先の頭骨を落とした。
「あ」っと言う私の声がまだ残っている間に入口のドアが閉まり、エレベーターが動き出した。私はあわてて鼠の祖先の頭骨を拾い上げた。
「宇宙船が揺れている、どうなるのだろう」
エレベーターはがたがた揺れながら、屋上にでた。私たちはあわてて外に出た。そのとたん、建物が大きくぐらぐらと揺れ、屋上に置いておいた鼠人間の頭骨がコロコロ転がってエレベーターの中に入り入口が閉まった。エレベーターの塔は下がって消滅した。
「あ、鼠人間の頭の骨が」
「しょうがない、建物が揺れている、早く離陸しないと危ない」
彼は気球に熱を入れた。
膨らんだ熱気球は押さえるのが大変になってきた。
「さあ、乗って」
私は鼠の祖先の骨を大事に抱えて気球に乗った。
気球はすーっと上空に上った。下を覗くと、遺跡を作っていた石は周りに散乱し、宇宙船は砂埃の中に見えなくなっていく。
熱い空気が熱気球を上へ上へと押し上げていく。
「未来ちゃんよくつかまってろよ」
灯森の操縦技術は優れていた。熱気球は上に上がると同時にもと来た方向へとスピードを上げて、遺跡から離れていった。遠くに砂埃が見えた。
こうして私たちは、気球の基地に戻ることができた。
この出来事を灯森は大学に報告しなかった。灯森は明日もう一度行って写真を撮ってから報告すると言った。
あくる日、再び気球に乗った。春藻はまだ風邪気味であったが、我々の話を聞くと一緒に行くと言い張った。
三人で、今度はカメラももち重装備で目的地まで一直線に飛んだ。
「どういうことだ」
灯森が下を見てうなった。
あのビル五階ほどの高い構造物はなくなり、石が散乱して、茸の地上絵も覆い隠されてしまっていた。
「どうなってしまったの」
「崩れたのか、いなくなったか、あそこに降りよう」
灯森が指差した先に、石がきれいに敷かれた場所があった。気球をそこに降ろした。
籠から降りると、三人であたりを歩いた。
「穴があいているわよ」
美藻が四角の穴を見つけた。石にかこまれた穴がぽっかりと開いている。
しかもそこには石段があった。
春藻は目を輝かせた。未来は見たことがあるような気がした。
ヘルメットのヘッドライトをつけ石段をおりた。長い石段だった。
行きついたところは、未来と灯森が見て回った地下の茸の培養室であった。
「ここだけが残って地上にでてきたんだ、どういうことなのだろう」
「宇宙船は飛んで行ったとしか考えられないわ」
「だけど、ここが地上に出てきたわけがわからない」
部屋の中を歩いたが、萎びた茸と鼠の祖先の骨はいたるところに転がっていた。
美藻は初めて見る遺跡に興奮して写真を撮りまくった。
「すごい発見ね」
「でも鼠人間の骨がないわ」
未来は部屋の隅々まで見て回った。
「鼠人間のことは誰も信じないね、これから慎重に調べよう」
灯森が言った。
「この鼠の祖先の骨、それにこの遺跡はここにあるわ、それこそ大発見、一生涯の研究に繋がるわね」
「未来ちゃんも大学院にすすんだらいいのに」
春藻は写真機のモニターに写した画像を確認している。
「どうしよう」
「この部屋が残っていただけでも大発見だ、それに太古の鼠の骨もある」
「そうね」
「どうして、宇宙船が消えてしまったのか。きっと、変事には後が残らないような仕掛けがあったのかもしれない。宇宙船が砂の中を移動してどこかに行っているかもしれないね、この地下工場は相当深いところにあったはずだから、もしかすると、この地下工場の下に宇宙船がもぐりこんだのかもしれないね、それで、工場が上に出てきた。この地下工場は海底が地上に出てきてから作ったので一緒に地下深くにもぐらすことができなかったのじゃないかな、」
「そうだとすると、この工場の下の下のほうにあの宇宙船があるかもしれないわね」
「そうだな、この地下工場を発掘するときにいずれ出てくるかもしれない」
「この茸しなびたけど、胞子を培養すれば生えてくるのじゃないかな、遺伝子解析は簡単に出来るよ」
春藻が言った。映像にもあったが、鼠人間の星でもこれを食べていた、と言うことは、地球上のものではないことがこれで証明できるかもしれない。
未来はあの宇宙船の中には、まだ生きた鼠人間たちがいるのではないだろうかと思った。灯森と宇宙船の中に入ったとき、なぜ鼠人間の星の映像が流れたのか、出ようとしたとき、エントランスの入り口すべてが開いていたのはなぜか、我々に存在を知らせるつもりだったのではないだろうか。いずれ、我々の文明が彼らを理解できるほどに発達したら、連絡するつもりかもしれない。それまで、静かに宇宙船の中でくらしているのだ。それに、いつか遠い星の鼠人間がふたたび地球に現れるのではないだろうか。
「私やっぱり大学院にいく」
私はそう言った。
「よし、三人でこの遺跡の発掘をしよう」
灯森が答えた。春藻も大きくうなずいた。
地上絵
私家版 第八茸小説集「遊茸空、2020、一粒書房」所収
茸写真:著者: 東京都日野市南平 2016-7-16


