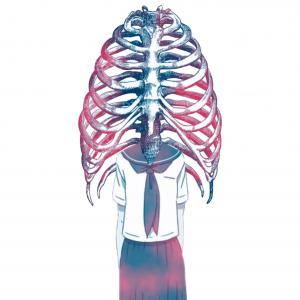廻る撫子、雨のなか
篭は揺れる。未だ一切の穢れを知らぬその眼差しは、安らかに閉じていた。
眠る赤子を、少年は見ていた。
唄は揺れる。揺り篭を持つ手は幼気を仄かに香らせ、その眼差しは純粋そのものであった。
子守る少年を、青年は見ていた。
池は揺れる。耳馴染みのララバイと水面に映る子供の姿を背に、その眼差しは大志に燃えていた。
抱く青年を成人は見ていた。
車内は揺れる。社会の荒波に揉まれ疲労したその眼差しは、窓の先の世界に期待した背中を懐かしんだ。
疲弊する成人を、老人は見ていた。
椅子は揺れる。案外捨てたものでもない此の世を抱擁し、頼りない小さな焔をその眼差しに灯し続ける。
居眠る老人を、赤子は見ていた。
夢は揺れる──。
廻る撫子、雨のなか