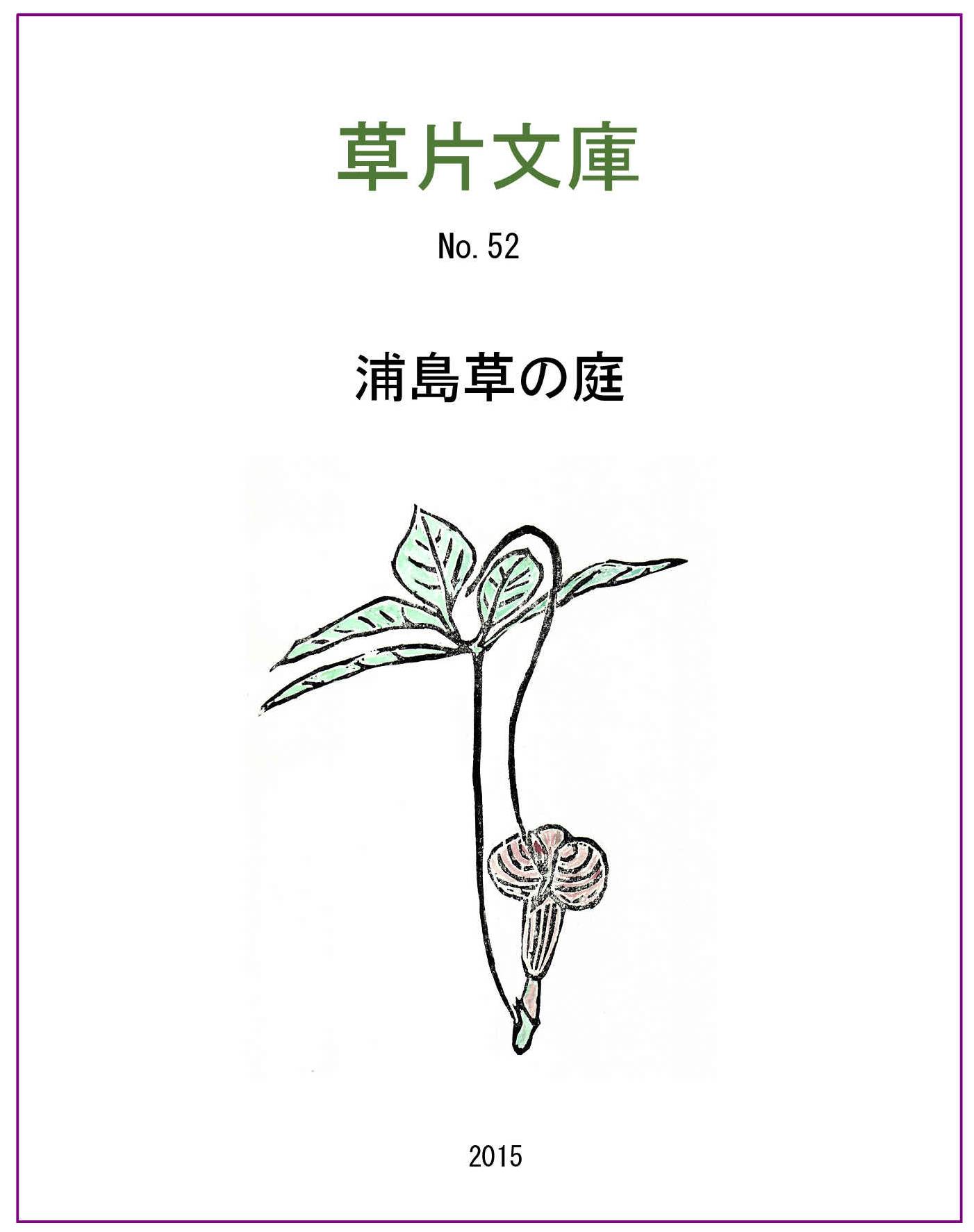
浦島草の庭
一幕
私の目の前を深紅の蝶がゆったりと舞っていく。
蝶はコンクリートの割れ目から伸びている傘の様な葉の先に止まった。何の植物だろう、見たことがない。前の方から歩いてきた毛の薄くなった老女が足を止めて、紅い蝶を不思議そうに見ている。確かに紅い蝶というのも珍しい。色だけではなく、このビルの谷間にいることも。
私は老女の脇を通り、友人のメディカルオフィスがある鳳凰ビルの前に立った。石段の上の入口の脇にある左右の鳳と凰の石像が私を見おろしている。石段を登り、自動ドアが開くと、広いエントランスの右側にエレベーター、左側には石でできた階段があった。正面にはインフォーメーションデスクがあるが誰もいない。
エレベーターに乗ると、十三のボタンを押した。目の前の扉が閉まる瞬間に、エントランスの大理石の床の上に、黒い影がさっと動いたような感じがした。誰か階段のほうに向かったようである。
そう思っていると、高速エレベーターはあっという間に十三階に私を運んだ。そこが友人のオフィスである。
エレベーターの扉が開くと、柔らかな薄桃色の絨毯が敷かれた廊下にでた。やはり薄桃色に塗られた壁には明るすぎるほどの照明器具が取り付けられている。精神科医である友人の考えなのだろう。エレベーターの扉の外も薄桃色に塗られている。私が降りて閉まると自分の回りは薄桃色に包まれ、一歩を踏み出すと、足の下から暖かな血が腹部を通り、胸をつきぬけ頭の中に登ってくるような、気持のよい心地がする。
廊下の中ほどに、垂氷(たるひ)クリニックと書かれた札が吊るしてあるドアがあった。ノックをし中に入ると、そこは待合室になっていた。この部屋は白に統一されている。真白な本革らしいソファーがいくつか並び、白い壁には静かな色調の絵がかかっている。白い色は病院のイメージがあり、薬の匂いが感じられるが、この部屋は決してそういった、医者に来たという感じを引き起こすことは無かった。どういったらいいのだろう。桃色に囲まれた後に入ったせいなのか、頭がすっきりするような、静まるような気持ちになる。これも彼の精神科医としての演出なのか。
一つの戸が開くと、大柄の女性がでてきた。背が高い。彫りの深い顔が私を見た。白い肌、茶色の瞳、日本人ではなさそうである。秘書のようだ。
「あの、垂氷君と会う約束をしている、諸衣(もろえ)ですが」
私が言い終わらないうちに、
「いらっしゃいませ、先生がお待ちです、どうぞ奥に」
彼女は本人が出てきた隣の部屋のドアをノックせずに開けた。
「先生、おいでです」
そこは専門書がぎっしり詰まった棚に囲まれた、十畳ほどのこぢんまりとした部屋であった。机の前に彼がいた。重そうな本が開かれ、原稿用紙が置かれている。
彼は眼鏡をはずして私を見た。彼はにこやかな顔になって、立ち上がった。色の白い細面の顔は全く変わっていない。
「よく来てくれたなあ」
ソファーを指差しながら、「座ってくれよ」と言うと、案内してくれた女性に、どこの国のものだか分からない、不思議なイントネーションの言葉で早口でなにやら話した。女性は頷きながら大きな目に微笑を浮かべて部屋を出て行った。
彼は長い髪をかきあげながら、私の前のソファーにこしかけ、昔と同じように、知らない人が見ると、どうかもすると皮肉ともとれそうな笑みを口元に浮かべた。彼の本当に嬉しい時の顔である。
「久しぶりだ、諸衣君」
彼と会うのは二十年ぶりになる。あの頃、私は某大学医学部で彼と席を同じくしていた。しかし、私は三年になった春に医学部をやめてしまった。人間の死臭とホルマリンの匂いが入り混じった空気の中での解剖実習に耐えることができなかったのである。そこを逃げ出した私は文学系の学部に移った。今はいくつかの大学で文学の講義をおこなう教師である。文学雑誌に評論もたまに載せることから、文学評論家とも思われている。
私は彼を見た。彼の柔らかな目つきの奥で、メスのように鋭い光がちらついている。一瞬にして私を判断してしまう目だ。これも学生のころとかわらない。彼の洞察力が彼を日本でも有数な精神科医に押し上げたのである。
彼は目を伏せると、あの静かな声で言った。
「変わらないね、君の繊細な目の動きは今でも忘れることはないんだ、精神科医になって十五年経ったかな、だけど、君ほどの人に出会っていないな」
「有名な精神科医にそういわれたのじゃ、僕は重症なのだろうな」
私は笑いながら、ちぐはぐな返答をして、彼も笑いながらそれを訂正した。
「そりゃあ、考え違いだよ、精神的に細かいということは、精密な脳を持っているということで、とても強いことなのだと思うよ」
「でもね、僕は医学部から逃げ出した落伍者だよ」
彼の目が遠くを見ているような穏やかさをとり戻した。
「うん、それは君の肉体のほうのコンディションのせいだったんだよ、君の体は病気もなく丈夫だったのだけど、余りにも精神が細やかで、肉体がそれを受けとめるほど強くなかったのさ、子どもの肉体だったのだろうな、肉体がいやがったのだよ」
彼の説明はやはり、精神的に未熟だったといっているのではないだろうか。
彼は机の上の煙草入れを取ると、蓋を開けて私に差し出した。
「まだ煙草はのんでいるのかい」
「うん」
緑色の不思議な紙巻煙草を私は一本とった。火をつける様子を彼の目は追い続けていた。彼は自分も一本とると火をつけた。
「今日訪ねてきたのは、君の担当の学生のことじゃないかね、君は文学の授業をもっているのだろ」
全くその通りである。しかし会いたいとだけ電話をして、話の内容は言っていない。私のゼミの女子学生の振る舞いで相談しに来たのである。だがこうも簡単に当てられるとは思っていなかった。
「さすが、高名な精神科の先生だねえ」
私の大げさな言いように、彼は照れ笑いをしながら、煙草の灰を灰皿に落とした。
「まぐれ当たりかな、と言うより、大学の先生でそういった相談を精神科に持ち込む人が意外と多いのだよ、特に女子学生との恋愛ざたでね、女子学生のほうからのこともあるし、先生自身の問題の場合もあるし、だけど君のはそういった問題ではないのだろう」
全くその通りである。
そこへ、先ほどの女性が紅茶を運んできた。
私の視線が女性にいったのを彼は見逃さなかった。
「秘書のマノン」
彼女は私を見て微笑んだ。私もちょっと頭をさげた。どこの国の人か彼は言わなかった。
彼女が部屋を出て行くと、彼は私に紅茶をすすめ、こう言った。
「自分自身のことで相談しにくる人は、目の動きが違う、自分のことだから、ちょっとおどおどしたところがある、恥ずかしさからかもしれないね、でも君の目は落ち着いている。他人のことだから目がぶれない、家族でもない、他人のことと言うと、学生のことだろうと想像がつく、はは、こんな抽象的なことしかいえないのが精神科医さ」
読心術者を目の前にして話をするというのは窮屈なものである。
「その通りだよ、私の受け持ちの女子学生のことだよ、ちょっと変わった子でね、僕のゼミはポーやホーソン、ホフマン、ユイスマンを扱うから、少し外れている子達が集まるのは当たり前なのだが、その中でもちょっと気になってね」
「幻想系の小説家だね、それにしても言語がみな違うけど、君は何ヶ国語こなすのだい」
「ラテン語を中心にやったので、意外と他の国の言葉に入りやすくてね、なんでも屋だよ」
「そりゃすごいね」
「いや、大したことはない、ただ、ゼミにくる学生たちは、そういった作家の本を手にしているということが、何か特別な世界に属している、他の人とは違うのだといった錯覚に陥っているのが多くてね、だけど今日話しにきた女の子はね、もってきた本がポーだとかユイスマンだとかというのと違って、医学生用の脳の解剖学の本だった。脳に興味を持つのもわかるのだが、脳はミステリーだからね、ただ彼女はそれ以上におかしかったのだな」
私は紅茶を一口飲んだ。
「それは講義のときだった、私が教室に入ると、彼女は一番前に座っていてね、彼女を目にしたときどきっとした、頭の毛を全部そり落としていたのだよ、腰まであった真っ黒の髪の毛が一本もなくなってしまっていた。正直言って、少しがっかりしたな、講義が終わると彼女がそばに来て、こうして頭の中を知るの、とか言ったのを覚えている。
その時、私はちょっと彼女の顔を見ただけだった。彼女の目は笑っていなかったに違いない、だけど私はそれに気付かなかった。
それから間もなくだけど。彼女はそりあげた頭の前のところに、血が固まったような傷跡をつけて講義にでてきたのだよ」
垂氷は彼にしては珍しく表情をこわばらせ、身を乗り出して話を聞いていた。
話が途切れると、ソファーに深く腰掛けなおして、私を見た。その目はやっぱりそうかといった、何かを知っているような目であった。
私は話し続けた。
「彼女は、その時、こう言ったんだ、『わたし、頭の中を覗こうと思ったんだ』、私はそれを聞いて、そんな冗談はよしたほうがいいね、と単純な反応をしてしまったのだが、彼女は蒼白い顔をして、『かみそりの角をあててみたのだけど、痛かったので止めたの』、と言うじゃないか、そして、それ以来、彼女は学校に来なくなってしまった」
彼は短くなった煙草を灰皿の上に押し付けた。
「その女性の名前はなんというのだい」
「椚(くぬぎ)原(はら)実夢(みむ)」
彼はうなずいて私を見た。このような話をしたら、誰でも動揺すると思うのだが、彼は変わることなく、低い声で私に尋ねた。
「その後、彼女はどうしたの」
「全く大学に来なくなり、事務所も親にまで連絡したようだが、無視されたというようなことを言っていた」
「その学生は精神病院にでも入れられたのだろうと君は想像しているわけだ」
私はうなずいていた。
「その女性は、君にとってかなり魅力のある子だね」
私はまたうなずいた。彼は立ち上がると、私にも立てというジェスチャーをした。
「病院を案内しよう」
彼は話しを打ち切って、私についてくるように手招きをした。部屋を出ると、
「ここも精神科としては、かなり知られるようになってね」と言いながら、隣の扉の前に立ち止まった。
戸を開けると、そこは書庫になっていた。木製の立派な書架に横文字の専門書がぎっしりと詰まっている。これも簡素だが無垢木の大きな机が置いてある。
「この先が入院病棟だ」
彼は反対側のドアを開けた。そこは長い廊下になっていた。反対側にいくつかのドアがある。
三つ目の入り口の前で、彼は立ち止まり、ドアの小窓を開くと中をのぞいた。
彼は自分のポケットから鍵束を取り出すと、そのドアの鍵を開け、振り向いて、私に手招きをした。入れということだろう。
彼の肩越しに7~8畳の大きさの部屋の中が見て取れた。絨毯が敷かれ、気持ちのいいオレンジ色の光で部屋が満たされていた。その真ん中あたりに、後ろを向いた女性が椅子に座っていた。
彼女が振り向いた。
私はどきっとした。まさか。
その女性は椚原実夢であった。長い青いベルベット製のスカートは足先まで隠し、さらに垂れ下がっていた。
彼女の髪は元のように長く伸び、きれいな女になっていた。と思ったのは一瞬で、
振り返った顔は表情の無い人形そのものだった。彼女の真っ黒だった眼の上を薄い白い膜が覆っている。彼女の目は見えなくなっていた。
私は棒立ちになっていた、垂氷は私の肩に手をおいた。
「驚いただろうね、つい一週間前ここに連れてこられた、両親にね、島根の旧家のお嬢さんさ、強度の統合失調症だね、頭のいい子がこういう状態になるけどね」
私の頭もぼーっとなっていた。彼の言っていることが遠くに聞こえる。崩壊した人間を見るのはつらい。
彼もそれを察したのだろう。私に戻ろうといって、入院病棟から出た。
彼の部屋にもどると、私は何も言えずにソファーに腰掛けた。
「今度は珈琲にしようか」
彼の声に、なんとなくうなずくと、電話で秘書にコーヒーを頼んだ。
「彼女の額の傷を見ただろう。自分の前頭に穴を開けたんだ、自宅でね。脳解剖の実習書を片手に、麻酔もかけないでね、極度の自己催眠に陥っていたのだろう、あの、ヘンケルの料理バサミを使ったんだ、その後、指を入れて中をかき回した、その時点で彼女はきっと今の状態になったのだろう、自分の崩壊さ、それが目的でもあったのだと思う、自分がわからなければ、未来が予測できない、それは幸せさ」
彼の言っていることにやっと私の頭が追いついた。
「彼女は元に戻ることができるのだろうか」
彼は首を横に振った。
「額の中の脳の部分は前頭前野といってね、そこがアイデンティティーを形成したりやる気を起こさせたり、要するに人間らしさを作り出しているところなのだよ、その昔、凶暴な患者さんの前頭前野を切り取っておとなしくさせる治療をしたのだが、今では禁止されている」
私は何も考えられないようなショックで帰ることさえ億劫になった。
マノンさんがコーヒーを持ってきてくれた。
「少し休んでから帰るほうがいいね」
彼が心配そうに声をかけるのがやっと聞こえた。私はコーヒーを口に運んだ。暖かい。ちょっとほっとする。
「頭が壊れると怖いことが平気でできるのだね」
「人間は脳そのものだから、脳が壊れれば人間じゃなくなる」
私は立ち上がった。
「そろそろ帰るよ」
「大丈夫かい、気をつけて帰ってくれたまえ、彼女はずーっとここにいるか、他の病院に移るか、将来のことは私も分からない」
「また来ていいかい」
「もちろん、君にも薬を処方するほうがよいかもしれないな」
私は首を横に振った。
「それじゃ」
「いつでもいいから、来るときは電話してくれ」
一緒に下まで行くという彼の申し出を断って廊下に出た。
薄桃色の廊下をゆっくりと歩き、エレベーターの前に来ると、来た時にはなかった「故障」の張り紙がしてあった。こんな気分の時に、十三階から歩いて降りなければならなくなったのはちょっとつらい。再び彼のオフィスの前を通って、廊下の反対側の階段室に行った。
椚原実夢がまさか垂氷のところにあのような状態で入院しているとは思わなかった。もう少し彼女と話をしていれば、このようことにならなかったかもしれないとも思い、少しばかり自責の念にかられていたのだ。
椚原実夢のことで頭がつまり、半分無意識に一歩一歩石段を下りていた。
自分の頭の中をいとも簡単にこじ開けることができる狂気もすさまじいが、それによりもたらされる人間喪失の恐ろしさ、ということは脳のあやうさ、などが頭の中を駆け巡った。
階段の窓から差し込む夕日が、赤く石段を照らし出す。
椚原のあの感情のなくなった呆けた顔は、自分の胸の奥をかきまわす。あのエキゾチックな彼女の顔がかさかさな、ただの紙のようになってしまった。のっぺらぼーのほうがまだ表情がある。
足先に数字の9が見えた。いつの間にかここまで降りてきたようだ。
ふとその先をみると男の子がいる。青い半ズボンをはいたおかっぱ頭の少年は背をこちらに向けて石段に腰掛けている。
このようなところで何をしているのだろう。私は少年を避けながら降りていった。
少年は腰掛けている石段を見つめている。
私が少年から二、三段下におりかけた時である。背後で何かが異様な速さで膨張し、天井に広がっていった気配を感じた。一瞬後ろを振り向いた。しかし何事かが起きたわけではなく、少年はうつむきかげんに自分の足元を見つめているだけである。
何をしているのだろう、といぶかしく思ったとたん、少年は立ち上がった。
誰かに操られているマリオネットの人形のように伸び上がって、色の白い端正な顔を私のほうに向けた。顔には血の気がなく、目が人形の顔に彫られた黒い穴のように空虚だった。
私はからだ中に寒気がして凍りついたように立ち尽くした。
少年は私のほうを向いてはいるが、わたしの頭を素通りして脳の奥をのぞいている。そしてこう叫んだ。
「この下に女の人がいるんだ」
少年の声は階段に響いた。
私は反射的に少年に声をかけていた。
「どうしたの」
普通に出したつもりの声は、余りにも小さく、少年に届いたかどうか分からないほどであった。少年は私の声には反応せず、再び石段に座り込み、うつむいて小さく縮まってしまった。自分は何もしなかったように。
少年は本当に私に何か言ったのだろうか。私は奇妙な感覚にとらわれながら、下に降りようと足を踏み出した。すると背後からふたたび少年の声がした。
「この下に女の人がいるんだ」
振り向くと、私を見ている少年のまぶたは、先ほどの人形の顔ではなく、厚ぼったく腫れ上がり、はめ込まれた硝子のような茶色の瞳孔は見開かれていた。覚せい剤か何かを打たれたように、しかし少年の目に感情が見られないのは、先ほどと同じだ。
少年は座ったまま、自分の細い足の下を指差し、
「この下に女の人がいるんだ」と繰り返した。
私は背筋がぞくぞくと波打った。この子は狂っている。病院から抜け出したのではないだろうか。そうならとってかえして垂氷に言わなければならないのだが、そう思ったが、振り返るのも怖くなり、急いで逃げるようにその場から石段を駆け下りた。心臓が波打っている。階段の数字が目に入る、8,7,6。くるくると数字がかわり、ビルのエントランスにでた。動悸が激しい。
インフォーメーションデスクにはやはり誰もいなかった。机の上に電話が置いてある。脇にビルに入っている会社と内線が書いた神があった。私は垂氷に電話を入れた。
マノンが出て、取り次いでくれた。
「どうしたんだい、大丈夫かい、息づかいが粗いじゃないか、どこにいるんだ」
「エントランスにいる。少年が階段のところにいた、八階だ、それがおかしいんだ、入院患者じゃないかと思って」
「階段で降りたのかい」
「うん、エレベーターが故障していた」
「そうだったのか、私のところは子どもの診療はやっていないから、そういう入院患者はいないね」
「あの子は狂っている」
「そうか、それじゃ、降りてみる、もう一度上がってくるかい」
そう言われて椚原の顔を思い浮かべ、また動悸が激しくなった。
「いや、このまま帰る」
「見とくから安心してくれよ、気をつけて帰れよ」
「ああ、今日はありがとう」
受話器を置いて、入口の前に行くと、自動ドアがすーっと開いた。左右の石の鳳凰が私を見ている。
椚原実夢の悲惨な姿もだが、石段に座っていた少年の姿が私のからだを凍りつかせている。少年の声が耳に渦巻いて、それに追い立てられるようにして、地下鉄に向かった。
あくる日の朝になっても、からだがほぐされていなかった。ほとんど眠れずにベッドの中で目を瞑っていただけのような気がする。シャワーを浴びても頭だけは温まることはなかった。
もう一度垂氷に会わなければこの状態から逃れることはできそうにもない。私は朝早く家をでると、彼に電話をすることに考えが及ばず、鳳凰ビルに来てしまった。
ビルの中は閑散としており、冷たい空気が澱んでいた。エレベーターの前には、まだ故障の紙が張ってある。
階段を上らなければならない。私は一歩一歩、登り始めた。石の階段を歩く私の足音だけが響く。
息が弾む、と、行く手にまた少年がいた。昨日と同じように階段に腰掛けて俯いていた。何階だろうかと見ると、8の数字が眼にはいった。昨日と同じところに腰掛けている。
少年の目が私を見た。私のからだが震えた。少年は立ち上がると低い声で言った。
「この下に女の人がいる」
同じことを言った。私はその声で走り出した。目を瞑るようにして少年の脇をすり抜け、走っていた。このようなエネルギーがどこにあったのだろうか。13階に着いた時には倒れそうに胸が苦しくなっていた。階段室のドアを開け、薄桃色の廊下の明かりの中に入ると、なぜか動悸がおさまってきた。かわりに多量の汗が噴出してきた。
しばらく息を整え垂氷のオフィスの前に立った。
ドアをノックすると、ちょっと間を置いて中に灯りがついた。人が動く気配があり、ドアが開いた。マノンが私を見て驚いた。
「あ、先生でしたか、どうぞお入りください、すぐ、先生をお呼びします」
彼女はここに住んでいるのだろうか。入院施設があるわけだから、看護師や警備員が泊りでいても不思議はない。
診察室には明かりがついている。私を見た彼女はあわてて隣の診察室に声をかけた。
「諸衣先生がお見えです」
彼女は診察室のドアを開け、急いで隣の処置室にいった。
私が入ると、彼は目を大きく見開いて私を見た。
戻ってきたマノンがガーゼの布をもってきて、私の顔をぬぐった。何をするのかと驚いていると。私の顔を拭いたガーゼが真っ赤になっているのを私に見せた。
「血が噴出しているぞ、何があったんだ」
垂氷の手は私を支えてソファーに腰掛けさせてくれた。
「コーヒーを持ってきてくれ」
彼はマノンに声をかけた。
「血の汗がでたんだ、あまりの緊張で血管が縮んで血液まで搾り出してしまったんだ、血の汗は本でしか読んだことがない、どうしたんだ」
「また、少年がいた」
「昨日電話をもらって、行ってみたが少年はいなかったな」
私は階下の石段に腰掛けていた少年の、底知れぬ不気味さを話して聞かせた。
話したことで、私の気持は少しばかりおさまっていった。秘書のいれてくれた珈琲がとても美味しく感じられた。
「少年が階段の石の下に女の人がいると言ったのか、それで今も少年はいるのだな」
私はうなずいた。
彼は「ちょっと見てくる」と立ち上がった。
「私も行こう」
「登ってきたばかりで大丈夫か、もし大丈夫なら実際に行って、その時のことをもう一度話してもらったほうが、君の気持は落ち着くだろう」
彼は精神科医になっていた。
「君の精神はあまりにも繊細だからな、病気ではなくて、そういう脳をもっているということだよ、椚原も繊細な脳の持ち主だが、彼女は病をもっている」
私を従えて垂氷は階段をゆっくり下りた。
9階までおりると、少年はまだうつむいたまま石段に腰掛けていた。私は立ち止まった。足の裏がジーンとしびれてきた。
「少年がいるね」
垂氷は確認するように私に言った。
「君、何しているの」
少年は俯いたまま彼に答えた。
「この下に女の人がいるんだ」
声が階段に跳ね返った。
「どこからきたの」
垂氷は私の脇を通って少年の前に立った。少年は垂氷に向かって顔をあげ、窓ガラスが飛び散らんばかりの、すさまじい悲鳴をあげた。少年の口からほとばしりでた声は、私の耳の中でがんがんと鳴り響いた。と前みると垂氷の姿が石段の下のほうに消えていった。
垂氷が下の踊り場で倒れている。
私は少年のことを忘れ、彼のところまで駆け下りた。背後から黒いものが飛び上がり、天井のほうに消えていった。
垂氷はからだを起そうとしていた。
「大丈夫か」今度は私が声をかける番になっていた。
彼はうなずいた。しかし破れたズボンの膝から血がにじみ出ている。膝の下がぽっかりと赤く割れ、血がどくどくと噴出している。彼は自分でズボンを切り裂き、血を抑えた。
私は彼に待っているように言って十三階に駆け上がった。
少年はもういない。しかし、少年の腰掛けていた石段が崩れている。崩れたところから、一本の太い黄色の骨が突き出して血に染まっている。
私はそれを脇に見て、彼のオフィスに行くとマノンに彼のことを話した。彼女はあわてて奥の部屋にいくと、三人の白衣を着た男性を引き連れてきた。看護師たちはすごい勢いで階段を駆け下りて行った。
その後、少年の叫びは本当になった。崩れた石段が掘り起こされ、長い髪の毛が巻きついた骨がでてきた。骨盤が石段の下に埋もれていて、女であることが分かった。女のからだが埋められていたのである。
垂氷と私は警察から事情聴取をされた。しかしそのビルが建った頃には私ももちろん、垂氷もまだそのビルとは全く関係がなく、警察からすぐに放免された。それより彼の足の怪我が完治するのに一月もかかってしまったのは大変だった。
それからだいぶ経ってから、女の身元が明らかにされた。知名度こそ低いが中堅の女優であった。舞台で活躍していたようである。私のように芸能音痴には縁がない女優である。だがどうしてそこに埋められていたのか誰も見当がつけられなかったのである。鳳凰ビルが建って二十五年経つ、その頃行方不明になった女である。
あの忌まわしい事件から一年程が過ぎようとしていた。私も何かと忙しい日々を送るようになっていた。いくつかの大学で講義をたのまれ、ある雑誌から定期的な執筆を依頼されていた。あの少年の存在はまだ解決はしていないが、少年の言っていたことが本当になったことで私の精神状態は安定した。
その日、都内の私立大学に出張して現代の小説について講演していた。最近は幻想という冠をつけた小説が多く出版されているが、内容の薄いものが多いことを話しているときであった。二百人を超す学生を相手の講演であったが、階段教室の一番上にいる学生が私を見つめているのに気がついた。どこかで見たような学生である。遠いので顔ははっきりしない。しかし私を虎視しているのが分かった。一般に後ろの席に座るような学生たちは居眠りでもしているのが常である。そんな雰囲気の中だからか、その一人の学生がひときわ私の目を引いた。
話に熱が入って九十分をちょっと超過してしまった。終わると学生はなだれのように出口に殺到し、あっという間に教室からいなくなった。
教壇の上の資料をカバンに入れふと見ると、最後の一人が出口からでようとするところであった。その学生が振り返って私をみた。後ろの席で私を見つめていた学生である。しかし振り返ったその学生は少年の顔であった。遠くからでもはっきりと分かった。その学生は後ろ姿が半ズボンの少年になって消えて行った。
垂氷のところで出会った少年の顔である。幻覚なのであろうか、私も荷物をまとめて階段を登り出口に向かった。
講堂の外に出ると、食堂に向かって学生たちがぞろぞろと歩いていくところであった。別棟の講師室に向かおうとした時である。石段の上に腰掛けている少年が目に止まった。今出てきた講堂の前の石段である。俯いて自分の足元を見ている。私の心臓が高鳴ってきた。あの少年である。私は戻って少年の前まで歩いた。立ち止まると、少年は言った。
「この下に女の人がいるんだ」
少年は立ち上がって私を見た。うつろな目は私に訴えかけていた。
また少年が言った。
「この下に女の人がいるんだ」
私が立ち尽くしていると、通りかかった事務の人が私に声をかけて来た。
「先生、ご苦労様でした、何を見ておられるのです」
私を教室に案内してくれた事務長だった。彼も私の見ているものを見た。
「石段に何かがありますね」
少年はおらず、少年がいた石段の壁からなにやら白いものが突きでている。事務長はそれに手をかけた。そのとたん、石段が脆くも崩れ落ちた。
「あ、こりゃあ、あぶない」
事務長はそう言ったあと、さらに大きな声を出した。
「先生、これ、骨ですよ」
崩れた後に頭蓋骨のようなものが転がりだした。
「私、人を連れてきます、先生、すみません、ちょっと見ていてください」
私はうなずいた。言われなくとも目を骨から離すことができなかった。
事務長は何人かの人を連れてきて、その回りに囲いを作り、青いシートをかけた。
「先生、大丈夫ですか、ありがとうございました、事務室でお茶でも」
私を誘ってくれた。
私は言葉が出なかった。その後知ったことだが、そこから二人分の骨が出てきたそうである。女の人だそうである。その講堂が建てられたのは古く、戦後間もなくの石造りである。ただ入口は十年ほど前に改装されており、石段もその時つくられたものだということである。ということは、その女性たちは十年前に埋められたことになる。身元は全く分かっていない。
私は気分的にずい分落ち込んだ、垂氷に電話をかけその出来事を報告した。
「大学の石段にあの少年がいて、そこから女性の骨が二体も出てきた、君のところと同じだ」
彼の声はあまり驚いたようではなかった。
「そうか、どうだい、診療所のほうに来ないかい、しばらく講義は休めよ」
私は彼の言葉に従った。
鳳凰ビルのエントランスには相変わらず人がいなかった。エレベーターで十三階に上がり、薄桃色の廊下に出るとやはり気持が落ち着いた。
垂氷は待合室のソファーに腰掛けていた。
「久しぶりだね、顔色は悪くない、からだのコンディションは良さそうだね」
そう言いながら自分の診察室に私を導きいれた。
「うん、だけど、気分は悪いよ」
「そうだろうな」
「あの少年は誰だろう、私の錯覚なのだろうか」
「君は繊細だからね、確かに少年は君の幻覚かもしれない」
垂氷は今回はっきりと言った。
「でも、前の時には、君も少年を見たのではないかな」
「いや、見ていないのだ、僕は石段から飛び出していた骨にぶつかって落ちた」
それを聞いて背筋が寒くなった。彼はそれに気がついた。
「気味が悪く思うかもしれないが、特殊なものを感じとることのできる人は、頭の中で何かと出会うものなのだ、自分が感じたことを、何かが自分に告げていると解釈してしまうものなのだ」
私には彼の言っていることがいくらかはわかった。
「こんな時に言うのはなんだが、椚原実夢が死んだよ」
頭に指を突っ込んだ女子学生が死んだということである。
私はあまり強いショックを受けることはなかった。なぜか彼女が死ぬのは自然のような気がしていた。人間としての彼女はすでに死んでいる。理由は聞かなかった。
あの少年が二回も私の頭の中で私に話しかけてきたほうが、私にはよりショックであった。
「あの少年のことが頭から消えないんだ」
「少し、ゆっくりしたほうがいいな」
秘書のマノンが黄金色の飲み物の入ったグラスを二つもって来た。
「あ、ありがとう」
垂氷の声が聞こえる。
「君の好きな、スコッチだ」
私はうなずいて口に運んだ。いい香りだ、だが石の下のあの匂いは、それにもまして甘いいい匂いだ。その時、そう思った、自分もあの匂いが好きなのだ。
そのあと、私が気がついたのはベッドの上であった。見慣れぬパジャマを着ている。
周りを見ると、本棚があり、机があり、明かりの差す窓には、奇妙な花の咲いている花瓶が置いてあった。紫色の筒状の花から長い紫色の糸が垂れている。葉は傘のように開いてその花の上を覆っている。そういえば、葉はビルのコンクリートの隙間から出ていたものによく似ている。
見慣れぬ女性が白衣を着て、私のベッドの脇で椅子に腰掛けていた。目を開けた私に彼女が言った。
「諸衣先生、気がつかれました。朝食は何がよろしいですか」
私は見たこともない周りの景色にちょっと怖気づいていた。
「ここはどこですか」
「垂氷病院の特別病室ですわ、私、看護婦の三花茂です、これから先生の担当になりました。何でもおっしゃってください」
「私は入院したのですか」
「はい、もうすぐ垂氷先生も見えます、朝食をお持ちしますが、何がお好きですか」
「いつも、パンと紅茶です、それに果物とヨーグルト」
「すぐ用意します」
彼女はそう言って部屋から出て行った。入れ替わりに入ってきたのは垂氷であった。
「諸衣、どうだ、気分は」
「うん、全く問題ないが、僕はなぜ入院したんだ」
「あれから、三日、ずーっと寝ていたよ、頭が疲れているんだ」
「あの少年が見えるのは、頭の病気なのか」
「病気といえばそうだが、君のその才能かな、繊細な頭だよ、もしかすると動物的なのかもしれないね、動物は嗅覚に優れている。人間は退化しているが、君は人間の脳をもち、かつ動物の嗅覚が衰えなかった」
「それじゃ、もう、家に帰っていいのだね」
「どうだろう、少年のことがもう少し薄れてから家に戻ったほうがいいのじゃないかな、ここに必要な本などをそろえるから、ここで仕事をしたまえ、外出も自由だよ、ただし看護婦さんといっしょでね、それに薬はちょっと飲んでもらうけどね、気持を落ち着ける薬だよ」
「安定剤か」
「いや、安定剤ではない、一部の機能を抑える薬だ、君の脳は他の人間と違う、その部分の働きを抑えることで、全体のバランスが取れる、そうしないと君が破綻する」
「まかせるよ、ところで、あの花はなんだい、奇妙だね」
「浦島草っていうらしい、看護婦が好きなんだ」
「あの看護婦さんは、昔からいるのかい」
「いや、最近きたばかりだ、見覚えがあるのかい」
「いや、ない」
そこへ看護婦が食事を運んできた。
「どこで召し上がりますか、ベッドの上に置きましょうか、それとも、あちらのテーブルにしますか」
看護婦が垂氷の顔を見た。「着替えて、テーブルのほうがいいのじゃないかな、普通の生活をしてくれよ、読みたい本などは、三花茂さんが家からもってきてくれるよ、講義だって自由にしてくれ、ただ、ここに帰ってきてくれよな」垂氷がそう答えた。
私はテーブルに私の朝食を用意している彼女を見た。細面の整った顔をしている。可愛らしい感じの女性だ、年は三十半ばぐらいだろうか。
ベッドの脇のサイドテーブルに用意されていた朝食は、いつも家で食べているものと変わりがなかった。新聞も用意されており、見ながら朝食を食べ、記事の中から、ユイスマンスの「さかしま」が文庫になったことを知り、その本を買いに行きたくなった。それに家にある原本ももう一度みたい。
そんなことを看護婦に言うと、垂氷の許可をとってくれて、その看護婦と一緒に本を買いに行くことになった。鳳凰ビルを出て、駅まで歩く間に、彼女と話したことで、その看護婦はずい分文学に詳しいことがわかった。大学のフランス文学科をでてそれから看護婦になったと言った。
買った本を持って帰ると、垂氷が私に、「家に帰ると、入院している効果が薄れるので、三花茂さんにユイスマンスの原本をとりに行ってもらってもかまわないだろうか、ついでに、家の中を掃除してくれると思うよ」と言った。
私は自宅の鍵を彼女に渡し、本のありかを教えた。私の自宅は三鷹駅から歩いて十五分ほどのところにある、祖父が戦後に建てた贅沢な古い家である。もうその祖父も両親もいない。私しか住んでいない。
その夕方、三花茂看護婦が家から本を数冊持ってきてくれた。頼んだもの意外に彼女が選んだものもあったが、とても素人とは思えない選び方だった。
「よくわかりましたね」
「いや、並んでいたものを持ってきただけです」
そんなはずはなかった、もってきた本は別々の分類で棚においてあったはずである。相当フランス文学に精通しているようである。
それからは、病室で、といってもホテルの一室のような雰囲気の部屋であるが、本を読むことと、文章を書くことで毎日をすごした。時として、三花茂看護婦と一緒に、本屋に行ったりもしたが、やはり部屋の中でものを書くのが好きである。
病室でいくつかの文を書き雑誌に載せた。
ある日、垂氷が一通の私宛の手紙をもって来た。
「差出人の名がないので、気になったが、一応もってきた。開けて見ておかしいことが書いてあったら、言ってくれ」
誰だろう。この病院に入院していることはほとんど人には言っていない。
彼から受け取った封書を切ると、中から毛筆で書かれた便箋が一枚と、ローカル新聞の切抜きが二枚でてきた。新聞は薄黄色く変色し、今にも崩れそうな古さだった。
私は達者な毛筆の文を目で追った。私の頭にまた暗い影が差した。
「貴君は小さい時、特殊な能力をもっていました。今でもそれは、君の頭の中に存在しているのです」
新聞の切り抜きの見出しには、『少年、水死体を発見』とあった。入水自殺を図り、深みに沈んだ女の死体のありかを、陸の上から指図して教えたというものである。もう一つは、『不思議な少年』と題され、山の中に埋められていた少女の死体を発見したという話であった。そこに写っていた写真の中の少年は私だった。
そうだった、思い出した、私は少年の時に、私が出会った二人の少年のように----。
便箋の文は、貴君は死人を見つけることの出来る少年でした、と結ばれていた。
やはり、少年は私の頭にいるのだろう、だがどうして今、このようなものを誰が送ってよこしたのか。折角少年のことを忘れようとしているところなのに。
垂氷がそれらを読むと、私のほうを見るでもなくつぶやいた。
「諸衣、これではっきりしたな、君の能力が」
誰がこれを送ったのだろう。私を知る人間はあまりいない。実は子どもの時の記憶があいまいで、父親と母親の顔を知らない。子どものころ事故で死んだことになっている。裕福であった事業家の祖父が私を施設に預け、大学に進ませてくれた。その祖父はかなりの財産を私に残して、天命を全うした。遠い親戚しかなく、私には家族がいないに等しい。
「しばらく、私のところで静養すれば、また普通の生活に戻れるよ」
垂氷はそう言って、部屋を出て行こうとしたので、
「誰が出したのか、調べてくれないか」
手紙の送り主を探してもらうつもりで言った。彼は振り返ってうなずいた。
入れ替わりに三花茂さんが入ってきた。
紫色の花を持って、窓辺の花瓶のところに行った。
「変わった花がお好きですね」
「浦島草は里芋の仲間だそうですよ、ほら、浦島が釣りをしているように見えるでしょう」
筒状の花の中から伸びている舌は確かに釣りの糸のようでもある。
彼女はそう言いながら花を取り変えた。
「お好きなんですか」
「庭に生えているのです」
飾り終えると私を見た。昔どこかで会ったことのあるような女性である。
それからそのような生活がしばらく続いた。
私のからだは、かなりしっかりしてきた。家にもどって自分の本棚に囲まれて、何か書きたいと思うようになってきた。少年のことは覚えてはいるが、前のように、奇妙な圧迫感はなくなっていた。垂氷もそれに気付いているようである。
「そろそろ退院したくなったろう」
「うん、どうだろう、家で薬を飲むから、戻っていいだろうか」
彼はうなずいた。
「いいよ、だが、三花茂さんに住み込みで、面倒を見てもらうのが条件だ」
「それはこちらからお願いしたいくらいだ、とても私のことを良くわかってくれているよ、やって欲しいことを言わなくてもしてくれる、もともと家の管理はハウスケアーに頼んでいたしね」
「それじゃいつでもいいよ、帰りたいときに帰って」
「それで、あの新聞の切抜きを送ったのが誰かわかったかな」
「うん、聞かれたら言おうと思っていたのだが、聞かれなかったから今まで黙っていたんだ。君の小学校の先生だよ、君は覚えていないだろうけど、その先生が君を支えてくれていたんだ、もう九十にもなる人だけどね」
「会ったほうがいいのだろうか」
「本人は会いたくないようだ、なぜあれを出したか聞いたが、君が私のところに入院しているということを知って、過去をはっきりと知ったほうが、君のためにいいのではないかと判断したらしい、実は私もそれで助かったと思っている。
少年が見えたのは、君が感じたことを自分で認めたくなかったところがあるからだよ、君の能力であることが分かったら、少年を見ることもなくなる」
「確かにそうかもしれない」
私も納得した。
三鷹の家に帰ると、庭に浦島草がたくさん生えていた。紫色の糸を垂らしている様は見ようによっては気味が悪い。だが、自分の家に浦島草が生えていることなど今まで一度も気付いたことはなかった。祖父が植えたのだろうか。もっとも、庭には興味がなく、庭の管理は祖父がたのんでいた植木屋がきていた。
庭の浦島草を見つめていると、病院から一緒についてきてくれた三花茂さんが、ずい分咲いていますねと笑顔で私を見た。
彼女を昔から知っている人のような気がしてきた。接し方が本当に自然である。
家に入ると彼女は私の荷物の整理をし始めた。
「三花茂さんは、二階の角の部屋を使ってください。昔家政婦さんの使っていた部屋です」
彼女はうなずいて、二階に上がっていった。私は久しぶりに書斎に入った。
二幕
丘陵に発展していった団地の一番上には木に囲まれた見晴らし台広場がある。あまり訪れる人もおらず、木のベンチは朽ち始めているが、遠く富士山から秩父の山々を望むことのできる、なかなか壮大な展望が開けている気持ちのよいところである。
もうこの年になると、あたりを散歩する楽しみしかない。数年前にこの丘の下の方に家を建て、猫一匹と暮らしている。朝早く起き、いつものように頭に浮かび上がる話をコンピューターにうち入れ、午前中は周りをぶらぶらと散歩をする。時々市の図書館まで散歩がてらに歩いて行くが、このところその回数も減ってしまった。調べ物をするエネルギーがなくなっている。
いつものように、ぶらぶらと見晴らし台に登ってくると、一昨日来たときは気がつかなかったのであるが、広場の奥の木々の間に、もっこりと土が盛り上がっているのが目に入った。その上には一本の花が咲いている。紫色の奇妙な筒状の花の中から長い紐をたらした浦島草である。その昔住んでいた三鷹の家の庭にたくさん生えていた。
土の盛り上がりはちょうど人が入る程の大きさである。昔だったら土饅頭といったところだ。なんとなく薄気味悪い。
私の世代では、田舎でもそうであろうが、東京では土葬にすることはない。土葬は古い風習ではないが、今ではほとんどないといっていい。今の人に土饅頭といってもイメージがわかないことだと思う。死人を埋めた上に盛る土の丘である。
公園にあるものは自然にできたようには見えない。ということは何か大きな物を埋めたのか土を捨てたかである。しかし浦島草が咲いているということは、どちらにしろ、盛ってある土のなかに浦島草の芋があったということである。里芋科の浦島草の根元には芋がある。
私の後ろから半ズボンをはいた少年が登ってきた。今時珍しいおかっぱ頭で、スカーフを首に巻いている。少年は私の方を見ることもなく通り越して、いきなり浦島草の生えている土饅頭のところにいった。立ち止まったまま浦島草をしばらく見ていると、いきなり私の方に振り向いて言ったのである。
「この中に女の人がいる」
私は眩暈を感じた。もう三十年以上前になるだろう。私は数年、精神科に入院と通院を繰り返していたことがある。大学の教師をしていた頃である。入院する前に私は、このような少年に会っているのである。医者である大学の同級生は私の脳の中にしか現れない少年だと言った。たしかに友人の治療方法が良かったのであろう、今では頭の中から少年のことは消え去っていた。
しかし、どうだろう今目の前に少年がいる。また少年が脳にもどってきたのだろうか。歳をとるにつれ、逆にからだもそれなりに丈夫になり、気持ちもゆったりと暮らせるようになった。家内はだいぶ前に他界して、もう長い間やもめ暮らしである。精神科医であった友人は、その世界ではかなり高名になったが、惜しまれながら死んだ。家内の死とそんなにかわらない頃であった。
私は少年をもう一度を見た。昔出会った少年とはどこか違う。この少年のほうが少し年をとっているようである。色の白い北ヨーロッパ人のように整った彫りの深い顔をしている。
少年は私をみると、再び、「この中に女の人がいる」と言った。そう言われても、昔のような動揺は感じない。私は少年に問いかけた。
「この中に女の人がいるの」
少年はこっくりとうなずいた。
「でもこんな中にいたら生きていることができないじゃないの」
少年は笑窪を寄せた。
その時、後ろから声がした。
「そこに死んだ女の人はいない」
その声を聞いて、わたしはぎくっとした。
もう一人、少年が丘に登ってきた。少年の顔を見て私は焦燥感を覚えた。今度こそ、私の脳にあの少年が戻ってきたのである。昔、コンクリートの中に埋まっていた死体を見つける少年だった。着ている物も姿も全く同じだった。
その少年が先に来た少年に向かって、また「死んだ女の人はいない」と言った。
ところが先に来た少年は土饅頭を指さすと、
「女の人がいる」と繰り返したのである。
私は遠巻きに二人の少年を観察していた。どちらも私の脳の中に住んでいるのだろうか。とすれば、どちらの言うことが正しいのだろうか。
私は後から来た昔私の脳に住んでいた少年に尋ねた。
「なぜ、またでてきたの」
少年は答えた。
「この子が嘘を言っているから、でてきた」
それを聞いていた、先に来た少年が、
「嘘じゃない、女の人がいる」と言った。
土饅頭の上に生えている浦島草が紫色の花を大きく揺らした。浦島草は徐々に持ち上がると土饅頭から抜け落ちた。浦島草の根元の塊がぶるぶる震えている。浦島草が抜け落ちたところに亀裂ができた。
土饅頭がぐらぐらと動いた。土が崩れ始めると、一本の白い手が突き出された。生臭い匂いがしてくると、もう一本の手が伸びてきた。ぐずぐずと土饅頭が崩れると、女性が土饅頭から転がりでてきて、上向けになり、やがて腹ばいになった。首を上げた。手足を立てて四つん這いのまま首を私の方に向けた。
どこかで見たことのある女性だった。
「ほら、女の人がいた」
先に来た少年が言った。
「ほら、死んだ女の人はいなかった」
後から来た少年が言った。
先に来た少年は生きている女性を見つけ、後から来た少年は死んだ女を見つける力があるのだろうか。よく考えると二人とも言っていることは間違っていなかった。
這い出てきた女性は立ち上がると、服の土を払った。髪の毛に付いた土をはらうと、こちらの方を見向きもせず、丘を下っていってしまった。二人の少年がその後を早足でついていく。やがて姿が見えなくなった。
空虚感に襲われ、私は崩れた土饅頭から抜け落ちた浦島草を拾うと家に戻った。浦島草を庭の隅に植え、玄関の鍵を開けて中に入った。
居間にはいると女がソファーに座っていた。
「あなた、私戻ってきた」
と言って私を見た。
土饅頭から這い出て来た女性だった。
それは私の妻だった。
その時から私の妻だった女は、居間に居続けることになった。私が食事をするときも、本を読むときも、いつも居間から私を見ていた。
私はやりきれなくなり散歩にでる。すると街角だろうが道の脇だろうが、土饅頭があり、一輪の浦島草が生えていた。そこへはかならずあの二人の少年が現れ、同じ問答をした。そして、浦島草を押し退けて女が這いでてきた。私は浦島草を拾って家に戻り庭に植えた。
家の中に入れば必ず妻であった女が居間のソファーに腰掛けて私を見ていた。
毎日毎日、土饅頭から浦島草を拾ってきて庭に植えているうちに、庭は浦島草で埋まってしまった。
もう浦島草を植える場所がなくなった時、昔から私の脳にいる少年が現れた。私に浦島草の庭を指して言った。
「この中に女の人がいる」
浦島草の群が持ち上がった。土饅頭になると、それが崩れ落ちた。その中から、朽ちた人の骨が現れた。
それは、私の妻であった。三花茂看護婦の顔をしていた。いや、フランス文学の私の教え子で、私の妻になった三花茂しおりであった。彼女が死んだとき、私は火葬を拒否したのだ。棺に横たわった彼女の周りを彼女も私も好きだった浦島草で埋めた。三鷹の家に葬りたかったが、それは市に拒否をされた。しかたなく高尾の墓地に埋めた。しかしここに引っ越してきたとき、私は掘り起こして自分の庭に埋めることにしたのである。しおりは動脈瘤破裂であっけなく死んだのだ。子宮にはまだ誰も知らない男の子がいた。それは私の脳によみがえり、死んだ女を嗅ぎつける少年となった。いや死んだのは動脈瘤破裂ではない。高尾の墓地ではなく、始めから庭に埋めたのだ。
振り向くと友人の垂氷が白くなったひげを生やしてニコニコと笑っていた。
「諸衣、もう一度私の病院にくるかい」
私は首を横に振った。
「浦島草のあるこの家で死ぬつもりだよ」
「奥さんが眠っているのだものな」
「それに、君だっている」
私はそう呟いて浦島草で埋まっている庭を見た。
浦島草の庭
私家版幻視小説集「お化け草、2018、一粒書房」所収
木版画:著者


