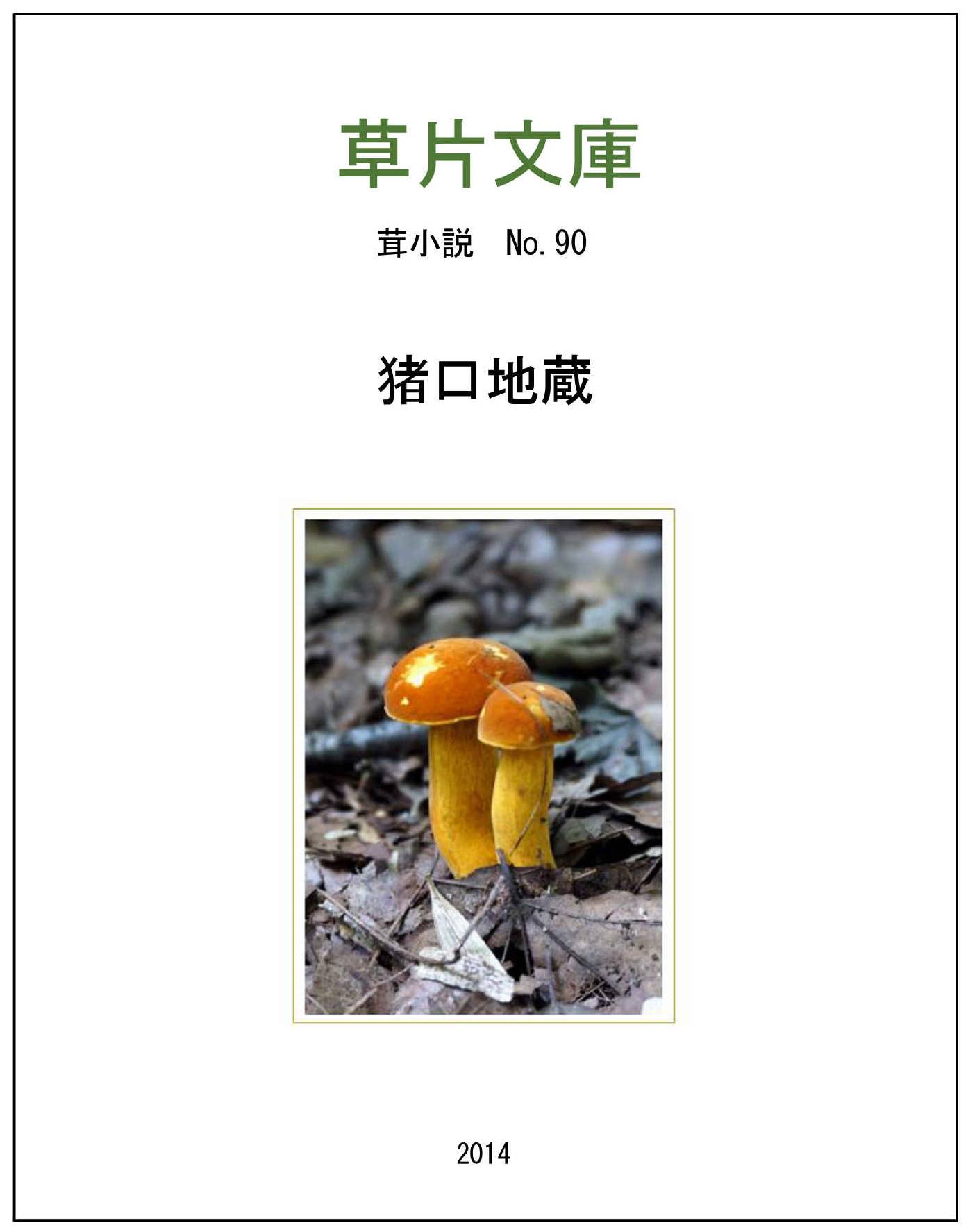
猪口(いぐち)地蔵
猪口(いぐち)長屋に住む左吉のかみさん、花のからだがいきなり動かなくなり、なにもできなくなった。目は寄目になり、一言も言葉がでない。これは狐でも憑いたかと、佐吉は拝み婆(ばばあ)の藤ばあさんを呼んだ。藤ばあさんのいうことには、からだのためではないようだ、やはり何か憑いているという。それでばあさんは夜通し拝むという。
猪口長屋の一角に小さな地蔵がある。猪口地蔵と呼ばれていたが、いつからおかれているのか誰も知らない。猪口長屋が作られるより遙か昔からあったそうで、周りに長屋が造られ、木戸番がおかれたことから、地蔵も取り込まれてしまったようである。しかし、誰彼といわず、長屋に住むものはその地蔵さんを大事にしており、何かあると地蔵さんにお願いする。地蔵の周りはいつも綺麗に掃除され、お供えものがあった。
藤ばあさんは猪口地蔵の前で、花が元に戻るようにと、曲がった腰をもっと折り曲げ、一晩中拝み続けた。そのお蔭かどうか、日が昇る頃になると、花が立ち上がり、朝食(あさげ)の準備を始めたということである。
猪口地蔵の社の中の石の地蔵さんには、胴体の上にはあったはずの首が乗っていない。首無し地蔵である。猪口地蔵についてはいろいろな噂があり、大変なご利益があると信じられており、長屋の者ばかりではなく、町の者も何か心配事があると願をかけに長屋までやってくる。
猪口長屋のある津村の地は、大名が山際に城を作ったことから発展した町で、城主は津村高堂という。若い頃江戸で修行をしてきたこともあり、江戸のつくりに似た町をこの地につくった。民を大事にする良い殿様であった。
佐吉の女房がおかしくなった頃、津村城の中でも病人がでた。高堂の娘、綾姫の食が細り、次第に痩せてくるという病にかかった。からだのどこが悪いというわけではなく、食べ物に興味を抱かなくなってしまったのだ。薬師は少しでも食物を口に入れてもらおうと、あらゆる手だてを施したのだが一向に良くならない。
「異国の薬を探して参れ」
殿の命をうけ、家来が薬を探しに遠くは九州の長崎まで旅をして、南蛮の薬というものを持って帰った。一時効を奏し、それを飲んだ姫は少しばかり食物を口にするようになった。綾姫の皮ばかりだった顔が少しばかりふっくらしてくると、殿は大いに喜んだ。ところが、それもつかの間、姫は再び食べなくなり、またもや痩せ始めた。いくら南蛮の薬を服しても、食べ物がのどを通らず、水しか飲まなかった。
「殿、何か悪き憑物がおるのではありますまいか」
家来の言葉に陰陽師を呼んだ。ところが、陰陽師も、「姫の周りに、悪戯をするものがいる気配は致しませぬ、他に根ざすものがあるかもしれませぬ」と匙をなげた。
殿は寺から僧侶を呼び護摩をたき、それでも埒が明かず、神社から神主を呼んで祈祷を行なわせた。その時、神主が白峰山の頂上にある白峰神社にお百度を踏むことをすすめた。殿はその神主から詳しく話を聞いた。藁にもすがる思いの城主はいかなることでも試みるつもりでいたのである。
「大宮司どの、私は仏教徒であるが、それでも効き目はあろうか」
「殿様、日本の神はそのようなことを問うたりはいたしませぬ、本心から願うものであれば誰であれお聞きくださいます」
「そうか、それにもう一つある、儂自らお百度を踏みたいと本心から思うのだが、今民のためにせねばならぬことがあり、気持とからだをそれだけに奉げるわけにはいかぬ、誰ぞに頼み申したら神は承知してくださらぬのであろうの」
「いえ、神はすべて見ておいでです、殿様がこの地の住人に大事なことをなさっていることをお知りです、誰でも良いのですが、殿様の血の繋がりがおありの方ならばより良いと存じます」
それをそばで聞いていた、姫の兄、大堂が言った。まだ十一だが、殿に似て頭が良く、将来を嘱望される君である。
「私がまいります。綾のためにお百度を踏みます」
それを聞いた城主は喜んだ。
「大堂たのんだぞ、大宮司どの、誰ぞ供をつけてもかまわぬかな」
「もちろんでございます。跡継ぎ様になにかあったら大変なこと、神はご存じです」
そのようなことで、朝早く大堂と力のあるお供の者二人が、白峰山に登ることになった。白峰山への道のりは長い。城から山の麓までは二里ほどある。しかも麓から神社のある頂上までは、険しくはないが、うねった長い道を登らなければならない。
十一にしかならない大堂にとって、大変な苦行であったに違いない。始めたのは夏の終わりであるから、百日というと師走になる。それでも大堂は毎日、率先して白峰山に登った。
その間、妹の綾姫の様子は安定し、食はいまだ細かったが、前より少しは食べ物が喉に通るようになった。
登り初めてから一月ほどたった頃である。大堂が林道を歩いていると、昨日来たときとうって変わって、周りがにぎやかに思えた。
「今日はやけに茸がたくさん生えておる、これは食えるものか」
「はい、猪口と申す茸にございます、美味い茸でございます」
「そうか、茸には体によいものがあると聞くが」
「確かに、茸には滋養と薬効がございます」
「綾姫にはどうであろう」
「私にはわかりかねますが、城の薬師に尋ねるのが良いと存じます」
その帰り、たくさん生えている猪口をいくつか採った。
大堂は城に帰って薬師にたずねた。
「おお、若様これは見事な猪口、旨いだけではなく、滋養に富み、からだによい物でございます」
「綾姫にどうであろう」
「それはもう、よいことでございます」
「何と申す茸か」
「町の衆はただ猪口と申しておりますが、花猪口の仲間かと思われます、まだ名前がございません、若様が名前をつけたらよろしいかと存じます」
「綾猪口にしよう、白峰山に登る楽しみが増えた。毎日採ってまいる」
「それがようございます、大堂さまがお採りになったもの、おいしく作れば綾姫様もきっとお召し上がりになることと思います」
綾猪口を柔らかくおいしく煮たものを、綾姫が少しではあるが口に入れた。それはみなが喜んだ。それも弾みになって、大堂は病になることもなく、毎日元気に白峰山にお参りにいった。
師走に入ってすぐの、あと三日でお百度という日であった。大堂が冷たい風に吹かれて白峰山に登っていくと、人の頭二つほどの緑の石が道添いに生えている樫の木の根本に埋れているのに気が付いた。下草が枯れたことで地表に顔を出したようだ。
「あれはなんだ」
大堂が指を差し、供の者に尋ねた。
「はて、ずいぶん古そうな石ですが、何でございましょうや、表面に苔が生えておりまする、長い間ここにあったのでございましょう」
供の者が枯れ枝を拾い、石の周りをほじくった。出てきたのは傘のような形をした石である。ひっくり返してみると、真ん中に割れた出っ張りがある。きっと柄のようなものがあったに違いない。
供の者が傘のような石を持ち上げると、大堂が驚いたように言った。
「これは猪口の傘に似ておるのう」
「おお確かに、若様、これに柄がついていればまるで、綾猪口のようでございます」
「これは何かの縁かも知れぬ、もって帰ることにしようぞ」
「はは、持ってまいります」
かなりの重さの石であったが、力に自信のあるお供の侍にとってたやすいことであった。
城に戻ると、石は洗うために厨(くりや)の水洗い場に持ち込まれた。供の侍が下働きの男に洗わせると、緑色の苔がすべて流され、まさに大きな猪口の傘になった。
それを見ていた、飯炊きのために雇われている下働きの町の女が呟いた。
「この笠石は、私らの長屋にある地蔵にのせたら似合うになあ」
家来がそれを聞いてもなにも気にとめなかったのは当たり前である。
「あの石を持ってきてくれまいか」
大堂がお付の者にいうと、洗ったばかりの石が部屋に運び込まれた。
「綾猪口の傘に似ていると思うが」
「はいさようで、だが、なにをする物かわかりませぬ」
「面白いから、この部屋に置いておいてくれ」
「はい若様」
茸の傘のような石は座布団の上に置かれた。
それから三日後、大堂のお百度参りは無事終わった。綾姫の様態は少しよくなったが、まだ食は細く痩せたままである。
それでも高堂は息子、大堂の百箇日の行をねぎらう宴を大広間で開いた。
「大堂が百日の行を果たし、祈願を無事に終えた、綾姫もよくなるに違いない、今宵は大堂をねぎらい、綾姫の回復を願う宴とする」
いつにもないごちそうが振る舞われた。高堂が綾姫の病を痛む気持ちのあらわれでもあった。
その場に呼ばれていた陰陽師が高堂に申し出た。
「お殿様、奇妙でございます。つい四、五日前はなかった妖気が城の中に立ちこめてございます。ただ、この妖気、姫様には悪いものではなく、病を治す糸口になるやも知れませぬ」
「なに、妖気とな、どこから出ておる」
「それが、大堂様のお部屋の方からでございます」
「そうか、大堂、部屋に参ろう」
殿は立ち上がり、大堂にも一緒に来るように促した。
「皆のもの今日は無礼講じゃ、綾姫のためにも楽しんでくれ」
そう言うと高堂は大堂をつれて陰陽師とともに大堂の部屋に行った。
「やや、これは、石でできた茸の傘でございますな」
部屋に入った陰陽師は座布団の上の石の傘を見てあわてた。
「それは、私が白峰山に行ったときに見つけたものでございます、土に埋もれておりました物を持って帰りました」
「これには、子供の病を治す鬼が住んでおります、ただ、この傘だけでは不十分、胴があったはずでございます、もしそろえば綾姫様ばかりではなく、みなの病を癒してくれましょうぞ」
「そうであるか、それでは白峰山を虱潰しに探すことにいたすぞ」
次の日から手の空いた者は白峰山の林の中をくまなく、石の茸の柄を探して歩いた。だがなかなか見つからない。
そんなとき、台所で女中頭に下働きの町女が言った。傘の石を洗うのを見ていた女である。
「わしの長屋に首のない地蔵があるんだけど、大堂様が山から持ってこられた傘がぴったりあうと思うんですがなあ」
「そのような物が花の住んでいるところにあるのかい、どこに住んでおる」
「へえ、猪口長屋でございます」
手伝いの女は猪口長屋の左吉の女房、花であった。
しかし、そのことが上の方に伝わったのは、しばらくたってからである。その女中頭が賄所の侍に綾姫様の食べ物を工夫するように言われたときだった。花が言ったことを思い出した女中頭は猪口長屋の話をした。
「そうか、何故早くに言わぬ、すぐに殿のお耳にいれよう」
それを聞いた殿は、
「なんと、猪口長屋と申すのか、なにか繋がりがありそうな」
すぐさま家臣に地蔵を見てくるようにいいつけた。
何人かの侍が猪口長屋に足を運んだ。
猪口長屋の者たちは間近に見たことのない立派ななりの侍が何人も押しかけたので、驚いて遠巻きにしてその様子を見ていた。
「おお、確かに、大きさといい,大堂様の見つけられた傘が合いそうじゃ」
「どういたそうか」
「石の傘を持ってきて、かぶせてみたらよろしかろう」
それを聞いた陰陽師が首を横に振った。
「いや、それでは、城から妖気がなくなってしまう、この地蔵を城に運んだほうがよろしかろう」
「では、そうしよう」
侍たちは、あれよあれよという間に地蔵を抱え、長屋から持ち出してしまった。
それを見ていた藤ばあさんが、「なにをするんじゃ」と追いかけたが、侍は何も言わず運んでいってしまったのである。
地蔵を城に運ぶと、殿は座敷に据えさせた。
「大堂が白峰山でみつけた猪口の傘を乗せてみよ」
笠は猪口地蔵にぴたりとはまりとれなくなった。
陰陽師は驚いた。
「殿、この地蔵に棲んでいた鬼が生き返りました、病を治すのに懸命な鬼でございます、この鬼に綾姫様の病を癒すよう祈祷をいたしましょう」
それから十日にわたり陰陽師は地蔵の前で火を焚き祈った。
高堂は白峰神社の宮司を呼ぶと、その地蔵の言われをたずねた。
宮司は「定かではありませぬが、昔からの言い伝えがございます」と話始めた。
むかし、白峰山に住んでいた木こりの娘が、得体の知れない病に冒された。木こりは何とかして娘の病をなおそうと、力の限りを尽くして薬を手に入れ、高名な薬師にみてもらい、滋養の多い物を食させたがらちが明かなかった。まさに綾姫と同じ状態である。そのようなとき、木を切っていた山の奥に、茸の形をした石が落ちていた。木こりはそれを引きずって住まいに持って帰ると、なれない道具を使い、茸のような石を地蔵の形に仕上げた。木こりはお手の物の木を使って社を建て、地蔵を安置し、祈願を欠かさなかった。それが奏したようで、娘の病気は完治した。木こりは娘のからだのために山の家をすて、里におり、農業を営むようになったそうである。そのあとも離れた山の地蔵参りを欠かすことなく、死ぬまで続けたということである。しかし、その後の地蔵の在処はわからなくなっていた。地蔵のからだは誰かわからないが、白峰山でみつけもって帰り里に祀ったということであった。大昔の話である。
高堂はうなずいて、「綾姫にも恩恵をこうむりたいものじゃ」と言った。
陰陽師の祈祷が終わると、綾姫の頬に赤みが差してきて、食事をとるようになった。
高堂の喜びようはなかった。
猪口地蔵のことを伝えた飯炊きの町の女にも、何なりとほしい物を言うようにと、褒美を与えようとした。
花は女中頭に言った。
「わしは、あの地蔵様に救われました。長屋では地蔵が居なくなったことで、皆寂しい思いをしております、私どももお参りができませんでしょうか」
女中頭はその言葉をそのまま伝えた。
高堂は「迂闊であった、自分の娘のことばかり考えておった、まず町民の暮らしを考えねばならぬはずであった、町の者たちにはすまぬことをした」と、家臣に命じ、猪口長屋の入口に、小さくも心のこもった社を建て猪口地蔵を返した。
「儂等もここに詣でることにしたい」
こうして、秋の茸の季節になると、必ず城主をはじめ城の面々が、猪口地蔵に詣でることになった。その日は、長屋どころか、町中が賑わいをみせたという。
時が経つにつれ、猪口長屋を囲むようにして、薬屋、食物屋、衣服屋ができ、国中から病気回復の祈願に人が訪れるようになった。左吉と花が開いた猪口茶屋では、綾猪口の雑炊が健康によいとの評判で、人を雇うほどの繁盛をしたという話である。
猪口(いぐち)地蔵
私家版第六茸小説集「茸童子、2020、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2016-9-6


