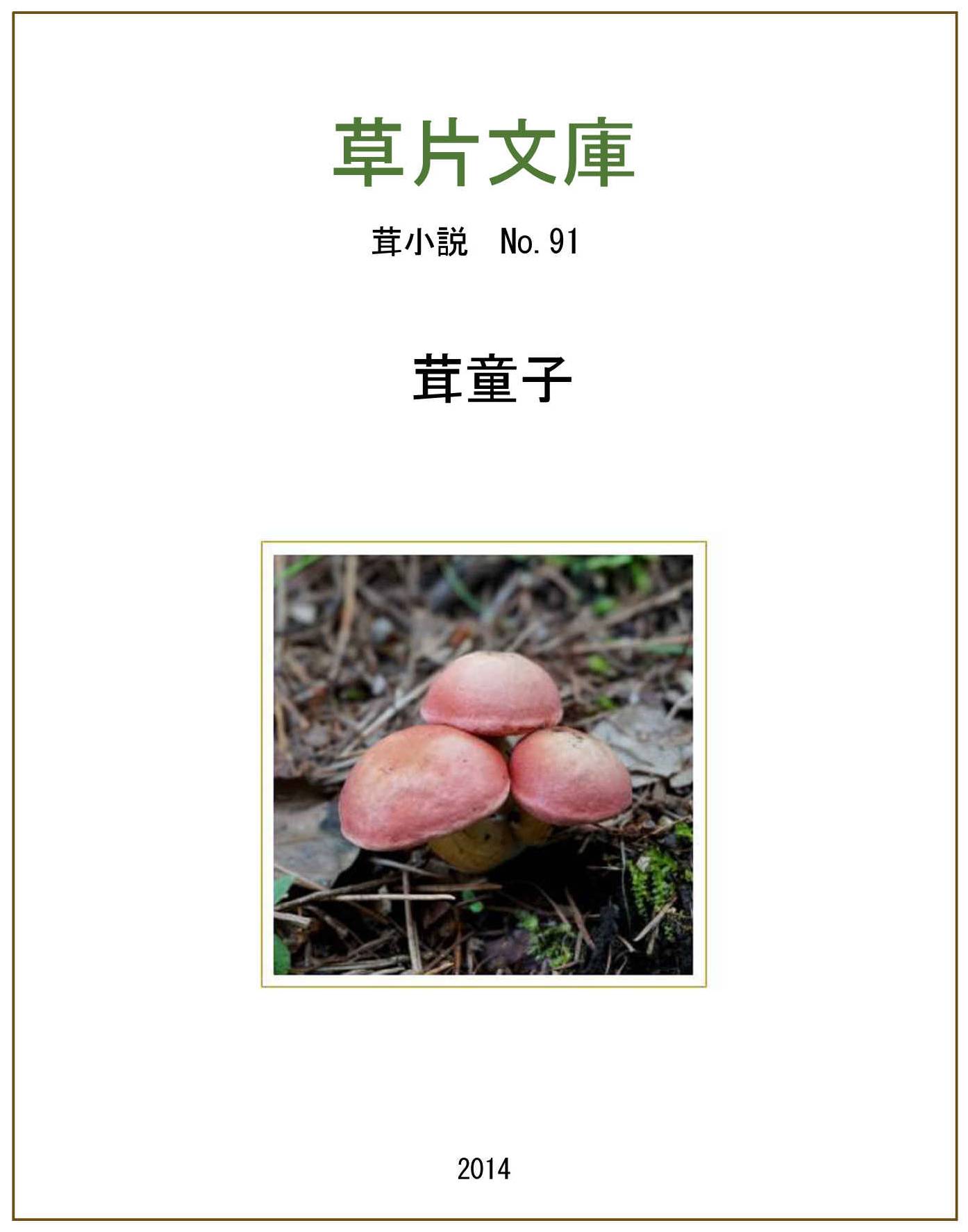
茸童子
「この夏は暑いのう」
「おお、そうだな、それより今日出おったぞ、儂の家にも」
右京が帳面をつけながら刀衛(とうえ)に言った。
二人とも、神瀬(かみせ)城の勘定方である。
「お主の家(うち)でも出たのか、儂の家ではほんの数日前に出た、やはり、床間から出おったのか」
「いや、厠だ」
「時はいつだった」
「それが、日の中(うち)なのだ」
「それで、そいつは屋敷から出(いで)ていってしまったのか」
「いや、床間の隣の押入に入った」
「それはよろしかったな、家の内におればよいわ」
ここの処、この町では座敷童子(わらし)の話で持切りなのである。座敷童子が棲むと、その家は繁盛すると言われている。出ていくと、家の家具やらなにやらみんな持っていってしまい、その家は没落するという。
「なにゆえ、このごろ座敷童子が姿を現すのであろうかな」
「うむ、なにか騒ぎでもおこるのではないか」
「だが、城の方ではさしたる気配はないが」
「そうよのう、器量のよい世継がおり、辺隣(あたりとなり)とは上手く向かい合っている、どこにも火種はない」
「うむ」
座敷童子ははじめ町人(まちゅうど)の家に出た。黒い顔をした御河童頭の男の子で、菰(こも)を身にまとっていた。大商人の屋敷にも、掘立小屋にも出て、ただ歩き回ったり、天井裏でがさがさと捜物をしたりして、一日か二日たつと、現れなくなった。しかし、噂のようにそれらの家が没落をするとか、裕福になるとかいった変化はなかった。
それが、近頃、武士の家にも出るようになったのである。
「いかで儂等の家に出るようになったのであろうな」
「わからん、城にはいないという」
そんな話をして、時をおかず城にも現れた。天守閣をはじめ、二の丸、三の丸、詰所、どこにでも座敷童子がいた。お城の中で行われていた評定のさなかに、いきなり殿の前を黒い髪を長く垂らした座敷童子が横切った。危うく守りの侍が刀を抜くところだったが殿がそれを押さえた。
「座敷童子どの、どうぞ自在になさってくだされ」
殿が声をかけると、座敷童子は振り返り、殿に微笑んだ。
座敷童子が壁の中に消えていくと、殿が集まっていた家来たちに言った。
「そちたちも座敷童子を大事にせい、童子たちは家のなかの悪い気配を吸い取ってくれるのじゃ」
家来たちはそういうものかと頭を垂れた。
「じゃが、このところたくさんでよるわ」
「殿、城の中が悪しきもので満たされてきたためではござりませぬか」
「うむ、そうかもしれん、そう思い、陰陽師を呼んだのだが、鬼の気配はないということだ」
「そうでございますか」
秋になると、町の家々から、ぱったりと座敷童子の影がなくなってしまった。もちろん城の中にも出なくなった。
「殿、座敷童子は何故あの暑い頃に出てきたのでございましょう」
「わからぬな、爺はどう思う」
「よい方か、悪い方か考えいたしておりましたが、座敷童子の世に何か起きているのではないかと思うようになりました。しばらくするとその有様が見えてくるのではないかと思います」
「我町に何か起きると申すのか」
「わかりませぬ、良きことかも知れません」
秋の長雨が続き、それも終わると、天高く青空が広がり、心地よい日が続くようになった。
その頃、城の一室では真っ赤な物がピョコピョコと板の間で動いていた。
女中がそれを目撃し家老に伝えた。
「ご家老様、赤い座敷童子が飛び跳ねております」
「なに、座敷童子が再び現れたとな」
家老は女中の言う部屋をのぞいた。
床間に真っ赤な童が立っている。ところが、よく見ると真っ赤な茸であった。
殿がよばれ、部屋にはいった途端、ぴょこんと掛軸の裏に消えていった。
「妙じゃな、黒い童子がおらなくなったと思うと、赤い茸が現れるとはな」
「はい、あらためてみなければなりませぬ」
やがて、城の中いたるところで、真っ赤な茸がピョコピョコと飛び跳ねるようになった。そうこうしているうちに、赤い茸は町中にも現れた。右京や刀衛の家でも床の上で跳ねている。童子と反対に城から始まり巷に広がったのである。
「右京、いったいあれはなに者ぞ、儂の家では赤い茸がぽこりと畳から顔を出すと、畳の上を飛び跳ねて、今度は天井に昇り、欄間の中に消えていったぞ」
「そうか、儂のところでは、厠から現れおった、お主のところは前の座敷童子が厠であったな」
「ああ、だが何で茸なのだ、赤い茸がなにしに我々の屋敷に現れるのだ」
「奇妙奇天烈、あれは茸ではないのではないか、座敷童子が姿を変えただろう」
「どうしてそう思う」
「どうしてといわれるとわからぬが、茸は動かぬ」
「姿を変えたのではないのかも知れぬぞ、座敷童子が赤い茸に家を明け渡したのかも知れぬ」
「どうしてだ」
「いや、儂もわからぬ、座敷童子はもうご隠居になったのだ」
「座敷童子が隠居すると、赤い茸が代わりになるのか」
「うむ、全くわからぬ」
しかし、右京と刀衛の話していたことは、当たらずとも遠からずといったところであったのである。
「殿、菩提寺の縁上和尚の言うことには、座敷童子は家の守り妖怪、妖怪といっても、その世界にはそのならいがあり、妖怪になるには、仏になった男の子の、しかも、長男でなければならぬそうでございます」
「それで、どうして、あのように、一時にたくさん出て、消えてしまったのじゃ」
「和尚が申すには、閻魔に呼び戻されたのではないかということでございます」
「どうしてじゃ」
「閻魔様はこの世の安定のためにおられる方、今の太平の世に座敷童子の役割はあまりないと思われたのではないかということでございます」
「それで、座敷童子はどこに行ったというのだ」
「無事がおとずれておらぬ異国に、その国にみあった妖怪として働いておるのではないかということでございます」
「それで、なぜ、赤い茸が現れたのであるか」
「和尚が言うには、これから、そのわけが判るだろうということでございます」
「それはどういうことか」
「赤い茸が家にいる間はわかりませぬが、家から離れたとき、その家がどのように変わるか見ておればよい、ということでございました」
「なるほど、そうか」
「それに、今は茸だが、やがて、童の姿になることだろうと申しておりました」
やがて町中の家に赤い茸が溢れた。
右京の家は町の山際を流れる神瀬川の脇にあった。そのあたりは城に仕える者の家が集まっている。神瀬城は神瀬川の山際に建つ天雅な城であった。刀衛の家は川から少し離れており、城勤めの者達に建てられた家に囲まれている。
ある日、刀衛の隣の家から火がでた。真夜中のことであった。風はあまり強くなかったが、乾燥していたことから、あっと言う間に燃え広がっていった。寝ていた刀衛は異様な雰囲気に気がつき、女房の光(みつ)を起して雨戸を開けた。脇の家から火の手があがっている。光に逃げる支度をさせ、自分も支度をした上で、外に出ると雨戸を閉めた。火消し水を汲んで自分の家にかけた。幸い風は反対向きで、火の勢いは反対の方向にむかった。燃えている家の裏の家に火がついたようである。
右京が駆けつけ、水をかけてくれた。舞い上がった大きな火の粉が刀衛の家を越えて裏の家に落ちた。その家は勢いよく燃え始めた。刀衛の家が風下になる。刀衛と右京はそちら側に回って、自分の家に飛んでくる火の粉に水をかけた。火消しがやってきて燃えている裏の家を壊した。そのお陰で刀衛の家には火が及ばなかった。火が収まったのは明け方になった頃である。刀衛は焦げてしまった門の脇の松の木を見上げ、疲れを感じていた。
「右京、かたじけなかった」
「いや、燃えずに残ってよかったな」
「うん、おかげさまだ」
「隣の家のどこから火がでたのであろう」
右京の顔にも疲れが見える。
「火消が竈(かまど)の火ではないかと言っていた」
「だが、何に火が移ったのだろうな」
「それは分からんが、気をつけなければな、茶でもどうだ」
「いや、今日は城に行かねばならぬから、ひと寝入りする、お主もそうだろう」
「そうだな、城で会おう」
右京は家に帰っていった。
その火事で六軒が焼け出された。城からは手厚い見舞いがとどき、仮の宿舎があてがわれたということである。
火事の跡には、刀衛といくつかの家がぽつんぽつんと焼け残っていた。ちょっと不思議な光景である。
その日、刀衛が登城すると、広間に家来衆が集まっていた。
「昨日、茸を喰った、なかなか旨いものであった」
「ああ、捕まえるのに苦労したが、俺はゆでて喰った、なんと旨いことよ、松茸どころではないなあ」
「俺は、焼いて喰った。酒がすすんでなあ、それで、寝込んでしまっていたら、竈から火がでてしまった」
そういった男は刀衛の隣の家の狭間四郎だった。
「四郎殿、大変であったな」
「あ、刀衛殿、申し訳ないことをした、だが、お主の家に火が飛ばなんでよかった」
「おかげさまで、四郎殿、ご家族は無事ですか」
「みな大丈夫だ、殿が焼けた家をすぐ普請するようにと、手配をしてくださるそうだ、本当に良い殿に仕えたものだ」
「そうですな、ところで、茸を喰ったという話をなさっていたが」
「そうなのだ、仲間の話しの中であの茸を捕まえて喰ってみようということになってな、昨夜はそれで一杯やっちまって、あの始末ということだ」
「あのぴょこぴょこ動く茸を捕まえるのは容易ではないのではござらぬか」
「儂は袋をかぶせて捕まえた」
「畳の中に消えてしまいませぬか」
「それは素早くやらなければならぬな、幾度か失敗しましてな、それでもあの茸は畳から顔を出したので、捕まえることができた、袋の中でもごもごしているところを首根っこをつかんで、焼いちまいました」
「そうだったのですか、食べることができるとは思いませんでしたな」
そばで聞いていた台所番の若い侍が四郎に声をかけた。
「殿に食べさせたいほど旨いものですか」
「それは旨い、殿も喜ばれるだろう」
「それでは正月の殿の膳にだそう」
台所番は言った。
それから町の家には必ず赤い茸が住むようになった。刀衛の家の中でも赤い茸が飛び回っていた。焼けてしまった両隣の家は、二ヶ月たった年の瀬にはもう新しい家が建ちそれぞれの家族が戻ってきたのである。
ところが年が明けた一月二日、また四郎の家から火がでた。火は瞬く間に広がり、刀衛は前の時と同じように消火に精をだした。寒空の中、前と同じ六軒と、新たに二軒の家が焼けてしまった。
今度も焼けずに残った家の門の前で、刀衛はやはり手助けに来た右京に言った。
「奇妙だ、また我が家は助かった、新しくなった家が全部燃えてしまった」
「火もとはまた四郎殿の家か」
「そうだ、やはり竈から火がでたそうな、しかも火種はなかったはずだと、四郎殿は申しておった」
「それは確かに奇妙な」
「それでな、おかしいと思い、焼けた家を調べてみると、赤い茸を喰った連中の家だけが燃えているのだ、四郎の話を聞いて、新たに二人が赤い茸を喰ってしまったようだ、その家が燃えている」
「ということは、あの赤い茸は家を火から守っているのではないか」
右京が言うと、刀衛は「あっ」と納得して、「城に行って、御老中に伝えなければならぬな」と、あわてて登城の支度をしに家に入った。
「儂も用意していく、御門の前で会おう」
右京も刀衛の考えたことに気がついて家に戻った。
城の門の前で待ち合わせた右京と刀衛は門番にことを告げ、御老中に会いたいことを申し伝えた。二人はすぐに通され、控えの間でちょっと待った。
老中が直々に部屋に入ってくると、
「なんぞあったか、急ぎの用とは、また火事になったと聞くがその方たちも焼き出されたのか」
のんびりとしたいつもの口調。
刀衛は、平伏したまま、ことの次第を説明した。
「なんと、あの赤い茸が火から家を守る妖怪とな、昨日、御膳に焼いた茸がでたが、偉く旨いものであった。用意した者が天守閣の中で捕まえたと言っておったが、もし火から城を守っていた茸たちだとすると大変なことじゃ」
「その通りでございます、今日の夜、火がでませんように、見回りをきつくお願いいたします、殿様には城からお離れになった方がよいと存じます」
「ふむ、考えておこう、ご苦労であった、万全を期すことにする」
二人が下城すると、家老は縁上和尚を城に呼び寄せた。
「縁上殿、今、家来が二人して急を訴えに参りました、赤い茸は火から家を守る大事な妖怪、昨夜の火事で燃えた家は、以前も火事で燃えており、その主はみな赤い茸を捕まえて食した者と申しております、いかがお考えになりますかな」
「ふむ、寺にも赤い茸が現れております、なにをするわけではなくピョコピョコと動き周り、座敷童子とはずいぶん異なったもの、だが、その侍が申すことは理にかなっております、赤い茸の役目が見えてきましたな」
「すると、茸が家を火から守っておるということになりますな」
「そのようなことを書き記したものはないが、なにが起こるか知れたものではない、閻魔が茸を童子として使いによこしたとておかしいこともありますまい。あの赤い茸が座敷童子になるやもしれませんな」
「とすると、今日、我々は赤い茸を食してしまいました。火事になるかも知れませぬ」
「用心にこしたことはありません」
「では、今日は殿に寝所から出ていただき、別の棟でお休みいただいたほうがよいのでしょうな、本丸から火の気を絶つことに致しましょう」
「それがよいと思われます」
ということで、その晩、殿をはじめ奥方様、お子様は本丸から離れたところでお休みいただいた。
家老をはじめ多くの家臣が寝ずの番についた。
天守閣には鼠一匹すらおらず火の気は全くなかった。
冴え渡った寒空に星が瞬いている。
真夜中のことである。番をしていた一人が空を見上げて大声を上げた。
「火の玉だ」
夜空にいきなり月より明るい物体が輝いた。
「大変だー、火の玉が落ちる」
その声で、皆外に飛び出した。そのときにはすでに赤い火の玉は天守閣にぶつかり天守閣はメラメラと燃え上がった。
「殿、お逃げくだされ」
家老の声が聞こえる。
殿は家臣に囲まれ、若殿様は供の者に背負われ、奥方様はお女中方に囲まれて城外にでた。神瀬川にかかる橋を渡って対岸についた。
その時、真っ赤に燃えていた城が崩れ落ちるのが見えた。
火を消すことなどできなかった。
「殿ご無事で」
「うむ、皆、仔細ないか」
「はい、幸いに怪我をした者もおりませんでした」
「茸童子の崇りよの、天罰じゃ」
「そうかも知れません、しかし、二人の家来のお陰で命は助かりました」
「たしかにそうじゃ、縁上に相談じゃ、どのような供養が必要なのか」
「はい考えておきまする、殿、今日は城下の下屋敷の方でお休みください」
「みなもそうするがよい」
「はい、それぞれ考えておりまする」
「それに落ち着いたところで、このことを伝えにきた二人に褒美をとらせねばのう」
「そうしていただければ幸いです」
縁上上人は殿の前で話をしていた。
「前にも申しましたように、このようなこと、今まで起きた記録はございませぬ、二人の御家来が申したように、火の粉を払い、家を守る大事な妖怪に違いがございません。ただ何故人間などに捕まって食されたか、不思議でございます。赤い茸はまだ妖怪になっておらず、茸の本性が抜けていなかったのかもしれませぬな、閻魔様に赤い茸が次の屋敷童子に選ばれ、そうなろうとしているところなでしょう。それを食うてしまわれた。閻魔様とて、なかなかお気持ちを和らげてくださるとは思われません。その証拠に、茸を食らった御家来の家は、新しくしても燃えてしまいました。その場所には家は建てられないと思います」
「とすると、あそこに天守を建てることは無理ということじゃな」
「はい、お城は新たに起こした方がよいと存じます。も少し川の上流に、新たな城を築かれ、今のところには、茸童子を奉る社を建て、年に一度は祭祀を行なうとよろしいかと存じます」
「そうか、城より先に茸童子の社を建てようぞ、町民誰もが詣でることのできるものにせよ、残っている二の丸、三の丸も、町の民の役に立つようなものにせよ、そうだ、童たちの学ぶ場所にせよ、武道の稽古も良いであろう」
「良きお考えでございます」
刀衛と右京は殿に拝謁した。
「刀衛と右京と申したな、このたびのこと感謝するぞ、して、どうじゃ、そなたたちに新しく建てる茸童子の社を守る仕事を頼みたい。二の丸、三の丸は民の童の学びの場にしたい、そちらが子供たちに教えるのじゃ」
「ありがとう存じます、これからも精一杯務めまする、右京は碁に長けております、子供たちに碁などを教えることができます。私は市田流師範でございます、剣の道をお教えできます」
「そうか、それでは、刀衛は二の丸で武を教えよ、右京は三の丸で文を教えよ、それに社の管理もたのむぞ」
こうして、天守のあったところには茸童子殿が建てられ、二の丸は武の丸、三の丸は文の丸として、町の子供たちに解放された。城のあったところは童子の場と呼ばれ、子供たちの教育施設として発展したのである。新しい城は少し離れたところに造られ新たな町並みができた。こうして町は大きくなった。
右京と刀衛は老中格として取立てられ、童子の場で子供たちの指導に当たった。
それから三年、家々の赤い茸は少女の座敷童子に成長し、家を守る役目に就いたのである。
そして八年後、茸童子の社には一人の座敷童子が住むようになった。閻魔に許されたのである。
茸童子
私家版第六茸小説集「茸童子、2020、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野県茅野市 2016-8-3


