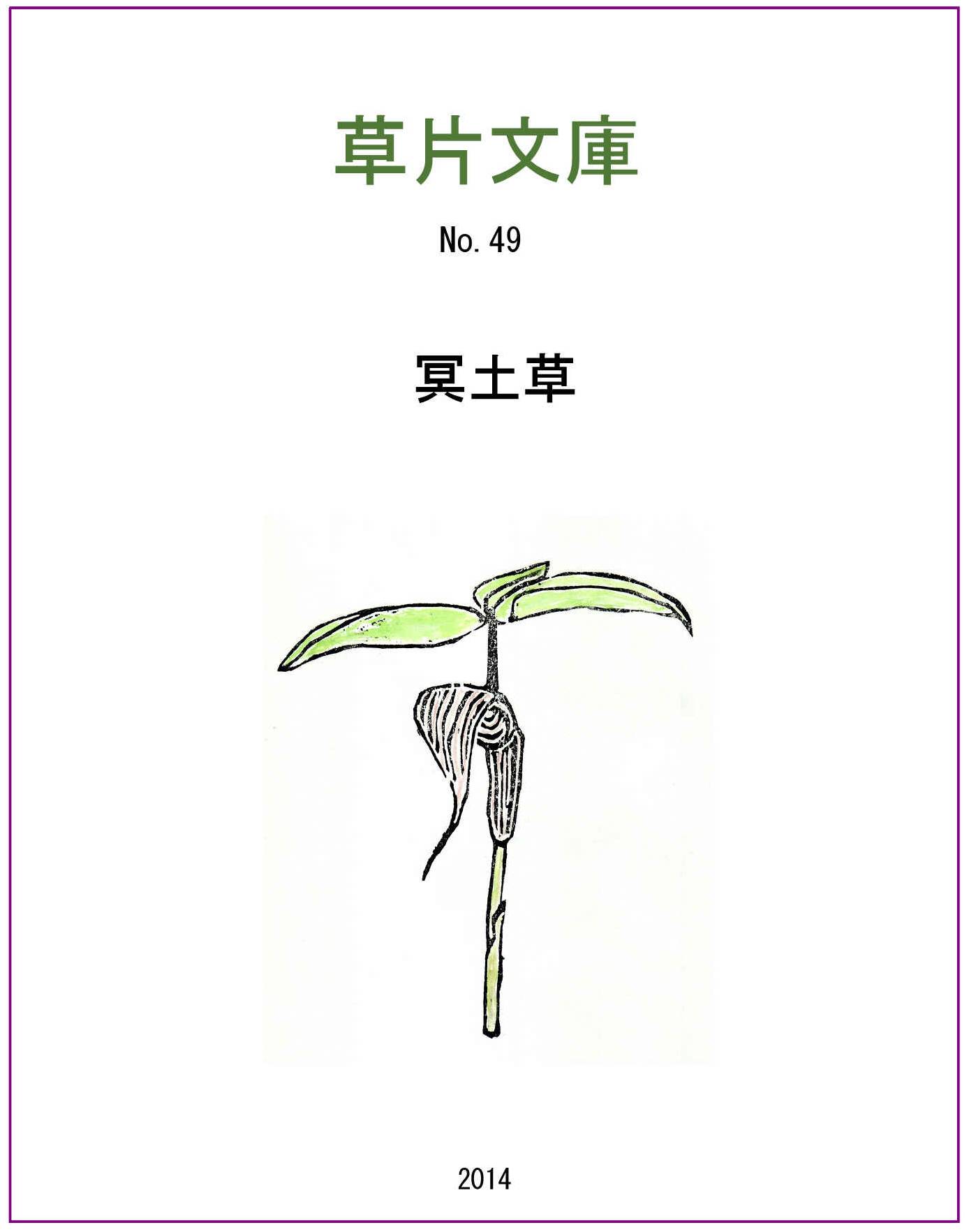
冥土草
八王子の町に住むようになって明日でちょうど一年になる。昨年の四月に都内より越してきた。八王子といっても、中央線や京王線が乗り入れている八王子市街ではなく、高尾山の麓である。木々の多い気持ちの安らぐ環境の良いところであることは確かであるが、私が住んでいるマンションは京王線の高尾山口から歩くと十五分かかる。しかし、緑に囲まれた静かなところで、文章書きにとって、とても落ち着くよい環境である。マンションに住んでいる人たちも退職した夫婦や、勤めているにしても重役出勤のできる立場の人たちで、ゆったりとくらしている風情がある。会うたびに必ず山野草の話をする老人は、高尾山へ毎日散歩に行く。そのとき見つけた草花をスケッチしてくると、家で図鑑と照らし合わせ、名前や学名を絵の下に記入するという日課をもっている。
今日もその人に一階のエントランスで会った。私は駅に向かおうと部屋を出たところで、その老人、岩見さんは高尾山から帰ってきたところだ。
「三村さん、今日はね耳形天南星の私ほどの背丈のものを見ましたよ、それは立派なもので、あの大きさになるまで、いったいどのくらいかかるのでしょう」
彼はスケッチブックを開いて見せてくれたが、そこには黄色の芯を持った天南星が描かれており、隣に自分の姿が輪郭として添えられている。たいして変わらないということは、百五十センチを越えているだろう。
「ほんとうに大きいですね」
「私も始めて見ました、いつも歩いている道沿いにあったのですが、今まで気がつかなかったようです、毎日のように行っているのですけどね、目が遅くなりました」
そう言って岩見さんはエレベーターに乗り込んでいった。
私はマンションを出ると、いつものように駅への道を歩いた。
駅に行く途中の田圃に向かう道と交差している十字路の角に、このあたりにはにあわない、しゃれた佇まいのコンビニ,三葉ストアーがある。その反対側の角に、小さな地蔵堂があって一本の桜の木が植わっている。
いつもちらっと見て通り過ぎるだけであるが今日は目が留まった。
扉の開いている地蔵堂の石の地蔵の前に紫色の花が瓶にさしてある。紫色の花の先から太いひげというか舌が伸びている。浦島草である。岩見さんがスケッチした天南星の仲間だ。誰かが山から採ってきて供えたのだろう。都内では見ることが大変だろうが、このあたりならたくさん生えているに違いない。
その日は神田の出版社に行き、その足で古本屋を回って帰ってきた。それでもまだ四時である。自由業の気楽さである。もう少し遅ければどこかで食事をしてくることになるが、このくらいの時間のときは、三葉ストアーで簡単なものを買って帰ることにしている。コンビニと言っても置いてあるものは馬鹿にならないもので、よほど口が肥えている人はおいておき、自分のようにさほど味がわからない者にはうまいものが多い。チェーンストアーでないのにもかかわらず、品ぞろえも大したもので、一人暮らしには助かっている。
反対側の地蔵を見た。浦島草はストアーの親父が供えたのだろうか。
私はコンビニのドアを押した。いつもは何人かの客がいるのだが、そのときは誰もいなかった。私は何となく和風のものが食べたくなって、大根おろしのかかったハンバーグ弁当を手に取った。決して安くはない、八百八十円の値札が張ってある。それにサラダの小さいパックをとりカウンターに持っていった。カウンターではたまに顔を出す主人が暇そうに私を見ていた。ちょび髭をはやした角張った顔の人の良さそうな男である。
「毎度ありがとうございます、今日はお帰りが早いですね」
主人とは何度か話したことがある。
「仕事が早く終わったものだから」
「物書きさんだと誰かにききましたよ、そうだ、岩見さんだ」
朝会った老人だ。このあたりに知っていることを言いふらしている。
「物書きだけど、流行作家というわけじゃないから、好きじゃなきゃできませんね」
「自由業の人はいいですよ、時間が好きなように使えるから」
「まあそうだけど、遊び癖がつくとすぐ食べていけなくなりますよ」
私は苦笑いをした。今日の主人は話がしたい雰囲気だ。地蔵のことを聞いた。
「地蔵さんに浦島草が供えてありました、ご主人ですか」
「ああ、あれね、わたしじゃないですよ、女の人がもってきて供えていくのですよ、手を合わせて、なんか願をかけているようだねえ、ここのところ毎日のように」
「浦島草というのは面白いですね」
「確かにね、私なんかここの生まれで、小さいころは山に行けばいくらでもあの花は見ることできましたけどね、今はそんなにはないでしょうね、それを毎日新しいものに取り替えていくのですよ」
「ほう、奇特な人ですね」
「しかも、いつも真夜中の零時なんですよ」
夜中だとは思っていなかったので驚いた。
「へー、何を願っているのでしょうね」
「なんでしょうな、うちのバイトの子は気味悪がっていますけどね、私も一度その子が休みのとき、ここから見ましたよ、後ろ姿だけですけどね、黒っぽい長いスカートに、後ろ髪を長く垂らした女性でしたね」
「どのくらい続いているんです」
「もう、二週間以上ですな」
「長いですね、よほど大事な願掛けですね」
「そう思いますよ、真夜中ですからね、いつまで来るのか私も気になってます」
私は払いを済ますと、コンビニを出た。そこから十分ほど歩くとマンションにつく。
私は紀行文を書く旅の作家となっているが、あまり遠くへ行くこと少なく、それでも東北、甲信越にはよく出かける。そこで神社やお寺、裏山の大きな木の前に供え物をして願をかけるという風習にはよく出会った。むしろ都内の江戸の庶民の町だったところには、願掛けの話がたくさん残っている。だが浦島草の類を用いるのは聞いたことはない。
マンションのエントランスに入ると、岩見さんがエレベーターから出てくるところに出くわした。
「今日はよく会いますね」
長い白髪の混じった眉毛を揺らして声をかけてきた。四角い顔に点のようにあるつぶらな目で私を見た。
「そうですね」
「三村さんのご本読みましたよ、日本中旅をされていてうらやましい。歴史のことばかりじゃなくて、植物についてもよく書いておられますね」
「ええ植物だけではなくて、目に止まった動物、鉱物、建物、そういってものをなんでも記録してきます」
「でも、高尾山のことは書いたものを拝見したことがありません」
「昔雑誌にすこしばかりかいたことがありますが、まだここにすんでまだ一年ですし、このあたりのことはこれから書きたいと思っています」
「高尾山にはおもしろい植物があるし、ぜひすばらしいご本をつくってください」
「そういえば、三葉ストアーの反対側の地蔵に浦島草を供えて、願を掛けている女性がいるみたいです、どこの人だかわからないと、コンビニの主人は言っていました、今時願掛けとは珍しいですね」
「ああ、あの女性ですか」
「ご存じですか」
「おや、三村さんも会っているはずですよ、ここの人ですよ」
この言葉にはびっくりした。確かにここにきて一年しかならない、顔はだいぶ知ったが、名前がわかっていないのだろう。
「どこの階のひとでしょう」
「ほら、先生の下の階に背の高い女の人が住んでいるでしょう、たまにここで見かけますよ」
「もしかしたら、色の白い、切れ長の目の、どちらかというと日本風の顔立ちの女性ですか」
「ええ、そうですよ、鹿野(かの)さんというのですが、最近、生まれてすぐのお子さんをなくされましてね、なんでも枕が赤ん坊の顔にかかって窒息死したのだそうですよ、お子さんの名はまちこちゃんと言ったかな、女の子でね、忍さんの不注意だと、旦那さんは離婚されましてね、かわいそうな境遇です」
「忍さんというのはどなたですか」
「あ、鹿野忍さんというのです、みなさん忍さんと呼んでいますよ、きっと、そんなことで、願をかけているより、供養なさっているのかもしれませんね」
「そうだったのですか」
「浦島草で供養というのは不思議な感じですね、浦島草にはなにかいわれがあるのでしょうか」
「さあ、私はしりませんね、本人には意味があるのでしょうな」
「高尾山には浦島草がたくさん生えているところがあるのですか」
「珍しくはないですね、だけどたくさんあるところは知りません」
「いや、ありがとうございました、散歩に出かけるのにお引止めしてすみません」
「いや、散歩じゃないのですよ、あのコンビニに買い物に、それじゃ」
岩見さんは元気に外に出ていった。
それから二、三日後のことであった。夕刻、買い物に出ようとエントランスまで降りると、忍さんが浦島草を三本抱えて外から帰ってきた。
うつむき加減で、人と顔を合わせたくないような雰囲気である。その彼女がふっと私の方を向き目が合った。
赤っぽい目をしている。だが、充血といった様子ではなく、そうモディリアニの女の青い目を薄赤くしたような感じである。
どきっとして声をかけてしまった。
「浦島草ですね、珍しいですね、どちらから採っていらっしゃったのですか」
彼女は立ち止まって考えるような仕草をした。
「あ、失礼しました。私は八十八号室の三村と申します、旅行記事などを書いています」
彼女はちょっとほっとしたような顔をした。
「七階の鹿野です。前の道を左のほうに歩いて三十分ほどのところに神社がありますの、その後ろの森に群生しているところがあります」
「浦島草を飾る方は珍しいですね」
「そうですか、この仲間の雪持草はお茶花ですわ」
「私は越してきてまだ一年ね、その神社にまだいっていません」
「きれいなところです、前の道を駅とは反対の方にお歩きになって、しばらく行きますと畑や田圃の中の道になります、そこから山裾に行って、道なりに歩くと神社の赤い鳥居が見えますのですぐわかります」
「ありがとうございます」
私が礼を言うと、彼女は軽く頭を傾げエレベーターに乗った。
買い物も急ぐわけではないので、駅とは反対に行ってみることにした。そちらの方にはなかなかいく機会がなかった。旅行作家にしてはあまり歩き回って、何かを捜すというようなことをしないほうだ。横着である。電車旅行はよくする。乗り物におんぶした作家ということになるだろう。スポーツが得意ではないのと、面倒くさがり屋ということにつきる。
少しいくと道沿いの建物が途切れ、周りは畑になった。畑の先は高尾山に連なる山際になる。
畑に植わっているものを見ながら歩いて行った。ネギが植わっていると思えば、ナスやトマトが植わっていたり、ひなげしが植わっていたり、雑多な様相を呈している。しじみ蝶が私の前を飛んでいく。
ときどき、軽自動車がすれ違うが、車はほとんど通らない。自転車に乗った人が通る程度である。道幅があまりないことと、同じ方向にいく幹線道路が駅から伸びていて、トラックやバスはそちらを通る。
用水路の橋を渡るとその先は田んぼの中を通る道になった。そこから少し行ったところで田を横切る農道に入り山際まで歩いた。山際に沿って人がやっとすれ違えるほどの細い道がある。片側は田んぼ、山際は木が生い茂っていて、ところどころに大きな農家がある。
道なりに行くと急に曲がり、その角に一軒の農家があった。農家の広い庭を横目に通り過ぎたところで赤い鳥居がいきなり現れた。
鳥居に止まっていた鴉が私に気がついたらしく、あわてて飛び上がって飛んで行った。鳥居に井草神社とある。
鳥居の先は石段に続く。見上げると、さほど高くないところに社殿の屋根が見えた。登っていくと石段の脇に何本かの蝮草が顔を出している。これも天南星の一つで、浦島草の仲間である。天南星にはよほど適した環境なのだろう。
石段を登りきると、背の高い杉の木に囲まれた境内が現れた。静かだ。社の入口脇にある大きな石碑には青磁色の地衣類がこびりついている。かなり古い神社だ。賽銭箱の前に垂れ下がる鈴を揺らす綱は換えたばかりと見えて、歴史を感じさせる社の肌あいとは不釣り合いにさわやかに輝いている。
境内の裏は山林と続いており、そこを登っていけば、緑の散策を楽しめそうだ。社の後ろにまわってみると、案の定、細い上り道が林の中へと続いていた。
社の周りを一巡したが、よく手入れをされていて、ごみが散らかっていない。礎の周りの乾いた土の中にはたくさんのスリバチ状の穴があった。あり地獄だ。
私は再び社の後ろに回り、林の中に向かう道を上った。林の中には薄日が射し込み、羊歯が大きな葉をのびのびと伸ばしている。ところどころに蝮草が花をつけ蝮の肌そっくりな模様の柄を伸ばしている。いろいろな方向を向いてまるで獲物を待つ蛇の鎌首だ。そこに浦島草は見当たらない。
道をさらに上っていくと、斜にいくわき道があった。その道を歩いていくと、広々とした空間がひらけた。高い木々に囲まれた草地だ。草の匂いが強くなる。見渡して驚いた。そこには数え切れないほどの浦島草が群生していた。忍さんの言ったのはここのことだろう。浦島草は長い舌を地面に届くほど延ばし、自分を覆う傘のような葉に絡みついたり、シダの葉に巻き付いたり、好き勝手な方向を向いている。
私がその見事な浦島草の群に足を踏み入れたようとした時である。群の中程で浦島草の花がわさわさと動いた。動物がいる。
足を止め、目を凝らしていると、すっくと真っ黒な生き物が立ち上がった。
背筋がぞくっとした。なんだ。
真っ黒な顔の人間だった。
黒い顔の人間が頭を振った。白い女の顔が現れた。顔にかかっていた長い黒髪が脇に振られたのだ。
女の赤い目が私を見た。
忍さんかと思ったほどよく似ているがそうではない。
女は俯いて両手に抱えている手の中のものを見た。
再び顔を上げたとき私に気がついた。女は表情をかえず私から目をそらすと、口元に笑いを漂わせ身をかがめた。その一瞬、女は浦島草の群落の中に吸い込まれ消えてしまった。
気が付いた時には誰もいなかった。何が起きたのか自分でも分からなかった。
浦島草の群の中からかさかさと音が聞こえ、女がいたところの浦島草の花が揺れはじめた。揺れは移動して山の上方に向かい、浦島草の途切れたところから真っ黒な大きな動物が現れた。てっきり女性だと思っていた私はまた頭が混乱した。見ている間に黒い生きものは林の中に消えていった。
しばらく立って上を見つめていた。そこで思い至ったのは、女性が大きな黒い色の犬を連れていた可能性である。それでやっと気持ちが落ち着いた。
気を取り直し、浦島草をかき分けながら女のいたところに行った。あたりの浦島草の花が折れ曲がり倒れてもいる。そこに彼女たちがいたことは確かである。
私は幻覚を見るような体質ではない。現実的な人間だと思っている。このような体験は初めてである。あまりの浦島草の多さに毒気を当てられた。浦島草の妖術にでもかかったような気持ちで、折れていた浦島草を一本とると神社に降りた。石段を降り、鳥居のところで井草神社を見上げた。神社はなにごともなくそこにあった。
夕食を買わなければ。マンションを通り越してコンビニに入ると、主人が私の持っている浦島草に気付いて声をかけてきた。
「三村さんも浦島草で願掛けなさるのかね」
「まさか、さっき忍さんに会って、井草神社に浦島草があることを教わったので行ってきたのですよ」
「忍さんてどなたです」
「地蔵さんに願かけている人です、うちのマンションの鹿野忍さんというんです」
「おや、あの女性は三村さんのお知り合いだったのですか」
「知り合いではなかったのですが、岩見さんが教えてくれて、さっきマンションを出るとき、彼女と偶然に会いましてね、井草神社の浦島草はすごい群落でした」
「そうですか、あの神社は古い神社で、昔は子育て神社といわれていたのですよ」
そんな会話をし、買い物を終えた私はマンションにもどった。
ウイスキーの空瓶に水を入れ、浦島草をさし机の上に置いた。インターネットを開いた。浦島草についてもう少し知りたいと思ったからだ。
サトイモ科の天南星属の多年草。日本に53種ある。ずいぶんあるものだ。花の形や色がどの種も個性があり面白い。忍さんの言っていた雪持草は浦島草のべろが白い玉になっていて、名前のとおり雪を抱えているようで気品を感じる。紫色の包(ほう)を持ち、紫色の長い舌を垂らす浦島草は奇妙だが、小型の姫浦島草は梟のようでかわいい。
根の芋は熱処理などをして食べるところもあるようだが、毒性のものも含むようだ。花の見かけから毒だと思い込まれているところがあるようだ。今はやりの覚醒剤や危険ドラッグが含まれるという記載は見られない。
酒瓶にさした浦島草の舌がふらふら揺れている。
スズランをさしておいた花瓶の水を飲んで死んだ人のことを聞いたことがある。清純な姿のスズランには心臓に悪い成分が含まれている。奇妙な形の浦島草をさしておいた水はどうだろう。逆においしいのではないだろうか。
浦島草を酒瓶から抜いて、雫を指で受け止めて舐めてみた。草の匂いはしたが特に甘くもなく辛くもない。氷を入れたタンブラーに角を入れ、浦島草を差しておいた水を注いだ。
一口に含んでみたが、いつものようにおいしい角ロックにすぎない。
ふと、何でこんなことをしているのだろうと、自分が可笑しくなってきた。浦島草という草は人を惑わすようだ。
ヤフーに浦島草、旅と検索をかけたところ、房総の銚子に群生があると書いてあった。誰かのブログのようだが、林一面に浦島草がおい繁り、林をのぞいたとき、全部の花が自分の方を向いていたとある。井草神社の浦島草はさまざまな方向を向いていたが、太陽の光の具合などに関係があるのだろう。そのブログを書いたのは女の子のようである。銚子なら遠くないし、行ってみてもいい。ここのところ旅行をしていない。天気も続くようだ。明日、調子にいてみよう。
次の日珍しく本気で出かける気になった。銚子は四時間程で行くことができる。遠くない。その日になって準備したこともあり、家をでたのが十時になってしまった。
京王線高尾山口から新宿にいき、東京駅で総武線快速に乗った。平日のこともあり、混んではいない。電車の中で携帯用のワープロ、ポメラを開いてこの旅行を計画したいきさつと浦島草の情報をまとめた。文章をまとめておくとあとで役に立つ。
千葉駅で総武本線に乗り換え、銚子に着いたのが二時近かった。昼飯を食べていないので駅の脇にあった寿司屋に入った。
カウンターにすわり、地魚の握りを頼み、板前さんに尋ねた。店の主人なのであろう、七十くらいの老人である。
「このあたりに、浦島草の群生があると書いてあったのですが、ご存知ですか」
老人は寿司を握りながら首を傾げた。
「さあ、その浦島草っていうのもわからんね」
「岩室っていう場所ありますか」
「それも知らんね、みっちゃん、知ってるか」
店の奥に声をかけた。若い女の子が暖簾(のれん)から顔をだし、「なにを」ときいた。
「浦島草だってよ」
「浦島草は知ってるよ」
「たくさん生えているところがあるのか」
「それは知らない」
「岩室、というところ知りませんか」
「知らないわ、浦島草はここから駅前の道を二十分ほど歩くと、林があってそこに生えているわ」
「有名なのか」
老人が女の子に尋ねたが首を横に振った。
「あんな花、誰も好きにならないよ、蛇草って言ってるよ」
「でもみっちゃんどうして知っているんだい」
「私の友達が好きなのよ、大庭みなこ、って作家が浦島草っていう小説を書いていて、それが好きなんだって、それであの林にあるから一緒に行こうっていうから、見に行ったんだけど、気味の悪い花なの」
「お客さん、おまちどう、そんなことで」
老人が私の前に握りを並べた。
「いや、ありがとうございました」
いさき、あじ、ひらめ、たい、まぐろ、いか、たこ、どれもなかなか旨い。それにそんなに高くない。
食べ終わって茶を飲んでいると、みっちゃんと呼ばれた女の子が、このあたりの地図を持ってきてその林の場所を教えてくれた。岩室ではないが行ってみることにした。
親切でうまい寿司屋だった。
道が単純でとても分かりやすい、ぶらぶらと歩いていくと、すぐに小学校らしい建物が見えた。そこを過ぎると公園らしい広場があり、先に小さな林がある。
そこだろうと思い、公園をつっきって林の中をのぞくと、すぐに浦島草が群生していた。あまり大きな群生地ではない。井草神社のほうがはるかに立派である。浦島草の花が一斉に自分の方を見た。これは錯覚で、偶然にどの花もこちらを向いていた。ブログに書いてあったように一定の方向を向いて咲いている。井草神社のものよりお行儀がいい。色も少し赤っぽい。
写真を撮った。井草神社のものと比べてみよう。数本切り取ってザックに入れた。自分はお行儀が悪い。
写真機の液晶画面で撮ったばかりの浦島草を見ていると、がさがさと音が聞こえた。目を上げると目先の浦島草が揺れた。一瞬昨日の井草神社の浦島草がフラッシュバックしたが、茶色い犬の顔が現れた。犬はちらっと私を見ると興味がなさそうに、脇を通り過ぎ、のそのそと公園を横切って行った。きのう井草神社の浦島草の中にいたのも、黒い犬だったのかもしれない。なんとなく安堵した。
高尾山口の駅に帰り着いたのは八時である。三つ葉ストアーに寄り、夕飯になにを食べようか迷って、うろうろしていると、主人がよってきた。
「三村さん、あの女性、忍さんが昨日の夜もあの花を地蔵に供えていましたよ、どんな願い事をしているのでしょうな」
「わかりませんけど、岩見さんの話では、最近お子さんを亡くしたようですよ」
「そうなんですか、そういえば、あの地蔵堂は、昔チフスで沢山の子供たちが亡くなったときに造られたと聞いたことがありますね」
「それでかもしれませんね、お子さんの供養でしょう」
主人は、私の目が一つの弁当の上にいっているのに気がついたようで、「この弁当はいい鮭を使っていますよ」と指差した。
結局、私はその鮭の弁当を買ってマンションに帰った。
エントランスで忍さんとすれ違った。駕篭を持っているところをみると、浦島草を採りに行くところだろう。こんなに遅くなってから大変なことである。彼女は私を認めちょっと微笑むと出て行った。
私は部屋にもどって、銚子の浦島草を取り出した。浦島草はそんなに萎れていない。井草神社で採ったものと比べてみると色がやはり少し赤い。生育地によって色の濃さなどに違いがあるのは他の植物でもよくみられることだ。
特定の植物に着目して日本の旅行記を書くのも悪くはない。ちょっと変わった花を選ぶと面白いだろう。浦島草などはうってつけである。
あくる朝、写真機をもって井草神社に行った。社の裏山にのぼり浦島草の広場に来た。浦島草は千葉のものより背が高く、いろいろな方向を向いた花をつけている。色も紫色が強い。あらためて写真を撮った。
その週は身近の江ノ島や城ヶ島など島の記事を頼まれたこともあり、ついでに浦島草があるかどうか見てきた。どちらの島にも群生しておらず、ぽつんぽつんと木の間の下草の一つとして咲いていた。いずれ全国を歩いてみよう、
インターネットで調べると、浦島草は日本のほとんどのところで見られるようである。桜前線ではなくて、浦島草前線をつくるのも面白い。
五月十八日の土曜日の夕方、出版社の連中と高尾山の上にあるビアガーデンに行くことになっていた。その日の午前中、もう一度、井草神社の浦島草を見ておこうと思い、写真機片手に石段を登った。石段脇の蝮草の花はもうしおれている。五月晴れのさわやかな日にもかかわらず、境内につくとむーっと蒸した空気が私を包んだ。
社の後にまわり林に入り、広場につくと浦島草はまだ咲き誇っていた。以前にもまして紫色の花の頭は色が濃くなり、背も高くなっている。
かすかに風が吹いているのであろう、ふらふらと花が揺れている。その上を金蠅が飛んでいる。蠅は浦島草の花にとまると中に潜り込んでいくが、おかしなことになかなか出てこない。のぞいて見るために蠅が入ったばかりの浦島草に近づいたとき、離れたところからがさがさと何かが動く音が聞こえた。目を上げると、浦島草の群れの中から長い黒髪の女がすっくと立ち上がった。女は赤い目を私のほうに向けた。手には白い布に包まれたものを抱えている。
このあいだの女だ。その時には自分の思い違いかと思ったが、また現れた。この女性も浦島草が好きなのだろうか。
今度は声を掛けた。ところがとたんに女はすーっと消えてしまった。
私は浦島草をかき分け、女が現れたところにいそいだ。浦島草の群の中に黒い生き者がいるのがちらっと見えた。前と同じだ。犬だろうか。後姿がかさかさと遠ざかっていく。追いかけていこうと急いだ。
そのとき、後ろから私の名前を呼ぶ女性の声がした。私は振り返った。浦島草の群の前で忍さんが蔓で編んだ駕篭を抱えて立っている。
「やはりいらしたのですね」
やはりというのはどのような意味なのだろうか。どう答えたらいいのだろう。
「あの、あれから、浦島草に興味を持ちまして、他のところの浦島草も見てきました、旅の雑誌に浦島草のことを書こうと思っています」
彼女への返答になっていない。ところが彼女はこう言った。
「そうですの、でもこの神社のように立派な浦島草はございませんでしたでしょう」
私の返答に合わせてくれたようだ。
「ええ、おっしゃる通りです、ここのものは立派ですね、浦島草を採りにこられたのですか」
「はい、今日は六本いりますの」
「前お会いした時には三本お持ちでしたね」
「はい、今日は特別です、最後になると思います」
「お地蔵さんに夜中に供えているということを三葉ストアーの主人からききました、今日が最後なのですか」
「ええ、あのコンビニの方たちは気になさっていたことでしょうね、何時もそうっと見てましてよ、気味が悪かったのではないかしら」
忍さんはちょっと微笑んだ。
「浦島草はお供えに大事な花なのですか」
「ええ、古い本に書かれていますの、浦島草は違う世から生えているそうです、根があるのはこの世ではありません」
「それはどういうことなのです」
「浦島草の根に膨らみがありがあります」
「根茎ですね」
「はい、その中は冥土だそうです」
「浦島草の花は冥土から生えているのですか」
「そうなのです、浦島草を地蔵に六十六日供え、最後の日は、六本のうち五本を地蔵に供え、一本を自分の部屋に祀り、祈るとあります」
「そうするとどうなるのです」
「浦島草の一つの冥土が開いて、浦島草の蔓を伝わって、戻ってくるのです」
「亡くなった方がですか」
「はい、娘です、生まれて一月になる前に死にました」
「うかがっています、お気の毒でしたね、採るのをお手伝いしましょうか」
「ありがとうございます、しかし、私一人でしなければなりません」
「あ、そうですね、それじゃあ、私はこれで帰ります」
「失礼します」
忍さんは深々とおじぎをした。じゃまをしてはいけない、長い黒髪の女と黒い動物が気になったが、私は後も振り返らずその場から去った。それにしても今日の彼女は雄弁だった。いつもの忍さんではない。私が浦島草の群落から現われたあの女や黒い生き物の後を追うのをやめさせるために声をかけたのではないだろうか。あの女と黒い動物は忍さんを助けるためにでてきたなにかか。
部屋に戻った私はいつの間にか、ベッドの上で寝ていた。
眼が覚めたのは三時半である。昼を食べていないが、もうその気もない。これから出版社の編集者たちと、高尾山頂のビアガーデンで飲むことになっている。
着替えて高尾山口駅にむかった。集まるのは私がほとんど専属のような旅の雑誌の編集者たちだ。五月の連休が終わっても、高尾山へ来る人の数が減らなかったが、さすがにこの時間になると登る人は多くない。
私が駅に着くと、すでに来ていた編集長の篠田が手を上げた。他の二人もすでに来ている。
「近くに住んでいるのに、おそくなってごめん」とあやまると、
篠田は笑いながら、
「ちょうど四時ですよ、三村先生、旅眼の六月号ができたので持ってきました」とザックから雑誌ととりだした。この号には昨年行った北海道のジャガイモの取材記事がのっている。ジャガイモの歴史を編集部の赤根女史がまとめ、写真は編集部の三浦が担当した。二人もすでに来て笑っている。
赤根が私の持っていた六月号を取り上げるとページを開いた。
「ほら、三浦君が撮った写真、よく撮れているでしょう」
私の書いた紀行文の中に、ジャガイモ畑にいる赤根と私の写真がある。
「三浦君は写真うまいね」
私の言ったことに、背の高い三浦が首を曲げて嬉しそうに「ありがとうございます」と反応した。この出版社は編集長の篠田が自分でやっている小さなもので、時々単行本も出す。この雑誌に載った文を、その都市の市役所や観光協会にパンフレットとして再編集し売ることで、それなりに経営が維持されている。結構需要があり、逆に取材旅費もちで依頼がくる。ジャガイモの話も北海道のその町から頼まれたものである。
「さあ、行きましょう」
篠田の声でケーブルカーに向かった。すでに赤根がケーブルカーの券を買って持っていた。それをもらうとすぐに乗ることができた。4時をすぎて乗るのは、夜景をみたい人やビアガーデン目的の人たちだろう。
我々がビアガーデンについたころはまだ明るかった。
ビールが運ばれてきて、乾杯の後は取材旅行の話になった。編集長の篠田は自分から出かけないことが多いので、取材中の出来事を聞きたがった。話を聞くことで次の企画のヒントを探しているのだ。
私は最近の浦島草の一連の出来事を話した。
「浦島草は知ってたけど、冥土から生えているなんて話は聞いたことがなかったよ、不思議な花だね」
「そうですね、面白い話だ、植物にはいろいろな謂れがありますからね、その地方、地方の」
篠田が頷いた。
「それで、銚子、江ノ島、城ヶ島で浦島草を探してみたんだ、どこでも同じように奇妙な顔をしているけど、それぞれの場所の雰囲気があって、ちょっと面白い。全国の浦島草行脚でもしてみようと思うんだけど書いたら載せてくれるかな」
「それ面白いですよ、ついでに他の植物も見ていただければ、いくつかのシリーズが一度にしあがっちまう、やりましょうよ」
「わたし、烏瓜の花も実も好き」
赤根はもとから花や実が大好き女子だ。
「沖縄には琉球烏瓜がありますね」
三浦君も写真をやっている関係か植物をよく知っている。篠田編集長も言った。
「あれは、琉球雀瓜だよ、烏瓜じゃないよ、普通の雀瓜ってのもかわいいよ」
「浦島草は四月か五月、烏瓜の花は八月、実は十月か十一月、これで冬の植物があると、一年中旅をすることになる」
「いいアイデアですね、冬はスノードロップが白い花をつけますね、春の手前で雪割草の花が開く」
篠田編集長がこんなに植物好きだとは思わなかった。彼はさらに続けた。
「これは、とっておきのもの、浦島草よりもっと早いのだけどね、寒葵(かんあおい)の原始的な花は面白いし、地域によって特異的なものがありますよ、このあたりは多摩の寒葵」
確かに寒葵の花は普通の人は知らないが好きな人は目の色を変える。
「どうです、三村さん、その辺でじっくりやりましょうか」
私は頷いた。かなり疼くものもある。話ははずんでビアガーデンの閉店までいることになった。天気が良い日であったので新宿の高層ビル群がきれいに瞬いていた。
最後のケーブルカーに乗って麓に降りると、もう一軒ということになった。終電を確認して近くの店にあたった。幸い、駅前、甲州街道沿いの蕎麦の老舗がまだ開いていた。そこの蕎麦はなかなか旨い。
「浦島草っていろいろな種類があるのですか」
赤根が聞いてきた。
「浦島草という名の付いているのは南国浦島草や姫浦島草かな」
「かわいい名ね」
「姫浦島は花もかわいいよ、ミミズクみたいだ、九州方面かな、暖かいところに咲くのだよ」
「見てみたいな」
「園芸店で売っているよ、浦島草の仲間に蝮草があるけど、そういうのをみんな天南星っていうんだ、中国名かな、それはたくさんの種類があるし、蒟蒻だって同じ仲間だよ」
「そうなんだ、それなら、蒟蒻の産地を回るのもいいわね」
「そりゃ、またいい考えだな」
そうやって、話はどんどん、企画ものになっていった。
終電近くなり、店をでて彼らがホームに入るのを見届けると家路についた。飲み物を買おうと三葉ストアーにはいり、雑誌などを見ていると、店員が窓から外をのぞいている。見ると、地蔵のところに、鹿野さんが黒装束でかがんでいる。
「願掛けをしている女の人だね」
店員が振り向いた。
「よく見るんですよ、いつも真夜中ですよね」
「お子さんを亡くして、供養をしているのだと思うよ,今日が最後だそうだよ」
店員はそうなのかと納得をした顔をしてカウンターにもどった。私はペットボトルのお茶を買うと外に出た。地蔵のところにすでに忍さんの姿はない。
道の先に忍さんの後姿が見える。だいぶ先なので追いつくのは無理だろう。私は飲んでいたこともあり急ぐ気もなかった。
忍さんはマンションに入らなかった。通り越してそのまま道を歩いていく。井草神社にもう一度行くところだろう。好奇心がわいてきた。私もマンションを通り越した。
忍さんが神社の方へ曲がっていくのが見えた。
少し遅れて神社の石段を登った。忍さんは浦島草の群落のところに行ったのであろう境内にはもう姿がない。神社の入り口にぽつんとついている街灯の明かりがあるだけで、神社の裏は真っ暗である。幸い私はいつもペンライトを携えている。足下を照らしながら林の中を登っていくと、雲から顔をだした月の薄明かりであたりが見えるようになってきた。
浦島草の群落が見えるところまで来ると、忍さんが中に入っていくところだった。
忍さんが通っていくと周りの浦島草の花がふらふらと揺れた。
忍さんは一本の浦島草の前に立った。その瞬間、彼女の周りの浦島草の長い舌が一斉に上に伸びあがった。その先には赤いものがぶら下がって蠢めいている。
小さな赤ん坊に見える。まさにそうだ手足を動かしている。これは幻覚か。
いくつもの浦島草の舌の先で赤子がぶらんぶらんと揺れている。
白い霧がただよいはじめた。乳の匂いだ。母親の匂いだ。
忍さんの顔が笑った。忍さんはすっと手を伸ばすと、一本の浦島草のべろにつるされた一人の赤子をつかまえた。
「まちこちゃん」
忍さんが赤子を引っ張り取ると、赤子は忍さんの手の上で大きくなった。赤子の泣き声が林の中にこだました。忍さんは胸をはだけ、赤子の手が乳に伸び、赤子の口が赤くなった乳首を咥えていた。ちゅちゅと音が林の中を木霊した。浦島草の舌のさきにつるさがっていた他の赤子たちは見る見る黒くなり縮んでいくと、ぽたりと下に落ちた。真っ黒な犬が現れて落ちた赤子を拾って食べた。
忍さんに赤子をとられた浦島草の筒状の花が真っ黒になり、黒いべろがぐーんと伸びてきた。べろは赤子と一緒に抱いている忍さんをからめとって花の中に放り込んだ。
黒い花の浦島草は背が伸び上がり、土の中から根の生えた芋が現れ次第に膨らみ、月の光に照らされてうごめいた。
自分は酔っている。いや頭はしっかりとしているはずだ。
黒浦島草の大きな芋の中が見える。忍さんが笑顔で赤ちゃんをあやしている。
浦島草は冥土から生えている冥土草だ。
周りの浦島草の花が一斉に自分の方を向いた。帰れと言っている。
私はふらふらと井草神社の階段をおりていた。
いつのまにかマンションの自分の部屋にいた。その後は覚えていない。
眼が覚めたとき、黒い浦島草の根の膨らみの中の忍さんの幸せそうな顔が目の前に浮かんだ。そのことだけは今でも思い出すことができる。
その日から鹿野忍はマンションからいなくなった。
冥土草
私家版幻視小説集「お化け草、2018、一粒書房」所収
木版画:著者


