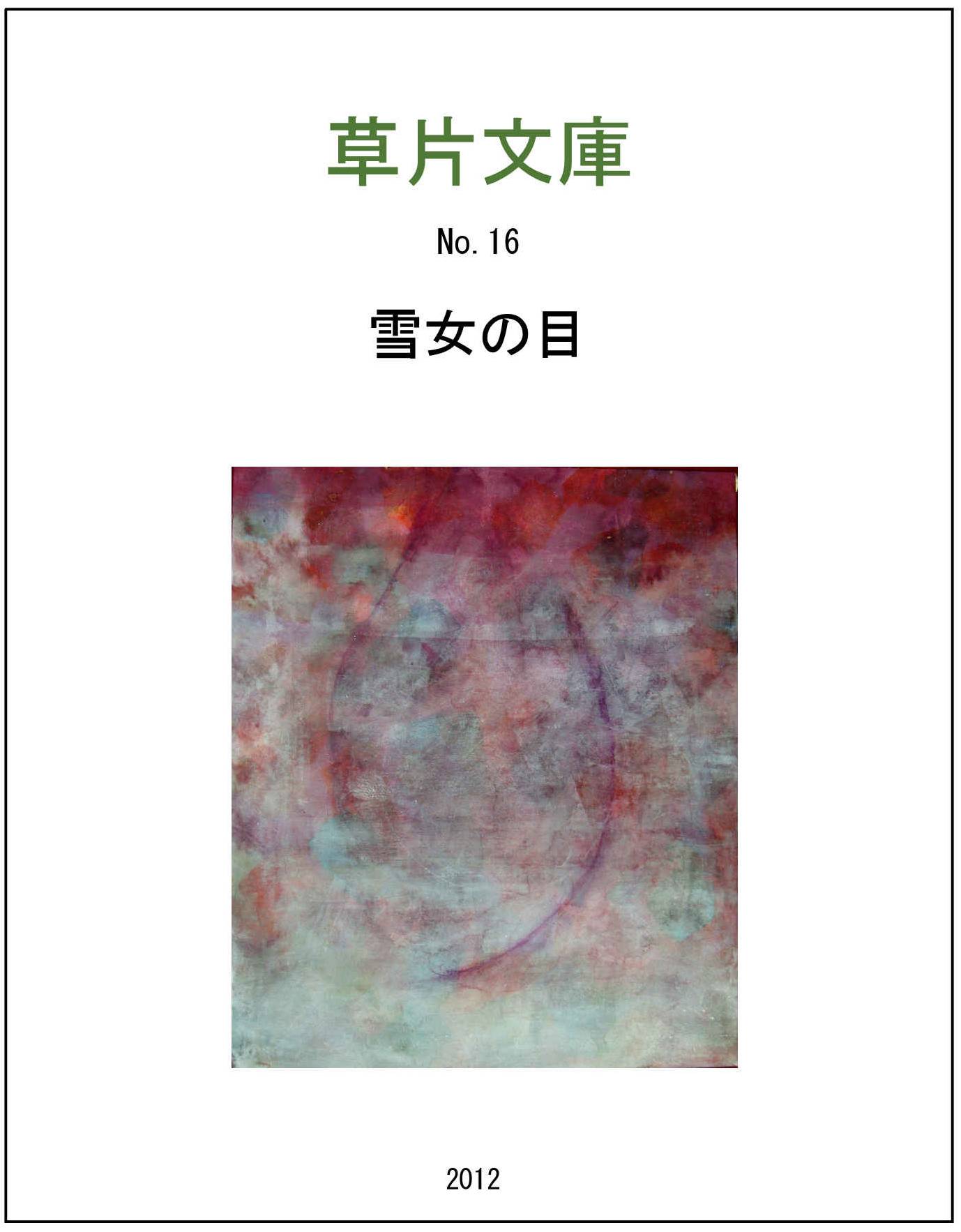
雪女の目
年が明けてすぐ、雪の一番深い時期にと思い、秋田の山奥の温泉郷に宿をとった。
この夏には軽井沢の別荘で雪にまつわる小説を書くことにしていた。そのために、雪深い世界の雰囲気を体験し、構想を練っておこうと思ったからである。
奥羽線湯沢駅からバスで一時間ほど行ったところに小安峡温泉がある。インターネットの映像では雪に埋もれそうな川の脇から蒸気が噴出している。古くから温泉が湧き出し、湯治場として知られていたところで、あまり観光化されていない。
宿は次郎兵衛旅館にした。部屋数は五つしかない小さな旅館だが、離れに温泉小屋がある。館内には古びた感じの温泉も二つある。食事も地味だが地元のものを使った質の高そうなものである。
私は試しに三泊ほど予約した。よければもっと逗留する予定であった。
一月の末、天気予報だと秋田地方は晴れとあった。しかし、それまでかなり長く雪が降っていた。天気予報どおりには行かないだろうと思いながら家を出た。
東京駅に行き、十時少し前の秋田新幹線に乗った。盛岡を過ぎる頃になると車窓から見える風景は雪景色に変わった。一時半、大曲に着いた。そこで奥羽線に乗り換える。大曲ではすでに新庄行きの電車が待っていた。
二両の電車は雪で覆われた田んぼの間を進んでいく。四十分も乗ると湯沢についた。
駅の前は雪掻きが行き届いており、タクシーが数台客待ちをしていた。羽後交通のバス乗り場は駅の広場の前の通りにあった。
あまり待つことなくバスが来た。乗客は意外と多い。
バスは街中を過ぎると広がる雪の田んぼを貫いている道を進んでいった。雪掻きがされており、バスは快適であった。能代春慶塗といわれる有名な漆器が作られている川連、うどんで有名な稲庭を過ぎると山間に入り、やがて川沿いに進んでいくと何軒かの旅館がみえる終点にきた。湯沢から一時間ほどかかっただろうか。
私はバスから降りると、地図を頼りに川沿いに歩いた。いくつかの旅館がある。有名な太郎兵衛旅館があった。歴史のある旅館でそれに決めようかと思ったが、もう少し小さな次郎兵衛旅館にしたのだ。名前からすると、太郎兵衛旅館の弟がやっている旅館かもしれない。道に沿って少し上流に行くと、ぽつんと古いつくりの宿らしき建物が眼にはいった。いかにもひなびた温泉宿である。白い湯気が建物の裏からあがっている。
次郎兵衛旅館と墨書された大きな板が雪囲いをした玄関口にかかっている。入り口には茶色くなった大きな提灯が二つ吊るされている。
玄関の戸を開けると、広々とした応接室になっていた。石油ストーブが赤々と燃えている。よく磨かれて黒光りしている床板に天井から釣り下がっている白いガラスの電気が映っている。脇にはたくさんのこけしが入った立派なガラス戸棚が置いてあった。壁には昭和の初めの頃と思われる雪に埋もれた旅館の写真が掛けてある。
奥から女将と思しき女性がでてきた。色白でうりざね顔の日本女性の典型的な顔をしている。四十前後だろうか、落ち着いた秋田美人である。そういえば湯沢は美人の多い町と聞いて来た。
「いらっしゃいませ」
女将は柔らかな声で腰を低くした。
白いブラウスに緑色のロングドレス。想像していた秋田の山奥の旅館の女将のいでたちではない。しかしよく似合っている。
「お世話になります」
私は名をつげ靴を脱いだ。女将が置いた荷物を持とうとしたので、たいした荷物ではないからと自分で持った。
女将は自ら私を部屋に案内してくれた。
女将のうなじを見ながら、二階のあがってすぐの部屋に入った。雪に埋もれた山が一望できる眺めのよい部屋である。
「この部屋は外の景色がよろしいと思います」
「秋田のなまりがありませんね」
私はテーブルの前にしつらえてあった寄りかかり椅子に座った。女将は背筋を伸ばして座るとお茶の用意を始めた。
「はい、この宿を買ってまだ二年ですの、私は新潟からまいりました」
女将は慣れた手つきで私の前にお茶を置いた。
「そうですか、新潟も雪の国ですね」
「はい、でも、ここはもっと雪深いところですわ」
「どうして秋田にこられたのですか」
「雪が好きなのですわ」
女将は私を見て微笑んだ。
「矢際先生は、ここではどのような小説をお書きになるのですか」
女将は私の仕事を知っていた。彼女は宿帳を私の前に置いた。
「ご存知でしたか」。宿帳に名前と住所を書いた。
「ええ、小説が好きですの、矢際先生のものもいくつか読ませていただきました」
「それは、光栄です」
「温泉は一階の外れに二つと、庭に面したガラス戸から外に出ますと、少し上がったところに温泉小屋がございます、温泉小屋には掛け流しの湯が二つございます、どちらも日により男女が入れ替えになっております。食事は朝夕ともお部屋のほうにお持ちいたします、お昼は食堂のほうで何かできると思いますのでお申し付けください、お風呂に行かれるときには、ここのタオルをお持ちください、風呂場には用意がございませんの、フロントにおりますので、お分かりにならないことがありましたら、いつでも結構ですので声をかけてください、電話は7を回していただければ」
一通りの説明を終えると女将は下に降りていった。
窓から見る雪景色は今まで泊まった北国の宿と大きな違いを感じないが、この静けさはとても心地がよくなぜか落ち着く。部屋の中の空気がからだに沁み込んでくるようだ。周りに泊り客がいないせいもあるのだろう。
テーブルの上に持ってきたPCをだし、ここまでのことを詳しく書き記した。どのようなことでも小説の材料になる。バスで見た雪の景色を細かく記録し感想を書いた。
夕食前に一風呂浴びようと、宿の着物に着替えて一階におりた。フロントを通って奥の浴室に行くと、女湯から一人の女性が出てくるところであった。泊り客のようだが女将とよく似た顔がたちだ。からだつきも似ている。ちょっと会釈をした。
男湯は小ぢんまりとはしていたが、ヒノキの浴槽はよく手入れがされている。湯は少し茶色がかって透き通りきれいだ。掛け流しの湯が厚いヒノキの枠からゆるゆると流れ落ちている。桶で湯をすくいからだに掛け中に入った。湯が盛り上がって周りから勢いよくあふれ出る。からだに湯がゆったりとまとわりつき気持ちがよい。手足を伸ばして窓をみると、ガラス越しに雪のかむった雑木林が見える。
見ていると、林の中で白くボーっとしたものが動いた。雪が落ちてけぶったのだろう。雪が少し舞い上がった。
湯から上がって、フロントの前を通ると女将が声をかけてきた。
「もうすぐお食事をお持ちしますが、その前にビールでもお持ちしましょうか」
「それはありがたい、お願いします」
私は返事をすると部屋にもどった。
テーブルの前に座ったとたん、小太りで丸顔の女中さんが入ってきた。おもちのように白い顔をしている。
「失礼すぃます、ビールお持ちしました」
女中さんはテーブルの前でひざをおろして中腰になると、ビールの栓を抜いた。コップにつぐと、「どうぞ」と、私の前に置いた。
「これは、キノコの塩漬けをもどしたもので、女将さんがお持ちしろとおっしゃいましたので、おいすぃいキノコでございます」
「あ、どうも、ほんとにおいしそうだ、地元の方ですか」
私はビールを一口飲んだ
「はあ、言葉わかんねえですか、すぃません」
「いや、わかりますよ、ここは長いのですか」
「へえ、前の女将さんのときからおりますで、前に働いていた人はみんないますで」
「この旅館はいつごろできたのですか」
「前の女将さんが三代目とかで、大正の終わりごろと聞いてますで」
「古いんですね」
私は紙に包んでおいた心づけを女中さんの前においた。女中さんは「あれえ」とそれを押し頂いてエプロンのポケットに入れると言った。
「すぃません、遠慮なくいただかせていただきます。はい、この建物も修理をしながら使っております。だけんど外の温泉小屋はそのままですわ」
女中さんはきちんと座りなおした。
「なぜ手放したのかなあ、前の人は」
なんでも話の種になる。根掘り葉掘りで悪いとは思ったがきいてみた。
「いや、お亡くなりになったんですわ、ご主人が病気で、そいだら、女将さんも消えてしまいました。遠くに女将さんの親戚の方がおって、宿を相続されたそうですが、お売りになったのです。前の女将さんは雪みたいに色の白い方でした。今の女将さんも色が白いですよ、きんれいなからだなさってます。あら、余計なことを。わたすぃ一緒にお風呂に入ったことがあるもんで」
消えてしまったという言葉に引っかかった。
「前の女将さんがこの宿をおもちだったのですね」
「へえ、ご主人は、婿に入ったわけじゃあねえんですが、宿を手伝いながら、好きなこけしをつくっておったです」
「入口においてあるこけしですね」
「はあ、ご覧になっただか、なかなか評判がよかったんですわ、なんらかの金賞をおとりになったりして」
「前の女将さんはどこにいったのだろう」
私は単刀直入に聞いた。
「それがあ、わからんのです。警察も捜したのですが。ご主人が亡くなったんで、どこぞで自殺しているのではないかと心配しましてなあ、でもわからんかったのです」
「なぜ、自殺と考えたのでしょうね」
「仲のよか夫婦でしたな」
夫婦仲がよいだけで自分から死ぬなどということがあるだろうか、なにか事情がありそうだ。
「今の女将さんのご主人はどんなかたです」
「あんら、女将さんはお一人ですよ、雪女の研究をなさってますで」
「え、雪女の研究」
「へえ、なんでも早稲田大学の人間科学部の大学院生だそうで、社会人入学なさったときいてますで」
「ほーインテリ女将だなあ」
「でんも、ほんとによくして下さいます、あら、長居してしもた、すぃんません、わたし、ユウ申しますで、なんかあったら呼んでくらっさい」
ユウさんはもう一度ビールを注いでくれると、お辞儀をして出て行った。
雪女の研究というのは面白そうである。ラフカディオ・ハーンの怪談に収められた雪女をはじめ、雪女の伝承はいろいろある。雪女を題材にした小説もたくさんある。私も、雪にまつわる小説を頼まれた時に、頭に浮かんだのが雪女であった。
夕食もユウさんが運んできた。しゃれた陶器に盛り付けられたいくつもの料理がテーブルの上に並んだ。山奥の宿に似つかわしい保存してあった山菜やキノコなど、地味な物であったが味がよかった。こんなにおいしく料理された猪の肉ははじめてであった。もちろん秋田の炊き立ての白米はいわずもがなのご馳走である。ビールとともにおいしく食べた。
食事が終わると、番頭さんが布団を引きにきた。
「どんでしょ、外のお風呂でも、その間に布団敷いておきますが」
四角い顔で深い皺のよった人の良さそうなおじいさんである。
「そうですね」
「寒いで、どてらをしっかりと羽織ったほうがよかです」
言われたとおりにどてらを羽織って、手ぬぐいと湯上りタオルをもった。一階の廊下のガラス戸を開けて庭に出た。素足で下駄履きではやはり寒い。まだ五時を少し過ぎただけだが外は真っ暗である。
少しばかり小高いところに温泉小屋があった。外にある電灯の明かりをたよりに雪かきされている斜面の石段を上がっていくと、雪に埋もれるように二棟が連なった形の温泉小屋があった。手前の建物の入口に男と書いた札が下がっている。
引き戸を開けると、小さな玄関になっていた。脇の下駄箱に下駄を入れ、上に上がり、ガラス戸を開けると脱衣場になっていた。入口が二重になっている。寒い土地柄である。
脱衣場には昔懐かしいスチームヒーターがあった。それでも寒いがあったまった後は気持ちよく感じるだろう。
裸電球が一つ灯っているだけで薄暗い。棚には数個の丸い籐籠が置いてある。
着物を脱いでガラス戸を開けると八畳ほどの室に洗い場と、二も入ると一杯になってしまうほどの小さな湯殿があった。居間の中に自然石の湯船を作りつけたような雰囲気である。
黒くいぶされた天井の張りから裸電球が一つ吊るされている。その薄明かりの中で、透明の湯が静かに波打っている。湯に入ると、ひなびた温泉場にきたという感じがわいてきた。気持がいい。
長湯をするほうではないが、カラスの行水といった短いほうでもない。ほどほど温まると、湯から上がった。温まったからだに、このひんやりとした空気は気持がいい。思っていた通りだ。
からだを乾かして小屋から出ると、今度は冷たい空気が顔を刺した。冷たいと思い、ふと斜面の木々の間を見ると、白くボーっと光っているものが動いた。内湯から見えたものと似ている。少し近づいてみると、ふーっと消滅した。
蒸気に光が反射したようにも見える。雪国の温泉場の現象であろうか。
ガラス戸を開け母屋に入ると、ほんわかと暖かい空気が身を包んだ。こういった空気の刺激は頭にも良さそうである。いいアイデアが浮かびそうだ。
フロントの前を通ると、女将が私を呼び止めた。
「先生、もしかまわなければ、いつか、ご本にサインをお願いできますか」
「もちろんかまいませんよ、それに私のほうでも雪女のことを教えていただきたい」
「あら、ユウさんが言ったのかしら、お恥ずかしい、そんなに知りませんの」
「今からでもよかったらいらしてください」
「小説を書かれる邪魔になりませんか」
「いや、今回は、雰囲気を感じておくというだけで、いろいろメモしております。小説は夏に軽井沢で一気に書き上げるつもりです」
「そうですの、それでは、もう少ししたらお邪魔してよろしいですか」
「どうぞ、お待ちしてます」
「ありがとうございます」
小説の材料がそろいそうで、よい宿屋を選んだものだと得した気分になった。
しばらくすると、廊下から声がした。
「先生、失礼します」
ふすまが開いて、和服に着替えた女将が部屋に来た。本と書類箱のようなものを抱えている。後ろからユウさんが瓶とグラスを抱えてついてきた。
「遠慮せずにお邪魔させていただきます」
女将は私の前に座った。ユウさんが抱えていたのはワインであった。テーブルにカットグラスの瓶を置くと、ここに置きますと言ってユウさんは出て行った。
「葡萄酒がお好きだと、どこかにお書きになっていたと思いまして、山葡萄で作ったワインですの、自家製ですから、密造酒といったとこかしら」
「ご自分でおつくりになったのですか」
「ええ、新潟でも、密造ワインのおいしい宿で知られていましたのよ、警察に知られたら大変」
女将は小さく笑った。
「どうぞ」
年代物のグラスに血のように黒味がかった赤い酒が注がれた。怖い色だ。
「遠慮なく」
口に含むと、芳醇な香りが広がった。苦味は強くない。酸味と苦味が程よく合わさっている。素人っぽさが残ってはいるが、これだけの味のワインを探すとなると大変である。
「これはいい」
おせいじではなく、本当にそう思った。
ユウさんがなにやら持ってもどってきた。
「あ、ありがとう、ワインのおつまみですの、いろいろなキノコに衣を付けて揚げました。洋風のてんぷらかしら」
「揚げたてのようですね」
「ええ、私が今つくりましたの、どちらかというと、私は洋風のものを作るので、この宿の食事の添え物程度です。お食事は和風ですので、前からいる板前さんが作ってくださいます、通いの方です」
「おいしい、これはワインにあいますね」
「先生のご本はここにおいておきますので、お帰りまでにサインをいただけますでしょうか」
「いや、今しますよ」
一つの本は幻想的な短編を集めた自分でも気に入っている一冊だった。もう一冊はヨーロッパの食べ歩きの本である。
私はペンを出してサインをしようと本を開いた時、女将の名前を聞いていないのに気が付いた。
「お名前をきいていなかったですね」
「あら、すみません、紅芽雪(あかめせつ)と申します」
「すてきな苗字ですね、それにお名前もゆきと読まないのですね」
「ええ」
紅芽雪宛のサインを入れ、今日の日付をいれた。
「私その小説大好きですの、本当の幻想小説だと思います」
「ありがとうございます」
「今度はどのような小説を書かれますの、雪国のお話ですか」
「ええ、まだ構想はできてないのです。それで、雪の深い場所を経験したかったのでここを選んだのですよ。とてもよいところだ」
「私もよい宿を手に入れたと思っております」
「あなたもは飲まれないのですか、一人で飲むのもさみしい」
「よろしいのですか、それでは私もいただきます」
彼女が手をたたくと、ユウさんが上がってきた。
「グラスをもう一つ持ってきてくださらない、すみませんが」
ユウさんは「はい」とうなずくと、女将のところによってきて、なにやら耳打ちをした。
女将は笑ってうなずいた。
ユウさんも笑って下に降りていった。
「なにかあったのですか」
「ほほ、残っている私のキノコの洋風てんぷら食べていいかというんです。板さんと風呂を管理している番頭さんとユウさんで、ビールを飲むのですって。今日はお客様が先生一人だから」
「え、でも、今日、着いてすぐの時でしたが、内湯から女の方がでてきましたが」
「あの方は私の友達ですの、お風呂に入りにきたのですわ、ときどき地元の人が入りにくるのですわ」
そこへユウさんがグラスを持ってきて彼女にワインを注いだ。
女将は「いただきます」と言って、静かにグラスを傾けた。
「雪女の研究をするにはもってこいの場所ですね、このあたりにも変わった雪女の話はあるのですか」
「ええ、ありました」
「普通は、雪女が小屋の中の人を凍りつかせてしまう結果になるお話ですね」
「はい、私もいろいろなヴァリエーションの話を集めました」
「雪女の役割はなんでしょうね」
「一つは、雪への警鐘だと思います。雪の怖さを子どもに教える伝承だと思います」
「他には、なにがありますか」
「少ないのですが、雪男、イエティのように、実在していたという話です」
「ほお、そのようなものがありますか」
「ええ、でもそうなりますと、あのきれいな顔の雪女ではなくて、サルに近いようなものになってしまいます」
「ああ、そうか、雪男の彼女ですね」。
「ところが、不思議なのがありました。人間の一種といいましょうか、特別の能力を持った人間の集団、しかも、女性しかいない種族というものでした」
「信憑性は薄そうですね」
「ええ、そうですね、ですけど、わたし興味はありました」
女将は持ってきた箱を開けた。
「ここに、私の集めた資料がありますの、ごらんになりますか。ご利用いただいても一向に構いませんの」
「でも、これから博士論文を書かれるのでしょう」
「そうですが、まだまだ、資料は足りません、まだ一年生ですから、あと一年は資料を集めますの、三年目で論文にまとめるつもりです、でも学位は難しいでしょうね、なかなか大学では学位を出してはくれません。小説の元にしてくださっても、私にとって何も問題はありませんの」
とてもありがたい申し出であった。どうせなら、雑誌に雪女の連載ものを書き、一冊の本に仕上げるのもよいかと思うようになった。もちろん、彼女の協力で作り上げた本としてだすのだ。資料の内容からヒントを得るかもしれない。
「遠慮なく読ませていただきます」
「先生はいつまで滞在されますか」
「そうですね、資料を読むのに何日かかるか分かりませんので、読み終えるまでということで」
「どうぞいつまでもいてください、この時期はお客様が少ないのでゆったりできると思います、私はそろそろ下にもどります。ユウさんたちにもう少しなにかつくってあげなければ、温泉は一日中いつでもお入りくださいませ。電気が消えているときはつけてお使いください、それでは、おやすみなさいませ」
女将はサインの入った本を抱えると自分のグラスを持って立ち上がった。
「ワインは置いておきます。お飲みください、ありがとうございました」
女将は廊下に出た。
「こちらこそありがとうございました」
私は後ろから声をかけた。
女将はちょっと振り返ると会釈をして戸を閉めた。
資料の箱を開けると、県ごと場所ごとにまとめた資料があった。かなりの量である。読むのに時間がかかりそうである。その夜は電車疲れもありすぐに寝ることにした。明日読もう。
あくる朝、母屋の風呂に入り、朝食後は部屋に引きこもって資料に目を通した。多くは雪女の目撃談と雪女の仕業とする事件だった。私もここに来る前にインターネットで簡単には雪女の事を調べた。いくつかのサイトがあったが、グリーンバードによるファンタジー辞典に雪女のことがコンパクトにまとまっていた。女将の集めた資料はほぼそこにでてくるものである。ただ、雪女郎と呼ばれている新潟の雪女の仕業と報じられたものが多く集められており、参考になりそうである。
資料を一つ一つ確認していくと赤い袋があった。中を見ると、黄ばんだ新聞の切抜きである。昭和11年1月18日とある。古いものである。新聞は秋田のものであった。その地方紙に宿屋の主人が凍死し、女将がいなくなったことが書いてある。場所は小安峡の次郎兵衛旅館である。この宿の出来事である。ユウさんの話だと、つい三年ほど前、ここの主人が病死し、女将がいなくなっている。同じようなことが時代を経て起きている。奇妙だと感じないほうがおかしいだろう。
そこへ、女将さんが「失礼します」と廊下から声をかけてきた。
どうぞと返事をすると、戸を開けて、女将が言った。
「先生、小安峡をご覧になりませんか、ご案内します。今日は天気もよいようですし、それに明日は雪の予報ですから外に出るのは大変かもしれません」
「それは、ありがたいことです、用意しますのでお待ちください」
「どうぞ、ごゆっくりと、下でお待ちしています」と女将は下におりた。
私は洋服に着替え、コートを羽織った。
玄関に用意されていた長靴を履いて外に出た。いい天気である。周りは雪にうずもれているが、川沿いの道は雪かきがなされており、気持ちよく歩けた。
橋のたもとに来ると、下に降りる階段があった。女将の案内で階段を下りると渓谷沿いに歩く道があった。
雪に埋もれた川べりから蒸気が上がり、硫黄の匂いが鼻をつく。水の流れが雪の白さに相まってより透明に感じられる。
「夏のこの場所もきれいですよ」
女将が振り返った。目が赤い。
「目をどうされました。名前のように赤目さんだ」
「ほほ、はい、硫黄に弱いのですわ」
時折、大きな蒸気が上がり、周りが見えなくなる。
蒸気が晴れたとき、対岸の雪の中から白くもやったものが湧き出ていた。蒸気とは違う。
「午後はどうなさいますか」
女将が聞いた。
「そうだ、資料のことでちょっとお聞きしたいことあるのですが、紅芽さんはお忙しいですか」
「いえ、今日のお客様は先生と一組のご夫妻だけですので、食事の用意のときだけ時間をとられますの」
対岸の雪の中を見た。もう、白い霧のようなものは消えていた。
昼食時間が終わりしばらくすると、女将が白いブラウスに緑色のロングドレスという宿に着いたときの出で立ちで部屋に来た。
「資料の中に、こんな切抜きがありましたよ」
私は赤い封筒に入った古い新聞の切抜きを見せた。
「あ、それも入っていましたの、それは、新潟の宿の古い宿帳に挟んであったものです。当時この宿のご夫妻が私どもの宿に泊まりに来たようです。そのご夫妻の事件の切り抜きです。新潟の宿の前々の主人が新聞を取り寄せて切り取ったようです」
「今度も、同じように、女将さんがいなくなっていますね」
「そうですの、それで、私も興味を持ったこともあって、ここを見にきて、気に入ってしまったのです」
「何か分かったことがありますか」
「ええ、昭和十一年の事件は、初代の主人がお酒に酔って宿に帰る途中で寝てしまい凍死するというものでした。言いづらいことですが、死体は雪の中に埋もれていて、激しく精をもらしており、歓喜の顔でなくなっていたそうです。女将さんが行方知れずになった理由は今もって分かりません」
「ほお、雪に埋もれて射精をしていたとは、よほどいい夢だったのでしょうね」
「そうだと思います。女将さんの夢を見ていたのではないかとのことです。とてもきれいな女将さんだったそうです」
「紅芽さんが宿をお買いになったときとは違うのですね」
「ええ、まあ」と女将は間をおいて話した。
「三代目のご主人は心筋梗塞で、朝布団の中でなくなっていたそうです。一代目と似ているところは、やはり精を放出し、喜びの顔をしていたそうです。最初に気がついたのはユウさんだそうです。ユウさんから詳しく聞きました」
「違うといってもやっぱり似ていますね、まさか、二代目もそうだったのではないでしょう」
女将が赤い目で私を見た。目を伏せると言った。
「同じなのです。二代目のご主人は、雪下ろしのときに落ちて、かまどに激しく頭を打ってなくなりました。二代目は陶芸家でした。庭のところに大きなかまどがしつらえてあったのです。かまどの上の雪はちょうどずれ落ちていて、レンガが顔を出していたのです。そこへ屋根からまっさかさまに落ちたので、あっという間もなくお亡くなりになったという話です。しかし、やはり精をもらし、顔は笑みをたたえていたそうです。お食事のときだす食器はみな二代目が焼いたものです」
「ずいぶん素敵な食器をそろえたものだと感心していたのですが、そうですか、それにしても、偶然の一致としては不思議すぎますね」
女将はだまってうなずいた。しかし、それ以上のことはなぜか聞けないような気がして、そのままにした。お女将が下を向いてしまったからである。
その後、雪女についてお互いに考えていることを話したが、特に目新しいようなことはなかった。秋田のほうの雪女は雪ん婆というようで、他の地方と違うところは必ずしも若い美しい姿をしていない場合が多いことぐらいだろうか。
その夜、私の寝床に女がそうっと入ってきた。女性が入ってくるまで寝入っていて全く気がつかなかった。女の素肌が乱れた私の浴衣を通して押し付けられたとき目があいた。暗がりの中でも女将であることはわかった。指先で触れた乳房はキヌのような肌触りで私の指を押し返した。乳首に手を当てると、目を閉じて小さく口を開けた女将の顔がぴくっと動いた。肌のきめ細やかな女将のからだの隅々まで手を這わせた。青く血管が浮き出る首筋がのけぞった。後は、自然と激しい動きになり、妻を十年前に亡くしてからはじめて女性と交わった。最後の一瞬は永遠に続くかのようにそのまま溶けて眠りについてしまった。
朝、めざめると、隣には誰もおらず、布団には誰かいた形跡もなかった。ふと気がつくと、下穿きが湿っている。射精をしていた。夢だったのだろう。夢精という現象があることは知っていたが、晩生な私は若い頃にも経験がない。それにしても、ほとんど現実としか思えない夢であった。
私は起きると替えを一つ持って内湯に降りていった。短い旅のつもりできたので、着替えをあまり持ってきていない。洗わなければならない。ちょっと恥ずかしいことである。
フロントの前を通ると、女将は帳簿を見ていた。
「お休みになれまして」
声を掛けてきた。
あらためてみる女将はきれいな女性だった。
「ええ、ぐっすりと眠れました。とても楽しい夢を見ました」
「それは、よございました、どんな夢でしたの」
私はちょっと言いよどんでしまった。
女将はそんな私を見て、
「私も夢の中にお邪魔させていただこうかしら」
と言った。
私は意味も考えずうなずいて風呂に向かった。
後ろから女将の「朝食を部屋に用意しておきます」という声が聞こえた。
見透かされているような気がして、少しばかり薄気味が悪かった。
男湯に向かうと、その先の女湯から女性が出てきた。宿に来たときにも会った女将の友達である。すれ違うときにちょっと会釈をした。こんな朝早くから宿の湯に入りにきている。
男湯の暖簾をくぐり湯に入った。朝から風呂に入れるのはこういうときだけである。贅沢な時間である。
窓の外に見える木の間に白いもやったものが見えた。何度か見た現象である。今度何なのか女将に聞いてみよう。しばらく浸かったあとに、下着を洗ってでた。
部屋にもどり、タオルと一緒に下着をタオルかけに掛けた。
食事が用意してある。干物、海苔、卵焼き、梅干、茸の佃煮、質素なものであるが、秋田の米の旨さを引き出すよい味付けがなされている。
食べ終わるころユウさんが来た。
「お食事はおすみですかね」
席を離れようとしていた私を見て食器を片付け始めた。ユウさんがタオル掛けに目をやると言った。
「洗濯物ですか、お風呂の廊下の突き当たりにドアがありますが、開けると土間になっていて、そこに乾燥機つきの洗濯機あります、一回百円です、洗剤はフロントに言ってください、温泉の湯だと匂いがつきますから」
「そうでしたか、それではもう一度洗ってきましょう」
言われて見ればたしかにそうだ。温泉の湯であらうとイオウ臭くなるだろう。下着を持ってフロントに下りた。
女将に洗剤をもらった。
「洗濯ですか、私がしましょうか」
「いえ、とんでもない、そうだ、お聞きしたいことがあります、この旅館の庭や小安峡で蒸気のような塊が下のほうから湧き出て、そう、生き物のように動くと、消えていくという現象を見ました。どんな自然現象なのでしょうか」
「あれをご覧になったのですね、見ることできる方はあまりいらっしゃいません、先生の目にはみえるのですね、あれは雪女の目と呼ばれています。伝承では雪女の見回りだそうです。雪女は雪の中で死を迎える人の付添い人です」
「死神みたいですね」
「いいえ、死を招くのではなくて、死の介助をするのです、雪の中で幸せのうちに死ねるように」
「雪の中で迎えた死だけですか」
「はい、そういう言い伝えです、雪女にみとってもらえれば、寒くもなく、生涯で最も幸せのときをもう一度経験しながら死ぬことができるそうです」
「雪女の目は蒸気でしょうか」
「どうでしょう、蒸気なら誰でも見ることができますが、ここのユウさんや、板前さんたちは見た事がないそうです」
「僕に見えるということは、雪の中でもうすぐ死ぬのかな」
「いいえ、あれが見えることと、死とは全く関係ありません」
雪女の目のことをあとでユウさんにきいた。見たことはないという話であった。ユウさんの話も女将から聞いたことと同じであった。
その晩、早く寝ようかと布団に入ったときであった、戸をたたく音がした。布団から出ると電気をつけた。
「お話をしてもよろしいでしょうか」
女将の声がした。
「どうぞ」
「おやすみだったでしょうか、明日にいたしましょうか」
「いいえ、大丈夫です」。
女将は戸を開けると部屋に入ってきた。
「雪女の目のことでお話ししたいと思いまして」
女将は封筒を持っていた。
私の前に座ると、封筒からセピア色になったキャビネ版の写真をとりだした。
「ご覧ください」
女将の差し出した写真は次郎兵衛旅館の庭であった。木々の間に白く靄ったものが浮き出ている。
「初代が写した写真ですの。初代は写真家でした」
「ほー、初代は写真家で、次は陶芸家、そしてこけし作家、面白い宿ですね」
その当時、写真を撮るということは大変な費用と、新しい知識を必要としたことだろう。
「この宿の脇に写真の現像のための小屋があったそうです、初代がつくったのです、今は跡形もありませんが」
「当時としたら、すごいものですね」
「この写真に雪女の目が写っています、初代は雪女の目を見ることができた人でした、見える人が写真をとると写るようです。おそらく、二代目も、三代目も見ることができたのだろうと思います」
女将はもう一枚封筒から写真をとりだした。雪の中の小安峡である。昨日私が案内されたところと同じ場所だ。やはり白い霧のようなものが固まって浮かんでいる。しかもその白い霧の中に赤い目のようなものが浮いている。知らないで見ると蒸気が靄っているだけとしか思わないだろう。しかし、それとはどこか違う。
「これが雪女の目ですか」と聞くと女将はうなずいた。
「そこまで見ることができて、しかも写真に写すことができたということは尋常ではなかったものと思います」
女将は私を見た。目がまだ赤いままであった。
「明日はだいぶ深い雪になりそうです。ゆっくりお休みになってください。遅くにお邪魔しました」
女将は立ち上がると、部屋を出ていった。なぜこの時間になって写真を持ってきたのだろうか。いぶかしく思いながら、もう一度寝る支度をした。
電気を消して布団に入ると、入り口の戸がすーっと開いた。暗がりのなかで、着物を脱ぐ女の動きが見えた。素裸のシルエットが私の前に来た。女将だ。女将の唇が私の唇に重ねあわされた。私の手は女将のからだを引き寄せた。着物を着ているときには想像できないほどみごと張った太ももに手をやると、女将がふっとため息を漏らした。その後は、どのくらい時間が経ったか分からないほど激しくそして溶けるように果てて眠りについてしまった。
あくる朝、気持ちよく目があき、天井板の木目がくっきりと見えた。昨日のことはなかったように布団は乱れていない。ふと、下のほうになまあたたかさを感じて、布団をはぐと、また射精をしてしまっていた。昨日の出来事は、夢だったのだろうか。それにしてもあの手の感触、下半身の出来事、夢ではないと思うのだが。
その日は大雪になった。経験をしてみないと分からないものである。大粒の雪が絶え間なく落ちる様は、雪に慣れていない自分にとって埋もれ死んでしまうのではないかと思うほど怖さがあった。庭は雪で埋め尽くされている。
このような日は温泉に入るか、文を考えるか、ごろごろするかしかない。コンピューターに向かい、今までの夢の中の出来事を記録していった。それだけで小説ができそうである。
風呂に行くと、またあの女性とすれ違った。こんなに雪が激しいときでも湯に入りにくるとは、よほどなかのよい友達なのだろう。
フロントに女将さんがいた。なんとなく気恥ずかしい。しかし、女将は何事も無かったかのように私のほうに顔を向けた。
「よく眠れまして」
「ええ、とても幸せな夢をみました」
「今日もですの。それはよございます」
「ところで、いま、すれ違った女性ですけど」
「春さんですね、雪があまりひどくなるとこれなくなりますけど、寒くなると、毎日のようにくるときもありますのよ」
「今日はすごい雪ですけど」
「今日は土曜日ですので、昨夜から泊りがけで遊びに来ています、私の部屋に止めています、お気に召されましたの、後で紹介しますわ」
「いや、そういうつもりで言ったのではないのです」
「春さんも矢際先生には興味をもっていますのよ、彼女は歌を読む人ですから、小説もたくさん読んでいます、わたしより読んでいますのよ」
女将は笑いながら言った。
男湯の向かうと、今までと違って奥のほうにかわっていた。男女が日によって変わるようだが、ここへ来てからこの湯には始めて入る。入口のつくりは同じだが、湯殿の壁はタイルが張ってあって、湯殿もタイル張りである。どうやらこのタイルは陶芸家の二代目が焼いたものらしい。いろいろな色や形のタイルがはめ込まれており、ガウディーの作品のようだ。大正の洋館を訪れた気分になる。
窓の外は前の男湯からとは違う角度から庭を見ることになる。今日も白い蒸気の塊が雪の上に浮いている。雪女の目である。チラッとその中に赤いものが見えたが、目なのかどうかはわからなかった。
昼になると、女将が春さんと一緒に部屋に来た。
「古米(ふるまい)春さんですの」
「はじめまして、春です、お邪魔してすみません」
春と呼ばれる女性は、しぼりだすような声で挨拶をした。
「矢際です」
春は女将より少し四角張った顔をしているが、背格好はほぼ女将と同じである。テーブルの前で背筋を伸ばして正座をした。
女将が日本酒を持参した。
「このお酒は古米さんのところでつくったものです。ふるくから古代米を栽培し、昔の製法で酒を仕込むのだそうです。私どもも少し分けていただいているのです。とてもおいしいお酒です」
「お名前も古米さんですのでよほど由緒がおありでしょうね」
「はい、湯沢のお城の佐竹公の奥方様は京都のお公家さんで、そのお姫様が古代米を作るように私の先祖に種をよこされたそうです。苦労して古代米を実らせ、それをお酒にして納めるようになり、先祖はこのあたりでは生活が楽な家になったということです。苗字をつける時代になると古米としたそうです」
「なるほど」
女将が腰のある陶器の猪口についでくれた。とろっとした紫色のお酒である。
「春さんもどう」
「ありがとう」
甘目のおいしい酒である。
「春さんも雪女のことはよく知っていますの、先代のときからここの湯にこられていたのです、私に代わってからも湯に入りにこられ、お友達になりました。私もいろいろ教わりました。雪の目のことも春さんからきいたのですの」
「さっきも、庭の雪の上に出ました。何か赤っぽいものが見えたのですが、目とはわからなかった」
「春さんも雪女の目が見える一人です」
「小安のように雪の深いところには、雪女の目が一日に何回も現れるといわれています、特に雪がひどく降ると現れます、雪女は伝承にある死にまつわる雪女で妖怪ととらえられています、しかし、妖怪というと気味が悪く悪さをするように思いがちですが、それは間違っているのです、本当は雪における死をみとどける司なので、どちらかというと、菩薩、地蔵のように、信仰の対象とすべき神格なのです」
春さんは女将と同じことを話した。
「ところが、人間の種族に雪女と呼ばれる集団がいたことが伝わっています」
「ええ、それは雪さんからもうかがいました」
「雪女の一族は女性だけだそうです。特殊に発達した頭の機能が、お互いの結びつきを強くし、雪の中でも裸でも暮らせるようなからだを持っていたといわれています」
「面白い伝承ですね、この地方だけのお話ですか」
「はい、ただその一族は日本のどこででも暮らしていたそうですが、小安にその故郷があったとされています」
雪さんが説明をひきとった。
「その場所は、人のいけないような山の中ということしか分かりませんが、雪女の一族は数十人だそうです」
「女性だけでどのように子孫をつくったのでしょうね」
女将と春さんは顔を見合わせてちょっと首をかしげた。
何かをいいたそうだが、私にはわからなかった。
珍しい話で小説の中心的テーマになりそうである。空想小説めいた話にも幻想的な話にももっていけるであろう。
そのあと春さんは小安について話すと、女将と部屋からでていった。
その夜、私が小説のあらすじのようなものを書いているときである。隣の部屋で物音がした。二階に泊り客はいないはずである。廊下に出た。音がするのは隣ではなかった。一番奥にある部屋から音が聞こえてくる。入り口が少し開いており、中の襖も半分開いて光が漏れている。覗いてみると、雪さんの白い顔がほんのりと赤くなり、口を開いている。雪さんの上から乳房に唇を押し付けている顔があった。その顔がこちらを向いた。春さんであった。私の動機が激しくなった。二人のきれいな女体が絡み合っている。どきどきしていると、いつの間にか、自分が女将と絡み合っていた。いつものように、激しく果ててしまった。
もう朝であった。また、下着を汚してしまった。昨日の出来事は夢の中でのことだったのだろうか。この宿に来て毎日の夢精である。私はこういうことには縁のない人間だった。それがこのように三日も続けて精を漏らしているのは、この宿にはなにか隠されたものがある。女将が何か隠している。
そんな思いでいると、戸が軽くたたかれた。雪さんの声がした。
「入らせていただきます」
雪さんは洗面器を抱えていた。まだ夢の続きなのだろうか。
雪さんは湯で寝ている私のからだを拭いた。恥ずかしさが半分と夢なのだという割り切り半分で妙な気持ちである。
雪さんが私を見た。目が赤かった。
「これは夢ですの、でも、現実でもありますの、先生、私どものことをお話したいと思いますが、その前にお願いがございます」
雪さんは裾をただすと私の前で正座をした。
私も起き上がって布団の上に座った。
「お嫁さんにしていただきとうございます」
私は不思議と覚めていた。もちろん、うなずいた。しかし、必ず条件があることはわかっていた。
「ありがとうございます。先生の寿命が尽きるまで、私、できる限りお尽くしいたします。私も春さんもお話した雪女の一族でございます。先生には少しずつ私どものことを知っていただこうと思います。この宿の主人として、どうぞ、たくさんの小説をお書きいただきたいと思います」
私の望むところであった。私はもうすぐ五十になろうとする作家である。すべてを悟った私はこの宿に入ることにした。私は寿命まで最高の人生が送れるはずである。
宿の玄関のこけしの棚の反対側に、私の著作の入った本箱がしつらえられるだろう。
わたしはそのまま雪さんにつれられて、雪女の一族の故郷に行くことになった。いつの間にか宿から外に出て雪の中を歩いていた。浴衣にどてらを羽織っただけであるのに寒くなく、うずもれることなく下駄のまま雪の上を歩いた。小安の山奥深くに雪の上を歩いていった。夢の中なのだろう。
そこは、小高い山に囲まれた平地であった。昔の活火山の火口だったところだという。雪が積もった平野になっていた。岩山にはいくつもの穴があった。我々がその場につくと、穴から女性たちがでてきた。だれもが肌の色は白く、きれいな顔立ちをした女ばかりであった。春さんもそこにいた。この雪の中で、薄い浴衣一枚である。きれいなからだをしていて、雪に溶け込むように白い。雪さんはわたしを雪女一族たちに紹介した。笑顔の女たちはみな美しく、しかし、個性があった。雪さんは女性たちと一つの穴に入っていった。私も後をついていくと、赤い湯が波打つ池のある広場にきた。雪女の一族はそこで浴衣を脱いだ。雪女たちはみなふたなりだった。彼女たちは真っ白なからだを赤く透きとおった湯の中に横たえた。
湯の中から白い蒸気が湧き出した。あたり一面白い蒸気におおわれると、中から赤い目が現れ、湯に浸かる雪女たちを見た。
雪女たちが湯の中に立つと、赤い目に向かって深々と首を垂れた。
白いもやもやは赤い目とともに消えていった。
雪女たちは、雪さんの周りに集まり、肌をみながさすり始めた。雪さんの顔が上気してきた。
その動きはわたしの頭にそのまま伝わり、私は精を放出していた。
そしてわたしは目覚めた。夢精をしていた。毎日これが続くことになるのだ。
次郎兵衛旅館で祝言をあげた。集まった人たちは春さんを始め、全国に散らばっている雪女一族の女たち、それにわたしの親戚であった。宿の従業員たちは、四代目は作家だと大喜びであった。
雪女一族の中心になる雪女たちは、春さんのように米農家だったり、春慶塗の店だったり、麺を打っていたり、様々な形で人間の世界に溶け込んでいた。
雪女一族は両性具有である。カタツムリのように、出会った者のどちらかが男になり、女になる。ただ、この種族はそれだけでは子どもができなかった。人間の男性を必要としていた。選ばれた男性は夢の中で雪女と交わる。それは男となった雪女の精を活性化させる。そして、一緒になった男性の死の瞬間、雪女は新たな生命を授かるのである。
雪さんの前の主人が新潟で死んだとき新しい命を産み落とした。その命は小安の雪女の里で大きくなっている。雪さんがいた新潟の宿には新しい女将がいる。やはり雪女だった。
子どもを産んだ雪さんは若返って小安峡の宿で新たな人生を始めたのである。
雪女一族がやっている宿が日本全国に散らばっている。沖縄にも九州にもこの一族は住むことができる。永遠に生きる雪女一族である。
雪さんとは床を隣に敷いても指一本触れるわけではなかった。しかし、夢の中で必ず新しい体験ができる。命尽きるときまでこれが続くのである。
一つ使命を託されたとすると、この雪女の一族について小説にまとめることだろう。それは生きているわたしのもう一つの大きな楽しみである。
蒸気の中に現れた雪女の赤い目が私にははっきりと見えるようになった。
それが本当の雪女の目であることも理解できた。雪女は雪女一族とは違う。死の恐怖を和らげる神である。雪女一族は神である雪女に仕える人間の種族である。私はその種族を存続くさせる役割を神の雪女から割り振られたのだと思う。
雪女は、私の死がどのような形で訪れようとも、頭の中は快感で詰まったまま死ぬことを許してくれたのである。
雪女の目
私家版雪女小説集「雪女、2015、222p、一粒書房」所収
表紙日本画:山内佳子


