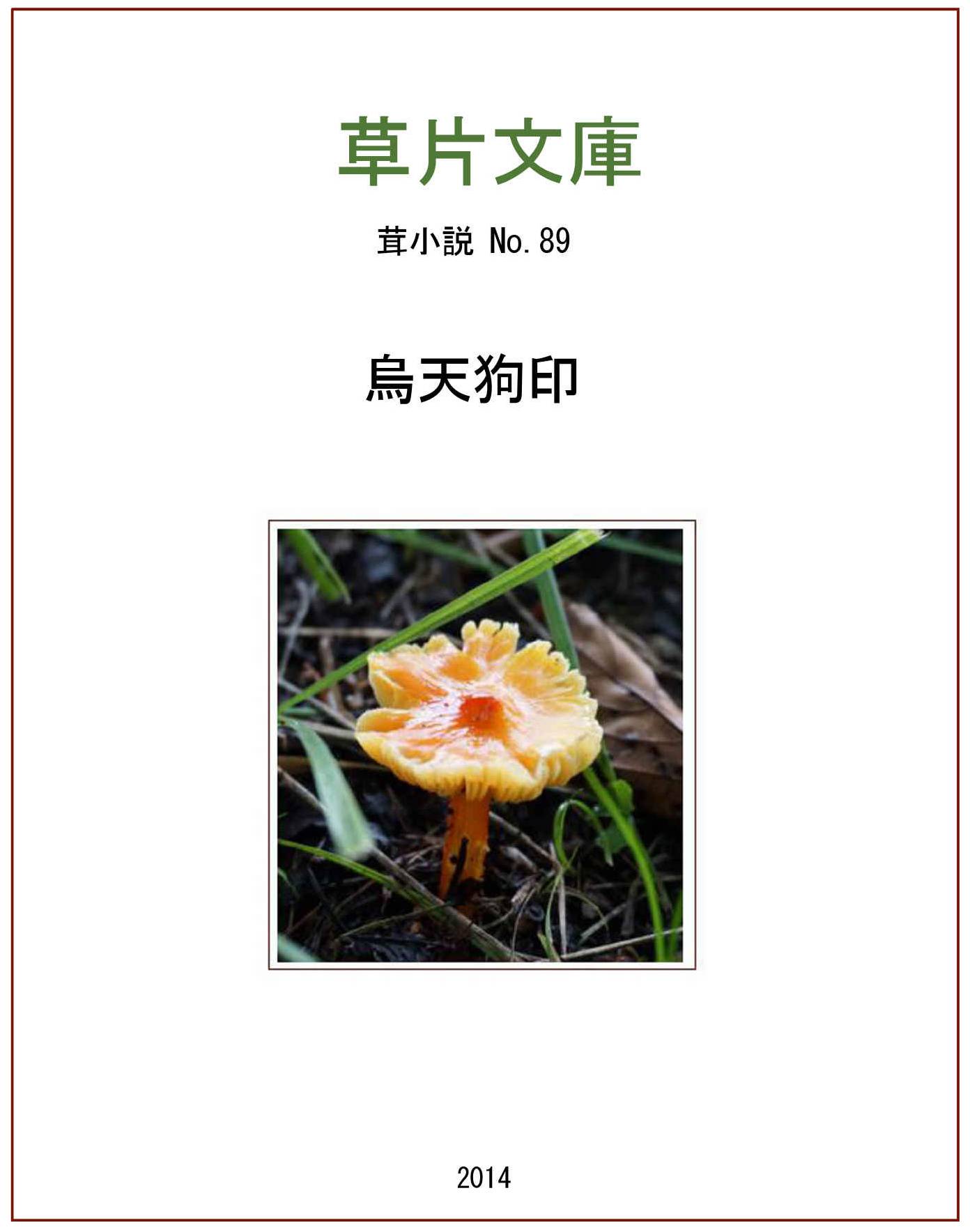
烏天狗印
ほんの数日前のことである。
彼が駅から家に帰る途中、八百屋の前を通ると、親指よりちょっと大きい程度の小さな松茸が二本店先に並んでいた。白い紙にマジックで大きく千円と書かれている。ずいぶん高い。
彼は興味半分に近寄ると、あの図太くて重そうな松茸とどこか違うのだろうと、小さな松茸をしげしげと眺めた。どこといって違いがなさそうである。ただよく香ってくることは確かだが。
家の中からおやじがでてきた。
「小さいがなあ、香は強いよ、大きい松茸の倍、いやもっと強いだろうな、部屋で食うと、家中匂うってやつだ」
「だから高いの」
「そうだよ、にいちゃん、味噌汁に入れてごらんよ、そりゃいい匂いだから」
そういえば、松茸を味噌汁に入れて食すということを聞いたことがない。味噌にあうとは思えないが、八百屋のおやじは味噌汁にしたことがあるのだろうか。松茸なんぞ口にいれる機会はないが、焼いて裂いて、熱熱に醤油をつけて食うのは旨そうだ。それに味噌をつけたら旨いかもしれない。土瓶蒸しも納得が行く、澄んだ汁の中に熱くスライスされた松茸が横たわっているのは見ているだけでも香ばしい。だけど、あの濁った味噌汁に入れるとなると、味噌の香りと松茸の香りが喧嘩して、あまり旨そうだというイメージはわかない。やってみたいとは思うが、そんな気持で見ていると、八百屋のおやじが「ちょったあ、まけるよ兄ちゃん」と言っている。
「味噌汁にいれたことあるの」
「あるさ、そりゃあ贅沢だぜ」
「どこでとれたの」
「俺が採ってきた、新宿から電車に乗って終点の高尾山口」
「高尾山で採れるの」
「たまたまさ」
「それじゃ、ただじゃない、高すぎない」
「だってよ、往復の電車賃、二つしかとれなかったから高いわけ、でもいいよ、まけるよ」
「そういうことか、じゃあ、一本だけ、片道分、まだ学生だから贅沢過ぎるけどね」
「あんちゃん学生さんか、よし、それなら片道ぶんで二本やるよ、彼女と一緒に食べなよ」
「いや、彼女いない」
「しょうがないね、そいじゃ、さらに一割引にしてやろう」
という具合で、ほんの五、六センチの松茸を二本四百五十円で買った。
一本は焼いて、一本は本当に味噌汁に入れてみよう。
彼は四畳半のアパートに帰ると、卓上コンロにボンベを着けて、網を用意した。焼くためである。味噌汁はいつもたっぷり作る、おかずなしで味噌汁ご飯にするためだ。
包んであった新聞紙から松茸を取り出すと、確かに部屋中に松茸の香りが充満した。強い香りである。これだけでも少しばかり大名気分になる。
一本はまるごと豆腐と一緒に沸いた湯にいれた。ちょっとして、赤味噌を溶かし、味噌汁のできあがり。後でもう一度暖めてご飯と一緒に飲むのである。
一本は丸のまま卓上コンロの上に載せ焼いた。
小さな冷蔵庫だが、バイト代が少しばかり入ったときに買っておいた恵比寿ビールがはいっている。いい機会である。発泡酒の中をかき分けて、本物のビールを取り出した。
コンロの上の松茸が香しい匂いを放っている。
ビールを開けてのどに流す。
焼けるのが待ちどうしい。
小皿に注いだ醤油に箸をさして、醤油をなめてみる。それだけで松茸の味がするような気がしてくる。
ひっくり返しながら、ちょっと焦げ目のできたところを裂いて、醤油をつけて口に入れた。
うまい、ともかく香りが強い。
ビールを一口飲んだ。
確かにこの松茸は小さいがあの値段は高くない。何せ東京で採れた物だ。
彼は松茸を細く、けちけちと裂きながら楽しんでビールを一本空けた。
さて、食事にしよう。
茶碗に白いご飯をもり、暖め返した味噌汁を椀に注いだ。
まず、味噌汁を一杯飲んだ。お椀に松茸が浮いている。丸ごとである。
箸で挟んで、松茸の頭をかじった。なかなかうまい。匂いも悪いものではない。お吸い物であれば、汁の匂いは松茸の香りにじゃまをしないが、味噌の匂いは影響をする。しかし案外迫力で、いける。
来年は是非大学を卒業して、給料取りになって、たまには松茸を食おう。そう思いながら、彼は白いご飯を三杯も食べ、作った味噌汁もすべて吸い尽くした。
至極満足して洗い物のために台所に立った。
茶碗と箸を洗うと、味噌汁を作った片手鍋の蓋をとった。そのとたん彼は目をむき出した。味噌汁の汁はもうないが、鍋のそこにコロンと松茸がころがっている。もう食べたはずである。ところが、一本、採り立ての松茸があった。
不思議どころの話ではない。
だが、彼はそうなった原因を考えることなく、得した気分になって、その一本を冷蔵庫の野菜かごに放り投げた。その無頓着が彼を大学八年生にさせたのだろう。
明日焼いて食べよう。今日のあの旨さを思い出して、彼の頭の中は嬉さと期待が渦巻いているだけで後は何もなかった。
明くる日は豆腐の味噌汁に、一本得した松茸を焼いて食べた。今日は発泡酒で我慢したがビールにすればよかったと反省した。
焼き松茸を食べた後は、白いご飯に豆腐の味噌汁である。味噌汁がまだ松茸の香りを発散させていた。鍋の蓋をあけお玉で豆腐の味噌汁をお椀によそうと、これまた驚いた。なんと松茸がコロンと一つ味噌汁とともにお椀に入ったのである。
「あれえ」
さすがに彼も驚いた。どうしたのだろう。部屋中が松茸と味噌の匂いで満ち満ちた。
どうもどころか、大そう府に落ちないことではある。と思いながらも、彼は白いご飯を二杯も食べてしまったのである。
それがその日だけで終わらなかった。毎日のように洗った味噌汁の鍋の底に松茸が現れ、それを取り出し、味噌汁を作ると必ず松茸入りの味噌汁になった。
毎日が幸せであったわけであるが、ふとあるとき奇妙なことに気がついた。飽き症であった自分がなぜ松茸には飽きないのかということである。何かが違うわけである。ともかく高価な松茸を食べることができる満足感と、もちろん味と香は抜群、言うことがないわけである。しかし外のものを食べたいと思わない自分に気がついた。食べてもまずくはないのだが充実感がない。松茸を食べたときだけ満足をする。
大学に行くと友人たちが、「何で、松茸の匂いがするんだ」と聞いてくる。
「八百屋でちょっとアルバイトして松茸を店に並べたんだ」
などと無理のある言い訳をしていたが、それが続くと、「昨日も松茸屋か」
と笑われたりする。
それでも、毎日鍋に松茸が現れ、焼き松茸か松茸味噌汁の食事が続いた。
半年たった頃だ。体重が減ってきた。少し気にして鏡に自分の顔を映してもどこといった変化はない。ただ体臭が松茸臭くなっている。風呂にはいると風呂の湯が松茸の匂いになる。寝て起きると布団に松茸の匂いが染み付いている。自分の息が松茸臭い。こうなってくると自分でも何かおかしいと思うようになってきた。しかし相変わらず毎日おいしく松茸の味噌汁と焼き松茸で幸せな食事をしている。
そして、とうとうそれがわかる日がきた。
その日は、起きると体がむずむずして外に出たくなった。
彼は京王線に飛び乗ると高尾山口に向かった。はやく高尾山に登らなければ、そう思うと電車の中を走りたくなる。それをこらえて、着いたとたんにホームに走り出た。周りで見ていた人は、トイレを我慢していて、飛び出したように見えたのではないだろうか。
彼は改札口を飛びだし高尾山を登り始めた。皆が行く一般道ではなく、少しごつい道だが、川にそった6号路と呼ばれている道を登った。頂上に行く手前で林の中に入り、下草がはびこった中を無意識のうちに登っていった。やがてたどり着いたのは、赤松林だった。彼が一番大きな赤松の根本に達すると、がさがさと下草をかき分ける音がして大勢の人たちが現れた。男も女も年寄りも若い人もいる。
どの人たちも松茸の匂いをプンプンさせている。見知らぬ人たちである。
彼らは思い思いに赤松の前で無言のまま立ち尽くした。
一番大きな赤松の上から烏が一羽、彼らの前に降りてきた。
いや違った。烏ではなく、烏天狗だった。
「育ったのう」
そう言うと、団扇をさっと振りおろした。
風は渦巻いて赤松の前に立っている人々の間を通り過ぎていった。
風が通り過ぎると、そこにいる人々の体から、洋服を貫いて小さな松茸の頭が出てきた。
また烏天狗が団扇を振りおろした。そのたびに風が当たった人間の松茸が成長した。
烏天狗が後ろを向いた。後ろにいた彼をめがけて団扇をおろした。
彼の体から生えた松茸がぐーんと大きくなった。
「今年は良くできた」
烏天狗が人間たちの前にくると、松茸をもぎ始めた。彼の前にも来た。
「お前さんのは特に立派だな、えらいぞ」
と褒めた。
烏天狗は彼の体から生えた松茸を引っこ抜いた。彼はあまりの気持ちよさに、身を捩じらした。松茸は烏天狗の肩にかけている袋に入れられていく。布の袋には烏天狗印の松茸とあった。
「松茸は赤松にしか生えぬ、人工につくることができぬが、人間を媒体にするとほれ、このようにできるのだ、人間に味噌汁を飲ませ人工栽培を行うわけである」
大きな袋に松茸が一杯になった。
烏天狗は、「皆ごくろうだった、また来年」と言い残し、空高く舞い上がっていった。
彼はやせ衰えてよろよろと高尾山を下っていった。他の人間たちもやせ細り、今にも折れそうである。
彼らは無言のまま京王線に乗った。
早く帰って味噌汁を飲もう、彼はそう思いながら窓の景色をうつろな目で見ていた。
美味しい松茸がまた食べられる。そうも思っていた。
烏天狗は彼から生えた松茸は桐の箱に並べ、特大のラベルを貼って二万円の値札を貼った。烏天狗印の松茸は京都の市場にならんでいた。
烏天狗印
私家版第四茸小説集「茸人形、2018、234p、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野県富士見町 2016-8-2


