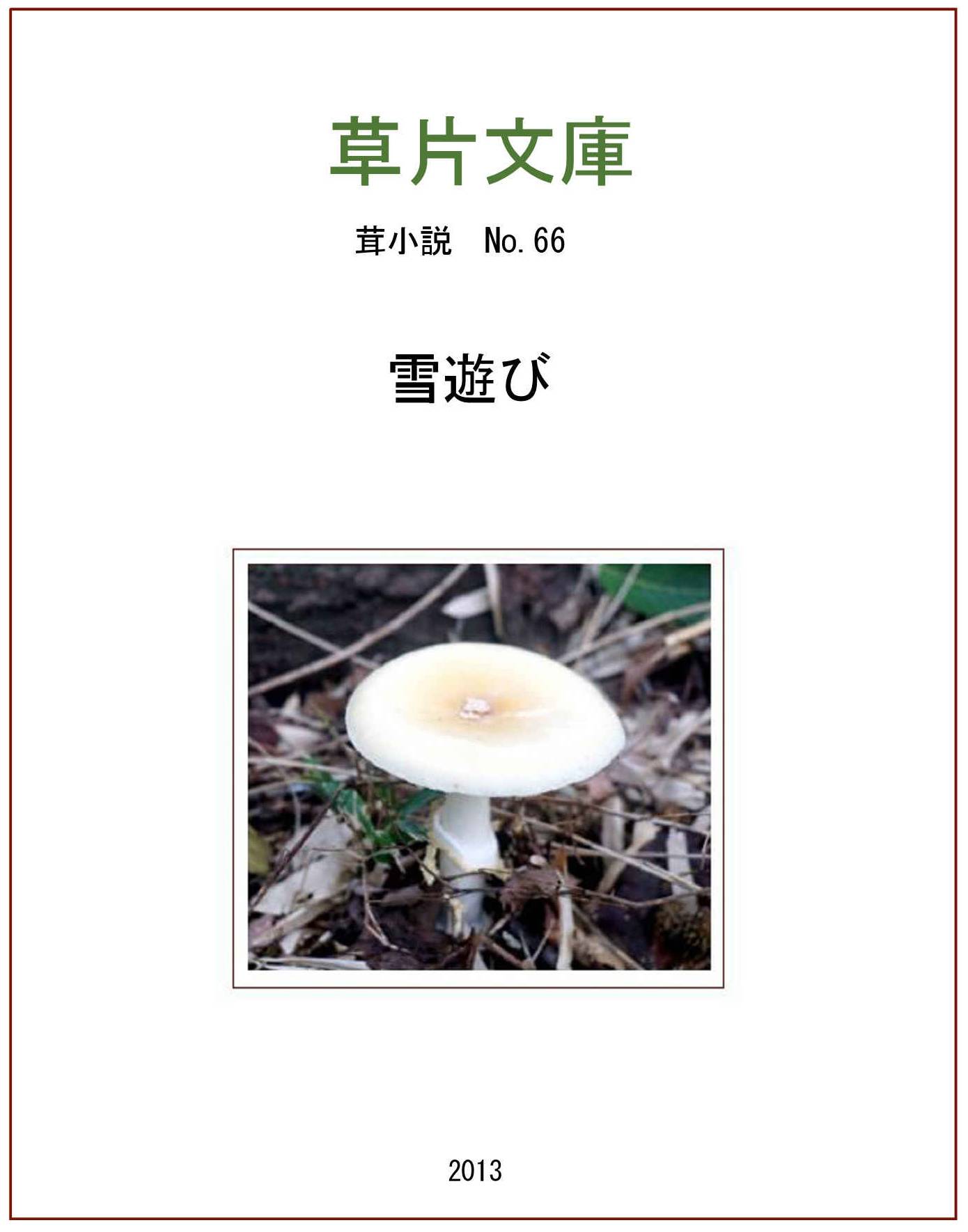
雪遊び
秋田のこの地方では雪が家の二階の窓まで積もる。毎年山の斜面にスノーモンスターが連なり、見事な景観を呈する。今年はもっとすごい。二十五メートルを超えるような高い杉の木がすっぽりと雪に覆われ、スノーモンスターどころではなく、雪の下に隠れてしまっている。それほど雪が降った。
その日は天気が良く、雪の斜面が日の光で真っ白に反射して、そのような中でサングラスもかけていなかったら、すぐ目をやられていただろう。
見事な景色を見ていたら、斜面の上の雪の表面がもこもこと動くと、すぽっと真っ赤なものが飛び出した。それを追いかけるように、次から次へ、いろいろな色のものが飛び出し雪の斜面に横一列にきれいに並んだ。
日生(ひなせ)信人はあわてて望遠レンズのついたカメラをむけた。見ると丈が十センチほどの小さな茸である。
どうして茸が出てきたのだろう。
茸たちは、あろうことに、一斉に雪の斜面をしゅーっと滑り出した。
その先を見ると、十メートルほど下の雪上に黒い丸が描かれている。そこに最初に到達した茶色の茸が小躍りをしている。茸たちは次々に到達して、最後の白い茸が黒い丸の中に滑り降りると、雪がいきなり破裂し、茸たちがふっ飛ばされ、斜面の上の元のところまで放り投げられた。
破裂した雪の中から真っ白な大きな茸が頭を出している。大きな茸は小さな茸がスタート点に落ちたことを確認してまた雪の中に潜っていった。斜面の上の小さな茸たちも雪の中にぎゅううともぐっていった。
何がおきたんだ、その様子を反対側の斜面から超望遠レンズで写真を撮った日生はカメラから目を離すと雪の斜面を見た。もうなにもない。
日生は雪の不思議な現象を捉えた写真集を数冊出している新進気鋭の写真家である。写真に写った現象のほとんどは説明のつくものであったが、彼の撮る写真はとてもきれいな上に幻想的であることから人気がある。写真の中には雪の物理現象として説明できないようなものもあり、専門家からも注目されていた。
今回、日生は小さな茸が滑りはじめたところは見逃していたが、大きな白い茸が雪煙を上げて出てきたところは捉えていた。だが茸は雪の塊にしか見えない。
「雪坊主の怪」とでもするか、彼は一人でつぶやいた。
ある地方では、目の前に雪坊主が現れ、目をつむった瞬間眉毛がなくなっていたという言い伝えがある。あるところでは、雪坊主を見た瞬間に頭の一部の毛が抜けて禿げたという話になっている。解説者の一人は雪上のつむじ風によるものではないかという説を出している。彼はすでにその現象をいろいろなところで写真に収めて一冊の本にしている。だが茸の姿を見たのは初めてだ。
今回は新しい現象を探すためいつもくる秋田に来た。この茸の出現にぶつかったのはラッキーだった。前の写真集に、雪の斜面にいくつもの小さなものが滑ったような跡を載せたことがある。小さく軽いものがすべったあとである。不思議なのは跡が突然現れていることだった。小動物なら足跡が残っているはずだがそれはない。斜面に突然現れ突然消えている。その写真集では雪の玉が何かの拍子にできて、転がり落ち消滅したのではないか説明した。それを雪玉の跡と名付けている。
ところが小さな茸が滑った跡だったことを知ることができた。それにしても冬に茸とは、幻覚でも見たのだろうか。
今回の山歩きでは、その茸に出会う前に、雪の斜面に幅の広い鱗状の跡が下の方までついていたり、ポコポコと深さ五センチほどの穴が続いていたりする現象も写真に撮った。そのほかにも、面白い形をした雪の盛り上がりや、雪の穴もあった。かなりの収穫で、雪坊主とともに一冊の本になりそうである。
竜(たつ)や龍というと水に住むのが通常だが、雪も水である。雪の中に竜が棲んでいてもいいだろうと文献を当たったがほとんどない。一つあったのは、池からあふれでた水にのって川を下り、海をぐるっと回って、北海道の川を鮭と一緒に上り、その結果、北海道の湖に住むようになった竜の話しであった。その竜はすっかり雪の世界が好きになり、雪の上を転げ回って遊んだという伝説である。
日光に反射するまだらの斜面。斜面全体が鱗のような模様で日の光に映え、それこそ竜の鱗のようであった。
日生はかなり満足して山を降りた。
今回も二台のカメラがフル稼働である。一台は昔ながらのフィルムの一眼レフカメラであるが、もう一つはデジタルの一眼カメラである。同じ会社のものなので、いくつもあるレンズは共通に使える。
宿にもどり、デジカメのほうで撮影状況を確かめた。動的なものはデジカメでしかとっていない。雪上の跡などは両方のカメラで写してある。竜の鱗のような模様がそれはきれいに撮れていた。
彼は明日東京に帰ることにした。フィルムカメラの結果を早く見たかった。上手く撮れていれば展覧会用のよい作品になる。フィルムの方が画像に味が出ることは間違いなかった。
「あれ、日生先生、もう帰るのですか」
帳場に言いに行くと、旅館の女将が残念そうな顔をした。旅館は何時もここと決めているので、女将とも懇意である。
「きれいなのが撮れたよ、次に来るとき、焼いたもの持ってくる」
「お願いしますね」
この旅館には彼の写した雪の写真がかなりの数飾ってある。それで宿賃も安くしてもらっている。もっとも彼の写真はこの小さな旅館の売り物にもなっているので、宣伝効果はかなりなものである。「日生信人、雪の写真ギャラリー併設」などと、旅館のパンフレットに書いてある。
日生は東京の笹塚にあるアトリエに戻ると、早速、現像室にこもった。いつものように時間をかけ慎重にフィルムを現像した。この暗室に置いてある設備は相当の投資をしたもので性能がいい物を集めてある。
彼はルーペをのぞき現像したフィルムを確認した。竜の鱗がシャープなものを数点ほど選び、連写した部分はすべて焼いて、その中からよいものを選ぶつもりである。
焼いたものをアトリエのデスクの上に広げると、なかなかの出来栄えで彼も満足のいくものであった。
写真の裏には、番号と撮影場所などのデーターを記し、サインを入れた。写真の番号と詳細をPCに整理していく。
そうやっていくと、いつものような雪坊主と思ったものが、どうやら違う様相が見えてきた。連写した一連のものを見ると、雪がもっこりもりあがり、大きくなって、雪を散らしている茸の像があらわになっていく。意外とはっきり写っている。まさに雪坊主だ。頭と胴体があるように見える。これは面白い現象だ。雪から顔を出した茸にみえるが、雪の季節に茸などがあるわけはないから、何かの現象だろう。雪の妖怪の一つとして売り出そう、そう思ったのである。雪坊主より妖怪雪茸がいい。これにしよう。
ちょうど画廊から四月の初めに一週間の個展の誘いがきている。今度の個展のタイトルはやはり、妖怪雪茸と雪竜を中心に考えることにしよう。画廊のオーナーに見せて意見をきこう。日生は久しぶりに心が躍る気持ちであった。
画廊「白」のオーナーの梅見栞も個展のタイトルに「雪竜と怪雪茸」と二つつなげることに賛成だった。この画廊は主に写真の作品を扱う画廊で、幻想的な写真家を集めていることから、かなりマニアックな連中に注目されている。
個展の前評判は上々どころではなく、いくつかの写真雑誌や新聞に紹介された。雪竜と妖怪雪茸は、かなり幻想性的な広がりのある写真で、今までのものより鮮明で、見る人を引き付けるよいものになった。
初日、日生はかなりの数の雑誌記者から取材を受けた。
次の日である。画廊に出勤してきた店員が、中ほどの壁に掛かっていた三枚の妖怪雪茸の写真が紛失しているのに気づいた。店員から連絡を受けた梅見が日生に電話で連絡してきた。警察にも届けはだしたということである。
マニアの一人がもっていってしまったのだろう。前にも盗難にあったことがある。画廊を閉めるときには確かにあった、と画廊の梅見も店員も言っていたが、日生は帰るときには立会っていない。彼は閉めるのを店にまかせて、途中から数人の雑誌記者ともに、話の続きをするため駅の喫茶店に入った。夜のうちに盗られたのだろうが、警察官が検証した限りでは、人が入った形跡をみつけることはできなかった。
写真のいいところは何枚も同じものを作っておけることである。連絡を受けた日生は新しいものをもって画廊に出向いた。
「ごめんなさい、先生、覚えている限りでは帰る時にはあったのよ」
写真を抱えてもってきた日生に梅見が申し訳なさそうにわびた。
「いいよ、これも宣伝になるからね、妖怪マニアかもしれないね」
日生は三枚を壁にかけた。
ところが次の日も同じことが起きた。やはり朝になると三枚の妖怪雪茸の写真だけ無くなっていた。二度重なると新聞社のかっこうのネタになった。
「二度も盗難」という見出しで、夕刊にかなり長い記事になった。
梅見は警備会社に依頼し、警備員を画廊内に常駐してもらうことにした。小さな画廊であるが、準備と事務のための比較的広い部屋があった。
ところが、またしても雪茸の三枚の写真は忽然と消えたのである。
これには警察も動いた。警察官が一晩、画廊の一角を重点的に見回った。それでもまた三枚の写真は消えた。日生はかなりの枚数の写真を焼き増ししなければならなかった。五日も同じことが続き、もう妖怪雪茸の写真を飾るのはやめることにした。
「密室、雪の茸の怪」と雑誌に紹介された。それからさらに不思議なことが起きたのである。
彼のアトリエから妖怪雪茸のフィルムが紛失したのである。
警察も協力的で、警察官がアトリエ近辺を見回ってくれたり、犯人の特定に結びつくことがないか、隈なく調査してくれてはいたのだが全くわからず、画廊での盗難と、アトリエでの盗難の犯人の糸口さえ見つからなかった。
「写真家のでっちあげ」などという三流週刊誌の記事まででてきた。もっともそのような雑誌にいちいち反論するような馬鹿な真似はしない。放ってある。
アトリエの盗難は心配である。彼には助手がいない。忙しいときに仲間が手助けにきてくれるのと、写真材料を入れている会社の従業員が手伝ってくれる。みな気のおけない連中である。通常アトリエは彼一人で管理しているのである。
盗難が起きてからは、誰かが必ずアトリエに泊まりにきてくれた。
その後、個展も無事におわり、かなりの評判を得たわけであるが、事件は解決しなかった。彼は密かに、原因は雪の茸にあると思っていた。あれは自然現象ではない。頭の片隅に本当の茸の妖怪と思いたいという気持ちがあった。
デジタルカメラに残っていた雪茸の像はフィルムのものほどはっきりしておらず、日生はもう一度あの画像、さらには映像を撮る計画を立てた。次の年の雪の一番多い一月から二月にかけ二ヶ月もの長い間、秋田の山の奥にいくことにしたのである。早くもあの旅館に予約を入れた。今春の個展での出来事を知っている女将は大喜びであった。
秋になると、寒い地方の高い山の頂上はもう白く染まり始める。秋田に行く前年の十一月末のこと、日生は長野の雪の山々を、重い装備を背負って縦断していた。山登りの専門家が行くような高い山ではなく、ほどほどの山であるが、すでに雪で埋もれている。何度か来ているので、山小屋のある場所は心得ているし、山登りが目的ではないので無理をすることはない。白馬に登っているとき、斜面に何かが一斉に滑って降りたような跡が八つあるのを見つけた。その跡の始まりのあたりに、かすかではあるが、小さな凹みが八つあった。穴に雪が積もった様に見える。何かが出てきて滑ったのではないだろうか。昨年の妖怪雪茸の現れた雪の上に見られた跡に似ている。
彼はすべった跡を追って下ってみた。十メーターほど降りただろうか。そこに大きな穴に雪が積もったような凹みが一つあった。写真を何枚か撮った。妖怪雪茸が飛び出した跡に似ていなくもない。
何かが雪の下に住んでいるのかもしれない。秋田の山で見かけたものの正体をぜひつきとめたい。来年の秋田が楽しみだ。
長野の山ではたいした収穫はなかったが、面白いものが一つあった。雪が三角のピラミッドのように盛り上がっているものを見た。高さは三メートルほどのものである。三つの面がきれいに平らになっており、日に当たって輝いていた。白い鏡のピラミッドである。なにがそうしたのか不思議な現象である。専門家は自然現象だというであろう。偶然に三角に盛り上がった雪の表面が溶けて、またすぐに凍りついて、風の具合などの関係で鏡のような面になったというに違いない。だが、雪の上に舞い降りた、異星人の宇宙船のようにも見えるし、雪の上に異星人のつくった合図のための装置にも見える。何とでも言えるのである。長野で撮った一番いい写真である。
その年の暮れである。秋田の予定は一月からであるが、年越しの雪の風景も写真に収めておきたいと思い、十二月中に旅館に入った。旅館のあたりはすでに雪が深い。
「日生先生、今年の個展はすごい評判でしたね」
女将は会う早々、個展のことを言った。
「うん、いろいろ苦労したけどね、知っていると思うけど、妖怪雪茸の写真は無くなってしまった。それで雪竜の写真をかなり大きな版に焼いて送っておいたけど、もう届いているかな」
「ええ、届いていますよ、お部屋のほうに入れてあります」
「女将さんにあげるつもりだよ、開けてください」
「うれしいー」
女将は彼と部屋までついてきた。日生は立てかけてあった写真を女将に渡した。
「額に入っているので、そのまま飾れるよ」
「素敵、サインはあるの」
「うん、いれてある」
「入口の一番いいところにかけます、これからのご予定は決まってますか」
「晦日は宿にいるけど、後は天気が良ければ山にかよいたいんだ」
「はい、わかってます、ここにカメラの機材がとどいてます」
女将は床の間の脇にある荷物を指さした。
「ありがとう」
「朝お弁当をお作りしますか」
「それもでかける前の日に頼むことにします、天気次第だから」
「はい、今日はどうぞゆっくりお湯を使ってください。おいしいもの作りますから」
「たのみます」
女将は雪竜の写真を大事そうに抱えて下に降りていった。
この部屋は二階のはずれにあって、必ずしも景色がよいわけではなく裏庭が見えるだけである。観光客にはつまらないかもしれないが、日生には庭の後ろの竹薮がとても興味のある景色であった。雪の積もった竹薮から雪女がでてくるのではないかと、彼は期待しているのである。本当に雪女がでるわけはないが、もやった蒸気だとか、何かの現象が人の形のように見えればそれでいいのである。それらしい写真が撮れれば、雪女のタイトルを冠した写真集をつくろうと考えていた。その部屋から竹薮を見たときの角度がよく、いつも見ていることができるので、彼には最も都合のよい部屋ということなわけだ。残念ながら、今までそれらしいものは現われたことがなかった。
宿についた次の日から雪になった。雪の降っている間はあまり撮影にはでない。
せいぜい宿の回りか、川沿いの道を歩いて面白い現象を探す程度である。雪が止み、青空が広がったその下の雪の景色の中に撮影にむいた現象が現れる。雪の表面がなだらかになっていることで、なにかがつけた模様がはっきりする。動物の足跡が不思議な絵をつくることもある。今までの写真はそう言った状況のときに撮ったものだ。
雪は三日ほど降った。その間はPCに向かって執筆をする。雪の怪異についてである。自分の撮った映像に見合った話を作っておくのである。後は窓から裏庭を見て、ときどこシャッターをきった。
夜、彼は宿の窓明かりに照らされている裏庭の斜面を見ていた。竹がしなり、ずいぶんと雪に埋もれているが、それほどの大雪ではなく、竹薮の中が見通せる。明日は写真を撮りにいけるだろう。
カメラの手入れをしながら窓をのぞいていると、裏庭の積もった雪の表面から雪煙がのぼった。すぐ収まったが、雪の表面が盛り上がり、もこもこと動きながら、竹やぶのほうに動いていくと、中に入り斜面を登っていく。やがて消えた。大きなもぐらが雪の中を歩いていくとあのようになるのではないだろうか。雪の中に何か住んでいるのだろうか。それが動物なのか自然現象であろうが、現場でそいつをつかまえたい。明日晴れたら裏庭も調べよう。
次の朝早く、日生は朝食を食べると、いつもはもってこないビデオカメラもリュックにいれた。フィルムカメラももったが、首からデジカメをつるした。瞬時を捕らえるにはデジカメでないと間に合わない。今度は本を作るための撮影である。日帰りで、いけるところに行くつもりになった。
「しばらくは晴れそうですよ、先生」、
女将が気を利かせて、昼のおむすびを用意してくれた。
その日は足慣らしのため、旅館の裏の山から奥の山にいくことにした。裏庭からは竹薮になっているので登ることはできない。宿から出て少し行くと山に登る道がある。道も雪に埋もれていて、すでに雪の斜面を歩く感覚である。かんじきをつけてないと沈んでしまう。
去年とは違い、今年の積雪は平年並みである。昨年よりは楽であるが、荷物かついでの登山はかなりきつい。
頂上に着くと、下のほうに宿の屋根がみえる。降りていけば途中から竹薮になり、裏庭にいきつく。そこから尾根づたいに登れば、もう少し奥の山にいくこともできる。日生はそちらに行きたくなった。このあたりは知っているところなので危険はない。彼は上を目指した。
ゆっくり歩いて、尾根を一つ越した。北側がなだらかな雪の斜面になっている。おそらく植林をしたばかりなのであろう、木々の頭が雪から顔を出していない。日生は尾根を迂回してその斜面を撮影するために反対側の山にまわった。斜面が見渡せるところにくると、荷物を下ろし撮影の準備をした。北斜面なので残念ながら光の調子は必ずしもよくはない。
三脚を雪の中に固定し、ビデオを取り付けた。首には一眼デジカメをつるし、万全の準備をした。しばらくここで待つつもりである。
二時間ほど雪が玉になって落ちる様子や、いきなり現れたウサギのビデオを撮ったが、特に珍しい現象はおきなかった。
十一時を回った頃であった。日の光が斜面の一部を照らした。全くの北斜面ではなく北東向きであったのであろう。狭い範囲だが明るくなった。彼はビデオのレンズをむけた。そのとき光の当たっている部分の斜面の上の一部から、一列に小さな雪の盛り上がりができた。彼はピントを合わせ撮影のスイッチを押すと、望遠レンズのついたカメラをかまえた。
「でた」思わず、声を出した。レンズの中で赤、黄、茶、白、いろいろな色の丸いものが雪の中から頭をだした。カメラで連写をし、ビデオのモニターを覗いた。
丸いものが雪の中からせり出してきた。ぽこっと飛び出したのは茸だった。
「何で茸なんだ」
小さな茸は一列に並ぶと滑り出した。ビデオでその様子を追った。滑り落ちた茸たちは斜面の下にくると止まった。そのとき、そこから大きな雪の盛り上がりが生じた。雪煙があがり、雪の固まりが割れると、中から大きな白い茸が現れた。その勢いで小さな茸は元のところまではじきとばされた。
「夢か」
日生は信じられなかった。ビデオを回してはいたが、頭は真っ白にちかい。
大きな茸は回転しながらふたたび雪の中に埋もれていった。その跡には少しへこんだ跡が残っただけである。あの妖怪雪茸は本当に茸だったのだ。
上に飛ばされた小さな茸も、回転しながら雪の中にもぐっていってしまった。妖怪雪茸の子どもである。茸の子供が雪の斜面で遊んでいる。
日生はビデオを再生してみた。確かに写っている。しかしこれを外に出しても、うまく作った映像としか考えてくれないだろう。どうしたら本当と思ってもらえるのだろうか。それともこの雪の白さと寒さに、光の具合で自分の頭の中がマジックマッシュルームを飲んだ時のようにおかしくなっているのだろうか。
考えていてもしょうがない。滞在中に誰かに一緒に来てもらって、この現象を見てもらうしか信じてもらえないだろう。
その日は遅くまでその場でカメラを構えていたが、同じことはおきなかった。
宿に戻り、女将に、
「妖怪雪茸がまたとれたよ」と報告した。
「よかったですね、でもまた盗まれないようにしないと、犯人はつかまっていないのでしょう」
女将はそう言った。
それから天気が続き、三日ほど同じところに出向いたが、同じ現象をとらえることはできなかった。
そこで場所を変えることにした、去年最初に妖怪雪茸を撮影した場所に行くことにした。宿の前の道を渓谷沿いに三十分ほど歩いたところから山間の道にはいる。そこから一時間ほど登っていくと、尾根にでて、尾根伝いにいくと綺麗な斜面をいくつもみることができる。そこの一つで出会ったのである。
彼は撮影装備を背負って出かけた。現場に着くと、前に撮影したところより、ずっと近くから撮影することにして、準備をした。
その日は残念なことになにも起こらなかった。風が起こした雪の吹雪を撮影できただけある。疲れたこともあり、一日休みまたでかけた。今度は撮影位置をもう少し遠くにした。
昼になり、もらってきたおにぎりを食べていると、斜面の上のほうがもこっと動いた。あわててビデオのレンズをかまえた。小さな茸がいくつもでてくるのだろうと待ちかまえていると、いきなり雪煙が間欠泉のように空に昇った。ビデオのボタンを押した。
地響きがした。三脚が揺れる。地震だったのかと思ったのだが。雪煙が収まると、そこに、とてつもなく大きな真っ白な茸があらわれた。雪の斜面を割ってそそり立った茸は、おそらく二階建ての家ほどの高さがある。それが、くるりと一回転すると、自分の方に顔を向けた、と彼自身は思った。
その危惧は間違っていなかった。前後がわからない茸ではあるが、明らかに彼を見た。大きな白い茸は雪の上に飛び出ると、雪をかき分けて彼の方に走ってきた。走るというのか、滑るというのかわからないが、ファインダーの中で大きくなってくる。
彼は怖くなって、三脚を抱えると、一目散に走り出した。後ろを見ると大きな白い茸が追いかけてくる。
尾根に出て渓谷沿いの道まで雪の積もった山道を駆け下りた。何度も滑りそうになり、後ろを振り返ると、白い茸がせまる。走って、走って、見慣れた宿の前を通る道にでた。それでも雪道である。足をとられながら懸命に走った。
宿の姿が見えてきた。もう少しだ。後ろを見ると、大きな茸もせまってくる。
宿の近くでビデオカメラから三脚をはずすと投げ捨て一目散に逃げた。
宿の入り口にきて、戸を開けて後ろを見ると、大きな茸が口をあけて食いつこうとしている。
彼は中に飛び込み、急いで入口を閉めると、宿の玄関の土間に転がり込んだ。
その音を聞きつけて女将がでてきた。
「あれ、日生先生、どうされました」
女将はけつまずいてころんだ彼を見た。あわてて起き上がった日生はやっとの思いで立ち上がった。
「ゆ、雪が」
言葉にならないまま、彼は無我夢中で靴を脱いだ。
「大丈夫ですか先生」
女将の声を後ろに聞きながら彼は急いで二階に上がった。
女将は玄関の戸を開けようとして外を見た。
「何だろうかね、雪が玄関をふさいでいるよ、若い衆呼んで、かいておいてくれないかね」
女将が奥に声をかけた。
宿の入口の前に、戸をさえぎるように雪が積もっている。
外のほうから何人かの男衆がスコップを持ってやってきた。
「この雪どこから落ちてきたのかね、屋根からかい」
不思議な顔をしている女将さんに一人が答えた。
「わかんねえな、屋根じゃねえよ、どっからか落ちてきたんだべ」
「日生先生が転がり込んできなすったわ、あぶなく埋もれるところだったようだよ」
女将さんが日生の部屋に行った。
「先生、入りますよ」
戸を開けると、日生は畳の上に寝ころがっていた。
「あれ、大丈夫かね、先生、怪我してませんかね」
彼はその声で目を開けた。
「うん、大丈夫、何とか助かった」
からだを起すと女将さんを見た。
「すみませんでしたね、あの雪はどこから落ちたかわかんないけど、先生が埋もれちまったりしたら大変でしたよ、でも何もなかったようでようございました、先生、湯にでも浸かってください、暖かいものを用意しますから」
女将は彼の手元に転がっていたビデオカメラと、デジカメを拾うとテーブルにのせて、「布団敷かせますから」と下に降りていった。
しばらくすると、動悸の治まった彼はテーブルの前に座り、ビデオを再生した。襲ってきた茸が撮れていた。真っ白な茸が雪煙を上げてやってくる。
しかし、これを見ても作りものと言われるだろう、どうしたら本当の映像だと信じてもらえるのだろうか。
何かが起きている。自分の妄想として片付けるのは簡単だが、ビデオを見ても、デジカメを見ても見たとおりに映っている。なぜ襲ってきたのか分からない。個展の写真やフィルムの消滅を考えると、人間に知らせてはだめだという警告なのか。みんなこいつらの仕業と考えると筋が通る。
まず落ち着かなければ、湯で温まろう。彼は湯に入りにいった。
湯から出ると、女将が別の部屋に暖かいものを用意しておきましたと、案内してくれた。食事をする部屋に、温かい鍋がテーブルの上に置いてあった。茸汁である。それにビールが添えられている。
「すみませんでしたね、でもあんなにたくさんの雪、どこから落ちてきたのかわからないのですよ、部屋は布団敷かせておきました」
女将さんが侘びを言った。
「いや、気にしないでください。間一髪でしたね、何か落ちてくるような気がして、あわてて、玄関に飛び込みました、三脚を道に落としたようだ」
彼は話をあわせた。妖怪雪茸が襲ってきたとは言えない。
「後で、若い衆に拾いに行かせますよ、それで、今日はどうでした」
「だいぶいい映像が撮れましたよ」
「明日から、また吹雪くようですよ、山の奥に行くのは危ないからできませんね」
「そうですか、また書き物でもするよ」
「そうですね」
女将はビールをついで出ていった。
もう自然現象では片付けられない。彼は茸鍋を突いた。
その晩、女将が言ったとおり雪が降り出した。宿の裏山が部屋の明かりで白く浮き出ている。ふと彼は夜の雪の世界は昼間より不可思議な現象がたくさん現れるのではないだろうかと考えた。夜だと映像や画像にとらえるのは難しいかもしれないが、見てみたい。宿の庭なら怖いことは起こらないだろう。
夜の九時ごろである。彼は厚着をするとデジカメを首にかけ、玄関に行き帳場にいた番頭さんに裏の庭を見ると言って長靴を借りた。
裏庭にまわり、山の上に広がる竹林の中をのぞいた。かなりの高さの雪が降り積もっている。ときどき竹林の中に上から雪がバラバラと落ちてくる。枝に積もった雪が落ちているのだろう。
何か出てきそうな雰囲気がある。想像しながら見ているだけで面白い。上の方で白く煙ることがある。竹に積もった雪が落ちるためだ。
彼は竹林の中にはいった。長靴がずぼずぼと雪に埋もれてしまう。
目の前を何かが横切った。
ふっと見ると、奥の方の竹の枝に赤い目玉が二つ見える。動物のようだ。すると、ばばばばば、ばりばりと大きな音がして、彼の背の倍もあろうとおもわれる妖怪雪茸が雪の中からあらわれた。そいつは彼を見ていた。
彼はとっさに逃げた。妖怪雪茸は大きくなりながら追いかけてきた。いそいで玄関先に回って、宿の中に飛び込んだ。また、間一髪だっただろう、どさっと言う音が聞こえた。彼が飛び込むと帳場にいた番頭さんが驚いて飛び出してきた。
「どうしました」
「いや、また雪が落ちてきて」
番頭さんが玄関の戸を開けると、ごぞっと雪の固まりが玄関になだれこんできた。
「おや、先生、またですね、どこからこんなにたくさんの雪が落ちてくるのかね、不思議だなあ、先生についてきたみたいだ」
番頭さんは若い連中を呼びに行った。
自分の部屋にいた女将さんもでてきた。
「先生大丈夫ですか、先生は雪に好かれているみたい」
と笑った。
真夜中、日生はうなされて目を開けた。
目の上の天井が雪に覆われていた。いや天井が雪でできていた。彼が横たわっていたところは湿った土の上であった。手で土に触れてみたが寒くはない。
土がだんだん温かくなってくると、彼の周りの土の中からいくつかの茸が顔を出した。茸たちは飛び上がると、彼の目の上の雪に穴をあけて上にのぼっていった。
降り積もった雪の外に出たようで、茸の数だけ穴があき、光が見える。彼は身をちょっと起こした。雪が持ち上がり雪の斜面から彼は顔を出した。
上を見ると、雪のつもった山の斜面を茸たちが滑り降りてくるところだった。茸が彼のところまで来ると、彼はがばっと起き上がった。雪が盛り上がって、雪吹雪が舞った。茸たちが弾き飛ばされ、斜面の上のほうに落ちた。
彼は立ち上がると、子供たちが無事着いたことを見て、また雪の中にもぐっていった。彼はまた雪の中で横たわった。
あくる朝、日生はなかなか起きてこなかった。女中さんが襖を開けると、日生は布団のなかで死んでいた。医者が呼ばれ、死因は心筋梗塞と判断された。本当の原因が分からなかったからである。
その後、彼の突然の死は新聞にも報道され、宿屋の女将のコメントがのっていた。
日生先生は毎日のように雪山に入られて、いろいろな映像を作られていたようです。その日も私が作ったおにぎりをもって、機材を担いで出かけられました。お疲れになってお帰りになり、突然お亡くなりになりました。相当ご無理をなさっていたのでしょう。すばらしい写真もたくさん残されていて、これから楽しみにしていたのに本当に残念です。とあった。
ここに注目すべき記述がある。「映像を作った」という女将の言葉である。日生が死んだことを聞いてあわてて宿に集まった写真家仲間がPCを見たところ、茸が雪の上をすべって下におり、そこに大きな茸、妖怪雪茸が突然現れ、はじきとばされた子供の茸はまた斜面の上にもどるという映像があった。さらに日生が書いた説明文に、積もった雪の下は妖怪の住む世界と書かれていた。
それを見た仲間は彼がその映像作ったと言った。それを聞いた宿の女将が、頭の中にそれがこびりついて、つい記者にそう言ったことから書かれた文なのである。日生はそれを聞くとがっかりするだろう。
しかし、その映像は日生の代表作になった。雪遊びをする茸の子と母である。宣伝にも使われ、彼の名前はアニメーション作家としても有名になった。しかし未だに、どうやって作られたのかその手法は解明されていない。
雪遊び
私家版第四茸小説集「茸人形、2018、234p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2015-9-3


