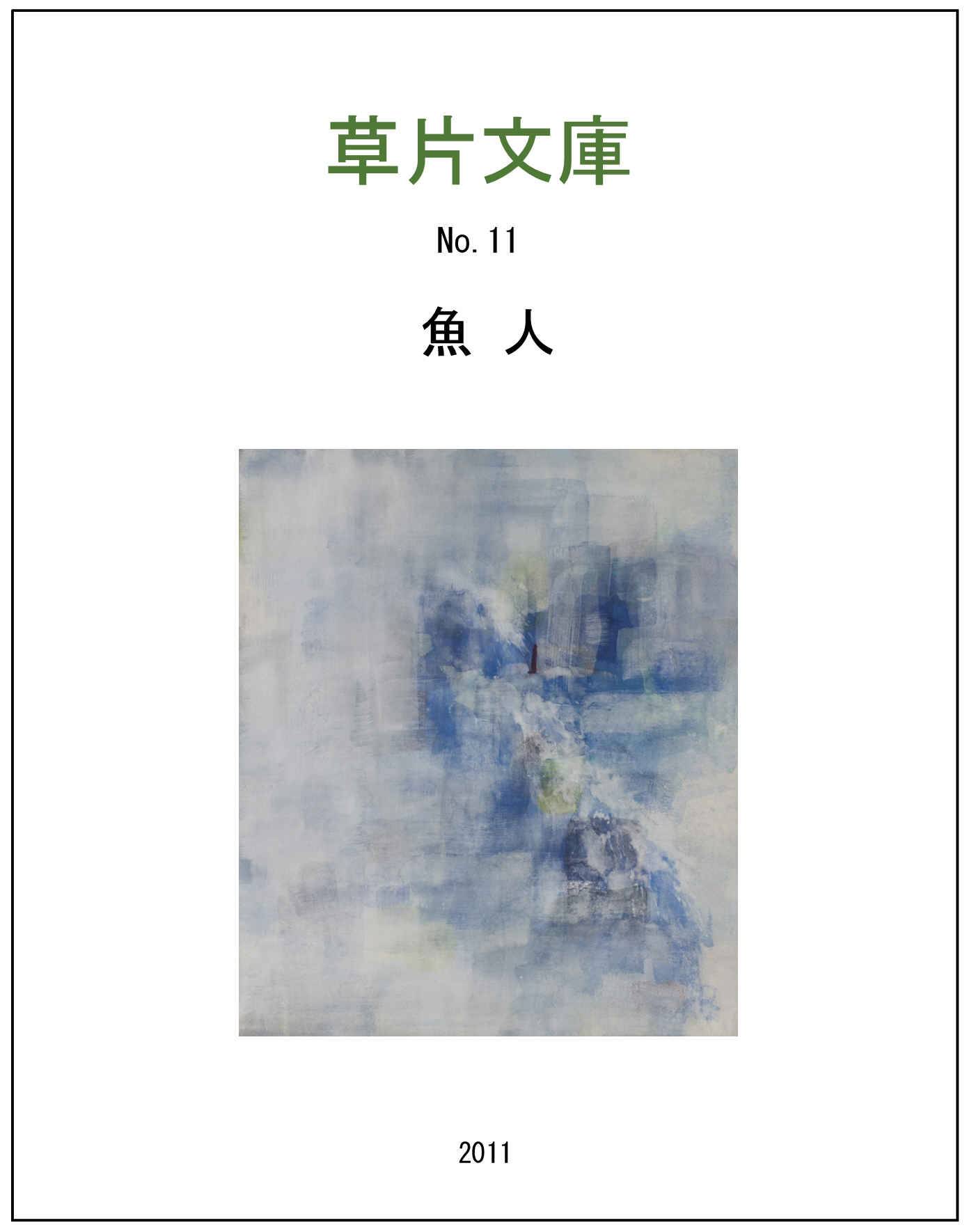
魚人
魚人(うおと)は机から顔を上げ、開けてある窓の外を見た。
闇の中に白いものが動いた。
まただ、と思う。きっと眼が疲れてきたのだろう。
両親を起こさぬよう、音を立てないようにして二階から降り、裏口から外に出た。
夜中の三時。空を仰ぐと星々が今にも落ちて降ってきそうだ。輝きがきれい。
受験勉強もあと少しだ。
防波堤の上まで歩いた。穏やかな海が黒くうねっている。風が頬を打つ。
父は一人で細々と漁を続けている漁師である。一人息子の魚人は大学に進み研究の道に入ろうとしていた。
海の中を自在に身をくねらす魚たち、岩に這い上がるカニの群れ、冬に訪れるアザラシの子供たち、生まれたときから海の生き物たちに囲まれていたこともあり、海の生命を研究してみたいと思うようになったのは不思議ではない。
魚人は漁をすることがいやではなかった。むしろ好きだった。漁師の父のあとを継ぐか大学に進むか迷った時期もあったが、父も母も大学に行くことをすすめてくれた。
魚人は沖を見つめた。水平線の一点に白いものが浮かんだ。白い霧のような塊は一心に魚人を見ているようにみえた。
魚人が住んでいるのは北の国の小さな港町である。昔は石炭の積み出しやらでにぎわったところであり、今でも漁港というより小さな商船が出入りする港である。漁業を営むものはさほど多くない。港の外れに十数艘の漁船が停泊しているのが見られるだけである。その一艘が父親、潮人(しおと)の船である。十トンに満たない小さな船である。
ここは、雪が下から降ってくるといわれるほど風が強いところである。吹きあげる冷たい風が雪を運んできて路や屋根に積み上げていく。見渡す限り白い世界になる。もうすぐその季節が来る。
しばらく海を見ていた魚人は海に背を向けた。背後にスーッと白いものがよってきているのを感じている。いつもそうだ。白いものが自分を見ている。
家にもどると、机の前に座って参考書を開いた。大学を出るからにはさらに上に行こうと考えていた。そうなると、将来父親のあとを継ぐことも無く、この町で暮らすことはなくなるだろう。
都会なみの町が、この村から電車で二時間ほどのところにあり、そこではそれなりの仕事を探すことはできる。ところがその電車が二時間に一本程度と少なく、通うのは大変である。この町は内陸の町とは隔離されている。
開いた参考書に魚から人までの脳の絵があった。人の脳がいかに発達しているかを示すものである。魚人は疑問に思った。確かに大きくなり、しわがより言葉が話せるようになった人の脳はすごい。だが、最も単純だと書かれている魚の小さな脳は海の中でのあの俊敏な動きを司っているのだ。こんなに小さな脳であの身のこなしを指令している。海の中にもぐると、キョロットこちらを見る魚の眼はいろいろなことを訴えかけてくる。高校生の魚人には脳の複雑さを理解することはまだできていないが、魚の生活はよく知っている。今最も流行になってきている脳の科学をしてみたい。そう思っていた。
また窓に白い影が映った。いつも魚人を見ている。それがこの町なのかもしれない。
受験の日、魚人を奮い立たせるかのように雪が降った。東京でも雪は降る。しかしこのような大雪ははじめてのことだということである。多くの大学で開始時間を遅らせる処置をとった。魚人の志望していた大学も開始を二時間も遅らせた。雪が吹雪く中、魚人はむしろ元気に泊まっていたホテルをでて入試会場に向かった。多くの受験生が意気の上がらない中で、雪は魚人にとって友であり、気持ちを引き締めるものであった。雪が町から魚人についてきた。
試験が終わったときには雪が止んでいた。だが雲はたれ薄暗い。
彼は飛行機で家に戻った。両親はただいまと帰ってきたにこやかな魚人の顔を見ると、ご苦労さんとしか言わなかった。魚人もうなずいただけであった。
母が用意してくれた遅い食事をとると、二階の自分の部屋に行き、電気を消してベッドに横たわった。長かった受験生活が終わったが実感はなかった。四月まで父親の仕事を手伝おう。結果がだめだったら、親父のあとを継ぐ。そう心に決めていたこともあり、気持ちはさっぱりしていた。
部屋の窓から暗い夜空に星が瞬いているのが見える。今日は雪が降らなかったそうだ。疲れているはずの魚人に眠りが訪れなかった。
魚人はコートを羽織ると裏口から外に出た。雪を踏みしめ海岸に向かった。
空には満点の星が輝く。だがいつものように風は強く海は荒れていた。水平線から白いもやもやしたものが湧き上がる。いつものだ。白いものがこちらを見ているのがわかった。顔らしきものはないが、そこには魚人を見ている目がある。
冷たい風が彼の髪の毛の隙間を吹き抜けていく。これが故郷の海だ。魚人はしばらく水平線を眺めていた。やがて白いものは消えていった。
あくる朝早く、今日は休めという父親に、一緒に行くと魚人は父親の小さな船にのった。
漁場につくと、網をかけ、別のポイントに行きまた仕掛ける、いくつか仕掛けた後、昨日仕掛けておいたところにいって引き上げると、ニシン、カジカ、カレイ、カスベなどの雑魚が入っていた。たいした値になる魚ではないが、家族が食べていくには十分であった。ときどき、マカスベなどが上がると知り合いの飲み屋に届けたついでに一杯やってくる。親父はそんなことを楽しみにしながら、小さな漁を営んでいる。海に危険はないとはいえないが、親父のように無理をしない漁師は一生を静かに終えることだろう。どのような職業でも危険は伴うものである。
魚人は網をあげるのを手伝った。
「魚人、今日はいいな、こんなのがはいっていた」
引き上げた網の中から、潮人が赤っぽい魚を持ち上げた。
「アカソイじゃ、白尾にもっていってやろう」
白尾は地元のすし屋である。
「刺身もうまい」
潮人は発泡スチロールの箱に魚を入れ氷をかけた。
こうして午前中早くには漁を終え港に戻る。昼は自宅ですませ、午後は網の繕いや船の手入れなどをする。潮人は拾った流木を削り、魚に見立てて作り上げるのを趣味にしている。もともと物を作るのが好きで、芸大の彫刻科を目指していたが失敗し、家を継いだ。そのようなこともあり、魚人が東京の大学を受けると言ったときも、当然のようにうなずいてくれたのである。
漁の手伝いは楽しいものであり、魚人も船の操り方などもすでに覚えた。
二月の終わりの日、漁から帰った魚人は大学に電話をした。合格発表の日である。受験番号をプッシュすると、味もそっけもない音声が流れた。彼は受かっていた。父親も母親も合格を祝ってくれた。
東京の山手線の内側にある大学の入学式の日、桜の咲く時期にもかかわらず、粉雪がまった。桜の花びらに雪が止まっているのを見るのは東京の人たちにとって驚異だった。しかし、それは魚人を迎える歓迎の印だったのだろう。それとも魚人についてきたのか。それから四年間の大学生活の間、東京で雪をみることが多かった。
下宿は大学の近くの古びたアパートを選んだ。多くの学生がアルバイトに汗をかき、流行の服に身を包むなかで、魚人は最低限の生活用品をそろえ、地味な格好で大学に通った。
大学での講義は新しいことだらけで魅力があった。興味のあることでもあり、先生たちの講義の内容は苦労することなく頭に残った。
半月も経つと大学での生活にも慣れた。
そのようなある日、夜も更けたアパートの窓に、白いものがぼんやりと現れた。ガラスにもやもやとした白い影が映るとその中の目が部屋の中をのぞいた。
魚人は故郷の海の彼方に浮かんだ白いものを思い出し、アパートの窓を開けた。もやっとした白いものはすぐ隣のアパートの屋根の脇にいた。窓から冷たい空気が部屋の中に流れ込んだ。潮の匂いも紛れていた。
あわてて窓を閉めると、白いものはスーッと消えていった。
もうすぐ五月の連休になる。東京に残って短期のアルバイトをしようかと思っていた魚人は、潮の匂いにつられ実家に帰ることを思いつかせた。故郷でアルバイトをするのも東京でするのも同じだと思ったからでもある。今頃、ヒラメ、カレイ、サクラマスや海老の漁が盛んだろう。手助けを求めている船もあるだろう。そのほうが、交通費を考えても実入りはいい。
連休の前の日に魚人は故郷にもどった。
裏口から家に入ると父親の潮人は拾ってきた流木を削っていた。
「何だ、玄関から入ればいいのに、どうだ、東京のほうは」
「うん、面白いよ」
母親の久実はカレイを煮ていた。魚人の好物である。
「カレイか、いいな」
「今日、父さんがたくさん獲ってきてね、漁協にもずいぶん持っていったのよ」
「よく育ったカレイがたくさん獲れたな、こんなことはめったにないぞ」
父親が木を削りながら言った。
久実が海老を入れた味噌汁と、ご飯をテーブルに並べた。
潮人も作業場から台所に来た。
「早く荷物を上においてらっしゃい」
久実の声にせかされて、魚人は自分の部屋に上がった、まだ一月しかたっていないのに、久しぶりの思いがある。
キッチンに下りると、テーブルの上がいつもと違いにぎやかだった。
「今日はな、この時期だがソイもとれたんで刺身にしてみた。まるで魚人が帰ってくるのを祝うようにたくさん獲れたんだ」
「そう、今日は神棚にお礼のお神酒を上げたのよ」
魚人が神棚を見ると、今まで無かった木彫りの神像があった。ロングドレスの長い髪の女性のような形をしている。
「あれは何」
魚人が聞くと、
久実は声を出さずに笑っている。
「わからん、網に引っかかった流木を乾かして、彫ってみたら自然とできちまった。なんか、ありがたそうなので、あそこに置いてみた」
潮人が頭を掻きながら言った。
「親父の作品か、そりゃありがたいな」
「なにいっとんだ」
みんな笑った。
その夜、窓を開けておくと五月の気持ちのいい風が入ってきた。魚人は堤防に行ってみた。海は凪いでいた。月明かりが水面を照らし、きらきらと金粉が舞っているようだ。
水平線のかなたに白くボーっと光るものが上がってきた。いつものだ。物理学も大学の講義の一つだ。まだ学び始めたばかりではあるが、これは自然現象とは違うのではないかと思う。では何かといわれると、分からないというしかない。
白いものは水平線のあたりでふらふらとゆれている。しかも自分を見ている。魚人は冷たい海にすむ生き物と今では親しみを感じていた。
連休の間、船に乗ることはなかったが、漁協の市場で雑用をこなした。小さな市場といっても毎日水揚げされる魚の管理には大変な作業がある。魚人はその時々に必要な部署にいって手伝った。漁協の仕組みもよく分かったし魚の顔も覚えた。
連休が明け大学にもどると本格的に勉強に取り組み始めた。
大学の生物学の講義は遺伝子のことが多かった。分子生物学という領域である。この大学には脳と動物のからだの働きの講義は無かった。次第に今の生物学と自分の気持ちにずれを感じてきたことも事実であった。それでも二年、三年と進むと、彼は先生方の注目を集めはじめた。生物学への熱心さばかりではなく、実験手技を学ぶ実習において、実に器用に厄介な実験をこなしていたからである。三年になると自分の行く道を選ばなければならない。ゼミの先生を選ばなければならない。彼は若手で神経細胞の発生を研究している先生につくことにした。
彼はネズミの胎児から採取した視覚野の神経細胞の培養をすることになった。基本技術を教わった後、彼一人で細胞の培養を試みることになった。一回目、二回目は培養途中で神経細胞は死滅してしまった。
三回目のことである。培養している神経細胞を顕微鏡で覗いているときであった。
コンピューターの画面には、培養中の神経細胞の突起の先端が絶えず動いている様子が映し出されている。だんだんとそうやって伸びていき、うまくいけば他の神経細胞の突起と接触するはずである。魚人は倍率を下げ全体像を見た。神経突起は不明瞭になったが、たくさんの神経細胞が瞬きをするようにうごめいているのを観察することができた。
その中に、白いもやもやしたものが現れた。
魚人は、あ、かびだ、失敗した、と思った。
培養はよほど熟練しないとうまくいかない。雑菌、カビが入るとあっという間に培養している細胞が死滅する。
顕微鏡の倍率を上げた。しかしカビや雑菌のようなものは見あたらなかった。
培養室が急に冷えてきた。温度管理は厳しく行われているので気のせいかとも思ったし、温度の上昇は問題だが、少し寒くても問題がない。魚人は気にしなかった。
また倍率を上げてみた。白いもやもやしたものが動いた。白いものの中に、魚人は目があるのを見た。人のような目がディスプレーの画面をみている魚人をみているような気がした。そのとたん白いものは消えていた。冷たい潮風を眼に受けたように感じた。
「どうだ」
急に後ろから声がした。
先生が後ろに立っていた。
「はい、カビが入ったと思ったのですが、大丈夫のようです」
先生は慣れた手つきで顕微鏡を操作し言った。
「こりゃすごいよ、もうこんなに突起が伸びている、シナプスをしているような場所もある」
シナプスとは神経の突起と相手方の神経細胞で作られる構造で、それがあると、神経連絡ができたことの証拠になる。
「こんな短期間でここまでいったのはどうしてかな。君の作った培養成分の表を見せてくれないか」
先生は彼のノートをみると、驚いたように言った。
「ほー、抗生物質はいれなかったのか」
「はい、最初は無しで頑張ってみようと思いました」
「そのほうが、いいのだろうな、そういうやり方もある、ただ、雑菌混入に関してはそうとう気を使わなければならないな」
「はい」
「おや、神経成長因子もいれていないのかい」
「はい、はじめ自然にはどのように伸びるのかみてみたかったものですから」
「それでもこんなに伸びるのか、不思議だな。シナプスをしているかどうか、電子顕微鏡で調べてみるといい」
「はい」
魚人は数日後、電子顕微鏡でそれを確認した。
大学生活は順風満帆であった。その暮れ、ゼミの学生四人と先生で合宿に行くことになり、スキー場のある近場の新潟湯沢に宿をとった。
宿についた日は天気が良かった。その日は軽くスキーを楽しみ、食後、論文読みをして温泉につかった。
次の日はうって変わって雪がちらつき始めた。5人は三つのリフトを乗り継ぎ、山の頂上から滑り始めた。途中天候がこんなに変わるのかと思われるほど風が強くなり、雪は激しくなり視界が悪くなった。雪に慣れている魚人はみんな一緒にゆっくりと下山することを提案した。ちょっとスキーを得意とする先頭の一人が先に滑って行ってしまった。止めるつもりで先生が後を追った。残りの三人はかたまってゆっくりと声をかけながら降りた。
ふっと前を見ると、白いものが魚人の前を横切った。
魚人は今はじめてはっきりとその姿を見た。白い髪を長くたらした白装束の女だった。赤い目を魚人に向けて笑った。一瞬だったが、魚人を昔から見つめる目であることがわかった。雪女、ふとそんな言葉が脳裏をかすめた。
吹雪の中、後ろをすべる二人が見たはずはなく、魚人はそれを誰にも言わなかった。
ゲレンデに帰りついた三人は先に降りた二人がもどっていないことを知った。天気のことをよく知る宿の人も心配していた。方向を間違えて滑っていったとすると、途方もないところに行ってしまっている可能性がある。夜になっても戻ってこなかった。
宿の人は温泉に使ってからだを温めてよく寝るようにと進めてくれたが、三人はなかなか寝付くことができなかった。
明け方近くになってからだろう、三人はやっと眠りに落ちた。
魚人は夢を見た。一人で行ってしまった学生と先生はゲレンデとはずいぶん離れた谷の下のほうで雪に穴を掘って身を寄せ合ってすでに冷たくなり始めていた。
その場に魚人の目の前を横切った雪女が二人の前に現れた。雪女は二人の男を抱きしめ、寛さん、道夫さん、と先生と学生の名を呼んだ。すでに朦朧としていた二人の男の目が見開かれた。二人の目には白い顔をした長い髪の女性の姿が映った。そのとたん彼らの心臓がコトッと音を立てて止まった。
はっと、眼を覚ましたところに、温泉の番頭さんが二人が見つかったことを知らせに来た。
「残念ですが、お二人は谷におち、お亡くなりになっていました」と番頭は言った。
この出来事は魚人の研究生活に終わりを告げるものであった。指導の先生がなくなり、他の先生に引き取られた魚人はそこでそれなりの成果は出し、よい成績で卒業研究を終えたが大学院に行くことの気力を失っていた。
卒業式の日もまた大雪になった。
朝、卒業式会場に行こうとアパートを出ると、空に白くもやもやしたものが浮かんでいた。それは雪の合間から魚人を見ていた。
スキー場での出来事は、雪女が故郷に帰るように仕組んだのではないかと魚人は思っていた。
魚人は漁協で正式に雇われることになった。夏休みや長く休みの取れるときに漁協でアルバイトをしていたこともあり、漁協としても大変喜んだ。大学をでたのにもったいないとの声も聞こえてきたが、魚人は至極満足であった。もちろんのこと、それ以上に父親と母親は喜んだ。
魚人は漁協につとめながら父親の船を手助けすることもできると考えた。
働き始めて数年が過ぎた。その間に母の久実が突然の脳溢血で倒れ、帰らぬ人となった。あまりにもあっけなかった。
それから一年、ようやく母の死もいたし方の無いことであろうと諦めがついた頃である。魚人は漁協の理事長の娘と見合いをした。理事長の娘は温和な気の利く、魚人より一つ年上の女性であった。理事長のほうからもちかけてきた話で、潮人はもちろん、魚人もその気であった。その娘とは何度か漁港や魚市場で顔を合わせていた。話をしたことはなかったが落ち着いた良いお嬢さんだと魚人は思っていた。とんとん拍子で話はまとまり、来年の春に結婚することになった。
正月の気分が抜けた一月の終わり頃である。神棚に酒をささげ、安全の祈りをあげ、潮人は言った。
「魚人、明日は仕事が休みだな、どうだ、漁に出るか」
「ああ、行こう、天気はよさそうだし」
「この木で彫った神さんをここにおいてから、魚がよく獲れるようになったんだわ」
潮人が手を合わせた。
魚人は神棚の上の父親が作った像を見た。その像も魚人を見た。雪女に似ている。
魚人は家にもどってから白い女が現れなくなったのは、ここにいていつも自分を見ているからではないかと思った。
あくる朝暗いうちに雪を踏みしめて港に行き、潮人の船である雪見丸に乗った。風は相変わらず強いが天気は悪くない。足元がすくわれてしまうかと思うほどの突風がいきなり吹く。顔が凍りつきそうに冷たい。
とも綱をとき船のエンジンをかけた。父親が操舵をし、魚人は甲板に立った。港から出て沖にすすむにつれて町の明かりが遠のいていく。
かなりの沖合に来たときである。ぐらっと、船が揺れた。大きなうねりが漁船を持ち上げて、また船は下がった。うねりは港のほうにすすんでいく。
潮人が叫んだ、「地震だ、今のは津波だ」
ラジオの音を大きくすると、アナウンサーが海岸に津波警報がでていることを言っていた。それにしても、組合から船にたいして連絡がなかったのはどうしてだろう。いつもであれば何らかの連絡があった。
潮人は無線で組合の事務所を呼び出した。なかなかでない。忙しいのであろうか。
地震の場合、沖に出ていたほうが安全である。町は今騒いでいるのであろう。
やっとつながったようで、潮人が話をしている。
潮人が魚人に言った。
「津波はたいしたことはなかったそうだぞ、それでも市場の一部が海の水につかったとよ、震源地は日本の領域ではないらしい、津波が来るとは考えていなかったようだな、組合にもその連絡はなかったそうだ」
その時、突風が吹いた、船がぐらっと再びゆれると、いきなり雪が横殴りにたたきつけてきた。
「親父、雪だ」
「え、あんなに晴れていたのに」
空には星が全く見えない。厚い雲に覆われた天から雪が吹き降りてくる。
「港にもどるにはちょっと危ない、地震の余波が来る可能性があるな。しばらくここにいたほうが安全だな」
そういいながら潮人はエンジンを止めた。
船はあれから大きく揺れることも無く、ただたたきつける雪に寒さを感じるだけである。それはいつものことであった。
もう一時間経つ。無線でやり取りをしているが、まだ大きな津波の危険があるという。その時、強い風が湾の方向から吹きつけ、船が沖に流され始めた。潮人はあわててエンジンをかけ湾にもどろうとしたが、エンジンがかからない。
魚人も操舵室に入った。そうやっているうちに風に押された雪見丸はどんどん沖に流されていく。黒い雲に覆われた空から、大粒の雪が強い風に乗って吹きつけてきた。
無線も途切れがちになった。潮人はだまったまま無線の調整をしている。あわてても仕方が無いだろう。食料はそんなに積んでいないが、数日は大丈夫である。そのうち天気もよくなるであろうし、地震の心配もなくなるであろう。
しかし、空の厚い雲はもう昇っているはずの太陽の光など一筋も通すことなく真っ黒に垂れ下がっている。船はどんどん流されていく。船ががたんという音とともに大きく持ち上げられ、急に落下した。潮人が頭を打ち付けてうずくまった。
「大丈夫か、親父」
魚人は頭を押さえている潮人を船室に入れ、手当てをした。かなりうったようで、頭の脇が切れて膨れている。消毒をして包帯を巻いた。
「すまんな」
潮人は船室に横たわった。
「大丈夫、船のほうは俺がやるから」
魚人は操舵室にもどって無線を聞いた。雑音しか聞こえてこない。二つ目の波の方が大きかったようだが港は大丈夫だろうか。こちらからの呼びかけは全く届いていないようである。
ふと燃料計をみると、全く燃料が無い。さっきの衝撃でタンクが壊れたようだ。おそらくタンクの中は海水で満たされているのだろう。
後は、無線が頼りである。しかし、バッテリーの残りも多くは無い。無駄にはできなかった。暖をとらなければこの寒さに耐えることはできないだろう。
船室に下りると、父親は眠っているようであった。また操舵室にもどった。
今あせってもしょうがないだろう。様子を見るしかない。
腕時計を見ると、出航してから八時間が経つ。それにしてもこの暗さはおかしい、地震にしろ、この天候にしろ、今までの経験では想像がつかない状態である。
魚人も少し寝ておくことにした。操舵室の床で壁に寄りかかって眼を閉じた。
魚人は部屋の寒さに気づいて目が覚めた。
暖房が完全に止まっている。親父はと船室を覗くとまだ寝ている。というより意識が無いのではないのかもしれない。呼びかけてみたが起きる様子が無い。打ち所が悪くないとよいのだが。降りていくと、潮人は軽いいびきを掻いている。毛布を重ねてかけ、何枚か操舵室に運んだ。外の雪は変わらず激しく、視界は全く無い。
周りが冷え始めた。無線をつけてみた。通じる様子が無い。
これで終わりなのか、とも魚人は思うようになった。毛布に包まると壁に寄りかかった。まだ寒くは感じていない。
いつの間にか魚人も寝てしまい、気がついて船室を覗くと、白いものがうごめいていた。潮人と添い寝をしている。白い手が潮人の額のところを押さえている。魚人が船室にあわてて下りると、白いものはスーッと消えていった。
「親父、起きてくれ」
魚人は潮人を揺さぶった。しかし、潮人は眼を開けようとはしなかった。
「親父」
父親に毛布をかけなおして魚人は操舵室にもどった。外は変わりなく吹雪だ。体力の消耗を防ぐため動かないようにするしかないだろう。
また、毛布に包まって壁に寄りかかった。
その時、ガツーンと音がして船が大きく揺れた。
あわてて外を見ると、雪はやんでいて、砂浜に船が乗り上げている。雪の降り積もった島である。こんなところに島があるはずは無い。空は黒い雲が覆っている。
操舵室から甲板にでると、砂にめりこんだ舟先の浜に白装束の女が立っていた。
長い髪の女は赤い目で魚人を見た。
雪女だ。雪女は宙に舞い、船先に息をはきかけた。船はびりびりと冷え、凍りついた。その拍子に砂浜から海に押しかえされ、ふたたび漂流を始めた。
舳先では雪女がフィギュアヘッドのように立ちすくみ魚人を見ていた。
魚人は凍りそうな足を引きずりながら操舵室にもどった。時の感覚がなくなり、頭の中も朦朧としてきた。
魚人は操舵室の壁によりかかって、毛布をかきよせると自分を包み込んだ。やがて、ぐらっと揺れ、床に倒れた。
操舵室の戸が開いた。雪女が入ってきた。赤い目を魚人に向けると、おだやかな表情で船底への戸を開けた。潮人が毛布をかぶって寝ている。
雪女は潮人の脇で横になると、日に焼けしわのよった額に白い手を当てた。
潮人が見る見る凍っていく。潮人は幸せそうなおだやかな顔になる。
魚人は船室の雪女が見えていた。
雪女の顔が母の顔になり、母の手が潮人の額に当てられ、暖かい思いが潮人のからだの中に満ちていくことを感じていた。あれだけ仲のよい夫婦であったのだから。
魚人は自分の脇にも雪女が来るのだろうと思っていた。来てほしいと思っていた。
雪女の手で静かに凍っていく自分を思うと幸せな気持ちになった。
魚人は潮人の脇から立ち上がった雪女に向かって最後の力を絞って声をかけた。
「俺のところにも来てくれ」
雪女は宙をすべるようにして船室から登ってきて、魚人の脇に来た。
雪女は白い衣装を脱ぎ捨てると、魚人の前に立った。
白い肢体は氷のようにきらきらと光り、豊かな乳房は白い液体をたたえていた。成熟したからだが魚人の目に眩しく映る。
雪女は脱いだ衣装を魚人にかけた。
ほんのりと暖かかった。
雪女の赤い目が魚人を見ていた。
雪女が触れたとき、雪女に声をかけられたとき、魚人が死ぬときである。
だが、雪女はただ見ていた。
魚人はいつのまにか夢の中にいざなっていった。
魚人が目を開けると見知らぬ人たちに囲まれていた。彼の乗った船はロシアの領土といわれる島に流れ着いていた。
その後、からだが回復した魚人は日本に送り返された。火葬にふされた潮人の骨も一緒に帰った。それは奇跡の生還と新聞に大きな見出しでとりざたされた。
魚人が国にもどって見たものは津波で壊滅的な状態になった自分の町であった。漁港は破壊され、多くの家が流されていた。彼の家ももちろんなかった。婚約した漁協の理事長も娘も命を落としていた。
国が建てた仮住まいの住宅に入った魚人は、壊れた防波堤に行った。
瓦礫が散乱しているが、遠くの水平線、海は変わることはなかった。
この町の再建には途方もない時間がかかるだろう。
魚人はまず何をしたらいいのか、考えがまとまらなかった。
ふっと見ると、壊れた堤防のがれきの中に、潮人が作った木彫りの女神が引っかかっている。
彼はしゃがんで手を伸ばし,女神を拾い上げると砂を払った。
あの雪女だ。親父が作ったんだ。
雪女は自分を助けてくれた。なぜだろう、これからその答えを見つけなければならない。こうなることを知っていた雪女はこの町を復興させることが望むところであったのだろう。親父の願いでもある。
魚人は雪女に託されたことを悟った。
父親の作った雪女の像をにぎりしめ、魚人は仮住まいに帰っていった。
魚人
私家版雪女小説集「雪女、2015、222p、一粒書房」所収
表紙日本画:山内佳子


