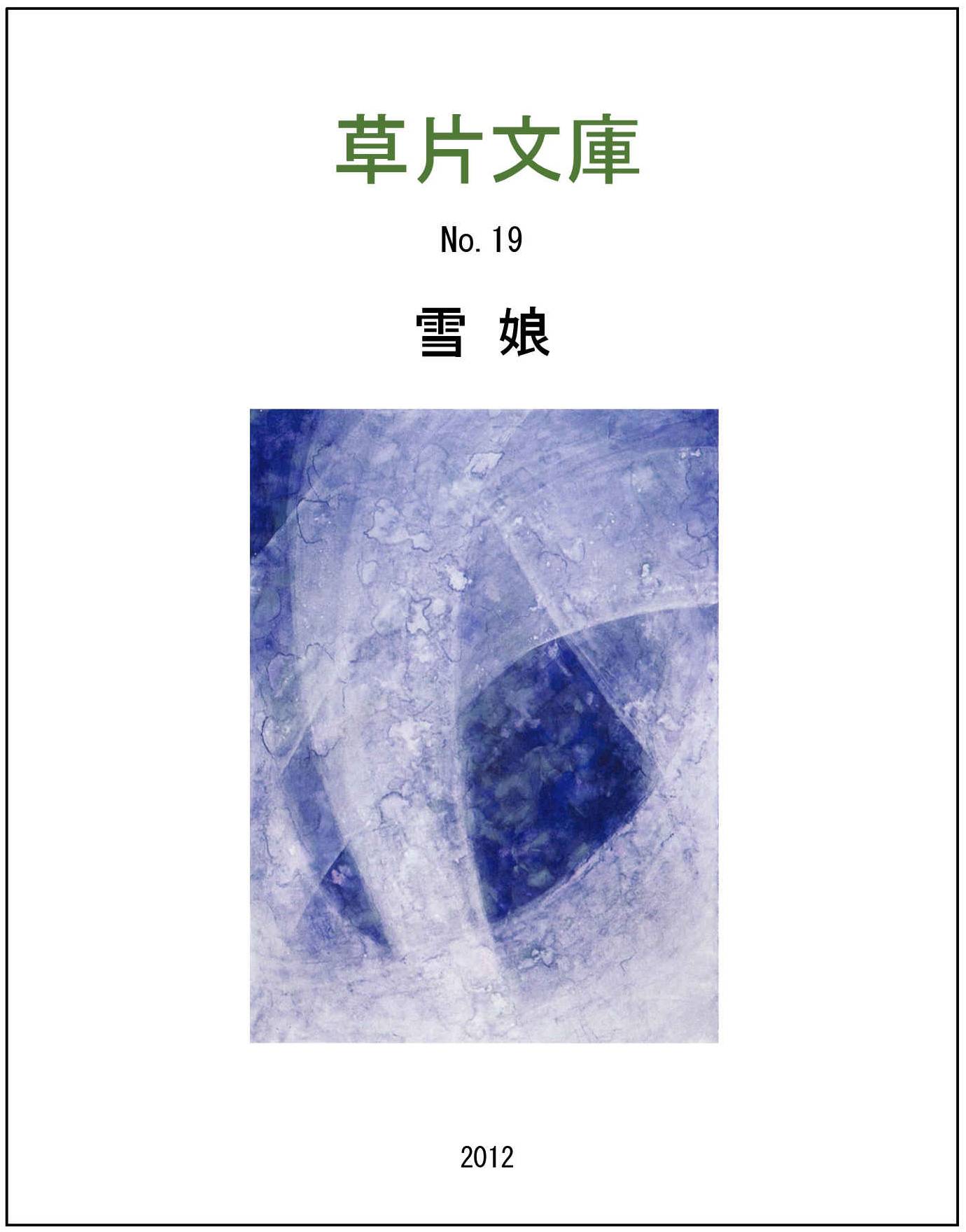
雪娘
雪の多いこの町で起こった不思議な光景である。
その娘は雪が降ると現れて、街角の石に腰掛けて広場を見ていた。
町を行く人々は、雪娘と呼んで噂をしていた。しかし、誰一人として声をかける者はいなかった。
雪娘はいつも猫と遊んでいた。こんな寒い日に猫が外にいるわけはないのに、いつも違った猫がそばにいて、雪娘は猫に話しかけていた。
「雪のお料理しましょうね、にゃんは何が食べたいの」
「蕗の薹を塩づけにしましょうね」
誰もこのつぶやきに耳を傾ける者はいない。
雪娘は町の駅からいつも一人で出てくる。
雪の降った日の、朝の十時より少し前になると、美良野(みらの)駅の出口の扉が開き、赤い長靴を履いて、白いふっくらとした毛皮のコートを着た色の白い娘が出てくる。誰もどの電車から降りたのか気がついた者はいなかった。というより、その時間帯に電車はないはずである。そういえば、大雪で電車が動いていないときにも、少女は小さな駅舎からでてきた。にもかかわらず誰も不思議とは思っていなかった。
雪娘は駅の前の広場を横切って、最近整備されて北欧風の建物が立ち並ぶ通りを歩いていく。しゃれたカットパーマの店の角を曲がって、多くの観光客が訪れる「時の広場」にやってくる。
その広場にはその町を有名にした時計台がある。
広場の中央に数本の白樺が植えられている。白樺に囲まれて小さな八角形の屋根をもつ小人が出てきそうな白い壁の家が見える。高さがほんの一メートルほどの小さな家だ。緑色の屋根の上には風見鶏がついていて、時おり風でくるっと動く。その小さな家が一時間ごとにオルゴールの音と共に、上へ上へとせり上がり、十メートルにおよぶ塔になり、先端の白い壁から四方に向けて不思議な動物たちが顔を出して、時を告げるのである。
動物たちはすべて設計者が考え出した想像上のもので、百種類にも及び、一度に四匹が顔を出すが、その組み合わせはランダムである。町ではその動物たちのフィギュアーを売り出す計画や、全部の種類の写真をとった人には北欧への旅をプレゼントするというキャンペーンも考えているという。
時が来れば大雪の時でも雪をかき分けその塔が現れ時を告げる。それがこの町の観光名所になった。設計者は雪の重みにも耐えるからくり構造を地下十メートルの空間につくり、その苦労話は多くの旅の本に掲載されている。
今、時計の塔がオルゴールの音と共にそそりたち、四種類の動物たちが顔を出して十時を告げたばかりであった。
娘は広場の前のカフェの脇にある石のオブジェに腰掛けると、大きなくりくりした黒い目を時計台に向けていた。
時計台がゆっくりと下がってきて、元の小さな家になった時、茶トラの猫が何処からともなく現れて、娘のそばでおちゃんこをした。
雪娘は猫の目を見た。
「今日は何をご馳走しようかな」
トラ猫は娘の大きな黒目を覗き込んだ。猫の目に娘の長いまつげが映っている。
「今日はつくしんぼの佃煮のお茶漬け」
トラ猫はジーッと娘を見ている。
遠くでその様子を見ていた旅行中と思われるカップルは、少女と猫の写真を撮って、微笑んでいる。「旅の雑誌に投稿しようよ」女性のほうが男性に言っている。
「うん、いい光景だな」
男性と女性はデジタルカメラの液晶画面を覗き込んでいる。
女性が顔を上げ、カフェの前を見た。
「あれ、女の子どこかに行っちゃったよ」
「ほんとだ、猫もいない」男性も顔を上げた。「もう一枚撮っとくのだったな」
「ちょっと追いかけてみる」
女性が娘の居たところに走っていったが、首を横に振った。
「いないわあ」
「しょうがないよ」
男性もカフェの前に歩いてきた。
「コーヒーでも飲んでいこう」
「そうね」
カップルはカフェに入った。
マスターらしき男がカウンターからでると、水を持って注文をとりにきた。
「ブレンドのコーヒー」
「はい」
注文を聞いて戻ろうとするマスターに男がたずねた。
「今、その前の石に女の子が腰掛けていましたね」
「ええ、いつもこの頃の時間になると来るのですよ」
「猫を連れてくるの」
「どうでしょう、いつも違う猫なんで、みていると猫はその日によって歩いてくる方角が違うんですよ」
カウンターに戻ったマスターはコーヒーの用意を始めた。
「女の子は何処から来るのです」
「さ、わかりません。何度か声を掛けたことがあるのですが、こちらを見ようともしないんです。猫とだけ話をしているんですよ。うちとしては、お客さんのようにあの子と猫に惹かれて店に入っていただけるので、大変感謝しているんです。ケーキを持っていってあげたのですが、首を横に振るだけでした」
コーヒーが運ばれ、カップルは飲みながらデジタルカメラを取り出し、写したものを液晶画面に呼び出した。
男はボタンを押しながら言った。
「おかしいな、無いよ、女の子の写真」
コーヒーを口に運びながら女が答える。
「最後に写したものを出せばいいのよ」
「そうしているんだけどね」男はカメラを見せた。
そこには石のオブジェ、それに、オブジェの上を見つめる猫しか写っていなかった。
娘は駅の前を横切って駅舎の戸を押し開けた。猫は隙間から駅の中に入ると、娘の後を追った。駅には誰もおらず、駅員も奥で仕事をしている。
娘は猫に話しかけながらホームに入った。
娘が山のほうを見つめていると、白い霧が線路に沿って駅のほうに漂ってきた。
「来た」
娘は猫に声をかけた。
トラ猫は娘を見た。
白い霧は駅のホームを埋め尽くした。
霧の中から真っ白い手が二本でてくると少女と猫を一緒くたに抱えあげた。
「猫ちゃん」
娘は始めて猫を抱き上げた。
「お母さま」
娘がそういうと、娘と猫は霧の中にすいこまれ、白い霧は線路に沿って元に戻っていった。
山のふもとにくると、白い霧は空に上り女の姿になった。
少女と猫は白い女に抱えられて山の中腹を飛んでいく。
雪が降ってきた。
雪が激しくなるにつれ、白い女は勢いを増し、雪に覆われた高い山のいただきを目指した。
この山はこの辺りでは最も高い山で、夏でも頂上付近に雪が残っていた。
白い女は山のいただきの窪みに少女と猫を降ろした。
猫は嫌がりもせず、雪の上で少女の足にこすりついた。
白い女が窪みの脇の雪の降り積もった表面に手をかざすと、雪の塊が崩れおち、岩屋の入口がぽっかりと口を開けた。
娘は開いた岩屋の中に入っていく。猫も後を追った。
白い女も岩屋に入り、再び雪の塊で蓋をした。入口を閉めたにもかかわらず、ほんのりと岩のトンネルは明るかった。
「今日の猫はどこの子なの」
白い女が聞いた。
「はいお母さま、駅の反対側の広尾さんのおばあさんが飼っている猫だと思います。名前はオトラといいます」
「そうかえ」
茶トラの猫は少女と一緒に、大きな部屋に入った。
部屋の中ではいろいろな模様の猫が、白い衣装の女たちの膝の上にのって顔を見上げている。
「オトラ、こっちにおいで」
娘の母親が呼ぶと、それまで娘のそばで見上げていたトラ猫は、ひょこひょこと白い女についてく。部屋の中では白装束の年かさの女が二匹の猫に話をしている。
「叔母さま、広尾さんのオトラです」
「おーそうかい」叔母と呼ばれた女が顔を上げ、トラ猫を見た。
トラ猫はその女に近づくと、ニャーゴと鳴いた。
「ここにいるのは、町のはずれの酒巻さんのシロと、町長さんの娘さんのチビじゃ」
トラ猫は他の猫と鼻をすりあわせた。その後、三匹はその女の目をずーっと見つめていた。
「それではお願いします」
娘の母親はその場を離れると、少女のところにもどった。
「さあお部屋にいきましょう」
「はい、お母様」
少女は白い女の後をついて部屋を出ると、洞窟の奥に進み、少女の部屋と思しき小部屋に入った。
そこには、小さな白いベッドがあった。娘はベッドに腰掛け、母親はそばの椅子に腰を下ろした
「楽しかったかい」
「はい、町の中はここと違ってきらきらとものがあります。あの時計台を見ているととても楽しい」
「猫たちはなんと言っておいでだい」
他のところの猫もここに来たいと言っていましたが、人間のことをよく知っている猫たちを選びました。選ばなかった猫たちにも、この猫たちが戻ってからお話を聞くようにいいました」
「そうです。それでいいのです。この町の猫への指導はこれで終わりです。次の猫集めは、来年の秋が来てからです」
「はい」
少女はベッドに横たわって、今までの町でのことを思い出していた。
去年行った小さな島の村にはたくさんの猫がいて、みんなついてきた。村の人がみんなで面倒を見ていた猫たちから一匹を選ぶ事は出来なかった。たくさんの猫がこの岩穴に来て、雪娘のベッドにたむろし、雪娘は嬉しい一日であった。猫たちの顔をなでながら一晩を過ごした。
今年は美良野の町の猫を連れてくる役目をもらった。
この地方の雪女は、子どものころにいくつもの役割をもらいながら大きくなっていく。この七歳の娘は来年になると山の動物たちから人間と動物たちの違いを学ぶことになる。
しばらくすると、白衣装の女たちと一緒にいた猫たちが、雪娘の部屋に入ってきた。一匹、二匹、次々と入ってきて、小さな部屋は猫だらけになった。広尾さんのおばあさんのオトラもいる。
猫たちはめいめい好きなところで身づくろいをしたり、伸びをしたり、丸まったりしている。オトラがベッドの上に飛び上がり、雪娘の枕元にきた。
「オトラ」
雪娘は猫の顎をなでさすった。
オトラはのどを楽器のようにごろごろいわせて目を細めた。
「なにを教わったの」
オトラは声を出すことなく答えた。
「ヒトが死にそうなときに、おれたちが何をすべきか教わったよ」
「なにをするの」
「そばにいる人によってちがうんだと。そのときその人が安らかに死ねるようにするんだ」
オトラは雪娘の脇で丸くなった。
「そう、むずかしいのね、私達雪女も、雪の中で死んでいく人を幸せにしてあげるのよ」
「おれら猫は家の中で死んでいく人を見守るのだそうだ」
オトラは髭を震わせて、ふすっと鼻息をもらした。
「そうね、猫ちゃんたちは人間にくっついてるものね」
広尾さんのおばあさんは、オトラが帰ってこなくて心配しているだろう。明日の夜は帰してあげる。雪娘も眠りについた。
雪娘が眠りについたころ、母親は白いロングドレスを身にまとうと岩屋をすっと抜けていった。
吹雪く中を無謀にもスキーに出かけた若い男が道に迷い、谷底に落ちて、雪の中で死にかかっている。
雪女は美良野の上を通って反対側の山にむかった。
空に舞あがり、町の駅を少し越えた住宅地の上に来ると、一軒の建物の中で寂しそうにしているおばあさんがいた。飼猫が帰ってこなくて心配して寝ることができないのだ。
明日になれば帰りますよ、そう呼びかけて、雪女は飛んだ。その声が聞こえたのか、老女はコタツでうとうととはじめた。
雪女はゲレンデのある山を越して、谷の底で雪に埋もれている男を見つけた。スキーは落ちたひょうしに折れてしまい、左側の足もねじ曲がっている。若い男はもうほとんど意識が無い。雪女は男の目の前に立った。男の目は閉じられ、まつげが凍りついている。
雪女の細く白い指が男の目に触れた。男は目の前に高校生の頃の恋人が立って微笑んでいるのをみていた。今日、温泉宿で帰りを待っている女性ではない。女性遍歴を多くもつこの若い男は初めての彼女と一緒の時が一番幸せだったようだ。
色の白い、少しポチャッとしたかわいらしい女の子が高校の制服姿で男の前で恥ずかしそうにたっている。多くの女の子が騒いでいるルックスのいい勉強の出来たこの男子生徒がまさか自分を選んでくれるとは思っていなかったといった表情である。その頃、スタイルがよくてきれいな女の子が回りにたくさんいるのに、彼はこの無口な目立たない娘を好きになったのだ。しかし高校を出て女の子は東京で就職し、それきりになっている。地元の大学に入った男はいろいろな女の子に囲まれて有頂天の日々を送ってきてこの日を迎えたのだ。
女子生徒は目をつぶって彼の唇に自分の唇を合わせた。彼も彼女をそうっと抱きしめた。ましゅまろみたい。ふっと彼の顔に笑みが浮かんだ。そのとたん、男の心臓がことりと音を立てて止まった。
脳の中では暖かい幸せが満ちて、男のからだは凍っていった。
役目を果たした雪女は空に舞い、美良野の町を横切って岩屋に戻った。町の上を飛んだ雪女は猫のオトラのおばあさんが布団に入ってやっと眠りについたことを知った。
朝になると、雪娘の部屋で寝ていた猫たちは部屋を出て、雪女たちの集まっている部屋にやってきた。
雪女の膝に上がると、猫たちはじっと女たちの目を見た。猫は人間たちの習性を雪女たちから伝授され、人たちがいかに死を恐れているのか知るのである。
夕方になると、雪女たちが猫を連れて少女の部屋にやってきた。猫たちは部屋に入ると、少女が服を着かえて出かけるのをおとなしく待った。今日は八匹の猫がいた。
「それじゃお願いね」
少女の母親は岩屋の出口まで猫と少女を送ってくると、出口をふさいでいる雪塊をふっと息を掛けて飛ばした。
外では雪が舞っており、もう明るくてもよい時間ではあるが暗く沈んでいる。猫たちに教えを説いた雪女たちも見送りに外に出てきた。
雪娘の母親は白い霧になると、娘と猫たちを包み込んだ。白い霧は風に乗り、線路の上を飛んで美良野の駅に来た。
駅舎から、雪娘が出てきた。猫たちも後をついた。
雪娘は駅の前の広場を横切ると住宅地に向かって歩いた。猫たちも後をついて歩いていった。町の人たちは猫たちがぞろぞろ歩いているので何事かと振り返った。
今日の雪娘の姿は町の人たちには見えなかった。
最初の家は市長さんのお宅だった。チビは家の戸をカリカリと掻いた。
家の中で大きな声がした。「チビが帰ってきた」市長さんの娘さんの声だった。戸が開くと、お嬢さんが飛び出してきてチビを抱き上げた。
「どこに行ってたの、心配させないで」
お嬢さんは他の猫たちがいるのにも気づかず戸を閉めると、チビを抱いて奥に入ってしまった。
少女は残りの猫たちを連れて歩き出した。
今度は酒屋さん、酒巻さんのうちだ。
酒屋さんに来ると、この寒いのに入口の戸が少し開いていた。
シロは両方の前足を戸にかけて押し開けた。とたんにお客が来た時のベルがなった。
「はーい」
酒巻さんの奥さんが奥からでてきた。
そこでシロを見つけると、大声で「お父さん、シロがもどってきましたよ」
大きな声で叫んだ。
どたどたと二匹の猫を抱えた主人が出てくると、猫を下ろしてシロをつまみあげた。
「おー帰ってきたか」
怒ったような声の調子と目じりの下がった顔とはまったく釣り合わない。
二匹の猫もシロを見上げてにゃあああと鳴いた。
シロの兄弟たちだった。
少女はその様子を見るとまた歩き出した。飯野さん、原さん、鈴木さん、日野さん、久谷さんの家に猫が戻っていって、最後にオトラの広尾さんの家に向かった。
広尾さんの家に着くと、オトラは台所のガラス戸によじ登って、お昼の支度をしているおばあさんに向かってにゃあと啼いた。
「あ、おとらちゃん」勝手口が開くとおばあさんが顔を覗かせた。
おばあさんの顔はくしゃくしゃになった。
オトラは一目散に勝手口から中に入った。
「どこにいってたんだえ、ほら、今ごはん作ってやるで」
家の中からはごとごとと猫のご飯の用意をする音が聞こえた。
雪娘は頭の中で猫に向かってバイバイというと、深く空気を吸ってふうーっと吐いた。霧が雪娘を包み始めた。時間が少しかかったが、白い霧は雪娘を覆い隠した。
雪娘は始めて自分で霧を作ることができた。顔が丸く膨らんで、とても嬉しそうに笑った。
霧に包まれて雪娘は空に上り、風に乗って岩屋に戻っていった。
雪の塊に手をかざし、開きなさいと命令をした。雪の塊が動いて岩屋の入口が開いた。入口を開けるのも始めて自分でできた。雪娘はうなずいた。
「お母様、もどりました」
奥に向かって声をかけた。
雪娘の母親が奥から出てきた。
「ご苦労様、自分で飛んで帰ってきて、自分で入り口を開けましたね、よくやりました」
「はい、もう独りで外に行くことができます」
「そうね、これからはいろいろなことを勉強してもらいますよ」
雪女の母親は、少女を皆のいる大きな部屋に連れて行き、雪女の一族に、
「この子も来年は八つ、今日のお勤めは全部自分で出来ました、これからはこの子を雪女として教えてくださいな」と言った。
「はいはい」
雪女たちは大きくうなずくと、目を閉じて、雪の山、雪の町、雪の海をみはっているのであった。
一週間後である。美良野の新聞に、コタツに入ったまま亡くなったおばあさんの脇で茶色の飼猫が添い寝をしていたことが小さく報じられていた。
母親からそのことを聞いた雪娘は岩穴からでると、霧を作り、町にいった。
広尾さんの家に行った。
「オトラ」と呼ぶと、家の中から虎猫が雪の中に出てきた。
「オトラ、これからどうするの」
茶色のトラ猫は雪娘にこすりつくと、ことばに出さず伝えた。
「おばあさんのお嬢さんが結婚して静岡にいる。猫好きで自分をつれて帰るということだよ。漁港は猫たちが気ままにすんでいるところなんだ」
オトラは静岡での生活を楽しみにしていた。
「よかったね、オトラ」
トラ猫は目を輝かせてニャーと啼いた。
その港町の猫たちに人のことを教えるのも楽しみだとオトラは言った。
「さよなら、オトラ」
雪娘はオトラの頭をなでると、暗くなった町の空にのぼっていった。
あと数年すると、雪娘は雪女としての役割を果たさなければならなくなる。
だけど、雪女のすることを教わりながら、しばらくは、どこかで猫たちを岩屋につれてくることになる。
オトラのいる港町にいくかもしれない。
雪娘は岩屋にもどった。
「明日は襟裳のほうから猫をつれてきておくれね」
「はい、おかあさま」
雪娘は自分の部屋にはいっていった。
雪娘
私家版雪女小説集「雪女、2015、222p、一粒書房」所収
表紙日本画:山内佳子


