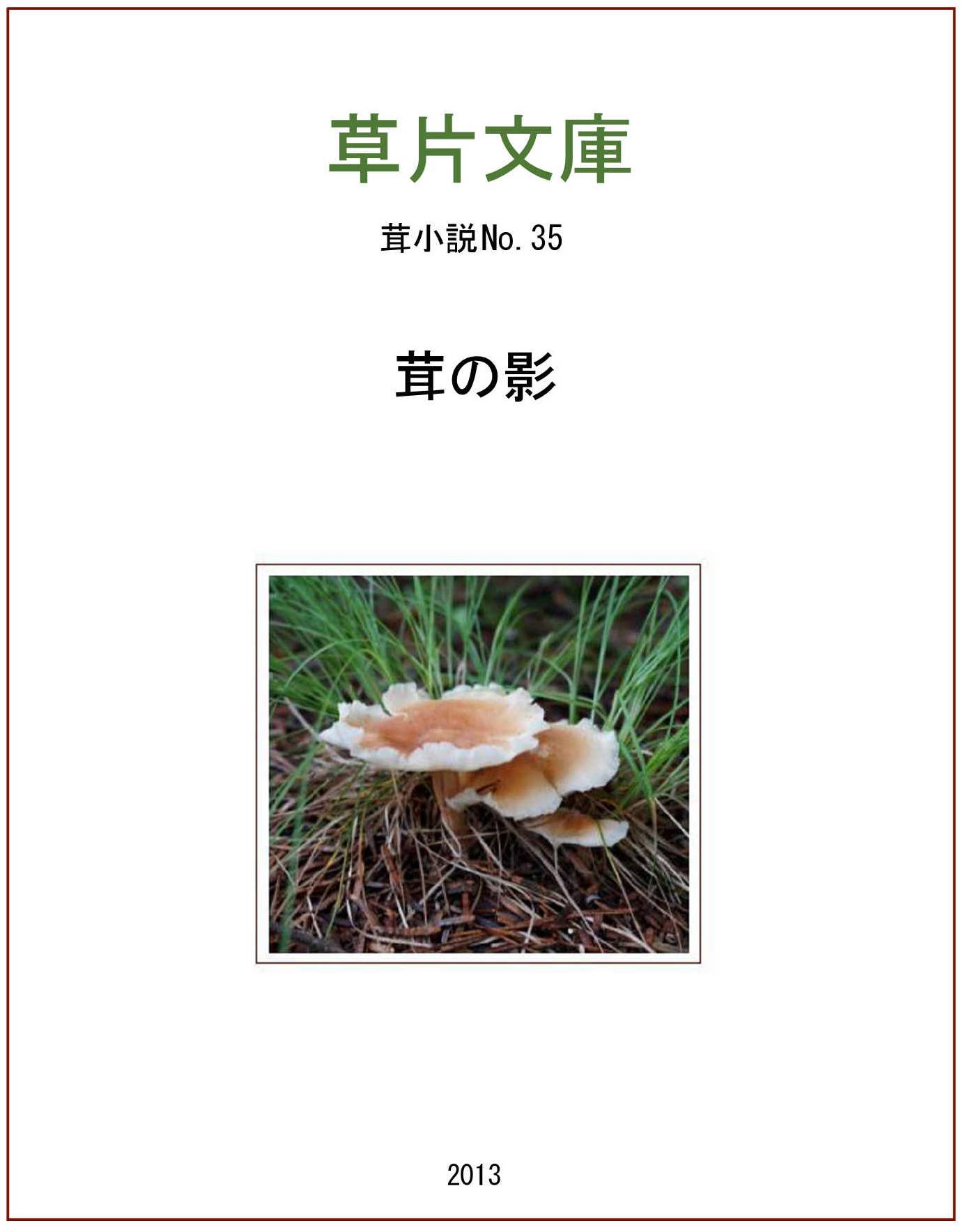
茸の影
最近どうもおかしい。からだがなんだか自分のものではないような気がしてならない。後ろからいつも見つめられているような錯覚もよくおきる。
いつからそうなったか思いだそうとしてもわからない、一週間前だったのではないかと思うこともあるし、一月、いや半年前からだと思うこともある。
からだの調子が狂っているわけでもなく、思い悩むようなこともなく、ストレスも溜まっていない。にもかかわらず、日に何度となくその感覚がおそってくる。
ふっと、誰かに見られていると思って、後ろを向いても誰もいない。
いたって精神的には健康のつもりでいること自体が、おかしい証拠なのだろうか。
変に悩んで本当におかしくなるのも困る。
そこで意を決して、精神科にかかることにした。
さて、どこの精神科がいいのだろう。両親などに相談したら大騒ぎになり大変なことになる。もちろん兄弟も無理だ。会社の同僚などは最も避けたい。
同僚に話をすると仲間外れにされるようなことは絶対といってない、むしろ、喜んで仲間にしてくれる。
説明をするとこうだ。会社の仲間はだれもが心を病んでいる。どこかおかしいのが当たり前という状態である。どこそこの精神科の医者は親切だ、あっちの病院はやめた方がよい、あそこの精神科のお医者様すてきよ、私に惚れてるの。といった具合だ。
そうじゃないのは僕と、もう一人、アラレちゃんだ。本名は洗井礼子ちゃんだ。アラレちゃんはいつも元気に走りまわっている。
という状況で、会社の仲間にはいることは怖い。もちろんアラレちゃんに相談するとアラレちゃんが孤独になる。まともなのはアラレちゃんだけになるからだ。
そういうことで電話帳を調べた。
精神科がいくつもある。この中からどのように選んだらいいのだろう。電話帳に宣伝文を載せているが皆同じで選びようがない。院長だれだれ、どこそこ出身。
精神科のとなりに心療内科というのがあった。これは何だ。
インターネットで調べてみた。心療内科はお腹が痛くなったり、胃の具合が悪くなったりするのは、胃や内蔵そのもののの障害もあるが、それをコントロールしている神経の働きがおかしくなっていることによるものが多い。ということは、頭の中を治す必要がある、という考えから、内科の先生が精神科や脳の勉強をして、そちらも加味して診察をする科だそうである。
僕は全く胃の具合も悪くなければ腸の具合も悪くない。ということは心療内科でもないことは確かだ。
コンピューターで検索していると、神経内科というのをみつけた。何をしてくれるのだろう。読むと、薬を使って頭の病気を治す科とある。精神科も薬を使うが、言葉を使って病を直すのが得意だそうであるが、神経内科は脳、神経に重点が置かれているようだ。神経内科に対して、脳外科というのがあった。これはどうも頭を開くのが好きで、脳にメスを入れて脳腫瘍などを取り除く科のようだ。
ということがわかってきたが、自分の症状はどうもこれらにぴたっとこない。調べていくと、カウンセラーという心理学を学んだ人たちがいることがわかった。最近よく言われる、心的トラウマというものを治す人たちのようだ。しかし、精神科よりもっと言葉であれこれ聞かれたりするようで、うるさいような気がして気乗りがしない。
インターネットで探っていくと、おもしろい記事があった。タイトルは、カウンセリングが心の病気を作っている、である。ちょっと読んでみた。からだを強くするには、自分で考えてよく動くこと、それじゃあ、心を強くするにはどうするのかというと、遊んで自分で解決する力を養うこと。
あまり手をさしのべすぎると、自分で回復させる能力が低下する。
というような様々な記事をみると、どこにも行きたくなくなってきた。
もうどうでもよくなってきて、何も考えずに、ネット検索を続けていたら、
「あたるも八卦、あたらぬも八卦、やってみればすーっとする」
という文句が目に入ってきた。
占いである。確かに占い師という手もある。占い師はカウンセラーより相手の顔を見ることに長けているのではないだろうか。資格などはないが、本当に能力のある占い師なら、変に心理学の知識のあるカウンセラーより、見方が真っ当かもしれない。
といっても占い師もピンからきりであろう。いろいろ考えたが、結局、どこか評判のいい占い師のことが聞こえてきたらいくことにした。それまでは今までのように、気にせず暮らしていこう、と決心したのだ。
そんな気持ちになって一週間たった金曜日の夕方である。最近は仲間と飲みに行くことも少なくなったが、その時は、仕事を終えたアラレちゃんが、誰か飲みにいこうと大声を上げた。アラレちゃんも少しストレスが溜まったのかもしれない。
みんな家庭に帰るか、心に何か抱えていてその気にならないか、誰も手を上げる者がいない。
まあ、僕ぐらいしかいないかなと思って、「おー、いくぞー」っと声をかけた。
「あーら文君、飲めたっけ」
僕の名前は栄互文法という。名前はフミノリと読む。
飲めない訳じゃない。
「飲めるよ、たくさんじゃないけど」
「よし、行こう」
「どこ行く」
「新宿だなあ、安いとこ」
それを聞いていた課長の針屋一男が、
「俺も行きたいが、今日は家に帰ると言っちまったんで飯ができてるんだ」
と残念がった。そういうことで、こうして大っぴらにアラレちゃんとデートということになった。
会社の外にでると、アラレが僕の顔をのぞき込んだ。
「ねーえ、文君、最近何か悩んでいるでしょう」
もう見透かされている。
「うーん、ばれたか」
「会社で唯一まっとうな文君がおかしくなったらこまるじゃん」
「いや、そんなにおかしくはなっていないよ」
「そんなことないよ、おかしいよ」
「うん、ちょっとそうかもしれない」
「どうしたの」
「いつも何かに見られているようなんだ」
「ふーん」
「なにか悪いことしたの」
「いや」
そのとき、また、後ろから何かに見られているような気がして、振り返った。
「どうしたの」
アラレちゃんが僕の動きを不思議に思ったのだろう。
「うん」どう説明したらいいのだろう。
ふと、自分の後ろの道路の石畳をみたとき、奇妙な違和感にとらわれた。
目に入った自分の影が、自分じゃない。
これはなんだろう。頭がとがって、帽子をかぶっているようだし、胴体は寸胴で、全く自分とは違う。
僕は、自分の影をまじまじと見た。
茸のような形をしている。
周りを見ても、茸のようなものはない。
「まあいいや、今日は気持ちよく飲もう」
アラレちゃんが言ったので、思考を停止した。
「うん」
それから二人して、地下鉄の駅まで歩いた。ビルの途切れたところで夕日が後ろから差してきた。
アラレちゃんと僕の影が歩いていく前にできた。
あっと思ったのは、僕の影は茸の形をしていて、アラレちゃんの影はれっきとした人間の影だった。
立ち止まってまじまじと影を見た。
「なに見ているの」
「僕の影が、茸になっている」
「なに、ふむふむ、なるほど、やっぱりね」
アラレちゃんは自分だけうなずいている。
「文君、ちょっといいとこいこうか」
「おもしろい飲み屋かい」
「飲み屋じゃないけど、きっと文君の悩みが解決する」
アラレちゃんになにかを気付かれてしまったようだ。こうなれば観念するしかない。
「うん、連れてってもらおうかな」
僕はうなずいた。
アラレちゃんは僕を連れて地下鉄に乗った。新宿とは反対の池袋行きだ。
「これから行くところはね、みんな知らないところよ、でも、そこにいくと誰でもすっきりするの」
「なぜそんなとこ知ってるの」
「ふふふ」
いつものアラレちゃんらしくなく、含み笑いしている。
新大塚をすぎ、もう池袋につく。池袋だったら山の手線のほうがずっと早く着くのになぜ地下鉄にしたのだろうか。
電車がスピードを落とした。降りる準備をしようとしたら、アラレちゃんが僕の腕をとって押しとどめた。そのまま乗って戻ろうというのだろうか。
池袋に着いた。あまり多くない乗客はのろのろと降りていった。
どうするのだろうと思っていると、空になった電車のドアが閉まった。
いつもだとそのまま新宿方面行きの電車になり、乗客が乗り込んでくるのだが。
いぶかしく思っていると、電車が先に進み始めた。車止めがあるだけのはずだが。
なんだか怖くなったが、スピードを上げた電車は僕とアラレちゃんを乗せて勢いよく進んでいく。
「どこにいくの、この電車」
「日の町」
「そんな駅あったっけ」
やがて、電車の走りが緩やかになり、駅に止まってドアが開いた。たしかに「日の町」と書いてある。
「丸の内線の終点は池袋じゃないの」
「ほら、本当の終点よ、日の町」
我々が電車から降りると、一組のカップルが電車に乗り込んだ。
電車は来た方向に動きだした。
ホームにある看板に日の町とあり、次は池袋と記してある。確かにここが終点のようだ。
エスカレーターに乗って上にあがると改札口があった。改札口をでてまたエスカレーターに乗って上にいくと外に出た。
そこには大な森が広がっていて、一本の道が地下鉄の駅からまっすぐに森の中に伸びていた。
遠くに雲を貫くように大きな茸が生えているのが見えた。いや、よく見ると大きなビルディングである。
アラレちゃんが道を歩き出したのでついていくと、道の脇にオープンカーが並んで止まっていた。アラレちゃんはその一つに乗り、僕に横に座るように手招きした。
「アラレちゃんの車なの」
アラレちゃんが車を運転するとは知らなかった。
「ううん、この町では自由に使っていいの」
僕が乗り込むと、アラレちゃんはボタンを押した。なんと、その車にはハンドルがない。
車はエンジンがかかると自動的に動き出した。バックをして、道にでると、大きなビルを目指してスピードを上げた。全自動の車だ。こんなに近代化された町が池袋の隣にあったのだろうか。
車は大きなビルの方向に向かっている。それにしても大きな建物である。
「あのビルに行くのかな」
「そうよ」
車はかなりのスピードで森の中を走っていく。森には鹿がいた。あ、猪もいる。錯覚だろうか。
「あそこに飲み屋があるのかな」
「飲み屋はまだ作ってないな、つくってもいいね」
「あのビルは何というの、ずいぶん高いけど何階立てなのかな」
「名前は「雲」クモビルよ、一番上は五百八十階」
「すごいね、日本で一番高いのじゃないかな、なぜ、有名にならないのだろう」
「日の町行きの地下鉄に乗るのは難しいのよ」
「僕たちは乗ったでしょう」
「私が乗り方を知ってたから」
「ふーん」
あっと言う間にビルに着いた。車は自動的に駐車場に入り停止した。
建物の上を見上げても、そびえたった建物の天辺はあまりにも高くて見ることができない。
「すごい建物だね」
「うん」
僕は建物の一階を見た。あれ、入り口がない。いや、窓もなく、ただ真っ白な建物である。そう、四角い煙突である。煙突が、雲の上まで延びている。
「これ煙突だね」
思わずつぶやいてしまった。
アラレちゃんは僕の言ったことに答えるわけでもなく、ただ、うなずいた。
「いくよ」
アラレちゃんの合図で、僕は彼女の後について、駐車場から続く大理石の階段を上っていった。
煙突のような窓も入り口もない建物の脇にたつと、その建物がコンクリートではなく、曇ったガラスのような物質でできていることがわかった。
アラレちゃんの手が建物の壁にふれた。そのとたん、その部分が透明になると、ドアになり左右に開いた。
アラレちゃんについて中にはいると、エントランスは反対側が見えないほどに感じるほど広い広場であった。アラレちゃんは上を向いて、片目をつむった。それが合図だったのかどうかわからないが、上の方から円盤がおりてきた。
「さあ、乗って」というアラレちゃんの声で円盤の入口が開き、僕は乗り込んだ。
円盤は上へ上へと飛んでいくと、一番上まで来て、一つの家の入口の前に着陸した。
アラレちゃんが、ただいまと声をかけると、カチャッと音がして入口の戸が開いた。
中にはいると、広い部屋の窓から池袋どころか、新宿、富士山、すべてが見渡せた。遠くに見えるの東京湾ではないだろうか。
「すごい部屋だな、ここは何回」
「一番上、五百八十階のAという家」
「これ、アラレちゃん買ったの」
「お父ちゃんからもらったのよ」
「へー、すごいお金持ちだね」
「お父ちゃんが建てたの」
「全くすごい、どんな人が住んでいるの」
「日の町行きの電車に乗れる人たち」
「ふーん
アラレちゃんは、ゆったりした木彫りの椅子に座るよう勧めてくれた。
「ちょっと待ってて、用意してくる」
アラレちゃんは、僕の前のテーブルにコップと水差しをおくと、僕を残して奥の部屋に入っていった。
ここまで、水も飲まずに来たのでのどが渇いていた。コップに水差しの水を注ぐと、一気に飲んだ。
それがまた、おいしい。
また飲んだ。ただの水のようだが、甘みというのか、なんだかわからないが、ともかくおいしかった。
三杯ほど飲んでやっとのどの乾きがとれた。
そこにアラレちゃんが、戻ってきた。それもびっくりした格好で。緋色のドレスに、日の色の靴下をはき、大きなガーネットの真っ赤な玉をじゅずつなぎにしたネックレスをしていた。いつも口紅をつけないのに、紅色の口紅をつけている。大人の格好も良く似合う。
「文法君」大きな黒い目を僕に向けた。
とてもきれいだ。
「その水ずいぶん飲んだわね」
「おいしい水だった」
「養老水よ、そんなに飲んだら死ねなくなっちゃうわ」
「どうゆうこと」
「何百歳も生きてしまうのよ」
「まさか」
「おいしいのはうまみ成分たっぷりだからね」
「うまみ成分って、あの料理のかい」
「そうよ、甘い、塩辛い、酸っぱい、苦いのを感じる仕組みが口の中にあるのは知ってるでしょう、近頃はうまみ、という第五の味の仕組みがわかってきたの、その水は茸の成分がはいっていて、それがうまみをたくさんもっているし、細胞を長生きさせる働きがあるの、寿命を長くするのよ」
「へー、科学的だね、それにしてもその格好はすごいね、まるで占い師の魔女だ」
「私、占術を習ったのよ、ここで開業してるの」
「ここから会社に通っているの」
「そうよ」
アラレちゃんは僕のテーブルの前に香の道具をおいた。火をつけると、白い粉を振りかけた。不思議な香りが漂ってきた。眠くはないがなぜかゆったりしてきた。
さらにテーブルの上に、干したタツノオトシゴと万年茸をおいた。
「さあ、悩み事を聞いてあげる」
そこで、最近後ろから誰かに見られているように感じていることを話した。
「いつからかわからないのね」
「そう、だけ、会社の集まりがあったすぐ後のような気がする」
「ああ、会社の旅行ね、信州に行った」
「どうもそのような気がする」
「やっぱりそうね、あのとき文君たち、宴会の後、茸の飲み屋に行ったでしょう」
「うん、いろんな茸のつまみがでてよかったよ」
「きっとそれね、それじゃ、このタツノオトシゴをもって、万年茸をじっと見てね」
なんだか、学芸会みたいだと思っていると、
「まじめにやってよ」と、アラレちゃんにしかられた。
アラレちゃんが目を閉じた、僕も一応目を閉じた。すぐに眠気が襲って来た。
いつの間にか夢の中に入っていた。
森の中を誰かと一緒に歩いている。いたる所に茸が生えているが、見たことのないものばかりだ。
ふと隣の人を見ると、背の高い男性で白い背広に、白い蝶ネクタイをしている。彼が僕の方を見た。タツノオトシゴだ。
「茸を召し上がりますか」
タツノオトシゴが聞いたので、意味もわからずうなずくと、
「それでは、まいりましょうと」と、歩きだした。
しばらく一緒に歩いていくと、木を切り払った広場にでた。切り株が至るところにあり、周りに茸が生えている。
「この切り株に腰掛けてください」
タツノオトシゴが丁寧に言ったので、ぼくはそこに腰掛けた。
「ちょっとお待ちください」
タツノオトシゴは森の中に入りすぐに戻ってきた。
「注文して参りました、お飲物のことを聞くのを忘れていましたが、ビールを頼んでしまいました」
ビールなら飲めるし、好きである。僕はうなずいた。タツノオトシゴが僕の隣の切り株に腰掛けた。
「なぜお姫様に連れてきてもらったのですか」
タツノオトシゴはよくわからないことを聞いてきた。
「お姫様って誰のことだろう」
「あなたを日の町に連れてきたお嬢さんですよ」
「アラレちゃんのことか」
「日の町の姫様です」
「アラレちゃんがこの町のお姫様」
「ご存じではなかったのですか、この町をお作りになった一族の姫です」
「そんなに偉い政治家なんだ」
「政治家ではありません、占茸(せんじ)術師の一族です」
「せんじじゅつ、っていうのは何をするの」
「草片を用いて未来を見ることのできる人たちです」
「草片って茸のことでしょ」
「そうです。動物でも植物でもなく、菌類は不思議な生き物です。違う世界に通じる生き物なのです」
そこにビールがきた。
もってきたのは、大きな座頭虫だった。背中に乗せてゆったりゆったり歩いてきた。
「おー、ありがとう」
タツノオトシゴが腰をかがめた座頭虫の背中の上の二つのビールをとって、一つを僕に渡してくれた。
「ごゆっくり」
座頭虫はゆっくりと森の中に戻っていった。
「どうぞお召し上がりください」
タツノオトシゴも自分のジョッキを口にもっていった。
僕もビールのジョッキをあげて飲もうとしたら、ビールの中に茸が三つぽこぽこと浮いている。
「茸が浮いているけど」
「そう、クサビラビールだからね」
僕は一口飲んだ。美味である。
「このビールを飲むと目がよくなるのです」
タツノオトシゴが言うと、たしかに、接写レンズのように、見ようとするものが拡大された。
「それで、どうして、お姫様があなた様をこちらにお連れになったのです」
「いつも誰かが後ろにいるようなので、アラレちゃんに相談したんだ」
「それで、影法師は茸の形をしているというわけですな」
「その通りなんですよ、いつの間にか僕の影がなくなって茸の影になってしまった」
「ふむ、そりゃあ、後ろ茸のせいですね」
「後ろ茸?」
そんな茸のことは聞いたことがない。
「きっと、後ろ茸を間違って食べてしまったのです」
「どのような茸」
「滅多に生えないのですが、たまに、そう一月に一本ほど生えるのですが、たいがいはそのまま涸れてしまいます。時にはあなたのように知らずに食べてしまう方がいるのです」
「後から見られているようなのは、その茸が僕にとりついたためなのか」
「そうです」
「もしこのままだと僕はどうなるのでしょう」
「後ろ茸に乗り移られると、茸になります」
「僕が茸になるわけですか」
「そうです、そして枯れていきます」
「寿命はどのくらいですか」
「乗り移られてから、長くて一週間でしょう」
「茸になったらもう苦しさなんてないんでしょうね」
「それはそうですが、乗り移られている最中は大変気分の良くない思いをすることになるでしょう」
「茸を退治することができないのでしょうか」
「できますよ、お姫様のご主人になることです」
「アラレちゃんと結婚しなければ茸になるわけか、でもアラレちゃんが結婚してくれなければだめなんだなあ」
「そうです、うまいプロポーズを考えないと結婚してくれません」
「僕はそういうのだめなんだ茸になるよ」
「消極的ですね」
「あなたはなぜそんなことを知ってるのですか」
「私も茸を知らないで食べたのです」
「それじゃ、人間だったのですね」
「そうです、でも姫にみてもらって、やはり茸になるか姫にプロポーズするかこの森の中で聞かれました。その時に森を案内してくれたのは鬼蜘蛛でした」
そこへ背広を着た鬼蜘蛛が、もっと飲み物がほしくないか聞きにきた。
「どうです、茸のビールをもういっぱい」
「ええ、いただきます」
「頼むね」と、タツノオトシゴが鬼蜘蛛に言った。
「それで、あなたは、なぜその姿になったのです」
「姫がプロポーズを受けてくれて、姫の夫になったからです」
「え、それじゃ、旦那さんになると、タツノオトシゴになってしまうわけ」
「いいえ、タツノオトシゴは私だけ、何になるかわかりません」
「もし、僕がアラレちゃんにプロポーズをして、受け入れられたら、何にされちゃうのだろう」
「わかりません、姫は茸を食べた人を助けるために、夫をたくさんもらわなければなりません、しかし夫は一人と決まっています。だから、ほかの動物になって、夫になるのです」
何となく理にかなっている。でも茸になって一週間で消えていくのと、他の動物になるのとどっちが良いのだろう。
「今、幸せですか」
僕はタツノオトシゴに聞いた
「確かに、人よりも幸せです」
そんなもんなんだ、納得したような、できないような奇妙な感じだ。
「今の鬼蜘蛛も、座頭虫もみな後ろ茸を食べてしまった者たちです」
「すると、アラレちゃんのご主人は皆この森で働いているのですね」
「はい」
「やっぱり、僕は茸になります」
そう言ったとたん目が覚めて、目の前に真っ赤な口紅をつけたアラレちゃんが、大きな目を見開いていた。
「茸になりたいなんて変な人、それでいいの?」
アラレちゃんはなぜか残念そうに僕を見た。
「それじゃ、町に戻ろう」
アラレちゃんは、いつもの服に着替えてくると部屋を出た。
また円盤に乗って一階に降りると、自動自動車で日の町駅に行き、一緒に地下鉄に乗った。
池袋にくると、並んで腰掛けていたアラレちゃんがいきなり立ち上がった。
「それじゃ、さよなら」
そう言うと、あっけにとられている僕を残して降りていってしまった。
池袋で一杯飲むつもりじゃなかったのかなと思ったが、アラレちゃんはホームから僕に向かって手を振っている。ニコニコしているが何か物足りない気持である。しょうがないので僕はそのまま家に帰った。
茗荷谷のアパートに戻ると、三階の自分の部屋にはいり、いつものように風呂を沸かし入った。その後サントリーの角瓶をあけてソーダ割りをつくった。
奇妙な気持でハイボールをぐっとあおった。
そこで、僕は茸になると言ったことを思い出した。そう言ったとたんアラレちゃんの態度が変わったのだ。旦那さんになるといわなければいけなかったのではないだろうか。僕は茸になるのだろうか。いつ茸になるのだろうか。こうなると運命を変えようとも思わないし、人生はっきりしてよかった。なるようになればいい。などと、今日起こったことが霧の中にかすんでいくような思いでまたハイボールを飲んだ。
茸になった自分を想像した。
いつものように角のソーダ割りはおいしかった。
茸になっても日常の生活をしよう、と訳のわからない結論に至ってなんとなく満足した。
朝、いつものように会社に出かけた。会社ではアラレちゃんが何事もなかったように机にむかっていた。
僕が入っていくと、
「おはよう」と、僕のほうを振り向いた。
ニコニコしている。
「おはよう、僕はいつ茸になるのだろう」
と聞くと、
「何言ってるの」と笑った。
「日の町にはどうやっていくの」
「日の町ってなあに、やあね、文君、相当疲れているみたい」
そういうと、また、コンピューターに向かった。
その日の夕方、アラレちゃんにもう一度、
「日の町に行って茸になりたい」、と言った。
それを聞くと、アラレちゃんは、笑いながら僕を見た。
「日の町で茸になってどうするの」
「日の町の森の中で赤い茸になって一生を終えることに決めた」
「そーお、それじゃ連れてってあげる」
その日も一緒に会社を出た。夕日がさすと僕の影は赤い茸だった。
こうして、また日の町にやってきた。雲をつくような白い大きな建物の五百八十階のAの部屋で、赤いドレスを着たアラレちゃんが、
「文君、本当に茸でいいのね」
と聞いたので、僕は頷いた。
それからしばらく経ってからである。僕は日の町の森の中で赤い茸になった。
これで一週間の命だ。
赤い茸になってからも、時々アラレちゃんが見に来てくれる。親切なお姫様だ。
「それじゃ、また来るからね、文君」
看護師さんの洗井礼子は仕事を終えて、市の総合病院の精神病棟から出てきた。
総合病院は真っ白な建物で、その五階に精神病棟がある。A室には茸になった患者がいる。退院するにはまだまだ時間がかかる。
茸の影
私家版第四茸小説集「茸人形、2018、234p、一粒書房」所収
茸写真:著者 長野県富士見町 2016-8-2


