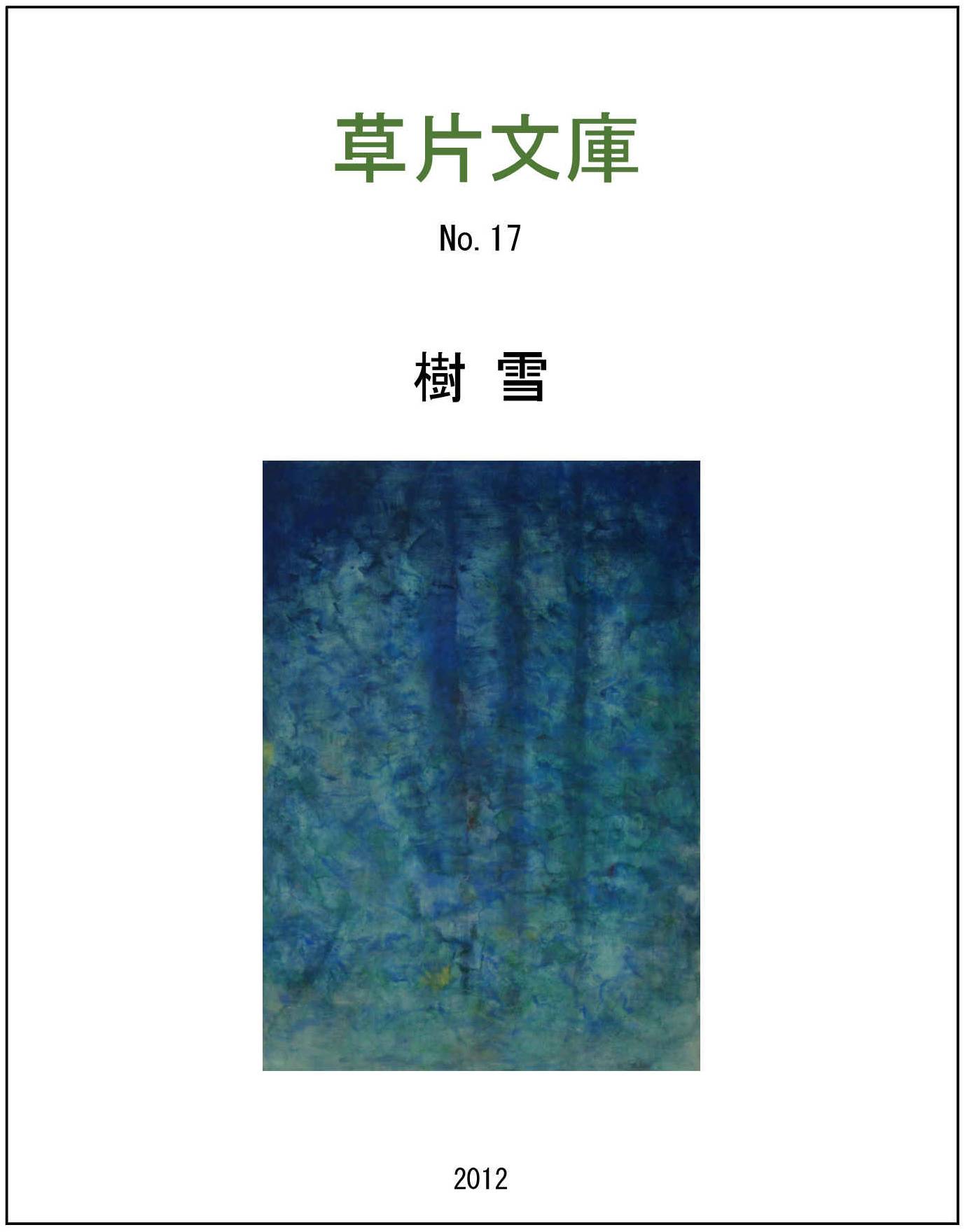
樹雪
雪はやんでいる。
富士の樹海の中に積もった雪の上を、木々をうまくよけながら雪女がすべるように進んでいく。真っ白の装束で雪の中に溶け込んでいることから、遠くから見ると、長い黒髪が雪の上を漂っていくように見える。
手に抱えているのは首をつったばかりの男の死体だった。
大雪の年の富士の樹海に住む雪女は忙しい。
一日に何人もの人間の死に立ち会わなければならないことがある。
雪女の使命は、どのような人間であれ、雪の中で死を迎える者であれば、死の間際に、生まれてからこの方までのなかで、その人間が最も幸福だった時間を再現し、苦を和らげ、死をみとってやることである。
雪女の樹雪(きゆき)は、その昔、富士誕生の大噴火のときに生まれた。そのために富士一帯の変化をよく知っている。樹海の広がる様が微速度カメラで撮影した映像のように目に焼きついている。
長い年月の末、生き物たちがやっと人間に行き着いたことから、雪女の役目が始まったのである。
未完成だが脳が発達した人間は未来を考える能力を持つことになり、死があることを知った。それは動物たちが本能として避けることを、意識のもとに遠ざけなければならない人間の性(さが)である。いまそのような死へのあまりにも過剰な恐怖心が人間の脳の発達を遅らせてもいる。
人間が雪の中で死のうとしているときに、その間際に駆けつけて、冷たい雪の中の死の恐怖を取り払ってやることが雪女の仕事であるが、その後片付けもする。
雪女は三十代の男の死体を樹海の奥の奥の、まだ人に知られていない洞穴の奥に運ぶと、地底の川のゆるゆるとした流れの中に沈めた。
水晶のように透き通った水は男の死体を静かに流れの中に包み込んだ。男は仰向けに沈んでいき、水底に静かに横たわった。
水底の岩陰から目の無い真白な幼虫が無数に出てくると男にとり付いた。
男の着ている粗末なワイシャツをあっという間に食いちぎり、肋骨の浮いた胸の皮膚を食い破った。
男は見る間に骨だけとなって洞窟の奥へ奥へと流れていった。
雪女は男の白い骨を見送ると、洞窟から出て、自分の岩屋へと向かった。
今日は二人ほど樹海で死んだ。一人は若い女性で、病気を苦にして樹海に入り、睡眠薬を飲んだ。九州の長崎にいる両親と遠く離れ、一人暮らしをしていたが、何の症状もなく元気なことから自分が病気に犯されていることを知らなかった。健康診断で精密検査を受けるように言われ病気が見つかった。医師に打ち明けられ生きる力を失ったのである。
樹海の入口から歩いてあまりいかないところで娘は睡眠薬を飲んだ。死ぬことが怖かったのだろう。気持ちが変わる前に急いで薬を口にしたのだと樹雪は思った。
樹雪は薬が深く効いてきた娘の口の中からからだに入り、冷たい思いを取り除くと、両親とのゆったりとした穏やかな生活を再現させた。娘の目に樹雪は母親として映っているに違いない。母親が手を差し伸べて迎えに来て、喜びの表情で娘は静かに息を引き取った。遺体が見つかれば両親は悲しむであろうが、ねんごろに弔うことになる。だから遺体はそのままにしておくのである。雪女は人に死を招いたり遅らせたりすることはしない。死んだ人に合わせた後片付けをする。
連れて帰り洞穴の水に沈めた男は身よりもなく、遺体が収容されたにしても無縁仏として処理されるだけである。洞穴の底を流れる水にのり、富士の奥深くに運ばれて安置されたほうが幸せなのである。富士の底にはそのような骨が集まっている場所がある。人類はそれを知ることは無いだろう。富士が墓石とは贅沢なものである。
雪がふたたび降り始めた。
富士の樹海は深々と冷え、手に持ったロープも凍りつきそうにごわごわとしてくる。首をつらなくても、このままでも死ぬことができそうだ。
しかし、雪が落ちてくるところではなく、どこか気持ちの良さそうな窪みでもあればと、さ迷っている少年がいる。まだ若い。ジーパンに青いセータ、それにハーフコートを羽織っているだけである。手にはロープをつるしていた。
少年は死に場所を探して歩き回った。
歩いていると、死にたいという気持ちは死の際の苦しさとの比較になっていく。寒さとの比較にもなっていく。だけど、もし、あの家に戻ったら、自分の頭は裂けてしまい、死よりも苦しいとも思う。
大学になぜ入らなければいけないんだと、少年はいつも思っていた。
それなら、家出をすればいいじゃないか、
頭の隅で声が聞こえる。
そんなに簡単なものではない。家出して、どこかで働いてといっても、まともに大人と口を利いたことの無い自分にできるわけがないと、少年は思っていた。死ぬほうが簡単だと思っていた。だけど、それもそんなに簡単ではない。
富士の樹海の映像はテレビで何度も流された。それは、迷路のような緑の茂った林の中だった。
雪の降り積もった樹海の映像は見たことが無かった。
雪の中を自殺しに来る人間は少ないのだろうか、予備校で誰かが話していたのを小耳にはさんだことだが、洞穴の写真を撮りに青木ヶ原に来たときに、何人かの監視の人に尋問を受けたということである。それで、夏に一度下見に来た。やはり見張りのような人がいた。そのときはそこそこ樹海の中を歩いただけで家に帰った。
少年は何の樹だか知らないが、枝がちょうどよい具合に張り出している大木を目にした。これで最後にしよう。
近寄ってみると、ロープも掛け易そうである。
少年はロープを投げた。最初は脇に飛んでいき、木の幹を打って、積もっていた雪が落ちてきたただけであった。
手がかじかんでいる。手をこすり合わせると、もう一度投げた。ロープは枝にかかった。その拍子にふたたび積もっていた雪が落ちてくると少年の襟元に入った。
冷たい。
躊躇する。
少年はロープに結び目をつくり、そばの石の上に上がった。
首にかけると、はっと石をけった。
その時、突然強い風が吹いた。
冷たい風は、雪をまき散らかし、少年のからだは吹き上げられた。
ロープは首から外れ、からだが雪の上にたたきつけられた。
少年はよろよろと立ち上がった。持っていたロープはもう使い物にならない。
少年は最初戸惑っていたが、意を決して雪の中を歩き始めた。何をしたらいいのか。樹海の中をさ迷っていると斜面に穴があいているのをみつけた。覗くと中は広そうである。穴の中で凍りつくのもいい、少年は穴の中にからだを入れた。
穴の中は思った通りかなり広い。少年は奥に入っていくと、暗闇の中で大きな黒いものを踏んだ。黄色い目が開いた。大きな熊であった。少年はびくっとするが動くことができなかった。熊は首を上げからだを起こした。少年のそばによってきて鼻先を少年の頬の近くに寄せた。肉汁のようななまぐさい匂いが鼻をつく。
大きな口を開けると少年の服に噛み付き、前足を少年のからだにかけた。
少年は怖さのあまりほとんど意識がない。
熊は少年が倒れると奥にひきずっていき、自分もごろんと横になると、少年を抱えるようにしてふたたび眠りについた。
しばらくすると少年は目を開けた。大きな熊の手が自分のからだを抱えているのに気づいた。熊の腹の動きが自分の背中に伝わってくる。
しかし、少年は動こうとはしなかった。
熊は自分の子どもとでも思って抱えこんだのだろか。
少年はいつか食われるかもしれないが、このままでいようと決意した。
どうせ、死ぬつもりだったのだ。
祠の中は決して暖かくは無かったが、熊に抱えられていると寒さは感じない。これでは凍死はしないだろう。のどの渇きと飢えがしのびよって、やがて死ぬのか。それとも、飢えに目が覚めた熊が自分をかじり殺すのだろうか。
少年は家に帰るよりも熊の温もりのほうが幸せに感じた。
樹雪はその情景を見ていた。その熊が少年を食べるとき、または、飢えて死ぬとき雪女は少年に夢を見させることはできない。雪に囲まれて死ぬとき以外、雪女はその死にかかわることはない。
樹雪は少年が青木ヶ原をさまよっている間に、頭の中を少しばかり覗いてみた。冷たさの中で死ぬ運命かどうかみたのである。しかし、少年の頭の中は混沌としていた。死は遠くにあるが、それほど遠くない。しかし、果たして、雪女が関わることになるのかその時点では分からなかった。
それよりもっと樹雪にとって困惑すること、いや怖いことがあった。この少年には温まるような楽しい記憶が無いのである。食べ物に不自由するわけでもなく、小遣いが無いわけでもない。勉強もできないほうではないし、運動も苦手ではない。両親はこの長男と、その妹をないがしろにしているわけではない。それなのにすべての記憶が悲劇であった。このような記憶しか残っていない人間ははじめてであった。生きていればこれから楽しい記憶もできるのだろうが。
熊に抱きかかえられ目を瞑っている少年の頭の中に入ると、熊に抱かれている今が一番暖かい気持ちになっている。
それは長く続くまい。
樹雪は少年の頭から離れた。富士の別のところで、死を迎えようとしている若い女性がいたからである。雪女はその女性のところにとんだ。
女性は樹海のなかではなく、富士の中腹の雪たまりの中に埋もれていた。山登りの経験のあるその女性は、一人で富士の山をめざした。死にたかったからである。
雪の深いところに達した女性は雪に穴を掘り、その奥に腰を下ろした。持ってきた睡眠薬を飲むと、そのまま眠りについた。からだは冷たくなり始めているが、まだ夢を見ている。樹雪は女性の前に立つと身につけていた白い装束を脱ぎ去った。
真っ白なからだを女性の前にさらすと、女性の目は紺色のもんぺをはいた祖母を見ていた。
母と父親を事故で亡くした女性は、北海道で中学生まで祖母に育てられ幸せな日々を送っていた。祖母が思わぬ病で死んだ後は高校にいきながらおじの農場で働き、卒業後東京に出てきた。ところが、無駄づかいもせず、こつこつとためた将来の資金は騙し取られ、信じた男は姿を消した。良くあることといえばその通りであったが、彼女の頭への衝撃は我慢しきれないものであり、頭の中のセロトニンが低下していった。欝になっていった彼女は、雪の富士に登ったのである。
樹雪はその女性の祖母となり、女性は祖母の手に引かれて雪解けの小川のほとりで蕗の薹をつんでいた。蕗の薹が袋に一杯になると、祖母と家にもどり、暖かい甘いミルクセーキを飲んだ。からだがぽかぽかしてきて、コタツに入ると眠くなった。気持ちのよい眠りが少女におとずれた。
女性の心臓はとっくに止まっていたが、その瞬間、脳の活動は停止した。
それをみとどけた樹雪は女性のからだを抱えると、富士の洞穴にはこんだ。女性の遺体が見つかっても、引き取り手がいないことは明らかであった。
樹雪は洞穴の奥の流れにその女性を沈めた。川底では白い幼虫が女性の衣服を食い溶かした。きれいな乳房が水にゆれた。それも白い幼虫が食いちぎり、真っ白な骨が残った。骨は水底をゆっくりと流れ、富士の底の水の墓場へと向かっていった。
それから四日後、熊に抱かれた少年の心臓の動きが、ことことと音を小さくしていった。五日目になると、心臓の音は途切れるようになった。
そこで奇妙なことが起きた。少年を抱えていた熊の両手がゆっくりと開き、少年を離した。
そのとたん、熊はぐわっと大声を上げ、いきなり仰向けになり、少年は祠の入り口のほうにはじきとばされた。熊は一回転して再び仰向けになると動かなくなった。
熊の心臓は止まっていた。病である。
弾き飛ばされた少年は最後の力をふりしぼって、祠から這い出した。外に出ると、そのまま雪の中にうずくまった。
樹雪ははっとした。少年が雪の中で死のうとしている。
少年の心臓はほとんど止まりそうだった。意識は朦朧としている。
樹雪が少年の前に飛んできた。
少年の前で衣装を脱ぐと、白い肌を雪の上にさらした。
少年は微笑んだ。少年は目の前に年老いた雌の熊が両手を広げているのを見た。少年は熊の手をとった。樹雪は雪の中で死ぬ人間に生涯で一番幸せな時をあたえる。しかし、自分が熊になるとは思ってもいなかった。
少年は熊のおなかに寄りかかって、暖かな思いで脳の働きを止めた。
樹雪は迷った、遺体が見つかれば引き取る両親はいる。しかし、少年は望んでいないことは明白である。
人間の血のつながりは強いものと思っていた。
富士の山ができた頃、大陸で生まれた原始人は血のつながりを作り始めていた。樹雪は原始人がヒトになるにしたがってそれが強くなることをみてきた。脳の働きも進化して、少しは高度になったと思われた人間は、血のつながりを放棄しようとしているのだろうか。初めての経験に樹雪はとまどった。
しばらくの時間があった。雪は少年の上に降り注いだ。
樹雪は白装束を身にまとうと、少年を抱えた。それだけではなかった。死んだ熊も抱えた。そのまま二つの遺骸を洞穴に運んだ。
洞窟の奥に達した樹雪は川の流れの脇に少年と熊を横たえた。
川の底で白い幼虫が石の陰から湧き出してきた。透き通った水の中を上に向かって浮いてくると水が真っ白になった。
幼虫は川から這い出ると、少年と熊のからだに取り付いた。
やがて少年と熊のからだは白い骨だけになった。
白い幼虫は骨にとりついたまま、脱皮をはじめ黒い虫になった。
数知れぬ黒い虫は一斉に舞い上がり、青い光りをともし始めた。
少年と熊を食べつくした幼虫がこの洞窟にしかいない蛍になり舞いはじめたのだ。
洞窟を多い尽くすように青い光りは上になり下になりふわふわととんだ。光りは流れの水面にきらきらと映り洞窟に光が満ちた。
やがて、蛍の光りは弱まり、蛍たちは洞窟の天井に卵を産み付けると、死んで川の流れに落ちていった。蛍の死骸も富士の下の墓場に運ばれていく。
樹雪はうっとりとして光りの舞いを見た。樹海蛍の光りの舞いを見るのは久しぶりであった。
幼虫は百年かけて成虫になり、数十分光ると卵を産んで死ぬ。
樹海蛍の舞いは樹雪の唯一の楽しみであった。
最後の光りが消えると、樹雪は少年と熊の骨を水の中にしずめた。
少年と熊の骨はゆっくりと川底に吸い込まれていき、富士の底に流れていった。
樹雪は自分の岩屋へと帰って行った。
樹雪
私家版雪女小説集「雪女、2015、222p、一粒書房」所収
表紙日本画:山内佳子


