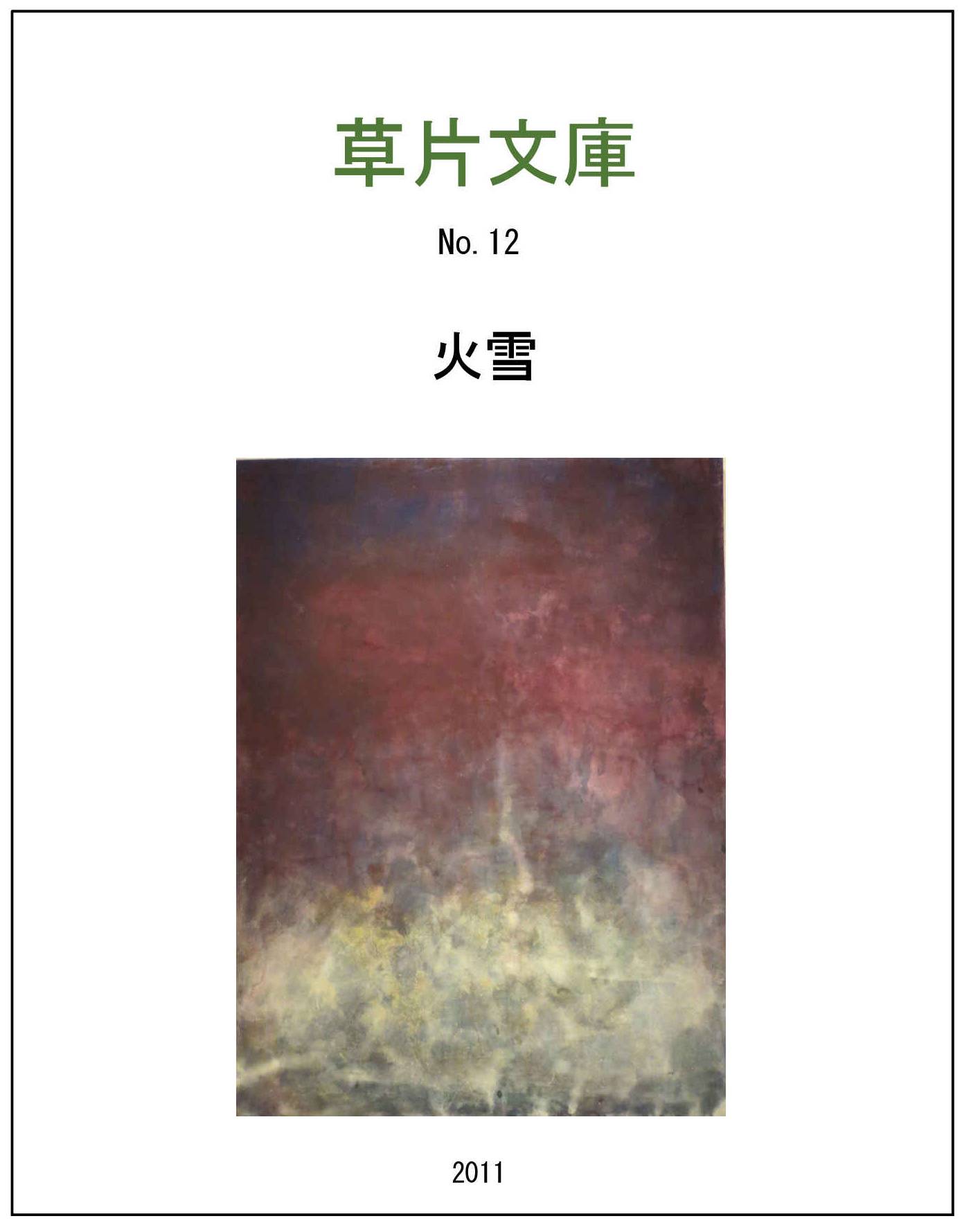
火雪
雪が深深と降る夜の大都会。
公園の一角で八人の雪女が輪になっている。
真ん中には一人の若い女がうつむいてたたずむ。
その女は顔を上げることもなく首を横に振った。
「いやや、絶対にいやや」
薄紫色のロングドレスに白いハイヒール、手には白いレースの手袋をしている。そのままステージでシャンソンでも歌いそうだ。ブロンドの、いやブロンドに染めているのかもしれないが、品よくカールした、ゆったりとした髪、彫りの深い顔。橙色の口紅をさした少し大きめの口が顔の印象をさらにダイナミックなものにしている。大きい目に涙を浮かべてまた言った。
「いやや、絶対いやや」
真っ白い装束の雪女たちは、なすすべがないといった顔でお互いうなずきあった。
「雪の舞か」
皆うなずいた。
長と思しき雪女の一人が女性の目の前に立った。
「どうしてもいやか」
女はうなずいた。
一人の雪女が涙を流しながら女性のほほにそうっと手を触れた。
指先が触れたとたん、
女は、さーっと、凍りつき、粉々に砕け、雪となり、きらきらと、公園に舞い上がり散っていった。
八人の雪女は渦巻く風に乗り空高く消えていった。
岩手の山奥の、呼び名もない山の頂で、子ウサギが雪の上で跳ねていた。
黒く大きな目をくりっとさせ、舞い降りる雪の結晶にじゃれつき、積もった雪の中に頭を突っ込んでトンネルを掘ったと思うと、後ずさりして、でんぐり返しをした。飛び跳ねて二本足で立って歩くことまでした。
少し離れたところでは、迎えに来た母ウサギがあきれたような顔をして見ていた。
「帰るのよ」
母ウサギは子ウサギを呼んだ。
子ウサギは、母ウサギを見た。
「いやや、もっと遊ぶ」
首を横に振った。
「みんなが待っているから、帰らなきゃだめよ」
母ウサギは子ウサギの脇に跳ねていった。
子ウサギの首根っこをくわえると、母ウサギは雪をかぶった大きな切り株の脇の穴に入った。
中に入ると、母ウサギは子ウサギを口から放した。
「ついてらっしゃい」
母ウサギのあとを子ウサギはおとなしくついていく。
暗い穴の中をしばらく歩くと、いきなり大きな岩屋にでた。
母ウサギは言った。
「ただいまもどりました。火雪(ひゆき)をつれもどしてまいりました」
子ウサギは、もうちょっと雪の上で遊びたかっただけなのに、と思っていた。
岩屋の奥から長い白髪をたらした老女がゆっくりとでてきた。
「ごくろうじゃ、少しくらいならいいが、今は危ないときなのじゃ、火雪にそれが分からなければ、もう外には出すまいぞ」
火雪は生まれたばかりの雪女だった。外の世界にはウサギの格好でしか行くことができない。
母ウサギは落ち着いたいかにも母親という風貌の女性に姿を変えると、雪女の長である春雪に、「ゆっくりと教えます。申し訳ありません」と言った。
「まだ火雪は子どもじゃ、仕方が無いが、今の時期、ウサギ狩りに射止められれば、雪女とてウサギとして死ぬしかない。危ないことであることを知らねば」
子ウサギは人でいえば三歳ほどのおかっぱの女の子に変わっている。
「雪女は数百年に一人の子どもを残すことができるだけじゃ、七歳になれば、どのようなことがあっても死ぬことは無い。そこまでは気をつけるのじゃ」
「はい、いつもついているようにします」
火雪は三年ほど前に葉雪が産んだ。
このあたりの雪女の世界では数百年ぶりのことといってよいだろう。
葉雪は今八百歳に近い若い雪女で、それまで子どもを産んだことは無かった。
雪女が子供を産むきっかけはいろいろある。このあたりの雪女は天変地異によることが多い。
雪女の寿命や、子どもを産む方法は種族で違う。日本にもいろいろな雪女がいる。
大きな地震によって、すでに死火山になっているこの山の奥の奥深くで、赤い火がついた。すでに冷えていたマグマのほんの一部に熱が残っていたのだろう、それは少しではあるが、赤いマグマが出現したのである。何百年後にはまた火山が出現する可能性がある。それを葉雪のからだは感じとり、子どもができた。そのようなことから、その子どもは火雪と名づけられた。
雪女は少ない。貴重な子どもであった。
何千年も生きながらえている長老の春雪は久々の子どもに喜んだ。
地球が様々な現象で暖かくなってきたことで雪が少なくなった。それは事実であるが、もっと人には知れぬ原因があったのである。
日本の雪女が減っているためである。雪女が雪を采配する。雪女が減れば雪は減る。雪女は雪と人をとりもつ司でもある。
火雪はいうなればおてんばであった。それだけ利発ということになるかもしれない。母親の葉雪は火雪が雪女の長に育ってくれることを願った。
春雪は上手に雪を司る長ではあった。しかし、やはり衰えがあった。雪の降り方が少なくなったのは、確かに人の世界の吐き出すものが温度を上げているためであるのは事実である。今まではそれ以上に雪女たちの力が強いものであった。それは雪女の長の采配によるものである。
春雪の力が弱くなっている。それは春雪自身が感じているところでもあった。新たな長が必要である。しかし周りの雪女たちに春雪のような力は無かった。
久しぶりに生まれた火雪に期待があつまっている。
火雪は毎日のように子ウサギになって雪の上を飛び跳ねていた。母の葉雪はいつもそばについていた。外に出さないと火雪は洞窟の中で走り回るどころか、岩にぶつかり、ころがりまわり、怪我の心配さえあった。
ある日、子ウサギに姿を変えた火雪は、いつもと反対側の斜面に行って雪の中で遊んでいた。葉雪はわが子を樹氷の影から見守っていた。
その時、狩人が近づくのが目に留まった。
葉雪は全速力で火雪の元に走っていった。気がついた狩人が鉄砲を構えた。
葉雪が駆け寄ってくるのを見た火雪は何が起きたか分からず、葉雪が来たほうへ飛び出した。
「あっ」と葉雪がふりかえり狩人を見ると、狩人は子ウサギを見て鉄砲を下に向けた。狩人はしばらくながめていたが、尾根のほうへ歩いて行ってしまった。
命拾いをした葉雪は、火雪をつかまえて、あれが狩人だと教えた。
そこへ本物のウサギが子どもを二匹つれて飛び出してきた。火雪は喜んでその子ウサギにじゃれついた。子ウサギたちも、飛び込んできた見慣れない子ウサギを追い払うでもなく一緒に駆け回った。母ウサギは葉雪と同じように立ち止まって見ていた。
母ウサギは葉雪に気がついた。ゆっくりと近づいてくると葉雪を見た。
母ウサギはそこにいるウサギが雪女であることを知っていた。動物たちはこの山にすむ雪女が動物に形を変えて子育てをすることを知っていたのである。
「元気がいいお子さんですね」
「ええ、火雪といいます」
ウサギとも話をすることができる。雪女の持っている能力である。
「飛び出してしまうのではないかとご心配でしょう」
「ええ」
葉雪は笑った。ウサギの母親に見透かされている。
三匹の子ウサギはじゃれあってもつれ合って転げまわっている。
「うちの子供が雪女になることはできないのでしょうね」
母ウサギは葉雪につぶやいた。
葉雪はこの親ウサギが子どもの行く末を案じ、そのつぶやきになったことに気づいていた。野性の動物たちは自分の子どもたちが無事に育ち一人前になるのは数パーセントであることを知っている。人にはわからないのだろうが、動物たちのつぶやきはいたるところに満ちている。
「そうねえ」
葉雪はやさしく親ウサギに言った。
母ウサギはうなずくでもなく、わかっていますよという様子で子どもを見た。動物たちにとって、雪女は山の頼りになる身近な神だが、不思議な存在であった。厳しい雪景色を作り出す冬の司でもあり、命を安らかに終わらせてくれる女神でもある。雪の時期だけみんなの前に現れる。
その日は火雪にとってとても楽しい一日であった。
洞窟にもどった火雪は葉雪に言った。
「お母様、火雪はあのウサギたちと一緒に住みたいの、岩屋に入れてはいけないの」
「それはできないのよ、わかっているでしょう」
「弟でも妹でもいいの、兄弟がほしい」
春になると雪女たちは出入り口から岩屋を出ることはなくなる。岩壁を空気のように通り抜け、まだ雪のある遠くの山へ飛んでいく。その間、火雪は岩屋から出ることはできず、ただおとなの雪女の話を聞くだけであった。
秋になり初雪が降ると、ふたたび火雪は外に出て遊んだ。仲のよかったウサギの兄弟はとっくに大人になり、何匹もの子どもをもつ親になっていた。その子どもたちと毎日を遊ぶようになり、やがて火雪も人でいうと五つほどになった。
その年齢になると鳥に姿をかえることができた。
火雪は真っ白なフクロウになった。フクロウになると、夜に出かけることが多かった。その頃は母親の葉雪がついてくることもなく、火雪は森の中を雪の上を好きなように飛び回ることができた。
ある月夜の晩、火雪がフクロウになって森の木々の間を行き来していると、いきなり舞い降りてきた一羽の茶色のフクロウが、地上のウサギの子どもをさらった。
「何をするの」
火雪がかなきり声を上げると、そのフクロウは一目散に自分の木の祠にもどり、獲物を子どもたちに与えた。
そのあと火雪の止まっている杉の木の枝の端に飛んできた。
茶色のフクロウは黄色い目で火雪を見た。
「雪女のお嬢さん、あたしたちは食べないと死ぬのですよ、子どもだって死ぬのですよ」
「食べるって」
火雪はウサギが葉っぱをもぐもぐ口の中でかんでいるのは知っていた。
「そうです、ウサギは草を食み、我々はネズミやウサギを食べるのです。それは我々のからだになります。そうしないとからだは土になるのです。そうでなくても、二十年も経たないうちに死ぬのですよ。雪女は何千年も生きるのでしょう」
火雪はうなずいた。
茶色のフクロウは木の下でネズミが動いたのを認めると、さっと飛んでいった。
それ以来、火雪は森の動物たちの営みに眼を向けなくなった。森の一番高い木の上で月や星を眺め、雪の降る日は雪の舞いをみていた。
木の枝にとりついた雪の結晶が月の光に輝き、風と雪たちは音楽を奏でた。火雪はそのような時、誰にも見つからないように、岩のくぼみで、緩やかな音に誘われて夢を見るのであった。
時折、遠くの町の音が耳にとどく。その中に、かすかではあるが、とてもすてきな音が混じっていることがあった。それはまだ火雪の見たことの無い、人が奏でる楽器の音だった。ギターである。火雪はギターの音が好きになった。火雪の口元から、音色にあわせて自然と歌声が洩れた。
吹雪いている夜のことである。葉雪が真っ白な雪女の衣装で岩屋の岩壁をすーっと抜けて外に出ていった。岩屋の入口から出て行かずに、岩を通過して出たということは、雪女としての役目を果たしに行ったということである。雪女は一瞬にして、日本のいたるところに行くことができる。
雪の中で死にかけた人が呼んでいる。
火雪は岩屋の出口をあけると、吹雪の中をフクロウになって飛び立った。
雪女の一族がどこにいるかわかる年になっていた。
いつもは遠く離れた雪山や雪里でのできごとで、フクロウが飛んでいけるような近いところではなかった。ところが、その日、葉雪の飛んだ所はすぐそばの山の陰であった。近くであれば火雪にも透視ができた。一人の登山者が遭難し、岩のくぼみで眠りかけていた。背負っていたキスリングによりかかり、冷えた手を時々こするように動かしている。
火雪はそこに向かって飛んだ。
遭難者は若い男性であった。火雪は人間を何度か見かけたことはあったが、みな猟師であった。ときどきはリュックを担いだ登山者であったこともあるがまれなことであった。
火雪が、岩のくぼみの近くまで来ると、葉雪が遭難者の前に降り立っているのが見えた。
葉雪は遭難者の額に手を当てている。
遭難者の男性は目を開けて、葉雪の姿を見ているに違いなかった。額の辺りが白く凍り始めている。脳が冷えていく。遭難者は冷たさも感じなくなっているのだろう。
葉雪は白い衣装を脱いだ。真っ白な後姿はとてもきれいだ。八百歳とは思えない若い女性の姿だった。遭難者の脳の中にきれいな女性の姿が焼きついたにちがいない。葉雪は脱いだ衣装を遭難者にまきつけた。からだが次第に冷えていく。寸時のことだが、遭難者は何ヶ月もの長い幸せな夢を見ているのだろう。それが雪女の使命である。
遭難者はまもなく凍った。
葉雪は遭難者に掛けた衣装をはぎ、自分の身にもどした。
葉雪の指が遭難者のまぶたに触れた。遭難者が静かに目を閉じると、葉雪はすーっと消え去った。
そこには冷たくなった遭難者がいた。
フクロウの火雪は近くの岩場からその成り行きをすべてみていた。
遭難者のそばによった。凍った遭難者は柔らかな笑みを浮かべていた。いずれ自分もこのようにして、雪の中で人の死をみとるのだろう。
このような形で学ぶ機会はない。遭難死は海を越えた国々が多い。こどもの雪女は、七歳を過ぎて永遠の雪女になったとき、親や経験のある雪女が、一緒にその場所につれていき学ばせる。若いころにこのような経験することは少ないのである。火雪は若くして雪女の仕事を学ぶことになったわけである。
火雪は岩屋にもどった。
葉雪が待っていた。
「見ていましたね、お前も大きくなったらああするのですよ」
と言った。
フクロウから童女にもどっていた火雪はうなずいた。
「あの男の人はどうなるの、お母様」
「あそこの雪が解けると、誰かに見つかるかもしれないが、万年雪になると、しばらくは見つかることは無いだろうね」
「ふーん」
「あの男の人は、東京に住んでいてね、帰ったら、結婚する予定だったのよ。結婚する前の最後の一人登山だったのよ」
「結婚てなあに」
「人間には男と女があってね、結婚して、子どもを作って、子どもを大きくして、一生を終えるのよ」
「ウサギと同じね」
「そうですよ、ウサギと違って、人は八十年ほどの寿命のなかで、子どもを一人か二人しか産まないけれどね」
「ふーん」
そこへ、春雪が来た。
「火雪も見たのだね」
「はい、おばあさま」
「それはよかったね、雪の中で、静かに、幸せに死をあたえるのが我われの使命なのですよ」
「はい」
来年は火雪も六歳になる。岩壁を通り抜けるようになり、町に行けば、人の目に見えない姿で人の生活を見ることができるようになる。
今の火雪は人でいうと中学生、来年は高校生というところであろう。
六歳になった火雪は人になってみた。雪女の衣装ではなく、真っ赤なドレスに身を包んだ。
岩屋から外に出ると、白い山並みが見渡せる。その下には、いくつもの小さな町が点在している。有名な温泉郷もいくつかある。その中の一つの町からかすかに聞こえるギターの音が火雪の気持ちを湧き立たせた。そのうち遊びに行ってみよう、火雪はわくわくした思いで毎日を過ごしていた。
その日は意外と早くにきた。雪女たちが長老を残してみんな出て行ったのである。火雪は雪がちらついている中、赤いドレスをまとって町の中を飛んだ。初めて直接目にした町は、家々の明かりが雪を照らしきれいだった。
一つの温泉旅館からギターの音が聞こえてきた。火雪は明かりが消えている部屋を窓から覗いた。暗がりの中で一人の男がベッドに腰掛けて二つのふくらみを持つ楽器を抱えて奏でている。それが火雪の気持ちを捉えていた音を出す楽器、ギターであった。
火雪は壁をすり抜け、男のいる部屋に入った。男は火雪が入るとアーっと大きな声を上げて、ギターを取り落とした。
男は見えないはずの火雪を見ていた。
男の驚いた顔はやがて歓喜の顔に変わった。
「君は誰」
そういった
「私が見えるの」
男は頷いた。
「君だけが見える」
男の目は両方とも白く濁っていた。
火雪には言っていることがわからなかった。
そこに、どたどたと足音がして、勢いよくドアを開けて一人の女性が入ってきた。電気を点けると言った。
「雪人さんどうしました。大きな音がして声が聞こえたので飛んできたのですが、どうしました」。
女の目に火雪は見えないようであった。
男は火雪を見ながら答えた。
「いや、なにか、冷たいものが触れたような気がして、すみません、騒がせてしまったようです」
「本当、この部屋はやけに寒いわね、暖房を強くしておきましょう。なんでもなくて良かったですね。まあまあ、大事なギターを放り出してしまって、よほどびっくりなさったのね」
女は暖房機をいじると、ギターを拾って男に渡した。
女が部屋の外に出ると、男は火雪に言った。
「彼女は僕の付き人の浜田早苗さん、何から何までやってくれる、とてもいい人なんです、彼女にあたなは見えなかったようだ、僕の幻覚なのだろうか」
火雪は、男の額に手を当てた。
「冷たい手だね、本当にそこにいるのだね」
火雪は答えた。
「はい、でも今の私は人には見えない」
名前を教えてほしい
「火雪」
「僕は生まれたときから目が見えない、人がどんな形をしているか、この世のものがどんな形をしているのか、手で触って知っているだけだ、親が教えてくれたことから想像はしていたが、女性というものがどのような形かも今まで知らなかった」
男は長谷雪人という盲目のギタリストだった。
雪人はギターを再び奏でた。低い声で歌った。
火雪は嬉しかった。
雪人も始めて聞く人の顔を見ながら歌った。それは今までよりもまして、澄んだ音をかなで、流れるように歌がでてきた。
火雪も歌いたかった。
やがて、雪人は弾くのをやめて、ベッドに横たわった。
「いつまで目の前にいてくれるの」
火雪は、時間の経つのも忘れていた。いつまでもこうしていたかった。だが、そろそろ雪女たちが岩屋にもどってくるころだろう。そうすれば火雪のいるところなどすぐ分かってしまう。人からも見える人間の形になれば雪女たちから一時は見つけられないだろう。しかし、今はできない。
火雪は、「いつまでもいたい、だけど、今日は帰る」
と言った。
「僕の公演は今日で終わりなんだ、明日東京にもどる、一緒に来てほしい」
「今は帰る、でも、明日必ずついていく」
火雪はくり返し言った。そのあと音もなくその場から消え、雪女の岩屋にもどった。
長老の春雪が、「おー火雪もどったね、他の者たちはまだなのだよ、お前はどこにいっていたのだい」と聞いた。
春雪は年老いてもう雪女たちの動きを追うことができなくなっていた。
「私は、月山のほうに遊びに行ってまいりました、ウサギたちと語らいました」
火雪ははじめてうそを言った。
「そうかえ、よかったの」
春雪は自分の部屋へともどっていった。
あくる朝は吹雪いていた。
火雪は遊びに行くと言って岩屋を出た。風に乗ると温泉郷から電車の駅まで行くバスを追いかけた。バスには雪人が乗っていた。
バスの窓を通り抜けると、雪人の斜め前の席に座った。雪人ははっとして真っ赤なドレスを着た火雪を見た。隣の早苗は気づくことはなかった。
火雪は電車にも乗り、雪人のマンションの一室までついていった。
雪人は自分の部屋に入ると言った。
「火雪さん、僕は君が見える、触れることもできる、真っ黒な中にあなたの姿だけが見える」
火雪は人間にも見える形になった。
「私は今、他の人にも見える形になりました、それでもかまいませんか」
「もちろん」雪人は火雪の肩に手を置いた。
「あったかい」
「はい、人間にも見える形になれば暖かくなります、そして私は仲間からもすぐには見つけられないでしょう」
「あなたは人間で無ければ何なのだろう」
「言わなければいけませんか」
「いや、かまわない、でもどうして僕についてきたのか教えてほしい」
「歌いたいのです。あなたのギターの音は風の中で聞いていました、私は雪女です」
火雪は打ち明けた。
「 雪女って、お話に出てくる雪女なの」
「雪女はいるのです、お話しの中だけではありません」
雪人はうなずいた。
「僕と歌おう」
火雪は雪人に合わせて歌った
透明なきれいな声だった。
それから、一月ほど火雪は雪人の部屋で歌の勉強をした。
雪人のギターで、何曲もの歌を覚えた。
雪人は言った。
「僕と一緒に、日本中を回って歌おう」
「うれしい」
火雪は何もかも忘れていた、雪女であることも。
「明日、事務所に行こう」
火雪はいきなり、雪人の紹介と言うことで、音楽事務所に連れて行かれた。
音楽事務所の女社長は火雪の美しさに驚き、雪人の伴奏で歌う声を聞くと、素性も聞かずにステージに出ることを許可した。それだけではなく、その音楽事務所の専属歌手として働くように言ってくれた。
早苗は二人の付き人となった。とても尽くしてくれ、火雪の素性を聞くこともしなかった。
世間知らずの火雪にいろいろなことを教えてくれた。サフラン色のドレスも見繕ってくれた。火雪の白い肌が品よく浮き出るすばらしいドレスであった。
ステージでは、火雪の歌声が雪人のギターを引き立たせ、雪人のギターは火雪の歌声を空に押し出し、フーガのように聴衆の耳を襲ってきた。雪人のギターのうまさはすでに定評のあるものであったが、それに火雪の歌が加わり、そこに今までに聞いたこともない音のデユオの誕生となったのである。
暮れも迫るある日、東京で雪が降った。
その日の夜は、大きなホールでのステージが予定されていた。火雪はいつものように、一時間前にステージ脇の控え室に入った。火雪が化粧を終え支度が整って、周りの人たちが部屋からでていくと、いきなり寒さが襲ってきた。
葉雪であった。
目の前に現れた葉雪は火雪を見た。
「きれいね」
「お母さま」
火雪は首をたれた。
「帰ってきて頂戴、火雪、みんな本当に帰ってきてほしいと思っているのよ」
「いやや、歌を歌いたい」
「でも、あなたは雪女、人間の幸せのために働くの」
「今も、人たちの幸せのために歌っているの」
「そう、そうね、でもあなたは雪女なの。皆ここに来ているの、そこの公園にいるの、ちょっと来て頂戴」
「行きます。でも、私は歌を歌いたいの」
火雪の目から涙がこぼれた。
火雪は葉雪の後をついてホールの裏口から外に出た。
裏口の警備員が、「どうしました」とうつむき加減で傘もささずに出てきた火雪に声をかけた。警備員に葉雪は見えない。
「ちょっと、外の空気をすいたいの、すぐもどります」
火雪は警備員に微笑んだ。
警備員はよくあることのように微笑み返した。
幕が開いた。
いつの間にかもどった火雪は、ステージのスポットライトを一人浴びて、雪人が弾くギターに合わせ歌っていた。
歌声はホールに満ちていった。
雪人の目に火雪は見えなかった。
目の奥の中にしか火雪はいなかった。
火雪は雪女であったことを思い出すことは無い。
火雪
私家版雪女小説集「雪女、2015、222p、一粒書房」所収
表紙日本画:山内佳子


