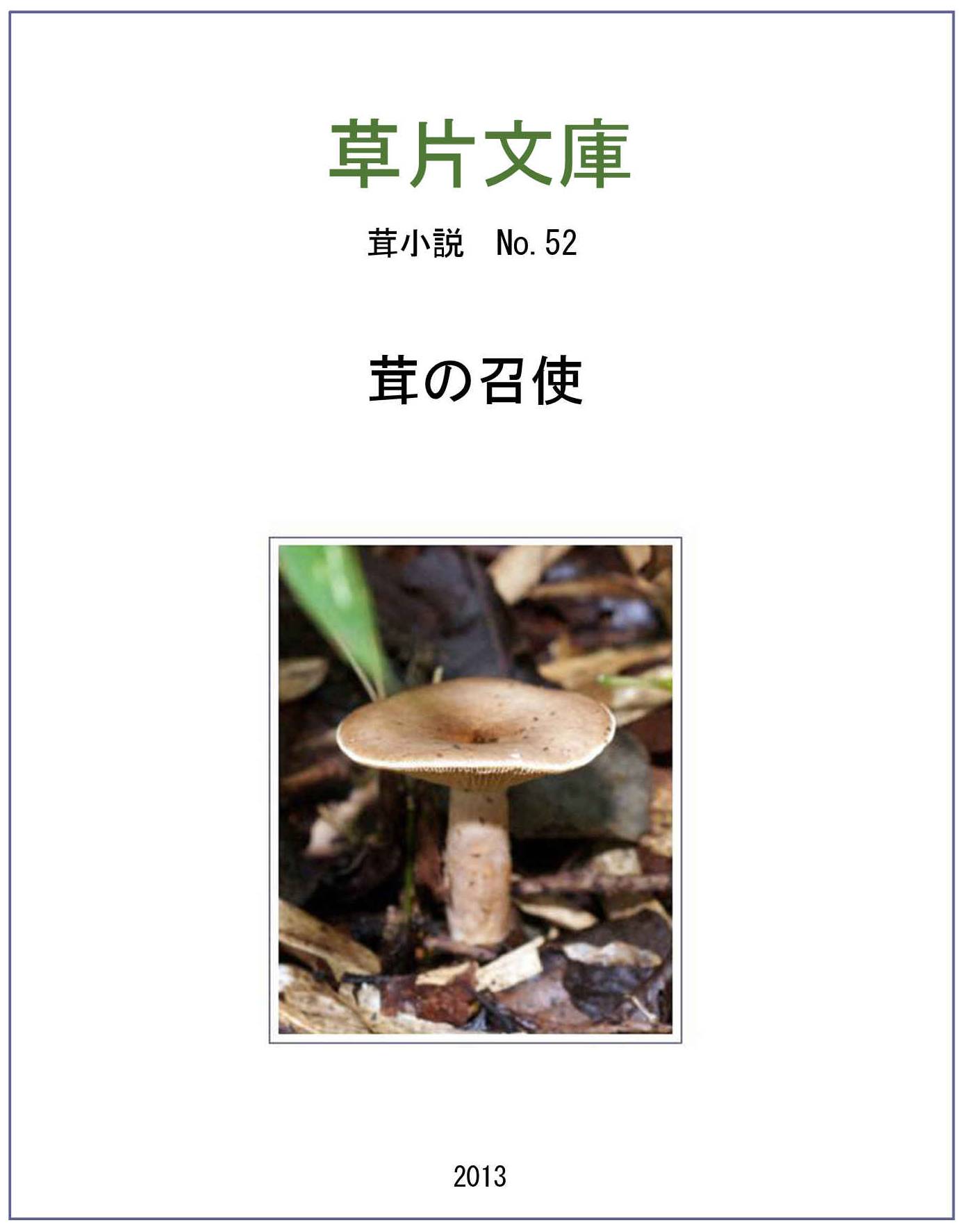
茸の召使い
秋祭りの季節である。我家の近くの神社にも夜店が立ち並んでいる。綿菓子、ハッカ、杏飴、昔ながらの懐かしい情景である。子どもの頃は暗くなった境内をその時だけは許されて、下駄を突っかけ、風に吹かれながら歩いたものである。電球がつる下がっているその下で、アセチレンガスの青い光と、あの臭いはたまらなくなつかしい。カルメラ焼きの匂いも忘れることができない。
屋台の一番はずれに、茶色のハンチング帽子をかぶった白い髭を生やしたおじさんが、茶色の皮のかばんの前で折りたたみ椅子に腰掛けている。うつむいて自分の手を見てなにやらしている。
小学三、四年生ほどの少年が老人の手の中のものを不思議そうに見ている。
近寄って、小学生の後ろに立った。
老人の皺だらけの手の上には、茶色の茸がぴょこんと立っている。老人が茸を指で包み込んで、ぱっと指を広げると、茸はもうなくなっていた。手の平の上になにもない。また同じことをすると、黒い茸があらわれた。手品をやっているようだ。
少年が老人の茸を指さした。
「どうして消えたの」
「この茸が勝手に隠れたんだよ」
「どこに隠れたの」
「小さく縮まって、私の指の間だよ」
「そいじゃ手を開いたまま、茸に小さくなれと言ってよ」
「ああ、いいよ、ほら、茸よ小さくなりなさい」
老人がそう言うと、黒い茸はすーっと小さくなり、米粒くらいになって、老人の指の間に潜り込んだ。
「本当だ」
どのような仕掛けなのかわからない。
「ぼおや、この茸がほしいかい」
「うん、でもお金持っていない」
老人は革のトランクを開けた。中には色とりどりの茸がごろごろと詰まっていた。
「いいよ、一つあげよう、好きなのを選びなさい」
「うん」
少年は赤い茸を選ぶと手の平に乗せた。
「どうやるの」
「茸と友達になれば何でもやってくれるよ」
「どうやって」
「茸を好きになるのさ」
「でも、茸に嫌われたらどうなるの」
「食べられちゃうさ」
「ふーん、僕大事にするよ」
「ああ、そうしなさい」
「ありがとう」
少年は茸を手の平に載せて、喜んで帰って行った。
老人は私を見た。
「お宅もほしいのかね」
「ええ、いくらですか」
「いや、お金はいらんのですがね、大人はこの茸と仲良くなるのは難しいですぞ、友達になれないと食べられてしまいます」
「お金をとらないで、あげてしまうだけでは、困らないのですか」
私は余計なお世話かとも思ったがつい聞いてしまった。
老人は真顔で答えた。
「そうですな、ご心配にはおよびません、私は茸に信頼されましたのでな、欲しいものはすべて、茸からもらっておるのです」
「手品の茸を配るのが趣味ということですね」
「はは、茸たちに頼まれているのですよ」
「私もそれでは一ついただこうかな、仲良くなって幸せになろう」
「大人にはあまり勧めませんが、本気なら、どうぞお好きなのをおとり下さい」
老人はトランクを開けた。
どれにしようか迷っていると、老人はだまって私の動きを見ている。
トランクの中の重なっている茸の下の方で何かきらっと光った。
目を凝らすと、一番下にある紫色の茸が傘の縁から水滴をたらしている。それが光に反射したようである。
「あ、茸が涙流している」
私が思わず口走ったことで、老人があわてた。
「お、そ、そりゃいかん、気がつかなんだ」
老人は茸をかき分け、一番下になっていた紫色の茸をつまみ出すと手の平に乗せた。
「すまんことをしました、どうしました」
紫の茸が身をくねらせた。面白い手品だ。
「あの赤い茸と仲がよかったのですか、一緒に行きたかったのですな、そりゃ、悪いことをしました」
私はその会話をほほえましく聞いた。
「私は、今独り身、しかもこの近くに住んでおります。あの少年もきっと近くに住んでいます、その紫の茸をもらって、赤い茸を捜してあげましょうか」
「そりゃあ、願ったりですな」
紫色の茸の傘が私の方を向いた。私は昨年家内に先立たれ、子供たちはヨーロッパ暮し、三匹の雌猫と一人暮しをしている。時間はたっぷりある。
老人は紫色の茸を私の手の平に乗せた。茸はぶるっと身震いをして小さくなると私の指の間にはさまった。
「あなたに、その紫色の茸を差しあげますが、くれぐれも仲良くしてくださいね、そうしないと、食べられちゃうから」
老人はまた食べられちゃうを繰り返した。
「さて、今日はそろそろ店じまいとしますかな」
トランクを閉めて立ち上がると、老人はかなり背の高いことが分かった。私も低いほうではないが、見上げるほどである。
手がくすぐったく感じ、指の先の紫色の茸が落ちるのではないかと見ると、大きくなって揺れている。
「くれぐれもよろしくおねがいします」
そう言って老人は神社の入り口のほうに向かった。彼は少し行くと、一度振り返ってわたしにおじぎをした。顔に奇妙な笑いが浮かんでいた。
私は茸を指で包むとそのまま家に帰った。
玄関の鍵を開け中にはいると、三匹の猫がお腹を空かせてよってきた。私はキッチンのテーブルの上に茸を置くと、「ちょっと待っててな、猫に餌をやるから」と茸に声をかけて、猫の皿の中にカリカリをあけてやった。猫たちが食べ始めたのでテーブルに戻ると茸がいない。おかしいと思ってテーブルの上を探すと、ノリタケの真っ白なティーカップの中で紫色の茸が満足そうによりかかっている。私がいつも使っているものだ。茸が動くわけはないから、私が間違えて入れてしまったのだろう。
「それがお気に入りか、それじゃおまえにやるよ、僕は別のカップにしよう」
私は冗談交じりでそう言うと、紫色の茸はカップの中で立ち上がって僕の方にお辞儀をした。私はびっくりした。手品の仕掛けではない。
それにしても律儀な茸である。
そこへ黒猫がテーブルの上に飛び乗ってきた。我家の猫はやり放題である。どうも私の躾が甘くていけないかもしれない。
黒はカップの中で立っている茸を見ると鼻先を茸の傘にくっつけようとした。
いきなり茸の傘が上下に開くと、猫の鼻にかみついた。ように見えた。驚いた黒は後ろに飛び跳ね、テーブルからずれ落ちた。実際に黒の鼻先が赤くなっている。黒はなにが起こったかわからず、前足で鼻先をぬぐっている。
白とグレーの猫も興味をもったとみえてテーブルの上に飛び乗った。今度は茸がカップから飛び出ると、白とグレーの鼻先にかみついた。二匹とも黒と同じようにテーブルから落ちた。
それ以後、猫たちはテーブルの上に全く上がろうとしなくなった。この紫色の茸はテーブルの上を自分のテリトリーにしたのである。
猫たちは椅子の上から、かろうじてテーブルの上を眺めるだけになった。夜店のトランクの中で涙を流していたのとは大違いだ。元気な茸だ。
私も茸が動き回っても驚かなくなっていた。
私は茸に「なにを食べたいんだい」とたずねた。すると、「食べ物は自分で探すからいい」と私の頭の中に返事があった。
「それじゃ何したい」
「ほっといてくれていい、自分の食事の用意でもしな」
つれない返事であった。
どうも猫たちにはこの会話が聞こえているようだ。三匹とも尾っぽをぱたんぱたんさせ、耳をとがらせている。
「それでは、飯の用意でもしよう」といつものように、カレーを暖めて、角瓶をとりだした。炭酸で割ってビール代わりに飲むのである。角のハイボールは一番うまい。
カレーの匂いが漂ってきた。
「お、旨そうな匂いだな」
紫の茸がティーカップの中で頭を振った。
「カレーははじめてか」
「ああ、あのじいさんは和食しか食わなかった」
「カレーにマッシュルームが入っているがいいのだろうか」共食いになると思って言ってみたが「西洋茸か、たいして旨くもないのに、俺は中身は食わんよ、そのどろどろとした黄色いものがいい、このカップに入れてくれ」
そう言うと、紫の茸はカップから飛び出した。
私はカレーの汁だけをカップに入れた。
「熱いよ」
そういい終わらないうちに、紫の茸はカレーの中に飛び込んだ。
「うふうふうふ、うん、うふ旨い」
そう言いながら、カレーの中に頭まで潜り込んだ。しばらくすると、ぽっこりと頭に黄色いカレーを載せたまま立ち上がった。
「うん、カレーはなかなか旨いものだ、おい、おまえは食べないのか」
茸がカレーに浸かるのが面白くて見とれていた。自分は食べていないことに気がついた。
茶碗にご飯をよそうとカレーをかけて食べた。今日のパックはタイカレーである。それに浸かっちまうというのはずいぶんピリピリするに違いないのだが、紫の茸はぜんぜん気にしていない。
「ちょっと、手間かけますが」いきなり茸の丁寧な言葉が聞こえた。
何だと見ると、カレーまみれの茸が、「その白い粒粒、ちょっとくれないか、別のカップに入れて」と言っている。
今度は飯のおねだりだ。私は戸棚から別のカップを出して、ご飯をよそってやった。
紫の茸はカレーから飛び出すと、テーブルの上をカレーだらけにして、飛び跳ね、ご飯の入っているカップへ飛び込んだ。ご飯の中を飛んだりはねたりした。茸はご飯粒だらけになった。カレーかけ茸飯である。ちょっと旨そうに見える。
「気分いいね」
茸はご飯粒だらけになってうっとりしている。
「ずーっとそうやってると、ご飯粒が乾くと堅くなってはがすのに大変だぞ」
私が本当に心配してやると、
「そうか、それなら、砂糖水をカップにくれないか」との要求だ。
私はカレーのカップを洗うと、砂糖水を入れてご飯のカップの前に置いてやった。
茸はぽんと飛び出ると、ぴちゃんと、砂糖水に飛び込んだ。
「ほー、いい気分だ、前のじいさんより今度のじいさんの方がいいな」
勝手なことをほざいている。
「さて、あたしは寝たい、乾いたティーカップを用意してちょうだい」
人使いのあらい茸である。しかも女言葉になった。ままよ、ご飯のカップを洗って、布巾で拭いて、茸の前に持っていってやった。
「湯上がりタオルがほしい」
と言うので、新しい布巾を出すと、茸はその上を転がって、乾いたカップに入り、船をこぎだした。
そういうことで、その日の夕食は茸を中心に大荒れだった。私は、少しばかり書き物をしてベッドに入ると、猫たちもいつものようにぞろぞろとベッドの上にやってきた。こうして茸との第一夜は終わったのである。
次の日の朝、八時を回ったころ目を覚ました。洗面所で顔を洗ってキッチンに行くまで茸のことを忘れていた。テーブルの上のティーカップを見て思い出したのだが、茸はいなかった。茸のことは夢だったのかと変な気持ちになったが、やっぱり気になって、テーブルの下を探した。しゃべる茸なんているわけは無いのに、と思い返して、朝食の用意をした。
猫は朝早くからどこかに出かけていていない。いつものことである。茸は猫にでも咥えられて持っていかれたのかもしれない。まだ茸が頭に引っかかっている。
さて、ハムとレタス、それに、食パン一枚、果物、ヨーグルトに紅茶、これが私の朝食である。
葡萄を洗い、紅茶をいれて、パンが焼きあがるのを待っていた時である。猫の出入り口から紫色の茸が飛び込んできた。
やっぱり本当だったんだ、奇妙なことである。
私が、「どこいってたんだ」と尋ねたのと同時に、黒い猫が入ってきた。次に白、グレーと続いた。
猫たちは茸を真ん中にして座り込んだ。
茸が猫に何かを言っているようであるが、私にはわからない。黒が髭と尾っぽを揺らして茸に説明している。茸が私に言った。
「朝食を食えよ」
トーストができているのを忘れていたのである。私はレンジを開けパンを取り出すと、マヨネーズとハム、レタスをはさんで、ひとかじりした。
「食事はしなくていいのか」
昨日のようにやっかいなことになるのも面倒だが、一応聞いてみた。
「いらん、今旨いものを食ってきた」
「旨いものってなんだい」
「こいつらが捕ってくれたんだ」
なにを捕まえたのだろう。この猫たちにそんなことはできるはずがない。ただ寝て起きて餌食って、また寝ている。
「鼠だ、そりゃ旨かった」
「鼠喰ったのか、茸が鼠をどうやって食うんだ」
紫茸が傘の途中をぱくっと口のように開けた。それにはぎょっとした。口の中にするどい歯がびっしり生えている。
私は黙ってうなずいた。茸売りの老人が食べられないようにしろといった意味がわかった。チャッキーのようだ。
私は葡萄を食べ、ヨーグルトを飲み終えた。
「さて、食事が終わったし、しばらくしたら、赤い茸を探しに行こうか」
そう紫茸に声をかけたのだが、もう興味が薄れているようだ。
「あの赤い茸はどうでもいいさ」
「だって、分かれたくなくて涙を流していたじゃないか」
それを聞いた紫茸は、また大粒の水滴を垂らした。
「ほら、涙を流しているじゃないか」
「あほらしい、あのじいさんはまだ我々のことをよくわかってないんだ、俺は、目立つために水滴をたらしたんだ、勝手におまえが泣いていると言ったんだ」
「どうしてやったんだ」
「あのトランクから出たかっただけだ。おまえのような奴が持ってってくれるのを楽しみにしていたんだよ」
「嘘つきか」
「そうだ、あたりまえだ、楽しく生きるためだ」
「それじゃ、あの赤い茸と離れたのが悲しかったのではないわけだ」
「俺は、そんなこと一言も言っていない、勝手にお前たちが茸に感情移入したんじゃないか」
そう言われればそうである。
「涙なんて出るわけがない。目がないんだぜ、せいぜい汁だ」
確かにそうである。
「それじゃ、赤い茸の少年を探さなくてもいいんだな」
「そうだ、だが、あいつが少年の家を飛び出して、ここに来るかもしれん、仲のよかった奴であることは確かだからな、あいつもしたたかだよ、本当は茶色い茸なのに、赤い方が拾ってくれると言って赤くなった」
「そんなことができるのか」
とたん、紫の茸は赤くなった。
「踏ん張ると赤くなるんだ」
そんなものか。
「それで、これからどうする」
「一週間ほどおじゃまさしてもらう」
ずーっといたらどうなるだろうと心配だったが、一週間なのだ。
「私のじゃまをしない限りかまわんが、大したもてなしはできんよ」
「かまわんよ、おもしろい猫たちと遊ぶさ」
猫がこっちを向いた。明らかに迷惑そうである。だが、しかたがない。
「それじゃ、私は仕事をはじめるからな」
「どうぞ、ほれ、猫、どこかに行こうぜ」
紫茸はぴょんぴょこ飛び跳ね、猫を誘って外に出ていった。
まったく、世の中の茸がみんなこれだったら大変だが、あの夜店のじいさんのトランクにある茸だけなのだろう。いっそ、茸の話でも書くことにするか。私は机に向かった。私は小説家である。
どのような話にしようか考えていると、キッチンの猫穴の戸がかたっと開く音がした。もう帰って来たのだろうか。気ままなものである。ほっとこう、そう思ったとたん、「だれかいないか」と、大きな声がした。
なにごとだと思い、キッチンに行くと、茶色い茸がテーブルの上で突っ立っている。
「夜店で少年にもらわれていった赤い茸じゃないか」
「そうだ、紫の親分はどこだい」
「今猫と遊びに行った」
「帰るのを待たしてもらうぞ」
「そりゃかまわないが、あの少年の家を出てきたのか」
「いや、出たわけじゃない、小学校に行っちまったんで、ちょっと親分に挨拶にきたのだ、探すのにちょっと苦労したがな」
「どうしてわかった」
「親分の匂いだ」
「鼻がいいんだな、少年の家の居心地はどうだ」
「なかなかいい、地味だがいい家庭だ、あの坊主も素直でいい、だからいろいろ手伝ってやっている。苦手な数学が嫌いじゃなくなる方法を教えてやった」
「親切な茸だ」
「親分はいつ帰ると言っていた」
「いや、知らん、どこに行ったかもわらんね」
「このテーブルはなかなか居心地がいい、見晴らしがいい」
茶色の茸が変なほめ方をした。
「このティーカップは親分の寝どこだな」
「どうしてわかりなさるのかな」
「親分の匂いさ、でも、変な匂いが残っている、ご飯粒の匂いはわかるが、もう一つがわからんな、ちょっと興味がある」
「それはきっとカレーの匂いだ」
「食べ物か」
「そうだ、きっと少年の家でもカレーはよく作ると思うよ」
「そうか、それは楽しみだ」
「ところで、赤い、いや茶色の茸君、君たちはどういう種族なんだ、人間とこのように話もできるし、どうやら、からだからいろいろ吸収するみたいだが」
「昔からいる茸族だよ、動物が食っちまう茸と基本的に同じだが、茸の中に神経が発達して、独自の生物になったんだ。動物ではなく動(どう)茸(じ)だ」
「ほー、どうやって増える」
「そのうちわかるさ」
「どうやってしゃべっているんだ」
「細胞がふるえて、身体が振動する、それが動物の脳に直接つたわる」
「なぜ、あの夜店のトランクにごろごろと入れられていたのだい、自分でどこへでもいけるだろう」
「ああ、そこが我々の弱いところで、一週間動くと一月休眠するんだ、その時はじいさんのところに帰ってトランクの中で寝かせてもらうのさ、あのじいさんには分不相応くらいの礼をやってるがね」
「でも休眠中に誰かに持って行かれたら困るだろう」
「あのじいさんの家には三百六十五個のトランクがあって、厳重にしまわれているのだよ。じいさんは日本中のどこかの夜店や街角に毎日行くのさ、その手助けもしている、あっという間に日本のどこにでも行くことができるんだ」
「そんなことが出来るのか」
茶色い茸と話しているところに、猫を従えて紫の茸が戻って来た。
「おう、茶公来てたのか」
「紫の親分久しぶりで」
「どうだ、あの坊やの家は」
「なかなかでござんすが、親分の方もお楽しみで」
「ああ、猫たちがいい、飼い主もまあまあだ」
飼い主を目の前にして、しゃあしゃあと言いおる。
「今、茶色い茸から、一週間でまた休眠だと聞いたが、あのじいさんのところに帰るのかい」
「そうだよ、あのじいさんはわしらが雇ったんだ、寿命がつきるまで、あのじいさんは苦労知らずだ」
「寿命が来たらどうするんだ」
「新しい奴を捕まえるんだ、おまえどうだ」
「おことわりだよ」
「まあ、職にあぶれたら声をかけな、悪いようにはしない」
「そりゃご親切に」
猫たちは紫の茸の周りで会話を聞いている。
「あと数日やっかいになるからな」
「ああ、どうぞ」
そこに、白い茸がやって来た。
「おお、白公も誰ぞにもらわれていったのか」
「うん、若い女の子だ」
「ほお、それで、いい気分なんだな」
「とんでもない、しみったれの、頭なしだ、ちょっと顔がきれいだと言われて、天狗になっているバカだ。料理もできない。俺を連れ出したのも、ほかの奴に見せびらかせて注目を浴びたいだけだ、かみついてやった」
「そうか、そりゃ災難だったな」
「まあいいさ、これも一つの経験だ」
「それで何か用かい」
「紫の親分がもらわれたと聞いたんで、こりゃ挨拶に行って面白いことのおこぼれをと思いましたんで」
「よし、それじゃ、明日の夜中、ここへ集合だ、茶公もこいよ」
「もちろんで親分、それじゃ、夜中にまいります」
茶と白の茸は敬礼して帰っていった。
「動茸族は何匹、いや何人いるんだい」
「俺たちは日本で進化したんだ、日本にしかいない、およそ、八万人だ」
「日本のどこにいるんだ」
「いろいろなところさ、沖縄から北海道まで津々浦々、雇っている人間は五千人だ」
「そんなにいるのか」
「皆年寄りで身寄りも無く、稼ぎも無い、かわいそうな奴らさ」
「なぜ、爺さんばっかりなのだ、婆さんもいるだろ」
「婆さんは駄目だ、皆しゃべっちまう、それに、茸は食いもんだと思っている」
「そんなもんか」
「もう一度探検するか、今度は俺一人で行ってくる」
ということで、残された三匹の猫は寝室に入るとベッドの上で丸くなった。私は今の出来事などを含めて記録に残すためにコンピューターに向かった。いずれ小説の材料になる。
その夜中、私の足下で丸くなっていた三匹の猫たちが起き上がったのを感じ、ちょっと目を覚ました。しかし、すぐまた寝入ってしまった。昨夜は筆が進んで遅くまで書いたせいだろう。
朝、いつにもまして遅く目が覚め、顔を洗ってキッチンにくると、三匹の猫が戻っていて見上げている。いつもより大きな声で餌をねだった。用意をしながらテーブルを見るとティーカップの中で紫茸がぐたーっとなっている。
「おい、大丈夫か」
ちょっと気になって声をかけると、傘を少し上に向けた。
「大丈夫だ、昨夜はちょっとやりすぎた、疲れた」
「ビタミン剤やろうか」
「ああ、どちらかというと、ドリンクの方がいい」
私は徹夜で物書きをする時のために滋養薬ドリンクを用意している。それを茸のティーカップにそそいでやった。
「おー、気持ちがいい、悪いねえ、今日はこのままここで寝て、明日、夜店のじいさんのところに帰ることにするよ」
「まだ、一週間経っていないじゃないか」
「ああ、だがエネルギーを使い果たした、もう休眠するよ、茶の奴も白の奴もそうすると思うよ」
「そうか、それじゃよく寝てくれよ」
猫たちがまた餌をねだった。餌の皿は空になっている。
「よく食べるね、きっと茸とよく遊んだんだ」
私はもう一度餌を三つの皿に入れてやり、自分の食事の準備をすると、いつものようにパンと紅茶とヨーグルトと果物の朝食をとった。
紫茸はティーカップの滋養ドリンクに浸かっておとなしくしている。
その日は後片付けをして、作家仲間の会合に出かけた。
いつものように仲間たちと、行きつけのバーでつまらないこまごました話をして、家に帰りついたのが夜の十一時であった。玄関を開けると、三匹の猫たちがどたどたと寄ってきて足に擦りついたり、手をかけたり、いつもと違ったおねだりである。お昼用に猫餌をそれぞれの容器にたっぷり入れておいたのだが、空っぽになっている。
「よく食うな」と酔っぱらったからだを引きずって、餌を入れてやった。猫たちは早速食らいつき、ボリボリと音を立てて食べた。
なんてやつらだろう。テーブルの上を見ると、紫の茸はティーカップの栄養剤に浸りながら、頭をこっくりこっくりしている。まだ寝ているのだ。
私は起こさないようにそーっとキッチンを出た。パジャマに着替えるとベッドにはいった。すぐ睡魔がおそってきた。だが、猫たちが食事を終えてベッドの上にあがってきたことは覚えている。
明くる朝、テーブルの上のティーカップの紫茸はしゃきっと立っていた。
「世話になったな、これでさらばだ、お礼にと言っちゃなんだが、あんたの小説が大当たりまではいかないが、食うには困らんほどの話題になるようにはからっておく」
「そりゃうれしいが、今でもそこそこの生活はできているから満足さ」
「その精神は見上げたものだ、それじゃ、さらばだ」
「住まいはどこなんだ」
「あのじいさんのいるところさ、俺たちのからだの中にカーナビ神経があってな、召使いのいるところはすぐわかるんだ」
「気が向いたらまた遊びにおいで」
「ありがとよ、一月寝たら来るかもしれねえな、それじゃ」
そう言い残して、紫茸は猫穴から出ていった。いなくなると、なんだか物足りなくなる。家族が多いのはいいものだ。
寒い冬の季節も終わり、芽吹きの季節になった。動く茸が帰って半年が経っている。一月寝たらまた来ると言っていたが、とうとう来なかった。
あれから茸たちは来ることがなかった。猫たちは食べてばかりいてずいぶん太った。
今日は近くの神社の春祭りだ。
昼間からわっしょいわっしょいと元気な声が聞こえてくる。
夜になり、いつものように見物に行くことにした。
神社にはいると、かなりの人がきている。参道の脇に四、五軒の屋台がある。ふらふら歩いていくと、はずれにあの老人が茶色のトランクを前にして椅子に腰掛けていた。手品をやっていないので、誰も周りにはいない。
「おお、来ましたな、待ってました、紫の茸がたいそう楽しんだそうで、ありがとうございますな」、そういって、トランクから茸を取り出し手のひらにのせた。
「今どうしていますか」
「はあ、家にあるトランクで休眠しとります」
「あの茸があなたのことを召使いなどと言っておりましたぞ」
「ええ、そう言っていただけますと、光栄です」
私はその返事には少しばかり驚いた。
「動茸の召使いになれたことは、総理大臣に選ばれるより大変で、光栄の至りですな」
「そういうもんですか」
「そうそう、紫の茸が言っておりました、なにが起きても驚かないように、その時にはこれを読んでくだされとのこと」
私は封筒を渡された。
「まさか、茸が手紙を書くわけがないですね」
「紫様が言ったことを私が書いたのです、それが私の役目でね」
老人は笑った。そこへ少女が目を輝かせて寄ってきた。
「その手の上の茸、どうするの」
「見ていてごらん」
老人の手の平から茸が消えた。
「あ、消えちゃった」
ぴょこんと再び手の上に現れた。
「茸どこに行ったの」
「どこだろうね」
私は老人に挨拶をすると、家に戻ることにした。手紙になにが書いてあるのか知りたかったからだ。
玄関の鍵を開けると、手紙どころではないことが起きていた。三匹の猫が床の上でひっくり返ってうんうんとうなっている。
お腹がぽっこりと盛り上がって、食べ過ぎて苦しがっているようだ。
黒のお腹をさすってやった。黒は少し楽になったらしく、大きな目で私を見た。白とグレーのお腹もさすってやった。
「こんなに食べちゃだめだよ」
私がそう言って、黒を見ると、黒はうーんといって、ふんばった。
「こんなとこでうんちか」
こりゃ困ったと思っていると、黒のお尻から紫色の茸がころころところがり出た。白からは茶色い茸がぞろぞろと転がり出た。グレーからは白い茸が飛び出した。猫たちはそれぞれ八匹の茸を生み出した。小さな茸は床の上でゆらゆら揺れている。猫たちはほっとして眠ってしまった。
なんてことだ、その時、何かあったら手紙を読めと、あの爺さんに言われたことを思い出した。
私はあわてて封筒を開いた。
そこにはこう書いてあった。
「猫との逢瀬は楽しかった。これから我々の子供が産まれた時のことを書いておく、生まれたらすぐ砂糖入りのお湯につけてよく拭いてやるように、その後は、毎日、日本酒を飲ませると、とてもよく育つ」
茶白紫の茸の子供たちが寝ている猫たちの周りに集まった。私はあわててラーメンどんぶりを三つ用意し、砂糖を入れて、中にお湯と水をそそいだ。
布巾を用意して、「紫おいで」と言ってみた。
すると、紫色の茸の子供が列をなしてどんぶりの前に並んだ。私は先頭の奴から砂糖水に浸し布巾で拭いてやった。八匹終わると、次は「茶こい」と言うとちっこい茶色い連中が整列した。茸の赤ん坊は生まれてすぐに頭が発達、いや、神経が発達しているらしい。また一匹ずつ砂糖水につけて拭いてやった。白い茸にも同じことをした。
茸の子供たちはピョコピョコ飛び跳ねてお互いにぶつかったり、転がったりしている。まさに猫の子供が遊んでいるようだ。とうとう寝ている猫の上で跳ねるやからがでてきた。みんな面白がって猫の上に集まった。三匹の猫は薄目を開けると、自分の子供だから仕方がないかといった表情で、また寝てしまった。
私は紙に書いてあることの続きを読んだ。
子供たちは一週間たつと思春期を迎える。そのころから休眠するのがでてくる。休眠した奴は、乾燥しないような場所に寝かせ、みんな休眠したら、ここに電話しろと電話番号が書いてあった。
まあ、一週間で片がつくのならと、茸たちを遊ばせたまま、日本酒を買いに行った。酒屋は近くにないので、駅の近くのスーパーまで行った。日本酒もピンからキリまである、どれにしようか迷ったが、一週間なら一升で足りるだろうし、上等のものを飲ましてやろうとちょっと奮発した。めずらしく土佐の酔鯨というラベルの四国で金賞というのがあった。そいつを買って帰った。
一日何回食べさせたらいいのかわからないが、私の食事のときに、必ず日本酒を用意してやった。しかし、人間でも赤ん坊には一日何回もミルクを飲ませる。そんなことから、三つのラーメンどんぶりに酔鯨をなみなみといれておくことにした。
すると、猫の周りを跳ねていた子供茸は寄って来て、順番に日本酒の中に飛び込むと頭までつかってひょこっと出てきた。
私の頭の中に、きゃあきゃあと喜ぶこどもの茸の声が聞こえた。まあ、喜んでもらって悪い気分はしない。
子茸は酒に浸かって出てくると、ちょっと大きくなっているようだ。
居間で原稿書きをしながら注意していると、三時間ごとに日本酒に飛び込んでいる。どのくらい減ったかのぞいてみると、半日でなくなる。もし夜にも日本酒を浴びるとなると、4回足してやらねばならない。そんな心配をしていると、子茸たちは夜には猫たちにくるまれて寝てしまった。夜遅くまで原稿書きをしていたが、起きる気配はない。
ということで、朝と昼にどんぶりを日本酒でいっぱいにしてやればよいことがわかった。しかし酔鯨一本では一週間もたないことになる。
小指ほどしかなかった茸たちはどんどん大きくなり、重くなってもきたようだ。上に乗られた猫たちはぎゃふんといった様子で茸を避けている。生まれて三日もすると、猫たちの後をついて外に出るようになった。
四日目である。酔鯨が空になったので、今度は秋田の高清水を買ってきた。新しい酒もお気に入りのようで、ポチャポチャと酒浴びをした。というより身体から酒を飲んでいるのである。かなりの大きさまで育った。
その夜、騒がしいのでベッドから起きてキッチンにいくと、三匹の猫が鼠をくわえてきて、茸たちが取り巻いて見ている。猫は茸たちに何か言っている。
猫はくわえている鼠を放した。とたん茸たちが寄ってたかって鼠をかじってしまった。なんと恐ろしい光景か。尾っぽまですべてなくなってしまった。
猫がまた外にでていった。茸たちもついていった。
寝室に戻ると、ベッドにはいった。すぐに寝てしまったので、その後のことはわからない。朝遅くにめざめると、猫と茸が一緒になってベッドの足元に、寝ているのに気がついた。
自分の朝食をとり、どんぶりに日本酒を入れてやったが、起きてくる気配がない。居間で仕事を始めても起きてこなかった。しばらくして気になるので、寝室をのぞいた。それに気がついたのか、紫色の一番大きく育ったやつが身を起こして私を見た。茸の世界でも大きく育った奴がガキ大将になるようで、こいつがいつも一番よく話しかけてくる。
「おっさん、昨日はおっかさんに鼠の捕り方を教わった」
おっかさんというのは猫の黒のことである。
「そうか、そりゃよかった」
「あんたは鼠が捕れるんかい」
「素手じゃとれない、鼠捕りを使う」
「やっぱりそうか、猫の方が能力が高いんだな」
変な理論だと思ったが説明が面倒なのでほうっておいた。
「おいらのおっかさんはすごいぜ、だだだーっと走ってパクっとくわえちまう」
「そりゃすごい、腹が減ったのか、酒は入っているよ」
「鼠をたくさん食ったから腹は減っていない」
「何か用か」
「どうも体の調子がおかしい、眠くなってきて、頭のてっ頂がむずむずする」
「そろそろ思春期だな」
「胞子がでそうだ」
「こんなところで出すな、眠いなら寝床に案内してやろう」
こいつは早く育ったから休眠になるのだろう。
私は空いていた押入の中の布団の上に乗せてやった。ここなら薄暗いし休眠の環境にはよいだろう」
ということで、休眠第一号は紫色の茸だった。
夕方になると、四つの茸が休眠を訴え、押入れに寝かしつけた。
次の日から、ぞろぞろと休眠に入り始めた。鼠を食べたために早く大きくなったのかもしれない。
とうとう全部が押入の上の段でごろごろと眠りについた。
私は書かれていた電話番号を携帯でプッシュした。
「もしもし」
「はい、動茸の召し使いでございます」
「子供の茸が休眠にはいりました」
「もしや紫茸をもっていかれた方でしたかな」
「ええ」
「早いですね」
「茸が鼠を食ったせいではないでしょうか」
「ああ、お宅の子供は猫が産んだのでしたな、合点がいきました。今日連れにまいります」
夕刻、黒塗りの高級車が私の家の前に止まった。
運転手がドアを開けると、夜店の老人がタキシードを着て、真新しい茶色のトランクを抱えて降りてきた。老人は玄関のベルを押して、直立不動で待っていた。
玄関の戸を開けると、老人は「失礼します」と入ってきて、また直立不動になった。
「動茸の長老から、くれぐれもよろしくとの仰せでありました。子供の世話をありがとうございました」
腰を深く折りまげた。
私はそのいでたちの立派さにも驚いたが、大仰な物言いにも驚いた。
彼を家に上げ、押入れに案内した。布団の上に子茸がころがっている。
「これは、いいところにお子さんを寝かして下された、感謝いたしますぞ」
トランクの鍵をあけると蓋をひらいた。
「何しろ、新しい命は貴重ですからな、最近、なかなか動茸のお子が増えませんでしてな、このあたりでは久しぶりでございますわ」
老人は寝ている茸を一つずつ取り出して、トランクの中に丁寧に並べた。
「かわいいですな」
蓋を閉めると、老人は「この子供の母君にもお会いしたい」と私にたずねた。私はその物言いに噴き出しそうになった。
老人はキッチンに行くと笑顔になった。
「おお、おお、あそこに固まって寝てらっしゃる、母君たちは」と台所の隅で丸まっている猫の黒、白、グレーを見た。
「猫殿、感謝いたします、これはほんのお礼でございます」
彼は粉の入った大きな瓶をとりだした。
「これは」と聞くと、
「またたび粉」でございますと、老人は笑顔で答えた。
さらに、「子育て役のあなた様は猫殿の召し使い、私と同じ立場でございますので、私と同様の報酬を差し上げるとのことでございました」
「それはどういうことで」
「未来でございます。あなた様が生まれ変わる時、動茸になる権利を差し上げます」
「よくわかりませんが」
「死んだ後、人もなにもかも次の世があります。あの世ではありません、望んだものにもなれますが、望んでもほかの人間は動茸にはなれません、あなたはその権利をさずけられたのです、おめでとうございます」
「あなたも死んだ後は動茸になりたいと思われるのですか」
「もちろんです、人間よりはるかに進んでいる生物です」
「でもあくまでも茸、人に食べられてしまうでしょう」
「ご冗談を、食べてみたらいかがです。ちょっとでも敵対すると、どうなるか、何でも食っちまう茸です、一番強い生物です」
「はあ、わかりました、光栄に思います」
茸が口を開けて鋭い歯をぎらぎらさせたのを思い出した。
「さて、私は行きます、もうお会いすることもないかもしれません、この茸の子供たちが大きくなって、訪ねて来るかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。ここの猫様はこの茸たちの母親ですからな、母は恋しいものです」
「猫ではない母親はいるのですか」
「もちろんです、人以外の動物なら母親になれます。鼠から生まれた動茸様もおられます、親に関わらず、みな平等なのが動茸世界です。人間が作れなかったユートピアです」
鼠から生まれた茸は鼠を喰うのだろうか。
ともかく、そう言い終えると、老人は家から出て、運転手が扉を開けて待つ高級車に乗り込んだ。車はゆっくりと走り出し、老人は私を見てもう一度お辞儀をした。
おかしな数週間であったが、終わってしまうと空虚感が漂い、それでも前よりも小説のアイデアは出てくるようになった。短編をいくつかの雑誌に載せたが、どれも評判はよかった。
そうこうしているうちに、黒が紫色の茸を連れてキッチンに入って来た。
茸の子供が大きくなって訪ねて来たのだ。最初に休眠したちょっとおませな紫茸だ。
私はどんぶりに、酒を入れてやった。
茸は日本酒にとっぷりとつかると、
「やはり生まれた家はいいね」と言ってしばらくいたが、
「角のたばこ屋の娘が夜店で僕を選んだんだ、近くだから来ることができた、また来るね」
そう言って帰っていったのである。
私はこのような生活をずーっと続けることになるのかと思うとちょっとうんざリもするが、茸たちに小説の材料になる話が聞けると思うと、それもいいなと考えるようになった。
久々に自分の小説集が出版される。
「茸の館」である。
茸の召使い
私家版第三茸小説集「海茸薬、2017、244p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2014-9-23


