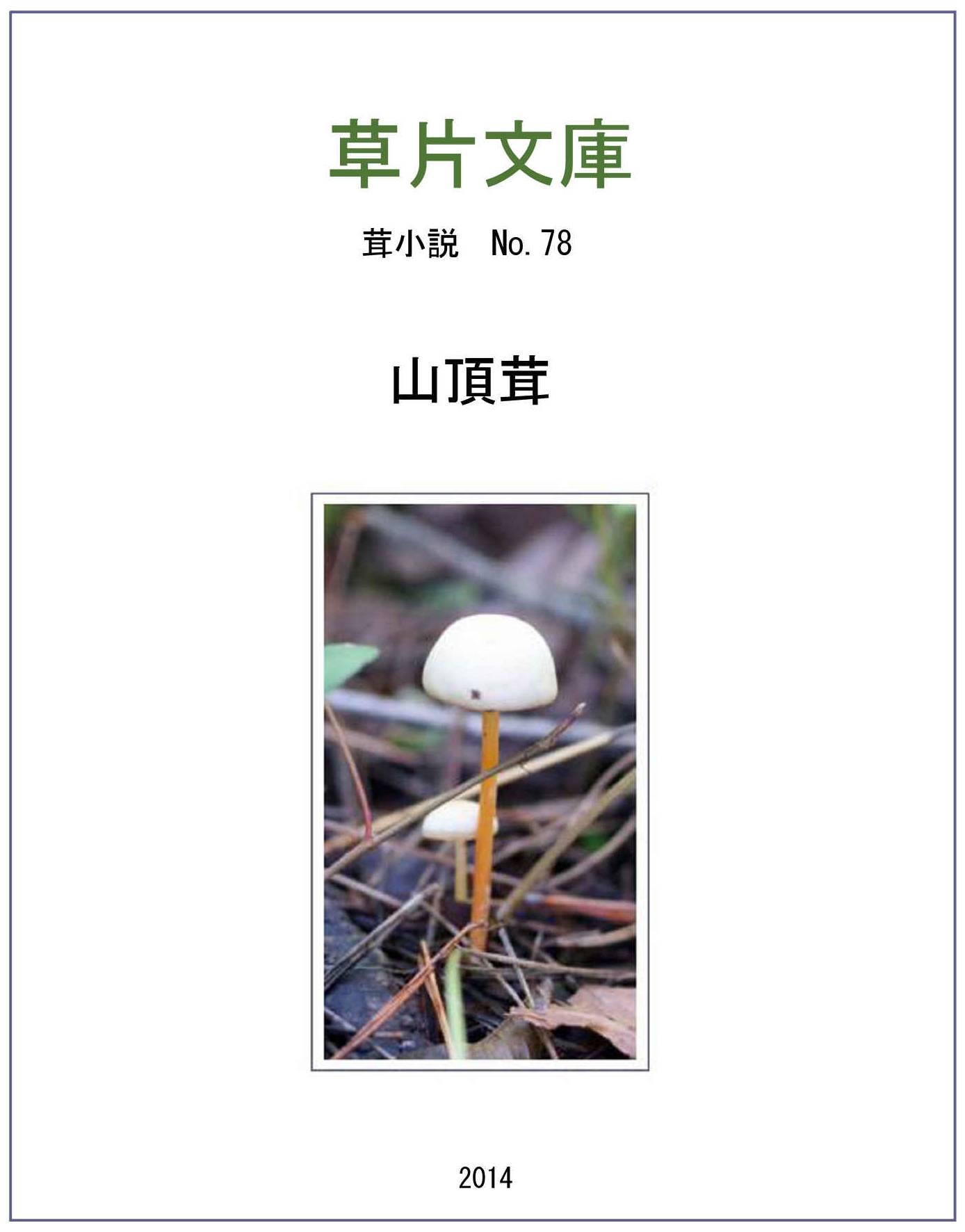
山頂茸(いただききのこ)
山の頂上に生えている茸を食べると長生きをする。こんな言い伝えが私の育った村にはあった。
「それ、どんな茸でもいいの」
友達にその話をしたらそう聞き返してきた。
「さあ、どうかしら」
祖父母からどの茸ではないといけないとは聞いていないような気もするが、忘れたのかもしれない。
「毒茸が生えていたらどうなの」
「そうねえ、今度田舎に帰ったときにおばあちゃんに聞いてみるわ」
祖母はもう九十八になる。だが、頭はしっかりとしており、昔の話をさせるといつまでもしゃべっている。ところが他の年寄りと違うところは、同じことを繰り返しているのではなく、次から次へと話が進展していくのである。
「それ、本当にあったことなの」
作り話かと思い、聞き返すと、きちんと同じ話ができる。ということは、その場の出任せ話とは違うのだろう。
夏になり、仕事を一段落させて田舎へ帰ることにした。秋田の奥羽線にある醍醐という駅からバスで奥の方に行く村である。東京の土産をなににするか、ちょっと悩んだ。祖母は舌も肥えており、土産のことはよく覚えている。同じ物を買っていくわけにはいかない。
今回は巣鴨まで行って地蔵の最中でも買っていこう。親たちには着るものがいい。
醍醐の田舎の家にタクシーで乗りつけると、縁側からばあちゃんがおりてきた。
「やっぱり、白子かい、待っとったで、タクシーなんぞで来るのはお前さんしかいないからにゃ」
ここに来るにはタクシーしかないじゃないか。バスなんか一時間に一本だ。
梅ばあさんは梅干しそっくりの顔をしわくちゃにして、年の割には身をしゃんと起こして、私を見た。
「母ちゃんは」
「買いもん行ってるよ」
「ほい、これ、とげぬき地蔵の最中」
「ありゃ、ありがとよ、あのとげぬき地蔵に行ったんきゃ」
「ああ、ばあちゃんの長生きを願ってきたよ」
そんなことするわけはない、何したって死なないような梅ばあさんだ。
「そりゃありがとよ、だがよ、願ってもらわにゃくても、長生きするんだよ」
自分でもそう言っている。どうして、と聞こうかと思ったが、この状態だと、立ったまま永遠に話さなければならなくなる。
「家に入るよ、ばあちゃん」
梅ばあちゃんは最中の袋を手に持って、よっこらと縁側の方に向かった。私は玄関に回って、勝手知ったる我屋へあがりこんだ。
「父ちゃんは」
「農協行ってるだ、おまえ、父ちゃんや母ちゃんに着いたこと電話してけれ、おらは電話ちょっとだめじゃ」
「うん」
「ここんとこ、冷素麺ばっかだ」
「東京駅でいろんなところの弁当四つ買ってきた」
「そうかあ、でも、母ちゃんに早く知らせてやれや、なんか買っちまうかもしれん」
「うん」
母親に電話を入れた。
「あたし、今家に着いた」
「なに食べたいかい」
「東京駅のお弁当買ってきたよ」
「そりゃあいいねえ、父ちゃんにも連絡しておくよ」
晩ご飯までには間がある。私は梅ばあちゃんの部屋にいった。といっても、真夏のこと、部屋はみんな開け放たれていて、ばあちゃんが巣鴨の地蔵最中を食べながらお茶を飲んでいるのが見える。
いい風が入ってくる。エアコンはあるが使わない。冬の暖房の補助に使っているだけである。
「ばあちゃん、話していい」
ちょっと耳が遠いが、ほとんど問題がない。梅干し顔をこちらに傾けて、嬉しそうに口をもぐもぐさせた。
「これうめえよ」
頭を食いちぎった地蔵さんの最中を私に見せた。
「よかったわ、ばあちゃんが美味しいって言うんなら」
「ええなあ、特に首をがぶっとやるのが快感じゃね」
言っていることは怖い。ばあちゃんはもう五つも食べてしまった。
「おめえも喰え」
「いや、いいわ、それより教えて」
「なんだべ」
「山頂(いただき)茸(きのこ)のことおしえてほしい」
「ありゃあ、なかなか出会わんで、でもあったら、そいつを食えば、そりゃあもう長生きするじゃ」
「いつからそんな言い伝えがあるの」
「いつからじゃろうな、わたしの祖父さんのそのまた祖父さんかもしれんじゃ」
「そんな昔から話があるの」
「そうだよ、言い伝えられてきたんだ、わたしゃ爺様から聞いたんじゃ、爺様はその爺様から聞いたと言っておった」
「どういう言い伝えなの」
「おめえも知ってるべ、おぼたし山」
「うん、そんなに高い山じゃないよね」
「そうじゃな、五百もあっかな」
海抜五〇〇メートルということである、散歩と言うより、ちょっとした山登りをすることになる。しかし、おぼたし山は、あまり木が多くなく、草に覆われていて、散歩気分で登れる山だった。周りに高い山がなかったので、ぽこっと飛び出ている。
「うん、わたしも小学生の時よく登った」
わたしは中学から家族と離れて都内で寮生活をしていたので、こちらにいたのは小学校までである。そのころは全国でも珍しかった都内の中高一貫女子学校に親の考えで入れられたってわけである。なんでも、標準語を身につけさせ、国際感覚を養わせるといった、その当時はやった教育文句に親がのせられたのである。私としてはとてもありがたく、英語を重視した教育のおかげで、それなりの大学にも行き、英語を生かせる外資系の会社にも入ることができた。
「あの山はな、その大昔、旅の高名なお坊様が登って、一本の小さな茸を採って村に戻られたいう話じゃ、そんでな、引きつけを起こしおった村の赤子にすりつぶして、牛の乳と混ぜて飲ましたそうじゃ、そうしたら、その赤子の引きつけは治るわ、百いくつまでも生きるはその効果は大したものだったそうじゃ、赤子にそれを飲ませるとき、その偉い坊様が言ったあそうじゃ、あの山の頂にある茸を食すと、病気をせず百までも生きると」
よくある話である。
「それでな、その山はぼたし山と呼ばれるようになり、それがいつしか丁寧におぼたし山と呼ばれるようになったんじゃ」
納得した。ぼたしというのが茸のことであることは知っていたが、おがついていたので、茸の山であることには気付かなかった。誰も教えてくれなかったのだ。
「おぼたし山の頂上に生える茸じゃなきゃだめなの」
「んだ」
「頂上ってどこ、あそこただ広くなっているだけじゃない」
「あの草原に、せんぶりが生えておってな、せんぶりは知っておるじゃろう、小さな草だが薬になる、苦い胃薬じゃ、かわいい黄色い花が咲きおるよ、ところが、その中にほんの一つか二つ、赤い花が咲くことがあるのじゃよ、その花の根本から、すっと、細い柄の真っ白な茸が生えておることがある。わしらは「いただきぼたし」と呼んでおるがな、そいつじゃなきゃだめじゃ。滅多に生えるものじゃない」
「ばあちゃんは食べたの」
そう聞いたら、おばあちゃんは梅干しのような顔の、あめ玉のような丸い目をわたしに向けて、にーっと笑った。
なんだか気味が悪い。
「食うた」
「だから、長生きするって言ったのね」
「うん」
ばあちゃんはうなずいた。
「じゃが、わからん、もう一つの言い伝えを守ると、確実に生きる」
「それを守ったらいいじゃない」
「うーん、むずかしいのう」
ばあちゃんがわたしをまた見た。目が赤くなっている。
「山頂茸って言うのは、山の頂に生えているという意味もあるがのう、命をいただくという意味もあってな」
「うん、わかる、長生きする茸だものね」
ばあちゃんが、溜息をついた。どうしてだかわからないが、長生きをするのも大変だということなのだろう。
そこにお父ちゃんとお母ちゃんが帰ってきた。
さて、その次の日、母親がなにやら朝から車で買出しに出かけた。わたしに一言声をかけてくれれば一緒に行ったのに。
父親が遅くに起きてきた。といっても父親は、年をとってからは、朝早く起きて、いろいろしてから、もう一度寝る癖があるので、二度目の起床である。
「父ちゃん、母ちゃんはもう買い物に行ったよ」
「ああ、きっと、朝市に行ったんだろう、山菜や、今とれる茸などもあるからな」
わたしは父にお茶を入れた。
「いや、ばあちゃんが、今日友達を呼ぶ言ってな、なんか買いに行ったんだべ」
「へー、友達が来るんだ」
「おまえも知っているかもしれんな、うちのばあちゃん、このあたりでは珍しく、女学校いっとったんだよ」
「うん、知ってる」
「町の方に仲のいい同級生がいてな、時々、みんなで遊びに来るんよ、よその温泉に行くこともある」
「何人来るの」
「四人、昔からの仲良し五人組いって、有名なんじゃ、みんな元気」
「ということは、みんな九十八歳」
「そうだよ、亭主はなみんな死んじまっている、ばあさんばっかり残っているだ、俺もそうなる」
「なに言ってるの、それより準備が大変じゃないの」
「なに、出前をとってある」
ばあちゃんが、部屋から出てきた。
「白子、きょう、友達が来るんじゃ、紹介しような」
「うん、いいよ、女学校の同級生だって」
「ああ、おぼたし山にみんなで登ったんじゃ」
「へー、女学校の時、うちに来たことがあるのね」
「ああ、何日か泊まっていったよ、うちの湯に浸かってな」
この家には掛け流しの温泉がある。十人は入れる大きな風呂場である。個人の家で源泉を持っているのはうちだけである。今ではその源泉から町の山際にあるホテルまでお湯を送る管を引いている。だから何もしなくても両親たちは暮らすことのできる収入がある。祖父の力である。
お昼になると、あれよあれよという間に、いろんな車が、広い庭先に止まった。
同じ背格好のおばあさんたちが降りてきた。だが、好みは随分違うようで、和服姿のおばあさんもいれば、ロングドレスの洋装のおばあさんもいる。すごいのはGパンをはいて、Tシャツのおばあさんがいる。ひゃ、真っ赤なミニスカートのおばあさんがいる。この人たちを見ると、うちのばあちゃんはもんぺ姿で至極まともだ。
止まっている車を見た。和服姿のおばあさんの乗ってきた大きな黒い外車は運転手がエンジンをかけて戻る支度をしていた。きっとあとで迎えにくるのだろう。ワーゲン、ミニクーパ、BMW、みんな外車だ。残った三台には運転手はいない。ということは自分で運転してきたわけだ。九十八歳のばあさんがすごい。目を丸くしていると、梅ばあちゃんが私のそばに来た。
何だこれは、梅ばあちゃんが、おしろい塗って紅付けて、アオザイを着ている。スリットから日に焼けた足がのぞいている。こんな格好始めて見た。
「白子、これからなあ、みんなでお湯はいって食事するが、一緒にどうでぇ」
「うん、いただき茸のこと聞きたいから、お願い」
みなさんがそばに寄って来た。
「梅チャン、お世話になります」
「いらっしゃいな、孫の白子だあな、今日は一緒させてもらうがよろしくなあ」
「あー、嬉しいねえ、若い子と一緒が一番だわ、きれいなお孫さん」
赤いミニスカートをはいたおばあさんが高い声を張り上げた。全く秋田弁がない。
「絹ちゃんだわ」梅ばあさんが紹介してくれた。和服姿のおばあさんを指さして「春ちゃん」、ロングスカートのおばあさんをさして、「よっちゃん」、Gパンのおばあさんは「みっちゃん」と、みなとても九十八には見えない。
「白子です、よろしくお願いします」
わたしがお辞儀をすると、梅ばあちゃんがみんなを家に案内した。
「それじゃ、湯入るべ」
ということで、おばあさんたちは玄関からぞろぞろと上がってくると、大広間に荷物をおいて、湯に入りにいった。
「なにしてる、白子、こんかい」
梅ばあちゃんが呼んだのでいってみると、タオルを二つ持っている。
「湯入るんだよ、一緒に入るって言ったじゃないか」
「え、今もうはいるの」
「そうだえ、儀式だもんな、湯、飯、酒飲んで楽しい話、寝る、フルコースだべ」
そういうことで、おばあさん五人と湯に入ることになった。
脱衣場ではすでにみんな裸になっている。年寄りであるには違いないが、どのおばあさんも、村のおばあさんとはちょっと違う。からだに皺が寄ってはいるが、元気のいい皺なのだ。
わたしが脱いで入っていくと、もう湯の中のおばあさんたちがわたしを見て、「色白いねえ、肌がきれいだ、おっぱい大きいねえ」などと声をあげた。
「まあ、入れよ」梅ばあちゃんに促されて湯に浸かった。おばあさんたちが私の周りを囲んだ。
春ちゃんがわたしの肩に触れた。
「すべすべだね、手入れ大変でしょう」
「いや、化粧はほとんどしません」
産んだ両親に礼を言う必要があるだろう。
「いいねえ若い子は、もてるでしょう」
絹ちゃんにお乳を触られた。
「わたしどうもそういうのだめで」
梅ばあちゃんが補足した。
「白子は小さいときから奥手でな、東京にでてからもそのままじゃ」
なんだかよくわからないことを言った。
みんな頷いた。
程々に暖まると、湯から上がり、なんとおばあさんたちは持ってきたパジャマに着替えた。色とりどりのフリルのついたかわいい奴である。梅ばあちゃんもピンクのパジャマに着替えた。いつもとは全く違う。そういう会なのであろう。
まだお昼を少し回っただけである。パジャマに着替えるとは早すぎるのではないだろうか。しかし、家の中を色とりどりのパジャマを着てうろうろする九十八のおばあさんたちをイメージすると何となく微笑ましい。
広間に行くと、食事を用意している最中だった。長いテーブルが畳の上に置かれて、その上に、なんと、ワインとパンがおいてある。そこに白衣を着たシェフ姿の男性が、スープを持ってきて会釈をした。
「これ何なの」
母親が入ってきたので聞いた。
「最近、近くにできたホテルにケータリングを頼んだんよ」
父親が出前頼んだと言っていたので、てっきり寿司でもとったのかと思っていた。風呂に入っている時に到着したようだ。
「でも、朝早く買い物に行ってたじゃない」
「うん、少しだけ、手作りのものを出すのよ、今日は地元の野菜のサラダ」
「いつもそうなの」
「梅ばあちゃんが好きでね、去年の会では、わざわざ秋田市の大きなホテルから来てもらって、なんとねえ、マグロの解体ショウをやったのよ」
「食べきれないじゃない」
「周りに配ったのよ」
「お金かかるでしょう」
「ばあちゃん金持だからね」
「どうして」
「源泉の権利ちゅうのはすごいのよ、今、三つの宿屋やホテルに配っているんよ、うちの湯はずいぶん熱いからね」
「へー」
「私らもずいぶん助かっているからね」
「母さんたちは一緒に食べないの」
「父ちゃんと向こうでいただくよ、今日のホテルもいいとこだよ」
「贅沢しているんだ」
そこへおばあさんたちがパジャマ姿で現れた。
「今日はフランス料理だあ」
みっちゃんが叫んだ。
みんなが席に座ると梅ばあちゃんの乾杯で食事が始まった。トリュフのスープから、アミガサタケを使った前菜、魚はサーモンのムニエル、柔らかいヒレ肉のステーキ、老人の歯にも食べやすく、東京でもこれほどのものを食べるのはお金がかかって大変だろう、というすばらしいものであった。
「このシェフはフランス帰りなんよ」
梅ばあちゃんが説明した。
「やっぱりねえ、昔パリにいたときに、食べたモリーユを思い出したわよ」
よっちゃんが言うと、絹さんがワインをくっと飲んだ。
「よっちゃんは旦那とずいぶん外国を歩いたから、西洋料理には慣れているわよね、私はなかなか食べる機会がなかったわ」
「なに言ってるの、春ちゃんは名うての謡のお師匠さん、若い頃はいろいろな殿ごに、いいところに連れてってもらってたじゃないの、最後にゃ、あんなに大きな会社の社長さんの奥様、クライスラーで送ってもらっているじゃない」
おや、まあ、みんなすごいこと。
「でも、なんと言っても、一番のお金持ちは、梅ちゃん」
そういったのは絹ちゃんだ。そんなことはないだろうと思っていたら、こんなことを絹ちゃんが言った。
「梅ちゃんの山にまた温泉が湧いたんでしょう、そりゃあ大変なものなんでしょう」
「わたし知らないけど、何なのおばあちゃん」
初耳である。
「そうじゃ、白子は知らなかったな、うちのほら、山奥の土地があるべ、二束三文てやつだがな、ボーリングやってもらったら、百度のお湯が出おった。そしたらな、そこにスキー場作りたいというのが現れてな、それで大金持ちや、ホテルやらなんやらも出来るらしい、ということはこれから金持ちになるんじゃ」
それは知らなかった。
「といってなあ、金が入っても、もう長く生きるわけではねえしなあ」
「あれ、みなさん、おぼたし山で山頂茸をみつけて、食べたんではないのですか」
みっちゃんが説明をしてくれた。
「わたしらねえ、そう十七くらいの時だったね、秋に梅ちゃんの家に集まって、お湯に入ったり、ハイキングしたり、茸狩したり、楽しかったね、そのとき、梅ちゃんのおじいさんがお元気でね」
梅ばあちゃんが口をはさんだ。
「ここの温泉を掘り出した人」
みっちゃんが続けた。
「おじいさんが、そのおじいさんの話といって、おぼたし山の赤花せんぶりにつく茸を食べると、必ず百までは生きるとおっしゃってね、私たち探しに行ったのよ」
春ちゃんが引き継いだ。
「いい天気だったわ、おぼたし山に登ると、周りの山々が紅葉していて、本当にきれいだった。そして茸を探したのよ、せんぶりの花の時期は終わってるのに、おぼたし山の頂上では黄色い花をつけていたわ、でもね、赤い花のせんぶりはなかなかなかったの」
絹さんが受け継いだ。
「そう、でも、あの時、梅ちゃんが、少し丈の高い草むらの中で、赤い花を付けているせんぶりの群をみつけたの、だけど、茸が生えていなければしょうがない、とみんなで探していると、にょきにょきと四本生えていたのよ、でも一本足りないでしょ、周りをずいぶん探したわ」
梅ばあちゃんが続けた。
「それでな、夕方になるし、また来ようと言って、帰ったのよ、四つしかないので、じいちゃんに相談したんじゃ、次の日に採りに行って、みんなで一緒に食べようって思ってたんじゃが、じいちゃんが、採りたてをまず皆で食べて、あと一本探して、また皆で食べれば百歳越えて長生きする言うんだ、それでみんなで、つぶした汁をジュウスに入れて飲んだんだよ、ところがよ、次の日からひどい雨降りになって、おぼたし山に行けなくなっちまった。そいだら、じいさんがよ、一人一つじゃなかったが、それでも百近くまでは生きるじゃろうと言ったんじゃ」
「本当になったのね」
わたしは、五人の九十八歳の顔を見た。みんな元気だ。
「それでよ、じいさんが言うには」
梅ばあちゃんが続けようとしたのを、
「まあ、いいじゃない、それくらいで、食事を楽しむのよ」
よっちゃんが話を遮った。
その話は打ち切りになり、みんなは食事を楽しんだ。そのあとも、五人は湯に再び入り、別の部屋に集まって、お茶を飲んだりしゃべったり、夜遅くまで、楽しんでいたようである。
わたしは食事のあと、自分の部屋に戻り、テレビを見て布団に入った。
その、夜中のことである。何時だかわからないが、おそらく真夜中のことだと思う。寝ているわたしの顔に何かが押し付けられた。掛け布団がはがされ手足が押さえられ、左手のパジャマの袖が捲り上げられた。
なにがなんだかわからずに、私は大暴れした。
すると、私は自由になり、梅ばあちゃんの声がした。
「白子、悪いことをしたね」
それで電気が点けられた。
周りには五人のお婆ちゃんたちが正座していた。
梅ばあちゃんが私を見た。
「白子よ、ごめんよ、お願いがあるんよ」
わたしも気を取り直して、返事をした。
「ばあちゃん、これなんなのよ」
「実は、わしらは百過ぎまでは、生きられんのよ、でもな、私のじいちゃんが言ったのよ、山頂茸の量が少ない時にはよ、大人の処女の血を飲めば、百どころか、百二十まで生きるってなあ、それで、さっき、みんなで相談したよ、私らどうしようかってな、長生きせんでもいい、と言う者もおれば、百一つでも超してみたいと思うと言う人もおってな、賛成多数で決めたんよ、そしたら、一つぐらい百を越したい、いや、百になるだけで良いってみんな思ってたんだな、だからな、白子、おめえの血をわけてくれよ」
わたしは本当にびっくりした。山頂茸は吸血鬼をつくる茸なんだ。
「でも、どうやって」
「ちょっとでいいんだ、よっちゃんは看護婦さん、旦那はお医者さんだっただよ、ほら検査の時に採るくらいだから、血を採らしてくれよ、頼むよ、新しい温泉の権利は白子にやるで」
ちょっと躊躇したが私は頷いた。
おばあさんたちの顔がぱっと明るくなった。
すると、よっちゃんが鞄を持ってきて、中から注射器を取り出した。私のそばに寄ってくると、パジャマの袖を上げ、わたしの腕を手に取って、手慣れた手つきで、静脈の位置をさすり、アルコール綿で拭いた。
「ちょっと、ちくっとしますからね」
もう看護婦さんになっている。
チクリともせず針は静脈に入り、赤黒い血が注射筒に満たされていく。
「はい終わりました」
よっちゃんは、針を抜くと、そのあとに、ガーゼの小さいものを当てて「しばらく押さえていてください」
そう言うと、みんな顔を輝かせてぞろぞろと、「ありがとう」と私の部屋から出ていった。痛くはなかったが、私はガーゼのついた腕を見て眠れなくなった。一応布団に入っていると、離れた部屋から声が聞こえてきた。
梅ばあちゃんの、「焼酎に混ぜて飲もうよ」という声がする。
夢なのじゃないだろうか。いや、腕には血を採られた跡がある。
なんだかわからないが、私は乱れた布団を直して中に入った。
次の朝、自分の腕をみると、ガーゼがはがれ、注射針のあとが小さな黒い点として残っていた。やっぱり夢ではなさそうである。本当に私の血を飲んだのだろうか。吸血鬼ばあさんたちはまだ起きてこない。
私は母親が買い物に出るということだったので一緒に付き合い町に出た。
いろいろ買い込んで、家に戻ると、ばあさんたちがパジャマから、来た時の姿に戻っている。
「白子、ありがとよ、おかげでぐっすり眠れたよ、約束の権利書は書き換えておくからよ」
「ほんとに飲んだの」
「もちろんよ、わたしたちは百歳より先まで生きることができるのです。みんな白子さんのおかげ」
みっちゃんが微笑んだ。
「さあ、朝ご飯は納豆に、たくわん、味噌汁」
こうして、私の血を飲んだおばあさんたちは帰って行った。
そんなことがあって、次の年を迎えた。
夏にまた実家に帰った。
梅ばあちゃんは至極元気だった。
「白子、ほれ、これが温泉の権利書じゃよ」
梅ばあちゃんは、手文庫の中から、役所の書類を取り出して見せてくれた。手渡そうとするので断った。
「ばあちゃん持っててよ、私が持っててもどうしたらいいか分からないから」
「それじゃ、父ちゃんと母ちゃんに預けておくからな」
「ありがとう」
「あそこに、温泉ホテルが建てば、おまえは働かなくてもよくなるよ」
「ええ、そうなの」
「そうさあ」
という会話をした。
ところが、大変なことが起きたのである。九月に入り、梅ばあちゃんが誕生日を迎えて九十九歳になった次の日に、突然ぽっくりと死んでしまった。
葬式の日、父親が私に言った。
「なぜか、あんなに、百過ぎまで必ず生きるんだと信じていたが、だめだったな」
「でも、ぽっくり逝ってしまって、本人はとても幸せでしたよ」
母親が答えた。
「そうね、でも、私に責任がありそう」
私は後ろめたい気持ちでいた。父と母は梅ばあちゃんが私の血を飲んだのは知らないようである。
葬式は無事済み、私は東京に戻った。
その後、やはり連絡があった。十月になってからである。母親からだった。
「白子、あのな、ばあちゃんの友達な、みんな誕生日の次の日にぽっくり亡くなってたのよ、梅ばあちゃんには知らせなかったのよ、友達の家族とも相談して、亡くなったことは黙っていようということになっていたの。幸い今年はクリスマスに集まることになっていたから、ばあちゃんはそれまで知ることはないと思ってたの、耳が悪くなってたから電話を使わないしね。ついこの間、十月一日に誕生日のよっちゃんが次の日になくなったわ」
私はその週末に実家に帰った。母親に教えてもらって、まず梅ばあちゃんの、そのあと、春さん、絹さん、よっちゃん、みっちゃんのお墓に行くことにした。
五つの花束を抱えてタクシーを呼んだ。
うちの墓は山の中腹にある。
タクシーを待たして、新しく建てられた梅ばあちゃんの墓の前に立った。
花束を置いて、線香に火を着けた。
「梅ばあちゃん、ごめんなさい、私もう二十五よ、うちの会社には金髪の恰好いい外人さんがうようよしているの、私もてるのよ、処女の血じゃなきゃだめだったのでしょう、効かないことはわかってたのに、言わなくてごめんなさい。でも言えなかったのわかってくれるでしょ、お母ちゃんだって私のことそんなふうに思ってないもの」
私は手を合わせた。
あと五人のおばあさんの墓の前でも同じことを言ってあやまった。
実家に戻ると、父親が「白子、温泉の権利書、おまえのだけど、持っていくかい」書類を持ってきた。
「私、持っててもわからないからお父さん何かあったら代わりにやってくれる」
「いいよ、その時は連絡するから」
そして、二年が過ぎた。山奥に超豪華なホテルとスキー場、ホテルのように立派な養老施設ができることになった。土地はお父ちゃんの名義になっており、ホテルに貸すことにしている。全く生活に困らないどころではないお金が入り、老人ホームの一番いい部屋に両親が入ることにもなった。なにせその山奥まで道もできることになってしまったのだ。ということは、その施設だけではなく、ほかの会社も何かを作るかもしれない。
温泉の権利というのも大変なものである。私は何もしなくてよい身分になったので、会社を辞め大学院にいき直した。
修士論文のテーマはポーランドのドラキュラ伯爵のことをテーマにした。もしかすると、ポーランドにも「山頂」茸が生えているのかもしれない。今のボーイフレンドはポーランド人の生物学者だ。
山頂茸(いただききのこ)
私家版第三茸小説集「海茸薬、2017、244p、一粒書房」所収
茸写真:著者 山梨県小淵沢 2013-9-16


