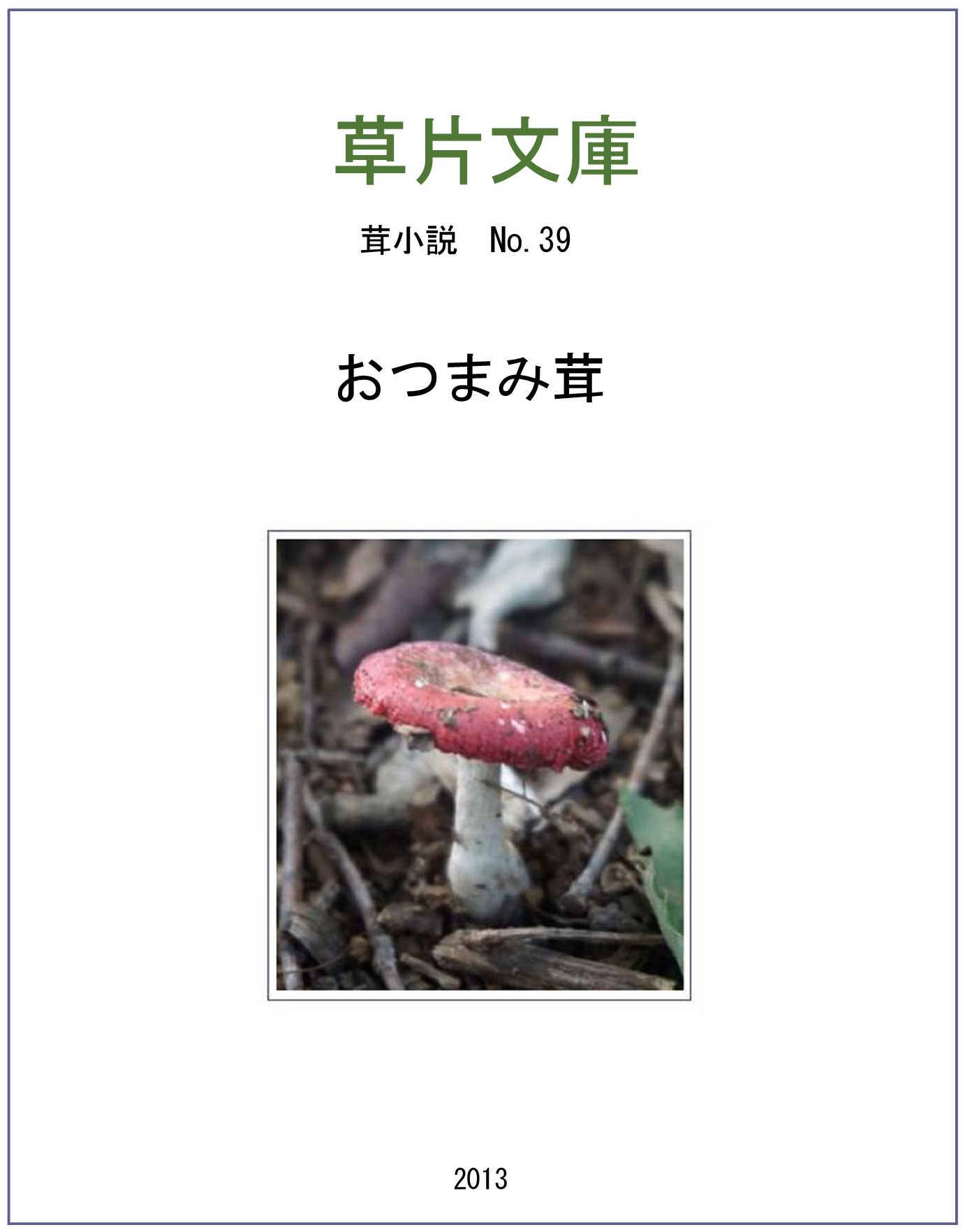
おつまみ茸
秋田の山奥に湯治に行ったときのことである。
三日ほど逗留して、帰る日の朝早く、宿の下駄を履いて散歩にでた。
宿からちょっと歩いた道沿いにビニールシートが敷かれ、いろいろな野菜が売られている。この時期のものであろう、特にいろいろな茸が並んでいる。天然ものの舞茸が新聞紙にくるまれて無造作に置かれている。東京にいったらさぞ高いことであろう。天然の滑子(なめこ)と思われるが、ストアーに並んでいるものからは想像できない大きな傘が茶色に輝いている。山伏茸や香茸、占地(しめじ)、みんな自然のまま転がっている。高級料理の原点ここにありというところだ。
道の一角でお年寄りが何人か集まっている。野菜や茸を持ってきた人たちである。つかの間、私が茸をのぞいているのを見ていたが、買いそうもないと思ったのであろう、また楽しそうに話を始めた。
のぞきながら歩いていくと、橋があり、下に小さな流れがあった。川底の石がきらきらと輝いている。
薄が穂を垂れて道の脇に並んでいる。
しばらく歩くと、道は山の林の間に入って行った。ちょっとした散歩にしては遠くに来てしまった。きりがないのでそろそろと思い、戻ろうとすると、藪の中からがさがさと、道に出てきた人がいた。籠を背負っている。山に茸採りに行ってきたのであろう。
見ると女の子だ。ほおっかむりをしていたので大人か子供かわからなかったが、こちらの方を向いた顔は少女である。小学校五、六年生ぐらいか。
私が立ち止まっていると、女の子が声をかけてきた。
「おじさん、茸いらない」
「美味しい茸があるのかい」
「そりゃ、あたいが見つけた茸はみんな美味しいよ」
「欲しいけど、お金を持ってこなかった」
「どこに泊っているの」
「語呂平旅館」
「語呂平さんならよく知っているよ、後で持って行くから見てよ」
「いいよ、でも今日帰るんだけど」
「すぐ行くから、それじゃあとでね」
そう言って、少女は道を上がっていった。
私は旅館に戻り、部屋に支度ができていた朝食をとった。食べ終えた頃に、女中さんが声をかけてきた。
「お客さん、茸買うって言ったかね、文ちゃんがそう言ってきたんだけどね」
「ああ、通していいですよ、文ちゃんていうんだねあの女の子は」
「山の上の家に住んでいるんですよ、いい子でね、小学校で一番できるんですよ、母親がいなくなってしまって、父親はからだを悪くしていて、家のことをみんなしているのですよ。それだけじゃないのですよ、あの子は大人顔負けの茸採り名人だで、あたしもあの子から買っているんですよ、道に出ている連中のものよりいいし安いし、お土産にはいいですよ」
女中さんがそんな話しをしているところに文ちゃんが上がってきた。
「今、文ちゃんのこと話していただよ」
「あ、綾おばさん、ありがとう」
文ちゃんは今時珍しいもんぺ姿で、編んだ手さげの籠に茸を入れて持ってきた。
「こんにちは」
「あ、こんにちは」
さっき会ったときには顔がよく見えなかったが、こんなに色が白く、垢抜けた顔をしているとは思っていなかった。綾さんと呼ばれた女中さんがごついからだつきをして、日に焼けたお百姓さん顔をしているせいもあって、この子はこのあたりの人のイメージとずいぶん違う感じを受けた。目鼻は小づくりだがどこかでみた子役さんのような顔である。
文ちゃんは畳の上に新聞紙を敷いて茸を並べた。ほとんどが道端で売っていたものと同じだが、いくつか見たこともないものもある。
「きれいな茸ばかりだね」
「うん、この舞茸は小ちゃいけど美味しい、天然占地も今日採れたの」
「その端にある大きな茸はなに」
拳の大きさほどの傘を持ったずんぐりした茶色の茸がある。
「これ、あたしが見つけたのは二度目、生で食べても美味しいの、皮をむいて食べるの、皮も食べられる」
「何という茸なの」
「名前は知らない」
これはみないいお土産になる。
「全部でいくら」
「千円」
「そりゃ安いよ、それじゃこれで」
私は財布から調度あった二千円を渡した。
「え、ありがとう」
文ちゃんはお金をポケットに入れると、茸を一つ一つ丁寧に新聞紙に包んで、持ってきた紙袋に入れてくれた。
「おじさん、ありがとう」
文ちゃんはもう一度礼を言うと、下に降りて行った。
舞茸だけでもとても二千円では買えない。帰ったら周りの家に配ろう。
女中さんが朝食を片づけに上がってくると、「お客さん、文ちゃんとても嬉しそうに、帰って行きましたよ」と言った。
「それはよかった、これで、千円ていうから、二千円あげたのですよ」
「おや、ずいぶんあげたんですね、それで喜んだんだわ」
「こちらじゃそんなに安いんですか」
「そうね、ここで買ったら三千円くらいね」
「それじゃ安かったんだ、道ばたで売っているの高いんだ」
「そうだねえ、そりゃしょうがないね、まあ、文ちゃんはまだ小学生だからね」
「東京に持っていったら高いよ」
「そうなんですよ、このあたりには取りまとめるような人間がおらんで、出荷ができりゃもっといいんですがね」
「これだけの茸だと五千円近いのじゃないかな」
「文ちゃんも、お客さんも幸せで、よかったです」
女中さんは笑顔で膳を持って下に降りていった。
まだ七時である。帰りのバスは十時と時間がある。もう一度風呂に入るか、何をしようか考えていると、ふと文ちゃんが採ってきた珍しい茸を思い出した。生で食べても美味しいと言っていた。あの不思議な茸を新鮮なうちに食べてみようか。
新聞紙にくるまれて一番上に乗っていたその茸を取り出した。手にずっしりと重い。茶色の表面はビロードのような感触で、あまり茸らしくない。
皮を剥くと言っていたが、このビロードの部分を剥がすことであろう。
茸の傘のてっぺんに爪を立てて、皮を捲り上げると摘んで下に引っ張った。ビロードのような皮がするリと剥けて、柄のところまできれいに剥がれた。襞のところはどうなっているのかと見ると、襞がなく、つるんとしているのできれいに剥けている。胞子はどこで作るのだろう。
剥いた痕はベージュ色になっている。このビロードのような皮は食べられるのだろうか。ちょっとかじってみた。じゅっと汁がでて、口の中に甘酸っぱい香りがただよった。かみきることはできないほど堅いので、くちゃくちゃとかんだ。ちょっとガムのようだ。薄荷(はっか)のガムをかんだように口がすーっと涼しくなりさっぱりした。
皮を全部剥いた。皮は後で食べよう。
ベージュ色になった茸は皮を剥がれて赤裸になった動物のようだ。
裸になった茸の頭に爪を立てつまんで下に引いた。すると、ラッキョウのように、綺麗に一枚の身が剥けた。食べてみると、アワビを醤油に漬けて作った煮貝のような味がする。旨い。ビールに合う。なんだかどうしても飲みたくなった。
階下に声をかけた。
「ビールを一本ください」
「はーい」
綾さんがビールを運んできた。
「朝からいいですね、何かつまみでも持ってきましょうか」
「いえいえいいんですよ、この茸が美味しくて、ビールが飲みたくなったんですよ」
「あれ、見たこともない茸だな」
「文ちゃんが、めったに採れないと言っていました」
「あたしも初めて見たですよ」
綾さんはビールをつぐと、「ごゆっくり」と下に降りていった。
ベージュ色の皮を剥いて食べてしまうと、まっ白な茸になった。
白い茸を剥がして口に入れると、舌の上でとろけ、白カビのチーズの香が口の中に充満した。たいした茸である。
ビールがまたこれ美味しく感じる。
チーズ茸をつまんでいると、ビールがなくなった。
「ビールもう一本お願いします」
綾さんが上がってきた。
「お客さんお強いですね」
「いや、珍しい茸で、つい飲んでしまいます」
「あれ、真っ白になっている」
「そう、茶色のビロードのような皮を剥くと、ベージュになり、白になったのですよ、それに、味も変わる」
「へー、珍しい茸ですね、今度文ちゃんに採ってきてもらおう」
「これは珍品茸ですよ」
白い皮を食べ終わると大きなエリンギほどの大きさになった。白の下からでてきたのは黄色であった。
そこを剥がして口に入れた。黄身の味そのものである。半熟の黄身に少しばかり塩味がついているような、これもいい味である。
黄色い皮を剥ぐと、真っ赤な小さな茸になった。
赤くなった茸に爪を立てて皮を剥こうとしたが、剥がすことができない。もうこれ以上剥くことはできないようである。
親指ほどになった真っ赤な茸を齧ってみた。赤い汁がでてきて、表現のできない、しかし、いい味が歯茎の間まで染透った。丸のまま口に入れて噛むと、ますます、美味しさが口いっぱいに広がった。
最後のビールを飲み干すと、今までに感じたことのない満足感が全身に広がった。
そのとたん、頭の中に冷たい空気が入ってきて、くっきりと気分がよくなり、からだが宙に浮いたような感じになった。
最後に表面のビロードのような茶色の皮を口にいれかんだ。口の中がすーっとする。
さて帰らなくては、私は着替えをして荷物をまとめると、帳場に行った。
帳場にいた女将さんが私を見た。
「お帰りですか、ありがとうございました」
請求書を部屋のキーボックスから取り出して私に渡した。
「茸でビールを二本も飲まれたそうで、お強いですね」
「いや、美味しい、不思議な茸でした」
「文ちゃんは面白い茸を採ってくる子ですよ」
宿賃を払い、玄関に向かおうとすると女将が言った。
「バスにはまだ時間がありますが、大丈夫ですか」
「ちょっと、そこいらを歩きたいので」
「じゃあ、お荷物をお預かりしましょう」
「いえ、たいしてないから」
「ありがとうございました、またいらしてください」
「はい、また来ます、湯もとても良かったですよ」
「お気をつけて」と言う女将の声を背中に聞いて、私は旅館の玄関を出た。
からだは、ふわりふわりと、浮いたように動き、頭の中はますます気持ちがよくなってきた。
いい匂いが漂ってきた。足が勝手に匂いの方向に動く、バス停とは反対の方向に足が向いた。小さな川の橋を渡り山道に入った。朝早く歩いたところである。
おそらく他人が見たら私の足取りはしっかりしたものに見えただろう。しかし、私はふわふわと宙に浮いた感覚で、道からそれると林の中に入っていったのである。
下草を掻き分けて進んでいくと、斜面のところに女の子がいた。
文ちゃんだ。石の上に立って私を見下ろしている。
「おじさん来たのね」
私は文ちゃんの前に立った。
「口を開いてこれ食べて」
文ちゃんの言うとおり、鳥の子どものように私は口をアーンと開けた。
文ちゃんが茶色の固まりを口の中に落とした。
私はそれをくちゃくちゃと噛んだ。甘い味の汁が喉を通って食道に降りていく。
「おじさん、この穴に入って」
文ちゃんが、大きな木の脇の穴を指差した。
私の体が勝手に動き、穴の中に飛び込んだ。
「それじゃ、土をいれるから、下を向いていてね」
文ちゃんはスコップで土をいれ始めた。かがんだ私の背中に土がぼろぼろと降りかかる。かなりの時間をかけて文ちゃんは土を投げ入れ、私の頭の上まで土が被さった。
「二千円もくれてありがとう、いいおじさんね」
私はからだが二つに折れていくように感じた。ぼきっと折れたとたんとても気持ちがよかった。また折れた、四つに折りたたまれた。
「秋になると茸になるから我慢していてね、おじさんは、あの茸の真っ赤な芯になるのよ」
また私は折れた。八つ折りになった私の体の周りに土がへばりついてきた。
文ちゃんはこの茸を栽培しているようだ。どうやって知ったのだろうか。だが、文ちゃんと話ができない。文ちゃんが私の上に載って言っている。
「この木の下に私の赤ちゃんを埋めたのよ、石を載せといたの、それでね、周りにお花を植えたの、たまにお参りをして、お花に肥料をやっていたら、石を持ち上げてこの茸がでてきたの、お腹空いていたし、美味しそうだったけど、おかあちゃんが熱出して寝ていたから、持っていってあげたの、お母ちゃんはそのまま剥いて食べたの、そうしたら、熱は下がって、元気になったのだけど、急に家を出ると、私の赤ちゃんを埋めたところにきて、木の枝で穴を掘って自分で入ってしまったわ、そうしたらね、次の年にそこにその茸が生えたの」
私は土の中で答えるすべもなく聞いていた。
「それで、人間がその茸に変わることがわかったのよ、しかも、この茸を食べた人は自分が茸になるためにここに来るの、この木は楠、そのせいじゃないかしら、アオスジアゲハは楠にひかれてくるのよ、きっと匂うの」
私はこれから夢を見ながら、真っ赤な茸になるようである。それに、いろいろな味が私の周りにへばりついて剥いて食べる茸になるのである。おつまみにした茸である。
「来年、私は中学生、もっと高く売れるわね、おやすみなさい」
文ちゃんの足音が遠ざかって行った。
おつまみ茸
私家版第三茸小説集「海茸薬、2017、244p、一粒書房」所収
茸写真:著者 日野市南平15-7-12


