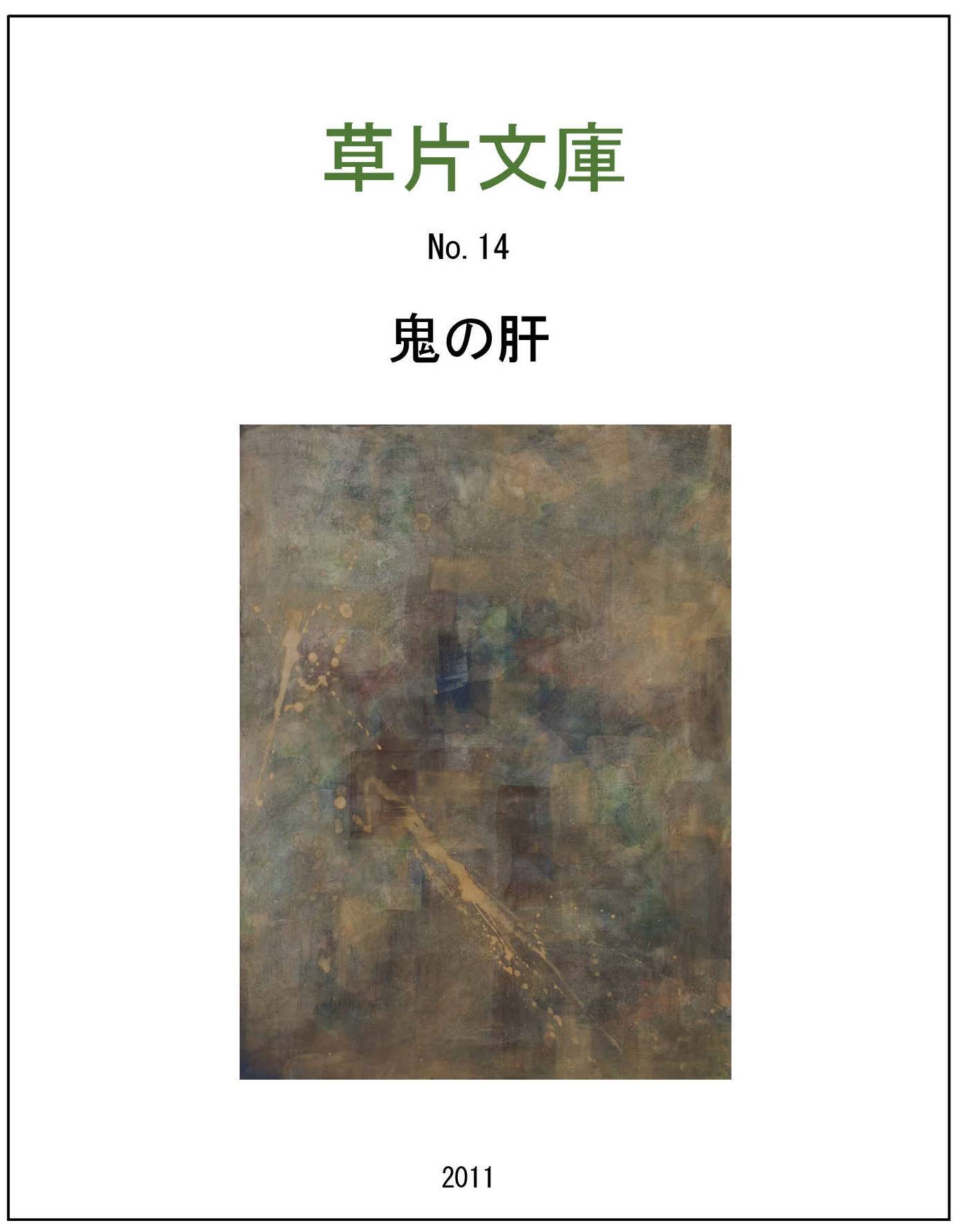
鬼の肝
昔々、北の国の小さな村での話である。
山のふもとに若い猟師がいた。
名前を藤(とう)助(すけ)という。
この村は稲の栽培には向かず、野菜などの作物も育ちが悪い土地柄であった。にもかかわらず、収めなければならない年貢のとりたては他の村と変わりなく、代官は容赦ない要求をしてきた。
村人たちは農業を営む傍ら猟に精を出していた。雪深い山ではあるが、動物は豊富で、春になるとだれしもが猟に出た。
藤助が十三歳になったばかり、父親から鉄砲の扱い方、猟の仕方を教わっているところであった。
藤助の家は代々の猟師で、父親の勘兵(かんべい)は村で一番といわれる腕をもっていた。当然のことに、藤助も猟師になるものと、勘兵の言うことをよくきいた。藤助は勘兵と一緒に猟に出て、勘兵にいわれるまま、勘兵の銃をつかってウサギやキツネをしとめた事がある。しかし、自ら鉄砲を持って猟に行き、獲物をしとめたこともなく、大きな獣、熊はもちろんのこと、鹿など撃ち倒すような経験はない。
ところが、これから大きな獣を射止めるこつを教わろうという矢先、勘兵が急に病に倒れて死んでしまったのである。
藤助は四人兄弟の一番上。下に二人の妹と、一番下のまだ五歳になったばかりの弟がいる。母親のマツは近くの名主の畑の手伝いをしているが、藤助の肩にも生活が重くのしかかってきた。
「父ちゃんのように立派な猟師にはようなってくれやな」
マツにいつもいわれていた。
藤助は母親とともに名主の手伝いに雇われたが、それでも父親が逝って半年もすると鉄砲を担いで山に入った。はじめは擦り傷をつくりながらも、ウサギや山鳩を獲らえ、それなりの糧を得ることができるようになった。
村医者の草庵は藤助の父親の勘兵に熊の胆をとってくるよういつも頼んでいた。
熊の胆は胆嚢を干したもので、胃の差込や、高熱、悪質な痛み、それに目の痛みなど多くの症状に効力があった。そういった万能な薬は高価なものである。
勘兵は熊をしとめると、熊の毛皮はもちろん、食えるところはすべて持って帰ってきた。そのような時は上機嫌で、熊の胆を必ず草庵のところへもっていった。
草庵は熊の胆ならいつでも高く買ってくれる。
どの猟師も熊を狙っている。何人か集まって、春の早い時期に熊の穴を見つけ、冬眠中の熊を追い出して、場合によれば子熊も一緒にしとめるという猟をおこなっていたが、勘兵は穴猟とも呼ばれるその方法を嫌っていた。勘兵は子どもをもった動物には鉄砲を向けることをせずに逃がした。勘兵の猟は何時も一人で、堂々と向かってくる大きな雄熊を射止めることを誇りとしていた。藤助もそれを目にしてきたのである。
藤助が十六になった一月の終わりごろ、草庵が藤助のところにやってきた。
「藤助、まだ熊はいないじゃろな」
「へえ、まだ、でてはいないです」
「そうじゃろうな」
「草庵様、なにか」
「熊の胆がのうなってしまった。たくさんあったが、町の医者に譲ってしまったのだ。町の代官の娘が癪もちで、今年はひどくての、知り合いの医者はもっている熊の胆をすべて代官に差し出したのだそうだ。それで町人に分ける分がのうなってな、わしのところに来て、どうしても少し分けてほしいというので、分けてやったのじゃ。そうしたら、この村でも今年は患うのが多なって、手持ちがほとんどなくなってしまったのじゃ」
冬眠中の熊をねらってくれはいまいかと、藤助に熊の胆をとってくるよう頼んできたのだ。若い藤助には難しいかもしれないが、高い値段で買うから、がんばってほしいと言う。いつもそのようなことを言ってくる医者ではない。父親を亡くした藤助の気持ちを奮い立たせようということでもあったのであろう。これは父親のきらいな穴猟である。迷った藤助であるが、子どものいない熊だけを狙うということで引き受けることにした。
藤助はまだ自信がない。
母親のマツは何も言わなかった。藤助の身を案じている、しかし期待もしている。藤助は母親の気持ちが手に取るようにわかった。
藤助が出かける朝、マツは握り飯を作り、米やたくあんなどを袋に入れて橇に結わえ付けた。熊は獲れないだろう、ウサギぐらいなら、そう思って藤助は橇を引いた。
雪の深い尾根を歩き、湖の脇にでた。小さな湖は凍りついており、その上に雪が積もっていた。林の中も雪で覆われている。熊が起きてくるにはまだまだ早い。穴の中で夢でも見ていることだろう。
藤助が歩いていくと、ウサギが前を横切って、雪の原のほうに走っていった。銃の用意をしてウサギの後を追った。今日はじめての獲物である。銃を構えた。しかしウサギが走っていった先には子ウサギがいた。母親であろうそのウサギは途中で止まり、振り返って藤助を見た。
藤助は銃をおろした。子どもをつれた動物は撃たない。勘兵の教えを守った。
顔を上げると、親子のウサギはすでに姿が見えなくなっていた。
それから獲物にはであわなかった。途中で橇に腰かけ、マツの結びを食った。
まずは猟師小屋にはいり、明日からの本格的な猟に備えなければならない。藤助は橇を引きながら、雪の山道を歩いていく。
黒い雲がでてきている。雪が降り出すのではないだろうか。案の定、冷えてきて雪がちらつき始めた。猟師小屋にいそいだ。たどり着いたときにはかなりの雪がふっていた。
雪を払い、橇も小屋に引き入れた。囲炉裏に火をおこし、鍋をかけると、水の中にもってきた米に野菜、それに味噌を少々いれた。
風のうなりが小屋の中まで聞こえてくる。入り口の戸がぎしぎしと音を立てるほど激しくなってきた。
食事を終えたころ、外の音がしなくなっていた。風が止んだのだろう。
藤助は戸を少し開けて外を見た。雪はしんしんと降っている。明日はかなり積もっているに違いない。明日は雪の積もった中、熊の穴を探さなければならない、穴猟をしたことのない藤助には大変な作業になるだろう。
火の種を絶やさないように気配りをして、筵の間に入って横になった。
あくる朝、案じていた雪は止み晴天であった。米をたき、朝飯を食い、握り飯を作って腰につるした。
熊の住処になりそうな穴を探すのは大変だ。銃を担いで、まず一回りのつもりででかけた。
林の入り口で白い動物が走った。またウサギだ。止まってこちらを向いている。子どもだ。藤助を見ると急いで逃げていった。
藤助は林の中にはいった。穴らしきものもいくつかあったが、熊のはいれるような大きさのものはなかった。歩き回ったが、とうとそれらしき穴をみつけることはできなかった。
日がおち始める前に、山小屋にもどると、板の間に蕗の薹と菜が置いてあった。
藤助は荷物を床に下ろすと、蕗の薹をつまみあげた。春の香りがぷーんとする。誰が持ってきたのだろう。雪の上には藤助の足跡しかなかった。不思議なことがあるものである。藤助は人並みの信心を持ってはいたが、神がこの様な具体的なことをするとは思っていない。しかし現実に蕗の薹が目の前にある。
楽天的なところがあるのだろう、藤助はいつかこの不思議も解決できることと、ありがたくいただくことにした。
藤助は炭に火をつけ、囲炉裏に鍋をかけて湯を沸かした。蕗の薹を湯の中に入れ、軽く湯がくと、味噌をつけて食べた。小さな頃は苦くて見向きもしなかったが、今は好んで食べる。父親が死んでから口も大人になった。というより、食べられるものは何でも食べないと腹が減ってたまらないのであった。
蕗の薹を食べ終わった後はその湯に菜と米を少々入れて塩を足して煮た。春の香がして昨日より食事が豪華に感じられた。
その夜も雪がまた降り始めた。風は無く静かである。蝋燭の火を消した。
むしろをかぶって、目をつぶると、初めて熊にあったときのことを思い出した。それは父親の勘兵に連れられて、紅葉し始めた山の中を歩いているときであった。その時は猟をすることが目的ではなく、茸を採りに行く途中であった。舞茸が必ず生える場所があると、勘兵が藤助を連れてきたのである。
山深い路を歩いていくと大きな木があった。木の根もとを勘兵が指差した。そこには大きく手を広げたような形で、茶色の舞茸が薄く差し込む日の光りに浮き出ていた。
「この木はな、ミズナラの木だ、ここには毎年舞茸が生えとる、俺はこういう場所を数え切れないほど知っておるんだ」
勘兵は藤助にそういって、両手を添えて舞茸を持ち上げた。そのまま静かに、籐籠にいれた。
その時だった、がさっと言う音とともに、ちょっと離れた木立の後ろで黒いものが動いた。
勘兵は、後ろに下がり、逃げる用意をしておけと茸の入った籠を藤助の背にしょわせた。
勘兵は肩にかけていた銃を構えると、黒いものが動いた木立に向けた。
勘兵がそうっと近づくと、巨大な熊が木立から現れた。
熊が勘兵に気付いた。
熊はグワーッと大きな声を上げ向かってきた。
勘兵はここぞとばかり、一発玉を放った。どーっという音がした。
藤助が見ると熊が前のめりに倒れていくところだった。
たった一発で熊は転倒し、そのまま息絶えたのである。
勘兵の撃った弾は熊の眉間にしっかりとめり込み、大きな穴を開けていた。
猟師になろうと思ったのはこのときだった。その迫力は藤助にとって余りにも大きかった。
熊のいた場所にミズナラの木があった。食い散らかされた舞茸が残っていた。その木も勘兵の頭の中にあった舞茸の木であった。先にそちらを見に行っていたら大変なことになっていただろう。
勘兵は早速、山刀で熊の腹を割き、熊の胆をとると、持っていた皮袋に入れた。その後、手早く皮をはぎ、丸めると自分が背負った。肉も少しばかり切り取ると、羊歯の葉にくるみ、舞茸を入れた籠の底にいれた。藤助の背中に血生臭い匂いが漂った。
「思わぬ収穫だ、これ以上はもってけえれねえ」
勘兵は藤助に帰るように促した。
「残りは明日取りに来てもいいが、きっとキツネたちの餌になってるべ」
クマの毛皮を背負った勘兵と肉の入った籠をしょった藤助は家にもどったのである。藤助がまだ八歳の頃だった。
藤助はそのようなことを思い出しながら眠りについた。
その夜中だった。周りの空気がやけに冷たくなってきたことで目が覚めた。
火が落ちてしまったのだろうかと思い、筵から這い出すと囲炉裏を覗いた。炭は灰をかぶっているが、ボーっと赤く光っている。
この寒さはなんだろうと、小屋の入口を見ると土間の上に白い霧がぼんやりと現れた。それは見る間に白い着物をまとった女になった。
空気がますます冷たくなる。
透き通るほど白い、うりざね顔をした女は赤い目を藤助に向けた。
雪女だ。
藤助は勘兵から雪女のことは聞いていた。村の年寄りからも話を聞いたことがある。
口をきいたらいかん、口をきくと連れて行かれ、冷たい雪の中に埋められる、みながそう言っていた。
藤助はおしだまって雪女をみつめていた。
雪女が口を開いた。
「藤助さん、お礼申します。二度も子どもを助けてくださいました。あれは、ウサギの子どもではなく、私どもの子ども、雪女の子どもです。ウサギに形を変えて遊ばせておりました。あなたの慈悲は忘れることはありません」
とても優しい声だった。雪女なのに暖かい春の風のような声だった。
「わたしは笹雪と申します。もし、お困りになるようなことがあったときには、私をお呼びください。笹雪、笹雪、笹雪と三度お呼びになったときには、藤助さんの前に現れます」
雪女は藤助を見た。その目は優しかった。
「蕗の薹と菜はほんのお礼、南のほうに生えていたものをもって参りました」
言い終わると雪女は赤い目を閉じ、音も無く入口の戸を開けてすーっと外に出て行った。
入口の戸が静に閉まると同時に、藤助の意識は薄れていき、ふたたび眠りに落ちた。
あくる朝、小屋の隙間から朝日が差し込むと、藤助は気持ちよく目覚めた。いつの間にか筵に入って寝ていた。昨日のできごとは夢だったのだろうか。だが確かに蕗の薹は食べた。それはいい香だった。
朝食をすますと、昨日とは違う方角に出かけた。今日もいい天気になった。
期待とは裏腹に、その朝も熊のいそうな穴を見つけることができなかった。
昼になり、切り株の上の雪を払い腰掛けると、朝作った結びを食った。
全くあてが無い猟であった。たとえ熊がいても勘兵のように一発で眉間に玉を撃ち込める自信は全くといって無かった。
結びを食いながら、目の前の雪の斜面を見ていると、少し下ったところに、雪が盛り上がっているところがあった。倒れた木に雪が積もったにしては丸みがあり、なにやら不自然である。
結びを食ってしまうと、雪を踏みしめてその膨らみに近づいた。意外に大きなものである。
藤助は雪をかいてみた。雪がぱらぱらと落ち、黒いものが現れた。すこしの雪しか覆っていない。明け方の雪が積もっただけのようだ。藤助が雪を払っていくと、そこに出てきたのは熊の毛であった。
藤助は驚いて、あわてて雪を落とした。現れたのは大きな年老いた熊であった。まだ冷え切っていない。
寿命が尽きて死んだ大きな雄熊の遺骸である。冬眠の途中、何らかの原因で穴から走り出てそのまま息が絶えたのだろう。年老いて心の臓でも痛くなり走り出た挙句の死かもかもしれない。
こんなことがあるのだろうか。昨日から不思議なことばかりでおこる。
熊の胆をもらおう。藤助は山刀を抜くと、勘兵がやっていたのを思い出しながら腹を割いた。
寒いどころではなく、額に汗して熊の腑分けを行った。やっとのことで胆嚢をみつけだすと、切り出し皮の袋に納めた。食べることのできる部分はできるだけ切り取り、はいだ皮にくるむと橇につけた。
銃を撃つことなく熊を獲ることができたのである。これも天が授けてくださったことなのだろう。藤助は何に感謝をしてよいのか判らなかったが、この運の良さを導いたすべてのものに深く感謝した。
小屋にもどり、帰り支度をして、ふと食べ残した蕗の薹が一つあるのを床の上に見つけた。手を伸ばして拾うと母親への土産にと懐に入れた。
無事に、しかも、予定していたより二日も早く藤助がもどってきたことに母親のマツは狂喜した。しかも熊を獲ってきたのである。
藤助がいくら説明しても、マツは藤助が熊を仕留めたと言った。
マツは近所に熊の肉のお裾分けをし、藤助が熊を獲ったと言いふらした。熊の肉は新鮮であり、周りの者も母親の言うことを信じた。
藤助は熊の胆を草庵に持っていった。草庵はたいそう喜んだ。
藤助も立派な猟師になったと大層な金子をくれた。
藤助が死んだ熊からとりだしたと説明しても、草庵は信じなかった。
「死んだ熊の胆は中のものがこのように汁ではなく、固まっているものだ」
藤助が仕留めた証拠と言った。
藤助は懐に入っているものを思い出した。蕗の薹である。それをマツにわたした。
「どうしたんだいこんなに早くに、蕗の薹は雪の下でも大きくなるけど、まだ早すぎないかね、この里でもまだ出ておらんじゃないか」
マツはちょっと顔をしかめた。
藤助が不思議に思って、「どうしたんだいおっかさん」ときいた。
「おまえ、これを誰かにもらったんじゃなかろうね」
マツは言った。
「いいや、どうしてだい」
「こんなに寒いときに蕗の薹を採ってこれるのは、雪女しかおらんじゃ」
「どうしてじゃ」
「雪女は蕗の薹を持ってきて、男をたぶらかす言う話じゃ、たぶらかされた男は、雪に埋もれて死ぬんじゃ」
「おっかあ、俺は、死んじょらん」
「そうじゃね、こんなに早く蕗の薹に会えるなんて幸せなこっちゃ、いい香じゃ」
マツの機嫌も直ったようであった。
それから藤助の名は村中に知れ渡った。
五年経った。藤助もいっぱしの猟師になり嫁をもらった。名をシノといった。草庵のところで下働きをしていた隣村の気立てのよい娘であった。下働きではあったが、利発であったことから、草庵の薬作りの手助けもしていた。薬草採りに山に入ることもあった。藤助も一緒に薬草探しをするようになり、いろいろな草の名を覚えた。猟に行くときには山奥の薬草を頼まれることもあった。
あるとき、草案が悲痛な顔をして藤助のところに来た。雪が降り積もった寒い冬の日であった。
「藤助、大変なことになった」
「何です、草庵様」
「町の代官が大変なことを言ってきた」
草庵の話は尋常ではなかった。代官の娘の腹の痛みが強くなり、病が日に日に悪くなった。熊の胆では痛みを抑えることができなくなっていたのだ。
周りの人々は、代官の悪行のたたりだと噂していた。
代官は娘の病を治すために祈祷師を呼んだ。祈祷師は社を建てるように代官に進言し、建てるにあたって、人柱にする健康な娘が必要だと言った。代官はそれをうけて、どこかの村から差し出すようにお触れをだした。あたりまえではあるが、どこからも返事は無く、代官は隣村の名主の娘に白羽の矢をたてた。名主の娘は泣く泣く引っ立てられていったのである。
社ができても娘の病は良くならなかった。無駄死にした娘の親たちのなげきはあまりにも大きかった。母親は自ら水死した。父親は狂った。
今度はどこから聞いたものやら、鬼の肝なら娘の腹の痛みは直る、鬼の肝を取ってこいと代官は触れを出した。
代官は村の名主たちに、鬼の肝を差し出さないと一月に一人の娘をそれぞれの村から引っ立てるといってきた。最初は藤助の村であった。村の名主は草庵に相談したのだそうである。
「藤助、鬼などがいるわけは無く、その肝を獲ってこいというのは、代官は気がふれたに違いない。それでも鬼の肝を差し出さなければ名主の娘が死ぬことになる」
名主の娘はキヌといって、名主のところで働いていた頃の藤助は小さかったキヌとよく遊んでやっていた。
草庵は続けた。
「そこで、藤助、わしは鬼の肝を作ろうと思う。代官は熊の肝はよく知っておるので、違う動物でなければならぬな、山の奥には何か変わった生き物はおらんじゃろうか。その肝に熊の肝を混ぜて、代官に差し出してみようかと思う。まあ、それは一時の気休めじゃ、その間に名主の娘は病気で死んだことにして、どこぞへ逃がそうと思うておる」
頼まれた藤助は晴れたある日、雪の山にはいった。
鬼の肝となると、熊ほどではなくとも大きな獣でなくてはならないだろう。
鹿、狐、狸、猿、川獺、藤助の知っている動物はさほど大きくはない。その動物たちとて、今つかまえるとなると大変である。本当の鬼というのはいるのだろうか。いるのなら、どこにいるのだろう。
そんなことを考えながら雪の中を歩き続けた。ウサギですらこの雪の中ではめったに見かけることはない。
日も暮れてから雪が舞ってきた。
藤助はいつもの猟師小屋に入った。
囲炉裏に火をおこし湯を沸かした。
草庵に頼まれてあてもなく出てきてしまったが、鬼を射止めるなど藤助にはできそうにもない。いや、誰であってもそんなことはできまい。
藤助は思案にくれて囲炉裏の脇に寝転んだ。
囲炉裏の火が燃えるのを見ていると、昔のことが思い出された。初めて藤助が熊の胆をとり出した時のことである。山の斜面に死んだばかりの熊が雪に埋もれていた。自分で射止めたわけではないのに、村では十三歳の藤助が射止めたことになってしまった。しかしあれから、ずいぶんたくさんの熊を自分の手で撃ち殺してきた。
そうだ、死んだ熊をみつけたあの前の晩、雪女に会ったのだ。困ったときには呼んでくれと言っていた。夢を見たのだろうと思い、忘れてしまっていたことである。
藤助は雪女の名前を思い出そうとした。あの白いうりざね顔の赤い目が自分を見て微笑んで言った名前である。
名前に雪がついていた。そうだ、笹雪といっていたような気がする。困ったときには三回名前を呼ぶと助けに来ると言っていた。
藤助は、身を起こすと、囲炉裏の前であぐらをかいた。
誰もいないところなのに、声を出して女の名を呼ぶのはなぜか恥ずかしい。なすすべが無く、こんなことに頼っている自分が恥ずかしいのかもしれない。
何もしないより気が紛れるであろう。藤助は小さな声で「笹雪さん、笹雪さん、笹雪さん」と呼んだ。
周りの空気が冷えてきた。あの時と同じだ。
入口の戸が音も無く開き、白い衣を着た女が小屋の中に入ってきた。あの雪女だ。本当だったのだ。こんなに綺麗だったんだ。子どものときに見た雪女の印象とずいぶん違った。
「藤助さん、立派になりましたね。お手伝いいたしましょう」
あの時のように優しい声だ。
笹雪が赤い目で藤助を見た。
藤助は声が出なかった。
「どうぞ、何なりと申し付けくださいな」
笹雪は白い顔に微笑を浮かべた。
「鬼の肝がほしい」
藤助は声を絞り出した。
「鬼の肝ですか。鬼はたくさんいますが、最も大きな鬼がいいでしょう、案内いたしましょう」
雪女は言い終えるとふっと振り向いた。
「こちらです」
小屋の戸が開いた。
外は真っ暗である。小屋の火の明かりが大粒の雪を照らし出す。
藤助も荷物をしょって銃を抱え外に出た。
「鬼を撃つことができるのでしょうか」
「はい、藤助さんなら撃つことはできます」
雪女は宙に浮かんだ。
雪女が雪の上を滑るように進んでいく後を、藤助は懸命について行った。
しばらく雪の上をいくと、行くと森に入った。
森の中の斜面の一角で雪女が立ち止まった。
雪女は袖を一振りした。
積もっていた雪が舞い上がり、斜面に岩穴がぽっかりと口を開けた。
「鬼はこの穴の奥にいます。私はここまでしか案内できません。ここからは一人で進んでください。鬼の寝ているときを見計らって心の臓を狙ってください」
雪女は藤助に透きとおった弾をわたした。
「この弾を銃にこめて、必ず心の臓を打ち抜いてください。そうすれば、鬼の寿命がつきることでしょう」
雪女は言い終わると、振り向きもせず、雪の中に消えていった。
藤助は手の平に乗っている弾を見た。
それは氷でできていた。しかし、握りしめても溶けることはなかった。
藤助は弾を銃にこめた。そのとたん、銃が凍りつくほど冷たくなった。
背負っていた袋から蝋燭を取り出すと火をつけ穴の中に入った。
カビの匂いが冷たい風とともに藤助のまわりに漂ってきた。
藤助は歩き始めた。穴の先は見通すことはできず、歩く先から暗闇が現れてきた。
何時歩いただろうか、歩いた距離はどのくらいになるか、村に帰るより遠い距離を歩いた感じがある。しかもほとんどまっすぐに歩いているようだ。
そう思った矢先、遠くに火打石の放つ火ほどの小さな光を藤助の目が捕らえた。
藤助は自分の持つ蝋燭の火を消した。暗闇がせまってきたが、先にある小さな光りがはっきりと見えた。そこから藤助は音を立てないようにゆっくりと進んでいった。
小さな明かりが大きくなってきた。蝋燭を消してからずいぶん時間が経った。
穴の奥には部屋があった。
岩に囲まれた部屋の中では真っ赤な鬼が石の台の上に寝ていた。はじめてみる鬼である。上向けに大の字になっていびきを掻いている。一本の角が頭の上から飛び出している。絵に描いたような鬼であった。
しかし、腰みのをつけただけの赤い鬼は想像していたより小さく貧弱である。腹が出ていて頭はとんがり小さい。
藤助は銃を肩から下ろすと撃鉄をあげた。
心の臓を狙うには、鬼のそばによって真上から撃たなければならない。それは少し危険である。鬼がこちらを向くのを待つしかないだろう。藤助は待った。
しばらくすると、赤い鬼のいびきが止まった。そのとたん、大きな伸びをして、寝返りを打ち、からだをこちらにむけた。間髪をいれずに藤助は引き金を引いた。
赤い鬼が「げーえ」と大声を上げてのけぞった。その後ピクリともしなくなった。
藤助の撃った弾は心の臓にめり込んでいる。
鬼の胸の銃弾がめり込んだところが白く変わっていく。凍っていく。
藤助は近寄ると、鬼のからだに山刀を突き刺した。そのとたん、鬼のからだが真っ二つに裂け、肝がころっところがりだした。
藤助は鬼の肝を拾うと皮袋に入れ、今来た穴を走った。走って走って、穴の外に出ると、走り続けて猟師の小屋にもどった。
鬼を射止めてからどのくらい経ったのだろう。
山の頂が少し明るい。もう夜が明ける。
藤助は小屋に入らず、そのまま村にもどる道を歩いた。
自分の家にたどり着いたときは昼に近かった。
家の戸を開けると叫んだ。
「鬼の肝をとったぞ、シノ」
妻のシノはが奥から出て来た。
「あなた、無事で」
シノは涙を流して喜んだ。
藤助はそのまま床の上に倒れた。
シノは草庵を呼びに行った。
あわててやってきた草庵は藤助に気付け薬を嗅がせた。
藤助が目を開けた。
「草庵様、鬼の肝をとってきました」
藤助は皮の袋を草庵に渡した。
草庵はうなずいて、皮袋から鬼の肝をとりだした。
「これは、これが、本物の鬼の肝とな」
鬼の肝を見て草庵の顔が青くなった。
「はい、その通りです」
人の肝とよく似ている、いや人の肝だ、草庵は思った。
藤助は鬼の穴を見つけたことを、雪女のことも隠さず話した。
「不思議なことよの、これが鬼の肝か、よしこれを代官に献上しよう」
草庵は鬼の肝をもって家にもどった。
草庵の家では名主の使いが待っていた。
「草庵様、代官様がお隠れになりましたそうで」
「え、どうした」
「はい、名主様のところにお使いが来ました。昨日夜更けのことだそうです、いきなり大声を上げてお命がなくなったそうでございます。内臓がくりぬかれ、凍っていたそうでございます」
「それは、また、ご病気か」
「いえ、何も分かりません」
「そうか」
草庵は急いで鬼の肝を薬に仕立て名主のところに行った。名主にその薬を代官様の屋敷に届け、娘に飲ますように言った。
名主の使いは代官の屋敷に行った。代官屋敷では急に死んだ代官の後始末で人びとがあわただしく動いていたが、使いのものはなんとか鬼の肝を渡すことができた。
それは代官の娘に渡され、それを飲んだ代官の娘の病は癒え、いつものくらしができるようになったとのことであった。
時が経ち、新しい代官が赴任し、村の生活は楽になった。
藤助は心の中でいまでも雪女のあの優しい声が聞こえる。
藤助さん、鬼であろうとも自分の子どもの幸せを願うものです。代官様は自分の身を削って子どもを助けたのです。あなたは代官様を助け、そして村も助けたのです。
あなたのおかげで村人たちに平穏な時が訪れたのです。
藤助は、その昔、子ウサギを追いかけた母ウサギの、振りむいた時の真剣な顔を雪女と重ね合わせていた。
鬼の肝
私家版雪女小説集「雪女、2015、222p、一粒書房」所収
表紙日本画:山内佳子


