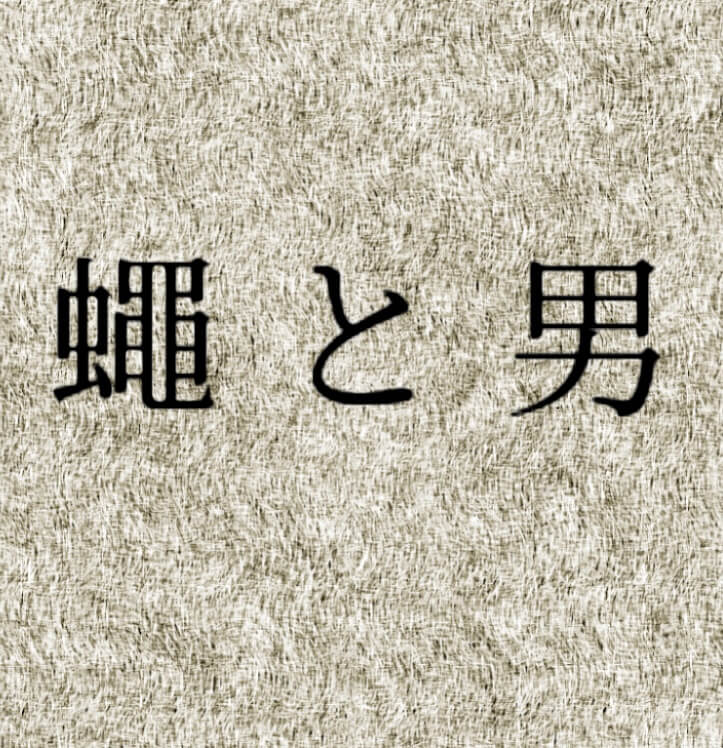
蠅と男
復帰作です。
秋田の或る土地に、箕之介と云う男がいた。箕之介は臆病で、噂事にも流されやすい性質だったが、銀細工の腕だけは町内一と評判の男であった。箕之介の作る銀細工はしなやかで美しく、またその輝きは磨かれた宝石のようであった。そのお蔭か、銀細工職人の多い土地柄ではあったが、箕之介の商売は大変に上手くいき、日々の生活に事欠くことは無かった。
或る朝のことである。箕之介は布団からむっくりと起き上がって、欠伸をひとつした。血行が良くなったのであろうか、腹周りが酷く痒くて、何度かぼりぼりと掻き毟った。箕之介は朝に大変弱い。その所為で何度か嫌な目にあっているから、箕之介はやはり朝が嫌いであった。その日も何時もの通り機嫌が悪く、意味もなくいらいらとしていた。然し、いらいらしていると言っても人間である限り腹は減るものである。毎度このようになるから箕之介は先読みをして、前日の晩に煮物か何かを作り置きするのが常であった。この時も筍の煮物を作っていたから、箕之介は重い腰を上げて台所へと向かった。
「むっ。」
筍の煮物を見た箕之介は咄嗟に声を上げた。筍に付いた鰹節に何か小さくて黒いものが乗っているのである。それは蠅であった。鰹節の上で気持ちよさそうに、前足を擦りながら小首を傾げている。普段の箕之介であれば手で払ってお仕舞いであるが、その時は気が立っていたものだから、箕之介は徐に手拭いを取って、蠅を見ながらじりじりと近づいていった。然し箕之介は感情の隅に残った少しばかりの冷静さに諭されて、蠅を何処かにやってから潰すことにした。手拭いはそれにも丁度良くて、ひと振りしたらブゥンと羽音を立てながら流しの縁についた。
「せいっ。」
箕之介が手拭いを勢いよく振り下ろすと、蠅は避けることも出来ずにぶちっと潰れた。赤黒い体液が手拭いに付いて、それが箕之介を更に苛立たせた。流しにこびりついた平たい蠅はそのままにされて、何時しか物言わぬ亜鉛鉄板と同化して了った。箕之介は筍を頬張ってから商売に出掛けた。
その日の商売も上手くいって、日昳を回る頃には用意していた銀細工を全て売りはらって了った。特に道楽など持ち合わせていない箕之介は即座に帰路に就こうとしたが、その途中で一軒の茶屋を見つけた。丁度小腹の減る時刻であったから、箕之介は何とは無しに、ふらっと店に入った。中は小綺麗な様子で、腰掛が幾つか並んでおり、壁にはひょっとこの面が飾られている。臆病な箕之介にはどうにも面が気味悪く思われて仕様がなかったから、なるべく其方を向かないようにしていた。
注文したみたらしの団子が届いたので、箕之介がいそいそと手を拭いていると、二つばかり隣の腰掛に座っている男どもの話が耳に入ってきた。それは噂話であった。
「そういやお前さん、隣町の銀細工屋が潰れたの聞いたかい。」
「聞いたさ、センさんとこのだろう。腕の良かったのは俺だって知ってるよ、だのにいきなりどうしちまったのかね。」
「変な噂が有るんだが、聞くかね。」
「おう、聞くさ。どんな噂だい。」
「頓狂な話ではあるんだが、何でも蠅を潰したのが良くなかったらしい。世間にゃ銀蠅と金蠅ってのがいてな、銀蠅を潰すと商売が、金蠅を潰すと金回りが悪く成るらしいのだ。」
「そりゃまた変な噂だ、確かなのかい。」
「俺だってよくわからんだが、実際潰れちまってるのだ、満更間違っても無いんじゃないかね......」
こんな話であった。よく噂話に踊らされて後悔することの多かった箕之介であるが、今度のは今朝起こったこととあんまりにも繋がっていたからか、疑う事もせず直ぐに心中穏やかでなくなった。箕之介がその時心配していたのは、潰したのが銀蠅か、それとも金蠅のどちらであったか、と云う事だ。金蠅ならば、まだよい。普段から金のあまり使わぬ男であったから、金回りの心配はせずに済んだ。然し銀蠅ならば大変なことである。何しろ商売が立ち行かなくなるということは、女房も子もいない箕之介にとって唯一の生き甲斐である仕事を失うと云うことだ。其れだけは嫌だと、箕之介は思った。直ぐに確認せねばならぬと気だけが急いて、ぐいっと茶を飲んだ勢いだけで団子を胃に流し込んだ箕之介は、払った代金の釣りを受け取るのも忘れて自家へと飛んでいった。
蠅のミイラはまだ流しにいた。朝潰されて昼まで放って置かれているのだから、乾きに乾いて、少しでも触ろうもんなら剥がれ落ちてしまいそうであった。昨日の敵は今日の友とはよく言ったものであるが、今の箕之介にとってこのミイラは、今朝の敵は今昼の友のようなものであった。いや、友と呼ぶには大層な命運をこの蠅は背負いすぎているなと、箕之介は思った。兎も角、箕之介にとって重要なのはそんな事でなく、蠅の色であった。然し体液が漏れ出す程酷く潰れてしまっているのだ、素人が見ても何方であるかなんぞ解る筈も無い。更に箕之介は銀蠅と金蠅を明確に見比べた事なんぞ無かったのだ。だがこの男は臆病者の小心者、箕之介である。こんな時に前向きな者であれば自己に都合のいい様に考えられるのであろうが、この男は蠅の色を銀であると思い込んで了った。
「拙い、これはやはり銀であるな。これでは商売が出来ぬではないか、ああ、困った困った。」
こんな事を呟きながら、箕之介は台所を右往左往していた。あまり動き回るものだから、そのうちに足の小指を食器棚の角にぶつけて、酷い思いをした。
それからというもの、箕之介は商売に身が入らなくなって、銀細工の売上も芳しくなくなって了った。元来人付き合いが得意な方で無かった箕之介は、何処か不貞腐れた様な感をお客に与えてしまいがちであったが、それがより酷くなってしまったのだ。こんな風に悪い事が起こると、箕之介の思い込みは尚酷くなった。また銀蠅の銀と云うのが良くなかった。お蔭で箕之介は得意の銀細工の熱意まで削がれてしまって、遂には仕事をぱったりと止めてしまった。
そんな折に、町に高名な占い師が来ると云う噂が流れた。それは相当の騒ぎになったから、勿論箕之介もそれを聞きつけた。然し、もう既に銀蠅を潰して了っているのだから、どうせ占いでも酷いことしか云われないだろうと思って、初めは行くまいとしていた。だが段々と興味の方が勝ってきて、そうなると行かないのが嘘であるかのように思われてくるのがこの男の性質である。習慣になっていた煮物作りをしている時も何処かそわそわとしていて、鰊に掛ける筈の、ぐつぐつと煮立った汁を手の甲に掛けたりしていた。然し占い師が町を発つその日にとうとう決心をして、簡単な準備をした後、町に歩いて行った。
幾ら高名な占い師であると云っても、即席の露店まで気の利いた造りには出来ないようで、露店の外観は何処かチープな印象を与える造りであった。それが箕之介の期待を飲み込んでしまって、代わりに一片の懐疑を吐き出していった。まあここ迄来たのだから、と自分を奮い立たせて、箕之介は『占』と大きく印字された布を潜った。
「......どうぞ、こちらへ。」
細くて低い、然しよく通る声が奥から聞こえる。その声色は男性のようであり、然し何処か女性じみた印象も与えるものだった。箕之介は声の主が男性であるのか女性であるのか、暫く自分の中で議論していたのだが、直ぐに其れが蒟蒻問答であると思い直して、占い師の方へと寄っていく。
結局の所、占い師は女性であった。深くフードを被っては居たが、長い前髪が垂れていたから、箕之介は女性なのだと思った。そんな事を考えていると、占い師は唐突に、
「最近、何か酷い事があったろう。」
と言った。箕之介はどきりとした。近頃で酷いことと言えば、挙がるものが多過ぎたからである。箕之介はこくこくと頷く。占い師はその後も幾つか言を発し、悉く箕之介を驚かせた。箕之介は占い師が本物だと思って、すっかり信じ込んで了った。最後に占い師は、
「近くの死に物を弔ってやれば、良くなる。」
と告げた。箕之介は家に飛んでいった。
家に帰る途中、箕之介は町の商店に寄って、線香を何本か買った、それも飛切り上等のやつである。また、八百屋で蜜柑も買った。そうして家に帰り着いた箕之介は、蠅を弔う準備を整えてから、台所へと向かった。
蠅はまだ流しの縁で煎餅のように平たくなっていた。箕之介は恐る々々それを剥がして、小さな小瓶の中へ入れた。何処に弔おうかと暫く悩んだ挙句、裏手の庭に決めた。庭には昨年の夏に植えた、松の若木が伸びている。箕之介はその根元に穴を掘って、小瓶を埋めた。線香に火をつけ、それを近くへと置き、手を合わせた。
「どうか、成仏してくだせぇ。」
箕之介は揺れる白煙を眺めながら、暫くその場を離れなかった。
それから一ヶ月程後、箕之介は非常に快活になって了っていた。念入りに弔ったと云う意識から、必ず事は好転すると思い込んでいた箕之介は、あの後銀細工に再び精を出したのだ。そして久しぶりの仕事が愉快で、それに打ち込んでいたら、商売が上手くいき始めたのである。
それと、これは本人の伺い知らぬ事であるのだが、町で箕之介は少し噂の種になっていた。
「銀細工の箕之介さん、近頃御庭で御線香焚いてらっしゃるのだけれど、御飼いになっていた犬でも亡くなられたのかしら。」
今日も箕之介は、不機嫌な朝を迎える。何時もの通りむっくり起きて、戸棚から小鉢を取り出して煮付けを食べ、仕事へ向かう。その途中、箕之介は裏庭を訪れて、一本の線香を立てて往くのだ。
蠅と男
この話は唐突に思い付いて書き始めたのですが、初めに夢想していた終わりとは大分違うものになりました。箕之介が動きたがっているようにしたら、こんな物語になりました。結果的に、これでよかったように思います。そんな感じであります。


