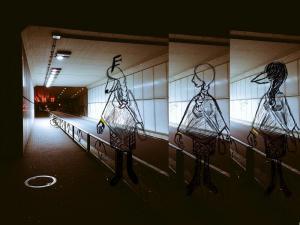夢の中で泣いて
前頭葉より
夢こそが現実である、と定義したのは一体どこの誰だっただろうか。そんなこともぼんやりするくらい、時間が経ってしまっていた。名前もわからぬ人々が、無作為に並べられ、寝かされている。この場合の「寝かす」は、パンやケーキの生地と同じ意味だ。しかし一つだけ違うのは、この時間には何の意味もないということである。だだっ広い白い空間は、冷蔵庫を思わせる。全員が寝息を立てて、目を瞑っている。彼らは、定義上の現実の中にいる。
いつからだろうか、そこに無意味さを見出したのは。ゆっくりと彼らは朽ちていき、数百年で死んでいく。そういう予定だ。語り手である僕は、まだ、死体処理をしたことがない。隣の棟から流れてきた、噂話に過ぎないが、彼らには終わりがあるらしい。それに付随され、僕らにも彼らと同じような終わりがある、という噂も流れていたが、一体誰が吹聴したというのか、前者の噂話よりも信憑性に欠けていた。
彼らは本当にずっと寝ている。ベッドの上で寝ているから、僕はこうして見守らなくてはならない。ベッドから落ちたら、何かと不都合なんだって。これもまた、一種の噂話。
僕はこうして考える。考えることを与えられてしまったから。
一番昔の記憶は、ここに立ってガラス越しに彼らを見ていたことから始まる。その時は、この世の構造についても、こんな恐ろしい思想にも、思いをめぐらすことなんてなかったのにな。
こうして、思いつくことのすべてを書き綴るのには訳がある。延々と続く日々の中、殆ど変わらない景色の中で、連なった恐ろしい思想ゆえである。
隣の棟へは休憩へ、度々出掛けて行った。休憩、という言葉は死後だろうか。同業者の間で交わされていた言葉を用いるならば「補給」の時間。酷使した視力や筋力の回復に向かった。その中で、幾つもの噂話を耳にした。僕の恐ろしい思想は、そうして培われていったし、他にも同じような考えを持つものも少なくないだろう。
いい加減、恐ろしい思想について、書き記さねば。もう、そんなに時間がない。何より、何千時間、何万時間とかけてきた仕事は、もはや癖だ。強い意識を共にせねば、癖を拭うことなんてできない。
僕は、彼らと共に終わろうと思う。
終わる、ということへの恐怖心は無く、いつか僕自身が伝説的な存在、もしくは噂話として語り継がれるだろうという予感に誇りすら感じる。なにせ、僕らはみんな、噂話が大好きだから。
死体処理は面倒だ。だから僕は考えた。考える、という残酷なオプションを惜しみもなく費やした。
彼らの寝ている部屋の温度はは、冷却水の気化によって維持されている。その管を断線し、部屋を水で満たすのだ。我ながら賢いことを考えたものだと自画自賛する。そうすれば、僕も終わる。終わったら…その後のことは考えないようにする。
満ち満ちていく水の群れを見ながら、僕は今一度の逡巡の中にいた。
僕は彼らを愛していた。
だからこそ目の前の現実に、この硬い胸をそっと撫で下すのだった。
彼らの密度はざっと0.95g/㎤。対して、僕は7g/㎤程ある。彼らはめいいっぱい天井近くまで上昇し、せっかく溜まった水もダクトへ流れ出ることだろう。
僕の視界は霞んでいく。こんなに細かいビット数にまで耐えられているとは、思いもしなかった。
そして最後に、僕は考える。
この世界は、緩やかに続く。
少なくとも僕には、そう見える。
終わりは、夢の中にあるのだろうか
夢の中で泣いて
所詮自分には何もできないんだって話です。
無力感というオチのつけ方は、幼稚だったかもしれません。でも実際、自分には何もできないんだと思うと、こうせざるを得なかったのです。