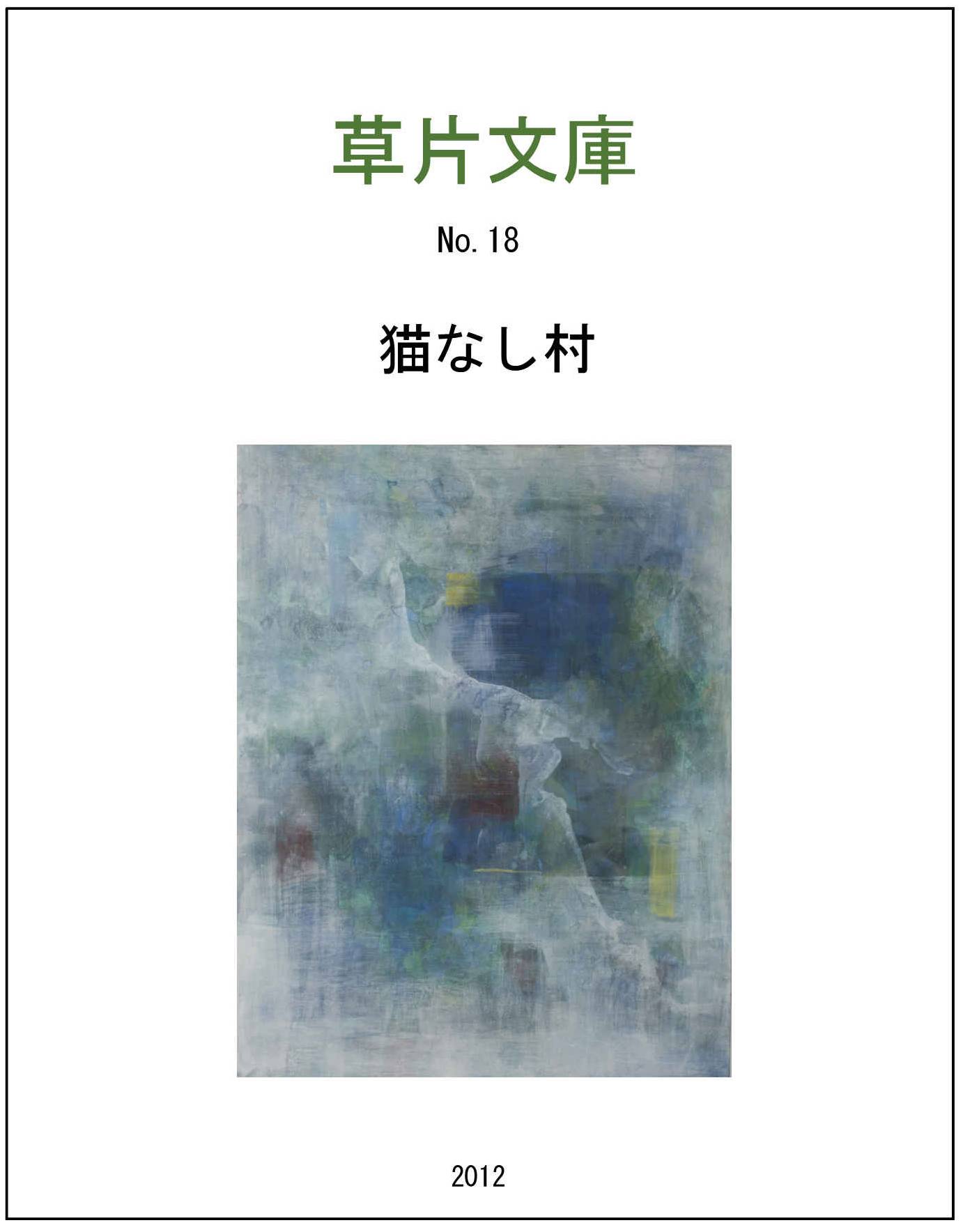
猫なし村
外では雪と風が強くなっている。
実(み)助(すけ)と祖父の九兵(くへい)が寝支度をしている。
「実助そろそろ寝るべ」
九兵が行灯の芯をもみ消そうと手を伸ばしたときである。とんとんと戸をたたく音がした。
こんな猟師小屋に人が来るわけはない
「じい、こりゃ雪女だべえか」
実助はまだ十歳になったばかりなのに肝が据わっている。今度の猟も、危ないからくるなといったのだが、どうしても熊を見てみたいと、一緒にこの山奥までやってきた。足手まといになるかと思っていた九兵は、実助の野生の鹿のような動きに舌をまいていた。むしろ九兵より雪の中での動きは俊敏であった。
「いや、風のいたずらだべえ。木の枝か何かがぶつかっているだ」
「そうか」
実助は筵の中にもぐりこんだ。
九兵が行灯の火を消すと真っ暗になった。
部屋の中は火を消したばかりの油のにおいが漂っていた。
目が慣れてくると囲炉裏の灰をかけてある炭火がボーっと赤く見える。
とんとん、戸をたたく音はまだ続いていた。
九兵はもういびきをかいている。
実助はなかなか寝付けなかった。
寝返りを打って、上を向いた。そのとたん、いきなり部屋が明るくなった。
「じいちゃん」実助は筵から顔を出した。
行灯に火が灯っている。
「うーん」九兵が目をあけた。
「おりゃ、火がまだ残っていたんだべ」と起き上がって芯をもみ消した。
また闇が訪れた。
とんとん、あいかわらず戸を叩く音がする。音は次第に高くなり、どんどん、と入口の戸が揺れるように叩かれた。
「うーん、どれ、見てくるか」
九兵が起き上がった。
また、行灯に火が灯った。
「こりゃ、へんじゃ」
がーっという音とともにつっかえ棒が外れ、戸が内側に倒れた。
雪が吹き込んできた。
「ていへんじゃ」
実助も起き上がった。
九兵はあわてて、倒れた戸を元のように立て直し、しんばり棒を強くかけた。
「すごい風じゃあ、じゃが明日はきっと晴天になる、獲物は多いぞ、実助も寝れ」
九兵と実助が筵にもぐりこむと、九兵はすぐにいびきをかき始めた。
しばらくすると、風は収まったようで、外の木々の擦れる音が聞こえなくなった。
実助はやっと眠くなり始めた。
その時、実助の足が引っ張られた。
なんだ、と筵から顔を出すと、ボーっと白く光るものが足元にいた。
目がはっきりしてきた。
目を凝らすと老女が実助の足元に座っている。
頭から真白の長い毛がふわりふわりと宙に舞い、赤い目をして実助を見ていた。
雪女だ。
九兵は全く気がついていない。
女は滑るように枕元に来ると、しわだらけの顔を実助に向けて言った。
「ぼお、名前はなんと言う」
雪女は実助が返事をしないのを見て、
「お前の家には猫がいるかい」
と聞いた。
実助はこっくりとうなずいた。
生まれたばっかりの子猫が三匹いた。一匹は茶トラ、一匹は黒で、残りは白、三匹とも眉間に二つの丸い灰色の模様があった。親猫は子供を産むと死んでしまっていないが、実助が大事に育てていた。猟に来ている間は九兵の連れのハマが面倒を見ている。祖母も猫を可愛がってくれた。
「名前はなんという」
雪女は身を乗り出して実助を覗き込んだ。
実助は自分のことか猫のことかわからなかったので、猫の名前を答えた。
「お茶こう、黒べえ、白ざえもん」
「そうか、明日は獲物がたくさん獲れるぞ」
雪女は満足そうにうなずくと、すううと消えていった。
実助のまぶたがおち、そのまま眠りについた。
あくる朝早く、薄暗い中で九兵が囲炉裏で湯を沸かし朝食の準備をしていた。
その音で実助が目を覚ました。
「よく寝ちょったな」
「うん」
実助は筵から這い出すと、目をこすりながら言った。
「じいちゃん、昨日、おばあが来た。雪女だべか」
九兵は、「えっと」顔を引きつらせた。
「夜中に、おばあさんがそばに来た。怖かった」
「何か言ったか」
「猫はいるか、といったから、うなずいた」
「それだけか」
「名前を聞いたので、お茶こう、黒べえ、白ざえもん、と言った」
「答えたのか」
「うん」
「でも、自分の名前を言わなくてよかったの」
「なしてじゃ」
「そりゃ、ほんもんの雪女じゃ、雪女に会ったら、何もしゃべってはいかんのじゃ」
「なしてじゃ」
「自分の名前を言うと、そのまま連れて行かれるで、連れて行かれて、雪の中に埋められてしまうのじゃ」
「獲物がとれるといっちょった」
「そうか、それは嬉しいこっちゃ、雪女は嘘をいわん。次に雪女に会ったときには一言もしゃべってはなんねえからな」
「うん」
実助は九兵がさし出した握り飯にかぶりついた。
昨日と違いその日はよく晴れた。朝早くから狩をはじめ、昼までに鹿を一頭仕留めることができた。ウサギも三頭ほど獲れ、九兵は大満足であった。
雪の中で、皮をそぎ、肉を丸め、内臓は皮の袋につめた。
実助も手伝った。解体した獲物を橇(そり)にくくると山を降りた。
険しい谷を越え、夕方、村に帰り着いた。
九兵の家の前で近所の人たちが寄り集まっていた。
実助のおっ父の衣兵とおっ母の夕もいた。ばあちゃんのハマもいた。
九兵がもどってきたのを衣兵が見つけると駆け寄ってきた。
「とつぁん、大猟じゃな、こりゃ今日はご馳走だ」
「実助もようやったぞ」と九兵は実助の頭をなでた。
近所の人たちもよってきた。
「何があったのじゃ」
九兵が尋ねると、ハマが、
「村の猫がみーんないなくなっちまった」と答えた。
「いつのことじゃ」
「今日の朝じゃ、うちの三匹もいなくなった、隣の三毛も、急に消えてしもたよ」
「神隠しか」
「そうじゃな」
「悪いことがおこらんとええが」
「じゃが、人間でなくてよかったな」
「ほんとうに」
村人たちはうなずいた。
実助が雪女のことを言おうとしたとき、九兵が「あれは誰にも言うてはあかん、だまっちょけ」と小声でとめた。
「あとで、鹿肉さとどけますで」九兵は隣人たちに言った
「楽しみにしてるでよ」ひとびとは家に帰っていった。
猫は雪に埋められてしまったのじゃろか。実助は自分が猫の名前を言ってしまったのでいなくなったのだと、悲しくなった。でも、よそんちの猫もいなくなったのだから違うかもしれない。実助が浮かない顔をしていると、
九兵は「猫でよかったなあ」と実助をなぐさめた。
それから八年が経った。実助も十八歳になり、いっぱしの猟師である。
あれ以来この村には猫が全く寄りつかなくなり、隣村からもらってきてもすぐに逃げ帰ってしまった。いつの間にかこの村は猫無し村と呼ばれるようになった。鼠が多くなり、鼠おいのためにどの家でも小型の犬を飼うようになった。
実助の家でも、九兵が雄の柴犬を一匹もらってきた。実助は猫と同じようにかわいがり、くん太と名づけていつも一緒に連れ歩いていた。
九兵が狩りに行くときには必ず連れていった。そんなこともあり、くん太は村でも評判の猟犬に育った。
実助の父の衣兵は、自分は畑仕事に向いていると、全く狩をしない。一方息子の実助は九兵から狩の仕方を一から教わり立派な猟師になった。村では猟師になる子どもが少なくなかったが、実助は最も腕のいい猟師として隣村にも知られるていた。
実助を育て上げた九兵はこのあたりでは珍しく長生きし、六十八で眠るように死んだ。
冬を迎えたある日、実助はくん太をつれて猟にでた。九兵とよく行った山の中の猟師小屋にたどり着くと、囲炉裏に火をおこし炊事の用意をした。
「明日は大猟じゃい」
実助はくん太に声をかけた。
くん太は土間の筵の上にからだを伏せると、実助を見上げた。
なべのものがぐつぐつと音を立て始めた。
「いい匂いじゃ、今日は精がつくように、ししの干肉を持ってきたんじゃ」
芋としし肉と米に少々の塩を入れて雑炊をつくった。
碗に少しすくい、味見をする。
「うん、うまい」
実助は碗に盛り付けると雑炊をすすった。
くん太のために、皿にいれ、さましてから土間においてやった。
「うまいだろ」
くん太は鼻に皺を寄せてべちゃべちゃと音を立てて食べた。
食べ終わる頃に雪が降り出した。
「雪か、明日になれば止むだろう」
実助は戸を開けて外を見た。黒い空から大きな雪が落ちてくる。見慣れた景色ではあるが、明日の猟のことを考え、すこし緊張していた。いつものことである。
実助は銃の手入れを終えると寝る支度をした。風も強くなってきたようだ。
大人になった実助は九兵と同じように寝付きがよく、筵に入るとすぐに眠った。
何時経ったのか分からないが、くん太が大きな声で吠えた。獲物をみつけたときの鳴き声だ。実助は飛び起きると銃をとった。
だが、何もいない。
戸がかたとも音がしないのはかえって気味が悪い。
ふっと土間を見ると、あたりがボーっと明るくなり白い袴をはいた若い女が、くん太をなでている。くん太は気持ちよさそうに目を瞑り、耳をたらして首を前に突き出している。
真っ白なうりざね顔の女の切れ長な目が実助を見た。長い黒髪が白い袴のすそまでたれている。
雪女だ。
もう何年前になるか、実助は九兵じいさんとこの猟師小屋に来たときのことを思い出した。あのときの雪女は年寄りだった。目の前にいる雪女とは似ても似つかない別の生き物のようだ。九兵は一切口をきいてはいけないと言っていた。
雪女が口をあけた。真っ赤な舌が生き物のようにひらひらと口の中で動いている。
雪女ははーっと、くん太に息を吹きかけた。くん太の顔に白い雪が降りかかり、髭が凍った。
くん太が殺される。
実助は銃を構えようとした。
「無駄です」
雪女が鈴のなるような声で言った。
実助は、銃を後ろに放り投げ、ひざまずくと首をたれて祈った。
心の中で、くん太を助けてくれと祈った。
雪女が微笑んだ。
「傷つけたりはしません、寝ているだけです」
実助は顔を上げた。
「一緒に来てください」
そう言って雪女は立ち上がった。
小屋の戸がするすると開いた。雪女が外に出た。
雪は止んでおり、月に照らされてまぶしいほどの白い世界が広がっている。
雪女が振りかえって中にいる実助に手招きをした。
実助は覚悟を決め、土間で雪靴を履き、くん太の頭をなでた。くん太は気持ちよさそうだ。
実助が外に出ると戸が静かに閉った。
雪女はゆるゆると雪が積もった林の中に入っていく。
実助は雪女の背に黒髪がゆらりゆらりと揺れるのを見ながら雪を踏みしめた。
何処に連れて行かれるのだろう。
どのくらい歩いたのか分からないが、山の斜面の雪の積もった大きな岩の前に来ると、雪女の細くて長い指が岩肌を撫でさすった。岩が沈み、岩屋への入口が開いた。岩屋の中は明かりが燈されている。
雪女は中へ入った。実助は奥へ奥へと導かれ、白い石造りの小さな部屋にたどり着いた。
壁の石に実助の手がちょっと触れると、あまりの冷たさで切り裂かれるような痛みを感じた。
部屋の中で立ち止まった雪女は、実助のほうにからだを向けると、するりと白い衣装を身からはずした。乳房は子どものように胸から少しばかり隆起しているだけある。しかし、しっかりした腰は成熟した女のからだである。
雪女は凍るようにつめたい床の上に横たわった。
実助はまだ女の経験がない。だが、下半身が自然と熱くなり、張り詰めてくるのをどきどきしながら感じていた。
雪女が実助を見た。実助のからだはもう自分のものではなかった。いつの間にか雪女のからだに覆いかぶさり、痛いほど熱くなったものを雪女の体内に入れていた。
雪女の顔を見つめているうちに、実助の腰の辺りが我慢ならないほど張ってきた。雪女の口元から、あっという声が漏れたとき、実助の精は吸い取られ、腰や足やいたるところの筋肉がしびれ、皮膚が麻痺して体中に快感が走った。こうして雪女は実助の初めての女になった。
時が止まっていた。
どのくらい経ったのか分からなかったが、雪女が上半身を起し、実助に立ち上がるように促した。実助は腑抜けたまま立ち上がった。
衣装を身にまといながら雪女が言った。
「実助さん、ありがとう、あなたは雪女の父になりました。この村の雪女の父です。私はつい先日生まれおちました。母は隣の部屋で息を引き取るところです。母は千年前に人間とまぐわい、私をからだの中で育てました。およそ千年がこの地方の雪女の命です。この国の雪女は命尽きるとき次の子どもを産むのです。あなたの子どもは千年たつと私から生まれるのです」
雪女が手招きをした。
「こちらへ」
雪女は隣の部屋に実助を連れて行った。
実助はその部屋に入って目を見張った。
石の台の上で死にかけている年老いた女が、猫に囲まれて目を瞑って横たわっていた。実助が子どものころ、九兵といっしょに猟に出た時に猟師小屋で会った雪女だ。
老女は眼を瞑ったまま言った。
「ぼーか、よい青年になった。ありがとよ」
老女はそれだけ言うと、もう息も無いようであった。
年老いた雪女の周りには猫たちが様々な格好をして寄り添っている。
猫たちが実助を見た。その中から大きな猫が三匹駆け寄ってきた。眉間に二つの丸い模様があった。
「お茶こう、黒べえ、白ざえもんじゃないか」
実助は思わず声を上げた。あれから八年、この猫たちもいい年になった。猫たちは実助にこすりついた。実助も三匹をかわるがわる抱き上げた。ずっしりと重い。
「私たちが死を迎えるとき、生きた動物の暖かさが必要になります。母は猫を選びました。この猫たちが長い間母によりそってくれました」
若い雪女はそう言った。
その時、実助は背筋に冷たいものを感じた。そうだ、声をだしてしまった。
実助は若い雪女を見た。
雪女は微笑んだ。
「心配いりません、あなたは、私の子どもの父親。これから雪はあなたの守り神になるでしょう」
雪女は実助の前に進み出た。実助がたじろぐと、赤い口を開けて白い息を実助に吹きかけた。冷たい霧が実助を包み込み「さようなら」という声が聞こえ、我に返ると実助は猟師小屋にいた。
くん太が実助を見るとくんくんとよってきた。囲炉裏では炭が赤く燃え、その周りに三匹の猫が丸くなって寝ている。
あくる朝、実助は大きな熊が穴から顔を出しているのを見つけた。冬眠中でも熊は時々起きてくる。ぼんやりしているとはいっても注意をしないと自分の命が危ない。実助はそろそろと近づくと銃を構え引き金を引いた。玉はみごとに熊の眉間に命中した。熊はあっけなく死んだ。
皮をはぎ、熊の胆をとり、肉をそいで丸め、必要な部分を橇にくくり付けた。
三匹の猫をその上に乗せ、くん太とともに村にもどった。
村に着くと、家の前で村人たちが集まって騒いでいた。
父親の衣兵が実助の姿を見つけて走ってきた。
「熊とったべか、すごいこっちゃ、やや、この猫達はどうした。前いたやつらだべ」
「そうだ、とっちゃん、お茶こう、黒べい、白ざえもんだ。もどってきよったんだ」
「そうか、村でも猫たちがもどったと騒いでるだ。なんかいいことあるんだべかな」
「きっとそうだ、今日は熊鍋にするからな」
少し雪がちらついてきた。
雪は実助を守ってくれる。
三匹の猫が嬉しそうに尾っぽをたてて、家の入口をまたいでとことこと中に入っていった。
昨日あったことは一生人に話すことはないだろう。
くん太が後をついて土間の中に入ってきた。
猫なし村
私家版雪女小説集「雪女、2015、222p、一粒書房」所収
表紙日本画:山内佳子


