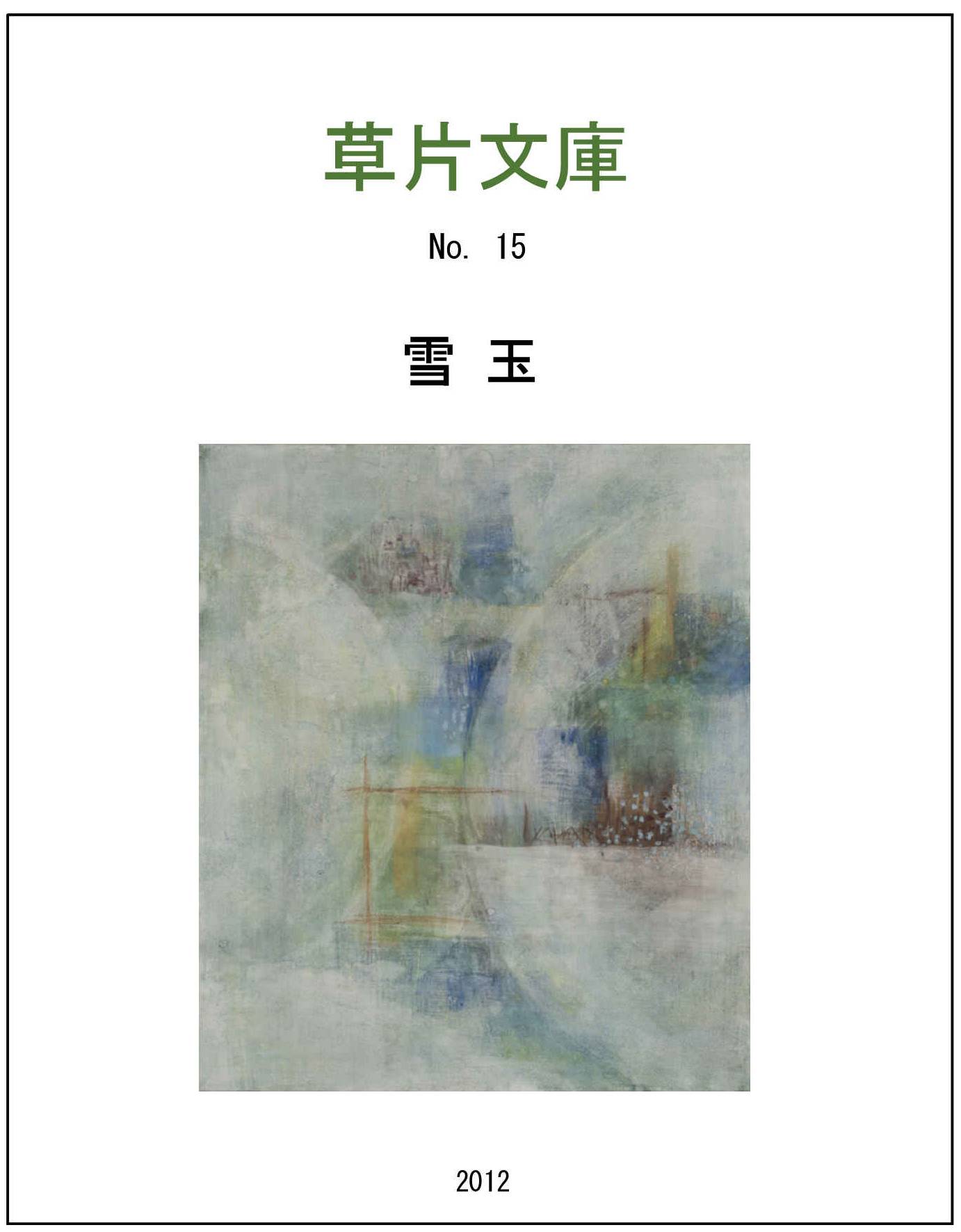
雪玉
その昔、とある雪国の山奥での話である。
ある年のこと、あまりにも雪が深く、一つの村に住んでいた数十人、すべての村人が、雪に埋もれて凍死するという出来事があった。
その村は町からいくつもの村を通り、山を越えていかなければならないほどの僻地にあった。村の名前もすでに人々の記憶に無い。
その村の隣の村、隣といっても、やはりいくつかの山を越さなければならないほど離れているが、一人の老人がかろうじて出来事を覚えていたに過ぎなかった。
老人はもう九十を過ぎているが、その村の惨事は本人にとって自分の一生の生活を支えてくれることになった、忘れることの出来ない事件であった。
それは老人が行商をしていた頃、年はまだ二十歳を少し過ぎたあたりのことで、七十年近くも昔のことになる。
老人の名は八蔵といって、水飲み百姓の八番目の子供である。当然のこと十二になったとき、町の商家に丁稚奉公にだされた。
八蔵はつらい仕事に耐えて十年頑張った末、その店の足袋や下駄、それに他で仕入れた干した海のものなどを売り歩くことが許され、独り立ちしたのである。いうなれば行商人になることができた。
八蔵は幾つかの村に寄りながら商いをし、自分の村につくと、自分の家に何日か居候をして、残ったものを安くその村人にわけた。町に仕入れに行く時には村の者たちが射止めた熊や鹿、それに鳥の肉の干したものなどを買って、町でそれを売った。生真面目でからだが丈夫だった八蔵は、村長から町長へ手紙を届けるのを頼まれたり、次第に他の収入も得るようになっていった。
村人から頼られるようになると、収入も増え、商いをはじめて八年も経つと、自分の村に小さな家を手に入れた。家があるといっても、ほとんど留守であり、独り身であったことから、兄弟姉妹に手入れを任せ自由に使わせていた。しかし、家があることで、そこを基点として、遠くまで商いに行けるようにもなった。
ある日、家に戻ると、土間ですぐ上の兄の七蔵が獲ってきた鳥を軒に吊るしていた。七蔵は村長の田をいくつか任されている傍ら猟にでていた。今ではなかなか腕の立つ猟師になっている。
「八蔵、また、家をかりとるでよう」
「兄(あに)さんどうぞいつでも使ってください。豊猟でしたね」
「ああ、このウサギはなかなかええぞ、皮を売ってくれんかい」
七蔵は茶色の肥ったウサギを吊るして見せた。
「ほんとですね、その皮なら、高く売れますね」
八蔵の話し言葉は商売がらずいぶん丁寧である。
八蔵は背負っている荷物を下ろすと風呂敷を解いた。
こまごまとした物の中から猟銃を取り出し兄に渡した。
「兄さん、使ってください」
驚いた七蔵はいきなり渡された銃を取り落しそうになった。
「こ、こりゃ、すごい新式の銃だ、こんな高いもんおりゃ買えん」
七蔵は目を見張って銃をながめている。
「土産です、いい獲物をしとめてください」
「そんなこといったって、こりゃ、何十円もしとっただろうに」
「お得意さんが安く譲ってくださったんです、兄さんの獲物でずいぶんもうけさせてもらってますよ、今回だって、兄さんのとった熊の胆が高く売れましてね、熊の毛皮と熊の胆を町の医者のところに持っていったら、こんなにくれました。半分私が貰います」
八蔵が懐から五円を差し出すと、
七蔵はまたびっくりして言った。
「こんなにたくさん、ありがたいことだなあ、ハルが大喜びじゃ、ありがたい、ありがたい」
七蔵は猟師の一人娘、ハルの家に住んでいる。義父は七蔵が婿に入って一年もしないうちに山で命を落とし、七蔵はハルと母親の面倒を見ることになった。今使っている銃は義父の使っていた古いものである。
「義姉さんとおばさんには、こんなもん買うてきました」
古着屋で買ってきた着物をだすと、七蔵は、
「すまんな、すまんな」と何度も頭を下げた。
「今日はわしんとこで飯くえや、もう帰ってくると思って、用意しちょったものがあるんじゃ」
「ありがたいな、そうさせてもらうわ」
八蔵はこのすぐ上の兄と仲が良かった。他の兄弟とも仲はいいが、七蔵とは一つ違いということもあって友達のように育ってきた。
「おっ父とおっ母たちのところに寄ってから行きます」
「ああ」
七蔵はとってきた獲物の処理を終わらせると家にもどった。
八蔵は両親たちのいる家に行った。そこで親や兄弟への土産を置くと、七蔵の家に向かった。
七蔵の家ではハルと母親のシゲが夕飯を作って待っていた。その日はご馳走だった。といっても鯉の煮付けに、芋や野菜の炒め物である。
八蔵が土間に入ると、
「八蔵さん、きれいなべべさ、ありがとうで、また、ずいぶんぎょうさんの銭ももらいましただな」
四十半ばになるシゲが、しわくちゃの笑顔で痛んでいる腰を立てた。
ハルも笑顔で八蔵を見た。
「ほんに、いつもありがとう、きれいな着物だわ」
七蔵が早く上がるようにせかした。
八蔵が土間からあがると、ちゃぶ台の料理の脇に湯飲み茶碗が二つ用意されている。
「まっとったんじゃ、早く飲みたくての」
「どぶろくですか」
八蔵が聞くと、
「いんや、酒じゃ、まっとうな酒じゃ」と七蔵は笑顔になった。
七蔵が座っている脇には五合徳利が置いてあった。村に酒を造っているところはないはずだが。どの家でもどぶろくを自分たちで作って飲んでいた。
七蔵が栓を抜くと、ぷーんとよい香があたりに満ちた。
「ええ匂いだ、良さそうな酒ですね」
八蔵が言うと、七蔵は肯きながら、徳利を傾け酒を湯飲みに注いだ。
八蔵はそれを受け取りながら、ちゃぶ台の前に座った。
「さあ、やってくれ」七蔵も自分の茶碗に酒を注いだ。
八蔵は酒が好きである。といって、深酒をした事は無く、ちょっとしたつまみで一合、二合ほど楽しむ程度に飲んだ。
八蔵は茶碗に口をつけ、少しだけ口に入れた。
「ほ、こりゃ」
つい、声が出てしまった。うまい酒はやっぱり町にでなければない。しかしこの酒は今までに飲んだ酒よりずっとうまい。喉に香ってくる。
七蔵も飲んだ。
「こりゃうまい酒じゃ、こんなんは初めてじゃ」
「兄さん、こんな上等な酒どうしたんです」
八蔵は煮た鯉に箸をいれた。
「半月ほど前だったか、若い男が徳利をいくつも背負ってやってきたんだ、それで、綿がほしというんだ、綿は貴重だからなかなかないが、ほら、お前も知ってるだろう、うちの親父が綿入れのどてらを着とっただろう、もう汚れてどうしょうもないものじゃ、猫の寝ぐらになっちょったんよ、それしかないというと、それでいいというんだ、それで、五合の酒ととり替えるっていうんで喜んで渡したんだ。
それでな何処から来たと聞くと、雲雪村というじゃないか、そんな村知らないというと、ここから、四つも山を越した奥にあるという。それを聞いていたおっ母が、おっ父から聞いたことがある言うじゃないか」
シゲが話を受けついだ。
「そうなんよ、八蔵さん、うちの父ちゃんが生きていたときになあ、ずいぶん昔ですけどな、熊を打ちに山に入って、半月も帰ってこなんだことがあって、てっきり、やられちまったかとあきらめておったら、ひょっこり帰ってきたんだわ、話を聞くとよ、雲雪村というのが、あの向こうの山から四つほど大きな山を超したところにあって、まぎれてそこまで行っちまったそうだ。山の裾野に十か二十の家がかたまっておって、鳥獣をうち、米などを作っているんだそうだよ。鳥や獣もたくさんおって、茸やぶどうなんかの山のものも豊富、とてもよいところだったそうだ、しかも、水がよくて、うまい酒を振舞ってもらったと言っておった、ただ、雪が余りにも深いところで、冬の間は大変だということを話してましたなあ」
また七蔵が引き継いだ。
「その雲雪村の若い衆はのお、又吉さんといったかの、子供が生まれたが、綿が欲しくて買いに来たと言うておった、ここも綿を手に入れるのは大変じゃというと、どんなに古くても汚くてもかまわねえいうで、取り替えたのじゃ、それでもそいつあ、ずいぶん喜んでいた」
「へー、そんな村のある事は一度も聴いたことがありませんでしたね」
「うん、いつか行ってみべえや、いい商いができるかもしれで」
「そうですね」
八蔵も相槌をうった。
そのようなことがあって、二年が過ぎたその年、八蔵の村では稲の実りも悪かったが、狩猟も振るわなかった。獲物が少なかったのだ。
秋も深まったある日、八蔵は雲雪村のことを思い出した。村では商売になるものが少ないこともあり、雲雪村に行って酒を仕入れようと思いたったのである。酒の味を忘れることが出来なかったことも一つの理由である。八蔵が町でうまい酒をさがしてみたがあれほどのものはなかった。
村のおおよその方向はシゲに聞いたが道はわからなかった。それでも旅慣れた八蔵はいろいろな生活品を背負って出かけた。
山そのものは険しくは無かったが、ほとんど人の通らないようなところを行くのは骨が折れた。
三つほど山を越すと、道らしきものも全く見当たらなくなった。
夏のように草が生い茂ってはいないが、それでも丈の高い羊歯が黄色っぽくなって折り重なっている。
八蔵は動物たちの通る道を見つけ、なんとか登りはじめた。しかし道は途切れ途切れになり、しばらくいくと全く分からなくなった。
雲行きも怪しくなってきた。黒い雲が垂れ込めてきて太陽を隠した。これでは方角がわからない。
いきなり、冷たい風が山の中を吹きぬけた。おお、寒い、八蔵は手をもんだ。
真黒な雲が山の上に現れ強い風が吹いたと思うと、いきなり、ごろごろというより、ごーっという大きな音とともに、あたりが白く輝いた。
バリバリという音がして目の前の大きな杉の樹が真二つに裂け、黒くこげて煙が上がった。裂けた木は下にずり落ちていった。
八蔵は命の縮む思いで歩いていった。
黒い雲はますます垂れ下がってきて、稲光があたりを照らした。周りの温度が急激に下がり、白いものが落ち始めた。
「もう、雪だ、そんなばかな」
大きな雪が容赦なく降ってきた。みるみるうちに足元の草が雪に埋もれていく。風で舞い上がった雪が目の前をふさぐ。
山の斜面の大きな岩の間に穴がある。八蔵はその岩穴の中にかけこんだ。岩穴は人二人分ほどの広さがあり、八蔵は荷をおろしてほっとひと息ついた。
八蔵はかじかんだ手で腰につけていた皮袋からいり豆を取り出した。豆を口に入れ噛み砕くと竹筒の水を飲んだ。
あまりの冷たさに風呂敷の中から手袋をとりだした。売り物の一つだが仕方が無い。こんなに早い時期から雪が降るとは思ってもいなかった。手袋をはめると歩く準備を整えた。
かなり村の近くまで来ているはずである。しかし道が明らかではない上に雪まで降っている。兄の義父のように道に迷ってしまいそうだ。いやすでに迷っている。引き返そうかどうしようか迷いながら八蔵は穴の中から首を出して外の様子を見た。冷たい雪が顔にあたる。少しばかり外にでた。吹雪いている。このまま歩くのは危険だ。しばらくここで様子を見たほうがよいかもしれない。
八蔵が岩穴の中にもどった。そのとき鈴を転がすような音(ね)が聞こえた。音のするほうを見ると、奥の岩壁に亀裂が広がっている。手がやっと入るほどの大きさの穴が亀裂の途中にある。
八蔵が近づくと穴の中から冷たい風が緩やかに頬を打った。
手をかざしてみると奥から風が吹きでているのがわかった。鈴の音もそこから聞こえてくるようだ。
しだいに鈴の音が大きくなってきた。吹き出す冷たい風が強くなってくる。
なんだろう、八蔵はぞくっとして割れ目から離れ、入口近くに逃れた。
リンリンと鈴の音が大きくなってきた。穴から風がひゅうーっと強く吹き出した。白い冷たい空気の流れが目に見えるようである。
八蔵のいる岩穴がぴりぴりと冷たく凍り付いていく。
このままでは危ないと思い、八蔵が立ち上がったときである。
リン、と大きく鳴って、穴の中から人の握りこぶしほどの大きさの雪の玉が飛び出してきた。雪玉はコロコロと転がってくると八蔵の足元で止まった。
真っ白なふわっとした雪玉である。
やれ、不思議な事もあればあるものと、八蔵がその雪玉を手に取ろうとすると、雪玉はころっところがって逃げた。
また、リンという音とともに二つ目の雪玉が穴からころがり出てきて八蔵の前で止まった。
そのあとは、リンリンリンと絶え間なく鈴の音がして、雪の玉が飛び出してくると八蔵の前に積み重なっていった。
八蔵は気味が悪くなり、穴を出ようとからだを動かした。すると雪玉は八蔵の足元を追い越して外に向かってころがり始めた。
三、四十もある雪玉は岩穴の外に出ると、積もり始めた雪の上に集まった。八蔵も外に出た。
それが合図かのように雪玉が一列になってころがり始めた。
どこにいくのだろう。八蔵はついていくことにした。どうしてそう思ったか八蔵には分からなかった。雪玉が誘っているようにも思えたのである。
雪玉は八蔵の歩に合わせるように木々の合間を縫って山の上へ向かった。
雪玉が転がった跡は雪の上に筋となった。八蔵はそれに添って歩いていった。
しばらく行くと山の頂についた。下を見ると真っ白になった山の合間に村が広がっていた。家々は雪に埋もれている。
雲雪村についたのである。八蔵はなにかほっとした気持と、人っ子一人見えない村に寒々とした思いに駆られた。
雪玉は斜面を一列のまま転がり降りていく。
八蔵も後をついて駆け下りていった。
雪玉は集落の中に入ると、雪を掻き分け道をつくりながら進んでいった。おかげで八蔵は歩くのに苦労をしなかった。
一つの雪玉が一軒の大きな家の前で止まった。列を成していた雪玉が集まって丸く輪を画いた。八蔵も歩を止めた。
雪玉から白い蒸気が立ち込めた。もやもやとした白い霧は空気中に漂いだした。やがて、白い霧は八蔵の目の前で何十人もの白装束の女になった。
雪女だ、岩穴の奥に雪女の住まいがあったのだ。八蔵は足がすくんでいた。
雪女たちは宙に舞い上がり、幾人かが集まると、それぞれの家の屋根の中に吸い込まれるように入っていった。
五人の雪女が八蔵の立っている大きな家の前に降りたった。
この村の長の家であろう。
雪女の一人が赤い目を八蔵に向けた。真っ白なうりざね顔の雪女の目は、八蔵についてこいと言っていた。
八蔵は雪女のもとに行った。雪女たちは一人、一人と家の中に消えていく。最後の一人が消えるとき、八蔵はいつの間にか雪女の後について家の中にいた。
質素ではあるがきれいに整った家の中は凍りついていた。
襖がするすると開けられ一番奥の部屋が現れた。
息絶え絶えの住人がそこに居た。若い夫婦が十になったかならないかの女の子をありったけの布に包んで抱きしめて凍り始めていた。後ろには老人夫婦が寄り添うように冷たくなるところであった。
五人の雪女たちは白装束を脱ぐと、そこにいる人たちの前に立った。雪女たちは真っ白なからだを住人たちの前にさらし口の中へ入っていった。
夫婦は出会ったばかりの若い頃の夢を見ており、老夫婦は孫ができたときの夢を見ている、女の子は赤い着物をつくってもらったときの夢を見ていた。みなの顔に笑みが浮かんだ。そのととたん心臓がことりと音を立てて止まると息絶えた。
雪女たちがその人たちの口から最後の息となって外に出た。白い乳房がきらきらと光っている。雪女たちは一斉に八蔵を見た。
一番前にいた雪女が言った。
「伝えてください」
再び白装束に身を固めた雪女たちは、雪に埋もれた入口の戸を開け、すべるように外に出て行った。
最後に出ようとした雪女が振り返り、住人の脇を指差した。
八蔵はそこに五合徳利がおいてあるのに気がついた。
八蔵は手を合わせ、徳利をもつと雪女の後をついて外に出た。
雪は止んでいた。
空を見あげると、どんより垂れ下がる雲の下で、雪女たちが浮遊している。
八蔵の頭の中では雪女が言ったことがぐるぐるとめぐっていた。
「伝えてください」
八蔵は隣の家に行った。どの家も戸が開けられており、凍りついた人々がよりそっていた。みなにこやかな顔であった。
最後の雪女が端にある一軒の家からでてくると、雪女たちは空へ空へとのぼっていき、厚い雲の中に消えていった。
八蔵は、雪玉のころがってきた跡をたどりながら、雲雪村を後にした。
岩穴までたどりつくと、雪は溶け、空は青く晴れ上がっていた。山の向こうの雪の深さを思うと不思議である。
岩穴は大きな岩で覆われていて、もはや中に入る事は出来なかった。
八蔵は岩穴に向かって一礼をすると、この事は必ず町に伝えようと心に誓った。
村に戻り、一晩自分の家でくつろぐと八蔵は町に向かった。
町についた八蔵は、昔勤めていた大店の旦那に、雲雪村の村民が雪に埋もれていることを話し酒を渡した。雪女の事は誰も信じないだろうと思い胸の中にしまっておくことにしたのである。
旦那はこのことを役所に伝えた。その後、村に役人が確かめに行き、すべての住人が死に絶えていることを確認した。役人が言うには住人たちは不思議と安らかな顔で死んでいたということであった。
もう一つある。雲雪村から持ち帰った酒である。そのうまさを町の造り酒屋で再現しようということになり、工夫がなされ、同じとはいかないまでも町で最も旨い酒になった。酒の名前は八蔵がつけた。雪(せつ)玉(ぎょく)という。
八蔵さんは、こんなことがあったんだ、と歯のなくなった口を開けて笑った。
年のわりには腰をしゃんと立て、奥の部屋から五合徳利をもってきて見せてくれた。
「ほら、あんたにやろう、あんたの村の最後のものだからな、約束したことだ」
八蔵さんはあの五合徳利を大事にしまっておいたのである。
私の祖母は雲雪村に調査に来た民俗学者の卵に惚れて、東京にでて一緒になった。民俗学者は私の祖父である。そして、私も民俗学を学ぶ学生となった。
八蔵さんは雪女に言われた「伝えてください」という言葉をしっかりと守ったのである。
雪玉
私家版雪女小説集「雪女、2015、222p、一粒書房」所収
表紙日本画:山内佳子


