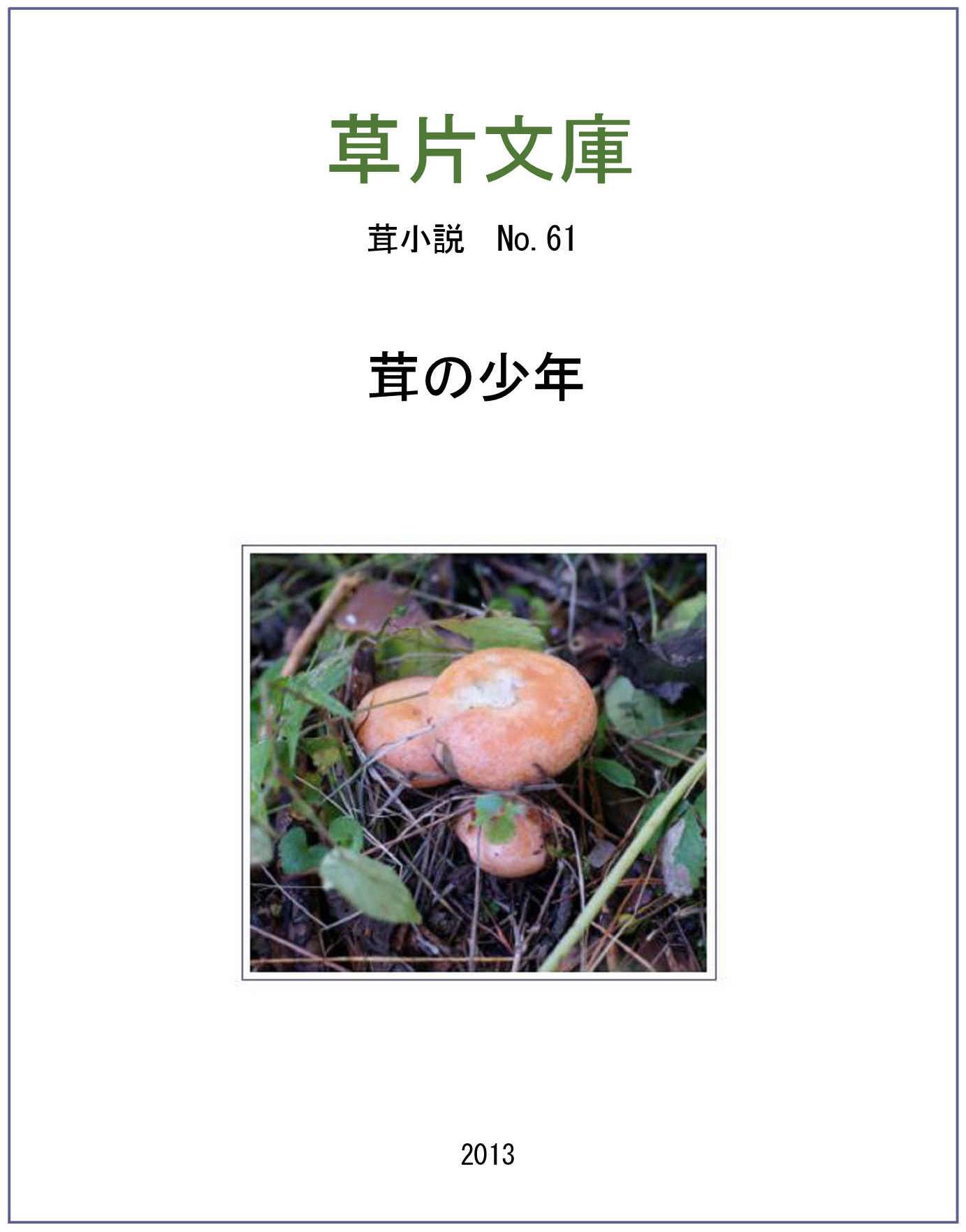
茸の少年
小学生の時である。場所は秋田の奥羽線沿線にある小さな町であった。各駅停車しか止まらない駅で、駅員は老人が一人、たしか五郎さんと言ったと思うが、六十過ぎの腰の曲がった人だった。私は隣のもっと小さな、駅員のいない駅からそこの小学校に通っていたので、五郎さんとは毎日挨拶をした。
「おはようさん」
「ごくろうさん」
朝と帰り、五郎さんはいつもこの一言であったがなぜか忘れることができない。真冬は雪が何メートルも積もるところである。雪の道を駅から近くとはいえ小学校まで歩くのは大変なことであったが、そんなとき五郎さんの一言の挨拶はとても自分を暖かくしてくれた、気持ちのこもったものであった。今では良き思い出である。
なぜ東京育ちの私が小学校の時にそのような雪国にいたのかというと、母親が父親とうまくいかず、母親の実家にやっかいになっていたからである。母親の実家はそのあたりの地主で、駅から五分のところに広い土地を持ち、瀟洒な家が建っていた。祖父も祖母もかなりのやり手で、その地域の名士であった。
その地域にも小学校はあった。ただ母の実家とはずいぶん離れた山際にあり、歩いていくと、一時間もかかっただろう。むしろ隣町の駅近くの小学校の方が通うのに楽であった。教育委員会に顔のきく祖母がとりなしてくれ、そこに通うことになったのである。電車に乗ればすぐであった。
小学校に通っていた子供たちの境遇は誰もが似たり寄ったりで、東京からきた私は違う目で見られた。特に隣の駅から通っているということで、電車にのってらあと、幾分うらやましくも思われていた。
しかし友達はすぐに何人もできた。その中で今でも奇妙に覚えているのが清君である。名字は確か三井であったと思う。彼は弁当に必ず茸を入れてきた。もちろんご飯の真ん中に梅干しが埋まっており、まわりの白いご飯の上には醤油で煮つめたような茸がスライスされて敷き詰められていた。僕は美味しそうだなといつも羨ましく思っていた。僕の弁当は海苔が敷き詰められており、佃煮や卵焼き、時には肉なども入っていた。きっと周りの子供たちは羨ましく見ていたのであろう。そのときの自分はそのようなことに気付いていなかった。
清君とは校庭の鉄棒のところで知り合いになった。僕は東京育ちだが、鉄棒は得意だった。そのころ逆上がりができた。清君の前でやってみせたら、尊敬の眼で見られ、是非教えてくれと言われた。そこで、鉄棒につる下がるところから付きあった。力がありそうな体をしていたにも関わらず、清君は懸垂力がなかった。というか、ちょっとした骨なのにそれがわかってないようであった。
「まねをしなよ」と言って、僕は足をあげながら腕に力を入れてお尻を持ち上げた。その時の腕の曲げ具合と、腰の曲げ具合、そのタイミングが重要だ。
「すげえ」と言いながら、彼もやるのだが、どたっと足が落ちてしまう。
腕と足のタイミングが全く合っていない。
僕は彼のお尻を持ち上げながら、「ほら腕を曲げて」と言った。
彼は何回も懸命にやったがなかなかできない。終りにしようと思ったとき、いきなりできた。「もうすぐ自分でできそうだあ」、彼は僕の支えなしで何度も繰り返し、とうとう一人でできるようになった。
その時の彼の顔は今でも覚えている。「出来た」、と満面に笑みをたたえた。
嬉しそうに、ポケットに手を突っ込んで、取り出した物を僕にくれた。
「明日は違うのを持ってきてやるよ」
僕の手の上には赤い茸がのっていた。とても綺麗だが、柄が細くて折れそうだ。
「ポケットに入れていて潰れなかったの」
「ああ、慣れているからな」
それで、なかなか逆上がりができなかったのではないだろうか。
「これどうするの」
「かじるんさ、腹減ったり、疲れたときにいいんだ」
「そんな大事なものもらっちゃ悪いよ」
「うちは沢山あるから大丈夫じゃ、また持ってきてやらあ」
「ありがとう」
そんなことで、清君からもらった茸をポケットに入れて家に帰った。家でその赤い茸をポケットから出してみると、まだしゃきっとしていて、採り立てのようだった。
おじいちゃんがそれを見て僕に聞いた。
「どうしたんだい、その茸」
「もらったんだ、友達から」
「どれ、見せておくれ」
おじいちゃんは赤い茸を手にとった。
「こりゃあ、卵茸といって美味い茸なんじゃ、日本じゃほとんど食べないが、ヨーロッパじゃあみんな食べる美味い茸じゃ」
「へー」、僕はおじいちゃんの物知りには驚いた。
「じゃが、不思議だの、今頃生えているものではないからな、なんていう子にもらったんじゃ」
「清君」
「名字はなんていうんだ」
「三井」
「隣町には三井という医者がいるが、そのうちかな」
「わかんない、今度聞いてみる」
「三井という医者はとても町の人たちに好かれておったよ、いろいろな物を発明してな。いい薬がたくさんある。その中には茸から作った薬もある」
「ふーん」
「この茸をなぜもらったんだい」
「逆上がり教えたんだ、できるようになったよ、清君」
「ほー、よかったな、それで清君はなぜこの茸を持っていたのかい」
「お腹が空いたり、疲れたときにかじるんだって言ってた」
「ほお、ちょっと食べていいかい」
「いいよ、みんなあげるよ」
僕がうなずくとおじいちゃんが茸の赤い傘のところを少し指で削って口に入れた。
「味が付いている、なかなかうまいな、酒の肴にも良さそうだ。しっかりしている、三井のお医者さんが保存する方法を考え出したのだろうな」
夕食の時に、その茸のスライスがテーブルの上に載せられた。
「これはおいしいわね」お母さんもおばあちゃんもそう言った。
おじいちゃんはお酒を飲みながら
「この作り方を教わりたいものだ」、と摘んだ。
そんなことがあって、清君とはいろいろと話すことが多くなった。目立たない子であったが、本当はその小学校で一番、二番の成績の良い子だったことが後でわかった。そのようなことを感じさせない、ゆったりとした子供だった。本当にできる子だったのだろう。
清君はたまに茸をくれた。
ある日、「おうちは何しているの」と聞くと、「医者さ」と答えてそれ以上は言わなかった。
清君におじいさんが言っていたことを聞いてみた。
「この茸の作り方はわかんないな、俺のおじいちゃんが作ったんだけど、瓶の中に昔からある汁に漬けておくんだ。そうすると、こうなるんだ。おじいちゃんはもういないし、とうちゃんに聞いてみてあげるけど、わからないかもしれないな」
次の日、清君は申し訳なさそうに、「やっぱりわからないって、書いたものもないって」と言った。
おじいちゃんにはそう伝えた。おじいちゃんは、
「そうか、三井のおじいさんが作ったのか、一度会ったことがあるな、もっと話をしておくんだったな」
残念そうであった。
僕はその後、彼の弁当を少し分けてもらった。卵焼きと交換した。清君は卵焼き旨いなあと感激していたが、実は茶色くなった茸のスライスのご飯の美味しいこと、今までもあんなに美味しいご飯には巡り会ったことがない。
あまりの感激に声がでなかった僕に「旨くないだろう」と清君は聞いた「とんでもない、美味しくてびっくりしているんだ」と言ったら、嬉しそうに笑っていた。
中学生になるときに僕は東京に戻った。母親が東京で教育を受けさせたいと希望したからである。僕はちょっと残念でもあった。それ以来彼には会っていなかった。
私は大きくなって医者になった。彼が何になったかなど気にかけたことがなかったが、ただ茸の少年ということで記憶に残っており、小学校時代のことを思い出すようなときには必ず彼の茸が思い浮かんだ。
それが、ひょんなところで、彼とおぼしき人物を特定することになったのである。
大学病院勤めで独身であることもあり、食事は外で食べるか、ときとしてレトルトものをマンションに買って帰った。少し高級なコンビニエンスストアーに入り、いつものようにレトルトシチュウをとってレジにいこうと、惣菜類の棚の前を通ったときである。茸の佃煮が目に止まった。ご飯の上に茶色の茸のスライスがのっている写真が袋に印刷されている。その画像が小学校の時の清君の弁当を思い出させたのである。醤油茸スライスと単純な名前がつけられている。
棚からその袋を手にとって会社名をみると、三井茸産業とあった。しかも秋田の会社である。彼がつくっているとほぼ確信し、それも買ってマンションに帰った。
部屋で醤油茸スライスを皿に出し、口に入れてみた。あのなつかしい味が口に広がった。やっぱりそうだ。
早速コンピューターを開き、インターネット上で三井茸産業を調べた。ホームページの最初にいろいろな茸の写真がでてきた。あの地方で採れた様々な茸の漬け物を販売している。栽培もしているようである。直販のコーナーもあった。私はすぐにインターネットで、最もシンプルでベーシックな茸の佃煮、醤油茸スライスを購入した。
二日後、頼んだものが到着した。
開けたら手紙が入っていた。はじめは会社の宣伝の文句が並べられているものだろうと思っていたが、出だしが「佐伯先生」だった。私の名前である。驚いて読んでいくと懐かしさでいっぱいになった。そしてさらに驚くことがあった。
醤油茸スライス買い上げのお礼のあとに、自分のことが書いてあった。
僕は医者にはなれなかったけど、祖父の技術を改良し、会社を興しました。貴君が心臓医になったのを知っていました。僕も君と同じ大学を受け失敗しました。もし入っていれば同級生ですね。我が家は家内が医者をやっています。旧姓足立久美といいます。先生の同級生です。先生のことはよく聞いています。秋田に来られたときには是非お寄りください。三井清。
個人の電話とインターネットのアドレスも書かれている。
足立久美はすごい才女であり、美貌の持ち主で、もちろん同級生のあこがれの的でもあった。それよりもすごかったのは、若い先生方の注目の的であった。子供もいる産婦人科の教授が目の色を変えていたことは皆のよく知るところである。ところが、彼女はそのようなことには見向きもせず、学業に精を出した。といって、まったくの石頭でもなく、映画にも行けば酒も飲んだ。集団で遊ぶことにもとてもよく付き合った。話もでしゃばることなく、といって、つっけんどんでもなく、ときとして面白い話題を振りまいてくれることもある。僕は残念ながら外で見ているぼんくら組だった。
彼女は医師の国家試験も難なく通り、地方の大きな病院に研修に行ったところまでは聞いていたがあとはわからなかった。それが、清君の奥さんになっているとは驚いたのを通り越して頭が混乱している。どのような出会いだったのだろうか。
今年は秋田の大学で学会がある。ついでに寄ろう。
届いた佃煮には秋田の白いご飯がおまけについてきた。レトルトである。その形はまさに清君の持っていた弁当箱である。涙が出てきそうだ。
ご飯を電子レンジにかけ、スライスされた茶色の茸の佃煮をご飯の上に載せ、買ってあった梅干しを一つ真ん中に入れた。これで彼が毎日持ってきていた弁当ができた。
さて、と、茸とご飯を箸ですくって口に入れた。香ばしい茸の香りと、彼に少し食べさせてもらったときに感じたおいしい米の味が口の中いっぱいに広がった。
うまい、これは毎日食べてもあきない。
あっというまに食べてしまった。ビールが飲みたくなった。おつまみにもう一袋茸の佃煮を開けた。ビールもあっという間になくなってしまった。
PCを立ち上げ、彼にメールを打った。
「あまりにもおいしくて、二袋食べてしまいました。清君の持ってきていたお弁当の味です。毎日でも食べたい思いです」
こうして、その夜は終わった。
明くる朝、病院にでる前にメールをあけると、清君から返事が来ていた。
「ありがとうございます。あの弁当は、僕にとっては苦痛でした。毎日毎日同じもので、おやじは体にいいからそうしなさいと母親に作らせたのです。ただ、そのおかげかどうかわかりませんが、全く病気知らずで育ちました。そんな僕が一度大病というか、他の人にとって大病ではないのだと思いますが、アレルギー性の皮膚炎をおこしました。全身に発疹がでてかゆくてたまらず、秋田の病院に通いました。僕は皮膚科ではなく内科に回され、アレルギー内科の治療を半年続けました。そのときの医師が家内です。是非遊びに来てください」
とあった。
へーと思い、あの日に焼けた清君はどのような男になったのか興味もある。もちろん、あの才女はどのような嫁さんになっているのか見たくもあった。秋田での学会が楽しみである。
大学病院の仕事は想像以上にきつい面がある。専門医を維持するには学会にも顔を出さなければならないし、研究論文を書いて大学での自分のポジションを確保しなければならない。そこで独立して病院を持つ先生が増えてくる。といっても独立したらしたで大変なこともたくさんある。
学会は学ぶ場だけではなく、かなりの息抜きになる場でもある。毎日が同じところで一日中患者との作業をくり返す現場の医師にとって、ほんの一日でもホテルに泊まって学会に顔を出し、懇親会で久しぶりの同級生に会って話をするのは気分的にリフレッシュする。
秋田での学会は大きなホテルが会場になった。自分は駅に隣接するホテルに泊まった。最後の土曜日は特に聞くものもないので、午後から清君のところを訪ねていくことにした。前もって電話はしてある。その場所は秋田市から新幹線で大曲にでて、そこから奥羽線で少しいったところである。その町には今でもホテルも宿屋もない。彼は自分の家にたくさん部屋があるから泊まれという。子供のころも彼の家には行ったことはなかったが、そうすることにした。次の日は日曜日で仕事がない。
昼ちょっと過ぎには駅に着いた。もう懐かしい駅舎はなく、当たり前の建物になっていた。駅員は中年の女性が一人いて切符を受け取っていた。駅の前もずい分変わっていた。広いロータリーになっていて、駅を降りれば見えた小学校が無い。周りには食物屋や本屋が並んでいる。
彼に電話を入れると、車をよこすから待っていてくれという。それから数分待っただけで迎えの車は来た。驚いたことには三井クリニックと名前のはいったマイクロバスであった。
白髪の運転手がおりてくると、丁重に私に頭を下げ、「先生どうぞお乗りください」とドアを開けてくれた。
「駅前には小学校があったんだけど、今はどうなりました」
運転手さんに尋ねると、「あの小学校は、今はなくなりましたんですよ、もっと山際に大きな小学校ができて、このあたりじゃ一番立派な小学校になりました」と言って運転席に乗り込んだ。
「実は三井君の家には行ったことはなかったんですが、どのあたりなんですか」
「小学校に近いところの高台にあります。昔からそこにあって、周りになんにもないところだったんですが、今ではかなりの住宅が建っています」
「運転手さんはここの方」
「はい、おやじの代から三井病院に世話になっています」
マイクロバスがあるくらいの大きな病院ということと、茸の佃煮との関係が結びつかなかった。運転手はなれた様子でマイクロバスを狭い道に走らせていった。
田圃に沿った道を進み、山際をしばらく行くと、立派な三階建ての小学校が丘の上に見えてきた。
「あれは、滝沢先生の設計なんです」
運転手が自慢げに言った。滝沢は今建物の設計では日本の一人者である。
赤茶色の煉瓦の敷かれた屋根をもつヨーロッパ風なきれいな建物である。
「建てるのに金がかかっただろうな」というと、「その先生が寄付されたんです。この小学校の出身で、三井先生のいとこさんで」
「ほー、それは知らなかった」
バスは坂道にはいり、ちょっと上ると、南京下見(したみ)の水色の瀟洒な建物が見えてきた。
大正の香りのする日本の洋風建築である。
「あそこが三井病院です」
マイクロバスを使うほどの大きな病院ではない。都内の個人病院を少し大きくした程度である。
車を玄関口につけると、運転手がドアを開けてくれた。
玄関には背の高い色の白い男が立っていた。
運転手が私の鞄を持とうとした。私は遠慮して入り口にすすんだ。
「やー、久しぶりです」
男が挨拶をした。「え」と僕は驚いた。
三井君は色の黒い坊主頭のどちらかというと、小太りの少年だった。
「三井君なのか、変わっちゃってわからなかった」
「君も、すごく精悍そうになった」
彼は笑窪を寄せてにこにことそばにきた。
「どうぞ、入ってください」
病院の中を突っ切って裏手にでると、その奥に病院と似たような作りの家があった。
「こっちが住まいです、あれが工場」とさらにその隣のコンクリートでできた体育館のように大きな建物を指さした。
「あそこで、茸の佃煮を作っているの」
「ええ、茸も最近は栽培できるようになりました」
「あの茸はなんという茸なの」
「もくず茸というんです。この山の奥でとれる茸で、ひいじいさんが見つけた茸なんです。そのとき、食べられるかどうかちょっとかじってみたら、旨かったので籠いっぱいとってきたらしい。ひいじいさんは茸のことをよく知っていただけじゃなくて、料理も得意で、もくず茸と他の茸をまぜて料理をつくったそうです。ところが、できたものはひどい味になって、椎茸や他の茸もまずくなってしまった。『せっかくの茸料理がもくずになっちまった』とひいじいさんは嘆いたところ、それを聞いていた、孫、すなわち僕のおやじが、まだ三歳になったばかりの時だけど、その茸を持って、もくずもくずとはしゃぎまわったということで、その茸の名前はもくず茸になってしまったわけです」
「面白い茸ですね」
「ひいじいさんは料理を失敗したけど、その茸だけを食べるようにすれば旨いだろうと、もくず茸を単純に醤油に漬けて食べたんだそうです、なぜ初めからこうしなかったと、反省したそうですけど、かなり旨かった。さらに味噌にもつけてみた。もっと旨くて、ご飯を何杯もお代わりしたくなった。そう、瀬戸内のままかりみたいですね、その味噌付けは周りの人に喜ばれたそうです。それで、その茸を味噌漬けで食べていたということです。
ひいじいさんがなくなってからだけど、味噌づけを続けていると、その味噌がしだいにとろけて、醤油のようになり、おじいさんがその液に他の茸もつけて食べてみたんです。そうすると他の茸もおいしくなり、また滋養に富んだものになったそうです。
おじいさんはその液について研究を始め、どのように改良したのかわからないのですけど、改良したエキスに漬けた茸はとってきたばっかりのような姿で味がよくなることがわかったのです。僕がポケットにいつも入れていた茸はその茸です、おじいさんがそのエキスをみつけたわけです」
そう言いながら清君は私を工場に連れていった。
工場は、ずいぶんたくさんの人が分担して働いていた。
その一角に頑丈な鍵のかかる部屋があった。
中に電気が点いていて、曇りガラスの窓から一人の人が作業をしている影が見える。
清君がノックした。
「先生が来たよ」
戸が開いて、顔を出したのは久美だった。
「いらっしゃい、久しぶりというより、何十年ぶりね、すごいお医者さんになったって聞いているわ」
「いや、そんな、こんにちは」
大学時代もそんなに話したこととのない久美である。こんにちはとしか言葉がでてこなかった。彼女は大学時代と同じように明るい笑顔を私に向けた。
「先生も、清の茸の佃煮に惚れた人ね、私と同じ」
ずけずけとものを言う女性になった。元からそうなのかもしれないが。
「今、例のおじいさんの茸を新鮮に保つ薬の研究を進めているんだ。成分が知りたくてね、久美は生化学が得意だから」
確かに足立久美は先端の学問をよく勉強していた。
「今ちょっと手を離せないの、もう少しで終わります、すぐいきます」
そういうと久美は研究室の戸を閉めた。
「久美は普段は短い昼休みを利用して研究を進めています、今日は土曜だったので、診療が終わるとすぐこの中に入っています、我々は先にいっていましょう、どうぞ家の方に」
ということで、住居の方に通され、今日泊まる部屋に案内された。二階の見晴らしの良い部屋である。
「佐伯先生、早夕飯にしますから、それまで飲みますか」
「うん、清君は飲むのかな、それに先生はよそうよ、佐伯君て呼ばれてたよね」
「ああ、そうしよう、もちろん酒は飲みますよ、秋田の人間ですから」
彼は書斎らしき部屋に私を案内してくれた。
部屋のぐるりは本箱になっており、ぎっしりと本が埋まっていた。
「どうぞ」
清君は真ん中のテーブルの椅子を勧めてくれた。
「ここが一番気の休まる部屋なんです」
「すごい本だなあ」
「本集めが僕の趣味になっています。世界の茸の本を集めています。きれいな本がたくさんありますよ」
そこへ、ビールとつまみを持って女性が入ってきた。
清君がお手伝いさんと紹介してくれた女性は、私の前のコップにビールをついで、「どうぞ」と勧めてくれた。つまみはいろいろな茸の料理だった。一つの皿には絹笠茸がそのままの形でいくつも乗っていた。今採ってきたばっかりといった瑞々しい形を保っている。
「これが、いま久美が研究しているものです。すでに塩漬けになっているのですが、そのままの形が維持されています」
「すごいな、これがおじいさんの見つけた薬の効果なんだね」
「ええ、じいさんのは長い間漬けておいて、食べるときにだすと、数日そのままの形を保つものでしたが、久美の薬は一度つけるだけで、そのままの形を保ちます。ただ、まだ一月しかもちません、それでもすごいのですが、半永久的にしようとがんばっています」
そこに、久美が自分のビールとコップを持って部屋に入ってきた。
「ごめんなさい、失礼しました。その茸食べてみてください」
皿の上の茸の中の絹傘茸を指示した。
私は口に入れた。しゃきっとしていて、ほんのり塩味があり、アミノ酸の多い茸であるので、味はそのもので珍味といってよいだろう。
「東京の料亭からは引き合いがきているのよ」
「旨いなあ」
「どんな茸でもできますから」
「この液体の成分はわかったのですか」
「ええ、ほぼ、ただ、その効果を持続させる方法を今考えているのです」
「さっき、清君から聞きました」
「まだまだです難しいですね」
「ところで足立さん、清君との出会いを聞かせてください。ともかく我々のクラスのマドンナが、どのようないきさつで秋田の茸のプリンスと一緒になったか」
「相変わらず面白い言葉を作り出すのね、清さんが茸のプリンスね、そうかもしれないわ」
相変わらずというけど、そんなに僕と一緒にいたことは無いのだが。たしかに駄洒落はよく言ったとは思うが。
「佐伯君もきっとびっくりしたんだ、僕は小学校の時はどっちかというとずんぐりで、色も日焼けしていたから、今の細くなった僕をみて、そう言ったんだよ」
「そうね、私は清さんの子供の頃を知らないからわからないけど」
「それで、出会いは」
「清さんがだいたい話したでしょう、それ以上のことはないわ、でも、赤いぽちぽちがあの白い清さんの体に一面にでていたときは、綺麗って思っちゃった。ふふ」
「医者がそんなこと考えてたの」
清君があきれている。
「治しちゃうのもったいないくらい」
「まいったな」
「しかも、精神的にぐったりして、今にも死にそうな顔をしていたわ。早く治してくれって大変だったの、その理由を聞いたら。茸ですって」
「茸の面倒を見ないと、死んじゃうんだ」
清君が口を挟んだ。
「それで、その茸ってなんなのって言ったら、次の診察のときに、ここの茸の佃煮をくれたのよ、おいしかった、お礼を言ったら、茸畑を見に来ないかって誘われたの、私、東京の人間で田舎がないもので、遊びに行くの楽しみだった」
「それで行ったわけ」
「ええ、日曜日にハイキングに行くような気持ちで行ったわよ。そうしたらなんと、お医者さんの家じゃない。その頃ご存命だったお父様はこのあたりのみんなに慕われている人で、とても柔らかないい方だった。お母様は亡くなっていたわね。
それに、清さんの茸畑を見せてもらったら、色とりどりの面白い形をした茸たちが、洞窟の中にたくさん生えていた。裏に洞窟の入り口があって、中が広くなっているの、温度と湿度が茸の生育にもっとも適していたのね。彼はこと細かくそれぞれの茸を紹介してくれたわ」
「あのときは目を輝かせていた」
「ええ、初めてだったし、本当にきれいだった。それから、その日はお父様と一緒に、お食事をいただいて、お爺さまが作ったという茸を新鮮に保つ不思議な薬液のことを聞いて興味を持ったの」
「おやじがこの液体を誰か研究してくれないかというようなことを言ったら、私がやりますって、おやじもびっくりしていたよ」
「それで、三井家に嫁ぐことになったわけか」
「そうね、東京の男たちのアホさかげんにうんざりしていたし、その点で、こっちの人たちは人間ね、いいわよ、あら、ごめんなさい、佐伯君も東京の男ね、まだ一人なの」
「うん」私は腐って返事をした。
「こっちのいい子を紹介しようか、東京のチャラチャラ女よりいいわよ」
「うん、いや、まだ一人でいたいな」
「もし、その気になったら連絡してよ、きれいで頭のいい子がごろごろしている」
「いや、ありがとう」
私は目の前にあるいろいろな茸の料理をつまんだ。ビール瓶を見ると、茸のラベルが張ってある。
「このビールは」
「うちで作っている地ビールでね、茸エールっていうんだ。この一種類しか作ってないけど、結構いけるでしょう」
「うん、旨い、何から何まで茸なんだね、病院の名前も茸クリニックにしたらいいよ」
「ははは、そしたらみんな来なくなって、茸が外に行列を作るかもしれないね、この虫食いを直してくれとかね」
「そういえば、マイクロバスは何に使っているの」
「あれは、動ける病人集め。ここは山奥まで家があるので、電話をもらった家を、順に回って、患者さんを乗せて病院に来て、終わったらまた巡回して戻すっていう仕組みをつくったんだ」
「それはいいね」
「ついでに、子供たちを小学校につれていくこともしているよ」
「すごいね、清君のところのお子さんも小学生くらいかな」
と、私が言うと、
二人は顔を見合わせた。
「そう、会っていただこうかしら」
「そうだな」
「別の部屋にいますから、来ていただけます」
久美と清が立ち上がったので私も後についた。
「何人いらっしゃるの」
「一人よ」
「男の子、女の子」
私は無邪気に聞いた。
「女の子」
書斎から出て、二つほど先のドアを久美がノックした。
返事はなかったが、久美がドアを開けた。
彼らは先に入ると、子供用のベッドの脇に寄った。
私も近寄ったのはいいが、ぎょっとして足がすくんだ。
私の目にはいったのは水に漬かった赤い服を着た女の子である。
「子供が死んだので、この液につけてあるの」
久美は私の顔を見て言った。
どうして死んだのだろうか。死んだ人間を保存するということは今までもいろいろな方法で行われてきた。きっと茸の保存液に漬けてあるのだろう。
生き返ることもできない子供をずーっとそのままにしていると、自分だけ年をとり、死んでいくのじゃないか。その時この子はどうなるのだ。改めて土に返す、火葬にする、消滅することの重要性を頭の中で巡らせていた。
「どうなすったの」
久美が考えごとをしている私を見た。
「いえ、事故でお亡くなりになったの」
「え、何言っているの」
清君も私の顔を見た。
彼らは笑いだした。
私はベッドの上のアクリルの水槽に入った女の子をもう一度見た。
「え」思わず私は声をあげた。
水槽の中には真っ赤な大きな茸が液体の中に横たわっていた。
「大きい茸でしょう、培養がうまくいっていたと思ったら。装置の不具合で死んじまったんです。それで、将来の子供部屋に安置したってわけです」
清君が説明してくれた。
「ねえ、佐伯君、本当の子供だと思ったんでしょう、昔から夢想家だったから」
そう言って久美が笑った。
私もなぜか嬉しくて笑った。心から笑えた。
「お子さんはこれからなの」
「ええ、保存液の研究が一段落したらね」
彼らは楽しそうに笑った。
その夜も茸づくしの料理がでた。久美は料理の腕もたいしたものだ。
そうして、その夜は遅くまで彼らの子供たち、茸たちの話を楽しんだのである。
茸の少年
私家版第三茸小説集「海茸薬、2017、244p、一粒書房」所収
茸写真:筆者 山梨県小淵沢 2013-9-16


